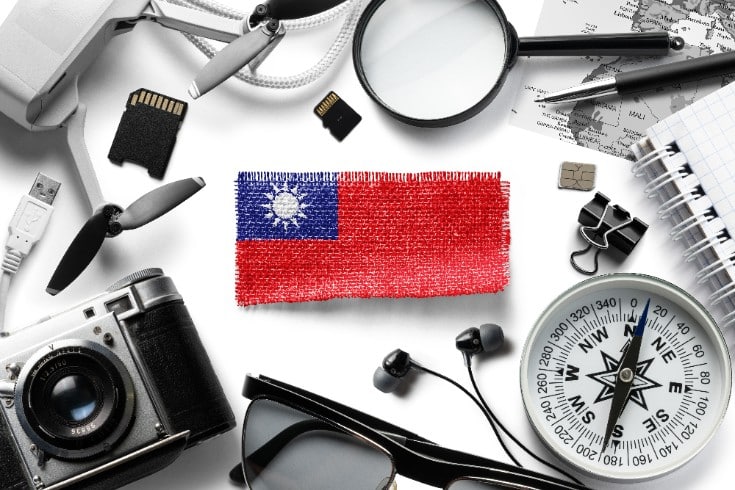ケニア共和国の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

ケニア(正式名称、ケニア共和国)は、東アフリカ経済共同体(EAC)のハブとして、域内経済成長の牽引役を担っています。近年、政府は「ビジネスのしやすさ」(Ease of Doing Business)を向上させるために、会社法やデジタル関連法など、重要な法制度の現代化を急速に進めてきました。
しかしながら、日本企業がケニアでの事業展開を検討する際、まず理解すべきは、その法体系が英国法の流れを汲むコモン・ロー(判例法)を基盤としている点です。これは、制定法を中心とする大陸法系の日本とは根本的に異なり、契約解釈や紛争解決の手続きに大きな影響を与えます。さらに、日本の法制度には見られない、外国籍者による不動産所有期間の厳格な制限、GDPR(EU一般データ保護規則)をモデルとした個人情報保護法における行政への強制登録義務、そして特定のコーポレートガバナンス機構の義務付けなど、実務上、遵守が求められる特徴的な制度が存在します。
本稿では、ケニア法全体を概観し、特に日本企業が留意すべき、日本法との重要な差異や、現地の事業環境に特有のリスク要因について、具体的な法令に基づき解説します。
この記事の目次
ケニア法体系の基盤と司法制度の特徴
ケニアの法体系は、憲法を最高法規とし、議会が制定する制定法(Acts of Parliament)、そしてコモン・ローの原則(判例法)、慣習法などが重層的に構成されています。日本が制定法主義を採る大陸法を主な基盤とするのに対し、ケニアでは、過去の判例が将来の裁判を拘束する原則である「判例拘束性の原則」(Stare Decisis)が強く機能します。このため、制定法の条文解釈においても、裁判所が過去の判例を重視する傾向があり、法律文書や契約書の作成においては、日本よりも文言の厳密性が重視されることになります。
ケニアの司法制度は、最高裁判所、控訴裁判所、高等裁判所を頂点とする階層構造を持っていますが、特筆すべきはその専門性です。高等裁判所のレベルには、環境土地裁判所(Environment and Land Court)と並んで、雇用・労働関係裁判所(Employment and Labour Relations Court)が憲法上の根拠に基づき設置されています。
この専門裁判所の存在は、日本企業が労働関連の紛争を処理する際に重要な違いをもたらします。日本では、労働紛争は主に地方裁判所の民事部や労働審判委員会によって処理されますが、ケニアではこの専門裁判所が一次管轄権を持つため、手続きや法解釈の傾向が異なります。専門裁判所は労働者保護に特化した判例を急速に蓄積する傾向があることから、企業側にはより高度で厳格な労働法コンプライアンスの専門性が求められることになります。
ケニアの会社設立とコーポレートガバナンス
ケニアの会社運営を規律するのは、国際的なガバナンス基準への準拠を目指して制定されたCompanies Act 2015年(会社法)です。この法律は、会社登記プロセスの効率化を進めましたが、同時に、日本の会社法には存在しない「会社秘書役」(Company Secretary, CS)という役職の義務付けを定めています。
このCSは、名称から想像される事務的な役割とは異なり、上級管理職またはそれ以上の地位にあり、重要なガバナンス機能とコンプライアンス機能を担います。CSの職務には、取締役会への法的責任に関する助言、法令や規制の遵守確保、法定記録の維持、規制当局への文書提出などが含まれます。
CSの選任は、公開会社(Public Company)では必須です。また、非公開会社(Private Company)であっても、払込資本金が500万ケニアシリング(KES 5 million)を超える場合、CSの任命が義務付けられます。この資本金の閾値を超えない小規模な非公開会社は、CSの選任が任意とされていますが、一定規模以上の外国資本が設立する法人は、創業当初からこの制度の適用を受けます。
CSに就任するためには、ケニア公認秘書役協会(ICSK)のメンバーであり、有効な開業証明書を保持していることが要件とされており、専門性が担保されています。日本の会社法では、取締役や監査役(または監査委員)が内部統制・コンプライアンス機能を担いますが、ケニアでは外部の専門家であるCSが法定の役職としてその役割を担う構造であるため、現地進出の際にはCSの独立性と専門性を確保し、ガバナンス体制に組み込むことが不可欠です。
ケニアの企業買収・M&A規律する法規制
競争法に基づくCAKへの届出義務
ケニアにおける企業結合(M&A)の規制は、日本の独占禁止法に相当するCompetition Act 2010年が中心となり、ケニア競争庁(Competition Authority of Kenya, CAK)がこれを管轄しています。
CAKは、M&A取引がケニア国内の競争に与える影響や、公共の利益の領域を評価し、承認の可否を決定します。届出が受理され、必要な情報が揃った後、CAKは原則として60日以内に決定を下すこととされています。
日本の企業が関与する国際的なM&A取引において特に注意すべきは、その規制の地理的な射程の広さです。Competition Actでは、合併当事者の双方が外国企業である「Foreign-to-foreign merger」(外国企業間合併)であっても、当該取引がケニア国内の競争に影響を及ぼす場合、CAKへの届出が義務付けられています。これは、日本の独占禁止法上の届出義務よりも適用範囲が広く、グローバルなM&Aを実行する日本企業は、対象会社がケニア国内にわずかな売上や資産を持つだけでも、ケニア法上の届出要件を慎重に検討しなければならないことを意味します。届出を怠った場合、CAKは罰則を課す権限を持っています。
Banking Actに基づく承認制
さらに、M&Aが金融機関や上場企業を対象とする場合、競争法上のCAKの承認に加え、Banking Actに基づきケニア中央銀行(CBK)の承認や、公開市場に関するCapital Markets Actに基づき資本市場庁(CMA)の承認など、業法上の追加的な規制当局の承認が必要となります。これにより、日本の金融関連M&Aと比較しても、手続きが多層的かつ複雑になる傾向があります。
また、東アフリカ共同体(EAC)の競争当局(EACCA)の管轄も考慮に入れる必要があります。合併当事者のEAC域内での合計売上高や資産が特定の閾値(例:3,500万米ドル超)を超える場合、EACCAへの届出も必要となる可能性があります。
ケニアの不動産所有権に関する制約
日本法においては、外国籍者や外国法人が日本の土地を所有することについて、原則として法的な制限は設けられていません。これに対し、ケニアの土地所有権に関する制度は、日本企業にとって最も重要な構造的差異の一つとなります。
ケニア憲法およびLand Actに基づき、ケニアの非市民(外国籍者)がケニア国内で不動産を所有する場合、その保有期間は最長99年間の借地権(Leasehold Tenure)に制限されています。非市民が永代所有権(Freehold interest)を取得した場合であっても、法律上、自動的に99年間のリースホールドとみなされます。
さらに、非市民は農業用地を所有することも明確に禁止されています。この制約は、外国籍者が主要な株主となっている現地法人(ケニア国内で設立された子会社)が土地を所有する場合にも適用されます。
この99年リースホールド制は、長期的な投資を行う日本企業にとって、根幹的なリスク要因となります。期間満了後におけるリース権の更新が現地法でどのように保証されるか、また、大規模な工場やインフラ投資の回収期間を99年未満に設定できるかについて、綿密な法的分析と事業計画の策定が求められます。
なお、外国企業がケニア国内で事業取引を行うためには、Companies Actに基づき、子会社として現地法人を設立するか、支店として登記することが必要であり、登記なしに不動産を所有したり、事業を行ったりすることは許可されていません。
ケニアのデジタル化とコンプライアンス

データ管理者・処理者に対する強制登録義務とDPIAの要求
日本の個人情報保護法(APPI)に相当するのが、Data Protection Act, 2019 (DPA) です。この法律は、ケニア憲法第31条を具体化するために制定され、EUのGDPR(一般データ保護規則)をモデルとして、個人データの収集、処理、保管、移転を包括的に規制しています。DPAは、適法性、公正性、透明性、目的の明確化と限定、正確性、保管期間の制限、機密性の確保といった、厳格なデータ保護原則をデータ管理者および処理者に課しています。
日本企業が特に注意すべき点は、日本のAPPIには通常見られない厳格な行政義務です。DPAの下では、データ管理者(Data Controller)およびデータ処理者(Data Processor)は、データ保護委員会事務局(Office of the Data Protection Commissioner, ODPC)への強制的な登録が義務付けられています。金融サービス、医療、通信など特定の高感度セクターに属する企業は、規模に関わらず登録が必要です。したがって、ケニアでデータ処理を行う企業は、事業開始前に必ずODPCに登録しなければなりません。
また、大規模な機密データの処理や、プロファイリング、新しいテクノロジーの利用など、高リスクの処理活動を実施する前には、データ保護影響評価(Data Protection Impact Assessment, DPIA)を実施することが義務付けられています。DPIAには、処理の体系的な記述、必要性・比例性の評価、リスク評価、およびリスク対処策の提示を含める必要があります。これは、データガバナンスにおけるGDPR型の厳格なコンプライアンスをケニアが要求していることを示しています。
AIガバナンスとデータ主権への注力
ケニアにはAIに特化した単独の法律はまだ存在しませんが、AIシステムの使用はDPA 2019やComputer Misuse and Cybercrimes Act 2018年(コンピューター誤用・サイバー犯罪法)など既存の法律によって規律されています。
ケニア政府は、AIガバナンスの整備に積極的であり、情報通信技術省(MICT)が「国家AI戦略2025-2030」を立ち上げ、AIアプリケーションに関するドラフト行動規範を策定するなど、国際的な規制動向に対応しています。
このAI戦略において、ケニアは「データ主権(Data Sovereignty)」の維持を優先事項として掲げており、ケニアが外国の法制度やプラットフォームに依存することなく、自国のデータ管理を確保することを重視しています。このデータ主権を重視する姿勢は、将来的に、国内にサーバー設置やデータ処理拠点の設置を義務付けるデータローカライゼーション規制につながる可能性を示しており、クラウドサービスやデジタル技術を用いたビジネス展開を検討する日本企業は、今後の規制動向を注視し、インフラ戦略を練る必要があります。
ケニアの雇用関係の規律と解雇手続
ケニアの労働関係を規律するEmployment Act 2007年は、労働者保護を重視しており、日本の労働法と比較して雇用主側の義務がより明確かつ厳格に規定されています。
解雇に際しては、労働契約書に明記がない場合、月給制の従業員に対しては28日間の予告期間を置くことが求められます。予告期間を置かない場合は、予告手当の支払いが必要です。
特に厳格なのは、企業の組織上の必要性に基づく整理解雇(Redundancy)の手続きです。雇用主は、整理解雇の手続きを開始する少なくとも1ヶ月前に、労働組合(組合員の場合)または労働官吏(Labour Officer)に書面で通知することが義務付けられています。解雇対象者の選定にあたっては、勤続年数(seniority)、能力(ability)、信頼性(reliability)といった公平な基準を用いたことを立証しなければなりません。
さらに、整理解雇の際には、勤続年数1年につき、最低15日分の給与に相当する法定退職金(Severance Pay)を従業員に支払うことが義務付けられています。これは、退職金の支払いが法的に義務付けられていない(任意設定の)日本とは決定的に異なる重要な点です。
不当解雇に対する立証責任は、厳格に雇用主側に課せられます。Employment Act第45条に基づき、雇用主は、解雇の理由が有効であり、かつ、従業員の行動、能力、または企業の運営上の必要性に基づいた公平な理由であることを証明できなければ、不当解雇と認定されます。また、手続きの公平性(Fair Procedure)を遵守したことも証明しなければなりません。
実務上の手続きにおいて、留意すべき特有の制限があります。Employment Act第48条は、労働官吏の前で行われる初期の聴聞会においては、弁護士(Advocates)が当事者の代理を務めることを禁止しています。この規定は、日本の労働審判制度とは異なり、雇用主企業の法務部や人事担当者が、専門的な法律の代理を伴わずに、厳格な手続きの場で労働官吏と直接交渉し、立証義務を果たさなければならない状況を生み出す可能性があり、手続き上のリスクを管理するための高度な準備が求められます。
ケニアの企業税制と許認可事業の概要
法人所得税と「支店利益送金税」
ケニアにおける法人所得税(Corporate Income Tax, CIT)は、居住者法人(現地子会社など)に対して原則30%が課税されます。
進出形態の選択に大きな影響を与える税制上の特徴として、非居住者の恒久的施設(Permanent Establishment, PE)である支店に対する課税構造が挙げられます。非居住者支店に対するCIT率は、居住者法人と同じく30%ですが(2024年1月1日以降) 、さらに、支店が本国(日本)へ利益を送金する際、支店利益送金税(Branch Repatriation Tax)として15%が源泉徴収されます(2024年1月1日以降)。
この15%の送金税は、支店形態を選択した場合の税務上の追加コストとなります。この税制は、ケニア政府が国内で活動する企業に対し、税務上の居住者たる現地法人(子会社)を設立して運営することを事実上推奨し、安定した税収基盤を確保したいという意図が読み取れます。したがって、日本企業がケニアで事業を展開する場合、税務効率の観点から、現地法人を設立する戦略が基本となります。
許認可が必要なビジネス分野
ケニアにおいて特定のビジネス分野で事業を展開するには、個別の法令に基づく許認可が必要です。これらは、日本の資金決済法、薬機法、医療広告ガイドラインなどに対応する規制です。
- 金融・資金決済分野(日本の資金決済法相当):銀行業、マイクロファイナンス、モバイルマネーを含むフィンテック事業は、Banking Actなどに基づき、ケニア中央銀行(CBK)の厳格な規制と事前の許認可の対象となります。
- 医薬品・医療分野(日本の薬機法・医療広告ガイドライン相当):医薬品、医療機器、およびその販売・広告は、Pharmacy and Poisons Board (PPB)などの特定の規制当局によるライセンスや承認が必須であり、日本の規制と同様に、広告内容についても詳細な規制が存在します。
- 通信分野:通信事業を行う場合は、Communications Authority (CA)の許認可が必要となります。
まとめ
ケニアは、東アフリカ市場へのゲートウェイとして魅力的な成長ポテンシャルを持つ一方で、その法制度は日本の大陸法体系とは大きく異なる構造を持っています。特に、コモン・ローに基づく法解釈の重要性、外国人による土地所有の99年リースホールド制限、払込資本金が500万KESを超える場合の会社秘書役(CS)の設置義務、GDPRモデルに基づくデータ管理者・処理者の強制登録、そして法定退職金制度や厳格な整理解雇手続きといった労働法上の厳しい要件は、日本の経営者や法務部員にとって、実務上の障壁となり得ます。
また、M&Aにおいては、外国企業間取引であってもケニア国内への競争影響があればCAKへの届出義務が生じるなど、国際的なコンプライアンスの範囲が広いことも確認されています。進出を成功させるためには、これらのケニア特有の法的要件、特に強制登録義務や労働紛争における手続きの厳格さに対し、初期段階から対応した専門的なデューデリジェンスとコンプライアンス体制の早期構築が不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務