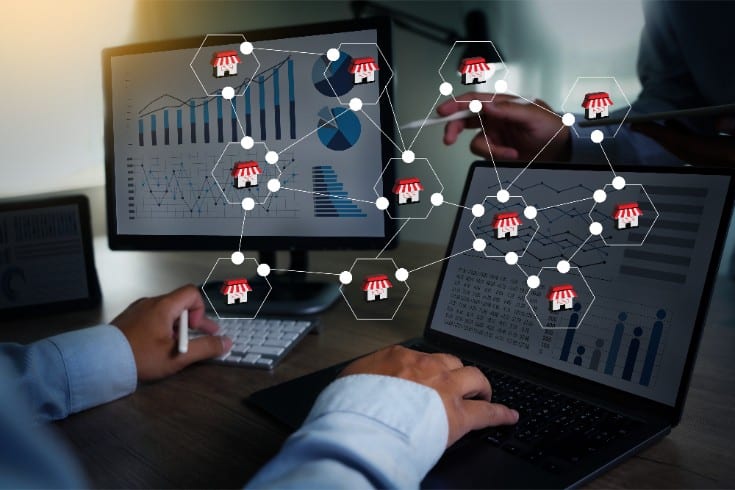台湾の広告規制を規律する公平交易法のポイント

台湾でのビジネス展開を検討する日本企業にとって、現地の法制度を正確に理解することは事業の成否を分ける重要な要素です。特に、広告プロモーションに関しては、日本の法体系とは大きく異なる台湾の規制環境に細心の注意を払う必要があります。台湾の「公平交易法」(Fair Trade Law, FTL)は、日本の景品表示法と独占禁止法の両方の側面を併せ持つ独自の法律であり、その広範な規制権限と厳格な連帯責任制度は、日本企業が台湾で直面する法的リスクを根本的に変え得るものです。
本記事では、この公平交易法における広告規制の核心に迫り、日本企業が事前に講じるべきコンプライアンス上の対策について、多角的な視点から解説します。
なお、台湾の包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
競争法と消費者保護を統合する台湾公平交易法
台湾の公平交易法は、その第1条において、「取引秩序の維持、消費者利益の保護、自由かつ公正な競争の確保並びに国民経済の安定及び繁栄の促進」を目的として制定されました。この目的規定は、日本の法体系を理解する上で重要な示唆を与えています。日本では、不当な表示を規制することで消費者保護を図る「景品表示法」と、不公正な取引方法や独占的行為を禁止することで公正競争を確保する「独占禁止法」が、それぞれ異なる役割を担い、消費者庁と公正取引委員会が管轄しています。
これに対し、台湾では、公平交易法という単一の法律が、これらの目的を統合的に果たしている点が大きな特徴です。実際に、公平交易法は、独占や企業結合、聯合行為(concerted action)といった日本の独占禁止法に相当する競争法上の規制と、虚偽・誤解を招く広告の禁止という日本の景品表示法に相当する消費者保護上の規制の両方を、同一の法律内で規定しています。
この統合的な法体系は、台湾の規制当局である公平交易委員会(FTC)の権限を格段に広げる結果をもたらします。例えば、ある不当な広告表示が、単なる消費者への誤認だけでなく、同時に公正な競争を阻害する行為としても捉えられた場合、公平交易委員会は競争法と消費者保護の両方の側面から包括的かつ厳格な調査や処分を行うことが可能です。これは、日本であれば管轄が分かれる可能性のある事案であっても、台湾では一つの当局が両方の角度からアプローチできるため、企業側はより重層的な法的リスクに晒されることになります。単なる法律の分類の違いではなく、企業が直面する法的リスクの構造そのものが、台湾ではより複雑であることを意味します。
台湾における虚偽・誤解を招く広告表示の禁止(公平交易法第21条)

台湾の広告規制において中心的な役割を果たすのが、公平交易法第21条です。同条第1項は、事業者が商品や広告、その他の方法を通じて、消費者の取引決定に影響を与える事項について、「虚偽不実又は引人錯誤の表示又は表徴」を行うことを禁じています。
この規定が日本の景品表示法と比べて特に厳格なのは、「虚偽不実」(false)と「引人錯誤」(misleading)を明確に区別し、後者の概念を非常に広く解釈している点にあります。「虚偽不実」は、表示された内容が客観的事実と異なる場合を指しますが、「引人錯誤」は、たとえ個々の事実が真実であったとしても、その表示が全体として消費者に誤った認識や判断をさせる可能性があれば、規制対象となります。
公平交易委員会は、この「引人錯誤」の概念に基づき、広告の全体的な印象や文脈を厳しく評価します。例えば、ウェブサイトでの不当な二重価格表示や、広告の小さな文字で書かれた割引の制限条件などがこれに該当する可能性があります。実際に、ある通信事業者が「通話・インターネット使い放題」と宣伝しながら、非常に小さな文字で制限条件を付記していた事例では、台湾の最高行政法院は、その小さな文字の表示が消費者の誤解を打ち消すに足りないと判断し、違反を認定しました。これは、広告の「事実性」だけでなく、「視認性」や「伝達方法」も厳しく問われることを示しています。
日本の景品表示法における「優良誤認表示」も、誇大な表現などを規制しますが、台湾の「引人錯誤」の概念は、広告の全体的な印象やデザイン、文字サイズといった文脈にまで及ぶと考えられます。したがって、日本企業が台湾で広告を運用する際には、単に広告内容のファクトチェックを行うだけでなく、広告が消費者に与える「全体的な印象」に対する綿密なリーガルチェックが不可欠です。日本の感覚でクリエイティブやコピーを作成すると、意図せず「引人錯誤」と判断されるリスクがあると言えるでしょう。
台湾の広告代理店の連帯責任
台湾の公平交易法が持つ、日本法と決定的に異なるもう一つの重要な特徴は、広告に関わる全てのプレイヤーに広範な「連帯責任」を課している点です。公平交易法第21条第5項は、広告主(事業者)だけでなく、以下の関係者にも連帯して損害賠償責任を負うことを規定しています。
- 広告代理業者: 「明知或可得而知」(知っていた、または知り得たはずの状況)で誤解を招く広告を制作・設計した場合、広告主と連帯して損害賠償責任を負います。
- 広告媒体業者: 「明知或可得而知」(知っていた、または知り得たはずの状況)で誤解を招く広告を伝播・掲載した場合、広告主と連帯して損害賠償責任を負います。
これに対し、日本の景品表示法における「ステルスマーケティング規制」は、広告であることを明示しない表示を禁止していますが、違反した場合の罰則を受ける主体は、少なくとも原則としては、広告主である「事業者」のみです。広告代理店やインフルエンサーなどの第三者は、少なくとも原則的には、罰則の対象にはなりません。
この違いは、日本企業が台湾で広告を打つ際のパートナー選定と契約プロセスに大きな影響を与えます。日本では、広告代理店や媒体が、広告主から提供された情報の真偽について、そこまで厳格な法的責任を負うことは想定されていません。しかし、台湾では、これらのパートナーにもデューデリジェンスの義務が課されており、これを怠れば連帯責任を問われるリスクがあります。これは、リスク管理の負担が広告主だけでなく、サプライチェーン全体に広がるということを意味します。
以下の表は、台湾公平交易法と日本の広告規制との主要な違いを整理したものです。
| 台湾 公平交易法(FTL) | 日本 景品表示法/独占禁止法 | |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 公平交易法(FTL) | 景品表示法、独占禁止法 |
| 規制対象 | 虚偽表示と誤解を招く表示(価格、品質、用途、原産地など) | 優良誤認表示、有利誤認表示(ステルスマーケティング規制も含む) |
| 責任の主体 | 広告主、広告代理業者、広告媒体業者、薦證者(インフルエンサー) | 原則として事業者(広告主) |
| 連帯責任の有無 | 明示的に規定あり(明知或可得而知が要件) | 規定なし(事業者への措置命令が主) |
| 罰則 | 行政罰(罰金)、損害賠償責任(インフルエンサーは報酬の10倍まで) | 行政罰(措置命令、課徴金)、事業者への刑事罰 |
台湾のインフルエンサーマーケティングに対する特殊な責任規定

インフルエンサーマーケティングが盛んな現代において、公平交易法はインフルエンサー(「広告薦證者」)に特有の連帯責任規定を設けています。公平交易法第21条第6項は、「広告薦證者」を「広告主以外で、広告中で商品やサービスに対する意見、信頼、発見、または親身体験の結果を反映する個人または組織」と定義しています。これには、著名な芸能人や専門家だけでなく、ブロガーやライブ配信者などの一般消費者も含まれます。
彼らもまた、「明知或可得而知」(明白に知っている)の状況下で誤解を招く薦證を行った場合、広告主と連帯して損害賠償責任を負うことになります。特に注目すべきは、公平交易法が「知名な公衆人物、専門家、または機関に属さない」広告薦證者については、その連帯責任を「受領した報酬の10倍の範囲内」に限定するというユニークな規定を設けている点です。
この規定は、一見すると責任を限定しているように見えますが、その本質は「インフルエンサー自身に直接的な法的責任がある」ということを明確化し、そのリスクを金銭的に定量化した点にあります。このルールは、インフルエンサー側に、広告内容の真実性について自身で確認する義務を強く課す動機となります。台湾の公平交易委員会は、ブロガーやインフルエンサーを明確に規制対象とすることを公表しており、実際に違反したインフルエンサーに罰金を科した事例も存在します。
日本企業にとって必要な台湾のリスク管理
上記で解説した台湾の厳格な広告規制環境を乗り越え、台湾でのビジネスを成功させるためには、日本企業は自社の立場に応じた実務的なリスク管理を徹底する必要があります。
広告主としての日本企業が取るべき対応
日本の景品表示法上、広告内容の不当表示が問題になった場合、原則として責任を負うのは広告主(事業者)のみです 。そのため、広告主は日本国内での広告活動においても、広告内容の真実性を担保するためのデューデリジェンスが不可欠です。一方で、台湾では公平交易法により、広告主だけでなく、広告代理業者や広告媒体業者も「知り得たはずの状況」で不実広告を制作・掲載した場合、広告主と連帯して損害賠償責任を負います。
この「連帯責任」の存在は、日本企業が広告主として台湾で事業を行う際に、新たなリスクのレイヤーをもたらします。もしパートナーである台湾の広告代理店や媒体が、虚偽広告によって消費者や競合他社から損害賠償を請求された場合、彼らも同様に連帯責任を負うことになります 。その結果、法的リスクを負った台湾のパートナーが、その原因を作ったとして日本企業(広告主)に対して求償権を行使する可能性が考えられます。
このようなリスクを回避するためには、広告主としての日本企業は、パートナー企業に対し、広告内容の真実性に関する調査義務を契約上で明確に課す必要があります。また、万が一の際の責任分担についても、詳細な条項を設けるべきでしょう。これにより、自社だけでなく、サプライチェーン全体のコンプライアンス意識を高め、予期せぬ法的紛争から自社の身を守ることにつながります。
広告代理店としての日本企業が取るべき対応
もし日本企業が台湾で広告代理事業を展開する場合、台湾の公平交易法が定める連帯責任は、直接的な法的リスクとなります。日本の法律では、広告代理店は原則として行政罰の対象にはなりませんが 、台湾では「明知或可得而知」という要件を満たせば、広告主と共に消費者等への損害賠償責任を負うだけでなく、公平交易委員会から行政罰を受ける可能性もあります。
したがって、台湾で広告代理事業を行う日本企業は、広告主から受け取った広告内容について、その真実性を自ら徹底的にデューデリジェンスする作業を怠ることはできません。具体的には、広告に記載された効能、効果、価格、品質などの主張について、客観的な証拠資料(科学的根拠、データ、第三者機関の認証など)の提出を広告主に求め、その内容を精査するプロセスを確立する必要があります。この厳格なデューデリジェンス体制は、単なる業務の一環ではなく、企業自身の存続に関わる重要なリスク管理となります。
まとめ
台湾の広告規制は、日本の法体系と類似する部分もありますが、特に「連帯責任」という点で、日本企業にとって見過ごせない重大な違いが存在します。安易に日本と同様の感覚で広告プロモーションを展開すると、予期せぬ法的責任を負うリスクがあることを認識すべきです。
広告主としての日本企業は、台湾のパートナー企業が連帯責任を負うリスクがあることを理解し、その求償を防ぐためにも、広告内容に関する厳格な契約とデューデリジェンスを徹底する必要があります。他方、台湾で広告代理事業を展開する日本企業は、自らが行政罰や損害賠償責任の直接的な対象となるため、広告内容の真実性についてより高い注意義務が求められます。
この複雑で厳格な規制環境を乗り越えるためには、現地の法律に精通した専門家による事前のリーガルチェックが不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務