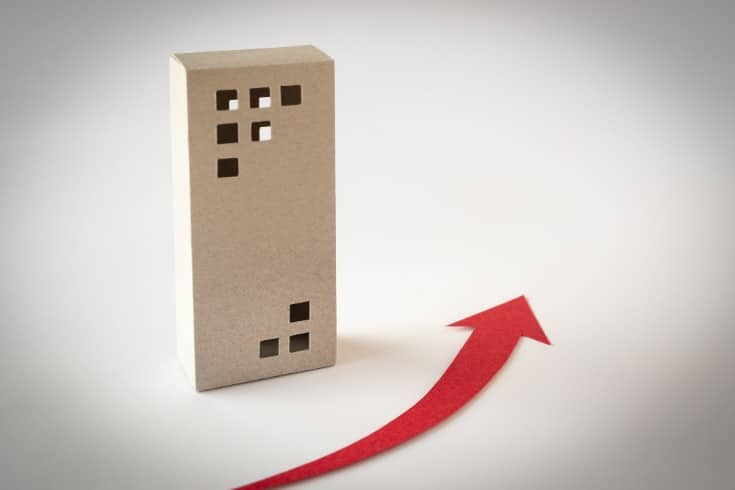гӮўгғЎгғӘгӮ«еҗҲиЎҶеӣҪ NASDAQгҒ®дёҠе ҙе»ғжӯўгҒЁгҒқгҒ®иҰҒ件гҒ«й–ўгҒҷгӮӢи§ЈиӘ¬

NASDAQгҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјдјҒжҘӯгӮ„жҲҗй•·дјҒжҘӯгҒҢдёҠе ҙгҒҷгӮӢгҖҒдё–з•ҢгҒ§жңҖгӮӮеҪұйҹҝеҠӣгҒ®гҒӮгӮӢиЁјеҲёеёӮе ҙгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮгӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гҒӘдәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’еҝ—еҗ‘гҒҷгӮӢж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®еёӮе ҙгҒёгҒ®дёҠе ҙгҒҜйҮҚиҰҒгҒӘзӣ®жЁҷгҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒNASDAQдёҠе ҙеҫҢгҒ®дјҒжҘӯгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒ®ең°дҪҚгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҺіж јгҒӘиҰҒ件гҒҢиӘІгҒӣгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дёҠе ҙе»ғжӯўгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢдјҒжҘӯгҒ®иІЎеӢҷзҡ„гҒӘеӨұж•—гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж ӘдҫЎгҒ®дҪҺиҝ·гҖҒж Әдё»ж•°гҒ®жёӣе°‘гҖҒгӮігғјгғқгғ¬гғјгғҲгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒ®дёҚеӮҷгҒӘгҒ©гҖҒеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢиҰҒеӣ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеј•гҒҚиө·гҒ“гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдёҠе ҙе»ғжӯўгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒдәҲжңҹгҒӣгҒ¬дәӢж…ӢгӮ’еӣһйҒҝгҒ—гҖҒжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒӘзұіеӣҪдәӢжҘӯжҲҰз•ҘгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢдёҠгҒ§дёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒNASDAQгҒ®дёҠе ҙз¶ӯжҢҒеҹәжә–гҖҒдёҠе ҙе»ғжӯўгҒ«иҮігӮӢи©ізҙ°гҒӘгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҖҒгҒқгҒ—гҒҰж—Ҙжң¬гҒ®еҲ¶еәҰгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘжі•д»ӨгӮ„иҝ‘е№ҙгҒ®еӢ•еҗ‘гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜеҲӨдҫӢгӮ’дәӨгҒҲгҒҰз¶Ізҫ…зҡ„гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
NASDAQдёҠе ҙз¶ӯжҢҒеҹәжә–гҒ®е…ЁдҪ“еғҸгҒЁеёӮе ҙгҒ®йҡҺеұӨжҖ§
NASDAQеёӮе ҙгҒҜгҖҒгҒқгҒ®дёҠе ҙеҹәжә–гҒ®еҺіж јгҒ•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҢNASDAQгӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гғ»гӮ»гғ¬гӮҜгғҲгғ»гғһгғјгӮұгғғгғҲгҖҚгҖҢNASDAQгӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гғ»гғһгғјгӮұгғғгғҲгҖҚгҖҢNASDAQгӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«гғ»гғһгғјгӮұгғғгғҲгҖҚгҒ®3гҒӨгҒ®еёӮе ҙеұӨгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҗ„еёӮе ҙгҒҜз•°гҒӘгӮӢеҹәжә–гӮ’йҒ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдјҒжҘӯгҒҜиҮӘзӨҫгҒ®иҰҸжЁЎгӮ„иІЎеӢҷзҠ¶жіҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ®еёӮе ҙгҒ«дёҠе ҙгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢж Әдё»ж•°пјҲ300дәәд»ҘдёҠпјүгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®еҹәжә–гҒҜгҖҒдё»гҒ«NASDAQгӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«гғ»гғһгғјгӮұгғғгғҲгҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢз¶ҷз¶ҡдёҠе ҙеҹәжә–гҒ§гҒҷгҖӮ
дёҠе ҙз¶ӯжҢҒеҹәжә–гҒҜгҖҒдё»гҒ«д»ҘдёӢгҒ®3гҒӨгҒ®йЎһеһӢгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
- ж ӘдҫЎгғ»жөҒеӢ•жҖ§еҹәжә–пјҡж ӘдҫЎгҖҒжө®еӢ•ж ӘгҒ®жҷӮдҫЎз·ҸйЎҚгҖҒж Әдё»ж•°гҖҒеҸ–еј•й«ҳгҒӘгҒ©гҖҒж ӘејҸгҒ®е…¬жӯЈгҒӘжөҒйҖҡгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҹәжә–гҒ§гҒҷгҖӮ
- иІЎеӢҷеҹәжә–пјҡж Әдё»иіҮжң¬гҖҒзҙ”еҲ©зӣҠгҖҒз·ҸиіҮз”Јгғ»з·ҸеЈІдёҠй«ҳгҒӘгҒ©гҖҒдјҒжҘӯгҒ®иІЎж”ҝзҡ„гҒӘеҒҘе…ЁжҖ§гӮ’зӨәгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®еҹәжә–гҒ§гҒҷгҖӮ
- дјҒжҘӯзөұжІ»еҹәжә–пјҡзӢ¬з«ӢеҸ–з· еҪ№гҒ®иЁӯзҪ®гҖҒзӣЈжҹ»е§”е“ЎдјҡгҒ®ж§ӢжҲҗгҖҒж Әдё»з·ҸдјҡгҒ®й–ӢеӮ¬гҒӘгҒ©гҖҒеҒҘе…ЁгҒӘгӮігғјгғқгғ¬гғјгғҲгӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҹәжә–гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҹәжә–гҒҜгҖҒдјҒжҘӯгҒ®иҰҸжЁЎгӮ„зү№жҖ§гҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒеҗ„еёӮе ҙеұӨгҒ§з•°гҒӘгӮӢж•°еҖӨиҰҒ件гҒҢиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж–°иҲҲдјҒжҘӯгҒҢдёҠе ҙгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„NASDAQгӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«гғ»гғһгғјгӮұгғғгғҲгҒЁNASDAQгӮ°гғӯгғјгғҗгғ«гғ»гғһгғјгӮұгғғгғҲгҒ®еҹәжә–гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
NASDAQдёҠе ҙе»ғжӯўгҒ®дё»иҰҒгҒӘе®ҡйҮҸзҡ„иҰҒ件гҒЁиҝ‘е№ҙгҒ®еҺіж јеҢ–
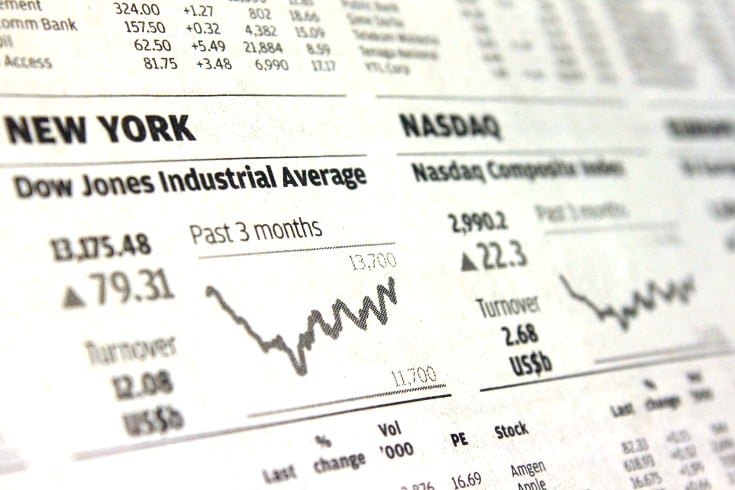
ж ӘдҫЎпјҲBid PriceпјүгҒ®еҹәжә–
NASDAQгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҠе ҙз¶ӯжҢҒгҒ®жңҖгӮӮеҹәжң¬зҡ„гҒӘеҹәжә–гҒ®дёҖгҒӨгҒҢгҖҒж ӘдҫЎгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮNASDAQгҒ®гғ«гғјгғ«гғ–гғғгӮҜпјҲRule 5810(c)(3)(A)(i)пјүгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒеҪ“и©ІдјҒжҘӯгҒ®ж ӘдҫЎгҒ®зөӮеҖӨгҒҢ30е–¶жҘӯж—ҘйҖЈз¶ҡгҒ§1.00гғүгғ«жңӘжәҖгҒ§жҺЁз§»гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒдёҠе ҙе»ғжӯўжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҹәжә–гҒ«жҠөи§ҰгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒNASDAQгҒӢгӮүгҖҢгғҮгғ•гӮЈгӮ·гӮ§гғігӮ·гғјгғ»гғҺгғјгғҶгӮЈгӮ№пјҲDeficiency NoticeпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢж”№е–„иҰҒи«ӢйҖҡзҹҘгҒҢзҷәиЎҢгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдјҒжҘӯгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®йҖҡзҹҘгҒ®еҸ—й ҳеҫҢ4е–¶жҘӯж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ«гҖҒзұіеӣҪиЁјеҲёеҸ–引委員дјҡпјҲSECпјүгҒёгҒ®гғ•гӮ©гғјгғ 8-KгҒ®жҸҗеҮәгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜгғ—гғ¬гӮ№гғӘгғӘгғјгӮ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®дәӢе®ҹгӮ’е…¬иЎЁгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
йҖҡзҹҘгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹдјҒжҘӯгҒ«гҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰ180жҡҰж—Ҙй–“гҒ®ж”№е–„жңҹй–“гҒҢдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жңҹй–“еҶ…гҒ«гҖҒзөӮеҖӨгҒҢ10е–¶жҘӯж—ҘйҖЈз¶ҡгҒ§1.00гғүгғ«д»ҘдёҠгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒдёҠе ҙе»ғжӯўгҒҜеӣһйҒҝгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒNASDAQгӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«гғ»гғһгғјгӮұгғғгғҲгҒ®з¶ҷз¶ҡдёҠе ҙиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒиҝҪеҠ гҒ§180ж—Ҙй–“гҒ®з¬¬2ж”№е–„жңҹй–“гҒҢд»ҳдёҺгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иҝ‘е№ҙгҒ®ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ®дҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгғЎгғҮгӮЈгғӯгғ гғ»гӮ°гғ«гғјгғ—гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҗҢзӨҫгҒҜгҖҒж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®гғ‘гғігғҮгғҹгғғгӮҜгҒ«гӮҲгӮҠгӮ·гғ§гғғгғ”гғігӮ°гӮ»гғігӮҝгғјеҶ…гҒ®еә—иҲ—гҒҢй–үйҺ–гҒ•гӮҢгҖҒеЈІдёҠгҒҢгҒ»гҒјгӮјгғӯгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиӢҰеўғгҒ«зӣҙйқўгҒ—гҖҒй«ҳгҒ„иІ еӮөжҜ”зҺҮпјҲ190%пјүгҒЁдҪҺгҒ„зҙ”еҲ©зӣҠзҺҮпјҲ1.79%пјүгӮ’жҠұгҒҲгҖҒж ӘдҫЎгҒҢдҪҺиҝ·гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж ӘдҫЎдҪҺиҝ·гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҗҢзӨҫгҒҜNASDAQгҒ®жңҖдҪҺе…ҘжңӯдҫЎж јиҰҒ件пјҲзөӮеҖӨ1гғүгғ«д»ҘдёҠпјүгҒ«жҠөи§ҰгҒ—гҖҒ2025е№ҙ2жңҲгҒ«дёҚйҒ©еҗҲгҒ®йҖҡзҹҘгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ«иҮігӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғЎгғҮгӮЈгғӯгғ гҒҜгҖҒжҠңжң¬зҡ„гҒӘзөҢе–¶ж”№йқ©гҒ«иҲөгӮ’еҲҮгӮҠгҖҒеӮҳдёӢгҒ®иӨҮж•°дәӢжҘӯгӮ’зөұеҗҲгғ»еҶҚз·ЁгҒ—гҖҒеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘдәӢжҘӯйҒӢе–¶гҒЁйЎ§е®ўгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еј·еҢ–гӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзөҢе–¶еҹәзӣӨгҒ®еҶҚж§ӢзҜүгӮ’и©ҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӢжҘӯж”№е–„гҒёгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҢгҖҒеёӮе ҙгҒӢгӮүгҒ®дҝЎй јеӣһеҫ©гҒ«з№ӢгҒҢгӮҠгҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҗҢзӨҫгҒ®зұіеӣҪй җиЁ—иЁјеҲёпјҲADSпјүгҒҜгҖҒ2025е№ҙ5жңҲгҒӢгӮү10е–¶жҘӯж—ҘйҖЈз¶ҡгҒ§зөӮеҖӨгҒҢ1.00гғүгғ«д»ҘдёҠгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҖҒ2025е№ҙ6жңҲгҒ«гҒҜNASDAQгҒӢгӮүгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№еӣһеҫ©гҒ®йҖҡзҹҘгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒдёҠе ҙе»ғжӯўгҒ®еҚұж©ҹгӮ’д№—гӮҠи¶ҠгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒиҝ‘е№ҙгҒ®еӢ•еҗ‘гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒNASDAQгҒҜгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғ«гғјгғ«гӮ’гҒ•гӮүгҒ«еҺіж јеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒ2025е№ҙ8жңҲгҒҫгҒ§гҒ«гҖҒж ӘдҫЎгҒҢ10е–¶жҘӯж—ҘйҖЈз¶ҡгҒ§0.10гғүгғ«жңӘжәҖгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒж”№е–„жңҹй–“гҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгӮҲгӮҠиҝ…йҖҹгҒ«дёҠе ҙе»ғжӯўгӮ’жұәе®ҡгҒ§гҒҚгӮӢж–°гғ«гғјгғ«гӮ’жҸҗжЎҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒжҠ•иіҮ家дҝқиӯ·гҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүгҖҒжҘөз«ҜгҒӘдҪҺдҪҚж ӘгҒ®еҸ–еј•гӮ’ж—©жңҹгҒ«еҒңжӯўгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғӘгғҗгғјгӮ№гғ»гӮ№гғҲгғғгӮҜгғ»гӮ№гғ—гғӘгғғгғҲгҒ®еҲ¶йҷҗ
гҒҫгҒҹгҖҒж ӘдҫЎеӣһеҫ©зӯ–гҒЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгғӘгғҗгғјгӮ№гғ»гӮ№гғҲгғғгӮҜгғ»гӮ№гғ—гғӘгғғгғҲпјҲж ӘејҸдҪөеҗҲпјүгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮӮеҲ¶йҷҗгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж ӘдҫЎгҒ®еҹәжә–гҒҜгҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гҖҢж ӘдҫЎгҒҢ1.00гғүгғ«д»ҘдёҠгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҹәжә–гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒж ӘејҸдҪөеҗҲгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®еҹәжә–гӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒж ӘдҫЎгҒҢ0.9гғүгғ«гҒ®дјҒжҘӯгҒҢ2ж ӘгӮ’1ж ӘгҒ«гҒҷгӮӢж ӘејҸдҪөеҗҲгӮ’иЎҢгҒҲгҒ°гҖҒгҒқгҒ®дјҡзӨҫгҒ®жҷӮдҫЎз·ҸйЎҚгҒҢеӨүгӮҸгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒеҚҳзҙ”гҒ«ж ӘдҫЎгҒҜ1.8гғүгғ«гҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиЁҖгҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜжң¬иіӘзҡ„гҒӘи§ЈжұәгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
NASDAQгҒҜгҖҒ2025е№ҙ1жңҲгҒ«гҒҜгҖҒж ӘејҸдҪөеҗҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж ӘдҫЎеҹәжә–гӮ’дёҖжҷӮзҡ„гҒ«еӣһеҫ©гҒ•гҒӣгҒҹдјҒжҘӯгҒҢгҖҒгҒқгҒ®1е№ҙд»ҘеҶ…гҒ«еҶҚеәҰеҹәжә–гӮ’еүІгӮҠиҫјгӮ“гҒ е ҙеҗҲгҖҒж”№е–„жңҹй–“гҒҢд»ҳдёҺгҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж–°гғ«гғјгғ«гӮ’ж–ҪиЎҢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғ«гғјгғ«еӨүжӣҙгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«ж•°еҖӨзҡ„гҒӘеҹәжә–гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒдјҒжҘӯгҒ®ж №жң¬зҡ„гҒӘиІЎеӢҷгғ»дәӢжҘӯдҪ“иіӘгҒ®ж”№е–„гӮ’дҝғгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶNASDAQгҒ®ж„ҸеӣігҒӢгӮүзӯ–е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮж–°гғ«гғјгғ«гҒҜгҖҒгғӘгғҗгғјгӮ№гғ»гӮ№гғҲгғғгӮҜгғ»гӮ№гғ—гғӘгғғгғҲгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒҷдјҒжҘӯгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒж №жң¬зҡ„гҒӘе•ҸйЎҢи§ЈжұәгӮ’иЎҢгӮҸгҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒдёҠе ҙз¶ӯжҢҒгҒҜеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеј·гҒ„гғЎгғғгӮ»гғјгӮёгӮ’зҷәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҜгҖҒNASDAQгҒҢеҪўејҸзҡ„гҒӘгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе®ҹиіӘзҡ„гҒӘдјҒжҘӯдҫЎеҖӨгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—е§ӢгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгғҲгғ¬гғігғүгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮВ
ж Әдё»ж•°гғ»жҷӮдҫЎз·ҸйЎҚгғ»жөҒеӢ•жҖ§гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҹәжә–
NASDAQгҒ®з¶ҷз¶ҡдёҠе ҙеҹәжә–гҒҜгҖҒж ӘдҫЎд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮдјҒжҘӯгҒ®иІЎеӢҷзҠ¶жіҒгӮ„ж ӘејҸгҒ®жөҒеӢ•жҖ§гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиӨҮж•°гҒ®иҰҒ件гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒNASDAQгӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«гғ»гғһгғјгӮұгғғгғҲгҒ§гҒҜгҖҒз¶ҷз¶ҡдёҠе ҙгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жңҖдҪҺ300дәәгҒ®ж Әдё»гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гӮ°гғӯгғјгӮ№еёӮе ҙпјҲ150дәәд»ҘдёҠпјүгӮ„гӮ№гӮҝгғігғҖгғјгғүеёӮе ҙпјҲ400дәәд»ҘдёҠпјүгҒЁйЎһдјјгҒ—гҒҹеҹәжә–гҒ§гҒҷгҖӮВ
гҒҫгҒҹгҖҒжңҖдҪҺжҷӮдҫЎз·ҸйЎҚиҰҒ件 (NASDAQ Listing Rule 5550(b)(2))гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒиӨҮж•°гҒ®еҹәжә–гҒ®дёӯгҒӢгӮүдёҖгҒӨгӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§дёҠе ҙгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ§гҒҚгӮӢйҒёжҠһиӮўгӮ’дјҒжҘӯгҒ«дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒNASDAQгӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«гғ»гғһгғјгӮұгғғгғҲгҒ§гҒҜгҖҒдјҒжҘӯгҒҜд»ҘдёӢгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ®еҹәжә–гӮ’жәҖгҒҹгҒҷеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷ гҖӮ
- ж Әдё»иіҮжң¬пјҲStockholders’ EquityпјүгҒҢ250дёҮгғүгғ«д»ҘдёҠ гҖӮ
- дёҠе ҙиЁјеҲёгҒ®жҷӮдҫЎз·ҸйЎҚпјҲMarket Value of Listed Securities, MVLSпјүгҒҢ3,500дёҮгғүгғ«д»ҘдёҠ гҖӮ
- з¶ҷз¶ҡдәӢжҘӯгҒӢгӮүгҒ®зҙ”еҲ©зӣҠпјҲNet Income from Continuing OperationsпјүгҒҢзӣҙиҝ‘дјҡиЁҲе№ҙеәҰгҒ§50дёҮгғүгғ«д»ҘдёҠгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜзӣҙиҝ‘3дјҡиЁҲе№ҙеәҰдёӯ2жңҹгҒ§50дёҮгғүгғ«д»ҘдёҠ гҖӮ
иҝ‘е№ҙгҒ®ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ®дҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгӮўгғјгғӘгғјгғҜгғјгӮҜгӮ№гҒҜгҖҒдёҠе ҙиЁјеҲёгҒ®жҷӮдҫЎз·ҸйЎҚпјҲMVLSпјүгҒҢ30е–¶жҘӯж—ҘйҖЈз¶ҡгҒ§3,500дёҮгғүгғ«гӮ’дёӢеӣһгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒ2024е№ҙ10жңҲгҒ«NASDAQгҒӢгӮүдёҚйҒ©еҗҲйҖҡзҹҘгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒ2025е№ҙ5жңҲгҒ«гҒҜгҖҒжңҖдҪҺж Әдё»иіҮжң¬250дёҮгғүгғ«гҒ®еҹәжә–гӮӮжәҖгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҗҢзӨҫгҒҜгҖҒдёҠе ҙе»ғжӯўгғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’еҒңжӯўгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒNASDAQгғ’гӮўгғӘгғігӮ°гғ‘гғҚгғ«гҒ«дёҠиЁҙгҒ—гҖҒз¶ҷз¶ҡдёҠе ҙгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®зҢ¶дәҲжңҹй–“гӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжңҖдҪҺе…ҘжңӯдҫЎж јиҰҒ件гҒ«гӮӮдёҖжҷӮзҡ„гҒ«жҠөи§ҰгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒе…¬иҒҙдјҡгӮ’еүҚгҒ«ж ӘдҫЎгӮ’еӣһеҫ©гҒ•гҒӣгҖҒгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гӮ’еӣһеҫ©гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жө®еӢ•ж ӘпјҲе…¬й–ӢжөҒйҖҡж ӘпјүгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒNASDAQгӮӯгғЈгғ”гӮҝгғ«гғ»гғһгғјгӮұгғғгғҲгҒ§гҒҜгҖҒжө®еӢ•ж Әж•°гҒҢ100дёҮж Әд»ҘдёҠгҖҒгҒқгҒ®жҷӮдҫЎз·ҸйЎҚгҒҢжңҖдҪҺ500дёҮгғүгғ«гҒҫгҒҹгҒҜ1,500дёҮгғүгғ«гӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒж–°иҰҸдёҠе ҙдјҒжҘӯгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒ2025е№ҙ4жңҲгҒ«гҒҜгҖҒеёӮе ҙдҫЎеҖӨеҹәжә–гӮ’жәҖгҒҹгҒҷйҡӣгҖҒгҒқгҒ®ж ӘејҸгҒҢIPOгҒ§еЈІеҚҙгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҒҝгҒҢиҖғж…®гҒ•гӮҢгҖҒж—ўеӯҳгҒ®еЈІеҚҙж Әдё»гҒҢдҝқжңүгҒҷгӮӢж ӘејҸгҒҜйҷӨеӨ–гҒ•гӮҢгӮӢгғ«гғјгғ«гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёҠе ҙе»ғжӯўгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒЁз•°иӯ°з”ігҒ—з«ӢгҒҰгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚ
дёҠе ҙе»ғжӯўгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒеҹәжә–жҠөи§ҰгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҹйҡӣгҒ®NASDAQгҒӢгӮүгҒ®йҖҡзҹҘгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮNASDAQгҒ®дёҠе ҙиіҮж јеҜ©жҹ»йғЁпјҲListing Qualifications DepartmentпјүгҒӢгӮүйҖҡзҹҘгҒҢзҷәиЎҢгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҖҒдјҒжҘӯгҒҜж”№е–„иЁҲз”»гӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҖҒдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹж”№е–„жңҹй–“еҶ…гҒ§еҹәжә–гӮ’еӣһеҫ©гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжңҹй–“еҶ…гҒ«еҹәжә–гӮ’жәҖгҒҹгҒӣгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒNASDAQгҒҜгҖҢдёҠе ҙе»ғжӯўжұәе®ҡйҖҡзҹҘжӣёпјҲStaff Delist DeterminationпјүгҖҚгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®жұәе®ҡгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒдјҒжҘӯгҒҜгҖҢгғ’гӮўгғӘгғігӮ°гғ»гғ‘гғҚгғ«пјҲHearings PanelпјүгҖҚгҒёгҒ®з•°иӯ°з”ігҒ—з«ӢгҒҰгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®з”ігҒ—з«ӢгҒҰгҒҜгҖҒжұәе®ҡгҒӢгӮү7ж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ«иЎҢгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠдёҠе ҙе»ғжӯўгҒҜдёҖжҷӮзҡ„гҒ«еҒңжӯўгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгғ‘гғҚгғ«гҒ®жұәе®ҡгҒ«дёҚжңҚгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҢNASDAQдёҠе ҙгғ»иҒҙиҒһеҜ©жҹ»и©•иӯ°дјҡпјҲNasdaq Listing and Hearing Review CouncilпјүгҖҚгҒ«дёҠиЁҙгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮи©•иӯ°дјҡгҒ®жұәе®ҡгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰNASDAQгҒ®жңҖзөӮзҡ„гҒӘжұәе®ҡгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒи©•иӯ°дјҡгҒ®жұәе®ҡгҒ«дёҚжңҚгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҖҒжңҖзөӮжүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдјҒжҘӯгҒҜSECгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰдёҠиЁҙгӮ’жҸҗиө·гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒNASDAQгҒ®иЈҒйҮҸжЁ©гҒҢзө¶еҜҫзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзұіеӣҪгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮNASDAQгҒ®иЈҒйҮҸжЁ©гҒ«гҒҜйҷҗз•ҢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ2024е№ҙ12жңҲ11ж—ҘгҖҒзұіеӣҪ第5е·ЎеӣһеҢәйҖЈйӮҰжҺ§иЁҙиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒNASDAQгҒҢжҸҗжЎҲгҒ—SECгҒҢжүҝиӘҚгҒ—гҒҹгҖҢеҸ–з· еҪ№дјҡгҒ®еӨҡж§ҳжҖ§й–ӢзӨәгғ«гғјгғ«гҖҚгӮ’жЈ„еҚҙгҒҷгӮӢеҲӨжұәгӮ’дёӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒSECгҒҢгҖҢгғЎгӮёгғЈгғјгғ»гӮҜгӮЁгӮ№гғҒгғ§гғігӮәгғ»гғүгӮҜгғҲгғӘгғіпјҲMajor Questions DoctrineпјүгҖҚгҒ«з…§гӮүгҒ—гҒҰгҖҒйҖЈйӮҰиӯ°дјҡгҒӢгӮүжҳҺзўәгҒӘжЁ©йҷҗ委иӯІгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дәӢй …пјҲдјҒжҘӯгҒ®зөҢе–¶ж–№йҮқгҒ«й–ўгӮҸгӮӢзӨҫдјҡзҡ„гғ»ж”ҝжІ»зҡ„иҰҒ件пјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгғ«гғјгғ«гӮ’жүҝиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жЁ©йҷҗгӮ’йҖёи„ұгҒҷгӮӢиЎҢзӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒҢзӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒNASDAQгҒҢжҠ•иіҮ家дҝқиӯ·гҒ®еҗҚгҒ®дёӢгҒ«иЎҢгҒҶгғ«гғјгғ«зӯ–е®ҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®жЁ©йҷҗгҒ«гҒҜгҖҒйҖЈйӮҰжі•гҒ®жһ зө„гҒҝгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶйҷҗз•ҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
NASDAQгҒЁж—Ҙжң¬гҒ®дёҠе ҙеҲ¶еәҰгҒ®жҜ”ијғ

дёҠе ҙз¶ӯжҢҒеҹәжә–гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӮөеӢҷи¶…йҒҺгҒЁж ӘдҫЎеҹәжә–
зұіеӣҪNASDAQгҒ®дёҠе ҙе»ғжӯўеҹәжә–гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҲ¶еәҰгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гӮ’иӘҚиӯҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒдёҠе ҙз¶ӯжҢҒеҹәжә–гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжңҖгӮӮж №жң¬зҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гҒҜгҖҒиІЎеӢҷеҹәжә–гҒ®иҖғгҒҲж–№гҒ§гҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®е…ЁеёӮе ҙпјҲжқұиЁјгғ—гғ©гӮӨгғ гҖҒгӮ№гӮҝгғігғҖгғјгғүгҖҒгӮ°гғӯгғјгӮ№пјүгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢзҙ”иіҮз”ЈгҒҢжӯЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒҢдёҠе ҙз¶ӯжҢҒеҹәжә–гҒ®ж №е№№гӮ’гҒӘгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеӮөеӢҷи¶…йҒҺгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰдёҠе ҙе»ғжӯўгҒ®жұәе®ҡзҡ„гҒӘзҗҶз”ұгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒдјҒжҘӯгҒ®еӯҳз¶ҡеҸҜиғҪжҖ§гӮ’зӣҙжҺҘзҡ„гҒ«е•ҸгҒҶгҖҒйқһеёёгҒ«жҳҺзўәгҒӘеҹәжә–гҒ§гҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒNASDAQгҒ®дёҠе ҙз¶ӯжҢҒеҹәжә–гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гҖҢеӮөеӢҷи¶…йҒҺгҖҚгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢеҚҳдёҖгҒ®еҹәжә–гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҖҒж Әдё»иіҮжң¬пјҲStockholders’ EquityпјүгҖҒдёҠе ҙиЁјеҲёжҷӮдҫЎз·ҸйЎҚпјҲMarket Value of Listed SecuritiesпјүгҖҒз¶ҷз¶ҡдәӢжҘӯгҒӢгӮүгҒ®зҙ”еҲ©зӣҠпјҲNet Income from Continuing OperationsпјүгҒӘгҒ©гҖҒиӨҮж•°гҒ®еҹәжә–гҒ®дёӯгҒӢгӮүдёҖгҒӨгӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§дёҠе ҙгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йҒ•гҒ„гҒҜгҖҒж—ҘзұігҒ®еёӮе ҙгҒҢйҮҚиҰ–гҒҷгӮӢеҒҙйқўгҒ®е·®гӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҹәжә–гҒҢдјҒжҘӯгҒ®гҖҢиІЎж”ҝзҡ„еҒҘе…ЁжҖ§гҖҚгӮ’зө¶еҜҫзҡ„гҒӘжқЎд»¶гҒЁгҒҷгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒNASDAQгҒҜгӮҲгӮҠеӨҡж§ҳгҒӘжҢҮжЁҷпјҲеёӮе ҙгҒӢгӮүгҒ®и©•дҫЎгҖҒеҸҺзӣҠеҠӣгҒӘгҒ©пјүгӮ’иЁұе®№гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ
дёҠе ҙе»ғжӯўжүӢз¶ҡгҒҚгҒЁж”№е–„жңҹй–“гҒ®зӣёйҒ•
дёҠе ҙе»ғжӯўгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚйқўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒж—ҘзұігҒ®еёӮе ҙгҒ«гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
жқұиЁјгҒ§гҒҜгҖҒдёҠе ҙз¶ӯжҢҒеҹәжә–гҒ«жҠөи§ҰгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰ1е№ҙй–“гҒ®гҖҢж”№е–„жңҹй–“гҖҚгҒҢдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдёҠе ҙе»ғжӯўгҒҫгҒ§гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҢзӣЈзҗҶйҠҳжҹ„гҖҚгҖҢж•ҙзҗҶйҠҳжҹ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж®өйҡҺзҡ„гҒӘжҢҮе®ҡгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжҠ•иіҮ家гҒҜеҸ–еј•з¶ҷз¶ҡгҒ®еҸҜеҗҰгӮ„е»ғжӯўгҒҫгҒ§гҒ®зҢ¶дәҲгӮ’ж®өйҡҺзҡ„гҒ«жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒNASDAQгҒ®ж”№е–„жңҹй–“гҒҜеҺҹеүҮ180жҡҰж—ҘгҒЁгҖҒжқұиЁјгӮҲгӮҠзҹӯгҒ„жңҹй–“гҒ«иЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒеүҚиҝ°гҒ—гҒҹгҖҢгғӘгғҗгғјгӮ№гғ»гӮ№гғҲгғғгӮҜгғ»гӮ№гғ—гғӘгғғгғҲгҖҚгҒ®еҲ¶йҷҗгӮ„гҖҢ0.10гғүгғ«жңӘжәҖгҖҚгҒ§гҒ®еҚіжҷӮе»ғжӯўгғ«гғјгғ«гҒӘгҒ©гҖҒиҝ‘е№ҙгҒ§гҒҜгӮҲгӮҠиҝ…йҖҹгҒӢгҒӨеҺіж јгҒӘеҜҫеҝңгҒҢеј·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжқұиЁјгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒдјҒжҘӯгҒ«еҚҒеҲҶгҒӘж”№е–„гҒ®ж©ҹдјҡгӮ’дёҺгҒҲгҖҒжҠ•иіҮ家гҒ«гӮӮж®өйҡҺзҡ„гҒӘжғ…е ұй–ӢзӨәгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒNASDAQгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒеёӮе ҙгҒ®е…¬жӯЈжҖ§гҒЁжҠ•иіҮ家дҝқиӯ·гӮ’гӮҲгӮҠиҝ…йҖҹгҒ«е®ҹзҸҫгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢжҖқжғігӮ’еҸҚжҳ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзұіеӣҪгҒ§гҒҜгҖҒе•ҸйЎҢгҒ®гҒӮгӮӢдјҒжҘӯгӮ’еёӮе ҙгҒӢгӮүиҝ…йҖҹгҒ«жҺ’йҷӨгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒеёӮе ҙе…ЁдҪ“гҒ®еҒҘе…ЁжҖ§з¶ӯжҢҒгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒпјҡNASDAQгҒ®дёҠе ҙе»ғжӯўеҹәжә–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгӮ’
NASDAQгҒ®дёҠе ҙе»ғжӯўеҹәжә–гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҲ¶еәҰгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢеҺіж јгҒ•гҒЁгӮ№гғ”гғјгғүж„ҹгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҚҳгҒ«дёҠе ҙеҹәжә–гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘдјҒжҘӯдҫЎеҖӨгҒ®еҗ‘дёҠгҒЁгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№з¶ӯжҢҒгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢз’°еўғгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«иҝ‘е№ҙгҒ®гғ«гғјгғ«еӨүжӣҙгҒҜгҖҒеҪўејҸзҡ„гҒӘеҜҫеҝңгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдәӢжҘӯгҒ®ж №жң¬зҡ„гҒӘеҒҘе…ЁжҖ§гӮ’е•ҸгҒҶж–№еҗ‘гҒёеҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«гӮҲгӮӢеҜҫзӯ–гҒ®гҒ”жЎҲеҶ…
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒITгҖҒзү№гҒ«гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒЁжі•еҫӢгҒ®дёЎйқўгҒ«й«ҳгҒ„е°Ӯй–ҖжҖ§гӮ’жңүгҒҷгӮӢжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ§гҒҷгҖӮгғҷгғігғҒгғЈгғјжі•еӢҷгҒ«зөҢйЁ“гҒЁе®ҹзёҫгӮ’жңүгҒ—гҖҒеӣҪйҡӣгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒЁйҖЈжҗәгҒҷгӮӢжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гӮҲгӮӢNASDAQдёҠе ҙгӮ’е…Ёйқўзҡ„гҒ«гӮөгғқгғјгғҲгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮNASDAQдёҠе ҙж”ҜжҸҙгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒдёӢиЁҳиЁҳдәӢгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ®еҸ–жүұеҲҶйҮҺпјҡNASDAQдёҠе ҙж”ҜжҸҙ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ