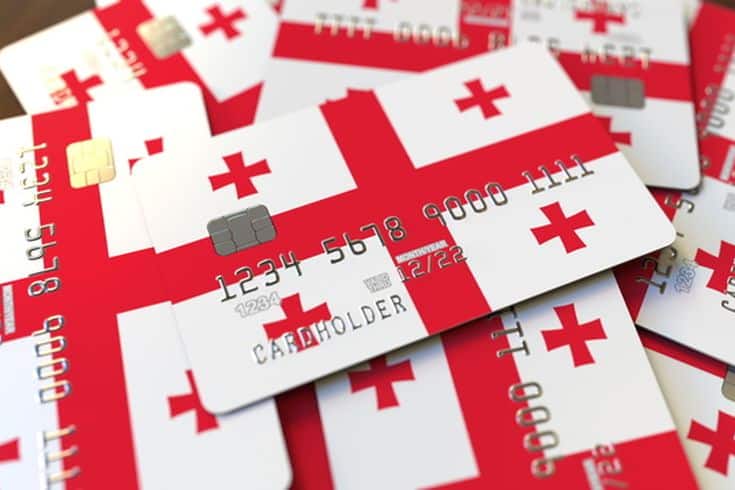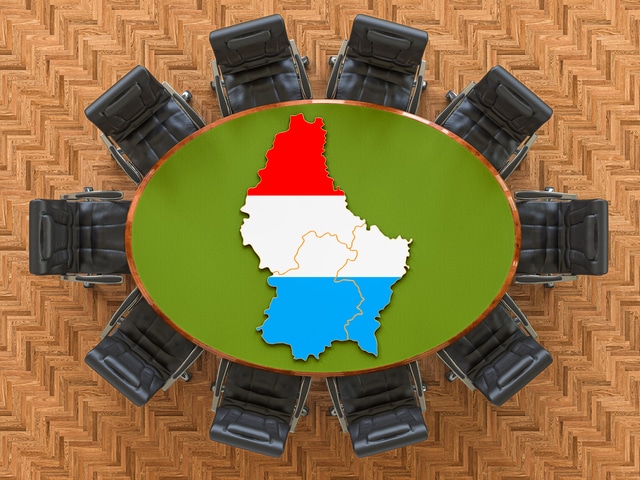Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü¦Ńü«Õźæń┤äµøĖõĮ£µłÉŃā╗õ║żµĖēµÖéŃü½ÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬Ńéŗµ░æµ│ĢŃā╗Õźæń┤äµ│ĢŃü«Ķ¦ŻĶ¬¼

Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│’╝łµŁŻÕ╝ÅÕÉŹń¦░ŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│ńÄŗÕøĮ’╝ēŃü¦Ńü«ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗŃü½ŃüéŃü¤ŃéŖŃĆüńÅŠÕ£░Ńü«µ│ĢńÜäÕ¤║ńøżŃĆüńē╣Ńü½µ░æµ│ĢŃüŖŃéłŃü│Õźæń┤äµ│ĢŃü«µ¦ŗķĆĀŃü©ķüŗńö©µģŻĶĪīŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüõ║łĶ”ŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńü«ńó║õ┐ØŃü©Ńā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ│ĢŃü»ŃĆü1889Õ╣┤Ńü½Õģ¼ÕĖāŃüĢŃéīŃü¤µ░æµ│ĢÕģĖ’╝łC├│digo Civil’╝ēŃéÆõĖŁµĀĖŃü©ŃüÖŃéŗÕż¦ķÖĖµ│Ģń│╗Ńü½Õ▒×ŃüŚ ŃĆüÕżÜŃüÅŃü«ńé╣Ńü¦µŚźµ£¼Ńü«µ│ĢõĮōń│╗Ńü©Õģ▒ķĆÜŃü«Ńā½Ńā╝ŃāäŃéƵīüŃüĪŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«ķüŗńö©ŃéäĶ┐æÕ╣┤Ńü«µ│Ģµö╣µŁŻŃĆüŃüŖŃéłŃü│ÕłżõŠŗµ│ĢńÉå’╝łJurisprudencia’╝ēŃü«ÕĮ╣Õē▓Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüķćŹÕż¦Ńü¬ÕĘ«ńĢ░ŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü«Õźæń┤äµ│ĢŃü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©ÕÉīµ¦śŃü½Õźæń┤äĶć¬ńö▒Ńü«ÕĤÕēćŃéÆÕ¤║ńżÄŃü©ŃüŚŃüżŃüżŃééŃĆüÕźæń┤äŃü«ŃĆīµ£ēÕŖ╣µĆ¦ŃĆŹŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗńŗ¼Ķć¬Ńü«µ”éÕ┐Ą’╝łŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹ’╝ēŃĆüÕ饵©®Õø×ÕÅÄŃü«ŃĆīµÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃĆŹŃĆüŃüŖŃéłŃü│ĶżćµĢ░ÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīķ¢óõĖÄŃüÖŃéŗķÜøŃü«ŃĆīĶ▓¼õ╗╗µ¦ŗķĆĀŃĆŹŃü½ķ¢óŃüŚŃü”ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü«µ©Öµ║¢ńÜäŃü¬ÕĢåµģŻĶĪīŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬ŃéŗŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃéƵÄĪńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½2015Õ╣┤Ńü«µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃü«ÕŖćńÜäŃü¬ń¤ŁńĖ«ŃéäŃĆüńĄīµĖłńÆ░ÕóāŃü«ÕżēÕī¢Ńü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ÕłżõŠŗµ│ĢńÉåŃü«ķĆ▓Õī¢Ńü»ŃĆüńÅŠÕ£░Ńü¦ķĢʵ£¤ńÜäŃü¬ÕÅ¢Õ╝ĢŃéÆĶĪīŃüåķÜøŃü½Õ┐ģķĀłŃü«ń¤źĶŁśŃü¦ŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńĄīÕ¢ČĶĆģŃéäµ│ĢÕŗÖµŗģÕĮōĶĆģŃüīńē╣Ńü½ńĢÖµäÅŃüÖŃü╣ŃüŹŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│Õźæń┤äµ│ĢŃü«ķćŹĶ”üńøĖķüĢńé╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüÕģĘõĮōńÜäŃü¬µ│Ģõ╗żŃéƵĀ╣µŗĀŃü©ŃüŚŃü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńü½µĘ▒ŃüÅķ¢óŃéÅŃéŗŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹ’╝łCausa’╝ēŃü«µ”éÕ┐ĄŃĆüÕźæń┤äÕ饵©®Ńü«õĖĆĶł¼µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃüī5Õ╣┤ŃüĖŃü©ń¤ŁńĖ«ŃüĢŃéīŃü¤ŃüōŃü©ŃĆüŃüØŃüŚŃü”ĶżćµĢ░ÕéĄÕŗÖĶĆģŃü«Ķ▓¼õ╗╗Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕĤÕēć’╝łõĖŹÕÅ»ÕłåĶ▓¼õ╗╗’╝ēŃü©ÕłżõŠŗŃü½ŃéłŃéŗõŠŗÕż¢’╝łķ╗Öńż║Ńü«ķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗’╝ēŃü«ķü®ńö©ń»äÕø▓µŗĪÕż¦ŃĆüŃüĢŃéēŃü½ńĄīµĖłµāģÕŗóŃü«µ┐ĆÕżēŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«õ║ŗµāģÕżēµø┤Ńü«ÕĤÕēć’╝łRebus Sic Stantibus’╝ēŃü«ŃĆīÕĖĖµģŗÕī¢ŃĆŹŃü¬Ńü®ŃüīŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü¦Ńü«Õźæń┤äµøĖõĮ£µłÉŃā╗õ║żµĖēµÖéŃü½ÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕźæń┤äŃü«µłÉń½ŗĶ”üõ╗ČŃü©ŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹ’╝łCausa’╝ēŃü«ÕĮ╣Õē▓
Õźæń┤äŃü«Õ┐ģķĀłĶ”üń┤ĀŃü©ŃüŚŃü”Ńü«ŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹ’╝łCausa’╝ē
Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│µ░æµ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüÕźæń┤äŃéƵłÉń½ŗŃüĢŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ŃĆīÕÉīµäÅ’╝łConsentimiento’╝ēŃĆŹŃĆüÕźæń┤äŃü«ŃĆīńø«ńÜä’╝łObjeto’╝ēŃĆŹŃĆüŃüØŃüŚŃü”ŃĆīÕĤÕøĀ’╝łCausa’╝ēŃĆŹŃü©ŃüäŃüåõĖēŃüżŃü«Õ┐ģķĀłĶ”üń┤ĀŃüīµÅāŃüŻŃü”ŃüäŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«µ░æµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕźæń┤äŃü«µłÉń½ŗĶ”üõ╗ČŃüīõĖ╗Ńü½ÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«µäŵĆØĶĪ©ńż║Ńü©ńø«ńÜäńē®Ńü«ńó║Õ«ÜµĆ¦Ńü½ńä”ńé╣ŃéÆÕĮōŃü”ŃéŗŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃü»ŃĆüÕźæń┤äŃü«ÕÉłµ│ĢńÜäŃü¬ÕŖ╣ÕŖøŃéƵö»ŃüłŃéŗńŗ¼Ķć¬Ńü«µ¤▒Ńü©ŃüŚŃü”µ®¤ĶāĮŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
µ░æµ│Ģń¼¼1274µØĪŃü»ŃĆüµ£ēÕä¤Õźæń┤äŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹŃéÆŃĆüŃĆīÕÉäÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīõ╗¢µ¢╣Ńü«Õ▒źĶĪīŃéÆÕŠŚŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ÕĮ╣ÕŗÖŃüŠŃü¤Ńü»ńĄ”õ╗śŃĆŹŃü¦ŃüéŃéŗŃü©Õ«ÜńŠ®ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Õ«ÜńŠ®Ńü»ŃĆüÕŹśŃü½ķćæķŖŁŃéäÕ»ŠõŠĪŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ńĄīµĖłńÜäŃü¬õ║żµÅøńē®ŃéƵīćŃüÖŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃüØŃü«Õźæń┤äŃüīµłÉń½ŗŃüŚŃü¤µ│ĢńÜäŃü¬µ£ĆńĄéńø«ńÜä’╝łFinalidad jur├Łdica’╝ēŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüŃüØŃü«ÕÅ¢Õ╝ĢŃüīµ│ĢńÜäŃü½Õ«╣Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃéŗŃü╣ŃüŹÕÉłńÉåńÜäŃü¬µĀ╣µŗĀŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃéÆÕłżµ¢ŁŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ŃĆüÕ«óĶ”│ńÜäŃü¬Ķ”üõ╗ČŃü¦ŃüÖŃĆé┬Ā
ÕĤÕøĀŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉł’╝łcausa inexistente’╝ēŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»ÕĤÕøĀŃüīµ│ĢÕŠŗŃéäÕģ¼Õ║ÅĶē»õ┐ŚŃü½ÕÅŹŃüŚŃü”õĖŹµ│ĢŃü¦ŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉł’╝łcausa il├Łcita’╝ē ŃĆüŃüØŃü«Õźæń┤äŃü»ńĄČÕ»ŠńÜäŃü½ńäĪÕŖ╣’╝łnulidad absoluta’╝ēŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ńĄÉµ×£ŃĆüÕźæń┤äŃü»ÕłØŃéüŃüŗŃéēÕŁśÕ£©ŃüŚŃü¬ŃüŗŃüŻŃü¤ŃééŃü«Ńü©ŃüŚŃü”µē▒ŃéÅŃéīŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģŃü»Õ▒źĶĪīŃüĢŃéīŃü¤ńĄ”õ╗śŃéÆńøĖõ║ÆŃü½Ķ┐öķéäŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé┬Ā
ŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃüīŃééŃü¤ŃéēŃüÖŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü©ÕłżõŠŗŃü«ÕŗĢÕÉæ
ŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”Õ¤║µ£¼ńÜäŃü½Õźæń┤äŃü«ÕŖ╣ÕŖøŃü½ÕĮ▒ķ¤┐ŃüŚŃü¬ŃüäŃü©ŃüĢŃéīŃéŗÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ÕĆŗõ║║ńÜäŃü¬ÕŗĢµ®¤Ńü©Ńü»õĖĆńĘÜŃéÆńö╗ŃüŚŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕłżõŠŗµ│ĢńÉåŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüŃüōŃü«ŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹŃü«Õ»®µ¤╗ń»äÕø▓ŃüīÕ║āń»äŃü½ŃéÅŃü¤ŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕÅżÕģĖńÜäŃü¬ÕĤÕøĀĶ½¢Ńü½ÕŖĀŃüłŃĆüÕłżõŠŗŃü»Õźæń┤äńĘĀńĄÉŃü½Ķć│ŃüŻŃü¤ÕĮōõ║ŗĶĆģŃü«ÕģĘõĮōńÜäŃü¬ÕŗĢµ®¤ŃéäµäÅÕø│’╝łĶĪØÕŗĢńÜäÕĤÕøĀ’╝ÜCausa Impulsiva’╝ēŃüīŃĆüÕģ¼Õ║ÅĶē»õ┐ŚŃü½ÕÅŹŃüÖŃéŗŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃéÆĶĆāµģ«Ńü½ÕģźŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ńé╣Ńü½ķ¢óŃüŚŃü”ŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆ’╝łTribunal Supremo’╝ēŃü»ŃĆü2021Õ╣┤6µ£ł22µŚźÕłżµ▒║’╝łÕĮōõ║ŗĶĆģÕÉŹķØ×Õģ¼ķ¢ŗŃĆüRecurso 3677/2018’╝ēŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüŃĆīÕĤÕøĀŃü«õĖŹµ│ĢµĆ¦ŃĆŹ’╝łCausa Il├Łcita / Causa Torpe’╝ēŃéÆńÉåńö▒Ńü©ŃüŚŃü”Õźæń┤äŃü«ńäĪÕŖ╣ŃéÆÕ«ŻĶ©ĆŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«õ║ŗµĪłŃü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü¦ńĘĀńĄÉŃüĢŃéīŃü¤ĶŠ▓Õ£░Ķ│āĶ▓ĖÕĆ¤Õźæń┤ä’╝łArrendamiento r├║stico’╝ēŃüīŃĆüÕ«¤ķÜøŃü½Ńü»ĶŠ▓Õ£░ŃéÆĶ│āÕƤõ║║Ńü½õĮ┐ńö©ŃüĢŃüøŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüÕģ▒ķĆÜĶŠ▓µźŁµö┐ńŁ¢’╝łPAC’╝ēŃü½Õ¤║ŃüźŃüŵ¼¦ÕĘ×ķĆŻÕÉłŃü«ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃéÆÕÅŚŃüæÕÅ¢ŃéŗŃü©ŃüäŃüåĶĪīµö┐õĖŖŃü«Ķ”üõ╗ČŃéÆÕĮóÕ╝ÅńÜäŃü½µ║ĆŃü¤ŃüÖŃü¤ŃéüŃü«ńĄČÕ»ŠńÜäŃéĘŃā¤ŃāźŃā¼Ńā╝ŃéĘŃā¦Ńā│’╝łõ╗«ĶŻģ’╝ēŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤Ńü©ŃüäŃüåŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüŃüōŃü«Õźæń┤äŃü«ń£¤Ńü«µ£ĆńĄéńø«ńÜä’╝łĶĪØÕŗĢńÜäÕĤÕøĀ’╝ēŃüīŃĆüĶŻ£ÕŖ®ķćæÕłČÕ║”Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗĶĪīµö┐õĖŖŃü«Ķ®Éµ¼║ŃéÆõ╝üÕø│ŃüŚŃü¤õĖŹµ│ĢŃü¬ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©Ķ¬ŹÕ«ÜŃüŚŃĆüµ░æµ│Ģń¼¼1275µØĪ’╝łõĖŹµ│ĢŃü¬ÕĤÕøĀŃéƵīüŃüżÕźæń┤äŃü»ńäĪÕŖ╣Ńü¦ŃüéŃéŗ’╝ēŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”Õźæń┤äÕģ©õĮōŃéÆńĄČÕ»ŠńÜäŃü½ńäĪÕŖ╣Ńü©Õłżµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ÕłżõŠŗŃü»ŃĆüÕźæń┤äµøĖõĖŖŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ŃĆīńø«ńÜäńē®ŃĆŹŃü©ŃĆīÕ»ŠõŠĪŃĆŹŃüīµśÄńó║Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüÕĮóÕ╝ÅńÜäŃü½Ńü»ÕÉłµ│ĢńÜäŃü¬õ║żµÅøŃü½Ķ”ŗŃüłŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü¦ŃééŃĆüŃüØŃü«Õźæń┤äŃü«ĶāīÕŠīŃü½ŃüéŃéŗÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü«ŃĆīń£¤Ńü«µ│ĢńÜäµ£ĆńĄéńø«ńÜäŃĆŹŃüīŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü«Õģ¼Õ║ÅĶē»õ┐Ś’╝łOrden P├║blico’╝ēŃü½ńģ¦ŃéēŃüŚŃü”õĖŹķü®ÕĮōŃü¦ŃüéŃéŗŃü©ĶŻüÕłżµēĆŃü½Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüńĄČÕ»ŠńÜäńäĪÕŖ╣ŃéƵŗøŃüÅŃü©ŃüäŃüåŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ│Ģńē╣µ£ēŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆńż║ŃüÖŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü¦Ńü«õ║ŗµźŁŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü½ńø┤ńĄÉŃüÖŃéŗµÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃü«ÕŖćńÜäŃü¬ń¤Łµ£¤Õī¢
Õźæń┤äÕ饵©®Ńü«õĖĆĶł¼µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃüī15Õ╣┤ŃüŗŃéē5Õ╣┤ŃüĖń¤ŁńĖ«
Õ饵©®Ńü«Õø×ÕÅÄÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńü½ńø┤ńĄÉŃüÖŃéŗµÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃü½ķ¢óŃüŚŃü”ŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ│ĢŃü»Ķ┐æÕ╣┤ŃĆüķØ×ÕĖĖŃü½ķćŹĶ”üŃü¬µ│Ģµö╣µŁŻŃéÆÕ«¤µ¢ĮŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŗŃüżŃü”ŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ░æµ│ĢŃü»ŃĆüńē╣ÕłźŃü«Õ«ÜŃéüŃüīŃü¬ŃüäÕĆŗõ║║ķ¢ōŃü«Õ饵©®’╝łÕźæń┤äõĖŖŃü«Õ饵©®ŃéÆÕɽŃéĆ’╝ēŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”15Õ╣┤ķ¢ōŃü«µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃéÆÕ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«õĖĆĶł¼Õ饵©®Ńü«µÖéÕŖ╣’╝łµŚ¦µ│ĢŃü¦Ńü»10Õ╣┤ŃĆüÕĢåõ║ŗÕ饵©®Ńü¦Ńü»5Õ╣┤’╝ēŃü©µ»öĶ╝āŃüŚŃü”ŃééķĢĘŃüäµ£¤ķ¢ōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆü2015Õ╣┤10µ£ł7µŚźŃü½µ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃü¤Ley 42/2015Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüµ░æµ│Ģń¼¼1964µØĪŃüīµö╣µŁŻŃüĢŃéīŃĆüÕźæń┤äõĖŖŃü«Õ饵©®ŃéÆÕɽŃéĆÕĆŗõ║║ķ¢ōŃü«Õ饵©®Ńü«õĖĆĶł¼µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃü»ŃĆü5Õ╣┤ķ¢ōŃü½Õż¦Õ╣ģŃü½ń¤ŁńĖ«ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«µö╣µŁŻŃü½ŃéłŃéŖŃĆüńÅŠĶĪīŃü«µ░æµ│Ģń¼¼1964µØĪń¼¼2ķĀģŃü»õ╗źõĖŗŃü«ķĆÜŃéŖĶ”ÅÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńē╣ÕłźŃü¬µ£¤ķ¢ōŃüīĶ©ŁŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäÕĆŗõ║║ķ¢ōŃü«ĶĪīńé║Ńü»ŃĆüńŠ®ÕŗÖŃü«Õ▒źĶĪīŃüīĶ”üµ▒éÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤µÖéńé╣ŃüŗŃéē5Õ╣┤Ńü¦µÖéÕŖ╣Ńü©Ńü¬ŃéŗŃĆé’╝łLas acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco a├▒os desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligaci├│n.’╝ēŃĆé
Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│µ░æµ│Ģń¼¼1964µØĪń¼¼2ķĀģ (ńÅŠĶĪī)
ŃüōŃü«5Õ╣┤Ńü©ŃüäŃüåµ£¤ķ¢ōŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ÕĢåõ║ŗÕ饵©®Ńü«µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ō’╝ł5Õ╣┤’╝ēŃü©õĖĆĶć┤ŃüŚŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕ饵©®ńÖ║ńö¤ŃüŗŃéēĶ┐ģķƤŃü¬Õø×ÕÅÄŃüŠŃü¤Ńü»µ│ĢńÜäµēŗńČÜŃüŹŃü«ķ¢ŗÕ¦ŗŃéÆńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéŗńé╣Ńü¦ŃĆüµŚ¦µ│ĢŃü«15Õ╣┤Ńü©ŃüäŃüåµ£¤ķ¢ōŃü½µģŻŃéīŃü”ŃüäŃü¤õ║ŗµźŁõĮōŃü½Ńü©ŃüŻŃü”Ńü»ŃĆüÕ饵©®ń«ĪńÉåõĮōÕłČŃü«µŖ£µ£¼ńÜäŃü¬Ķ”ŗńø┤ŃüŚŃéÆĶ┐½ŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ńĄīķüĵĬńĮ«Ńü«ķü®ńö©Ńü©µÖéÕŖ╣ń«ĪńÉåŃü«ńø▓ńé╣
ŃüōŃü«µ│Ģµö╣µŁŻŃüīŃééŃü¤ŃéēŃüÖµ£ĆŃééÕż¦ŃüŹŃü¬Õ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«ÕĮ▒ķ¤┐Ńü»ŃĆüµ¢ĮĶĪīµŚź’╝ł2015Õ╣┤10µ£ł7µŚź’╝ēõ╗źÕēŹŃü½µŚóŃü½ÕŁśÕ£©ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤Õ饵©®Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗńĄīķüĵĬńĮ«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ńĄīķüĵĬńĮ«Ńü«ķü®ńö©µ¢╣µ│ĢŃü»ŃĆüµ¼ĪŃü«ķĆÜŃéŖŃü¦ŃüÖŃĆé
- µ¢░µ│Ģµ¢ĮĶĪīµŚź’╝ł2015Õ╣┤10µ£ł7µŚź’╝ēõ╗źķÖŹŃü½µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃüīķ¢ŗÕ¦ŗŃüĢŃéīŃü¤Õ饵©®’╝ܵ¢░ŃüŚŃüä5Õ╣┤ķ¢ōŃü«µ£¤ķ¢ōŃüīÕ«īÕģ©Ńü½ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
- µ¢░µ│Ģµ¢ĮĶĪīµŚźõ╗źÕēŹŃü½µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃüīµŚóŃü½ķ¢ŗÕ¦ŗŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¤Õ饵©®’╝ÜŃüōŃéīŃéēŃü«Õ饵©®Ńü»ŃĆüµŚ¦µ│Ģ’╝ł15Õ╣┤’╝ēŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹµÖéÕŖ╣Õ«īµłÉµŚźŃéÆĶ©łń«ŚŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüµŚ¦µ│ĢŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü¤µÖéÕŖ╣Õ«īµłÉµŚźŃüīŃĆüµ¢░µ│Ģµ¢ĮĶĪīµŚźŃü¦ŃüéŃéŗ2015Õ╣┤10µ£ł7µŚźŃüŗŃéē5Õ╣┤ÕŠīŃĆüŃüÖŃü¬ŃéÅŃüĪ2020Õ╣┤10µ£ł7µŚźŃéłŃéŖŃééķüģŃüäÕĀ┤ÕÉłŃĆüµÖéÕŖ╣Ńü»Õ╝ĘÕłČńÜäŃü½2020Õ╣┤10µ£ł7µŚźŃü½Õ«īµłÉŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«ńĄīķüĵĬńĮ«Ńü»ŃĆüµ░æµ│Ģń¼¼1939µØĪŃüĖŃü«Õ¦öõ╗╗Ńü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüLey 42/2015Ńü«ń¼¼5ńĄīķüÄĶ”ÅÕ«ÜŃü½ŃéłŃéŖÕ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆü2015Õ╣┤õ╗źÕēŹŃü«ÕÅżŃüäÕźæń┤äŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅÕ饵©®Ńü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆü2020Õ╣┤10µ£ł7µŚźŃüŠŃü¦Ńü½ķü®ÕłćŃü¬µÖéÕŖ╣õĖŁµ¢ŁµÄ¬ńĮ«’╝łÕéĄÕŗÖĶĆģŃüĖŃü«Ķ½ŗµ▒éŃéäĶŻüÕłżõĖŖŃü«Ķ½ŗµ▒éŃü¬Ńü®’╝ēŃüīÕÅ¢ŃéēŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüæŃéīŃü░ŃĆüµŚóŃü½µ©®Õł®ŃéÆÕż▒ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńüīķ½śŃüäŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü¦Ńü«õ║ŗµźŁÕ▒Ģķ¢ŗŃĆüńē╣Ńü½ķüÄÕÄ╗Ńü«Õźæń┤äŃéäÕ饵©®ŃéÆńČÖµē┐ŃüÖŃéŗM&AŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüµÖéÕŖ╣ń«ĪńÉåŃü«Ķ┐ģķƤµĆ¦Ńü©µŁŻńó║µĆ¦ŃüīµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
ĶżćµĢ░ÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü½ŃüŖŃüæŃéŗķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗Ńü«õŠŗÕż¢µĆ¦
õĖŹÕÅ»ÕłåĶ▓¼õ╗╗’╝łMancomunada’╝ēŃü«µÄ©Õ«Ü
µŚźµ£¼Ńü«ÕĢåÕÅ¢Õ╝ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕ饵©®Õø×ÕÅÄŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃāśŃāāŃéĖŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗’╝łSolidariaŃĆüŃéĖŃā¦ŃéżŃā│ŃāłŃā╗ŃéóŃā│ŃāēŃā╗Ńé╗ŃāÖŃā®Ńā½Ķ▓¼õ╗╗’╝ēŃéÆÕźæń┤äŃü½ńøøŃéŖĶŠ╝ŃéĆŃüōŃü©ŃüīõĖĆĶł¼ńÜäŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ░æµ│ĢŃü»ĶżćµĢ░ÕéĄÕŗÖĶĆģŃü«Ķ▓¼õ╗╗µ¦ŗķĆĀŃü½ķ¢óŃüŚŃü”ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”õĖŹÕÅ»ÕłåĶ▓¼õ╗╗’╝łMancomunada’╝ēŃéƵĩիÜŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
µ░æµ│Ģń¼¼1137µØĪŃü»ŃĆüķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗Ńü«õŠŗÕż¢ńÜäŃü¬µĆ¦Ķ│¬ŃéƵśÄńó║Ńü½ńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õĖĆŃüżŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü½ŃüŖŃüäŃü”õ║īĶĆģõ╗źõĖŖŃü«Õ饵©®ĶĆģŃüŠŃü¤Ńü»õ║īĶĆģõ╗źõĖŖŃü«ÕéĄÕŗÖĶĆģŃüīÕģ▒ÕŁśŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕÉäÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīŃüØŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü«ńø«ńÜäńē®ŃéÆÕ«īÕģ©Ńü½Ķ”üµ▒éŃüÖŃéŗµ©®Õł®ŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Õ«īÕģ©Ńü½Õ▒źĶĪīŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåŃüōŃü©Ńü»µäÅÕæ│ŃüŚŃü¬ŃüäŃĆéķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗Ńü©Ńü¬ŃéŗŃü«Ńü»ŃĆüńŠ®ÕŗÖŃüīµśÄńż║ńÜäŃü½ķĆŻÕĖ»Ńü©ŃüŚŃü”Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü«Ńü┐Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆé
Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│µ░æµ│Ģń¼¼1137µØĪ
õĖŹÕÅ»ÕłåĶ▓¼õ╗╗Ńüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕÉäÕéĄÕŗÖĶĆģŃü»ŃĆüÕźæń┤äŃüŠŃü¤Ńü»µ│ĢÕŠŗŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ķć¬ÕĘ▒Ńü½Õē▓ŃéŖÕĮōŃü”ŃéēŃéīŃü¤Õłåµŗģķā©ÕłåŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«Ńü┐Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕ饵©®ĶĆģŃü»ŃĆüÕÉäÕéĄÕŗÖĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ÕłåÕē▓ŃüĢŃéīŃü¤ÕéĄÕŗÖŃéÆÕĆŗÕłźŃü½Ķ½ŗµ▒éŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃĆüõĖĆõ║║Ńü«ÕéĄÕŗÖĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ÕéĄÕŗÖŃü«Õģ©ķĪŹŃéÆĶ½ŗµ▒éŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ«¤ÕŗÖŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃĆīķ╗Öńż║Ńü«ķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗ŃĆŹŃü«ķü®ńö©µŗĪÕż¦
õĖŖĶ©śŃü«ŃéłŃüåŃü½ķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗’╝łSolidaria’╝ēŃüīŃĆīµśÄńż║ńÜäŃü¬ÕÉłµäÅŃĆŹŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ńü«Ńü┐µłÉń½ŗŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕÄ│µĀ╝Ńü¬ÕĤÕēćŃüīŃüéŃéŗõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆ’╝łTribunal Supremo’╝ēŃü«ÕłżõŠŗµ│ĢńÉåŃü»ŃĆüÕĢåÕÅ¢Õ╝ĢŃü«Õ«ēÕģ©Ńü©Õ饵©®ĶĆģŃü«õ┐ØĶŁĘŃéÆķćŹĶ”¢ŃüŚŃĆüŃüōŃü«ÕĤÕēćŃéÆńĘ®ÕÆīŃüÖŃéŗÕéŠÕÉæŃü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µ£Ćķ½śĶŻüŃü»ŃĆüĶżćµĢ░Ńü«ÕéĄÕŗÖĶĆģķ¢ōŃü½ŃĆīÕģ▒ÕÉīŃü«µ│ĢńÜäńø«ńÜäŃĆŹ’╝łcomunidad jur├Łdica de objetivos’╝ēŃüīÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗŃü©Ķ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃü¤Ńü©ŃüłÕźæń┤äµøĖŃü½ķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗ŃüīµśÄńż║ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüÅŃü©ŃééŃĆüŃĆīķ╗Öńż║Ńü«ķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗ŃĆŹ’╝łsolidaridad t├Īcita’╝ēŃü«µłÉń½ŗŃéÆĶ¬ŹŃéüŃéŗµ│ĢńÉåŃéÆńÖ║Õ▒ĢŃüĢŃüøŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«µ│ĢńÉåŃü»ŃĆüńē╣Ńü½õ╝üµźŁŃé░Ńā½Ńā╝ŃāŚÕåģŃü«ĶżćµĢ░Ńü«µ│Ģõ║║ŃüīÕģ▒ÕÉīŃü¦ŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»ŃāłŃéƵĩķĆ▓ŃüŚŃü¤ŃéŖŃĆüÕÉīõĖĆŃü«õ║ŗµźŁńø«ńÜäŃü«Ńü¤ŃéüŃü½Õźæń┤äŃéÆńĘĀńĄÉŃüŚŃü¤ŃéŖŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕĮóÕ╝ÅńÜäŃü¬µ¢ćĶ©ĆŃéłŃéŖŃééŃĆüĶżćµĢ░Ńü«ÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīÕģ▒ķĆÜŃü«ńĄīµĖłńÜäŃā╗õ║ŗµźŁńÜäńø«ńÜäŃéÆķüöµłÉŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ńĘŖÕ»åŃü½ÕŹöÕŖøŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕ«¤µģŗŃüīķćŹĶ”¢ŃüĢŃéīŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃü»ŃĆüÕģ▒ÕÉīŃü«ńø«ńÜäŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ÕŹöÕāŹŃüŚŃü”ŃüäŃéŗĶżćµĢ░Ńü«ÕéĄÕŗÖĶĆģŃü«ŃüåŃüĪŃĆüŃü®Ńü«ÕéĄÕŗÖĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃééÕéĄÕŗÖÕģ©ķĪŹŃü«Õ▒źĶĪīŃéÆĶ½ŗµ▒éŃü¦ŃüŹŃéŗ’╝łķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗Ńü©ÕÉīµ¦śŃü«’╝ēµ│ĢńÜäõ┐ØĶ©╝ŃéÆÕŠŚŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü¦Ńü«ŃéĖŃā¦ŃéżŃā│ŃāłŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝ŃéäÕģ▒ÕÉīķ¢ŗńÖ║Õźæń┤äŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüŃüōŃü«ŃĆīķ╗Öńż║Ńü«ķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗ŃĆŹŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆÕø×ķü┐ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüÕŹśŃü½ŃĆīõĖŹÕÅ»ÕłåĶ▓¼õ╗╗Ńü¦ŃüéŃéŗŃĆŹŃü©Ķ©śĶ╝ēŃüÖŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü«µ│ĢńÜäĶ▓¼õ╗╗ŃéƵśÄńó║Ńü½ÕłåÕē▓ŃüŚŃĆüÕģ▒ÕÉīŃü«µ│ĢńÜäńø«ńÜäŃéÆÕɔիÜŃüÖŃéŗÕźæń┤䵦ŗķĆĀŃéƵäÅÕø│ńÜäŃü½µ¦ŗń»ēŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃĆüõ║ŗµźŁŃā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåõĖŖµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕéĄÕŗÖõĖŹÕ▒źĶĪīŃü©Õźæń┤äŃü«õĖŹÕØćĶĪĪŃüĖŃü«Õ»ŠÕ┐£

ÕÅīÕŗÖÕźæń┤äŃü½ŃüŖŃüæŃéŗĶ¦ŻķÖżµ©®Ńü«ķ╗Öńż║ńÜäŃü¬ÕɽµäÅ’╝łµ░æµ│Ģń¼¼1124µØĪ’╝ē
Õźæń┤äŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüÕÅīÕŗÖÕźæń┤ä’╝łReciprocal Obligations’╝ēŃü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģÕÅīµ¢╣Ńüīõ║ÆŃüäŃü½Õ»ŠõŠĪńÜäŃü¬ńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ░æµ│Ģń¼¼1124µØĪŃü»ŃĆüÕÅīÕŗÖÕźæń┤äŃü½ŃüŖŃüäŃü”õĖƵ¢╣Ńü«ÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīńŠ®ÕŗÖŃéÆÕ▒źĶĪīŃüŚŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕźæń┤äŃü«Ķ¦ŻķÖż’╝łResolution’╝ēµ©®ŃüīŃĆīķ╗Öńż║ńÜäŃü½ÕɽµäÅŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆŹŃü©Õ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
µ░æµ│Ģń¼¼1124µØĪŃü½ŃéłŃéīŃü░ŃĆüńŠ®ÕŗÖõĖŹÕ▒źĶĪīŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ķó½Õ«│ŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤ÕĮōõ║ŗĶĆģŃü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ŃüäŃüÜŃéīŃüŗŃü«ķüĖµŖ×ĶéóŃéÆĶĪīõĮ┐Ńü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
- ńŠ®ÕŗÖŃü«Õ▒źĶĪīŃü«Õ╝ĘÕłČĶ½ŗµ▒é
- Õźæń┤äŃü«Ķ¦ŻķÖżĶ½ŗµ▒é
ŃüäŃüÜŃéīŃéÆķüĖµŖ×ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü¦ŃééŃĆüĶó½Õ«│ŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤ÕĮōõ║ŗĶĆģŃü»ŃĆüŃüØŃü«õĖŹÕ▒źĶĪīŃü½ŃéłŃüŻŃü”ńö¤ŃüśŃü¤µÉŹÕ«│Ńü«ĶŻ£Õä¤Ńü©Õł®µü»Ńü«µö»µēĢŃüäŃéƵ▒éŃéüŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüÖŃĆéÕźæń┤äĶ¦ŻķÖżŃéƵłÉÕŖ¤ŃüĢŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüĶ¦ŻķÖżŃéƵ▒éŃéüŃéŗÕü┤ŃüīŃĆüĶć¬ŃéēŃü«ńŠ®ÕŗÖŃéÆÕ▒źĶĪīŃüŚŃü¤ŃüŗŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Õ▒źĶĪīŃüÖŃéŗµäŵĆØŃüīŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃüīĶ”üõ╗ČŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕéĄÕŗÖĶĆģŃüīÕ▒źĶĪīµ£¤ÕēŹŃü½ŃĆüńŠ®ÕŗÖŃéÆÕ▒źĶĪīŃüŚŃü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüåµśÄńó║Ńü¬µäŵĆØŃéÆĶĪ©µśÄŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉł’╝łõŠŗ’╝ܵ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆ2010Õ╣┤3µ£ł30µŚźÕłżµ▒║’╝ē ŃĆüÕ▒źĶĪīµ£¤ŃéÆÕŠģŃü¤ŃüÜŃü½Õźæń┤äŃü«Ķ¦ŻķÖżŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ńĄīµĖłµāģÕŗóÕżēÕī¢Ńü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗõ║ŗµāģÕżēµø┤Ńü«ÕĤÕēć’╝łRebus Sic Stantibus’╝ē
ÕøĮķÜøńÜäŃü¬ÕĢåõ║ŗÕźæń┤äŃü¦Ńü»ŃĆüõ║łµ£¤ŃüøŃü¼ńĄīµĖłµāģÕŗóŃü«ÕżēÕī¢Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Õźæń┤äŃü«Õ¤║ńżÄŃüīÕ┤®ŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«Õ»ŠÕ┐£ŃüīÕż¦ŃüŹŃü¬Ķ½¢ńé╣Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõ╝ØńĄ▒ńÜäŃü½ŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ│ĢŃü»ŃĆīÕźæń┤äŃü»Õ«łŃéēŃéīŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃĆŹ’╝łPacta Sunt Servanda’╝ēŃü©ŃüäŃüåÕż¦ÕĤÕēćŃéÆķćŹĶ”¢ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕźæń┤äńĘĀńĄÉÕŠīŃü½õ║łµ£¤ŃüøŃü¼õ║ŗµģŗŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃĆüõĖƵ¢╣Ńü«ÕĮōõ║ŗĶĆģŃü½ĶæŚŃüŚŃüÅõĖŹÕł®Ńü¬ńŖȵ│üŃüīńö¤ŃüśŃü¤Ńü©ŃüŚŃü”ŃééŃĆüÕźæń┤äŃü«Õżēµø┤ŃéäĶ¦ŻķÖżŃéÆĶ¬ŹŃéüŃéŗõ║ŗµāģÕżēµø┤Ńü«ÕĤÕēć’╝łDoctrina Rebus Sic Stantibus’╝ēŃü»ŃĆüķØ×ÕĖĖŃü½õŠŗÕż¢ńÜäŃü¬ķü®ńö©Ńü½ķÖÉÕ«ÜŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆü2014Õ╣┤6µ£ł30µŚźŃü½µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆ’╝łTribunal Supremo’╝ēŃüīõĖŗŃüŚŃü¤Õłżµ▒║’╝łSentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014’╝ēŃü»ŃĆüŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü«ķü®ńö©Ķ”üõ╗ČŃü©µĀ╣µŗĀŃéÆÕåŹÕ«ÜńŠ®ŃüŚŃĆüńĄīµĖłÕŹ▒µ®¤Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤õ║łµĖ¼õĖŹÕÅ»ĶāĮŃü¬ńŖȵ│üŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü«ķü®ńö©ŃéÆŃĆīŃé╣ŃāÜŃéżŃā│Õźæń┤äµ│ĢŃü«µ×ĀńĄäŃü┐Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ÕĖĖµģŗÕī¢ŃüÖŃéŗŃĆŹµ¢╣ÕÉæŃü½ĶłĄŃéÆÕłćŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«ÕłżõŠŗõ╗źķÖŹŃĆüRebus Sic StantibusŃü»ŃĆüõ║łµ£¤ŃüøŃü¼ńŖȵ│üŃü½ŃéłŃüŻŃü”Õźæń┤äõĖŖŃü«ńĄ”õ╗śŃü©Õ»ŠõŠĪŃü«ÕØćĶĪĪŃüīÕż¦ŃüŹŃüÅÕ┤®ŃéīŃĆüµ£ēÕä¤Õźæń┤äŃü©ŃüŚŃü”Ńü«µäÅÕæ│ÕÉłŃüäŃüīŃĆīµŁ¬ŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤ŃĆŹ’╝łdesfigurado’╝ēŃü©Õ«óĶ”│ńÜäŃü½Ķ®ĢõŠĪŃüĢŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńüīķ½śŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü«ŃĆīõ┐ĪńŠ®Ķ¬ĀÕ«¤Ńü«ÕĤÕēćŃĆŹ’╝łprincipio de la buena fe’╝ēŃéƵĀ╣µŗĀŃü«õĖĆŃüżŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüÕźæń┤äŃü«ÕØćĶĪĪŃéÆÕø×ÕŠ®ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«µØĪõ╗Čõ┐«µŁŻŃéäĶ¦ŻķÖżŃéÆÕæĮŃüśŃéŗÕłżµ¢ŁŃéÆõĖŗŃüÖŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«µ│ĢńÉåŃü«ńÖ║Õ▒ĢŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«õ╝üµźŁŃüīŃé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü¦ķĢʵ£¤Ńü½ŃéÅŃü¤ŃéŗŃā¬Ńā╝Ńé╣Õźæń┤äŃĆüŃāĢŃā®Ńā│ŃāüŃāŻŃéżŃé║Õźæń┤äŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Õż¦Ķ”ŵ©ĪŃü¬Õ╗║Ķ©ŁÕźæń┤äŃü¬Ńü®ŃéÆńĘĀńĄÉŃüÖŃéŗķÜøŃü«Ńā¬Ńé╣Ń黵¦ŗķĆĀŃü½ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆõĖÄŃüłŃüŠŃüÖŃĆéŃééŃüŚõ║łµĖ¼õĖŹÕÅ»ĶāĮŃü¬Õż¢ķā©ńÆ░ÕóāŃü«ÕżēÕī¢Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Õźæń┤äÕ▒źĶĪīŃüīŃĆīķüÄÕ║”Ńü½Ķ▓ĀµŗģŃĆŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕźæń┤äŃü«Õ▒źĶĪīńČŁµīüŃü½Õø║Õ¤ĘŃüÖŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃéÆķĆÜŃüśŃü”Õźæń┤äµØĪõ╗ČŃü«õ┐«µŁŻŃéäĶ¦ŻķÖżŃéƵ▒éŃéüŃéŗŃü©ŃüäŃüåńÅŠÕ«¤ńÜäŃü¬µ│ĢńÜäµēŗµ«ĄŃüīńó║õ┐ØŃüĢŃéīŃü¤Ńü©Ķ¦ŻķćłŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÅéĶĆā’╝ܵ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆ2014Õ╣┤6µ£ł30µŚźÕłżµ▒║Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ½¢µ¢ć’╝łInDretµÄ▓Ķ╝ē’╝ē
ŃüŠŃü©Ńéü
Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗµ░æµ│ĢŃüŖŃéłŃü│Õźæń┤äµ│ĢŃü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīńÅŠÕ£░Ńü¦Õ«ēÕ«ÜŃüŚŃü¤õ║ŗµźŁŃéÆÕ¢ČŃéĆŃü¤ŃéüŃü½õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¬Ķ”üń┤ĀŃü¦ŃüÖŃĆéÕźæń┤äŃü«µ£ēÕŖ╣µĆ¦Ńü½ķ¢óŃüŚŃü”ŃĆüÕźæń┤äńĘĀńĄÉŃü«ń£¤Ńü«µ│ĢńÜäÕŗĢµ®¤ŃüŠŃü¦Õ»®µ¤╗Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŖÕŠŚŃéŗŃĆīÕĤÕøĀŃĆŹ’╝łCausa’╝ēŃü«µ”éÕ┐ĄŃü«ńÉåĶ¦ŻŃü»ŃĆüńĄČÕ»ŠńÜäńäĪÕŖ╣Ńü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆÕø×ķü┐ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüÕźæń┤äÕ饵©®Ńü«õĖĆĶł¼µÖéÕŖ╣µ£¤ķ¢ōŃüīŃĆü2015Õ╣┤Ńü«µ│Ģµö╣µŁŻŃü½ŃéłŃéŖŃĆüµŚ¦µ│ĢŃü«15Õ╣┤ŃüŗŃéē5Õ╣┤ŃüĖŃü©ÕŖćńÜäŃü½ń¤ŁńĖ«ŃüĢŃéīŃü¤õ║ŗÕ«¤Ńü»ŃĆüÕ饵©®ń«ĪńÉåŃü½ŃüŖŃüäŃü”µ£ĆŃééÕ«¤ÕŗÖńÜäŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½2020Õ╣┤10µ£ł7µŚźŃü«ńĄīķüĵĬńĮ«Ńü½ŃéłŃéŗµÖéÕŖ╣Õ«īµłÉŃü«Õ╝ĘÕłČńÜäŃü¬Ńé½ŃāāŃāłŃé¬ŃāĢŃāØŃéżŃā│ŃāłŃü»ŃĆüķüÄÕÄ╗Ńü«Õ饵©®ń«ĪńÉåõĮōÕłČŃü«Ķ”ŗńø┤ŃüŚŃéÆõ┐āŃüÖŃééŃü«Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüĢŃéēŃü½ŃĆüĶżćµĢ░ÕéĄÕŗÖĶĆģŃü«Ķ▓¼õ╗╗µ¦ŗķĆĀŃü»ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”ÕłåÕē▓Ķ▓¼õ╗╗’╝łMancomunada’╝ēŃü¦ŃüéŃéŗŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüµ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃü«ÕłżõŠŗµ│ĢńÉåŃüīŃĆīÕģ▒ÕÉīŃü«µ│ĢńÜäńø«ńÜäŃĆŹŃéƵĀ╣µŗĀŃü©ŃüÖŃéŗķ╗Öńż║Ńü«ķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ¬ŹŃéüŃéŗń»äÕø▓ŃéƵŗĪÕż¦ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüÕģ▒ÕÉīõ║ŗµźŁŃü½ŃüŖŃüæŃéŗĶ▓¼õ╗╗ń»äÕø▓Ńü»ÕĮóÕ╝ÅńÜäŃü¬Õźæń┤äµ¢ćĶ©ĆŃéÆĶČģŃüłŃü”µģÄķćŹŃü½Ķ®ĢõŠĪŃüĢŃéīŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃĆüÕż¦Ķ”ŵ©ĪÕźæń┤äŃü½ŃüŖŃüæŃéŗķĢʵ£¤ńÜäŃü¬Ńā¬Ńé╣Ńé»ń«ĪńÉåŃü«Ķ”│ńé╣ŃüŗŃéēŃü»ŃĆüńĄīµĖłµāģÕŗóŃü«µ┐ĆÕżēŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüõ║ŗµāģÕżēµø┤Ńü«ÕĤÕēć’╝łRebus Sic Stantibus’╝ēŃü«ķü®ńö©ŃüīŃĆīÕĖĖµģŗÕī¢ŃĆŹŃüŚŃü”ŃüäŃéŗńé╣ŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃéēŃü«ķćŹĶ”üńøĖķüĢńé╣ŃéÆĶĖÅŃüŠŃüłŃĆüŃé╣ŃāÜŃéżŃā│µ│ĢŃü½ķü®ÕÉłŃüŚŃü¤Õźæń┤äµøĖŃü«õĮ£µłÉŃĆüÕ饵©®Ńü«ķü®µÖéŃüŗŃüżķü®ÕłćŃü¬ń«ĪńÉåŃĆüŃüØŃüŚŃü”õĖćŃüīõĖĆŃü«ń┤øõ║ēńÖ║ńö¤Ńü½ÕéÖŃüłŃü¤µł”ńĢźń½ŗµĪłŃü»ŃĆüńÅŠÕ£░õ║ŗµźŁŃéƵłÉÕŖ¤ŃüĢŃüøŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ķŹĄŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ
Ńé┐Ńé░: Ńé╣ŃāÜŃéżŃā│ńÄŗÕøĮµĄĘÕż¢õ║ŗµźŁ