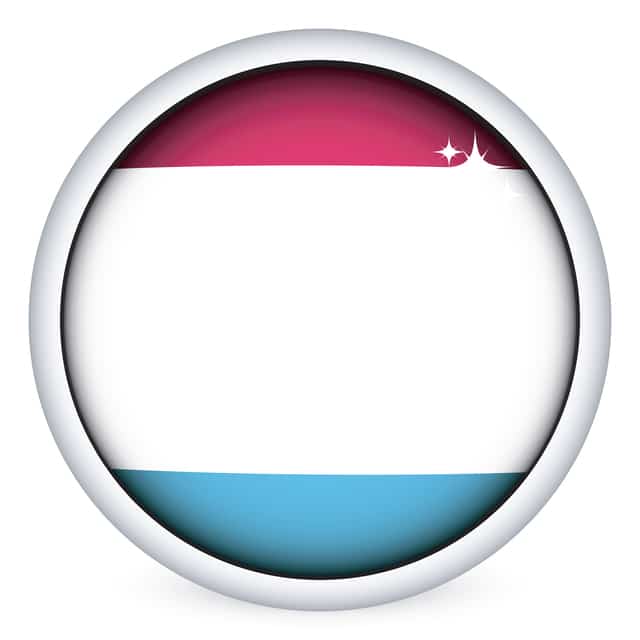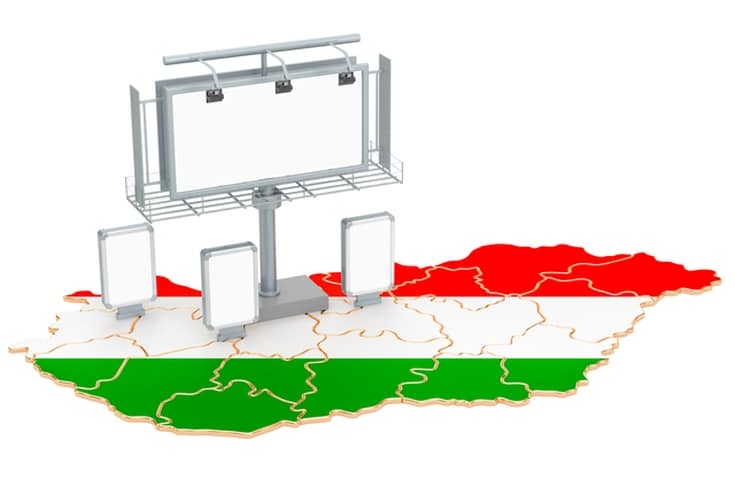アルメニア労働法と2026年末までの「雇用契約の完全デジタル化」

アルメニア共和国(以下、アルメニア)への進出や事業展開を検討する日本企業にとって、現地の労働法制の理解は不可欠です。アルメニアの雇用関係は、その基本を「労働法典(Labour Code)」によって規律されています。日本法と同様に、労働時間、安全衛生、そして雇用契約の期間(原則として期間の定めなし)など、労働者保護に関する諸原則が定められています。
しかし、近年アルメニアの労務管理において最も劇的な変化であり、日本企業が絶対に対応しなければならないのが、2024年12月4日に採択された改正法(HO-525-N)によって導入された「雇用契約の完全デジタル化」です。この改正により、アルメニア労働法典には「第13.1章 デジタル雇用契約システム」が新設されました。これは、雇用契約の締結、変更、終了のすべてを、政府が管理する統一電子プラットフォーム上で、デジタル署名を用いて行うことを「義務付ける」という、非常に先進的かつ強制力のある制度です。
「雇用契約の完全デジタル化」の制度の下で、2026年1月1日から全ての「新規」契約が、そして2027年1月1日(または2026年12月31日)までに全ての「既存」契約が、デジタルシステムへの移行を法的に義務付けられます。そして、この制度は、日本で進められているような「ペーパーレス化」とは全く異なり、国家による「強制的」な一元管理システムです。そして、最大のポイントは、このプラットフォームの管理・運営主体が労働省ではなく、「国家歳入委員会(State Revenue Committee, SRC)」、すなわち日本の「国税庁」に相当する「税務当局」である点です。これにより、雇用関係の発生と納税義務が完全に紐付けられ、100%の労務・税務コンプライアンスが法的に強制されることになります。
本記事では、この強制的なデジタル化システムの詳細、日本の電子化制度との根本的な違い、そして2026年以降のアルメニアにおける労務・税務・移民法務の一括監視体制に対応するための具体的な準備とアクションプランを解説します。
なお、アルメニアの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
2024年アルメニア労働法典改正(HO-525-N)と「第13.1章」の新設
アルメニアの労働法務における「雇用契約の完全デジタル化」の法的根拠は、2024年12月4日に採択された「アルメニア共和国労働法典の改正及び補足に関する法律(Law HO-525-N)」です。
この法律は、アルメニア労働法典に「第13.1章 デジタル雇用契約システム(CHAPTER 13.1. DIGITAL SYSTEM FOR CONCLUDING EMPLOYMENT CONTRACTS)」を新設しました。この新制度の目的は、雇用契約の締結、修正、終了、およびそれに関連する情報管理のプロセス全体をデジタル化することにあります。
これらの改正に関する公式情報は、アルメニアの公式法律情報システム(ARLIS)で確認することができます。
アルメニア「完全デジタル化」への移行スケジュール
この新制度への移行は、猶予期間が設けられているものの、段階的かつ強制的に実施されます。特に2026年以降のスケジュールは、アルメニアでの事業運営の前提となるため、日本企業はこれを正確に把握し、準備を進める必要があります。
移行プロセスは、以下の3段階で実施されます。
| 対象 | 法的拘束力 | |
|---|---|---|
| 2025年7月1日 | 全ての雇用契約 | 任意 (Voluntary) 従来の紙ベースの契約とデジタルシステムが併存可能。 |
| 2026年1月1日 | 全ての「新規」雇用契約 | 義務 (Mandatory) この日以降、全ての「新しい」雇用契約は、デジタルシステムを通じて締結することが法的に義務付けられる。 |
| 2027年1月1日 (または2026年12月31日) | 2026年1月1日以前に締結された、全ての「既存」の有効な雇用契約 | 義務 (Mandatory) 既存の紙ベースの全契約を、この期限までにデジタルシステムに登録(デジタル化)することが義務付けられる。 |
第1フェーズと第2フェーズは、これからアルメニアに進出する企業にとって重要ですが、すでにアルメニアで事業を行っている日本企業にとっては、第3フェーズが極めて重要です。2027年1月1日(または2026年12月31日)という期限までに、既存の全従業員分の紙の契約書をデジタルシステムに登録し直すという、膨大な事務作業とコンプライアンス対応が求められることになります。
アルメニアと日本における雇用関係の電子化の相違点
アルメニアのこの新制度を、日本で近年進められている労働条件通知書の「電子化」や「ペーパーレス化」の延長線上で捉えることは、重大な誤解を招きます。両者は、その設計思想、目的、そして法的強制力において根本的に異なります。
日本における「効率化」のための規則改正
まず、日本の制度を整理します。日本では、労働基準法施行規則の改正により、労働条件通知書をEメールやSNSなどで電子的に交付することが認められています。
しかし、日本法における絶対的な前提条件は、「労働者本人が希望し、同意すること」です。これは、あくまで労働者の利便性や選択の自由を保障するための「オプトイン(Opt-in)」モデルです。日本における電子化の主目的は、企業の「事務作業の効率化」や「ペーパーレス化」にあり、政府が個々の雇用契約の締結プロセスを直接監視することではありません。その形態も、各企業がEメール、電子契約サービス、人事システムなど、独自にツールを選択・運用する「分散型」モデルと言えます。
アルメニアにおける「強制」と「一元監視」
一方で、アルメニアの新制度は、労働者の希望や同意を一切要件としない、国家による強制的な制度です。そして、日本企業が最も衝撃を受けるべき事実は、このデジタルプラットフォームの管理・運営主体です。それは労働省ではなく、「国家歳入委員会(State Revenue Committee, SRC)」、すなわち日本の「国税庁」に相当する「税務当局」なのです。
このデジタル雇用契約システムは、独立した労働システムとして構築されるのではなく、SRCがすでに運用している「電子報告システム(Electronic reporting system)」の「一モジュール(a separate module)」として組み込まれます。
なぜ、労働省ではなく税務当局が雇用契約を管理するのでしょうか。その理由は、このSRCプラットフォームが、当初から税務・給与報告と連携するように設計されている点にあります。雇用契約、ステータスの変更、そして契約終了といった人事情報が、所得税の申告・納税に使用されるのと全く同じエコシステムで捕捉されるのです。
ここから言えることは、この制度の真の目的は、労働者の権利保護という側面以上に、「税収の確実な確保」と「労働市場の完全な透明化による脱税の防止」という、SRC(税務当局)の任務にあるということです。これは、労働法務のデジタルトランスフォーメーションであると同時に、それ以上に、国家による強力な「財政管理(Fiscal Control)」の手段にほかなりません。この「税務当局による一元監視」という点こそが、日本の「同意に基づく効率化」との最大の違いです。
新制度がアルメニアの労務・税務に与える影響

管理主体が税務当局(SRC)であるという事実は、アルメニアでビジネスを行う企業にとって、具体的かつ劇的な影響をもたらします。
労務・税務コンプライアンスの完全な可視化と「グレーゾーン」の排除
新制度の下では、企業(雇用主)は、SRCの電子報告システムにログインし、労働法典が要求する必須項目(従業員の氏名、役職、勤務地、業務開始日、基本給与、労働時間など)を入力して契約書を作成します。そして、雇用主と従業員がデジタル署名で契約を締結した瞬間、税務当局(SRC)は、雇用関係が発生した事実と、その契約に紐づく正確な給与額(=源泉徴収すべき納税義務)を、リアルタイムで完全に把握します。
これにより、「税務署に知られずに人を雇う」ことは物理的に不可能となります。従来、一部の企業で行われていた可能性のある「給与の過少申告」や「社会保障の未加入」といった、税務・労務上のグレーゾーンは、このシステムによって技術的に完全に排除されることになるでしょう。
「労働」「税務」「移民」の一括監視体制
この新制度の監視体制は、SRC(税務当局)だけで完結しません。この統一プラットフォームには、以下の機関もアクセス権を持ち、データを共有します。
- RA保健労働検査機関 (RA Health and Labor Inspection body):労働法違反(違法な労働時間、サービス残業、安全衛生義務違反など)の監督。
- 内務省 移民・市民権サービス (Migration and Citizenship Services):外国人労働者のステータス管理(ビザ、労働許可、不法就労)の監督。
これは、法執行におけるパラダイムシフトを意味します。従来の「労働」「税務」「移民」という縦割りの監督体制ではなく、3つの監督官庁が「SRCの単一プラットフォーム」という「単一のデータソース(Single Source of Truth)」を共有する体制に移行します。
これにより、法執行は「事後対応型」から「事前予防型」へと変化するでしょう。例えば、ある企業が日本人駐在員を雇用し、システムに登録したとします。移民局は即座にそのデータを照会し、その人物のビザや労働許可が不適切であれば、即座に不法就労として検知できます。同時に、労働監査局は契約上の労働時間(例:週40時間)を把握し、後にSRCに報告される給与データと照合することで、サービス残業の発生を自動的に検知することも可能になります。
アルメニアに進出する日本企業は、「労働法」「税法」「移民法」のどれか一つでもコンプライアンス違反があれば、それが他のすべての監督当局に即座に共有される、「100%クリーン」であることを前提としたコンプライアンス体制の構築が、法的に強制されることになるのです。
従来の「契約なき雇用」の終焉と法的背景
なぜアルメニア政府が、これほど強力な監視システムを導入するに至ったのでしょうか。その背景には、長年の課題であった「書面契約なき雇用」の問題があります。
アルメニア労働法典は、第102条において「書面による雇用契約なしに…行われる労働」を「違法(Illegal employment)」と明確に定義しています。しかし、現実にはこの「違法」な状態が横行し、労働者の権利が保護されない事態が裁判で争われてきました。
この問題を象徴するのが、2012年7月18日のアルメニア憲法裁判所判決(Galust Shirinyan v. “Sirkap Armenia” CJSC事件)です。この事件では、労働者が未払給与を請求したところ、会社側が「書面契約がない」ことを理由に支払いを拒否し、控訴裁判所も「書面契約がなければ雇用関係は発生しない」として労働者の請求を棄却しました。しかし、憲法裁判所はこれを覆し、「書面契約が存在しない場合でも、給与の銀行振込履歴などの『他の十分な証拠』が存在すれば、雇用関係の存在と条件を証明する可能性を排除しない」と判断しました。
このShirinyan判決は、書面契約がないという不法状態を、裁判所が「他の証拠」で救済しようとした「事後的な司法的解決策」でした。しかし、今回の2024年の新法(HO-525-N)は、この問題を「技術的」かつ「立法的」に解決するものです。新制度下では、「SRCシステムに登録されたデジタル契約」が唯一の「合法な」雇用契約となります。これにより、Shirinyan判決が対処しようとした「書面なき雇用」という問題状況そのものが、将来的に根絶されることになります。これは、過去の判例法理の積み重ねを、テクノロジーによって一挙に乗り越え、労働市場を国家の完全な監視下に置くという、法制度における大きな転換と言えるでしょう。
アルメニアにおけるデジタル署名とシステムへの準備
2026年1月1日以降、この新制度への対応は「任意」ではなく「義務」となります。日本企業が取るべき具体的な準備について解説します。まず、雇用契約は、雇用主と従業員の双方が「電子デジタル署名(electronic digital signature)」を使用して締結することが義務付けられます。その署名方法は、従業員の国籍によって異なります。
- アルメニア国民:国民IDカードに組み込まれた電子署名、または「Yes em (Ես եմ)」という国の識別プラットフォームを通じたモバイル電子署名を使用します。
- 外国人従業員:日本からの駐在員など、外国人従業員の場合は、「別の形式のデジタル署名(例:CoSign)」、または「納税者識別番号(TIN)」やSRCが提供するログイン情報を使用する必要があります。
したがって、企業は、現地採用者だけでなく、日本人駐在員も含めた全ての従業員が、有効なデジタル署名を期限までに取得・アクティベートできるよう、社内プロセスを早急に整備する必要があります。従来の「紙の契約書にサインして郵送」というプロセスは完全に廃止されます。新しいプロセスは、以下の通りです。
- 雇用主がSRCシステムに契約内容(給与、役職など)を入力する
- 雇用主がデジタル署名を行う
- 従業員に通知が送られ、従業員が自身の個人アカウントから内容を確認してデジタル署名を行う
- 双方の署名後、雇用主がSRCに登録申請を送信し、税務当局によってデータが記録される
実務上の留意点として、雇用契約には「プラットフォームに反映されない付属書(annexes)」を含めることが可能とされています。プラットフォームは、その付属書の「存在」を記録(note)するに留まります。この規定から、給与や役職といった労働法典上の必須項目はSRCシステムで管理しつつ、より機密性の高い情報(例:知的財産権の帰属、詳細な競業避止義務、秘密保持義務)については、従来の紙(または別途の電子署名)による「付属書」として管理できる可能性が考えられます。企業は、どの情報をシステムに登録し、どの情報を付属書とするかの切り分けについて、法的な検討が必要となるでしょう。
アルメニア労働法における解雇規制
この新しいデジタルシステムは、契約の「締結」時だけでなく、「終了(termination)」の手続きにおいても使用が義務付けられます。したがって、アルメニアの解雇法制の基本を理解しておくことが不可欠です。
アルメニア労働法典は、解雇(雇用契約の終了)に法定の理由を要求しています。主な解雇事由には、組織の清算や人員削減(Redundancy)といった「経済的理由」のほか、職務への不適格、長期の労働不能、規律違反(無断欠勤、酩酊状態など)、信頼の喪失といった「労働者側の理由」があります。
日本の解雇法制、特に整理解雇(人員削減)は、判例法理(いわゆる「整理解雇の四要件」)によって厳格に制限されており、(b)解雇回避努力義務や(c)人選の合理性など、使用者の広範な努力が要求されます。アルメニア法も人員削減を法定事由としていますが、その規律は、法定の通知期間と退職金の支払い義務に重点が置かれています。
アルメニア法では、解雇事由と勤続年数に応じて、法定の「予告期間」と「退職金(Severance Pay)」が細かく定められています。例えば、職務不適格や長期労働不能の場合、勤続年数に応じて35日~60日の予告期間が必要であり、退職金も勤続年数に応じて10日分~44日分の平均給与が要求されます。一方で、規律違反による解雇の場合は、予告期間は不要(即時解雇可)、退職金も不要とされています。
まとめ
アルメニアが導入する「デジタル雇用契約システム」は、単なるIT化の推進やペーパーレス化ではありません。このシステムは、労働法典の改正(HO-525-N)を手段とし、「国家歳入委員会(SRC)」(税務当局)が主導する、「労働市場の完全な透明化」と「税務・労務・移民コンプライアンスの強制」を目的とした、極めて強力な国家監視システムです。進出企業は、国家によるトップダウンのデジタル監視システムに適応することが、事業継続の絶対条件となります。
アルメニアでの事業展開にあたり、日本企業が直ちに取るべきアクションは以下の3点にまとめられます。
- スケジュールの厳守:2026年1月1日の新規契約義務化、2027年1月1日の既存契約デジタル化という期限を厳守した社内体制を構築すること。
- デジタル署名の整備:駐在員・現地スタッフ全員のデジタル署名(アルメニア国民は「Yes em」、外国人はTINなど)を早期に整備すること。
- 100%コンプライアンス体制の構築:雇用契約がSRC(税務)、労働監査局、移民局に直結していることを前提に、一切の「グレーゾーン」を排除した、クリーンな労務管理・給与計算・税務申告体制を構築すること。
アルメニアを含む海外諸国における、このような先進的かつ複雑な法改正への対応や、現地法(労働法典第13.1章、および付属書)に準拠した雇用契約書の整備、コンプライアンス体制の構築は、現地の法実務とITシステムの両方に対する深い知見を要します。当事務所は、グローバルに事業を展開するクライアント企業が、各国の複雑な規制環境に対応し、その法務戦略を円滑に実行できるようサポートいたします。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務