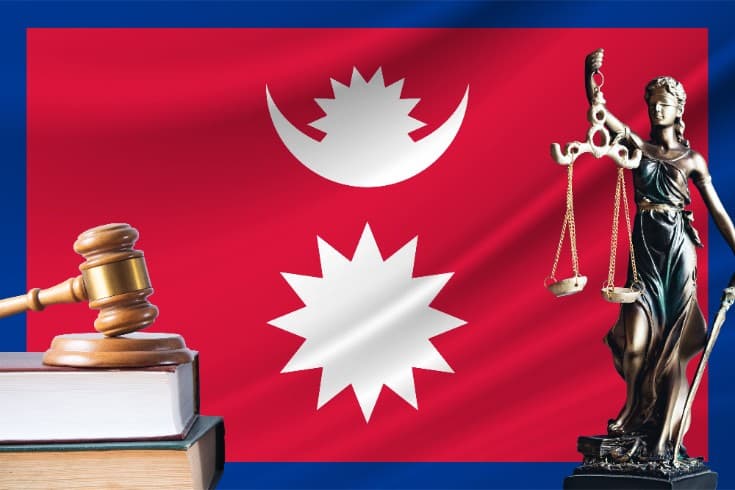еП∞жєЊгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБМеЃЪгВБгВЛгВ≥гГЉгГЭгГђгГЉгГИгВђгГРгГКгГ≥гВє

еП∞жєЊгБЄгБЃдЇЛж•≠йА≤еЗЇгБѓгАБеЬ∞зРЖзЪДгБ™ињСжО•жАІгВДжЦЗеМЦзЪДй°ЮдЉЉжАІгБЛгВЙгАБе§ЪгБПгБЃжЧ•жЬђдЉБж•≠гБЂгБ®гБ£гБ¶й≠ЕеКЫзЪДгБ™йБЄжКЮиВҐгБІгБЩгАВгБЧгБЛгБЧгАБдЇЛж•≠гВТжИРеКЯгБЂе∞ОгБПгБЯгВБгБЂгБѓгАБзПЊеЬ∞гБЃдЉБж•≠зµ±ж≤їпЉИгВ≥гГЉгГЭгГђгГЉгГИгВђгГРгГКгГ≥гВєпЉЙгБЂйЦҐгБЩгВЛжЈ±гБДзРЖиІ£гБМдЄНеПѓжђ†гБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
жЬђз®њгБІгБѓгАБеП∞жєЊгБЃдЉБж•≠зµ±ж≤їгВТжФѓгБИгВЛж≥ХзЪДжЮ†зµДгБњгВТгАБгБЭгБЃж†єеєєгБІгБВгВЛдЉЪз§Њж≥ХгВДи®ЉеИЄеПЦеЉХж≥ХгАБгБЭгБЧгБ¶йЦҐйА£гБЩгВЛжЬАжЦ∞гБЃи¶ПеЙЗгБЂеЯЇгБ•гБНи©≥зі∞гБЂиІ£и™ђгБЧгБЊгБЩгАВзЙєгБЂгАБжЧ•жЬђгБЃж≥ХеЊЛгВДеХЖжЕ£и°МгБ®гБЃйЗНи¶БгБ™зЫЄйБХзВєгБЂзД¶зВєгВТељУгБ¶гАБињСеєійА≤гВАгВ∞гГ≠гГЉгГРгГЂгБ™йАПжШОжАІеРСдЄКгБЂеРСгБСгБЯж≥ХжФєж≠£гБЃеЛХеРСгВТеИЖжЮРгБЧгБЊгБЩгАВ
жЬђи®ШдЇЛгБМгАБеП∞жєЊгБІгБЃгГУгВЄгГНгВєе±ХйЦЛгВТж§Ьи®ОгБЩгВЛжЧ•жЬђгБЃзµМеЦґиАЕгВДж≥ХеЛЩжЛЕељУиАЕгБЃжЦєгАЕгБЂгБ®гБ£гБ¶гАБеЃЯеЛЩдЄКгБЃжМЗйЗЭгБ®гБ™гВЛгБУгБ®гВТзЫЃжМЗгБЧгБЊгБЩгАВ
гБ™гБКгАБеП∞жєЊгБЃеМЕжЛђзЪДгБ™ж≥ХеИґеЇ¶гБЃж¶Ви¶БгБѓдЄЛи®Ши®ШдЇЛгБЂгБ¶гБЊгБ®гВБгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБУгБЃи®ШдЇЛгБЃзЫЃжђ°
еП∞жєЊгБЃдЉБж•≠зµ±ж≤їгБЃеЯЇжЬђ
еП∞жєЊгБЃдЉБж•≠зµ±ж≤їеИґеЇ¶гБѓгАБжЧ•жЬђгБЃж≥ХеИґеЇ¶гБ®еРМжІШгБЂгАБи§ЗжХ∞гБЃж≥ХеЊЛгВДи¶ПеЙЗгБМйЪО屧зЪДгБЂзµДгБњеРИгВПгБХгБ£гБЯе§Ъ屧зЪДгБ™жІЛйА†гВТжМБгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЭгБЃдЄ≠ж†ЄгВТгБ™гБЩгБЃгБМгАБгБЩгБєгБ¶гБЃдЉЪз§ЊгБЂеЕ±йАЪгБЧгБ¶йБ©зФ®гБХгВМгВЛдЉЪз§Њж≥ХпЉИCompany ActпЉЙгБ®гАБдЄКе†ідЉБж•≠гБЂеѓЊгБЧгБ¶гВИгВКеО≥ж†ЉгБ™и¶ПеИґгВТи™≤гБЩи®ЉеИЄеПЦеЉХж≥ХпЉИSecurities and Exchange Act, SEAпЉЙгБІгБЩгАВгБУгВМгБЂеК†гБИгБ¶гАБйЗСиЮНзЫ£зЭ£зЃ°зРЖеІФеУ°дЉЪпЉИFSCпЉЙгБЃйЦҐйА£и¶ПеИґгВДгАБеП∞жєЊи®ЉеИЄеПЦеЉХжЙАпЉИTWSEпЉЙгБКгВИгБ≥еП∞еМЧгВ®гВѓгВєгГБгВІгГ≥гВЄпЉИTPExпЉЙгБЃи¶ПеЙЗпЉИдЄКе†ідЉБж•≠гБЃдЉБж•≠зµ±ж≤їгГЩгВєгГИгГЧгГ©гВѓгГЖгВ£гВєеОЯеЙЗгБ™гБ©пЉЙгБМгАБи©≥зі∞гБ™йБЛзФ®еЯЇжЇЦгВТеЃЪгВБгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБУгБЃдЇМйЗНжІЛйА†гБѓгАБдЉЪз§ЊгБЃи®≠зЂЛгВДйБЛеЦґгАБеПЦзЈ†ељєгБЃзЊ©еЛЩгБ®гБДгБ£гБЯеЯЇжЬђзЪДгБ™дЇЛжЯДгВТдЉЪз§Њж≥ХгБМеЃЪгВБгАБжКХи≥ЗеЃґдњЭи≠ЈгБ®еЄВе†ігБЃдњ°й†ЉжАІзҐЇдњЭгБ®гБДгБЖзЫЃзЪДгБЃгБЯгВБгБЂгАБеЕђйЦЛдЉБж•≠гБЂеѓЊгБЧгБ¶зЙєеИ•гБ™йЦЛз§ЇзЊ©еЛЩгВДеЖЕйГ®зµ±еИґгБЃдїХзµДгБњгВТи®ЉеИЄеПЦеЉХж≥ХгБМеО≥ж†ЉгБЂи¶ПеЃЪгБЩгВЛгБ®гБДгБЖиАГгБИжЦєгБЂеЯЇгБ•гБДгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБУгБЃжІЛеЫ≥гБѓгАБжЧ•жЬђгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБ®йЗСиЮНеХЖеУБеПЦеЉХж≥ХпЉИйЗСеХЖж≥ХпЉЙгБЃйЦҐдњВгБ®йЕЈдЉЉгБЧгБ¶гБКгВКгАБжЧ•жЬђгБЃзµМеЦґиАЕгВДж≥ХеЛЩжЛЕељУиАЕгБЂгБ®гБ£гБ¶гАБеП∞жєЊгБЃж≥ХеИґеЇ¶гБѓжѓФиЉГзЪДзРЖиІ£гБЧгВДгБЩгБДеЯЇзЫ§гБІгБВгВЛгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВ
гБУгБЃеИґеЇ¶зЪДгБ™й°ЮдЉЉжАІгБѓгАБеНШгБ™гВЛеБґзДґгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВж≠іеП≤гВТзіРиІ£гБПгБ®гАБеП∞жєЊгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБѓ1929еєігБЂеИґеЃЪгБХгВМгБ¶дї•жЭ•гАБгГЙгВ§гГДгВДжЧ•жЬђгБЃеХЖж≥ХгАБгВєгВ§гВєгБЃдЉБж•≠ж≥ХгБЛгВЙеЉЈгБДељ±йЯњгВТеПЧгБСгБ¶гБНгБЊгБЧгБЯгАВгБЧгБЛгБЧгАБзђђдЇМжђ°дЄЦзХМе§ІжИ¶еЊМгАБзЙєгБЂ1946еєігБЃдЉЪз§Њж≥ХжФєж≠£дї•йЩНгБѓгАБз±≥еЫљгБЃж≥ХеОЯеЙЗгБМеЊРгАЕгБЂеПЦгВКеЕ•гВМгВЙгВМгБ¶гБДгБНгБЊгБЧгБЯгАВеРМжІШгБЂгАБеП∞жєЊгБЃи®ЉеИЄеПЦеЉХж≥ХгБѓгАБз±≥еЫљгБЃ1933еєіи®ЉеИЄж≥ХгБКгВИгБ≥1934еєіи®ЉеИЄеПЦеЉХж≥ХгВТгГҐгГЗгГЂгБ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБУгБЃеЕ±йАЪгБЃйА≤еМЦгБЃйБУз≠ЛгБМгАБжЧ•жЬђгБ®еП∞жєЊгБЃдЉБж•≠ж≥ХеИґгБЃй°ЮдЉЉжАІгВТзФЯгБњеЗЇгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩгАВ
еП∞жєЊгБЃйЭЮеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБЃгВђгГРгГКгГ≥гВє
йЭЮеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБЂйЦҐгБЧгБ¶гБѓгАБеП∞жєЊгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБѓжЧ•жЬђгБ®жѓФгБєгБ¶ељєеУ°жІЛжИРгБЂе§ІгБНгБ™жЯФиїЯжАІгВТи™НгВБгБ¶гБДгБЊгБЩгАВзЙєгБЂгАБ2018еєігБЃдЉЪз§Њж≥ХжФєж≠£гБЂгВИгВКгАБеПЦзЈ†ељєдЉЪгВТи®≠зљЃгБЩгВЛгБУгБ®гБ™гБПгАБеПЦзЈ†ељєгВТ1еРНгБЊгБЯгБѓ2еРНгБ®гБЩгВЛгБУгБ®гВВеПѓиГљгБ®гБ™гВКгБЊгБЧгБЯгАВгБУгБЃе†іеРИгАБеПЦзЈ†ељє1еРНгБМдЉЪйХЈпЉИдї£и°®иАЕпЉЙгВТеЕЉдїїгБЧгАБеПЦзЈ†ељєдЉЪгБЂйЦҐгБЩгВЛи¶ПеЃЪгБѓгБЭгБЃдЉЪз§ЊгБЂгБѓйБ©зФ®гБХгВМгБЊгБЫгВУгАВгБУгВМгБѓгАБзЙєгБЂеНШзЛђгБЃж≥Х䯯憙䪿гБМеП∞жєЊгБЂе≠РдЉЪз§ЊгВТи®≠зЂЛгБЩгВЛе†іеРИгБЂгАБжЧ•жЬђгБЃгАМеПЦзЈ†ељєдЉЪйЭЮи®≠зљЃдЉЪз§ЊгАНгВИгВКгВВгБХгВЙгБЂз∞°зі†еМЦгБХгВМгБЯгАБзґ≠жМБзЃ°зРЖгВ≥гВєгГИгБЃдљОгБД嚥жЕЛгБІгБВгВЛгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБ1гБ§гБЃж≥Х䯯憙䪿гБІжІЛжИРгБХгВМгВЛйЭЮеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБѓгАБзЫ£жЯїељєгВТи®≠зљЃгБЩгВЛењЕи¶БгВВгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ
йЭЮеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБѓгАБи≤°еЛЩиЂЄи°®гБЃеЕђйЦЛзЊ©еЛЩгВТи≤†гБДгБЊгБЫгВУгБМгАБдЉЪз§ЊгБЃйАПжШОжАІгВТ祯дњЭгБЩгВЛгБЯгВБгБЃеЯЇжЬђзЪДгБ™жГЕ冱йЦЛз§ЇгБѓж±ВгВБгВЙгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВдЉЪз§ЊеРНгАБжЙАеЬ®еЬ∞гАБдЇЛж•≠еЖЕеЃєгАБдЉЪз§ЊзКґж≥БгАБеПЦзЈ†ељєгГ™гВєгГИгАБи≥ЗжЬђйЗСй°НгБ™гБ©гБЃеЯЇжЬђзЪДгБ™дЉБж•≠жГЕ冱гБѓгАБеХЖж•≠зЩїи®ШгВ¶гВІгГЦгВµгВ§гГИгВТйАЪгБШгБ¶дЄАиИђгБЂеЕђйЦЛгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБ2018еєігБЃдЉЪз§Њж≥ХжФєж≠£гБЂгВИгВКгАБгГЮгГНгГЉгГ≠гГ≥гГАгГ™гГ≥гВ∞еѓЊз≠ЦгВТеЉЈеМЦгБЩгВЛзЫЃзЪДгБІгАБйЭЮеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгВВгАБеПЦзЈ†ељєгАБзЫ£жЯїељєгАБгГЮгГНгГЉгВЄгГ£гГЉгАБгБКгВИгБ≥10%дї•дЄКгБЃж†™еЉПгВТдњЭжЬЙгБЩгВЛ憙䪿гБЃжМБеИЖзКґж≥БгБЂйЦҐгБЩгВЛ庳搰冱еСКжЫЄгВТжФњеЇЬж©ЯйЦҐгБЂжПРеЗЇгБЩгВЛзЊ©еЛЩгБМи™≤гБХгВМгБЊгБЧгБЯгАВйЗНи¶БгБ™е§ЙжЫігБМгБВгБ£гБЯе†іеРИгБѓ15жЧ•дї•еЖЕгБЃе†±еСКгБМењЕи¶БгБІгБЩгАВ
еП∞жєЊгБЃеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБЃгВђгГРгГКгГ≥гВє
еП∞жєЊгБЃеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБѓгАБи®ЉеИЄеПЦеЉХж≥ХгБЂеЯЇгБ•гБНгАБйЭЮеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгВИгВКгВВйБ•гБЛгБЂеО≥ж†ЉгБ™гВђгГРгГКгГ≥гВєи¶БдїґгБМи™≤гБХгВМгБЊгБЩгАВжЬАгВВйЗНи¶БгБ™и¶БдїґгБЃдЄАгБ§гБМгАБзЛђзЂЛеПЦзЈ†ељєгБЃи®≠зљЃзЊ©еЛЩгБІгБЩгАВеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБѓгАБеПЦзЈ†ељєдЉЪгБЃзЈПи≠∞еЄ≠жХ∞гБЃ5еИЖгБЃ1дї•дЄКгАБгБЛгБ§жЬАдљО2еРНгБЃзЛђзЂЛеПЦзЈ†ељєгВТи®≠зљЃгБЩгВЛзЊ©еЛЩгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгБУгВМгБѓжЧ•жЬђгБЃеИґеЇ¶гВИгВКгВВеО≥ж†ЉгБІгБВгВКгАБжЧ•жЬђдЉБж•≠гБМжЬАгВВж≥®жДПгБЩгБєгБНзЫЄйБХзВєгБЃдЄАгБ§гБІгБЩгАВгБХгВЙгБЂгАБ2024еєігБЛгВЙеНКжХ∞дї•дЄКгАБ2027еєігБЛгВЙгБѓгБЩгБєгБ¶гБЃзЛђзЂЛеПЦзЈ†ељєгБМйА£зґЪ3жЬЯгВТиґЕгБИгБ¶е∞±дїїгБІгБНгБ™гБДгБ®гБЩгВЛдїїжЬЯеИґйЩРгВВе∞ОеЕ•гБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБѓзЫ£жЯїеІФеУ°дЉЪпЉИAudit CommitteeпЉЙгБЃи®≠зљЃгБМзЊ©еЛЩдїШгБСгВЙгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВзЫ£жЯїеІФеУ°дЉЪгБѓгБЩгБєгБ¶гБЃзЛђзЂЛеПЦзЈ†ељєгБІжІЛжИРгБХгВМгАБжЬАдљО3еРНгБМењЕи¶БгБІгБЩгАВеІФеУ°дЉЪгБЂгБѓгАБе∞СгБ™гБПгБ®гВВ1еРНгАБдЉЪи®ИгБЊгБЯгБѓи≤°еЛЩгБЃе∞ВйЦАзЪДзЯ•и≠ШгВТжМБгБ§иАЕгБМеРЂгБЊгВМгВЛењЕи¶БгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВжЧ•жЬђгБЃзЫ£жЯїељєдЉЪи®≠зљЃдЉЪз§ЊгБЂгБКгБСгВЛзЫ£жЯїељєгБ®гБѓзХ∞гБ™гВКгАБеІФеУ°дЉЪгБ®гБЧгБ¶йЫЖеЫ£гБІж©ЯиГљгБЩгВЛзВєгБМзЙєеЊігБІгБЩгАВ
гБХгВЙгБЂгАБеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБѓе†±йЕђеІФеУ°дЉЪпЉИRemuneration CommitteeпЉЙгВТи®≠зљЃгБЩгВЛзЊ©еЛЩгВВгБВгВКгБЊгБЩгАВгБУгБЃеІФеУ°дЉЪгБѓжЬАдљО3еРНгБІжІЛжИРгБХгВМгАБгБЭгБЃйБОеНКжХ∞гВТзЛђзЂЛеПЦзЈ†ељєгБМеН†гВБгВЛењЕи¶БгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
ињСеєізЙєгБЂж≥®зЫЃгБЩгБєгБНгБѓгАБ2023еєі6жЬИ30жЧ•дї•йЩНгАБгБЩгБєгБ¶гБЃеП∞жєЊдЄКе†ідЉБж•≠гБЂеѓЊгБЧгАБжЬАйЂШгВђгГРгГКгГ≥гВєи≤ђдїїиАЕпЉИChief Governance Officer, CGOпЉЙгБЃдїїеСљгБМзЊ©еЛЩдїШгБСгВЙгВМгБЯзВєгБІгБЩгАВCGOгБѓгАБгВђгГРгГКгГ≥гВєйЦҐйА£ж≥Хи¶ПгВДгГЩгВєгГИгГЧгГ©гВѓгГЖгВ£гВєгБЄгБЃйБµеЃИгВТ祯дњЭгБЧгАБеПЦзЈ†ељєгБЃиБЈеЛЩйБВи°МгВТжФѓжПігБЩгВЛељєеЙ≤гВТжЛЕгБДгБЊгБЩгАВеЕЈдљУзЪДгБЂгБѓгАБеПЦзЈ†ељєдЉЪгВДеІФеУ°дЉЪгБЃйБЛеЦґгАБеПЦзЈ†ељєгБЄгБЃжГЕ冱жПРдЊЫгАБи¶ПеИґжЫіжЦ∞жГЕ冱гБЃдЉЭйБФгБ™гБ©гБМеРЂгБЊгВМгБЊгБЩгАВгБУгВМгБѓгАБгВђгГРгГКгГ≥гВєгВТзµМеЦґгБЃжЬАйЗНи¶Би™≤й°МгБ®дљНзљЃдїШгБСгБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБЃи®ЉеЈ¶гБІгБЩгАВ
зЛђзЂЛеПЦзЈ†ељєгБЃдїїжЬЯеИґйЩРгВДCGOгБЃи®≠зљЃзЊ©еЛЩеМЦгБѓгАБеП∞жєЊгБМгВђгГРгГКгГ≥гВєж∞іжЇЦгВТеЫљйЪЫзЪДгБ™гГЩгВєгГИгГЧгГ©гВѓгГЖгВ£гВєгБЂеРИгВПгБЫгВИгБЖгБ®гБЩгВЛгАБйЭЮеЄЄгБЂеЉЈгБДжДПењЧгБЃи°®гВМгБІгБВгВЛгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВгБУгВМгБѓгАБеНШгБ™гВЛи¶ПеИґеЉЈеМЦгБІгБѓгБ™гБПгАБеЄВе†ігБЃдњ°й†ЉжАІгВТйЂШгВБгАБеЫљйЪЫзЪДгБ™жКХи≥ЗгВТеСЉгБ≥иЊЉгВАгБЯгВБгБЃжИ¶зХ•зЪДгБ™еЛХгБНгБІгБЩгАВеЃЯйЪЫгАБеП∞жєЊгБѓACGAпЉИAsian Corporate Governance AssociationпЉЙгБЃгГ©гГ≥гВ≠гГ≥гВ∞гБІгАБгВҐгВЄгВҐ11еЄВе†ідЄ≠4дљНгБЂгГ©гГ≥гВѓгБХгВМгБ¶гБКгВКгАБгВЈгГ≥гВђгГЭгГЉгГЂгАБй¶ЩжЄѓгАБжЧ•жЬђгБЂжђ°гБРдљНзљЃгБЂгБВгВКгБЊгБЩгАВгБУгБЃйЂШгБДи©ХдЊ°гБЃиГМжЩѓгБЂгБѓгАБеПЦзЈ†ељєдЉЪгВДжГЕ冱йЦЛз§ЇгБЂйЦҐгБЩгВЛеО≥ж†ЉгБ™и¶ПеИґгБ®гАБгБЭгВМгВТжФѓгБИгВЛCGOгБЃгВИгБЖгБ™жЦ∞гБЧгБДељєеЙ≤гБЃе∞ОеЕ•гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
еП∞жєЊгБЂгБКгБСгВЛињСеєігБЃж≥ХжФєж≠£

еП∞жєЊгБЃдЉБж•≠зµ±ж≤їгБѓгАБињСеєігАБгВ∞гГ≠гГЉгГРгГЂгБ™жљЃжµБгБЂж≤њгБ£гБ¶жА•йАЯгБЂе§ЙеМЦгВТйБВгБТгБ¶гБКгВКгАБжЧ•жЬђдЉБж•≠гБМзЙєгБЂж≥®зЫЃгБЩгБєгБНж≥ХжФєж≠£гБМзЫЄжђ°гБДгБІгБДгБЊгБЩгАВ
гБЭгБЃдЄАгБ§гБМгАБ姲憙䪿жМБеИЖйЦЛз§ЇгГЂгГЉгГЂгБІгБЩгАВ2024еєі5жЬИгАБеП∞жєЊгБЃи®ЉеИЄеПЦеЉХж≥ХгБѓжФєж≠£гБХгВМгАБеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБЃж†™еЉПгВТ5%дї•дЄКеПЦеЊЧгБЧгБЯ憙䪿гБѓгАБйЗСиЮНзЫ£зЭ£зЃ°зРЖеІФеУ°дЉЪпЉИFSCпЉЙгБЄгБЃе†±еСКгБ®еЕђи°®гБМзЊ©еЛЩдїШгБСгВЙгВМгБЊгБЧгБЯгАВгБУгВМгБѓгАБеЊУжЭ•гБЃ10%гБ®гБДгБЖеЯЇжЇЦгБЛгВЙеЉХгБНдЄЛгБТгВЙгВМгБЯгВВгБЃгБІгАБдЉБж•≠гБЃжФѓйЕНж®©е§ЙеЛХгБЂйЦҐгБЩгВЛйАПжШОжАІгВТе§ІеєЕгБЂйЂШгВБгВЛгВВгБЃгБІгБЩгАВгБУгБЃзВєгБѓгАБжЧ•жЬђгБЃйЗСиЮНеХЖеУБеПЦеЉХж≥ХгБЂгБКгБСгВЛгАМе§ІйЗПдњЭжЬЙ冱еСКеИґеЇ¶гАНгБ®гБїгБЉеРМгБШж∞іжЇЦгБЂеЉХгБНдЄКгБТгВЙгВМгБЯгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВгБХгВЙгБЂгАБзЈПзЩЇи°М憙еЉПгБЃ1%гБЂзЫЄељУгБЩгВЛдњЭжЬЙ憙еЉПгБМеҐЧжЄЫгБЧгАБгБЭгБЃзµРжЮЬдњЭжЬЙжѓФзОЗгБМ1%дї•дЄКе§ЙеЛХгБЧгБЯе†іеРИгВВгАБFSCгБЄгБЃе†±еСКгБМењЕи¶БгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВгБУгБЃињљеК†зЪДгБ™е†±еСКзЊ©еЛЩгБѓгАБжЧ•жЬђгБЃеИґеЇ¶гБ®еРМжІШгАБдњЭжЬЙзКґж≥БгБЃзґЩзґЪзЪДгБ™зЫ£и¶ЦгВТзЫЃзЪДгБ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гВВгБЖдЄАгБ§гБЃе§ІгБНгБ™жљЃжµБгБМгАБгВµгВєгГЖгГКгГУгГ™гГЖгВ£пЉИESGпЉЙ冱еСКгБЃзЊ©еЛЩеМЦгБІгБЩгАВ2025еєідї•йЩНгАБгБЩгБєгБ¶гБЃеП∞жєЊдЄКе†ідЉБж•≠пЉИи≥ЗжЬђи¶Пж®°гВТеХПгВПгБЪпЉЙгБѓгАБж•≠зХМеЫЇжЬЙгБЃESGгГ™гВєгВѓгАБгГСгГХгВ©гГЉгГЮгГ≥гВєжМЗж®ЩгАБж∞ЧеАЩйЦҐйА£йЦЛз§ЇгВТеРЂгВАеєіжђ°гВµгВєгГЖгГКгГУгГ™гГЖгВ£гГђгГЭгГЉгГИгВТ8жЬИ31жЧ•гБЊгБІгБЂзЩЇи°МгБЩгВЛгБУгБ®гБМзЊ©еЛЩдїШгБСгВЙгВМгБЊгБЩгАВгБУгВМгБѓгАБеЫљйЪЫзЪДгБ™ESGжГЕ冱йЦЛз§ЇеЯЇжЇЦпЉИGRIгВДSASBгБ™гБ©пЉЙгБЂжЇЦжЛ†гБЩгВЛгБУгБ®гБМж±ВгВБгВЙгВМгБЊгБЩгАВгБУгБЃзВєгБЂгБ§гБДгБ¶гАБйЗСиЮНзЫ£зЭ£зЃ°зРЖеІФеУ°дЉЪпЉИFSCпЉЙгБѓгАБгВµгВєгГЖгГКгГУгГ™гГЖгВ£гБЂйЦҐгБЩгВЛжФњз≠ЦгБЂгБКгБДгБ¶гАБжШО祯гБ™гГ≠гГЉгГЙгГЮгГГгГЧгБ®жЬЯйЩРгВТеЃЪгВБгБ¶гБКгВКгАБгГИгГГгГЧгГАгВ¶гГ≥гБІдЄАи≤ЂгБЧгБ¶и¶ПеИґеЉЈеМЦгВТйА≤гВБгБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБЖзЙєеЊігБМй°ХиСЧгБІгБЩгАВдЊЛгБИгБ∞гАБCGOгБЃдїїеСљгБѓ2023еєі6жЬИ30жЧ•дї•йЩНгБЂеЕ®дЄКе†ідЉБж•≠гБЂзЊ©еЛЩдїШгБСгВЙгВМгБЊгБЧгБЯгАВгБУгБЃгВҐгГЧгГ≠гГЉгГБгБЛгВЙи®АгБИгВЛгБУгБ®гБѓгАБеП∞жєЊгБѓж≥Хи¶ПеИґгВТйАЪгБШгБ¶еЄВе†іеЕ®дљУгБЃдЄАеЊЛгБ™ж∞іжЇЦеРСдЄКгВТињЕйАЯгБЂеЫ≥гБ£гБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВ
еП∞жєЊгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБ®жЧ•жЬђж≥ХгБЃзХ∞еРМ
еП∞жєЊгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБ®жЧ•жЬђгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБѓе§ЪгБПгБЃеЕ±йАЪзВєгВТжМБгБ°гБЊгБЩгБМгАБеАЛеИ•гБЃи¶ПеЃЪгВДгБЭгБЃйБЛзФ®гБЂгБѓйЗНи¶БгБ™йБХгБДгБМе≠ШеЬ®гБЧгБЊгБЩгАВ
еПЦзЈ†ељєгБЃеЦДзЃ°ж≥®жДПзЊ©еЛЩгБ®ењ†еЃЯзЊ©еЛЩ
еП∞жєЊгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБѓгАБеПЦзЈ†ељєгБЂеѓЊгБЧгБ¶гАМењ†еЃЯзЊ©еЛЩпЉИDuty of LoyaltyпЉЙгАНгБ®гАМеЦДзЃ°ж≥®жДПзЊ©еЛЩпЉИDuty of CareпЉЙгАНгВТи™≤гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩпЉИдЉЪз§Њж≥Хзђђ23жЭ°пЉЙгАВгБУгВМгБѓжЧ•жЬђгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБЂгБКгБСгВЛеПЦзЈ†ељєгБЃењ†еЃЯзЊ©еЛЩпЉИдЉЪз§Њж≥Хзђђ355жЭ°пЉЙгБКгВИгБ≥еЦДзЃ°ж≥®жДПзЊ©еЛЩпЉИж∞Сж≥Хзђђ644жЭ°пЉЙгБ®ж≥ХзЪДгБ™еЖЕеЃєгБѓгБїгБЉеРМзЊ©гБІгБВгВКгАБеПЦзЈ†ељєгБѓдЉЪз§ЊгБЃжЬАеЦДгБЃеИ©зЫКгБЃгБЯгВБгБЂи°МеЛХгБЩгВЛењЕи¶БгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
ж≥®зЫЃгБЩгБєгБНгБѓгАБеП∞жєЊгБЃи£БеИ§жЙАгБМгБУгВМгВЙгБЃзЊ©еЛЩгВТйЭЮеЄЄгБЂеО≥ж†ЉгБЂиІ£йЗИгБЧгАБйБ©зФ®гБЧгБ¶гБДгВЛзВєгБІгБЩгАВ2001еєігБЃдЉЪз§Њж≥ХжФєж≠£гБЂгВИгБ£гБ¶гАМењ†еЃЯзЊ©еЛЩгАНгБМжШОжЦЗеМЦгБХгВМгВЛдї•еЙНгБЛгВЙгАБи£БеИ§жЙАгБѓж∞Сж≥Хзђђ535жЭ°гБЃгАМеЦДзЃ°ж≥®жДПзЊ©еЛЩгАНгВТж†єжЛ†гБ®гБЧгБ¶гАБеПЦзЈ†ељєгБЃи≤ђдїїгВТињљеПКгБЧгБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгАВ
ињСеєігБЃжЬАйЂШж≥ХйЩҐпЉИжЧ•жЬђгБЃжЬАйЂШи£БеИ§жЙАгБЂзЫЄељУпЉЙгБЃеИ§ж±ЇгБѓгАБгБУгБЃеВЊеРСгВТгБХгВЙгБЂжШО祯гБЂгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВдЊЛгБИгБ∞гАБжЬАйЂШж≥ХйЩҐ112еєіеЇ¶еП∞дЄКе≠Чзђђ2800еПЈж∞СдЇЛеИ§ж±ЇпЉИ2023еєі6жЬИ29жЧ•пЉЙгБІгБѓгАБдЉЪз§Њж≥Хзђђ206жЭ°зђђ2й†ЕпЉИеПЦзЈ†ељєгБЃиЗ™еЈ±еИ©еЃ≥йЦҐдњВгБЃйЦЛз§ЇзЊ©еЛЩпЉЙгБЃи¶ПеЃЪгБМе∞ОеЕ•гБХгВМгВЛеЙНгБЃдЇЛж°ИгБЂгБКгБДгБ¶гАБеПЦзЈ†ељєгБМеИ©зЫКзЫЄеПНйЦҐдњВгБЂгБВгВЛгБЂгВВгБЛгБЛгВПгВЙгБЪгАБгБЭгБЃйЗНи¶БеЖЕеЃєгВТйЦЛз§ЇгБЧгБ™гБЛгБ£гБЯи°МзВЇгБМеХПгВПгВМгБЊгБЧгБЯгАВйЂШз≠Йж≥ХйЩҐгБѓгАБж≥ХдЄНйБ°еПКгБЃеОЯеЙЗгБЛгВЙйЦЛз§ЇзЊ©еЛЩгВТи≤†гВПгБ™гБДгБ®еИ§жЦ≠гБЧгБЯгБЃгБЂеѓЊгБЧгАБжЬАйЂШж≥ХйЩҐгБѓгАМи™ђжШОзЊ©еЛЩгБѓењ†еЃЯзЊ©еЛЩгБЃеЕЈдљУеМЦи¶ПеЃЪгБІгБВгВЛгАНгБ®гБЧгАБдЉЪз§Њж≥Хзђђ23жЭ°зђђ1й†ЕгБЃењ†еЃЯзЊ©еЛЩгБЂеЯЇгБ•гБНгАБеПЦзЈ†ељєгБѓйЦЛз§ЇзЊ©еЛЩгВТи≤†гБЖгБ®еИ§жЦ≠гБЧгБЊгБЧгБЯгАВгБУгБЃеИ§ж±ЇгБѓгАБгБЯгБ®гБИжЭ°жЦЗгБЂжШОи®ШгБХгВМгБ¶гБДгБ™гБПгБ¶гВВгАБењ†еЃЯзЊ©еЛЩгБМеПЦзЈ†ељєгБЃи°МеЛХгВТеЊЛгБЩгВЛж†єеєєзЪДгБ™и¶ПзѓДгБІгБВгВКгАБгБЭгБЃйБХеПНгБЂгБѓи≤ђдїїгБМдЉігБЖгБ®гБДгБЖгАБеП∞жєЊгБЃеПЄж≥ХгБЃеЉЈгБДеІњеЛҐгВТз§ЇгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
憙䪿йЦУгБЃи≠∞ж±Їж®©и°Мдљње•СзіД
еП∞жєЊгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБѓгАБйЭЮеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБЂгБКгБДгБ¶гАБ憙䪿йЦУгБЃи≠∞ж±Їж®©и°Мдљње•СзіДпЉИVoting AgreementпЉЙгБЃжЬЙеКєжАІгВТи™НгВБгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБУгБЃзВєгБѓгАБжЧ•жЬђгБЃдЉЪз§Њж≥ХгБМи≠∞ж±Їж®©и°Мдљње•СзіДгБЃжЬЙеКєжАІгБЂгБ§гБДгБ¶жШО祯гБ™и¶ПеЃЪгВТжМБгБЯгБЪгАБе≠¶и™ђгВДеИ§дЊЛгВВжЬЙеКєжАІгБЂгБ§гБДгБ¶жІШгАЕгБ™и¶ЛиІ£гБМгБВгВЛгБЃгБ®жѓФиЉГгБЧгБ¶гАБеП∞жєЊгБЃж≥ХеИґеЇ¶гБМгВИгВКжШО祯гБ™жЦєеРСжАІгВТз§ЇгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВ
йБОеОїгАБеП∞жєЊгБЃи£БеИ§жЙАгБѓи≠∞ж±Їж®©жЛШжЭЯе•СзіДгБЃжЬЙеКєжАІгБЂеѓЊгБЧгБ¶еР¶еЃЪзЪДгБ™и¶ЛиІ£гВТз§ЇгБЩгБУгБ®гБМе§ЪгБЛгБ£гБЯгВВгБЃгБЃгАБињСеєігБѓзХ∞гБ™гВЛеВЊеРСгБМи¶ЛгВЙгВМгБЊгБЩгАВзЙєгБЂгАБйЦЙйОЦеЮЛиВ°дїљжЬЙйЩРеЕђеПЄгБЂйЦҐгБЩгВЛи¶ПеЃЪгБМе∞ОеЕ•гБХгВМгБЯгБУгБ®гБЂгВИгВКгАБ憙䪿йЦУгБЃеРИжДПгБѓгАБгБЭгБЃжЬЙеКєжАІгБМи™НгВБгВЙгВМгВЛеЬЯе£МгБМжХігБДгБЊгБЧгБЯгАВи£БеИ§жЙАгБѓгАБ憙䪿еЕ®еУ°гБМзЈ†зµРгБЧгБЯи≠∞ж±Їж®©и°Мдљње•СзіДгБЂгБ§гБДгБ¶гАБдЉЪз§ЊеЕ®дљУгБЃжЙАжЬЙиАЕгБЯгВЛ憙䪿гБМдЉЪз§ЊгБЃеЗ¶еИЖжЦєж≥ХгВТиЗ™зФ±гБЂж±ЇеЃЪгБІгБНгВЛгБ®гБДгБЖиАГгБИжЦєгБЂеЯЇгБ•гБНгАБгБЭгБЃжЬЙеКєжАІгВТи™НгВБгВЛеИ§жЦ≠гВТдЄЛгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБУгБЃгВИгБЖгБ™еИ§дЊЛгБЃз©НгБњйЗНгБ≠гБЂгВИгВКгАБгВЄгГІгВ§гГ≥гГИгГЩгГ≥гГБгГ£гГЉгВТзµДжИРгБЩгВЛйЪЫгБЃе•СзіДгБЃжЬЙеКєжАІгБЂеѓЊгБЩгВЛдЇИжЄђеПѓиГљжАІгБМйЂШгБЊгВКгАБжКХи≥ЗеЃґгБЂгБ®гБ£гБ¶еЃЙењГгБЧгБ¶дЇЛж•≠и®ИзФїгВТзЂЛгБ¶гВЙгВМгВЛзТ∞еҐГгБМжХіеВЩгБХгВМгБ§гБ§гБВгВКгБЊгБЩгАВ
гБЊгБ®гВБ
жЬђз®њгБІиІ£и™ђгБЧгБЯгВИгБЖгБЂгАБеП∞жєЊгБЃдЉБж•≠зµ±ж≤їгБѓгАБйЭЮеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБЂгБѓжЯФиїЯжАІгВТгАБеЕђйЦЛдЉЪз§ЊгБЂгБѓеЫљйЪЫеЯЇжЇЦгБЂжЇЦжЛ†гБЧгБЯеО≥ж†ЉгБ™зЊ©еЛЩгВТи™≤гБЩгБ®гБДгБЖгАБдЇМгБ§гБЃзХ∞гБ™гВЛеБійЭҐгВТжМБгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВињСеєігБЃж≥ХжФєж≠£пЉИCGOгБЃзЊ©еЛЩеМЦгАБ5%гГЂгГЉгГЂгБЄгБЃеЉХгБНдЄЛгБТгАБESG冱еСКзЊ©еЛЩеМЦпЉЙгБѓгАБдЉБж•≠гБЃйАПжШОжАІгБ®еЄВе†ігБЃдњ°й†ЉжАІгВТйЂШгВБгВЛгБ®гБДгБЖеП∞жєЊжФњеЇЬгБЃжШО祯гБ™жДПжАЭгВТз§ЇгБЧгБ¶гБКгВКгАБдїКеЊМгВВеРМжІШгБЃеВЊеРСгБМзґЪгБПгБ®иАГгБИгВЙгВМгБЊгБЩгАВгБЧгБЯгБМгБ£гБ¶гАБжЧ•жЬђдЉБж•≠гБѓгАБжЧ•жЬђгБЃеИґеЇ¶гБ®гБЃи°®йЭҐзЪДгБ™й°ЮдЉЉзВєгБЂеЃЙ况гБЩгВЛгБУгБ®гБ™гБПгАБзЙєгБЂгВђгГРгГКгГ≥гВєдљУеИґгВДжГЕ冱йЦЛз§ЇгБЂйЦҐгБЩгВЛеО≥ж†ЉгБ™йБХгБДгВТжЈ±гБПзРЖиІ£гБЧгАБйБ©еИЗгБ™дљУеИґгВТжІЛзѓЙгБЩгВЛгБУгБ®гБМгАБдЇЛж•≠жИРеКЯгБЃйНµгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
гВЂгГЖгВігГ™гГЉ: ITгГїгГЩгГ≥гГБгГ£гГЉгБЃдЉБж•≠ж≥ХеЛЩ
гВњгВ∞: еП∞жєЊжµЈе§ЦдЇЛж•≠