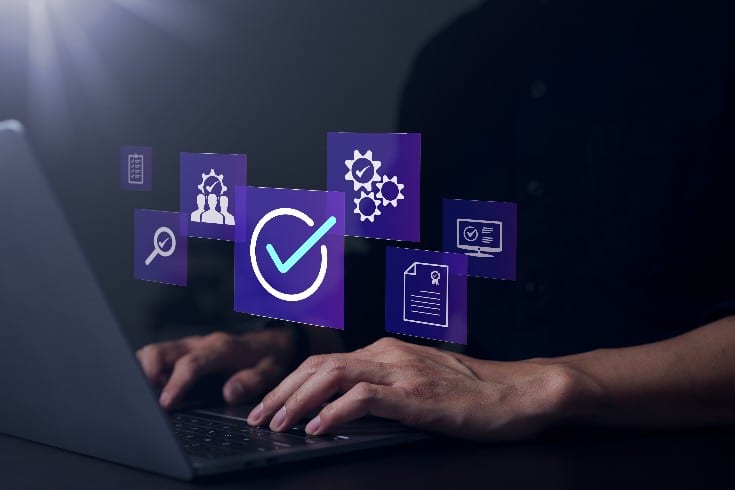インド共和国の許認可・規制環境を弁護士が解説

2025年現在、インドは世界第5位の経済規模を誇り、数年以内に日本を抜いて世界第3位の経済大国となることが予測されています。モディ政権が掲げる「メイク・イン・インディア(Make in India)」政策の下、インドは単なる安価な労働力の提供地から、巨大な消費市場およびグローバルサプライチェーンの重要な拠点へと変貌を遂げました。この急激な経済成長の裏側で、インドの法規制環境は劇的な変化を見せています。かつて「ライセンス・ラージ(許認可行政の弊害)」と呼ばれた官僚主義的な障壁は、デジタル化によって手続きの簡素化が進む一方で、「コンプライアンス・ラージ(法令遵守の厳格化)」とも呼ぶべき新たな局面を迎えています。
日本企業がインドへ進出する際、最も留意すべき点は、インドの法体系が連邦政府と州政府の複雑な権限配分の上に成り立っており、かつ英国法の影響を強く受けた厳格な文書主義と判例法主義が採用されていることです。日本の法規制と比較すると、インドの規制は「原則禁止・例外許可」の構造をとるものが多く、特に資本取引や外貨管理においてはその傾向が顕著です。また、近年では製品の品質基準(BIS認証)や環境規制が非関税障壁として戦略的に活用されており、これらへの対応を誤ると、製品の通関停止や工場の操業停止、さらには取締役個人の刑事責任追及といった重大なリスクに直面することになります。
本記事では、インド市場への参入を検討する日本の経営者や法務担当者を対象に、インドの許認可制度の全体像を解説します。具体的には、会社設立プロセスのデジタル化、厳格な外国為替管理法(FEMA)による投資規制、インド規格局(BIS)による強制認証制度、そして独特な環境規制や取締役の法的責任について、最新の法改正や重要な判例を交えて詳述します。日本法との違いを意識しながら、実務的な観点からインドビジネスの法的課題を紐解いていきます。
なお、インドの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
インドにおける法人設立とガバナンス
インドでの事業拠点の設立は、すべてのコンプライアンスの出発点となります。2013年会社法に基づく法人設立プロセスは、近年、劇的なデジタル変革を遂げました。かつては複数の省庁を行き来し、膨大な紙の書類を提出する必要がありましたが、現在は企業省(MCA)が提供する統合ウェブフォーム「SPICe+(スパイス・プラス)」によって、手続きの大半がオンラインで完結する仕組みとなっています。
このSPICe+は2つのパートから構成されています。パートAでは商号の予約を行い、パートBでは会社の設立登記申請に加え、取締役識別番号(DIN)、納税者番号(PAN/TAN)、従業員積立基金(EPFO)、物品サービス税(GST)などの登録を一括で行います。日本の会社設立手続きでは、法務局での登記、税務署への届出、年金事務所への申請などがそれぞれ別の手続きとして存在しますが、インドではこれらが単一のフォームに統合されている点が大きな特徴です。これにより、会社設立にかかる日数は大幅に短縮されました。
資料:インド企業省公式サイト
しかし、手続きが簡素化されたとはいえ、日本企業特有の実務的なハードルは残っています。その一つが「居住取締役(Resident Director)」の要件です。2013年会社法第149条第3項は、すべてのインド会社に対し、前暦年において少なくとも182日間インドに滞在した取締役を最低1名選任することを義務付けています。日本の場合、代表取締役の居住要件は撤廃されていますが、インドではこの要件が厳格に適用されます。進出初期段階で駐在員の滞在日数が不足している場合、信頼できる現地パートナーや専門家を暫定的な居住取締役として起用するなどの対策が必要となります。
また、すべての取締役はデジタル署名証明書(DSC)を取得する必要があり、日本居住の取締役がこれを取得するためには、パスポートや住所証明書に対してアポスティーユ認証などの手続きが必要となります。日本の印鑑証明書制度とは異なり、インドでは電子署名が法的な本人確認の基盤となっていることを理解しておく必要があります。
インド外国為替管理法と対内直接投資規制

インドへの資金移動や投資は、1999年外国為替管理法(FEMA)によって厳格に管理されています。日本の外国為替及び外国貿易法(外為法)は、原則として自由な取引を認めつつ、例外的に特定の取引を規制する「事後報告」中心の体系ですが、インドのFEMAは「資本取引は原則禁止、許可されたもののみ可能」という構造をとっています。したがって、日本企業がインドへ送金する際は、その取引が明示的に許可されているか、あるいは事前の政府承認が必要かを確認しなければなりません。
インドへの外国直接投資(FDI)には、大きく分けて「自動ルート」と「政府承認ルート」の2つのエントリー・ルートが存在します。自動ルートは、政府やインド準備銀行(RBI)の事前承認を必要とせず、投資実行後にRBIへの報告を行うだけで済むルートです。現在、製造業を含む多くのセクターで100%のFDIが自動ルートで認められています。一方、政府承認ルートは、防衛産業の一部や小売業など、国家安全保障や国内産業保護の観点から慎重な審査が必要なセクターに適用され、関係省庁の事前承認が必須となります。
以下の表は、主要セクターにおけるFDI規制の概要を示したものです。
| セクター | FDI上限 | ルート区分 | 備考 |
| 製造業 | 100% | 自動ルート | 契約製造も含む |
| 保険 | 100% | 自動ルート | 近年の改正により上限が引き上げられた |
| 防衛産業 | 100% | 自動/政府 | 74%までは自動ルート、それ以上は政府承認 |
| 宇宙 | 100% | 自動/政府 | 衛星製造等は74%まで自動ルート |
| マルチブランド小売 | 51% | 政府承認 | 最低投資額や国内調達義務など厳しい条件あり |
特に注意が必要なのが、2020年に発行された「プレスノート3」による規制です。これは、インドと国境を接する国(中国、パキスタン等)からの投資、または「実質的支配者」がそれらの国に所在する場合の投資について、セクターを問わずすべて「政府承認ルート」とすることを定めたものです。日本企業であっても、中国企業との合弁事業や、中国拠点を経由した投資スキームを採用している場合、この規制の対象となる可能性があります。
FEMA違反に対する執行は年々厳格化しており、報告の遅延や手続きの不備に対しては多額のペナルティが科されます。RBIは違反を金銭的に解決する「コンパウンディング(和解)」制度を設けていますが、これは違反を自発的に申告した場合に有効な手段です。最近の最高裁判所の判決(Vijay Karia事件など)では、FEMA違反があったとしても契約自体の効力や外国仲裁判断の執行が直ちに否定されるわけではないとの判断が示されていますが、実務上の送金段階ではRBIの承認が不可欠であることに変わりはありません。
インド規格局と製品認証制度
「メイク・イン・インディア」政策の一環として、インド政府は国内産業の保護と粗悪品の排除を目的に、製品に対する強制認証制度を拡大しています。その中心となるのが、インド規格局(BIS)による認証制度です。日本のJISマーク制度は多くの品目で任意表示ですが、インドのBIS認証は、対象品目に指定されると製造・輸入・販売が一切禁止される「強制認証」となる点が大きく異なります。
BIS認証には主に2つのスキームがあります。一つは、鉄鋼製品、化学品、自動車部品などを対象とした「ISIマーク(スキームI)」です。この認証を取得するためには、インドへの製品サンプルの送付と試験だけでなく、BIS監査官による製造工場の実地監査(海外工場も含む)が必須となります。もう一つは、電子・IT機器を対象とした「強制登録制度(CRS・スキームII)」です。こちらは工場監査が原則不要で、指定ラボでの試験と書類審査により登録が行われます。
近年、インド政府は「品質管理命令(QCOs)」を相次いで発令し、BIS認証の必須品目を急速に拡大しています。特に鉄鋼製品や化学品、玩具、履物などが新たに対象となり、認証未取得の製品が通関で止められるトラブルが頻発しています。日本企業が注意すべきは、完成品だけでなく、部品や原材料も規制の対象となる場合がある点です。例えば、特定の特殊鋼がQCOの対象となった場合、その鋼材を使用する部品メーカーも、認証を取得した材料を使用しなければなりません。
BIS法違反に対する罰則は厳しく、認証のない製品を販売・保管した場合、初犯でも最低20万ルピーの罰金、再犯の場合は製品価格の最大10倍の罰金や禁錮刑が科される可能性があります。また、BIS法違反は「認知すべき犯罪(Cognizable Offence)」とされ、警察は令状なしで捜査・逮捕を行う権限を持っています。
資料:インド規格局公式サイト
インドの環境規制と汚染管理

インドの環境規制は、連邦政府が基準を策定し、各州の公害防止委員会(SPCB)が許認可の権限を持つという構造です。工場を設立・操業するためには、水質汚濁防止法および大気汚染防止法に基づき、SPCBから「設立同意(CTE)」と「操業同意(CTO)」という2段階の許認可を取得する必要があります。これは日本の公害防止協定や設置届よりも強力な許認可であり、CTOなしでの操業は即座に違法とみなされ、工場の閉鎖や電力供給の停止といった措置が取られます。
産業セクターは、汚染指数に基づいて「赤(Red)」「橙(Orange)」「緑(Green)」「白(White)」の4つのカテゴリーに分類されています。赤カテゴリーは重汚染産業として厳格な規制を受けますが、白カテゴリー(太陽光発電やLED組立など)は実質的に非汚染産業とみなされ、CTEやCTOの取得が免除され、単なる「通知(Intimation)」のみで足りるとされています。
また、環境事案を専門に扱う「国家グリーン法廷(NGT)」の存在も無視できません。NGTは「汚染者負担の原則」を厳格に適用し、環境法令に違反した企業に対して、懲罰的な意味合いを含む高額な「環境補償金」の支払いを命じることがあります。最近の最高裁判決(M/s C L Gupta Exports Ltd事件、2024年8月22日判決)では、NGTが企業の売上高のみを基準に過大な罰金を科すことを戒め、環境損害との因果関係に基づく算定を求めるなど、司法による牽制も行われていますが、環境コンプライアンスのリスクは依然として高いと言えます。
インド取締役の責任とリスクマネジメント
インドにおける企業経営において、取締役が負う法的責任は日本以上に重く、特に「代位責任(Vicarious Liability)」のリスクには細心の注意が必要です。会社法、FEMA、環境法などの多くの法令において、企業が違反行為を行った場合、その時点で「会社の業務を担当し、責任を有していた者」も自動的に処罰の対象となると規定されています。
これにより、実際には不正に関与していない非常勤取締役や、日本本社から派遣された非業務執行取締役であっても、名目上の役職を理由に刑事告発されるケースが後を絶ちません。特に、インドでは小切手の不渡りが刑事罰の対象となるため、不渡りが発生した際に取締役全員が訴えられることが通例化しています。
こうしたリスクを軽減するためには、特定の取締役(通常は現地のManaging DirectorやCEO)を「不履行責任者(Officer in Default)」として指名し、当局に届け出ておくことで、他の取締役の責任範囲を限定する手法が有効です。また、最近の法改正(新刑事訴訟法など)により、裁判所が召喚状を発する前に被告側(取締役)に聴聞の機会を与える規定が設けられるなど、不当な訴追を防ぐための手続き的な保護も強化されつつあります。
まとめ
インドの許認可制度は、英国法由来の複雑な体系に、急速な経済成長に伴う新たな規制が積み重なることで、非常に難解なものとなっています。特に、BIS認証のような技術的規制や、FEMAのような厳格な資金管理は、日本でのビジネス常識が通用しない分野です。しかし、これらの規制は市場参入のハードルであると同時に、一度クリアすれば、コンプライアンス体制の整っていない競合他社に対する強力な参入障壁としても機能します。
日本企業としては、進出前から「予防法務」に投資し、現地の最新の規制動向をモニタリングする体制を構築することが不可欠です。また、すべての手続きがデジタル化されている現在、データの正確性や期限管理はガバナンスの基本となります。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務