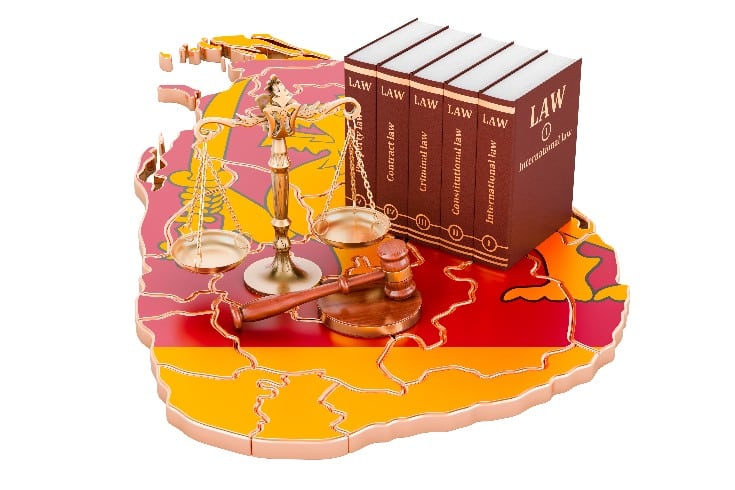ロシア連邦の会社法が定めるコーポレートガバナンスに関する法制度
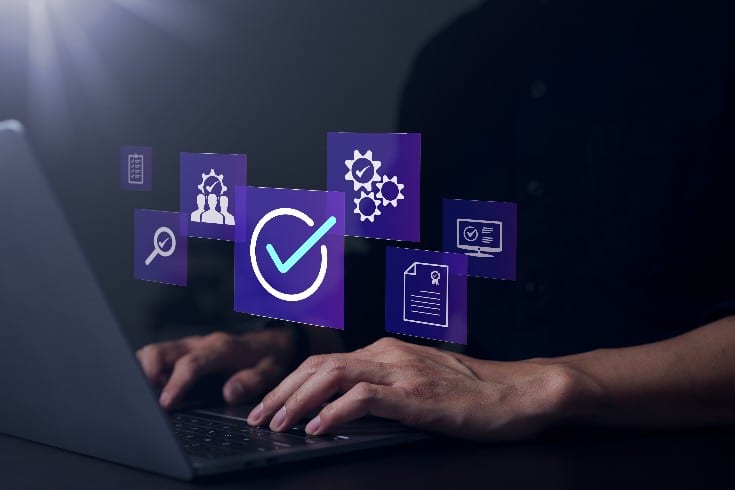
ロシア連邦で事業を展開する、あるいはその可能性を検討する場合、現地の会社法が定める企業統治(コーポレート・ガバナンス)の法的枠組みを正確に理解することは必要不可欠です。
本記事では、ロシアの会社法が定める企業統治の中核をなす法的概念を、日本のそれと比較しながら詳細に解説します。特に、経営陣の個人責任や親会社の責任にまつわる厳格な法的基準、そして近年の判例によって強化されるリスクの所在を深く掘り下げ、リスク管理策についても解説します。
なお、ロシア連邦の包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
ロシアにおける企業形態と統治の基礎概念
ロシアの商事会社は、主に株式会社(Joint-Stock Company, JSC)と有限責任会社(Limited Liability Company, LLC)に大別されます。日本の会社法における株式会社や合同会社といった事業形態と類似点を持ちますが、その法的性質や統治構造には独自の規定が設けられています。
JSCでは、株主は会社債務に対してその保有する株式の価値の範囲でしか責任を負いません。これは日本の株式会社における株主の有限責任原則と同様です。JSCはさらに「公開型」(Public Joint-Stock Company, PJSC)と「非公開型」(Non-public Joint-Stock Company, NPJSC)に分類されます。公開型は株式等が公開で取引されるものを指し、株式の自由な譲渡が可能で、最低資本金は10万ルーブルです。一方、非公開型は公開型の要件に当てはまらないものを指し、最低資本金は1万ルーブルです。
ロシアの株式会社のコーポレートガバナンス

ロシアの企業統治における意思決定構造は、株主総会、取締役会、執行機関の三つの主要な機関によって形成されています。それぞれの機関には明確な役割と権限が与えられています。
株主総会
ロシア民法第103条および連邦法「株式会社法」第47条から第63条に基づき、株主総会は会社の最高統治機関と位置づけられています。株主は、会社の合併や解散、定款の変更、取締役の選任といった重要な事項に対して議決権を行使する権利を有します。この点における基本的な原則は日本法と共通していますが、ロシアの公開JSCでは、法律で定められた専属的権限以外の事項について株主総会が議決できないなど、その権限が厳格に規定される場合がある点が異なります。
取締役会(監督委員会)
公開JSCでは、取締役会の設置が法律によって義務付けられています。議決権を持つ株主が1,000名を超える場合は7名以上、10,000名を超える場合は9名以上の取締役が必要となります。ロシアの企業統治コードでは、独立取締役を置くことが推奨されており、取締役会全体の3分の1を占めるべきとされることが一般的です。取締役会は、日常業務を遂行する執行機関を監督し、会社の戦略的意思決定を承認し、法令遵守を監視する役割を担います。
ロシアの取締役会制度には、日本の慣行と明確に異なる重要な原則があります。それは、取締役会長と執行機関のトップ(ジェネラル・ディレクター)を同一人物が兼任することはできないという権限分離の原則です。この規定は、権限の集中を回避し、取締役会による監督機能が実効的に働くようにするための仕組みです。日本の企業に見られる「会長兼社長」といった慣行とは異なります。
単一執行機関としてのジェネラル・ディレクター
ジェネラル・ディレクター(総支配人)は、アメリカのCEO(最高経営責任者)に相当する最高執行責任者であり、会社の日々の業務を統括します。ロシアの法人法において、ジェネラル・ディレクターは「単一の執行機関」とされ、法律や定款で他の機関に明示的に与えられていないすべての権限、いわゆる「残余の権限」を有します。これにより、ジェネラル・ディレクターは委任状なしに会社を代表して行動することが可能となります。
ロシアのジェネラル・ディレクターの地位は、その権限が圧倒的に集中しているという点で、日本の代表取締役とは異なります。この単一執行機関は、意思決定の迅速性を高める一方で、その人物の意思や行動が会社の運命を大きく左右するという問題があります。この権限集中リスクを軽減するため、2014年の民法改正により、複数名のジェネラル・ディレクターを置くことが可能になりました。これは、ヨーロッパで広く採用されている「四つ目原則」(four-eyes principle)をロシアにも導入し、相互牽制によるガバナンス強化を目指したものです。
ロシアの有限責任会社(OOO)のコーポレートガバナンス
社員総会
有限責任会社の最高統治機関は、社員総会です。社員は、合併や解散、定款の変更、会社役員の選任といった重要事項に対して議決権を行使します。日本の合同会社における社員総会と同様に、有限責任会社の社員総会は、会社法および定款で定められた事項について決議する権限を持ちます。ロシアの法律では、すべての有限責任会社に対し、年に一度の社員総会の開催が義務付けられており、これに違反した場合は罰金が科される可能性があります。
総支配人(ジェネラル・ディレクター)
有限責任会社は、少なくとも一人の総支配人(ジェネラル・ディレクター)を置くことが法律で義務付けられています。この総支配人は「単一の執行機関」として、会社を代表し、日常業務を統括する役割を担います。総支配人は、法律や定款によって他の機関に明確に与えられていない「残余の権限」をすべて行使することができます。
取締役会と複数名体制
株式会社(JSC)とは異なり、有限責任会社では取締役会の設置は義務ではありません。しかし、定款で定めることにより取締役会を設置することは可能であり、その場合は会社の事業全般を監督する役割を担います。この点も、日本の合同会社が取締役会の設置を義務付けられていないのと共通しています。
また、2014年の民法改正により、有限責任会社でも複数名の総支配人を置くことが可能になりました。これにより、欧州で一般的な「四つ目原則」(four-eyes principle)に沿った、複数名による相互牽制のガバナンス体制を構築できるようになりました。
複数名体制を導入する場合、それぞれの総支配人の権限を「共同行使」または「独立行使」のいずれかに定めることができます。
- 共同行使:共同行使権限を持つ総支配人が締結する契約は、すべての総支配人の署名がなければ無効となります。
- 独立行使:各総支配人が単独で会社を代表して行動し、契約を締結することができます。
しかし、株式会社のジェネラル・ディレクターに関するものと同様、ロシアの法人公的登記簿(EGRUL)が、総支配人の権限が共同であることを明確に登記するシステムに完全に対応していないという問題があります。
持分の譲渡と法人の有限責任
有限責任会社の社員は、原則として会社債務について有限責任を負います。ただし、親会社が子会社に指示を与えて取引を行わせ、その結果として子会社が破産した場合など、例外的に親会社が責任を負う場合があります。
また、有限責任会社の持分を第三者に譲渡する場合、他の社員には法律で定められた先買権(pre-emptive right)が与えられています。日本の合同会社と同様に、持分を売却する際には、他の社員に対してその売却を提案し、書面による拒否を得た上でなければ第三者に売却することができません。ただし、2025年7月に施行された改正法により、社員全員の同意を得て定款に規定を設けることで、この先買権の適用を完全に排除することが可能となりました。これは、有限責任会社の持分譲渡に関する柔軟性を大幅に高めるものです。
ロシアにおける経営陣の法的責任

ロシアでは、会社の経営陣に対する法的責任追及の基準が非常に厳格であり、日本の法務実務に慣れた者にとっては想定外の個人責任リスクを伴う可能性があります。
善管注意義務と忠実義務の厳格な適用
ロシア民法第53条の1は、会社の経営陣に対し「誠実かつ合理的に」会社のために行動する義務を課しています。この義務に違反して会社に損失をもたらした場合、経営陣は個人的な責任を追及される可能性があります。
近年のロシア最高裁判所の判例は、この「誠実かつ合理的」な行動の基準をより具体的に明確化しました。判例は、経営陣の責任を問う具体的な状況として、以下のような行為を挙げています。
- 利益相反取引の不開示:利益相反のある取引を行ったにもかかわらず、その事実を株主や取締役会に開示しなかった場合、損失は経営陣の過失によるものと推定されます。
- 不適切な報酬設定:会社の授権された機関の承認なしに、自らの報酬を決定または変更した場合、不適切な支払いは返還を求められる可能性があります。
- 不十分なデューデリジェンス:取引先の信用調査を怠った結果、会社が損失を被った場合。
- 内部手続きの不遵守:契約締結に際して、法務部や会計部門による承認といった社内の通常の手続きを遵守しなかった場合。
この基準は、日本の会社法における「経営判断の原則」と比較して非常に厳格であると思われます。日本では、経営判断が不合理でない限り、取締役は責任を免れるのが一般的ですが、ロシアの裁判所は、例えば取引先に対するデューデリジェンスの怠慢といった不合理な行為に対しても、経営陣に個人的な責任を課すことに積極的です。
法人格否認の法理(Piercing the Corporate Veil)と付随的責任
ロシアの司法実務では、支配者が会社を利用して債権者を害する場合に、判例法理として法人格否認の法理が確立しています。この法理は、ロシア民法第1条第3項の「誠実原則」や同法第10条の「権利濫用禁止」といった一般原則に基づいて適用されます。
特に注目すべきは、近年の裁判で、外国の親会社がロシア子会社の債務に対して連帯責任を負う、いわゆる「リバース・ピアシング」の傾向が顕著になっている点です。これは、親会社が制裁措置を理由にロシアの債権者への債務履行を拒否するなど、企業構造を悪用して債権者を害した場合に適用されるとされています。ロシアの裁判所は、これらの外国親会社とロシア子会社を「統一された意思決定センターを持つ同一の経済グループ」と見なし、債務履行を拒否する行為を「権利の濫用」と解釈している事例が見られます。
まとめ
ロシア連邦における事業運営の法的リスクを管理するため、日本企業は以下のような実践的な対応策を講じる必要があります。
- 内部統制とコンプライアンスの抜本的強化:ロシアの裁判所が要求する厳格な「プロフェッショナルなマネージャー」としての基準を満たすため、単なる形式的な法令遵守ではなく、現地の司法動向を反映した実効的な内部統制システムの構築が不可欠です。取引先との契約締結時には、信用調査(デューデリジェンス)を徹底し、内部決裁手続きを厳格に遵守することが、経営陣の個人責任を回避する上で極めて重要となります。
- 権限と責任の明確化:ジェネラル・ディレクターの強力な権限を前提として、親会社との間で権限委譲の範囲を明確に規定し、特に重要な意思決定には複数人の承認を必要とする体制を整えるべきです。また、利益相反管理に関する明確な方針を定め、経営陣による情報開示を徹底させることは、コンプライアンスリスクを低減する上で不可欠です。
- 専門家との継続的な連携:ロシアの法律と判例は常に進化しており、特に地政学的な影響を強く受ける分野では、最新の情報を得る必要があります。ロシア法に精通した信頼できる法務パートナーと密接に連携し、定期的な法的監査を実施することが、リスクを未然に防ぎ、不測の事態に迅速に対応するための鍵となります。
ロシアにおけるコーポレート・ガバナンスを巡る法的環境は、日本の慣行とは大きく異なるだけでなく、近年の国際情勢を背景に、予測不可能な要素を内包しています。日本の経営者や法務部員には、これらの特異な法的リスクを深く理解し、それに対応するための堅牢なガバナンス体制を構築することが強く求められます。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務