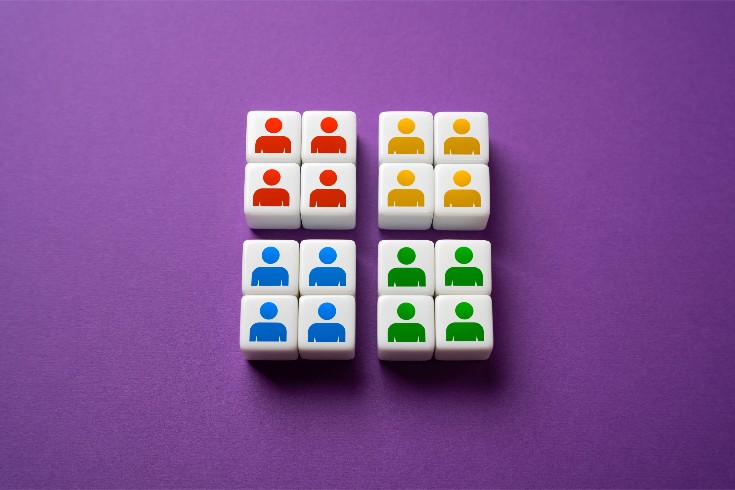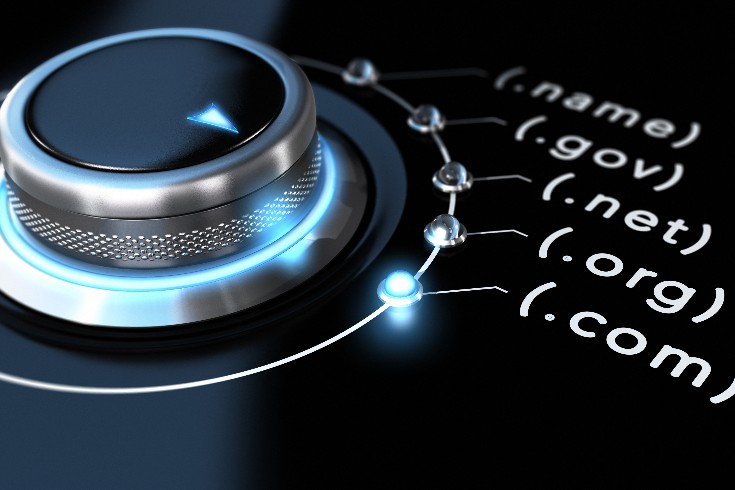システム開発への下請法の適用と違反したときの罰則を解説

IT業界において、システム開発業者が他の開発業者に開発を委託する際には、業務委託契約を締結する場合がほとんどです。
契約を締結するにあたり、契約当事者のうち、特に親事業者が確認すべき法律があります。
それは、下請法(下請代金支払遅延等防止法)です。
下請法は、下請取引の公正化および下請事業者の利益保護を目的に、親事業者の義務、禁止事項、制裁などを定めている法律です。
下請法について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご参照ください。
会社間においてシステム開発を委託する際、下請法はどのように適用されるのでしょうか。
また、下請法に違反した場合どのような罰則があるのでしょうか。
本記事では、IT実務においてよく行われる、「システム開発・運用」と「コンサルティングレポート」の業務委託を例にとって、それぞれの区分について詳しく見ていきます。
なお、下請法は令和8年1月からは「中小受託取引適正化法」に改正されます。詳しくは以下の記事をご参照ください。
この記事の目次
下請法の適用対象はどのように決まるのか

下請法は、下請取引の公正化および下請事業者の利益保護を目的に、親事業者の義務、禁止事項、制裁などを定めている法律です。
下請法の適用対象となると、下請事業者が手厚く保護される一方、親事業者は厳しい規制を受けます。
取引内容である委託契約の法的性質が、請負契約・準委任契約にかかわらず、上記に当てはまる限り下請法の対象です。
しかし、すべての取引が下請法の適用対象になるわけではありません。
下請法は、適用対象となる下請取引の範囲を、取引の内容と資本金の区分の両面から定めています。以下では、取引内容と資本金区分について解説します。
下請法の適用対象となる資本金区分

下請法には、取引の内容に応じて親事業者及び下請事業者の資本金の区分が規定されています。
この資本金の区分には、4つのパターンがあり、これに当てはまる取引のうち、特定の内容のものが、下請法の適用対象です。
パターン①:親事業者の資本金が3億円超かつ下請事業者の資本金が3億円以下
パターン②:親事業者の資本金が1千万円~3億円かつ下請事業者の資本金が1千万円以下
対象となる取引内容は、製造委託・修理委託・情報成果物制作委託(プログラムの作成に限る)・役務提供委託(情報処理に係るものに限る)とされています。
システム開発・運用はこの区分にあたります。
パターン③:親事業者の資本金が5千万円超かつ下請事業者の資本金が5千万円以下
パターン④:親事業者の資本金が1千万円~5千万円かつ下請事業者の資本金が1千万円以下
対象となる取引内容は、情報成果物制作委託(プログラムの作成以外)・役務提供委託(情報処理に係るもの以外)とされています。
コンサルティングレポートはこの区分にあたります。
下請法の適用対象となる取引内容

下請法の規制対象となる取引は、委託内容によって、おおまかに①製造委託 ②修理委託 ③情報成果物制作委託 ④役務提供委託の4つに分けられます。
システム開発・運用など
システム開発・運用については、③情報成果物制作委託、④役務提供委託に当てはまる可能性が高いです。それぞれの定義と取引内容の具体例を説明します。
まず③情報成果物制作委託について見ていきます。
「情報成果物作成委託」は下請法で以下のように定義されています。
この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。
下請法第2条第3項
また、情報成果物とは、プログラム(ソフトウェア、システムなど)、映像や音声、音響などから構成されるもの(テレビ番組や映画など)、文字、図形、記号などから構成されるもの(デザイン、報告書など)をいいます。
情報成果物作成委託には以下の3つの類型が存在します。
①他者に販売、使用許諾を行うなどの方法で情報成果物を他者の用に供することを業とする事業者(親事業者)が、その情報成果物の作成を他の事業者(下請事業者)に委託する
例えば、システム開発業者が、ユーザーに提供する名刺管理システムの開発を他の業者に委託する場合や、ゲームソフト制作・販売業者が、消費者に販売するゲームソフトの作成を他の業者に委託する場合がこれにあたります。
②ユーザー(発注元)から情報成果物の作成を受託した事業者(親事業者)が、他の事業者(下請事業者)に作成を委託(再委託)する
例えば、システム開発業者が、ユーザーから開発を請け負ったシステムの一部の開発を他の業者に委託(再委託)する場合がこれにあたります。
③事業者(親事業者)が、自社で業として作成している自家使用の情報成果物の作成を他の事業者(下請事業者)に委託する
例えば、Web制作業者が、自社のイントラサイトの一部の開発を他の業者に委託する場合がこれにあたります。
次に、④役務提供委託の定義は以下の通りです。
この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。
下請法第2条第4項
例えば、ソフトウェア販売業者が、当該ソフトウェアの保守・運用を他の事業者に委託することがこれに当たります。
コンサルティングレポート
コンサルティングレポートは、情報成果物に該当するため(下請法第2条第6項第3号)、その作成を委託することは、③情報成果物制作委託にあたります。
下請法で定められた親事業者の義務と禁止事項

当該取引が下請法の適用を受ける場合、親事業者はどのような義務を負うのでしょうか。禁止事項と併せて解説します。
親事業者に課される4つの義務
下請法上、親事業者には次の義務が課されています。
- 給付内容や代金、支払期限等を記載した書面を交付する義務
- 下請代金の支払期限を定める義務
- 下請け業者の給付、給付の受領、下請代金の支払等を記載した書類を作成し、保管する義務
- 支払代金を期限までに支払わなかった場合に、遅延利息を支払う義務
親事業者に課される禁止事項
下請法上、親事業者には次の禁止事項が課せられています。
- 受領拒否の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 下請代金の支払遅延の禁止
- 不当な返品の禁止
- 買いたたきの禁止
- 物品の購入やサービス利用の強要の禁止
- 報復措置の禁止
- 原材料などの対価の早期決済の禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 不当な経済上の利益提供を要請することの禁止
- 不当な給付内容の変更、やり直しの禁止
詳しくは、経済産業省「情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」に記載されています。
上記禁止事項のなかでも、IT業界で問題になりやすい下請代金や給付内容について、以下で詳しく解説します。
下請代金の額・支払期日
下請代金の額については、市場価格に比べて著しく低い額を不当に定めることや、下請事業者に帰責性がないにもかかわらず、発注後に減額することは禁止されています。
支払期日については、物品等を受領した日(役務提供の場合は役務が提供された日)から60日以内のできる限り短い期間内に定めることが必要です。
遅滞利息については、親事業者が支払いを遅延した場合には、下請事業者に対し、物品等受領日から起算して60日を経過した日から支払日まで、日数に応じて年利14.6%の遅延利息を支払わなければなりません(公正取引委員会規則参照)。
物品等の受領と返品
下請事業者になんら責任がないにもかかわらず、注文した物品などの受領を拒むことは禁止されています。
また返品について、親事業者は、下請事業者に責任がないにもかかわらず返品することは禁止されています。ただし、受領後の納入品にただちに発見できない欠陥があることが判明した場合、6か月以内であれば返品することができます。
不当なサービス要請・給付内容変更
親事業者が下請事業者に、契約内容となっていない金銭、役務の提供等を要請することや、下請事業者に責任がないのに費用を負担せずに仕様など給付内容の変更・やり直しをさせることは禁止されています。
インボイス制度との関連
親事業者は、インボイス制度に沿った対応が必要です。下請事業者が免税事業者であることを理由に一方的に代金を減額する行為は、下請法の禁止事項に該当するおそれがあります。
また、免税事業者から課税事業者へ転換した下請事業者が価格の見直しを求めたにもかかわらず、要請を拒否して従来の価格を維持する行為も同様です。親事業者としては、インボイス制度の運用だけでなく、下請法の規定にも十分配慮した対応が求められます。
親事業者が下請法に違反すると判断された場合
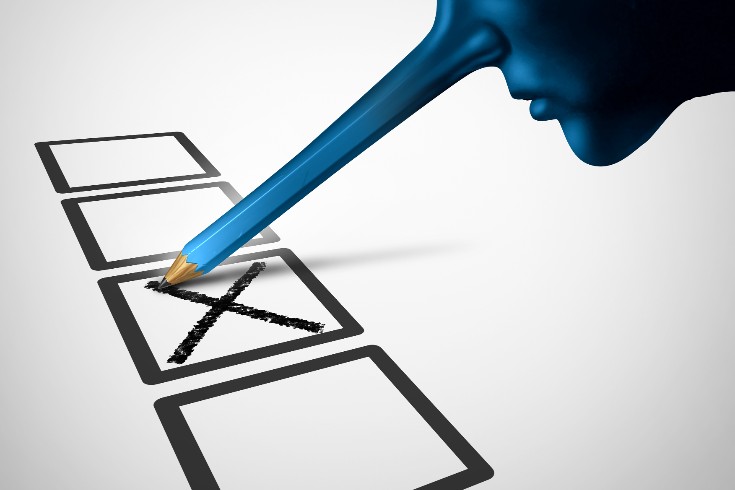
公正取引委員会は、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるために、必要があると認めるときは、 親事業者・下請事業者の両者に対し、下請取引に関する報告をさせ、親事業者の事業所等で立入検査を行わせることができます(下請法第9条第1項)。
公正取引委員会や中小企業庁は、下請法違反行為が認められると、違反親事業者に対して勧告を行います。公正取引委員会が勧告をした場合、違反内容、社名が公正取引委員会のホームページ上に下請法勧告一覧として、公表されます。
親事業者が、下請事業者への書面の交付義務や書類の作成・保存義務に違反した場合や、上記の調査・検査に対する拒否、虚偽報告などを行った場合には、50万円以下の罰金が科されます。
また、下請法違反に対する罰則は両罰規定であり、違反した場合、行為者個人が罰せられるだけでなく、会社も罰せられます(下請法第10条、第11条、第12条)。
「下請法」から「中小受託取引適正化法」へ(2026年以降)
令和8年(2026年)1月1日より、下請法の改正が施行されます。法律名称が変更されるほか、保護対象の拡大、禁止行為の明確化など、中小事業者や個人事業主の取引環境を改善する重要な変更が行われます。
法律名称の変更:中小受託取引適正化法(取適法)
令和8年(2026年)1月1日より、現行の「下請法」(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、「中小受託取引適正化法」に変わります。正式名称は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。
また「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に名称変更されます。
適用対象の拡大
規制および保護の適用対象が拡充されます。
従業員基準の追加
従来の資本金基準に加え、従業員基準(300人、100人)が適用基準に追加され、規制対象が広がります。
対象取引の追加
適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託である「特定運送委託」が追加されます。
物品の拡大
製造委託の対象物品に金型以外の型(木型、治具等)が追加されます。
禁止行為の追加
委託事業者が遵守すべき禁止事項に、特に以下の2つが追加されました。
協議に応じない一方的な代金決定の禁止
中小受託事業者からの価格協議の求めがあった場合に、協議に応じないなど、一方的な代金決定を行うことが禁止されます。
手形払等の禁止
「手形払」が禁止されます。また「電子記録債権」など、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なその他の支払手段についても禁止されます。
参考:公正取引委員会|2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!
下請法の改正について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご参照ください。
下請法違反のおそれがある場合は自発的申し出で勧告回避の可能性も

下請法に違反している可能性がある場合、公正取引委員会が調査に着手する前に、以下に掲げる一定の事由を満たし、親事業者が自発的に申し出ることで、勧告を回避できる可能性があります。
1 公正取引委員会が当該違反行為に係る調査に着手する前に,当該違反行為を自発的に申し出ている。
平成20年12月17日 公正取引委員会「下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて」
2 当該違反行為を既に取りやめている。
3 当該違反行為によって下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置(注)を既に講じている。
4 当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることとしている。
5 当該違反行為について公正取引委員会が行う調査及び指導に全面的に協力している。
(注) 下請代金を減じていた当該事案においては,減じていた額の少なくとも過去1年間分を返還している。
このように、勧告を回避するためには、自発的な申し出のほかにも多くの条件を満たす必要があります。下請法違反の恐れがある場合には、すみやかに弁護士に相談してこれらの対処を行うことをおすすめします。
まとめ:下請法(取適法)については弁護士に相談を
下請法は、立場の弱い下請事業者を不当な不利益から守り、公正な取引秩序を維持するために極めて重要な法律です。親事業者には「発注書面の交付義務」をはじめとする4つの義務と、「受領拒否」や「不当な代金減額」など11の禁止行為が厳格に定められています。
これらの規制は、資本金区分によって自動的に適用されるため、「知らなかった」「悪意はなかった」という弁明は通用しません。日常の商慣行のつもりが、意図せず下請法違反となっているケースも散見されます。下請法に違反した場合、公正取引委員会による調査や勧告、指導の対象となるだけでなく、違反の事実が公表されれば、企業の社会的信用は大きく失墜します。
システム開発・運用等の委託は、下請法の規制対象となる可能性があります。自社の取引が下請法の規制対象となっていないか、また、契約書の整備や発注プロセスが法令を遵守できているかを改めて確認し、運用に少しでも不安がある場合は、専門家である弁護士に速やかに相談し、コンプライアンス体制を整備することを強く推奨します。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に高い専門性を有する法律事務所です。当事務所では、東証上場企業からベンチャー企業まで、さまざまな案件に対する契約書の作成・レビューを行っております。契約書の作成・レビュー等については、下記記事をご参照ください
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務