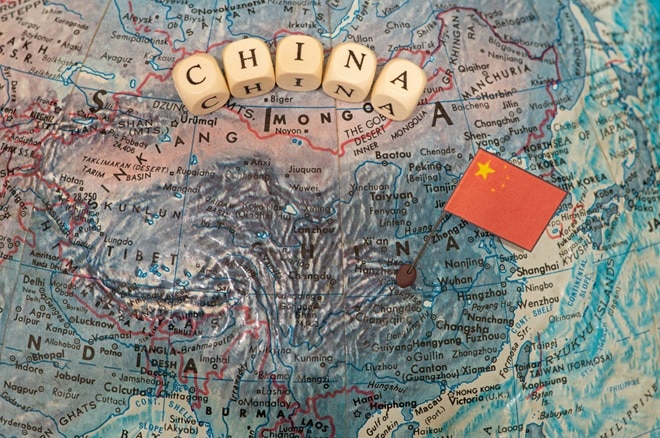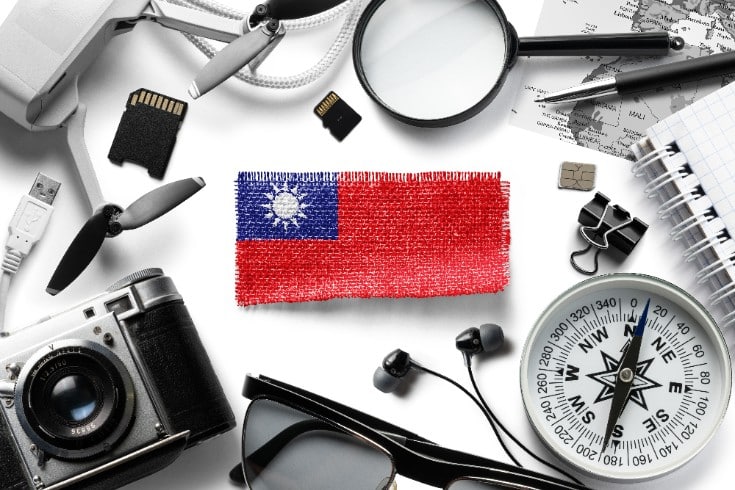イタリア共和国での契約書作成などにおける重要概念である「causa」

イタリア(正式名称、イタリア共和国)でのビジネス展開を検討される日本企業にとって、現地の契約法に関する深い理解は不可欠です。イタリア民法典は、契約の有効な成立に際して、当事者の「合意」のみならず、「Causa」(原因)、「目的」、「形式」という四つの必須要件を定めています。これらの要件は、日本の契約法には直接的に存在しない概念や、異なった法的機能を果たすものも含まれており、日本企業が契約を締結する際に予期せぬリスクに直面する可能性があります。
本記事では、イタリア民法典の条文や最新の裁判例に基づき、これら四つの必須要件が何を意味し、なぜ日本企業が慎重な検討を要するのかを、日本の法体系との比較を交えつつ詳細に解説します。
なお、イタリアの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
イタリアにおける契約成立の必須要件
イタリア民法典(Codice Civile)は、契約の有効な成立に不可欠な要件を厳格に定めています。民法典第1325条は、契約の必須要件として、「当事者の合意(accordo)」「原因(Causa)」「目的(oggetto)」「形式(forma)」の四つを挙げています。これらのうち一つでも欠けると、契約は無効と判断されます。日本の民法における契約の成立要件は、原則として当事者間の「申込み」と「承諾」という「合意」のみであり、イタリア法が要求する厳格な構造とは根本的に異なります。
イタリア民法典「当事者の合意」(Accordo delle parti)
イタリア民法典第1325条が挙げる最初の要件は「当事者の合意」です。これは、二つ以上の当事者が同じ目的に向かって意思を相互に表明し、その意思が合致することを意味します。合意は、書面または口頭で明示的に行われることもあれば、行動によって黙示的に成立することもあります。
この概念は日本の「合意」と一見類似していますが、日本の民法では原則として「申込み」と「承諾」の合致によって契約が成立するため、より簡潔な構造と言えます。ただし、イタリア法では、この合意が錯誤(errore)、詐欺(dolo)、強迫(violenza)といった「意思の瑕疵」によって形成された場合、契約は無効ではなく、取消しが可能となります。この点は、日本の民法における錯誤、詐欺、強迫の規定と共通する部分です。
イタリア民法典「Causa」(原因)

「Causa」は、当事者の主観的な意思の合致である「合意」とは別に、契約が持つ客観的な機能を意味します。
典型的な売買契約を例に挙げると、その「Causa」は、売主が買主へ財産の所有権を移転する義務と、買主が売主へ代金を支払う義務という、相互の対価関係そのものにあります。この相互の約束こそが、契約が社会的に有する「正当な理由」となり、その契約が法的に保護される根拠となります。この概念は、英米法における「約因(consideration)」と類似していますが、英米法が「価値あるものの交換」を厳密に求めるのに対し、イタリア法は必ずしも厳格な価値交換を要求せず、「合法的な目的」や「社会経済的な機能」を重視する点で違いがあります。
「Causa」と「Motivi」(動機)の厳格な区別
イタリア法では、契約の客観的な機能を指す「Causa」と、契約を締結する個人の個人的な理由や目的である「Motivi」(動機)は厳格に区別されます。例えば、ある企業が新製品を販売するために特定の商品を仕入れる契約を締結する際、「市場シェアを拡大したい」という目的は個人的な「Motivi」に過ぎず、契約の有効性には原則として影響を与えません。一方、この契約の「Causa」は、「商品の所有権の移転」と「代金の支払い」という相互の約束となります。この動機は、契約の客観的な機能である「Causa」とは異なり、原則として法的関連性がないとされています。
「Causa」と日本の「公序良俗」の比較
日本法にも、契約の有効性を制限する一般的な概念として「公序良俗」があります。民法第90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定めています。この概念は、社会的妥当性を著しく欠く行為に法的効力を与えないことを目的としています。
イタリア法も、Causaが「強行法規、公序、善良な風俗」に反する場合に違法となり、契約が無効になると定めており(民法典第1343条)、この点で両者の概念は類似しています。しかし、その機能には根本的な思想の違いがあります。
日本の公序良俗は、契約が成立した後にその内容が社会的に不当である場合に無効という判断を下す、いわば「ネガティブ・チェック」としての側面が強い概念です。これに対し、イタリア法のCausaは、契約の有効性の根源となる積極的な要件です。契約が成立する時点で、その「社会経済的な正当性」がなければ無効という判断が下されるため、より厳格かつ能動的な審査基準と言えます。
この思想の違いから、日本企業はイタリアでの契約締結に際し、単に「公序良俗に反しないか」という受動的な観点だけでなく、その契約がイタリア法における「Causa」の要件を具体的に満たしているかという、より積極的な観点から慎重に検討する必要があります。特に、日本の商慣習に由来する、形式的には有効であるように見える契約形態が、イタリア法において「Causa」の要件を満たさないと判断されるリスクを考慮しなければなりません。
Causaの不在(Mancanza di causa)による契約の無効
契約に社会経済的な機能が完全に欠けている場合、イタリア民法典第1418条第2項に基づき、契約は無効となります。これは、契約という法的な枠組みが、無意味な行為を保護しないという考え方に基づいています。
具体的には、以下のような事案が挙げられます。
- 既に自己が所有する物を購入する契約:買主はすでに所有権を有しているため、契約に「所有権移転」という機能が欠けており、無意味なものと判断されます。
- 対価が極めて象徴的な金額である売買契約(”vendita nummo uno”):100ユーロでローマのスペイン広場のマンションを売買するといった事例では、売買の「交換」という機能が失われているため、契約が無効と判断される可能性がある、などと説明されています。
Causaの違法性(Causa illecita)による契約の無効
民法典第1343条に基づき、契約のCausaが強行法規、公序、善良な風俗に反する場合、契約は無効となります。これは、違法な目的を持つ契約を法が保護しないという原則を明確にしたものです。
この点に関して、イタリア最高裁判所は、2022年5月31日判決(第17568号)において、犯罪行為に起因する契約の無効を巡る重要な判断を下しました。この判決は、詐欺(truffa)による契約は単なる「意思の瑕疵」として取り消しの対象となる一方、恐喝(estorsione)や無能力者への不当な勧誘(circonvenzione d’incapace)による契約は「無効」となると区別しています。
この区別は、契約の無効を判断する際に、単なる「形式的基準」(当事者の意思の瑕疵)ではなく、「実体的基準」(契約が侵害する法的利益の性質)が採用されていることを示しています。恐喝や無能力者への不当な勧誘は、個人の財産権だけでなく、個人の自由や自己決定権といった、より高次の「公共の利益」を侵害すると判断されます。そのため、これらの行為に起因する契約は、その「Causa」が公共の秩序に反するとして、取り消しではなく無効という重い法的制裁が課せられるのです。
「正当な理由」(Giusta causa)と契約解除の限界
代理店契約など、長期的な関係を前提とする契約では、当事者の債務不履行や客観的な事情の変更を理由に、「正当な理由(Giusta causa)」による契約解除が問題となることがあります。この「Giusta causa」もまた、単なる当事者の意思ではなく、契約の客観的な目的に照らして判断されます。
この点に関して、ローマ裁判所は2022年6月23日判決(第5995号)において、販売目標の未達を理由に代理店契約を「正当な理由」により解除する旨の条項を無効と判断しました。この判決は、当事者が「正当な理由」という法的概念を、法律が定める最低限の保護を損なう形で恣意的に定義することはできないと判断したものです。これは、契約の自由(autonomia contrattuale)が、Causaや誠実義務(buona fede)といった公的な原則によって制約されるというイタリア法の根本原則を改めて示したものです。
この判決は、日本企業が日本の商慣習に沿って作成した契約書をそのままイタリアで使用することが危険であるという典型的な例でしょう。契約書に明確な解除事由を定めたとしても、それが「Causa」の概念や法が定める保護原則に反する場合、裁判所によって無効と判断される可能性があります。特に、契約解除の条項や、一方的な義務を課す条項を設ける際には、その条項がイタリア法における「Causa」の要件と矛盾しないか、また、当事者間の公平性を著しく損なわないかといった観点から、細心の注意を払って作成する必要があります。
イタリア民法典「目的」(Oggetto)
契約の「目的」とは、契約によって当事者が追求する利益や、その契約によって生じる行為や給付を指します。イタリア民法典第1346条は、契約の目的は「可能で、適法で、確定しているか、または確定可能でなければならない」と定めています。
- 可能性(Possibilità):物理的または法的に目的が実現可能である必要があります。例えば、すでに破壊された建物を売買する契約は物理的に不可能であり、無効です。また、法的に譲渡が禁止されている公共の記念碑を売買する契約も、法的に不可能であるため無効となります。
- 適法性(Liceità):目的が法律、公序良俗、善良な風俗に反してはなりません。例えば、公共事業の許可を得るために賄賂を支払う契約や、麻薬の売買契約は目的が違法であるため無効となります。
- 確定性・確定可能性(Determinatezza o determinabilità):目的は、その契約が何に関するものかを明確に特定できるか、または将来的に特定できるものでなければなりません。
日本の民法にも「目的」に関する概念は存在しますが、イタリア法のように独立した必須要件として列挙はされていません。しかし、「公序良俗」や「意思能力・行為能力」の要件の中で、違法な目的や内容が不明確な契約が無効となる点は共通しています。
イタリア民法典「形式」(Forma)
イタリア民法典第1325条は、契約の形式は「法律によって無効の罰則のもとに規定されている場合に限り」必須要件となると定めています。これは、原則として契約は口頭であっても成立する「自由な形式の原則」が基本であることを意味します。しかし、不動産の所有権移転契約など、特定の種類の契約では、法律により「公証証書または私署証書」による書面形式が義務付けられており、これに従わない場合は無効となります(民法典第1350条)。
この点は日本の民法と類似しています。日本の民法も契約の成立に形式を要しない「諾成契約」が原則ですが、不動産の売買契約など、紛争予防や証拠保全の観点から書面での契約締結が推奨されています。しかし、書面がなくても契約は成立し、その法的効力に影響はありません。
まとめ
本記事で解説してきたように、イタリアと日本の、契約の成立に関する要件や考え方は、以下のように整理できると思われます。
| 項目 | イタリア法での要件 | 日本法との比較 |
|---|---|---|
| 合意 (Accordo) | 当事者の意思の合致。意思の瑕疵(錯誤、詐欺、強迫)は取消事由となる。 | 契約は当事者の「申込み」と「承諾」の合致で成立。意思の瑕疵の扱いは類似。 |
| Causa (原因) | 契約の客観的な社会経済的機能。契約成立の積極的な要件。 | 直接的な概念は存在しない。類似概念の「公序良俗」は、契約内容の妥当性を事後的に判断する側面が強い。 |
| 目的 (Oggetto) | 契約の対象となる給付や利益。可能、適法、確定または確定可能でなければならない。 | 明文の必須要件はないが、違法な目的や不明確な内容の契約は「公序良俗」等の理由で無効となる。 |
| 形式 (Forma) | 不動産契約など、法律で定められた場合に限り必須。原則は自由。 | 書面は原則として不要(諾成契約)。特定の契約については法律で定めがある場合がある。 |
イタリア契約法における「合意」「Causa」「目的」「形式」という四つの必須要件は、日本の法体系とは異なる独自の思想に基づいています。特に「Causa」は、単なる当事者の意思の合致を超え、契約自体の社会経済的な正当性を問うものであり、日本企業がイタリアで契約を締結する際には最も注意すべき点です。
形式的に日本の法律に沿って作成された契約書であっても、イタリア法上の「Causa」や「目的」の要件を満たさない場合、無効と判断されるリスクがあるため、契約書上では、これらが満たされていることを明確化する規定を設けるべきです。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務