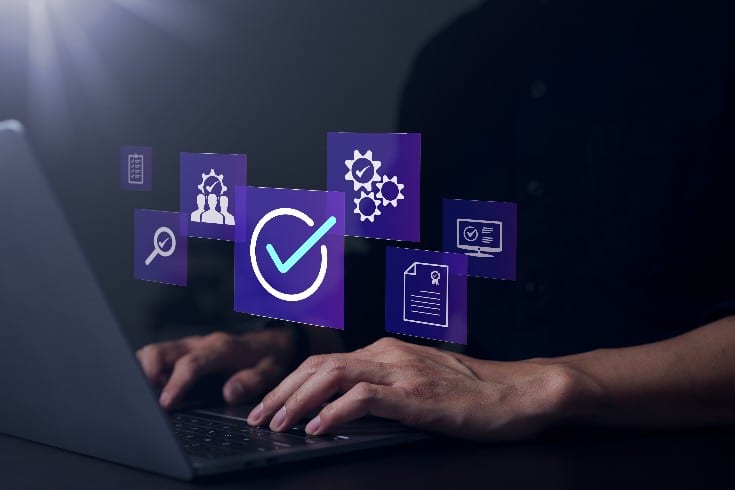гӮҝгӮӨгҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

гӮҝгӮӨгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒгғүгӮӨгғ„гӮ„гғ•гғ©гғігӮ№гҒ®жі•е…ёгӮ’гғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҹеӨ§йҷёжі•зі»гҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдё»иҰҒгҒӘжі•еҫӢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е…ӯжі•гҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгҖҢж°‘е•Ҷжі•е…ёгҖҚгҖҢеҲ‘жі•е…ёгҖҚгҖҢж°‘дәӢиЁҙиЁҹжі•е…ёгҖҚгҖҢеҲ‘дәӢиЁҙиЁҹжі•е…ёгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹдҪ“зі»зҡ„гҒӘжі•е…ёгҒЁгҒ—гҒҰж•ҙеӮҷгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒӘжі•еҫӢж§ӢжҲҗгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеӨҡгҒҸгҒ®е…ұйҖҡзӮ№гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮҝгӮӨгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜе®Ңе…ЁгҒ«зҙ”зІӢгҒӘеӨ§йҷёжі•зі»гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжӯҙеҸІзҡ„гҒ«иӢұеӣҪжі•гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгҒ•гӮүгҒ«з¬¬дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеҫҢгҒҜзұіеӣҪжі•гӮӮеҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҹзөҗжһңгҖҒзҸҫеңЁгҒҜгҖҢж··еҗҲжі•гҖҚзҡ„гҒӘжҖ§иіӘгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж··еҗҲзҡ„гҒӘжҖ§иіӘгҒҜгҖҒзү№гҒ«зҹҘзҡ„иІЎз”ЈгӮ„еӣҪйҡӣеҸ–еј•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж–°гҒ—гҒ„гғ“гӮёгғҚгӮ№й ҳеҹҹгҒ§йЎ•и‘—гҒ«зҸҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҢгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒҷгӮӢеҚҳдёҖгҒ®еҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ§е…ЁгҒҰгҒ®жЎҲ件гӮ’еҮҰзҗҶгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮҝгӮӨгҒ«гҒҜзӣ®зҡ„еҲҘгҒ«еҲҶеҢ–гҒ—гҒҹиӨҮж•°гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒйҖҡеёёгҒ®дәӢ件гӮ’жүұгҒҶеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®д»–гҒ«гҖҒжі•еҫӢгҒ®еҗҲжҶІжҖ§гӮ’еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҖҒж”ҝеәңж©ҹй–ўгҒЁгҒ®зҙӣдәүгӮ’жүұгҒҶиЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖгҖҒи»ҚдәәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢдәӢ件гӮ’жүұгҒҶи»ҚдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжҳҺзўәгҒ«еҢәеҲҶгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгӮҝгӮӨгҒ®ж··еҗҲжі•зҡ„гҒӘжҖ§иіӘгҒЁгҖҒзӢ¬зү№гҒӘиЈҒеҲӨжүҖгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’и©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйҮҚиҰҒгҒӘзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©еҸҠгҒіеӣҪйҡӣеҸ–еј•иЈҒеҲӨжүҖгӮ„еҠҙеғҚиЈҒеҲӨжүҖгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒгҒқгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгӮ„гҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгӮ’гҖҒжңҖж–°гҒ®еӢ•еҗ‘гӮ„еҲӨдҫӢгӮ’дәӨгҒҲгҒӘгҒҢгӮүжҺҳгӮҠдёӢгҒ’гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгӮҝгӮӨзҺӢеӣҪгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
В
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гӮҝгӮӨжі•дҪ“зі»гҒ®еҹәжң¬ж§ӢйҖ
гӮҝгӮӨгҒ®зҸҫд»Јжі•гҒҜгҖҒ19дё–зҙҖеҫҢеҚҠгҒ«гғ©гғјгғһ5дё–пјҲгғҒгғҘгғ©гғӯгғігӮігғјгғіеӨ§зҺӢпјүгҒҢжі•еҲ¶еәҰгҒ®иҝ‘д»ЈеҢ–гҒ«зқҖжүӢгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«з«ҜгӮ’зҷәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®ж¬§зұіеҲ—еј·гҒҢгӮҝгӮӨпјҲеҪ“жҷӮгҒҜгӮ·гғЈгғ пјүгҒ«иҰҒжұӮгҒ—гҒҹжІ»еӨ–жі•жЁ©гӮ’ж’Өе»ғгҒ—гҖҒеӣҪ家гҒ®дё»жЁ©гӮ’еӣһеҫ©гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж”№йқ©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгӮҝгӮӨгҒҜ欧е·һеӨ§йҷёжі•гҖҒзү№гҒ«гғ•гғ©гғігӮ№жі•гӮ„гғүгӮӨгғ„жі•гӮ’гғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒҰдё»иҰҒгҒӘжі•е…ёгӮ’з·ЁзәӮгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮҝгӮӨгҒ®дё»иҰҒгҒӘжі•е…ёгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢж°‘е•Ҷжі•е…ёгҖҚгӮ„гҖҢеҲ‘жі•е…ёгҖҚгҒӘгҒ©гҒҢеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁе…ұйҖҡгҒҷгӮӢеӨҡгҒҸгҒ®зү№еҫҙгҒҢеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮВ
гӮҝгӮӨжі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮігғўгғігғ»гғӯгғјгҒЁгҖҢж··еҗҲжі•гҖҚ
гӮҝгӮӨгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜеӨ§йҷёжі•гӮ’еҹәзӣӨгҒЁгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгӮӮгҖҒе®Ңе…ЁгҒ«зҙ”зІӢгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжӯҙеҸІзҡ„гҒ«гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®еҪұйҹҝгҒҢеј·гҒҸгҖҒ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰеҫҢгҒҜзұіеӣҪгҒӢгӮүгӮӮеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒҚгҒҹзөҗжһңгҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈгӮ„еӣҪйҡӣеҸ–еј•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзү№е®ҡгҒ®жі•еҲҶйҮҺгҒ§гҒҜгӮігғўгғігғ»гғӯгғјгҒ®иҰҒзҙ гҒҢиүІжҝғгҒҸзҸҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж··еҗҲзҡ„гҒӘжҖ§иіӘгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зҙ”зІӢгҒӘеӨ§йҷёжі•зі»гҒ«еұһгҒҷгӮӢжі•дҪ“зі»гҒЁгҒ®й–“гҒ«йҮҚиҰҒгҒӘйҒ•гҒ„гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ
гӮҝгӮӨгҒ®ж··еҗҲжі•гҒҢеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹиғҢжҷҜгҒ«гҒҜгҖҒеӣҪ家主権гӮ’гӮҒгҒҗгӮӢжӯҙеҸІзҡ„гҒӘзөҢз·ҜгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ19дё–зҙҖгҖҒгӮҝгӮӨгҒҜиӢұеӣҪгҒЁгҒ®гғңгғјгғӘгғігӮ°жқЎзҙ„гӮ„зұіеӣҪгҒЁгҒ®еҸӢеҘҪйҖҡе•ҶжқЎзҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҖҒ欧зұіи«ёеӣҪгҒ«жІ»еӨ–жі•жЁ©гӮ’иЁұгҒҷгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮҝгӮӨеӣҪеҶ…гҒ§еӨ–еӣҪжі•гҒҢдҪөиЎҢгҒ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзү№ж®ҠгҒӘзҠ¶жіҒгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҠ¶жіҒгҒӢгӮүи„ұеҚҙгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮҝгӮӨгҒҜ欧зұіи«ёеӣҪгҒҢдҝЎй јгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁиӘҚгӮҒгӮӢиҝ‘д»Јзҡ„гҒӘжі•дҪ“зі»гӮ’иҮӘгӮүж§ӢзҜүгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒ«иҝ«гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®ж–Үи„ҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӨ§йҷёжі•гӮ’гғўгғҮгғ«гҒЁгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒзү№гҒ«еӣҪйҡӣе•ҶеҸ–еј•гӮ„йҮ‘иһҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҲҶйҮҺгҒ§еҪұйҹҝеҠӣгҒ®еӨ§гҒҚгҒӢгҒЈгҒҹиӢұеӣҪгғ»зұіеӣҪжі•гҒ®е®ҹеӢҷгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶйҒёжҠһгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгӮҝгӮӨгҒ®гҖҢж··еҗҲжі•гҖҚгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢеҒ¶з„¶гҒ®з”Јзү©гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдё»жЁ©еӣһеҫ©гҒЁгҒ„гҒҶеӣҪ家зҡ„гҒӘиӘІйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘжі•ж”№йқ©гҒ®зөҗжһңгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒж–°гҒ—гҒ„гғ“гӮёгғҚгӮ№еҲҶйҮҺгҒ§гӮігғўгғігғ»гғӯгғјзҡ„иҰҒзҙ гҒҢйЎ•и‘—гҒ«зҸҫгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе®ҹеӢҷдёҠгҒ®еӮҫеҗ‘гҒҢеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
ж°‘е•Ҷжі•е…ёгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮігғўгғігғ»гғӯгғјз”ұжқҘгҒ®иҰҒзҙ
гӮҝгӮӨгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҢгӮігғўгғігғ»гғӯгғјгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢйЎ•и‘—гҒӘдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®жңүеҠ№иҰҒ件гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢзҙ„еӣ пјҲconsiderationпјүгҖҚгҒ®жҰӮеҝөгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгӮігғўгғігғ»гғӯгғјеҘ‘зҙ„жі•гҒ®дёӯж ёгӮ’гҒӘгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒеҘ‘зҙ„гҒҢжі•зҡ„гҒ«жңүеҠ№гҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеҪ“дәӢиҖ…еҸҢж–№гҒҢзӣёдә’гҒ«дҪ•гӮүгҒӢгҒ®дҫЎеҖӨгҒ®гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’дәӨжҸӣгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҺҹеүҮгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҖҢзҙ„еӣ гҖҚгҒҜгҖҒйҮ‘йҠӯгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҸҗдҫӣгҖҒзү©е“ҒгҒ®еј•гҒҚжёЎгҒ—гҒӘгҒ©гҖҒзӣёдә’гҒ«дҫЎеҖӨгҒ®гҒӮгӮӢзҙ„жқҹгӮ„зҫ©еӢҷгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•гҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҙ„еӣ гҒ®жҰӮеҝөгҒҜеӯҳеңЁгҒӣгҒҡгҖҒеҪ“дәӢиҖ…й–“гҒ®ж„ҸжҖқиЎЁзӨәгҒ®еҗҲиҮҙгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°еҘ‘зҙ„гҒҜжңүеҠ№гҒ«жҲҗз«ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдёҖж–№гҒҢз„Ўе„ҹгҒ§дҪ•гҒӢгӮ’зҙ„жқҹгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒ§гҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҒқгҒ®зҙ„жқҹгҒҜжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮҝгӮӨгҒ®жі•еҫӢгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзӣёдә’гҒ®зҫ©еӢҷгӮ„дҫЎеҖӨгҒ®дәӨжҸӣгҒҢгҒӘгҒ„еҘ‘зҙ„гҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰжі•зҡ„жӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„гҒЁи§ЈйҮҲгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒгӮҝгӮӨгҒ§гҒ®еҘ‘зҙ„дәӨжёүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзҙ„еӣ гҒ®еӯҳеңЁгҒҢжҳҺзўәгҒ«иҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®жңүеҠ№жҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢдёҠгҒ§йқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘиҰҒзҙ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮВ
гӮҝгӮӨгҒ®еӨҡеұӨзҡ„гҒӘеҸёжі•еҲ¶еәҰ
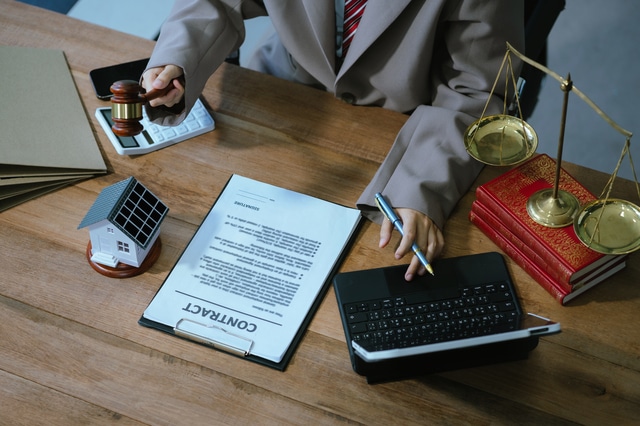
ж—Ҙжң¬гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҢгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒҷгӮӢеҚҳдёҖгҒ®еҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ§е…ЁгҒҰгҒ®жЎҲ件гӮ’жүұгҒҶгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮҝгӮӨгҒ«гҒҜзү№е®ҡгҒ®зӣ®зҡ„еҲҘгҒ«еҲҶеҢ–гҒ—гҒҹиӨҮж•°гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгӮҝгӮӨжі•еӢҷгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒЁжңҖгӮӮз•°гҒӘгӮӢзӮ№гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮгӮҝгӮӨгҒ®зҸҫиЎҢжҶІжі•гҒ®дёӢгҒ§гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®4гҒӨгҒ®дё»иҰҒгҒӘиЈҒеҲӨжүҖгҒҢжҳҺзўәгҒ«еҢәеҲҶгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- жҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖпјҲConstitutional Courtпјүпјҡжі•еҫӢгӮ„ж”ҝд»ӨгҒ®еҗҲжҶІжҖ§гӮ’еҲӨж–ӯгҒ—гҖҒжҶІжі•гҒ«йҒ•еҸҚгҒҷгӮӢжі•д»ӨгӮ„ж”ҝеәңгҒ®иЎҢзӮәгӮ’еҜ©жҹ»гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜ1997е№ҙжҶІжі•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеүөиЁӯгҒ•гӮҢгҖҒеҲӨжұәгҒҜе…ЁгҒҰгҒ®еӣҪ家ж©ҹй–ўгӮ’жӢҳжқҹгҒҷгӮӢеј·гҒ„жЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ2001е№ҙгҒ®гӮҝгӮҜгӮ·гғігғ»гӮ·гғҠгғҜгғғгғҲе…ғйҰ–зӣёгҒ®иіҮз”Јйҡ и”Ҫз–‘жғ‘гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲӨжұәгҒӘгҒ©гҖҒж”ҝжІ»зҡ„гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨеҲӨдҫӢгҒҢеӨҡж•°гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе№іе’Ңзҡ„гҒӘзҺӢе®Өж”№йқ©иҰҒжұӮгҒҢгҖҒжҶІжі•гҒ«еҸҚгҒҷгӮӢгҖҢз«ӢжҶІеҗӣдё»еҲ¶гҒ®и»ўиҰҶгҖҚгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹеҲӨдҫӢгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮВ
- иЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖпјҲAdministrative Courtпјүпјҡж”ҝеәңж©ҹй–ўгӮ„е…¬еӢҷе“ЎгҒЁж°‘й–“дјҒжҘӯгғ»еҖӢдәәгҒ®й–“гҒ®зҙӣдәүгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜж”ҝеәңж©ҹй–ўеҗҢеЈ«гҒ®зҙӣдәүгӮ’жүұгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®иЎҢж”ҝиЁҙиЁҹгҒ«дјјгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮҝгӮӨгҒ§гҒҜгҒ“гҒ®иЎҢж”ҝиЈҒеҲӨжүҖгҒҢзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹеҸёжі•зі»зөұгӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж…ўжҖ§и…ҺдёҚе…ЁжӮЈиҖ…гҒ®дәәе·ҘйҖҸжһҗеӣһж•°еҲ¶йҷҗгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҙиЁҹпјҲA.593/2560пјүгҒӘгҒ©гҖҒеӣҪж°‘гҒ®жЁ©еҲ©дҝқиӯ·гҒ«й–ўгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘеҲӨжұәгӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ
- и»ҚдәӢиЈҒеҲӨжүҖпјҲMilitary Courtпјүпјҡдё»гҒ«еӣҪи»ҚгҒ®и»ҚдәәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҲ‘дәӢдәӢ件гӮ’з®ЎиҪ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгӮҜгғјгғҮгӮҝгғјеҫҢгҒ®2014е№ҙгҒӢгӮү2016е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒҜгҖҒж°‘й–“дәәгҒ«гӮҲгӮӢдёҖйғЁгҒ®зҠҜзҪӘпјҲзҺӢе®ӨдёҚ敬зҪӘгҖҒеӣҪ家е®үе…Ёдҝқйҡңй–ўйҖЈзҠҜзҪӘгҒӘгҒ©пјүгӮӮи»ҚдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®з®ЎиҪ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮи»ҚдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒҜеӣҪйҳІзңҒгҒ®з®ЎиҪ„дёӢгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮжі•еҫӢгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ§гҒӮгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒи»ҚдәәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢзӮ№гҒҢж°‘й–“иЈҒеҲӨжүҖгҒЁеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйқһеёёдәӢж…ӢжҷӮгҒ«гҒҜгҖҒи»ҚдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒҢж”ҝжІ»зҡ„гҒӘзӣ®зҡ„гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢжҮёеҝөгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹеҸёжі•ж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҪ№еүІгҒҢеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҖҒдәәжЁ©дҫөе®ігҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒҢгӮҝгӮӨгҒ®ж”ҝжғ…дёҚе®үгӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒйҖҡеёёгҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒи»ҚдәӢиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еӢ•еҗ‘гҒ«гӮӮжіЁж„ҸгӮ’жү•гҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮВ
- еҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖпјҲCourts of JusticeпјүпјҡжңҖгӮӮеәғзҜ„гҒӘз®ЎиҪ„гӮ’жҢҒгҒЎгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘж°‘дәӢдәӢ件гҖҒеҲ‘дәӢдәӢ件гҖҒзЁҺеӢҷгҖҒеҠҙеғҚгҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈгҖҒйҖҡе•ҶгҖҒз ҙз”ЈгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЈҒеҲӨгӮ’жүұгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ第дёҖеҜ©иЈҒеҲӨжүҖгҖҒдёҠиЁҙиЈҒеҲӨжүҖгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®дёүеҜ©еҲ¶гҒҢжҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ
гӮҝгӮӨгҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«зӣҙзөҗгҒҷгӮӢе°Ӯй–ҖиЈҒеҲӨжүҖгҒ®и©ізҙ°и§ЈиӘ¬
ж—Ҙжң¬гҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒҢгӮҝгӮӨгҒ§гғ“гӮёгғҚгӮ№гӮ’еұ•й–ӢгҒҷгӮӢйҡӣгҖҒжңҖгӮӮй–ўгӮҸгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ®гҒҢгҖҒеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖеҶ…гҒ«иЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе°Ӯй–ҖиЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®е°Ӯй–ҖеҲҶйҮҺгҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹиЈҒеҲӨе®ҳгӮ„гҖҒе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгӮ’жҢҒгҒӨж°‘й–“дәәпјҲжә–иЈҒеҲӨе®ҳпјүгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒеҠ№зҺҮзҡ„гҒӢгҒӨе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘзҙӣдәүи§ЈжұәгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©еҸҠгҒіеӣҪйҡӣеҸ–еј•иЈҒеҲӨжүҖпјҲCIPITCпјү
зҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©еҸҠгҒіеӣҪйҡӣеҸ–еј•иЈҒеҲӨжүҖпјҲCentral Intellectual Property and International Trade Court, CIPITCпјүгҒҜгҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”Јжі•пјҲе•ҶжЁҷгҖҒи‘—дҪңжЁ©гҖҒзү№иЁұгҒӘгҒ©пјүгҒҠгӮҲгҒіеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘе•ҶеҸ–еј•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢж°‘дәӢгғ»еҲ‘дәӢдәӢ件гӮ’е°Ӯй–ҖгҒ«жүұгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгғҗгғігӮігӮҜгҒ«иЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзҸҫеңЁгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгҒқгҒ®з®ЎиҪ„гҒҜгӮҝгӮӨе…ЁеңҹгҒ«еҸҠгҒігҒҫгҒҷгҖӮ
CIPITCгҒҜгҖҒиҝ…йҖҹгҒӘзҙӣдәүи§ЈжұәгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰзү№еҲҘгҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒ2023е№ҙгҒ«ж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹж–°гҒ—гҒ„иҰҸеүҮгҒ§гҒҜгҖҒиЁјдәәе°Ӣе•ҸгҒ«гғҶгғ¬гғ“дјҡиӯ°гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮҝгӮӨиӘһгҒҢе…¬з”ЁиӘһгҒ§гҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒеҪ“дәӢиҖ…гҒ®еҗҲж„ҸгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°иӢұиӘһгҒ®иЁјжӢ жӣёйЎһгӮӮеҸ—зҗҶгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒ2023е№ҙ7жңҲ1ж—ҘгҒ«зҷәеҠ№гҒ—гҒҹж–°гҒ—гҒ„иҰҸеүҮгҒҜгҖҒиЁҙиЁҹй–ўйҖЈжӣёйЎһгҒ®йӣ»еӯҗйҖҒйҒ”гӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®иҝ‘д»ЈеҢ–гӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®зү№еҲҘгҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгҒҜгҖҒзү№гҒ«еӣҪйҡӣзҡ„гҒӘзҙӣдәүгӮ’еҝөй ӯгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮігғўгғігғ»гғӯгғјзҡ„гҒӘе®ҹеӢҷж…ЈиЎҢгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒгӮҝгӮӨгҒ®IPзҙӣдәүгҒҢд»–гҒ®ж°‘дәӢиЁҙиЁҹгӮҲгӮҠгӮӮиҝ…йҖҹгҒ«еҮҰзҗҶгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№дёҠгҒ®дёҚзўәе®ҹжҖ§гҒҢж—©жңҹгҒ«и§Јж¶ҲгҒ•гӮҢгҖҒжҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘж„ҸжҖқжұәе®ҡгӮ’иҝ…йҖҹгҒ«иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮВ
гӮҝгӮӨгҒ®CIPITCгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®еҲӨдҫӢжі•зҗҶгӮ’еҪўжҲҗгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘеҲӨжұәгӮ’еҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒВ 2020е№ҙ10жңҲ16ж—ҘгҒ«CIPITCгҒҢдёӢгҒ—гҒҹINVE AquacultureзӨҫгҒ®зү№иЁұдҫөе®іиЁҙиЁҹеҲӨжұәгҒҜгҖҒ1е„„600дёҮгӮҝгӮӨгғҗгғјгғ„пјҲзҙ„350дёҮзұігғүгғ«пјүгҒЁгҒ„гҒҶгӮҝгӮӨеҸІдёҠжңҖй«ҳйЎҚгҒ®жҗҚе®іиі е„ҹйЎҚгӮ’иӘҚгӮҒгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§жіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮҝгӮӨгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§зҹҘзҡ„иІЎз”Јдҫөе®ігҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҗҚе®іиі е„ҹйЎҚгҒҜжҜ”ијғзҡ„е°ҸйЎҚгҒ«з•ҷгҒҫгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒҜгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҒҢдҫөе®іиҖ…гҒ®иЎҢзӮәгӮ’еҺігҒ—гҒҸи©•дҫЎгҒ—гҖҒзү№иЁұжЁ©иҖ…гҒ®жҗҚе®ігӮ’еҚҒеҲҶгҒ«иЈңеЎ«гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘжҪ®жөҒгҒ«жІҝгҒЈгҒҹе§ҝеӢўгӮ’зӨәгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒд»ҠеҫҢгҒ®гӮҝгӮӨгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзҹҘзҡ„иІЎз”Јдҝқиӯ·иЁҙиЁҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒй«ҳйЎҚгҒӘжҗҚе®іиі е„ҹгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҜй«ҳгҒҫгҒЈгҒҹгҒЁиЁҖгҒҲгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒжЁЎеҖЈе“ҒеҜҫзӯ–гӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж—Ҙжң¬гҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒйқһеёёгҒ«еј·еҠӣгҒӘжӯҰеҷЁгҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮВ
еҠҙеғҚиЈҒеҲӨжүҖ
еҠҙеғҚиЈҒеҲӨжүҖпјҲLabour CourtпјүгҒҜгҖҒйӣҮз”ЁеҘ‘зҙ„гҖҒеҠҙеғҚзө„еҗҲгҖҒеҠҙзҒҪиЈңе„ҹгҒӘгҒ©гҖҒеҠҙеғҚй–ўдҝӮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҙӣдәүгӮ’е°Ӯй–ҖгҒ«жүұгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒгғҗгғігӮігӮҜгҒ®дёӯеӨ®еҠҙеғҚиЈҒеҲӨжүҖгҒЁең°ж–№гҒ®еҠҙеғҚиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҠҙеғҚиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘжі•еҫӢ家гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢе°Ӯй–ҖиЈҒеҲӨе®ҳгҖҚгҒЁгҖҒйӣҮз”ЁиҖ…гғ»еҠҙеғҚиҖ…еӣЈдҪ“гҒӢгӮүйҒёгҒ°гӮҢгҒҹгҖҢжә–иЈҒеҲӨе®ҳпјҲassociate judgeпјүгҖҚгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢжҲҗгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«жі•еҫӢгӮ’йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҠҙдҪҝеҸҢж–№гҒ®з«Ӣе ҙгӮ„жҘӯз•ҢгҒ®ж…Јзҝ’гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҹдёҠгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠзҸҫе®ҹзҡ„гҒӢгҒӨе…¬е№ігҒӘи§ЈжұәгӮ’е°ҺгҒ“гҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж„ҸеӣігӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжүӢз¶ҡгҒҚгҒҜжҜ”ијғзҡ„йқһе…¬ејҸгҒ§иҝ…йҖҹгҒӘи§ЈжұәгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҖҒе’Ңи§ЈгӮ„д»ІиЈҒгҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ–еӣҪдәәйӣҮз”ЁиҖ…гӮ’еҗ«гӮҖж—Ҙжң¬гҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгӮҝгӮӨгҒ®еҠҙеғҚзҙӣдәүгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҠҙеғҚеҜ©еҲӨеҲ¶еәҰгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒиҝ…йҖҹгҒӢгҒӨе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘеҜҫеҝңгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒҢж°‘й–“дәәгҒ®иҰ–зӮ№гӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҪўејҸзҡ„гҒӘжі•и§ЈйҮҲгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзҙӣдәүгҒ«иҮігҒЈгҒҹзөҢз·ҜгӮ„е®ҹж…ӢгҒҢгӮҲгӮҠйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮВ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гӮҝгӮӨгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁеӨҡгҒҸгҒ®е…ұйҖҡзӮ№гӮ’жҢҒгҒЎгҒӨгҒӨгӮӮгҖҒжӯҙеҸІзҡ„иғҢжҷҜгҒ«ж №е·®гҒ—гҒҹзӢ¬иҮӘгҒ®гҖҢж··еҗҲжі•гҖҚзҡ„жҖ§иіӘгҒЁгҖҒеӨҡеұӨзҡ„гҒӘиЈҒеҲӨжүҖгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©еҸҠгҒіеӣҪйҡӣеҸ–еј•иЈҒеҲӨжүҖгӮ„еҠҙеғҚиЈҒеҲӨжүҖгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе°Ӯй–ҖиЈҒеҲӨжүҖгҒ®еӯҳеңЁгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒҢгӮҝгӮӨгҒ§гғ“гӮёгғҚгӮ№гӮ’иЎҢгҒҶдёҠгҒ§дёҚеҸҜж¬ гҒӘзҗҶи§ЈдәӢй …гҒ§гҒҷгҖӮ
жңҖж–°гҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҖҒгӮҝгӮӨгҒ®еҸёжі•гҒҢзҹҘзҡ„иІЎз”Јдҝқиӯ·гӮ’еј·еҢ–гҒ—гҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘе®ҹеӢҷж…ЈиЎҢгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҳҺзўәгҒ«зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгғ“гӮёгғҚгӮ№дёҠгҒ®зҹҘзҡ„иІЎз”ЈгӮ’дҝқиӯ·гҒ—гҖҒзҙӣдәүгӮ’жңүеҲ©гҒ«и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж©ҹдјҡгҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еёёиӯҳгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢжі•зҡ„гҒӘеҸ–гӮҠжүұгҒ„гӮ„гҖҒзү№жңүгҒ®иЈҒеҲӨжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮдәӢе®ҹгҒ§гҒҷгҖӮгӮҝгӮӨгҒ§гҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒзҸҫең°гҒ®жі•зҡ„гғ»еҸёжі•зҡ„гҒӘзү№жҖ§гӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: гӮҝгӮӨзҺӢеӣҪжө·еӨ–дәӢжҘӯ