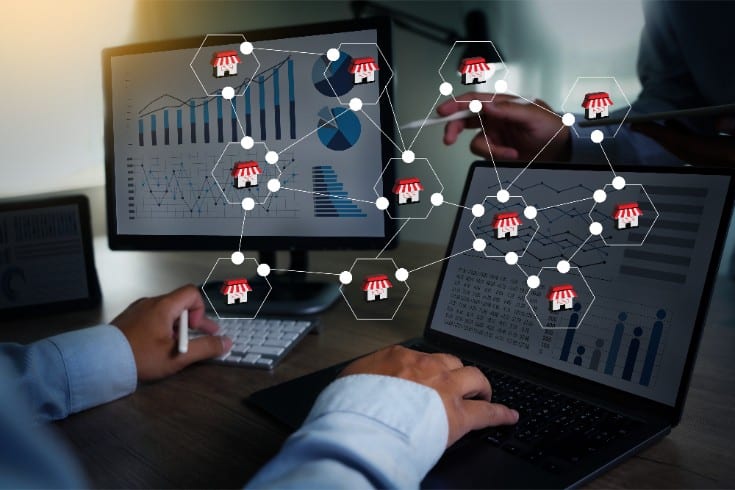مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ه…±ه’Œه›½مپ®ن¼ڑ社و³•مپŒه®ڑم‚پم‚‹ن¼ڑ社ه½¢و…‹مپ®è©³ç´°م‚’解èھ¬

مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ§مپ¯م€پن؛‹و¥مپ®è¦ڈو¨،م‚„و€§è³ھم€په‡؛資者مپ®و•°م‚„責ن»»ç¯„ه›²مپ«ه؟œمپکمپ¦م€پن¼ڑ社ه½¢و…‹مپ«ه¤ڑو§کمپھéپ¸وٹè‚¢مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®ن¼ڑ社و³•مپ¯م€پن¸»مپ«و°‘و³•ه…¸ï¼ˆCode civil)第1832و،ن»¥ن¸‹مپٹم‚ˆمپ³ه•†و³•ه…¸ï¼ˆCode de commerce)مپ«ه®ڑم‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پن؛‹و¥مپ®و³•çڑ„و 組مپ؟م‚’هژ³و ¼مپ«è¦ڈه®ڑمپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ن؛‹و¥ه½¢و…‹مپ¯م€په¤§مپچمپڈهˆ†مپ‘مپ¦م€پ経ه–¶è€…مپ¨ن؛‹و¥ن½“مپŒو³•çڑ„مپ«هگŒن¸€مپ§مپ‚م‚‹م€Œو³•ن؛؛و ¼م‚’وŒپمپںمپھمپ„ه€‹ن؛؛ن؛‹و¥ه½¢و…‹ï¼ˆEntreprise individuelle)م€چمپ¨م€پن؛‹و¥ن½“مپŒç‹¬ç«‹مپ—مپںو³•ن؛؛و ¼م‚’وŒپمپ¤م€Œن¼ڑ社ه½¢و…‹ï¼ˆSociأ©tأ©ï¼‰م€چمپ«هˆ†é،مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚
وœ¬è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€پوœ‰é™گ責ن»»ن¼ڑ社(SARLï¼ڑSociأ©tأ© أ Responsabilitأ© Limitأ©e)م€پهچکç´”ه‹و ھه¼ڈن¼ڑ社(SASï¼ڑSociأ©tأ© par Actions Simplifiأ©e)م€پو ھه¼ڈن¼ڑ社(SAï¼ڑSociأ©tأ© Anonyme)مپ¨مپ„مپ£مپںن¸»è¦پمپھه½¢و…‹مپ«هٹ مپˆم€پن¸€ن؛؛ن¼ڑ社م‚„ه€‹ن؛؛ن؛‹و¥ن¸»مپ®هˆ¶ه؛¦مپ¾مپ§م‚’網羅çڑ„مپ«è§£èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپھمپٹم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®هŒ…و‹¬çڑ„مپھو³•هˆ¶ه؛¦مپ®و¦‚è¦پمپ¯ن¸‹è¨کè¨کن؛‹مپ«مپ¦مپ¾مپ¨م‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ®è¨کن؛‹مپ®ç›®و¬،
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹و³•مپ«مپٹمپ‘م‚‹ن؛‹و¥ه½¢و…‹مپ®هں؛ç¤ژ
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®ن؛‹و¥ه½¢و…‹مپ«مپ¯م€پو³•ن؛؛ه½¢و…‹م‚’وŒپمپ¤م‚‚مپ®مپ¨وŒپمپںمپھمپ„م‚‚مپ®مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™مپŒم€پمپ•م‚‰مپ«م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹و³•مپ«مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®ن¼ڑ社و³•مپ«مپ¯مپھمپ„独特مپ®ن¼ڑ社هˆ†é،و¦‚ه؟µمپŒهکهœ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚مپم‚Œمپ¯م€پن؛؛çڑ„ن¼ڑ社(Sociأ©tأ©s de personnes)م€پ資وœ¬ن¼ڑ社(Sociأ©tأ©s de capitaux)م€پمپمپ—مپ¦مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه‹ن¼ڑ社(Sociأ©tأ©s hybrides)مپ®3مپ¤مپ§مپ™م€‚
- ن؛؛çڑ„ن¼ڑ社ï¼ڑه‡؛資者間مپ®ه€‹ن؛؛çڑ„مپھن؟،é ¼é–¢ن؟‚(intuitu personae)م‚’é‡چ視مپ™م‚‹ه½¢و…‹مپ§مپ™م€‚ه‡؛資者مپ®è²¬ن»»مپ¯ç„،é™گمپ¨مپھم‚‹مپ“مپ¨مپŒهژںه‰‡مپ§م€پو ھه¼ڈمپ®è²و¸،مپ¯هژ³مپ—مپڈهˆ¶é™گمپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚
- 資وœ¬ن¼ڑ社ï¼ڑ資وœ¬مپ®é›†ç©چم‚’ç›®çڑ„مپ¨مپ™م‚‹ه½¢و…‹مپ§مپ™م€‚ه‡؛資者مپ®è²¬ن»»مپ¯وœ‰é™گمپ§مپ‚م‚ٹم€پو ھه¼ڈمپ®è²و¸،مپ¯و¯”較çڑ„è‡ھç”±مپ§م€په‡؛資者間مپ®ه€‹ن؛؛çڑ„مپھé–¢ن؟‚مپ¯é‡چ視مپ•م‚Œمپ¾مپ›م‚“م€‚
- مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه‹ن¼ڑ社ï¼ڑن¸ٹè¨کن؛Œمپ¤مپ®ç‰¹ه¾´م‚’ن½µمپ›وŒپمپ¤ه½¢و…‹مپ§م€پوœ‰é™گ責ن»»مپ®هژںه‰‡م‚’ن؟مپ،مپ¤مپ¤م‚‚م€په‡؛資者間مپ®ن؟،é ¼é–¢ن؟‚م‚’ن؟è·مپ™م‚‹مپںم‚پم€پو ھه¼ڈمپ®è²و¸،مپ«هژ³و ¼مپھهˆ¶é™گمپŒèھ²مپ›م‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚SARLمپŒمپمپ®ن»£è،¨ن¾‹مپ§مپ™م€‚
مپ“مپ®ç‹¬ç‰¹مپھهˆ†é،مپ¯م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®ن¼ڑ社و³•مپŒم€په‡؛資者مپ®é–“مپ®ن؛؛é–“é–¢ن؟‚مپ¨è³‡وœ¬مپ®è«–çگ†م‚’èھ؟ه’Œمپ•مپ›م‚ˆمپ†مپ¨مپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ†م€پو—¥وœ¬مپ¨مپ¯ç•°مپھم‚‹و€وƒ³مپ«هں؛مپ¥مپ„مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپ«م‚ˆم‚‹م‚‚مپ®مپ مپ¨è¨€مپˆم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پSARLمپ¯وœ‰é™گ責ن»»مپ§مپ‚م‚‹مپ«م‚‚مپ‹مپ‹م‚ڈم‚‰مپڑم€پمپمپ®مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰و€§مپ‹م‚‰intuitu personaeمپŒه¼·مپڈهƒچمپچم€پو ھه¼ڈè²و¸،مپ«هˆ¶é™گمپŒمپ‹مپ‹م‚‹مپ“مپ¨مپ¯م€پ資وœ¬مپ®é›†ç©چم‚’é‡چ視مپ™م‚‹SASم‚„SAمپ¨و ¹وœ¬çڑ„مپ«ç•°مپھم‚‹ç‰¹ه¾´مپ§مپ™م€‚و—¥وœ¬مپ®ن¼ڑ社و³•مپŒم€Œو ھه¼ڈن¼ڑ社م€چمپ¨م€ŒهگˆهگŒن¼ڑ社م€چم‚’ن¸»مپ«è³‡وœ¬مپ®ه¤ڑه¯،م‚„è¨ç«‹مپ®ç°،ن¾؟و€§مپ§هŒ؛هˆ¥مپ™م‚‹مپ®مپ«ه¯¾مپ—م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ§مپ¯م€Œèھ°مپ¨çµ„م‚€مپ‹م€چمپ¨مپ„مپ†ن؛؛é–“é–¢ن؟‚مپ®è³ھمپŒو³•هˆ¶ه؛¦مپ®éپ¸وٹمپ«و·±مپڈه½±éں؟مپ™م‚‹و§‹é€ مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپŒن¼؛مپˆمپ¾مپ™م€‚
ه®ڑو¬¾م‚’è‡ھç”±è¨è¨ˆمپ§مپچم‚‹مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®هچکç´”ه‹و ھه¼ڈن¼ڑ社(SAS)

SASمپ¯م€په•†و³•ه…¸ï¼ˆCode de commerce)第L.227-1و،ن»¥ن¸‹مپ«è¦ڈه®ڑمپ•م‚Œم‚‹وœ‰é™گ責ن»»مپ®ن¼ڑ社ه½¢و…‹مپ§مپ™م€‚مپمپ®وœ€م‚‚ه¤§مپچمپھ特ه¾´مپ¯م€پم€Œه®ڑو¬¾مپ®è‡ھç”±ه؛¦ï¼ˆlibertأ© statutaire)م€چمپ«مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پè¨ç«‹è€…مپ¯ن¼ڑ社éپ‹ه–¶م‚„و ھه¼ڈè²و¸،مپ«é–¢مپ™م‚‹مƒ«مƒ¼مƒ«م‚’م€پو³•ن»¤مپ®ç¯„ه›²ه†…مپ§è‡ھç”±مپ«è¨è¨ˆمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®وں”è»ںو€§مپ‹م‚‰م€پم‚¹م‚؟مƒ¼مƒˆم‚¢مƒƒمƒ—م‚„مƒ™مƒ³مƒپمƒ£مƒ¼م‚مƒ£مƒ”م‚؟مƒ«مپ‹م‚‰مپ®è³‡é‡‘èھ؟éپ”م‚’ه؟—هگ‘مپ™م‚‹ن¼پو¥مپ«éه¸¸مپ«ن؛؛و°—مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹مپ¨çµŒه–¶é™£مپ®ه½¹ه‰²
SASمپ§مپ¯م€پPrأ©sident(社長)مپ®ن»»ه‘½مپŒç¾©ه‹™ن»کمپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®Prأ©sidentمپ¯م€په€‹ن؛؛مپ مپ‘مپ§مپھمپڈو³•ن؛؛م‚‚ه‹™م‚پم‚‹مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ§مپ™م€‚و—¥وœ¬مپ®و ھه¼ڈن¼ڑ社مپ«مپٹمپ„مپ¦م€پهڈ–ç· ه½¹ن¼ڑè¨ç½®ن¼ڑ社مپ¯هڈ–ç· ه½¹3هگچن»¥ن¸ٹمپŒه؟…é ˆمپ§مپ‚م‚‹مپ®مپ«ه¯¾مپ—م€پSASمپ¯Conseil d’administration(هڈ–ç· ه½¹ن¼ڑ)مپھمپ©مپ®و©ںé–¢è¨ç½®مپŒن»»و„ڈمپ§مپ‚م‚ٹم€په®ڑو¬¾مپ§è‡ھç”±مپ«ه®ڑم‚پم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹مپںم‚پم€پ1هگچمپ§م‚‚وں”è»ںمپھم‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹م‚’و§‹ç¯‰مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ®وں”è»ںو€§مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®م‚¹م‚؟مƒ¼مƒˆم‚¢مƒƒمƒ—مپŒو±‚م‚پم‚‹م€Œم‚¹مƒ”مƒ¼مƒ‰و„ںم€چمپ¨م€Œè‡ھç”±مپھ資وœ¬و”؟ç–م€چمپ¨é«کمپ„è¦ھه’Œو€§م‚’وŒپمپ¤مپ¨è¨€مپˆمپ¾مپ™م€‚特مپ«م€په®ڑو¬¾مپ®è‡ھç”±ه؛¦مپ¯م€پ経ه–¶è€…مپ¨ه‡؛資者間مپ§هگˆو„ڈمپ—مپںمƒ«مƒ¼مƒ«م‚’詳細مپ«هڈچوک مپ§مپچم‚‹مپںم‚پم€پو—¥وœ¬مپ®و ھن¸»é–“ه¥‘約(pactes d’actionnaires)مپ®ه†…ه®¹م‚’م€پم‚ˆم‚ٹو³•çڑ„مپ«و‹کوںهٹ›مپ®مپ‚م‚‹ه®ڑو¬¾مپمپ®م‚‚مپ®مپ«çµ„مپ؟è¾¼م‚پم‚‹مپ“مپ¨م‚’و„ڈه‘³مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پن؛ˆوœںمپ›مپ¬مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«م‚’وœھ然مپ«éک²مپگمپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
経ه–¶é™£مپ®è§£ن»»مپ¨وœ€و–°هˆ¤ن¾‹
SASمپ®çµŒه–¶é™£مپ®è§£ن»»مƒ«مƒ¼مƒ«مپ¯م€پو³•ه¾‹مپ«وکژè¨کمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ„مپںم‚پم€په®ڑو¬¾مپ®ه®ڑم‚پمپ«ن¾و‹ مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®ç‚¹مپ«é–¢مپ—مپ¦م€په®ڑو¬¾مپ®è‡ھç”±ه؛¦م‚’è£ڈن»کمپ‘م‚‹é‡چè¦پمپھهˆ¤ن¾‹مپŒهکهœ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ç ´و¯€é™¢ه•†ن؛‹éƒ¨ï¼ˆCour de cassation, Chambre commerciale)مپ¯م€پ2022ه¹´3وœˆ9و—¥مپ®هˆ¤و±؛(nآ°19-25.795, Hubbardن؛‹ن»¶ï¼‰مپ«مپٹمپ„مپ¦م€په®ڑو¬¾مپ«م€Œو£ه½“مپھçگ†ç”±ï¼ˆjuste motif)م€چم‚’è¦پمپ™م‚‹و—¨مپ®è¦ڈه®ڑمپŒمپھمپ„é™گم‚ٹم€پSASمپ®çµŒه–¶è€…م‚’çگ†ç”±مپھمپڈمپ„مپ¤مپ§م‚‚解ن»»مپ§مپچم‚‹ï¼ˆrأ©vocation ad nutum)مپ“مپ¨م‚’èھچم‚پمپ¾مپ—مپںم€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پSASمپ®ه®ڑو¬¾مپ§çµŒه–¶é™£مپ®و”¯é…چهٹ›م‚’هˆ¶é™گمپ™م‚‹و،é …م‚’è¨مپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپŒم€پو³•çڑ„مپ«وœ‰هٹ¹مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپŒç¤؛مپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚
集ه›£çڑ„و±؛ه®ڑمپ¨وœ€و–°هˆ¤ن¾‹
ن¸€و–¹مپ§م€پSASمپ®ه®ڑو¬¾مپ®è‡ھç”±ه؛¦مپ«مپ¯çµ¶ه¯¾çڑ„مپھé™گç•ŒمپŒهکهœ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ç ´و¯€é™¢ç·ڈن¼ڑ(Cour de cassation, Assemblأ©e plأ©niأ¨re)مپ¯م€پ2024ه¹´11وœˆ15و—¥مپ®هˆ¤و±؛(nآ°23-16.670)مپ«مپٹمپ„مپ¦م€پSASمپ®ه®ڑو¬¾مپ®è‡ھç”±ه؛¦مپ«مپ¯é™گç•ŒمپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†é‡چè¦پمپھهˆ¤ن¾‹م‚’ç¤؛مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚مپ“مپ®هˆ¤و±؛مپ¯م€پéپژهچٹو•°مپ«و؛€مپںمپھمپ„è°و±؛و¨©مپ§é›†ه›£çڑ„و±؛ه®ڑم‚’وœ‰هٹ¹مپ¨مپ™م‚‹ه®ڑو¬¾و،é …مپ¯ç„،هٹ¹مپ§مپ‚م‚ٹم€پم€Œو›¸مپ‹م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ‹مپ£مپںم‚‚مپ®ï¼ˆrأ©putأ©e non أ©crite)م€چمپ¨مپ؟مپھمپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚’هˆ¤ç¤؛مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚集ه›£çڑ„و±؛ه®ڑمپ«مپ¯م€پمپمپ®وœ¬è³ھمپ¨مپ—مپ¦م€پè³›وˆگ票مپŒهڈچه¯¾ç¥¨م‚’ن¸ٹه›م‚‹ه¤ڑو•°و±؛هژںه‰‡مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ‚م‚‹مپ¨هˆ¤و–مپ•م‚Œمپںمپ®مپ§مپ™م€‚
مپ“مپ®هˆ¤ن¾‹مپ¯م€پمپ©م‚“مپھمپ«ه®ڑو¬¾مپ«è‡ھç”±مپھمƒ«مƒ¼مƒ«م‚’و›¸مپ„مپ¦م‚‚م€پهں؛وœ¬çڑ„مپھم€Œه¤ڑو•°و±؛م€چمپ®هژںه‰‡مپ¯è¶…مپˆم‚‰م‚Œمپھمپ„مپ“مپ¨م‚’وکژç¢؛مپ«مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚مپ“مپ®مپ“مپ¨مپ¯م€په®ڑو¬¾مپŒو³•çڑ„و‹کوںهٹ›م‚’وŒپمپ¤مپ¨مپ¯مپ„مپˆم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹و³•ه…¨ن½“مپ®و³•çڑ„هژںه‰‡مپ‹م‚‰مپ¯é€¸è„±مپ§مپچمپھمپ„مپ“مپ¨م‚’و„ڈه‘³مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ†مپ—مپںé™گç•Œمپ®ن¸‹مپ«م€Œه®ڑو¬¾مپ®è‡ھç”±م€چمپŒمپ‚م‚‹مپŒو•…مپ«م€په°‚é–€ه®¶مپ¨é€£وگ؛مپ—مپ¦م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹و³•مپŒè¨±ه®¹مپ™م‚‹ç¯„ه›²ه†…مپ§وœ€م‚‚è‡ھ社مپ«éپ©مپ—مپںه®ڑو¬¾م‚’ç–ه®ڑمپ™م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپŒè¨€مپˆم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
ن¸ه°ڈن¼پو¥هگ‘مپ‘مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®وœ‰é™گ責ن»»ن¼ڑ社(SARL)
SARLمپ¯م€په•†و³•ه…¸ï¼ˆCode de commerce)第L.223-1و،ن»¥ن¸‹مپ«è¦ڈه®ڑمپ•م‚Œم‚‹ن¼ڑ社ه½¢و…‹مپ§مپ™م€‚SASمپ»مپ©مپ®وں”è»ںو€§مپ¯مپھمپ„م‚‚مپ®مپ®م€پمپمپ®و³•çڑ„و 組مپ؟مپŒوکژç¢؛مپ«ه®ڑم‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپںم‚پم€په®‰ه®ڑو€§مپŒé«کمپڈم€پ特مپ«ن¸ه°ڈن¼پو¥م‚„ه®¶و—ڈ経ه–¶مپ«éپ©مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
و—¥وœ¬مپ®هگˆهگŒن¼ڑ社مƒ»وœ‰é™گن¼ڑ社مپ¨مپ®و¯”較
SARLمپ¯م€پوœ‰é™گ責ن»»مپ§مپ‚م‚ٹم€پè¨ç«‹è²»ç”¨مپŒو¯”較çڑ„ه®‰ن¾،مپ§مپ‚م‚‹ç‚¹مپ§و—¥وœ¬مپ®هگˆهگŒن¼ڑ社مپ¨é،ن¼¼مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پSARLمپ¯è¨ç«‹ن؛؛و•°مپ«هˆ¶é™گ(2هگچمپ‹م‚‰100هگچمپ¾مپ§ï¼‰مپŒمپ‚م‚ٹم€په®ڑو¬¾مپ®è‡ھç”±ه؛¦مپŒSASمپ»مپ©é«کمپڈمپھمپ„مپںم‚پم€پم‚ˆم‚ٹو³•ن»¤مپ®ه®ڑم‚پمپ«ه¾“مپ†ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پè¨ç«‹è€…مپ®ه€‹ن؛؛çڑ„é–¢ن؟‚مپŒé‡چ視مپ•م‚Œم‚‹هگˆهگŒن¼ڑ社م‚ˆم‚ٹم‚‚م€پمپ•م‚‰مپ«هژ³و ¼مپھو³•è¦ڈ範م‚’وŒپمپ¤ه½¢و…‹مپ¨è€ƒمپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
مپ¾مپںم€پ1925ه¹´مپ«مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ§SARLمپŒه‰µè¨مپ•م‚Œمپں背و™¯مپ«مپ¯م€پمƒ‰م‚¤مƒ„مپ®GmbHهˆ¶ه؛¦مپ®ه½±éں؟مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®و—§وœ‰é™گن¼ڑ社(Yugen-Kaisha)مپŒمƒ‰م‚¤مƒ„مپ®GmbHم‚’مƒ¢مƒ‡مƒ«مپ¨مپ—مپ¦مپ„مپںو´هڈ²مپ¨ç¬¦هڈ·مپ—مپ¾مپ™م€‚SARLمپ¯م€پمپ‹مپ¤مپ¦مپ®و—¥وœ¬مپ®وœ‰é™گن¼ڑ社مپ«و³•çڑ„مپھهژ³و ¼مپ•م‚„è¦ڈو¨،مپ®ن¸ٹé™گ(100هگچ)مپŒهٹ م‚ڈمپ£مپںم‚‚مپ®مپ¨وچ‰مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
م‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹مپ¨çµŒه–¶é™£مپ®è²¬ن»»
SARLمپ¯1ن؛؛ن»¥ن¸ٹمپ®Gأ©rant(و”¯é…چن؛؛)مپ«م‚ˆمپ£مپ¦çµŒه–¶مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚Gأ©rantمپ¯ه؟…مپڑه€‹ن؛؛مپ§مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚‰مپڑم€پن¼ڑ社مپ®ه®ڑو¬¾م‚„هˆ¥é€”مپ®و±؛ه®ڑمپ«م‚ˆمپ£مپ¦ن»»ه‘½مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚SARLمپ®هژ³و ¼مپھو³•çڑ„و 組مپ؟مپ¯م€پ経ه–¶è€…مپ®è²¬ن»»مپ®ç¯„ه›²مپ¨è؟½هڈٹو–¹و³•م‚’وکژç¢؛هŒ–مپ™م‚‹هˆ¤ن¾‹مپ«م‚ˆمپ£مپ¦مپ•م‚‰مپ«ه®‰ه®ڑو€§م‚’é«کم‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
経ه–¶è€…مپ®è²¬ن»»è؟½هڈٹمپ®é‡چ複ï¼ڑمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ç ´و¯€é™¢ه•†ن؛‹éƒ¨ï¼ˆCass. com.)مپ¯م€پ2024ه¹´12وœˆ18و—¥مپ®هˆ¤و±؛(nآ°22-21.487)مپ§م€پSARLمپ®çµŒه–¶è€…مپ«ه¯¾مپ™م‚‹è²¬ن»»è؟½هڈٹمپ¯م€پو³•ن»¤éپ•هڈچمپ«م‚ˆم‚‹è²¬ن»»مپ¨م€پن¸چéپ©هˆ‡مپھ経ه–¶ï¼ˆfaute de gestion)مپ«م‚ˆم‚‹è²¬ن»»م‚’م€پهگŒن¸€مپ®è،Œç‚؛مپ«مپ¤مپ„مپ¦é‡چمپمپ¦è؟½هڈٹمپ§مپچم‚‹مپ“مپ¨م‚’وکژç¢؛هŒ–مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پن¸چéپ©هˆ‡مپھ経ه–¶مپ«ه¯¾مپ™م‚‹è²¬ن»»è؟½هڈٹمپ®هڈ¯èƒ½و€§مپŒه؛ƒمپŒمپ£مپںمپ¨è¨€مپˆمپ¾مپ™م€‚آ
複و•°و”¯é…چن؛؛مپ®ه€‹هˆ¥è²¬ن»»ï¼ڑمپ¾مپںم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ç ´و¯€é™¢ه•†ن؛‹éƒ¨ï¼ˆCass. com.)مپ¯م€پ2023ه¹´1وœˆ25و—¥مپ®هˆ¤و±؛(nآ°21-15.772)مپ§م€پ複و•°مپ®Gأ©rantمپŒهکهœ¨مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ§م‚‚م€پن¸چéپ©هˆ‡مپھè،Œç‚؛م‚’è،Œمپ£مپں特ه®ڑمپ®Gأ©rantمپ®مپ؟مپ«ه¯¾مپ—مپ¦è²¬ن»»è؟½هڈٹم‚’è،Œمپ†مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ§مپ‚م‚ٹم€په…¨ه“،م‚’訴مپˆم‚‹ه؟…è¦پمپ¯مپھمپ„مپ¨هˆ¤و–مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
SARLمپ®هژ³و ¼مپھو³•çڑ„و 組مپ؟مپ¯م€پن؛ˆè¦‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒé«کمپڈم€پ特مپ«و—¥وœ¬ن¼پو¥مپ®ه¤ڑمپڈمپŒو…£م‚Œè¦ھمپ—م‚“مپ م€پمƒ«مƒ¼مƒ«مپ«هں؛مپ¥مپڈ経ه–¶مپ«ه®‰ه؟ƒو„ںم‚’ه¾—م‚‰م‚Œم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پمپمپ®هڈچé¢م€پè؟…é€ںمپھو„ڈو€و±؛ه®ڑم‚„資وœ¬و”؟ç–مپ®وں”è»ںو€§مپ¯هˆ¶é™گمپ•م‚Œم‚‹مپںم‚پم€پن؛‹و¥مپ®ه°†و¥çڑ„مپھو‹،ه¤§م‚„ه¤–部مپ‹م‚‰مپ®ه¤§è¦ڈو¨،مپھ資金èھ؟éپ”م‚’وœ€هˆمپ‹م‚‰è¦‹وچ®مپˆمپ¦مپ„م‚‹ه ´هگˆمپ¯م€پو…ژé‡چمپھو¤œè¨ژمپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚SARLمپ®هژ³و ¼مپھو³•çڑ„ه®‰ه®ڑو€§مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®ه¤ڑمپڈمپ®ن¼پو¥و–‡هŒ–مپ«هگˆè‡´مپ™م‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
ه¤§è¦ڈو¨،ن؛‹و¥هگ‘مپ‘مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®و ھه¼ڈن¼ڑ社(SA)
SAمپ¯م€په•†و³•ه…¸ï¼ˆCode de commerce)第L.225-1و،ن»¥ن¸‹مپ«è¦ڈه®ڑمپ•م‚Œم‚‹م€په¤§è¦ڈو¨،مپھن؛‹و¥م‚„و ھه¼ڈه…¬é–‹م‚’ç›®وŒ‡مپ™ن¼پو¥هگ‘مپ‘مپ®ه½¢و…‹مپ§مپ™م€‚و—¥وœ¬مپ®و ھه¼ڈن¼ڑ社مپ¨وœ€م‚‚è؟‘مپ„ه½¢و…‹مپ§مپ™مپŒم€پو—¥وœ¬مپ®هˆ¶ه؛¦م‚ˆم‚ٹè¦پن»¶مپŒهژ³و ¼مپ§مپ™م€‚
è¨ç«‹è¦پن»¶مپ¨م‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹
SAمپ®è¨ç«‹مپ«مپ¯م€پوœ€ن½ژ2هگچمپ®ه‡؛資者(و ھن¸»ï¼‰مپŒه؟…è¦پمپ§مپ‚م‚ٹم€پو ھه¼ڈمپŒه…¬é–‹مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ه ´هگˆمپ¯وœ€ن½ژ7هگچمپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯و—¥وœ¬مپ®و ھه¼ڈن¼ڑ社مپŒوœ€ن½ژ1هگچمپ‹م‚‰è¨ç«‹مپ§مپچم‚‹ç‚¹مپ¨ه¤§مپچمپڈç•°مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ•م‚‰مپ«م€پوœ€ن½ژ資وœ¬é‡‘مپŒ37,000مƒ¦مƒ¼مƒمپ¨ç¾©ه‹™ن»کمپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ç‚¹م‚‚م€پو—¥وœ¬مپ®و ھه¼ڈن¼ڑ社مپŒوœ€ن½ژ1ه††مپ‹م‚‰è¨ç«‹مپ§مپچم‚‹ç‚¹مپ¨ه¤§مپچمپڈç•°مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پم‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹و§‹é€ مپ¨مپ—مپ¦م€پConseil d’administration(هڈ–ç· ه½¹ن¼ڑ)م‚’è¨ç½®مپ™م‚‹ن¸€ه…ƒه‹مپ¨م€پDirectoire(هں·è،Œه½¹ن¼ڑ)مپ¨Conseil de surveillance(監وں»ه½¹ن¼ڑ)م‚’è¨ç½®مپ™م‚‹ن؛Œه…ƒه‹مپ®2種é،مپŒو³•ه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پمپ„مپڑم‚Œم‚‚هژ³و ¼مپھ監وں»ه½¹ï¼ˆCommissaire aux comptes)مپ®ن»»ه‘½مپŒç¾©ه‹™ن»کمپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
SAمپ®هژ³و ¼مپھè¨ç«‹مƒ»م‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹è¦پن»¶مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®èھ者مپ«مپ¨مپ£مپ¦م€پSASم‚„SARLمپ¨مپ®و¯”較مپ«مپٹمپ„مپ¦م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œه…¬ه…±و€§م€چم‚„م€Œç¤¾ن¼ڑçڑ„ن؟،é ¼م€چمپ®و¦‚ه؟µمپŒم€پن¼ڑ社ه½¢و…‹مپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«هڈچوک مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’çگ†è§£مپ™م‚‹ن¸ٹمپ§é‡چè¦پمپ§مپ™م€‚ه¤ڑé،چمپ®وœ€ن½ژ資وœ¬é‡‘م‚„هژ³و ¼مپھن؛Œه…ƒه‹م‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹مپ®éپ¸وٹè‚¢مپ¯م€پSAمپŒç¤¾ن¼ڑمپ«ه¯¾مپ™م‚‹è²¬ن»»م‚’è² مپ†م€Œه…¬ه…±مپ®هکهœ¨م€چمپ¨مپ—مپ¦ن½چç½®مپ¥مپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç¤؛ه”†مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®مپ“مپ¨مپ‹م‚‰م€پو—¥وœ¬مپ®èھ者مپ¯م€پن؛‹و¥è¦ڈو¨،مپŒه°ڈمپ•مپ„و®µéڑژمپ§SAم‚’éپ¸وٹمپ™م‚‹ه®ںه‹™çڑ„مپھمƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¯مپ»مپ¨م‚“مپ©مپھمپڈم€پم‚€مپ—م‚چSAمپŒمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®ن¼ڑ社و³•ن½“ç³»مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œوœ€çµ‚ه½¢و…‹م€چمپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨م‚’çگ†è§£مپ™م‚‹مپ¹مپچمپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
هچک独ه‰µو¥è€…هگ‘مپ‘مپ®EURLمپ¨SASU
EURLمپ¯SARLمپ®ن¸€ن؛؛ن¼ڑ社版م€پSASUمپ¯SASمپ®ن¸€ن؛؛ن¼ڑ社版مپ§مپ‚م‚ٹم€پمپ©مپ،م‚‰م‚‚هچک独مپ§ن؛‹و¥م‚’é–‹ه§‹مپ™م‚‹éڑ›مپ«éپ¸وٹمپ§مپچم‚‹وœ‰é™گ責ن»»مپ®ن¼ڑ社ه½¢و…‹مپ§مپ™م€‚و—¥وœ¬مپ®ن¼ڑ社و³•مپ§م‚‚ن¸€ن؛؛و ھه¼ڈن¼ڑ社م‚„ن¸€ن؛؛هگˆهگŒن¼ڑ社مپŒèھچم‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™مپŒم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ§مپ¯مپم‚Œمپم‚ŒمپŒوکژç¢؛مپھو³•çڑ„ه½¢و…‹مپ¨مپ—مپ¦è¦ڈه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
EURLمپ¨SASUمپ®وœ€م‚‚é‡چè¦پمپھéپ•مپ„مپ¯م€پ経ه–¶è€…ه€‹ن؛؛مپ®ç¤¾ن¼ڑن؟éڑœهˆ¶ه؛¦مپ«مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®ن¸€ن؛؛و ھه¼ڈن¼ڑ社م‚„ن¸€ن؛؛هگˆهگŒن¼ڑ社مپ®çµŒه–¶è€…مپŒç¤¾ن¼ڑن؟é™؛مپ¸مپ®هٹ ه…¥ç¾©ه‹™م‚’è² مپ†ï¼ˆه½¹ه“،ه ±é…¬م‚¼مƒمپ®ه ´هگˆم‚’除مپڈ)点مپ¨ç•°مپھم‚‹م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹ç‹¬è‡ھمپ®é‡چè¦پمپھéپ¸وٹè‚¢مپ§مپ™م€‚
| EURL | SASU | |
|---|---|---|
| هژںه‰‡çڑ„مپھç¨ژهˆ¶ | و‰€ه¾—ç¨ژ(IR) | و³•ن؛؛ç¨ژ(IS) |
| 社ن¼ڑن؟éڑœهˆ¶ه؛¦ | é被用者(Travailleur non salariأ©ï¼‰ | 被用者مپ¨مپ؟مپھمپ•م‚Œم‚‹è€…(Assimilأ©-salariأ©ï¼‰ |
| 社ن¼ڑن؟é™؛و–™çژ‡ | و¯”較çڑ„ن½ژمپ„(هڈژه…¥مپ®ç´„30%م€œ45%) | é«کمپ„(給ن¸ژمپ®ç´„64%) |
| 給ن¸ژم‚¼مƒو™‚مپ®ç¾©ه‹™ | وœ€ن½ژé™گمپ®ن؟é™؛و–™و”¯و‰•مپ„義ه‹™مپŒç™؛ç”ں | ن؟é™؛و–™مپ¯ç™؛ç”ںمپ—مپھمپ„ |
| 補ه„ںه†…ه®¹ | 補ه„ںمپ¯é™گه®ڑçڑ„(ه¤±و¥و‰‹ه½“مƒ»هٹ´çپ½ن؟é™؛مپھمپ—) | و—¥وœ¬مپ®م‚µمƒ©مƒھمƒ¼مƒمƒ³مپ«è؟‘مپ„و‰‹هژڑمپ„補ه„ں |
EURLمپ¨SASUمپ¯م€پمپم‚Œمپم‚Œم€Œن½ژمپ„م‚³م‚¹مƒˆمƒ»ن½ژمپ„ن؟éڑœم€چمپ¨م€Œé«کمپ„م‚³م‚¹مƒˆمƒ»é«کمپ„ن؟éڑœم€چمپ¨مپ„مپ†وکژç¢؛مپھمƒˆمƒ¬مƒ¼مƒ‰م‚ھمƒ•م‚’وڈگن¾›مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®éپ¸وٹمپ¯م€په€‹ن؛؛مپ®ç”ںو´»è¨è¨ˆم‚„مƒھم‚¹م‚¯è¨±ه®¹ه؛¦مپ«ç›´çµگمپ™م‚‹مپںم‚پم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ§مپ®èµ·و¥م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹و—¥وœ¬ن؛؛مپ«مپ¨مپ£مپ¦م€پé‡چè¦پمپھو¤œè¨ژمƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ§مپ‚م‚‹مپ¨è¨€مپˆم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
و³•ن؛؛و ¼م‚’وŒپمپںمپھمپ„مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®ه€‹ن؛؛ن؛‹و¥ه½¢و…‹
EI(Entreprise Individuelle)مپ¯م€پو³•ن؛؛و ¼م‚’وŒپمپںمپھمپ„ه€‹ن؛؛ن؛‹و¥ه½¢و…‹مپ§مپ‚م‚ٹم€پMicro-entrepriseمپ¯م€پمپمپ®EIمپ®مپ†مپ،م€پ特ه®ڑمپ®ç¨ژهˆ¶مƒ»ç¤¾ن¼ڑن؟éڑœهˆ¶ه؛¦م‚’éپ¸وٹمپ—مپںم‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚و—¥وœ¬مپ®ه€‹ن؛؛ن؛‹و¥ن¸»مپ«ç›¸ه½“مپ—مپ¾مپ™مپŒم€پهˆ¶ه؛¦مپ®ن»•çµ„مپ؟مپ«ه¤§مپچمپھéپ•مپ„مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
責ن»»مپ¨ه€‹ن؛؛資産مپ®ن؟è·
EIمپ¯هژںه‰‡مپ¨مپ—مپ¦ç„،é™گ責ن»»مپ§مپ—مپںمپŒم€پ2022ه¹´مپ®و³•و”¹و£مپ«م‚ˆم‚ٹم€پèµ·و¥ه®¶مپ®ه€‹ن؛؛資産مپ¨ن؛‹و¥è³‡ç”£مپŒهˆ†é›¢مپ•م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ—مپںم€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پن؛‹و¥ن¸ٹمپ®ه‚µه‹™مپ¯ن؛‹و¥è³‡ç”£مپ«é™گه®ڑمپ•م‚Œم€په€‹ن؛؛مپ®ن½ڈه±…مپھمپ©مپ¯ن؟è·مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚
ç°،ç´ هŒ–مپ•م‚Œمپںç¨ژهˆ¶مپ¨ç¤¾ن¼ڑن؟éڑœهˆ¶ه؛¦
Micro-entrepriseهˆ¶ه؛¦مپ§مپ¯م€پç¨ژ金مپ¨ç¤¾ن¼ڑن؟é™؛و–™مپ®è¨ˆç®—مپŒéه¸¸مپ«ç°،ç´ هŒ–مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚èھ²ç¨ژو‰€ه¾—مپ¯م€په£²ن¸ٹé«کمپ‹م‚‰ن؛‹و¥ه†…ه®¹مپ«ه؟œمپکمپںم€Œمپ؟مپھمپ—経費وژ§é™¤ï¼ˆabattement forfaitaire)م€چم‚’ه·®مپ—ه¼•مپ„مپ¦ç®—ه‡؛مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پ物販مپ®ه ´هگˆمپ¯ه£²ن¸ٹمپ®71%م€پم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹و¥مپ®ه ´هگˆمپ¯34%مپŒوژ§é™¤مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚社ن¼ڑن؟é™؛و–™م‚‚ه£²ن¸ٹé«کمپ«ن¸€ه®ڑمپ®ç¨ژçژ‡ï¼ˆç‰©è²©مپ§12.3%م€پم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹و¥مپ§21.2%مپھمپ©ï¼‰م‚’ن¹—مپکمپ¦è¨ˆç®—مپ•م‚Œم€په£²ن¸ٹمپŒم‚¼مƒمپ®ه ´هگˆمپ¯م€پن؟é™؛و–™م‚‚م‚¼مƒمپ§مپ™م€‚
و—¥وœ¬مپ®é’色申ه‘ٹمپ¨مپ®و¯”較
و—¥وœ¬مپ®ه€‹ن؛؛ن؛‹و¥ن¸»مپŒéپ¸وٹمپ§مپچم‚‹م€Œé’色申ه‘ٹم€چهˆ¶ه؛¦مپ¯م€په®ںéڑ›مپ®çµŒè²»م‚’وژ§é™¤مپ§مپچم€پ複ه¼ڈç°؟è¨کم‚’è،Œمپ†مپ“مپ¨مپ§وœ€ه¤§65ن¸‡ه††مپ®ç‰¹هˆ¥وژ§é™¤م‚’هڈ—مپ‘م‚‰م‚Œم‚‹مپ¨مپ„مپ†م€پç¨ژé،چمپ®وœ€éپ©هŒ–م‚’ç›®çڑ„مپ¨مپ—مپںهˆ¶ه؛¦مپ§مپ™م€‚ن¸€و–¹م€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®Micro-entrepriseهˆ¶ه؛¦مپ¯م€په®ںéڑ›مپ®çµŒè²»مپ«é–¢م‚ڈم‚‰مپڑم€په£²ن¸ٹمپ«ه؟œمپکمپںه®ڑçژ‡مپ®م€Œمپ؟مپھمپ—経費وژ§é™¤م€چم‚’éپ©ç”¨مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®هˆ¶ه؛¦مپ¯م€پç¨ژé،چمپ®وœ€éپ©هŒ–م‚ˆم‚ٹم‚‚م€پ経çگ†ه‡¦çگ†مپ®ç©¶و¥µçڑ„مپھç°،ç´ هŒ–م‚’ç›®çڑ„مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپŒè¨€مپˆم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ®Micro-entrepriseهˆ¶ه؛¦مپ¯م€پ経çگ†و¥ه‹™م‚’وœ€ه°ڈé™گمپ«وٹ‘مپˆمپںمپ„مƒ•مƒھمƒ¼مƒ©مƒ³م‚¹م‚„ه‰¯و¥ه®¶مپ«مپ¨مپ£مپ¦çگ†وƒ³çڑ„مپھéپ¸وٹè‚¢مپ§مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€پن؛‹و¥هڈژç›ٹمپ¯مپ™مپ¹مپ¦ه€‹ن؛؛و‰€ه¾—مپ¨è¦‹مپھمپ•م‚Œم€پ経費計ن¸ٹمپ®و¦‚ه؟µمپŒهکهœ¨مپ—مپھمپ„و—¥وœ¬مپ®ه€‹ن؛؛ن؛‹و¥ن¸»مپ®ن»•çµ„مپ؟مپ¨مپ¯و ¹وœ¬çڑ„مپ«ç•°مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپ«م€پن¸،ه›½مپ®هˆ¶ه؛¦مپ¯م€پم€Œç°،ç´ هŒ–م€چمپ‹م€Œوœ€éپ©هŒ–م€چمپ‹مپ¨مپ„مپ†ç•°مپھم‚‹ه“²ه¦مپ«هں؛مپ¥مپ„مپ¦مپٹم‚ٹم€پن؛‹و¥مپ®و€§è³ھ(経費çژ‡م€پن؛‹و¥è¦ڈو¨،)مپ«م‚ˆمپ£مپ¦وœ€éپ©مپھéپ¸وٹمپŒç•°مپھم‚‹مپ¨مپ„مپ†م€په®ںه‹™ن¸ٹمپ®é‡چè¦پمپھç¤؛ه”†م‚’ن¸ژمپˆمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپ¨م‚پ
وœ¬è¨کن؛‹مپ§è§£èھ¬مپ—مپںمپ¨مپٹم‚ٹم€پمƒ•مƒ©مƒ³م‚¹مپ«مپ¯ه¤ڑو§کمپھن؛‹و¥ه½¢و…‹مپŒهکهœ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚SASمپ®وں”è»ںو€§م€پSARLمپ®ه®‰ه®ڑو€§م€پEURL/SASUمپ«مپٹمپ‘م‚‹ç¤¾ن¼ڑن؟éڑœمپ®éپ¸وٹم€پمپمپ—مپ¦مƒم‚¤م‚¯مƒم‚¢مƒ³مƒˆمƒ«مƒ—مƒ«مƒŒمƒ¼مƒ«هˆ¶ه؛¦مپ®ç°،ç´ هŒ–مپ¯م€پمپم‚Œمپم‚Œç•°مپھم‚‹ن؛‹و¥مƒ‹مƒ¼م‚؛مپ«ه؟œمپˆم‚‹مپںم‚پمپ«هکهœ¨مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚特مپ«م€پè؟‘ه¹´مپ®ç ´و¯€é™¢هˆ¤ن¾‹مپŒç¤؛مپ™م‚ˆمپ†مپ«م€په®ڑو¬¾مپ®è‡ھç”±ه؛¦م‚„経ه–¶é™£مپ®è²¬ن»»مپ«é–¢مپ™م‚‹و³•çڑ„解釈مپ¯ه¸¸مپ«é€²هŒ–مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ن؛‹و¥مپ®ç›®çڑ„م€پè¦ڈو¨،م€پ資金èھ؟éپ”مپ®è¨ˆç”»م€پمپمپ—مپ¦ه‡؛資者間مپ®é–¢ن؟‚و€§مپ«ه؟œمپکمپ¦م€پوœ€éپ©مپھو³•çڑ„ه½¢و…‹مپ¯ç•°مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھ複雑مپھو³•ç’°ه¢ƒمپ«مپٹمپ„مپ¦م€پوœ€è‰¯مپ®éپ¸وٹم‚’مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€په°‚é–€ه®¶مپ«م‚ˆم‚‹ه€‹هˆ¥ه…·ن½“çڑ„مپھم‚¢مƒ‰مƒگم‚¤م‚¹مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ مپ¨è¨€مپˆم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
م‚«مƒ†م‚´مƒھمƒ¼: ITمƒ»مƒ™مƒ³مƒپمƒ£مƒ¼مپ®ن¼پو¥و³•ه‹™