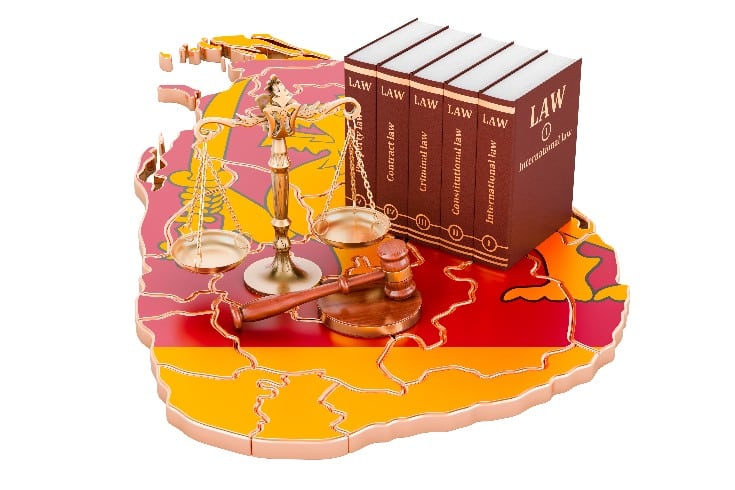ŃâëŃéĄŃâäňŐ┤ň⏊│ĽŃü«ŔŽĆňłÂŃüĘŠŚąŠťČń╝üŠąşŃü֊äĆŃüÖŃü╣ŃüŹÚçŹŔŽüń║őÚáůŃü«ŔžúŔ¬Č

ŃâëŃéĄŃâä´╝łŠşúň╝ĆňÉŹšž░ŃÇüŃâëŃéĄŃâäÚÇúÚéŽňů▒ňĺîňŤŻ´╝ëŃü»ŃÇüEUňččňćůŃüžŃééšë╣ŃüźňżôŠąşňôíń┐ŁŔşĚŃüîŠëőňÄÜŃüäňŤŻŃüĘŃüŚŃüŽščąŃéëŃéîŃüŽŃüŐŃéŐŃÇüŃüŁŃü«ňŐ┤ň⏊│ĽńŻôš│╗Ńü»ŃÇüÚÇ▓ňç║Ńé劥ťŔĘÄŃüÖŃéőŠŚąŠťČń╝üŠąşŃüźŃüĘŃüúŃüŽŃÇüŠąÁŃéüŃüŽÚçŹŔŽüŃü¬šÁîňľÂŃâ¬Ńé╣Ńé»ŃüĘŃü¬ŃéŐňżŚŃüżŃüÖŃÇ銌ąŠťČŃü«ňŐ┤ň⏊│ĽŃüîňłĄńżőŃü«šęŹŃü┐ÚçŹŃüş´╝łŔžúÚŤçŠĘęŠ┐źšöĘŠ│ĽšÉć´╝ëŃüźŃéłŃüúŃüŽšÖ║ň▒ĽŃüŚŃüŽŃüŹŃüčŃü«Ńüźň»żŃüŚŃÇüŃâëŃéĄŃâäňŐ┤ň⏊│ĽŃü»ŃÇüŔžúÚŤçŃü«ŠťëňŐ╣ŠÇžŃÇüňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŃü«ňłÂÚÖÉŃÇüŃüŁŃüŚŃüŽňŐ┤ńŻ┐Úľóń┐éŃüźŃüŐŃüĹŃéőňżôŠąşňôíňü┤Ńü«ÚľóńŞÄŃéĺŃÇüňůĚńŻôšÜäŃü¬Š│Ľń╗ĄŃüźŃéłŃüúŃüŽňÄ│Šá╝ŃüźŠ│ĽňůŞňîľŃüŚŃüŽŃüäŃéőšé╣ŃüîňĄžŃüŹŃü¬šë╣ňż┤ŃüžŃüÖŃÇé
ŠťČŔĘśń║őŃüžŃü»ŃÇüŠŚąŠťČŃü«šÁîňľÂŔÇůŃéäŠ│ĽňőÖŠőůňŻôŔÇůŃüîšë╣ŃüźšĽÖŠäĆŃüÖŃü╣ŃüŹŃÇüŃâëŃéĄŃâäňŐ┤ň⏊│ĽŃü«ńŞëŠťČŃü«Šč▒ŃüźšäŽšé╣ŃéĺňŻôŃüŽŃüŽŔžúŔ¬ČŃüŚŃüżŃüÖŃÇéńŞÇŃüĄšŤ«Ńü»ŃÇüŔžúÚŤçń┐ŁŔşĚŠ│Ľ´╝łK├╝ndigungsschutzgesetz, KSchG´╝ëŃüźňč║ŃüąŃüĆŃÇüŃÇżń╝ÜšÜ䊺úňŻôŠÇžŃÇŹŃü«ŔŽüń╗ÂŃüĘŃÇǚÁéŠëőŠ«ÁŃü«ňÄčňëçŃÇŹ´╝łUltima Ratio´╝ëŃü«ňÄ│Šá╝Ńü¬ÚüęšöĘŃüžŃüÖŃÇéń║îŃüĄšŤ«Ńü»ŃÇüňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŠ│Ľ´╝łArbeitszeitgesetz, ArbZG´╝ëŃüîň«ÜŃéüŃéő1ŠŚą10ŠÖéÚľôŃü«ňúüŃüĘŃÇüŠťÇńŻÄ11ŠÖéÚľôŃü«ÚÇúšÂÜń╝ĹŠü»ŠťčÚľô´╝łRuhezeit´╝ëŃü«ÚüÁň«łšżęňőÖŃüžŃüéŃéŐŃÇüŠŚąŠťČŃü«ŠčöŔ╗čŃü¬ňŐ┤ňâŹňłÂň║ŽŃüĘŃü«Š▒║ň«ÜšÜäŃü¬ÚüĽŃüäŃé嚥║ŃüŚŃüżŃüÖŃÇéńŞëŃüĄšŤ«Ńü»ŃÇüń║őŠąşŠëÇŠć▓Š│ĽŠ│Ľ´╝łBetriebsverfassungsgesetz, BetrVG´╝ëŃüźňč║ŃüąŃüĆń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝Ü´╝łBetriebsrat´╝ëŃü«ň╝ĚňŐŤŃü¬ňů▒ňÉîŠ▒║ň«ÜŠĘę´╝łZustimmungsrecht´╝ëŃüžŃüÖŃÇé
ŃüôŃü«ňłÂň║ŽŃü»ŃÇüń║║ń║őŃéäňŐ┤ň⏊Łíń╗ÂŃüźÚľóŃüÖŃéőŠ▒║ň«ÜŃüźŃüŐŃüäŃüŽŃÇüšÁîňľÂň▒ĄŃü«Ŕ笚ö▒ň║ŽŃéĺňĄžŃüŹŃüĆňłÂÚÖÉŃüŚŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃéëŃü«ňÄ│Šá╝Ńü¬ŃâźŃâ╝ŃâźŃéĺšÉćŔžúŃüŚŃÇüÚüęňłçŃü¬Š│ĽňőÖŠłŽšĽąŃé办őš»ëŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃüîŃÇüŃâëŃéĄŃâäňŞéňá┤ŃüžŃü«ŠłÉňŐčŃüźńŞŹňĆ»ŠČáŃüĘŃü¬ŃéőŃüžŃüŚŃéçŃüćŃÇé
ŃüôŃü«ŔĘśń║őŃü«šŤ«ŠČí
ŃâëŃéĄŃâäŃüźŃüŐŃüĹŃéőŔžúÚŤçŔŽĆňłÂŃüĘŃÇżń╝ÜšÜ䊺úňŻôŠÇžŃÇŹŃü«ňúü´╝łK├╝ndigungsschutzgesetz – KSchG´╝ë
KSchGŃü«ÚüęšöĘŔŽüń╗ÂŃüĘŠŚąŠťČŠ│ĽŃüĘŃü«ŠžőÚÇášÜäŃü¬ňĚ«šĽ░
ŃâëŃéĄŃâäŃü«ŔžúÚŤçń┐ŁŔşĚŠ│Ľ´╝łK├╝ndigungsschutzgesetz, KSchG´╝ëŃü»ŃÇüÚŤçšöĘńŞ╗ŃüîňżôŠąşňôíŃéĺŔžúÚŤçŃüÖŃéőÚÜŤŃü«ŔŽüń╗ÂŃéĺň«ÜŃéüŃéőńŞ╗ŔŽüŃü¬Š│ĽňżőŃüžŃüéŃéŐŃÇüÚŁ×ňŞŞŃüźňÄ│Šá╝Ńü¬ŔŽĆňłÂŃéĺŔĘşŃüĹŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃü«Š│ĽňżőŃü»ŃüÖŃü╣ŃüŽŃü«ňżôŠąşňôíŃüźšä튣íń╗ÂŃüźÚüęšöĘŃüĽŃéîŃéőŃéĆŃüĹŃüžŃü»Ńü¬ŃüĆŃÇüÚüęšöĘŃéĺňĆŚŃüĹŃéőŃüčŃéüŃüźŃü»ń║îŃüĄŃü«ńŞ╗ŔŽüŃü¬ŔŽüń╗ÂŃéĺŠ║ÇŃüčŃüÖň┐ůŔŽüŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇéšČČńŞÇŃüźŃÇüňŻôŔę▓ń╝üŠąşŃüîňŞŞŠÖé10ňÉŹŔÂůŃü«ňżôŠąşňôíŃéĺÚŤçšöĘŃüŚŃüŽŃüäŃéőŃüôŃüĘ´╝łň░ĆŔŽĆŠĘíń╝üŠąşńżőňĄľ´╝ë ŃÇüšČČń║îŃüźŃÇüŔžúÚŤçŃüĽŃéîŃéőňżôŠąşňôíŃüîňŻôŔę▓ń╝üŠąşŃüž6Ń⊝łŔÂůňőĄňőÖŃüŚŃüŽŃüäŃéőŃüôŃüĘŃüžŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃéëŃü«ŔŽüń╗ÂŃéĺŠ║ÇŃüčŃüŚŃüčňá┤ňÉłŃÇüŔžúÚŤçŃüźŃü»ŃÇżń╝ÜšÜ䊺úňŻôŠÇžŃÇŹ´╝łsoziale Rechtfertigung´╝ëŃüîň┐ůŔŽüŃüĘŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ŠŚąŠťČŃü«ňŐ┤ň⏊│ĽŃüźŃüŐŃüäŃüŽŃÇüŔžúÚŤçŃü«ŠťëňŐ╣ŠÇžŃéĺňłĄŠľşŃüÖŃéőÚÜŤŃü«ňč║Š║ľŃü»ŃÇüňŐ┤ňâŹňąĹš┤äŠ│ĽšČČ16ŠŁíŃüźň«ÜŃéüŃéëŃéîŃüčŔžúÚŤçŠĘęŠ┐źšöĘŠ│ĽšÉćŃüžŃüéŃéŐŃÇüŃÇîň«óŔŽ│šÜäŃüźňÉłšÉćšÜäŃü¬šÉćšö▒ŃéĺŠČáŃüŹŃÇüšĄżń╝ÜÚÇÜň┐ÁńŞŐšŤŞňŻôŃüžŃüéŃéőŃüĘŔ¬ŹŃéüŃéëŃéîŃü¬Ńüäňá┤ňÉłŃÇŹŃüźŔžúÚŤçŃü»šäíňŐ╣ŃüĘŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃü»ňłĄńżőŃü«šęŹŃü┐ÚçŹŃüşŃüźŃéłŃüúŃüŽňŻóŠłÉŃüĽŃéîŃüčŠ│ĽšÉćŃüžŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃüźň»żŃüŚŃüŽŃâëŃéĄŃâäŃü«KSchGŃü»ŃÇüŃüôŃü«ŃÇżń╝ÜšÜ䊺úňŻôŠÇžŃÇŹŃü«ŠŽéň┐ÁŃéĺŠ│Ľń╗ĄŃü«ŠŁíŠľç´╝ł┬ž 1 KSchG´╝ëŃü«ńŞşŃüžŠśÄšó║ŃüźÚí×ň×őňîľŃüŚŃÇüňłÂň║ŽšÜäŃüźŔžúÚŤçŃéĺŔŽĆňłÂŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃü«Š│ĽŠ║ÉŃü«ÚüĽŃüäŃü»ŃÇüŔžúÚŤçŃü«ÚŤúŃüŚŃüĽŃü«Ńü┐Ńü¬ŃéëŃüÜŃÇüŔžúÚŤçŃâŚŃâşŃé╗Ńé╣ňůĘńŻôŃüźŃüŐŃüäŃüŽŃÇüšÁîňľÂňü┤ŃüźŠąÁŃéüŃüŽÚźśŃüäŠëőšÂÜŃüŹšÜäŃüőŃüĄšźőŔĘ╝Ŕ▓Čń╗╗ŃéĺŔ¬▓ŃüÖŃüĘŃüäŃü択őÚÇášÜäŃü¬ňĚ«šĽ░Ńüźš╣őŃüîŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ň░ĆŔŽĆŠĘíń╝üŠąş´╝łňżôŠąşňôí10ňÉŹń╗ąńŞő´╝ëŃü«ňá┤ňÉłŃÇüKSchGŃü»ÚüęšöĘŃüĽŃéîŃüÜŃÇüŔžúÚŤçń┐ŁŔşĚŃü»šĚęŃéäŃüőŃüźŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃüîŃÇüŔžúÚŤçŃüîňůČŠşúŠÇž´╝łFairness´╝ëŃü«ňč║Š║ľŃéĺŔĹŚŃüŚŃüĆÚÇŞŔä▒ŃüÖŃéőňá┤ňÉłŃü¬ŃüęŃÇüŔžúÚŤçŃüîšäíňŐ╣ŃüĘŃü¬ŃéőňĆ»Ŕ⯊ǞŃü»Š«őŃéőŃüčŃéüŃÇüň«îňůĘŃüźŔ笚ö▒ŃüźŔžúÚŤçŃüžŃüŹŃéőŃéĆŃüĹŃüžŃü»ŃüéŃéŐŃüżŃüŤŃéôŃÇé
ŔžúÚŤçŃü«ŃÇżń╝ÜšÜ䊺úňŻôŠÇžŃÇŹ´╝łsoziale Rechtfertigung´╝ëŃü«ńŞëŃüĄŃü«Úí×ň×ő
KSchG ┬ž 1 Abs. 2ŃüźŃéłŃéîŃü░ŃÇüŔžúÚŤçŃüżń╝ÜšÜ䊺úňŻôŠÇžŃéĺŠîüŃüĄŃüĘŔ¬ŹŃéüŃéëŃéîŃéőŃüčŃéüŃüźŃü»ŃÇüń╗ąńŞőŃü«ńŞëŃüĄŃü«Úí×ň×őŃü«ŃüäŃüÜŃéîŃüőŃüźňč║ŃüąŃüĆŃééŃü«ŃüžŃü¬ŃüĹŃéîŃü░Ńü¬ŃéŐŃüżŃüŤŃéôŃÇé
- šÁîňľÂńŞŐŃü«šÉćšö▒ (Betriebsbedingte Gr├╝nde)´╝Üń╝ÜšĄżŃü«ňĄľÚâĘŃüżŃüčŃü»ňćůÚâĘŃü«šĚŐŠÇąŃü«šÁîňľÂńŞŐŃü«ň┐ůŔŽüŠÇžŃüźŃéłŃéŐŃÇüňŻôŔę▓ňżôŠąşňôíŃü«ÚŤçšöĘšÂÖšÂÜŃüîńŞŹňĆ»ŔâŻŃüźŃü¬ŃüúŃüčňá┤ňÉł´╝łńżő´╝ÜÚťÇŔŽüŃü«ŠŞŤň░ĹŃÇüšÁäš╣öň揚ĚĘ´╝ëŃÇé
- ňżôŠąşňôíŃü«ŔíîňőĽńŞŐŃü«šÉćšö▒ (Verhaltensbedingte Gr├╝nde)´╝ÜňżôŠąşňôíŃüîňŐ┤ňâŹňąĹš┤äńŞŐŃü«šżęňőÖŃéĺńżÁň«│ŃüŚŃÇüŃüŁŃü«ÚüĽňĆŹŃüîň░抣ąŃééšÂÖšÂÜŃüÖŃéőňĆ»Ŕ⯊ǞŃüîŃüéŃéŐŃÇüŃüőŃüĄŃÇüÚüĽňĆŹŃü«šĘőň║ŽŃüîÚçŹňĄžŃüžŃüéŃéőňá┤ňÉłŃÇéŃüôŃü«šĘ«Ńü«ŔžúÚŤçŃü«ňëŹŃüźŃü»ŃÇüň░抣ąŃü«ÚüĽňĆŹŃéĺÚü┐ŃüĹŃéőŠęčń╝ÜŃéĺńŞÄŃüłŃéőŃüčŃéüŃÇüÚÇÜňŞŞŃÇüAbmahnung´╝łŔşŽňĹŐŃâ╗Šö╣ňľäŔŽüŠ▒é´╝ëŃüîň┐ůŔŽüŃüžŃüÖŃÇé
- ňżôŠąşňôíŃü«ŔâŻňŐŤńŞŐŃü«šÉćšö▒ (Personenbedingte Gr├╝nde)´╝ÜňżôŠąşňôíŃü«ňÇőń║║šÜäŃü¬šë╣ŠÇžŃéäŔâŻňŐŤ´╝łńżő´╝ÜÚĽĚŠťčŃü«šľżšŚůŃüźŃéłŃéőšÂÖšÂÜšÜäŃü¬ŠČáňőĄ´╝ëŃüźŃéłŃüúŃüŽŃÇüÚŤçšöĘšÂÖšÂÜŃüîńŞŹňĆ»ŔâŻŃüźŃü¬ŃüúŃüčňá┤ňÉłŃÇé
šÁîňľÂńŞŐŃü«šÉćšö▒Ńüźňč║ŃüąŃüĆŔžúÚŤçŃü«ŠťÇšÁéŠëőŠ«ÁŃü«ňÄčňëç´╝łUltima Ratio´╝ë
šÁîňľÂńŞŐŃü«šÉćšö▒ŃüźŃéłŃéőŔžúÚŤç´╝łBetriebsbedingte K├╝ndigung´╝ëŃü«ŠťëňŐ╣ŠÇžŃéĺňłĄŠľşŃüÖŃéőńŞŐŃüžŃÇüŠťÇŃééňÄ│Šá╝Ńü¬ŔŽüń╗ÂŃüĘŃü¬ŃéőŃü«ŃüîŃÇüŠťÇšÁéŠëőŠ«ÁŃü«ňÄčňëç´╝łUltima Ratio´╝ëŃüžŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃü»ŃÇüÚŤçšöĘšÂÖšÂÜŃéĺňŤ×Úü┐ŃüÖŃéőŃüčŃéüŃü«ňůĘŃüŽŃü«ŠŐÇŔíôšÜäŃÇüšÁäš╣öšÜäŃÇüšÁłšÜäŃü¬ń╗úŠŤ┐ŠëőŠ«ÁŃüîň░ŻŃüĆŃüĽŃéîŃüčňá┤ňÉłŃüźÚÖÉŃéŐŃÇüŔžúÚŤçŃüżń╝ÜšÜäŃüźŠşúňŻôňîľŃüĽŃéîŃéőŃüĘŃüäŃüćŔÇâŃüłŠľ╣ŃüžŃüÖŃÇé┬á
ŃüôŃü«ňÄčňëçŃü«ŠťÇŃééÚçŹŔŽüŃü¬šĆżŃéîŃü»ÚůŹšŻ«Ŕ╗óŠĆŤšżęňőÖŃü«ňż╣ň║ĽŃüžŃüÖŃÇéÚŤçšöĘńŞ╗Ńü»ŃÇüŔžúÚŤçŃéĺŔíîŃüćňëŹŃüźŃÇüňżôŠąşňôíŃéĺŃüŁŃü«ŔâŻňŐŤŃüźň┐ťŃüśŃüŽŃÇüŃüčŃüĘŃüłňŐ┤ň⏊Łíń╗ÂŃüîňĄëŠŤ┤ŃüĽŃéîŃüčŃüĘŃüŚŃüŽŃééŃÇüń╗ľŃü«šę║ŃüäŃüŽŃüäŃéőŔüĚňőÖŃüźÚůŹšŻ«Ŕ╗óŠĆŤŃüÖŃéőňĆ»Ŕ⯊ǞŃéĺňż╣ň║ĽšÜäŃüźŠĄťŔĘÄŃüŚŃÇüň«čŔíîŃüÖŃéőšżęňőÖŃéĺŔ▓áŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ÚÇúÚéŽňŐ┤ňâŹŔúüňłĄŠëÇ´╝łBundesarbeitsgericht, BAG´╝ëŃü»ŃÇüŃüôŃü«ňÄčňëçŃéĺňÄ│Šá╝ŃüźÚüęšöĘŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéńżőŃüłŃü░ŃÇüBAG 2004ň╣┤11Šťł23ŠŚąňłĄŠ▒║´╝ł2 AZR 24/04´╝ëŃüźŃüŐŃüäŃüŽŃÇüŔúüňłĄŠëÇŃü»ŃÇüŔžúÚŤçŃü»ŃÇüÚŤçšöĘńŞ╗ŃüóňşśŃü«šÁîňľÂńŞŐŃü«ňĽĆÚíîŃéĺŃÇüÚůŹšŻ«Ŕ╗óŠĆŤŃü¬ŃüęŃü«ŔžúÚŤçń╗ąňĄľŃü«ŠëőŠ«ÁŃüžŔžúŠ▒║ŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃüîńŞŹňĆ»ŔâŻŃü¬ňá┤ňÉłŃüźŃü«Ńü┐Ŕ¬ŹŃéüŃéëŃéîŃéőŃüĘŠśÄšó║ŃüźšĄ║ŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇ銌ąŠťČŃü«šÁîňľÂŔÇůŃüîŔžúÚŤçŃüźŔŞĆŃü┐ňłçŃéőÚÜŤŃÇüŃüôŃü«ń╗úŠŤ┐ŔüĚňőÖŠĄťŔĘÄŃü«ŔĘśÚî▓ŃüĘŔĘ╝ŠőáŃü«ŠĽ┤ňéÖŃéĺŠÇáŃéőŃüĘŃÇüŔžúÚŤçšäíňŐ╣ňłĄŠ▒║ŃüźŔç│ŃéőŃâ¬Ńé╣Ńé»ŃüÁŃéüŃüŽÚźśŃüĆŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé┬á
ń║║ňôíňëŐŠŞŤŠÖéŃü«ŃÇżń╝ÜšÜäÚüŞŠŐ×ŃÇŹ´╝łSozialauswahl´╝ëŃü«šżęňőÖ
šÁîňľÂńŞŐŃü«šÉćšö▒ŃüźŃéłŃéŐŔĄçŠĽ░Ńü«ňżôŠąşňôíŃéĺŔžúÚŤçŃüÖŃéőň┐ůŔŽüŃüîŃüéŃéőňá┤ňÉłŃÇüÚŤçšöĘńŞ╗Ńü»ŃÇüŔžúÚŤçŃüĽŃéîŃéőňżôŠąşňôíŃéĺÚüŞň«ÜŃüÖŃéőÚÜŤŃüźŃÇüšĄżń╝ÜšÜäÚüŞŠŐ×´╝łSozialauswahl´╝ëŃüĘňĹ╝Ńü░ŃéîŃéőŠ»öŔ╝âŔííÚçĆŃâŚŃâşŃé╗Ńé╣ŃéĺšżęňőÖń╗śŃüĹŃéëŃéîŃüżŃüÖŃÇé
ŃüôŃü«ŃâŚŃâşŃé╗Ńé╣ŃüžŃü»ŃÇüŔžúÚŤçň»żŔ▒íŔÇůŃéĺÚüŞň«ÜŃüÖŃéőňč║Š║ľŃüĘŃüŚŃüŽŃÇüňőĄšÂÜŠťčÚľôŃÇüň╣┤ÚŻóŃÇüŠëÂÚĄŐšżęňőÖŃÇüÚçŹň║ŽÚÜťň«│Ńü«ŠťëšäíŃü¬ŃüęŃüîńŞ╗ŔŽüŃü¬ŔęĽńżíŔŽüš┤áŃüĘŃü¬ŃéŐ ŃÇüŃüôŃéîŃéëŃü«ŔŽüš┤áŃüźňč║ŃüąŃüŹŃÇüšĄżń╝ÜšÜäŃü¬ń┐ŁŔşĚŃü«ň┐ůŔŽüŠÇžŃüîńŻÄŃüäňżôŠąşňôíŃüőŃéëŔžúÚŤçŃüĽŃéîŃéőŃüôŃüĘŃüźŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ÚÇúÚéŽňŐ┤ňâŹŔúüňłĄŠëÇŃü»ŃÇüšĄżń╝ÜšÜäÚüŞŠŐ×Ńü«ÚüőšöĘŃüźŃüŐŃüäŃüŽŃééňůĚńŻôšÜäŃü¬ňč║Š║ľŃé嚥║ŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéńżőŃüłŃü░ŃÇüBAG 2017ň╣┤4Šťł27ŠŚąňłĄŠ▒║´╝ł2 AZR 67/16´╝ëŃüžŃü»ŃÇüÚÇÜňŞŞŃü«ŔÇüÚŻóň╣┤ÚçĹŃü«ňĆŚšÁŽŔ│çŠá╝ŃéĺŠîüŃüĄňżôŠąşňôíŃü»ŃÇüŔőąŃüäňżôŠąşňôíŃéłŃéŐŃééń┐ŁŔşĚŃü«ň┐ůŔŽüŠÇžŃüîńŻÄŃüäŃüĘňłĄŠľşŃüžŃüŹŃéőŃüĘŃüäŃüćŔŽőŔžúŃü║ŃüĽŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüżŃüčŃÇüšë╣ň«ÜŃü«ň╣┤ÚŻóň▒ĄŃüźšÁ×ŃüúŃüŽÚüŞŠŐ×ŃéĺŔíîŃüćŠëőŠ│Ľ´╝łAltersgruppenbildung´╝ëŃüîň╣┤ÚŻóňĚ«ňłąŃüźŃüéŃüčŃéëŃü¬ŃüäŃüĘŃüäŃüćňłĄŠľşŃé隥║ŃüĽŃéîŃüŽŃüŐŃéŐ´╝łBAG 2011ň╣┤12Šťł15ŠŚąňłĄŠ▒║ 2 AZR 42/10´╝ëŃÇüŔĄçÚŤĹŃü¬Š│ĽšÜäňłĄŠľşŃüîň┐ůŔŽüŃüĘŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
š┤Ťń║ëŔžúŠ▒║ŃüźŃüŐŃüĹŃéőŔúťňäčÚçĹŠö»ŠëĽŃüäŃüźŃéłŃéőÚŤçšöĘÚľóń┐éŃü«ŔžúŠÂł
KSchGŃüźňč║ŃüąŃüĆŔžúÚŤçš┤Ťń║ëŃüźŃüŐŃüäŃüŽŃÇüŔúüňłĄŠëÇŃüîŔžúÚŤçŃéĺšäíňŐ╣ŃüĘňłĄŠľşŃüŚŃüčňá┤ňÉłŃüžŃééŃÇüÚŤçšöĘÚľóń┐éŃü«šÂÖšÂÜŃüîňŻôń║őŔÇůňĆ╣ŃüźŃüĘŃüúŃüŽŠťčňżůŃüžŃüŹŃü¬ŃüäŃüĘŔ¬ŹŃéüŃüčňá┤ňÉłŃÇüŔúüňłĄŠëÇŃü»ŃÇüÚŤçšöĘÚľóń┐éŃéĺŔžúŠÂłŃüŚ´╝łAufl├Âsung des Arbeitsverh├Ąltnisses´╝ëŃÇüňżôŠąşňôíŃüźńŞÇň«ÜŃü«ŔúťňäčÚçĹ´╝łAbfindung´╝ëŃü«Šö»ŠëĽŃüäŃéĺňĹŻŃüśŃéőŃüôŃüĘŃüîŃüžŃüŹŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃü«ŔúťňäčÚçĹŃüźŃéłŃéőš┤Ťń║ëŔžúŠ▒║Ńü«ňłÂň║ŽŃü»ŃÇüŔžúÚŤçŃü«šäíňŐ╣ŃéĺńŞ╗ň╝ÁŃüŚšÂÜŃüĹŃüčšÁɊםŃÇüňÄčňëçŃüĘŃüŚŃüŽňÄčŔüĚňżęňŞ░ŃüĘŃü¬ŃéőŠŚąŠťČŠ│ĽŃüźŃü»ŔŽőŃéëŃéîŃü¬ŃüäŃÇüŃâëŃéĄŃâäšë╣ŠťëŃü«ŠčöŔ╗čŃü¬ŔžúŠ▒║ŠëőŠ«ÁŃéĺŠĆÉńżŤŃüŚŃüżŃüÖŃÇé┬á
ňÄ│ň»ćŃüźš«íšÉćŃüĽŃéîŃéőŃâëŃéĄŃâäŃü«ňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŃüĘń╝ĹŠü»ŠťčÚľô´╝łArbeitszeitgesetz – ArbZG´╝ë

ňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŃü«ńŞŐÚÖÉŃüĘŠŚąŠťČŠ│ĽŃÇî36ňŹöň«ÜŃÇŹŃüĘŃü«Š▒║ň«ÜšÜäŃü¬ÚüĽŃüä
ŃâëŃéĄŃâäŃü«ňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŠ│Ľ´╝łArbZG´╝ëŃü»ŃÇüňżôŠąşňôíŃü«ňüąň║Ěń┐ŁŔşĚŃéĺńŞ╗Ńü¬šŤ«šÜäŃüĘŃüŚŃÇüŃüŁŃü«ŔŽĆňłÂŃü»ŠŚąŠťČŃü«ňŐ┤ňâŹňč║Š║ľŠ│ĽŃüĘŠ»öŔ╝âŃüŚŃüŽŠąÁŃéüŃüŽňÄ│Šá╝ŃüžŃüÖŃÇéArbZG ┬ž 3ŃüźŃéłŃéŐŃÇüňżôŠąşňôíŃü«ňőĄňőÖŠŚą´╝łWerkt├Ągliche Arbeitszeit´╝ëŃü«ňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŃü»ŃÇüń╝ĹŠćęŠÖéÚľôŃéĺÚÖĄŃüŹŃÇüňÄčňëçŃüĘŃüŚŃüŽ8ŠÖéÚľôŃéĺŔÂůŃüłŃüŽŃü»Ńü¬ŃéŐŃüżŃüŤŃéôŃÇé
ňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŃü»ŃÇüńŞÇŠÖéšÜäŃüź10ŠÖéÚľôŃüżŃüžň╗ÂÚĽĚŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃüîŔĘ▒ň«╣ŃüĽŃéîŃüżŃüÖŃÇéŃüŚŃüőŃüŚŃÇüŃüôŃü«ň╗ÂÚĽĚŃü»ŃÇü6ŠÜŽŠťłŃüżŃüčŃü»24ÚÇ▒ÚľôŃü«ň╣│ňŁçŃüžŃÇü1ŠŚąŃüéŃüčŃéŐ8ŠÖéÚľôŃéĺŔÂůŃüłŃü¬Ńüäňá┤ňÉłŃüźÚÖÉŃéëŃéîŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃü«ň╣│ňŁçňîľŔŽĆňłÂŃüîňÄ│Šá╝ŃüźÚüęšöĘŃüĽŃéîŃéőšé╣ŃüîÚçŹŔŽüŃüžŃüÖŃÇé┬á
ŠŚąŠťČŃüźŃüŐŃüäŃüŽŃü»ŃÇüňŐ┤ńŻ┐ňŹöň«Ü´╝łŃüäŃéĆŃéćŃéőŃÇî36ňŹöň«ÜŃÇŹ´╝ëŃéĺšĚášÁÉŃüŚŃÇüŔíîŠö┐ň«śň║üŃüźň▒ŐŃüĹňç║ŃéőŃüôŃüĘŃüźŃéłŃüúŃüŽŃÇüŠ│Ľň«ÜňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŃéĺŔÂůŃüłŃéőŠÖéÚľôňĄľňŐ┤ň⏴╝łŠ«őŠąş´╝ëŃüîńŞÇň«ÜŃü«ÚÖÉň║ŽňćůŃüžŔĘ▒ň«╣ŃüĽŃéîŃüżŃüÖŃÇéńŞÇŠľ╣ŃÇüŃâëŃéĄŃâäŃü«ArbZGŃüźŃü»ŃÇüŠŚąŠťČŃü«ŃÇî36ňŹöň«ÜŃÇŹŃü«ŃéłŃüćŃü¬ŃÇüň║âš»äŃü¬Š«őŠąşŃéĺňĆ»ŔâŻŃüźŃüÖŃéőŠčöŔ╗čŃü¬ňłÂň║ŽŃéäŃÇüŃÇîš╣üň┐ÖŠťčŃÇŹŃéĺšÉćšö▒ŃüĘŃüŚŃüčńżőňĄľŔŽĆň«ÜŃüîňşśňťĘŃüŚŃüżŃüŤŃéôŃÇéŃâëŃéĄŃâäŠ│ĽŃü»ŃÇüŠŚąŠťČŃü«ňłÂň║ŽŃü«ŃéłŃüćŃü¬ŠŐťŃüĹÚüôŃéĺŔĘ▒ň«╣ŃüŚŃü¬ŃüäŃÇüŠąÁŃéüŃüŽňÄ│Šá╝Ńü¬ňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŔŽĆňłÂŃé劼ĚŃüäŃüŽŃüŐŃéŐŃÇüŠŚąŠČíňŐ┤ň⏊ÖéÚľôš«íšÉćŃü«ÚüÁň«łŃüîń╝üŠąşŃü«ÚçŹňĄžŃü¬Ŕ▓ČňőÖŃüĘŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ÚÇúšÂÜŃüŚŃüčń╝ĹŠü»ŠťčÚľô´╝łRuhezeit´╝ëŃü«šżęňőÖ
ŃâëŃéĄŃâäňŐ┤ň⏊│ĽŃü«ňüąň║Ěń┐ŁŔşĚŠÇŁŠâ│ŃéĺŔ▒íňż┤ŃüÖŃéőŃü«ŃüîŃÇüňőĄňőÖšÁéń║ćňżîŃü«ń╝ĹŠü»ŠťčÚľô´╝łRuhezeit´╝ëŃü«ŔŽĆň«ÜŃüžŃüÖŃÇéArbZG ┬ž 5 Abs. 1ŃüźŃéłŃéŐŃÇüňżôŠąşňôíŃü»ŃÇüŠŚąŃÇůŃü«ňőĄňőÖšÁéń║ćňżîŃÇüńŞşŠľşŃü¬ŃüĆŠťÇńŻÄ11ŠÖéÚľôŃü«ÚÇúšÂÜŃüŚŃüčń╝ĹŠü»ŠťčÚľôŃéĺŠîüŃüčŃü¬ŃüĹŃéîŃü░Ńü¬ŃéëŃü¬ŃüäŃüĘšżęňőÖń╗śŃüĹŃéëŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ŃüôŃü«ŃÇî11ŠÖéÚľôŃâźŃâ╝ŃâźŃÇŹŃü»ŃÇüŠŚąŠťČŃü«šÁîňľÂŔÇůŃüîŠůúŃéîŔŽ¬ŃüŚŃéôŃüáŠčöŔ╗čŃü¬ŃéĚŃâĽŃâłÚüőšöĘŃéäŃÇüš¬üšÖ║šÜäŃü¬ŠĚ▒ňĄťŠąşňőÖŃéĺňÄčňëçšÜäŃüźŠÄĺÚÖĄŃüŚŃüżŃüÖŃÇéŃüéŃéőňżôŠąşňôíŃüîňĄť10ŠÖéŃüźňőĄňőÖŃéĺšÁéń║ćŃüŚŃüčňá┤ňÉłŃÇüŠČíŃü«ňőĄňőÖŃéĺÚľőňžőŃüžŃüŹŃéőŃü«Ńü»ŃÇüš┐Ł9ŠÖéń╗ąÚÖŹŃüžŃü¬ŃüĹŃéîŃü░Ńü¬ŃéŐŃüżŃüŤŃéôŃÇéŃüôŃéîŃéĺÚüĽňĆŹŃüÖŃéőŃüĘŃÇüŠ│Ľń╗ĄÚüĽňĆŹŃüĘŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ŃüôŃü«11ŠÖéÚľôŃâźŃâ╝ŃâźŃü«ńżőňĄľŃü»ŠąÁŃéüŃüŽÚÖÉň«ÜŃüĽŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇ隌ůÚÖóŃéäšë╣ň«ÜŃü«ŃéÁŃâ╝ŃâôŃé╣ŠąşšĘ«ŃüźŃüŐŃüäŃüŽŃü«Ńü┐ŃÇüńżőňĄľšÜäŃüź1ŠÖéÚľôščşšŞ«ŃüîŔĘ▒ň«╣ŃüĽŃéîŃüżŃüÖŃüîŃÇüŃüôŃü«ščşšŞ«ňłćŃü»ŠÜŽŠťłňćůŃüżŃüčŃü»4ÚÇ▒Úľôń╗ąňćůŃüźŃÇüňłąŃü«ń╝ĹŠü»ŠťčÚľôŃé劝ÇńŻÄ12ŠÖéÚľôŃüźň╗ÂÚĽĚŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃüžň«îňůĘŃüźšŤŞŠ«║ŃüĽŃéîŃü¬ŃüĹŃéîŃü░Ńü¬ŃéŐŃüżŃüŤŃéô´╝łArbZG ┬ž 5 Abs. 2´╝ëŃÇé
ŃüżŃüčŃÇüňőĄňőÖŠÖéÚľôńŞşŃü«ń╝ĹŠćę´╝łRuhepausen´╝ëŃééňÄ│ň»ćŃüźŔŽĆň«ÜŃüĽŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéArbZG ┬ž 4Ńüźňč║ŃüąŃüŹŃÇüňżôŠąşňôíŃü»6ŠÖéÚľôŔÂůÚÇúšÂÜŃüŚŃüŽňâŹŃüĆŃüôŃüĘŃü»ŃüžŃüŹŃüżŃüŤŃéôŃÇé6ŠÖéÚľôŔÂů9ŠÖéÚľôń╗ąńŞőŃü«ňőĄňőÖŃüžŃü»ŠťÇńŻÄ30ňłćŃÇü9ŠÖéÚľôŔÂůŃü«ňőĄňőÖŃüžŃü»ŠťÇńŻÄ45ňłćŃü«ń╝ĹŠćęŃüîšżęňőÖń╗śŃüĹŃéëŃéîŃüŽŃüŐŃéŐŃÇüŃüôŃéîŃéëŃü«ń╝ĹŠćęŃü»ŃüŁŃéîŃü×ŃéÇńŻÄ15ňłćňŹśńŻŹŃüźňłćňë▓ŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃüîňĆ»ŔâŻŃüžŃüÖŃÇéŃüôŃü«ňÄ│Šá╝Ńü¬ń╝ĹŠü»šżęňőÖŃü»ŃÇüŠŚąňŞŞšÜäŃü¬HR´╝łŃâĺŃâąŃâ╝Ńâ×Ńâ│Ńâ╗Ńâ¬ŃéŻŃâ╝Ńé╣´╝ëš«íšÉćŃéäšĚŐŠÇąŠÖéŃü«ň»żň┐ťŔâŻňŐŤŃéĺŠá╣ŠťČšÜäŃüźňłÂš┤äŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃéĺŠäĆňĹ│ŃüŚŃüżŃüÖŃÇé┬á
ŃâëŃéĄŃâäŃÇîňů▒ňÉîŠ▒║ň«ÜňłÂň║ŽŃÇŹ´╝łBetriebsverfassungsgesetz – BetrVG´╝ëŃü«ŠĘęÚÖÉ
ń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝Ü´╝łBetriebsrat´╝ëŃü«ŔĘşšŻ«ŔŽüń╗ÂŃüĘŠ│ĽšÜäňť░ńŻŹ
ŃâëŃéĄŃâäŃü«ń╝üŠąşŃüźŃüŐŃüĹŃéőňů▒ňÉîŠ▒║ň«ÜňłÂň║Ž´╝łMitbestimmung´╝ëŃü»ŃÇüń║őŠąşŠëÇŠć▓Š│ĽŠ│Ľ´╝łBetriebsverfassungsgesetz, BetrVG´╝ëŃüźŃéłŃüúŃüŽŔŽĆň«ÜŃüĽŃéîŃüŽŃüŐŃéŐŃÇüňżôŠąşňôíŃüîń╝üŠąşŃü«ŠäĆŠÇŁŠ▒║ň«ÜŃâŚŃâşŃé╗Ńé╣ŃüźňĆéňŐáŃüÖŃéőŠĘęňłęŃéĺń┐ŁÚÜťŃüŚŃüżŃüÖŃÇé
ń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃü«ŔĘşšŻ«ŔŽüń╗ÂŃü»ŃÇüń╝üŠąşňćůŃüźňŞŞŠÖé5ňÉŹń╗ąńŞŐŃü«ÚüŞŠîÖŠĘęŃé劝ëŃüÖŃéőŠüĺňŞŞšÜäŃü¬ňżôŠąşňôíŃüîŃüäŃéőňá┤ňÉłŃÇüňżôŠąşňôíŃü«ŃéĄŃâőŃéĚŃéóŃâćŃéúŃâľŃüźŃéłŃéŐňžöňôíń╝ÜŃéĺŔĘşšŻ«ŃüÖŃéőÚüŞŠîÖŃüîŔíîŃéĆŃéîŃéőňĆ»Ŕ⯊ǞŃüîŃüéŃéőŃüĘŃüäŃüćŃééŃü«ŃüžŃüÖŃÇéŃüôŃü«ŔĘşšŻ«Ńü»ňżôŠąşňôíňü┤Ńü«ŠĘęňłęŃüžŃüéŃéŐŃÇüÚŤçšöĘńŞ╗ŃüîÚüŞŠîÖŃü«ÚľőňžőŃé䊳ɚźőŃéĺňŽĘň«│ŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃü»ŃÇüšŐ»šŻ¬Ŕíîšé║ŃüĘŃüŚŃüŽšŻ░ŃüŤŃéëŃéîŃéőňĆ»Ŕ⯊ǞŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃü»ŃÇüňÇőňłąŃü«ňŐ┤ň⏚ÁäňÉłŃüĘŃü»šĽ░Ńü¬ŃéŐŃÇüń║őŠąşŠëÇňůĘńŻôŃü«ňżôŠąşňôíń╗úŔíĘŃüĘŃüŚŃüŽň║âš»äŃü¬ŠĘęňłęŃé劝ëŃüŚŃüżŃüÖŃÇ銌ąŠťČŃü«ňŐ┤ńŻ┐Úľóń┐éŃüźŃüŐŃüäŃüŽŃÇüňŐ┤ńŻ┐ňŹöŔş░ń╝ÜŃéäňŐ┤ň⏚ÁäňÉłŃüîńŞ╗ŃüźŃÇîňŹöŔş░ŃÇŹŃéäŃÇîń║ĄŠŞëŃÇŹŃéĺňŻ╣ňë▓ŃüĘŃüÖŃéőŃü«Ńüźň»żŃüŚŃÇüŃâëŃéĄŃâäŃü«ń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃü»ŃÇüšÁîňľÂŃü«ŠäĆŠÇŁŠ▒║ň«ÜŃâŚŃâşŃé╗Ńé╣ŃüźšŤ┤ŠÄąšÜäŃüźÚľóńŞÄŃüÖŃéőŃÇüŃéłŃéŐň╝ĚňŐŤŃü¬ŠęčÚľóŃüžŃüÖŃÇéŠ│ĽňżőńŞŐŃÇüňŐ┤ńŻ┐Ńü»šŤŞń║ĺń┐íÚá╝Ńü«š▓żšą×ŃüžňŹöňŐŤŃüÖŃéőšżęňőÖŃéĺŔ▓áŃüúŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃüî´╝łBetrVG ┬ž 2 Abs. 1´╝ë ŃÇüšÁîňľÂŃü«Ŕ笚ö▒ň║ŽŃéĺňĄžŃüŹŃüĆňłÂÚÖÉŃüÖŃéőňü┤ÚŁóŃééŠîüŃüíŃüżŃüÖŃÇé┬á
ń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃü«ŃÇîňÉîŠäĆŠĘęŃÇŹ´╝łZustimmungsrecht´╝ëŃü«š»äňŤ▓´╝łBetrVG ┬ž 87´╝ë
ń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃü«ŠĘęÚÖÉŃü«ŠáŞň┐âŃü»ŃÇüBetrVG ┬ž 87ŃüźŔŽĆň«ÜŃüĽŃéîŃéőŃÇżń╝ÜšÜäń║őÚáůŃÇŹ´╝łSoziale Angelegenheiten´╝ëŃüźÚľóŃüÖŃéőňů▒ňÉîŠ▒║ň«ÜŠĘę´╝łZustimmungsrecht´╝ëŃüžŃüÖŃÇéŃüôŃéîŃéëŃü«ń║őÚáůŃüźŃüĄŃüäŃüŽŃÇüÚŤçšöĘńŞ╗ŃüîńŞÇŠľ╣šÜäŃüźŠ▒║ň«ÜŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃü»ŃüžŃüŹŃüÜŃÇüń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃü«ňÉîŠäĆŃéĺňżŚŃéőŃüőŃÇüňŐ┤ńŻ┐ÚľôŃü«š┤Ťń║ëŔžúŠ▒║ŠęčÚľóŃüžŃüéŃéőń╗▓ŔúüŠęčÚľó´╝łEinigungsstelle´╝ëŃü«Š▒║ň«ÜŃéĺňżůŃüčŃü¬ŃüĹŃéîŃü░Ńü¬ŃéŐŃüżŃüŤŃéôŃÇéň«čŔ│¬šÜäŃüźŃÇüń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃüîŃüôŃéîŃéëŃü«ń║őÚáůŃüźň»żŃüŚŃüŽń║őň«čńŞŐŃü«ŠőĺňÉŽŠĘęŃéĺŠîüŃüĄŃüôŃüĘŃüźŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ňů▒ňÉîŠ▒║ň«ÜŠĘęŃü«ňůĚńŻôšÜäŃü¬ň»żŔ▒íŃüźŃü»ŃÇüń╗ąńŞőŃü«ŃééŃü«ŃüîňÉźŃüżŃéîŃüżŃüÖŃÇé
- ňžőŠąşŃüŐŃéłŃü│šÁ銹şŠÖéňł╗ŃÇüń╝ĹŠćęŠÖéÚľôŃü«ÚůŹšŻ«ŃÇüŃüŐŃéłŃü│ń║őŠąşŠëÇňćůŃü«ňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŃü«ŔçĘŠÖéšÜäŃü¬ščşšŞ«ŃüżŃüčŃü»ň╗ÂÚĽĚŃÇé
- Ŕ│âÚçĹŔĘłš«ŚŃü«Šľ╣Š│ĽŃÇüŃüŐŃéłŃü│ňç║ŠŁąÚźśŠëĽŃüäňłÂň║ŽŃéĺňÉźŃéÇŔ│âÚçĹňÄčňëçŃü«ŔĘşň«ÜŃÇé
- ňżôŠąşňôíŃü«ŔâŻňŐŤŃüżŃüčŃü»ŔíîňőĽŃé嚍úŔŽľŃüÖŃéőŃüčŃéüŃüźńŻ┐šöĘŃüĽŃéîŃéőŠŐÇŔíôŔúůšŻ«Ńü«ň░Äňůą´╝łńżő´╝ÜšŤúŔŽľŃéźŃâíŃâęŃÇüń║║ń║őŔęĽńżíŃéŻŃâĽŃâłŃéŽŃéžŃéó´╝ëŃÇé
ňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŃéäń╝ĹŠćęŃü«ÚůŹšŻ«ŃÇüŔęĽńżíŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃü«ň░ÄňůąŃü¬ŃüęŃÇüŠŚąŠťČŃü«šÁîňľÂŔÇůŃüîŃÇîš«íšÉćŠĘęŃÇŹŃü«š»äšľçŃüĘŔÇâŃüłŃéőń║őÚáůŃüźń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃüîŠĚ▒ŃüĆÚľóńŞÄŃüÖŃéőŃüčŃéüŃÇüŠŚąňŞŞšÜäŃü¬HRš«íšÉćŃüőŃéëňĄžŔŽĆŠĘíŃü¬šÁäš╣öňĄëŠŤ┤ŃüżŃüžŃÇüŃüéŃéëŃéćŃéőŠäĆŠÇŁŠ▒║ň«ÜŃü«Ńé╣ŃâöŃâ╝ŃâëŃüîńŻÄńŞőŃüŚŃÇüňŐ┤ńŻ┐š┤Ťń║ëŃü«Ńâ¬Ńé╣Ńé»ŃüîÚźśŃüżŃéőňĆ»Ŕ⯊ǞŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ń║║ń║őŃüŐŃéłŃü│šÁłšÜäń║őÚáůŃüźŃüŐŃüĹŃéőÚľóńŞÄŠĘę
ń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃü»ŃÇüń║║ń║őń║őÚáůŃüźÚľóŃüŚŃüŽŃééňÉîŠäĆŠĘęŃé䚼░Ŕş░šö│šźőŠĘęŃéĺŠîüŃüíŃüżŃüÖŃÇéšë╣ŃüźŃÇüŠÄíšöĘ´╝łEinstellung´╝ëŃéäňćŹÚůŹšŻ«´╝łUmgruppierung´╝ëŃü«ÚÜŤŃÇüÚŤçšöĘńŞ╗Ńü»ń║őňëŹŃüźňžöňôíń╝ÜŃüźÚÇÜščąŃüŚŃÇüňÉîŠäĆŃéĺňżŚŃéőň┐ůŔŽüŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ŃüżŃüčŃÇüń╝üŠąşŃü«šÁłšŐŠ│üŃüźÚľóŃüŚŃüŽŃééŃÇüńŞÇň«ÜŔŽĆŠĘíń╗ąńŞŐŃü«ń╝üŠąşŃüžŃü»šÁłňžöňôíń╝Ü´╝łWirtschaftsausschuss´╝ëŃü«ŔĘşšŻ«ŃüîŠ▒éŃéüŃéëŃéîŃüżŃüÖŃÇéÚŤçšöĘńŞ╗Ńü»ŃÇüňĄžŔŽĆŠĘíŃü¬šÁäš╣öňĄëŠŤ┤ŃÇüń║őŠąşň揚ĚĘŃÇüňĚąňá┤ÚľëÚÄľŃü¬ŃüęŃü«ŔĘłšö╗´╝łBetrVG ┬ž 111´╝ëŃüźŃüĄŃüäŃüŽŃÇüń║őňëŹŃüźń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃüźňîůŠőČšÜäŃü¬Šâůňá▒ŠĆÉńżŤŃüĘňŹöŔş░ŃéĺŔíîŃéĆŃü¬ŃüĹŃéîŃü░Ńü¬ŃéŐŃüżŃüŤŃéôŃÇéŃüôŃéîŃéëŃü«ňĄëŠŤ┤ŃüîňżôŠąşňôíŃüźńŞŹňłęšŤŐŃéĺŃééŃüčŃéëŃüÖňá┤ňÉłŃÇüšĄżń╝ÜŔĘłšö╗´╝łSozialplan´╝ëŃü«ńŻťŠłÉšżęňőÖŃüîšÖ║šöčŃüŚŃüżŃüÖŃÇ隥żń╝ÜŔĘłšö╗Ńü»ŃÇüňŻ▒Úč┐ŃéĺňĆŚŃüĹŃéőňżôŠąşňôíŃüŞŃü«šÁłšÜäŃü¬ŔúťňäčŃéĺň«ÜŃéüŃéőŃééŃü«ŃüžŃüéŃéŐŃÇüšÁîňľÂň揚ĚĘŃü«Ńé│Ńé╣ŃâłŃé嚍┤ŠÄąšÜäŃüźŠ▒║ň«ÜŃüąŃüĹŃéőŔŽüš┤áŃüĘŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ŃüŁŃü«ń╗ľŃü«ŃâëŃéĄŃâäŃüźŃüŐŃüĹŃéőÚçŹŔŽüŃü¬ňżôŠąşňôíń┐ŁŔşĚňłÂň║Ž
šľżšŚůŠÖéŃü«Ŕ│âÚçĹšÂÖšÂÜŠö»ŠëĽ´╝łEntgeltfortzahlungsgesetz – EntgFG´╝ëŃü«šżęňőÖ
ŃâëŃéĄŃâäŃü«šÂÖšÂÜŔ│âÚçĹŠö»ŠëĽŠ│Ľ´╝łEntgeltfortzahlungsgesetz, EntgFG´╝ëŃü»ŃÇüňżôŠąşňôíŃü«šľżšŚůŠÖéŃü«ŠëÇňżŚń┐ŁŔşĚŃéĺňÄ│Šá╝Ńüźň«ÜŃéüŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéňżôŠąşňôíŃüůŠ░ŚŃéäŠÇ¬ŠłĹŃüźŃéłŃéŐňŐ┤ňőÖńŞŹŔâŻŃüĘŃü¬ŃüúŃüčňá┤ňÉłŃÇüÚŤçšöĘńŞ╗Ńü»6ÚÇ▒Úľô´╝ł42ŠÜŽŠŚą´╝ëŃüźŃéĆŃüčŃéŐŃÇüŔ│âÚçĹŃü«ňůĘÚ폴╝ł100%´╝ëŃéĺšÂÖšÂÜŃüŚŃüŽŠö»ŠëĽŃüćšżęňőÖŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ŠŚąŠťČŃüžŃü»ŃÇüšŚůŠČáŠÖéŃü«Ŕ│âÚçĹŔúťňäčŃü»ń╝üŠąşŃü«ŔúüÚçĆŃéäň░▒ŠąşŔŽĆňëçŃüźňžöŃüşŃéëŃéîŃéőÚâĘňłćŃüîňĄžŃüŹŃüäŃüžŃüÖŃüîŃÇüŃâëŃéĄŃâäŃüžŃü»ŃüôŃéîŃüîŠ│Ľň«ÜŃü«ň┐ůÚáłŃé│Ńé╣ŃâłŃüĘŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇéÚŤçšöĘńŞ╗ŃüźŃéłŃéő6ÚÇ▒ÚľôŃü«Šö»ŠëĽšżęňőÖŃüîšÁéń║ćŃüŚŃüčňżîŃééňŐ┤ňőÖńŞŹŔâŻŃüîšÂÜŃüĆňá┤ňÉłŃÇüŃüŁŃü«ňżîŃü»Š│Ľň«Üňüąň║Ěń┐ŁÚÖ║šÁäňÉł´╝łGKV´╝ëŃüőŃéëšľżšŚůŠëőňŻô´╝łKrankengeld´╝ëŃüîŠö»šÁŽŃüĽŃéîŃüżŃüÖŃÇéšľżšŚůŠëőňŻôŃü»ŃÇüÚÇÜňŞŞŃÇüšĚĆňĆÄňůąŃü«70%ŃÇüŃüčŃüáŃüŚš┤öňĆÄňůąŃü«90%ŃéĺńŞŐÚÖÉŃüĘŃüŚŃüŽŃüŐŃéŐ ŃÇüŠťÇÚĽĚŃüž3ň╣┤ń╗ąňćůŃüź78ÚÇ▒ÚľôŃüżŃüžňĆŚšÁŽňĆ»ŔâŻŃüžŃüÖŃÇéŃüôŃü«ňłÂň║ŽŃü»ŃÇüń║łŠťčŃüŤŃüČŠČáňőĄŃüîń╝üŠąşŃü«ŃéşŃâúŃââŃéĚŃâąŃâĽŃâşŃâ╝ŃüŐŃéłŃü│ń║║ń║őŃé│Ńé╣ŃâłŔĘłšö╗ŃüźšŤ┤ŠÄąšÜäŃü¬ňŻ▒Úč┐ŃéĺňĆŐŃü╝ŃüÖŃüôŃüĘŃéĺŠäĆňĹ│ŃüŚŃüżŃüÖŃÇé┬á
Š│ĽňżőŃüžń┐ŁŔĘ╝ŃüĽŃéîŃü芝ëšÁŽń╝ĹŠÜçŃü«ŠĘęňłę´╝łBundesurlaubsgesetz – BUrlG´╝ë
ÚÇúÚéŽń╝ĹŠÜçŠ│Ľ´╝łBundesurlaubsgesetz, BUrlG´╝ëŃüźňč║ŃüąŃüŹŃÇüňżôŠąşňôíŃüźŃü»ŠťÇńŻÄÚÖÉŃü«ŠťëšÁŽń╝ĹŠÜçŃüîŠ│ĽňżőŃüžń┐ŁŔĘ╝ŃüĽŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéÚÇ▒5ŠŚąňőĄňőÖŃü«ňżôŠąşňôíŃü«ňá┤ňÉłŃÇüŠ│ĽňżőŃüźŃéłŃéŐŠťÇńŻÄ20ňŐ┤ň⏊ŚąŃü«ŠťëšÁŽń╝ĹŠÜçŃüîń┐ŁŔĘ╝ŃüĽŃéîŃüŽŃüŐŃéŐ ŃÇüŃüôŃéîŃü»ňąĹš┤äŃüźŃéłŃéŐŃüôŃéîŃéłŃéŐńŞŹňłęŃü¬ŠŁíń╗ÂŃéĺŔĘşň«ÜŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃüîŃüžŃüŹŃü¬ŃüäńŞőÚÖÉňÇĄŃüžŃüÖŃÇéŃâëŃéĄŃâäŃü«ňŐ┤ňâŹŔÇůŃüąŠťČŃéäOECDň╣│ňŁçŃüĘŠ»öŔ╝âŃüŚŃüŽňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŃüîŔĹŚŃüŚŃüĆščşŃüäŔŽüňŤáŃü«ńŞÇŃüĄŃüĘŃüŚŃüŽŃÇüŃüôŃü«ŃéłŃüćŃü¬ňÄ│Šá╝Ńü¬ňŐ┤ň⏊ÖéÚľôŔŽĆňłÂŃüĘŠëőňÄÜŃüäń╝ĹŠÜçňłÂň║ŽŃü«ňşśňťĘŃüîŠîÖŃüĺŃéëŃéîŃüżŃüÖŃÇé
ŃüżŃüĘŃéü
ŃâëŃéĄŃâäŃü«ňŐ┤ň⏊│ĽŃü»ŃÇüKSchGŃüźňč║ŃüąŃüĆŔžúÚŤçń┐ŁŔşĚŃü«ňÄ│Šá╝ŃüĽŃÇüArbZGŃüźŃéłŃéőňŐ┤ň⏊ÖéÚľôš«íšÉćŃü«ÚŁ×ŠčöŔ╗čŠÇžŃÇüŃüŁŃüŚŃüŽBetrVGŃüźňč║ŃüąŃüĆń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃü«ň╝ĚňŐŤŃü¬ňů▒ňÉîŠ▒║ň«ÜŠĘęŃüĘŃüäŃüćŃÇüńŞëŃüĄŃü«Š▒║ň«ÜšÜäŃü¬šë╣ňż┤ŃüźŃéłŃüúŃüŽŃÇüŠŚąŠťČŃü«ňŐ┤ň⏊│ĽńŻôš│╗ŃüĘŃü»ńŞÇšĚÜŃéĺšö╗ŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ŠŚąŠťČŃü«šÁîňľÂŔÇůŃüîŃÇîšÁîňľÂňłĄŠľşŃÇŹŃéäŃÇîš«íšÉćŠĘęŃÇŹŃüĘŔÇâŃüłŃéőÚáśňččŃüîŃÇüŃâëŃéĄŃâäŃüžŃü»Š│ĽňżőŃéäń║őŠąşŠëÇňžöňôíń╝ÜŃü«ňÉîŠäĆŠĘęŃüźŃéłŃüúŃüŽňÄ│ŃüŚŃüĆňłÂš┤äŃüĽŃéîŃéőŃüĘŃüäŃüćń║őň«čŃéĺŃÇüŠłŽšĽąšşľň«ÜŃü«Š«ÁÚÜÄŃüőŃéëš╣öŃéŐŔż╝ŃéÇň┐ůŔŽüŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇéšë╣ŃüźŃÇüń║║ń║őŔęĽńżíŃéĚŃé╣ŃâćŃâáŃü«ň░ÄňůąŃéäŃÇüšÁîňľÂńŞŐŃü«šÉćšö▒ŃüźŃéłŃéőń║║ňôíňëŐŠŞŤŃü»ŃÇüňÄ│Šá╝Ńü¬ŠëőšÂÜŃüŹšÜäŔŽüń╗´╝łŠťÇšÁéŠëőŠ«ÁŃü«ňÄčňëçŃÇüšĄżń╝ÜšÜäÚüŞŠŐ×´╝ëŃéĺŃé»Ńâ¬ŃéóŃüŚŃü¬ŃüĹŃéîŃü░ŃÇüÚźśÚíŹŃü¬Ŕ│áňäčŃâ¬Ńé╣Ńé»Ńéĺń╝┤ŃüćŃüôŃüĘŃüźŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ŃüôŃéîŃéëŃü«ŔĄçÚŤĹŃü¬Š│Ľń╗Ą´╝łKSchG, ArbZG, BetrVG´╝ëŃü«ÚüęšöĘŃéĺŔ¬ĄŃéőŃüôŃüĘŃü»ŃÇüń╝üŠąşŃü«ń┐íšöĘŃüĘšÁłšÜäŃü¬ň«ëň«ÜŠÇžŃéĺŠĆ║ŃéőŃüîŃüÖÚçŹňĄžŃü¬Ńâ¬Ńé╣Ńé»ŃüĘŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃÇéŃâëŃéĄŃâäŃüžŃü«ń║őŠąşň▒ĽÚľőŃéäšÁäš╣öň揚ĚĘŃéĺÚÇ▓ŃéüŃéőŃüźŃüéŃüčŃüúŃüŽŃü»ŃÇüšĆżňť░Š│ĽŃü«ňÄ│Šá╝Ńü¬ŠëőšÂÜŃüŹŔŽüń╗ÂŃüĘŃÇüŠŚąŠťČšÜäŃü¬šÁîňľÂŠľçňîľŃüĘŃü«Ńé«ŃâúŃââŃâŚŃéĺňčőŃéüŃéőŃüčŃéüŃü«Š│ĽňőÖŃéÁŃâŁŃâ╝ŃâłŃüîńŞŹňĆ»ŠČáŃüžŃüÖŃÇé
ŃéźŃâćŃé┤Ńâ¬Ńâ╝: ITŃâ╗ŃâÖŃâ│ŃâüŃâúŃâ╝Ńü«ń╝üŠąşŠ│ĽňőÖ