ÕÅ░µ╣¥Òü«Õè┤Õâìµ│òÒü«ÞºúÞ¬¼

ÕÅ░µ╣¥Òü»ÒÇüÕ£░þÉåþÜäÒü¬Þ┐æµÄѵǺÒéäµûçÕîûþÜäÞª¬ÕÆîµÇºÒüïÒéëÒÇüµùÑþ│╗õ╝üµÑ¡Òü½Òü¿ÒüúÒüªÚ¡àÕèøþÜäÒü¬µèòÞ│çÕàêÒü¿ÒüùÒüªÞ¬ìÞ¡ÿÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒüùÒüïÒüùÒÇüÒüØÒü«Õè┤Õâìµ│òÒü»µùѵ£¼Òü¿µ»öÞ╝âÒüùÒüªÕè┤ÕâìÞÇàõ┐ØÞ¡ÀÒü½µÑÁÒéüÒüªÕÄ│µá╝ÒüºÒüéÒéèÒÇüÕ«ëµÿôÒü¬ÒÇîµùѵ£¼Õ╝ÅÒÇìÒü«Õè┤ÕïÖþ«íþÉåÒü»ÚçìÕñºÒü¬µ│òþÜäÒâ¬Òé╣Òé»ÒéƵïøÒüÅÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
µ£¼Þ¿ÿõ║ïÒü»ÒÇüÕÅ░µ╣¥Õè┤Õâìµ│òÒü«Õƒ║þñÄÒÇüþë╣Òü½µùÑþ│╗õ╝üµÑ¡Òüîµ│¿µäÅÒüÖÒü╣Òüìõ©╗ÞªüÒü¬Þ½ûþé╣ÒéÆÕñÜÞºÆþÜäÒü½Õêåµ×ÉÒüùÒÇüÕ«ƒÞÀÁþÜäÒü¬Òâ¬Òé╣Òé»Õø×Úü┐þ¡ûÒü¿Òé│Òâ│ÒâùÒâ®ÒéñÒéóÒâ│Òé╣Õ╝ÀÕîûÒü«µîçÚçØÒéƵÅÉõ¥øÒüùÒü¥ÒüÖÒÇéÕìÿÒü¬Òéïµ│òõ╗ñÞºúÞ¬¼Òü½þòÖÒü¥ÒéëÒüÜÒÇüµ│òµö╣µ¡úÒü«ÞâîµÖ»ÒéäÕè┤õ¢┐þ┤øõ║ëÒü«þÅ¥þèÂÒÇüÒüØÒüùÒüªÞªïÚüÄÒüöÒüòÒéîÒüîÒüíÒü¬µ¢£Õ£¿þÜäÒâ¬Òé╣Òé»Òü½ÒüñÒüäÒüªÒééµÀ▒ÒüŵÄÿÒéèõ©ïÒüÆÒéïÒüôÒü¿ÒüºÒÇüÞ¬¡ÞÇàÒü«þÜ嵺ÿÒüîÕÅ░µ╣¥õ║ïµÑ¡ÒéƵêÉÕèƒÒü½Õ░ÄÒüÅÒüƒÒéüÒü«þó║Õø║ÒüƒÒéïþƒÑÞ¡ÿÕƒ║þøñÒéÆþ»ëÒüÅõ©ÇÕè®Òü¿Òü¬ÒéïÒüôÒü¿ÒéÆþø«µîçÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé
Òü¬ÒüèÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«Õîàµï¼þÜäÒü¬µ│òÕêÂÕ║ªÒü«µªéÞªüÒü»õ©ïÞ¿ÿÞ¿ÿõ║ïÒü½ÒüªÒü¥Òü¿ÒéüÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüôÒü«Þ¿ÿõ║ïÒü«þø«µ¼í
ÕÅ░µ╣¥Õè┤Õâìµ│òÒü«Õà¿õ¢ôÕâÅÒü¿Õƒ║µ£¼þÉåÕ┐Á
Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òÒü«ÕêÂÕ«Ü
ÕÅ░µ╣¥Õè┤Õâìµ│òÒü«õ©¡Õ┐âÒéÆÒü¬ÒüÖÒü«Òü»ÒÇüÕè┤ÕâìµØíõ╗ÂÒü«µ£Çõ¢ÄÕƒ║µ║ûÒéÆÕ«ÜÒéüÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàÒü«µ¿®Õê®ÒéÆõ┐ØÚÜ£ÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒéÆþø«þÜäÒü¿ÒüùÒüª1984Õ╣┤7µ£ê30µùÑÒü½ÕêÂÕ«ÜÒüòÒéîÒüƒÒÇîÕè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│ò´╝êÕï×ÕïòÕƒ║µ║ûµ│ò´╝ëÒÇìÒüºÒüÖÒÇéÒüôÒü«µ│òÕ¥ïÒü«ÞªÅÕ«ÜÒü½ÚüòÕÅìÒüÖÒéïÕè┤ÕâìµØíõ╗ÂÒü»þäíÕè╣Òü¿ÒüòÒéîÒÇüõ╝üµÑ¡ÒüîÕè┤ÕâìÞÇàÒü¿õ║ñÒéÅÒüÖÕè┤ÕâìÕÑæþ┤äÒéäÕ░▒µÑ¡ÞªÅÕëçÒü»ÒÇüÒüôÒü«µ£Çõ¢ÄÕƒ║µ║ûÒéÆõ©ïÕø×ÒéïÒüôÒü¿Òü»Þ¿▒ÒüòÒéîÒü¥ÒüøÒéôÒÇé
ÒüôÒü«Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òÒü«ÕêÂÕ«ÜÒü½Òü»ÒÇüÚçìÞªüÒü¬µ¡┤ÕÅ▓þÜäÞâîµÖ»ÒüîÕ¡ÿÕ£¿ÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé1970Õ╣┤õ╗úÒüïÒéë1980Õ╣┤õ╗úÒü½ÒüïÒüæÒüªÒÇüÕÅ░µ╣¥ÒüîÕ»¥þ▒│Þ▓┐µÿôÒüºÕÀ¿ÚíìÒü«Ú╗ÆÕ¡ùÒéÆÞ¿êõ©èÒüÖÒéïõ©¡ÒÇüþ▒│Õø¢Òü«õ©ÇÚâ¿Òü«Õè┤ÕâìþÁäÕÉêÒü»ÒÇüÕÅ░µ╣¥õ╝üµÑ¡Òü«õ¢ÄÒé│Òé╣Òâêþ½Âõ║ëÕèøÒüîÕèúµé¬Òü¬Õè┤ÕâìµØíõ╗ÂÒü«õ©èÒü½µêÉÒéèþ½ïÒüúÒüªÒüäÒéïÒü¿ÒüùÒüªÒÇüþ▒│Õø¢Þ▓┐µÿôµ│ò301µØíÚáàÒü¬Òü®ÒéƵá╣µïáÒü½Õè┤ÕâìµØíõ╗ÂÒü«µö╣ÕûäÒéƵ▒éÒéüÒéïÕ£ºÕèøÒéÆÒüïÒüæÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÒüôÒü«Õø¢ÚÜøþÜäÒü¬Òé│Òâ│ÒâùÒâ®ÒéñÒéóÒâ│Òé╣ÞªüÞ½ïÒüîÒÇüÕÅ░µ╣¥µö┐Õ║£Òü½Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òÒü«ÕêÂÕ«ÜÒéÆõ┐âÒüùÒüƒÞªüÕøáÒü«õ©ÇÒüñÒü¿ÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒü«ÒéêÒüåÒü¬þÁîþÀ»ÒüïÒéëÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«Õè┤Õâìµ│òÒü»ÒÇüÕìÿÒü¬ÒéïÕø¢Õåàµö┐þ¡ûÒüºÒü»Òü¬ÒüÅÒÇüÕø¢ÚÜøþÜäÒü¬ÞªÅþ»äÒü¿Õè┤ÕâìÞÇàõ┐ØÞ¡ÀÒüîÕ¢ôÕêØÒüïÒéëÕ╝ÀÒüŵäÅÞ¡ÿÒüòÒéîÒüªÒüäÒéïÒü¿ÒüäÒüåþë╣Õ¥┤ÒéƵîüÒüúÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒüùÒüƒÒüîÒüúÒüªÒÇüµùÑþ│╗õ╝üµÑ¡Òü»ÒÇüµùѵ£¼Òü«Õø¢Õåàµ│òÕƒ║µ║ûÒüºÒü»Òü¬ÒüÅÒÇüÒéêÒéèÕÄ│ÒüùÒüäÕø¢ÚÜøþÜäÒü¬Õè┤ÕâìÞªÅþ»äÒü½þàºÒéëÒüùÒüªÞç¬þñ¥Òü«µàúÞíîÒéÆÞ®òõ¥íÒüÖÒéïÕ┐àÞªüÒüîÒüéÒéïÒü¿ÒüäÒüêÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒéîÒü»ÒÇüÕìÿÒü¬Òéïµ│òþÜäþ¥®ÕïÖÒü«Õ▒ÑÞíîÒéÆÞÂàÒüêÒÇüõ╝üµÑ¡Òü«þñ¥õ╝ÜþÜäÞ▓¼õ╗╗´╝êCSR´╝ëÒü«õ©ÇþÆ░Òü¿ÒüùÒüªµìëÒüêÒéïÒüôÒü¿ÒüîÒÇüÕÅ░µ╣¥õ║ïµÑ¡Òü½ÒüèÒüæÒéïµîüþÂÜÕÅ»Þ⢵ǺÒéÆþó║õ┐ØÒüÖÒéïõ©èÒüºõ©ìÕÅ»µ¼áÒüºÒüéÒéïÒüôÒü¿ÒéƵäÅÕæ│ÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé┬á
Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òÒü«Úü®þö¿Õ»¥Þ▒íÒü¿õ©╗ÞªüÒü¬ÕåàÕ«╣
Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òÒü»ÒÇüÕî╗Õ©½ÒéäÕñûÕø¢õ║║õ╗ïÞ¡ÀÕè┤ÕâìÞÇàÒü¬Òü®õ©ÇÚâ¿Òü«õ¥ïÕñûÒéÆÚÖñÒüìÒÇüÕø¢þ▒ìÒéÆÕòÅÒéÅÒüÜÒüÖÒü╣ÒüªÒü«Õè┤ÕâìÞÇàÒü½Úü®þö¿ÒüòÒéîÒü¥ÒüÖÒÇéÒü¥ÒüƒÒÇüÕà¼ÕïÖÚâ¿ÚûÇÒü½ÒüèÒüäÒüªÒééÒÇüÞ翵ÖéÞüÀÕôíÒéäµèÇÕÀÑÒÇüÕÅ©µ®ƒÒü¬Òü®Òü½Òü»Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òÒüîÚü®þö¿ÒüòÒéîÒéïÕá┤ÕÉêÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òÒü»ÒÇüÕè┤ÕâìÕÑæþ┤äÒü«þÀáþÁÉÒüïÒéëÒÇüÞ│âÚçæÒÇüÕè┤ÕâìµÖéÚûôÒÇüõ╝æµùÑÒÇüõ╝æµÜçÒÇüþü¢Õ«│Þú£ÕäƒÒÇüÕ░▒µÑ¡ÞªÅÕëçÒÇüÞºúÚøçÒÇüÚÇÇÞüÀÚçæÒü½Þç│ÒéïÒü¥ÒüºÒÇüÕè┤ÕâìµØíõ╗ÂÒü«Õ║âþ»äÒü¬õ║ïÚáàÒéÆþÂ▓þ¥àÒüùÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé1996Õ╣┤Òü«Õêصö╣µ¡úõ╗ÑÚÖìÒÇüÚü®þö¿þ»äÕø▓Òü«µïíÕñºÒÇüÕñëÕ¢óÕè┤ÕâìµÖéÚûôÕêÂÒü«Õ░ÄÕàÑÒÇüÞ│âÚçæÒâ╗ÚÇÇÞüÀÚçæÞªÅÕ«ÜÒü«õ┐«µ¡úÒü¬Òü®ÒÇüþñ¥õ╝ÜþÁêÒü«ÕñëÕîûÒü½Õ»¥Õ┐£ÒüÖÒéïÒüƒÒéüÒü«µö╣µ¡úÒüîþ╣░ÒéèÞ┐öÒüòÒéîÒüªÒüìÒü¥ÒüùÒüƒÒÇé
Þ┐æÕ╣┤ÒÇüÕÅ░µ╣¥ÒüºÒü»Õè┤Õâìþ┤øõ║ëÒüîµ┤╗þÖ║ÕîûÒüùÒüªÒüèÒéèÒÇüÕè┤ÕâìþÁäÕÉêÒü«µ┤╗ÕïòÒééÚíòÞæùÒü½Òü¬ÒüúÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒüƒÒü¿ÒüêÒü░ÒÇü2019Õ╣┤Òü«ÒâüÒâúÒéñÒâèÒé¿ÒéóÒâ®ÒéñÒâ│ÒéäÚòÀµáäÞê¬þ®║ÒüºÒü«ÕñºÞªÅµ¿íÒü¬ÒâæÒéñÒâ¡ÒââÒâêÒéäÕ«óÕ«ñõ╣ùÕïÖÕôíÒü«Òé╣ÒâêÒâ®ÒéñÒé¡Òü»ÒÇüÒâíÒâçÒéúÒéóÒüºÒééÕñºÒüìÒüÅÕÅûÒéèõ©èÒüÆÒéëÒéîÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÒüôÒéîÒü»ÒÇüµ│òÕêÂÕ║ªÒü«µò┤ÕéÖÒü¿ÕÉîµÖéÒü½ÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàÒü«µ¿®ÕꮵäÅÞ¡ÿÒüîÚ½ÿÒü¥ÒüúÒüªÒüäÒéïÒüôÒü¿ÒéƵÿÄþó║Òü½þñ║ÕöåÒüùÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÕè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òÒü«ÕÄ│µá╝Òü¬Õè┤ÕâìÞÇàõ┐ØÞ¡Àõ©╗þ¥®Òü»ÒÇüµäÅÕø│ÒüøÒü¼Õë»õ¢£þö¿ÒéÆþöƒÒü┐ÒÇüÕè┤õ¢┐ÕÅîµû╣Òü«õ©ìµ║ÇÒéƵïøÒüÅÒüôÒü¿ÒééÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒüîÒÇüÒüØÒéîÒüîÞ┐àÚǃÒü¬µ│òµö╣µ¡úÒü©Òü¿þ╣ïÒüîÒéèÒÇüÕ©©Òü½µ│òÕ¥ïÒüîÕïòþÜäÒü¬ÒééÒü«Òü¿ÒüùÒüªÕ¡ÿÕ£¿ÒüùÒüªÒüäÒéïÒüôÒü¿ÒéƵäÅÕæ│ÒüùÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒü«ÒüƒÒéüÒÇüµùÑþ│╗õ╝üµÑ¡Òü»ÕÅ░µ╣¥Õè┤Õâìµ│òÒéÆÚØÖþÜäÒü¬µ│òÞªÅÚøåÒü¿ÒüùÒüªµìëÒüêÒéïÒü«ÒüºÒü»Òü¬ÒüÅÒÇüÕ©©Òü½µ£Çµû░Òü«ÕïòÕÉæÒéÆÞ┐¢ÒüåÒüôÒü¿Òüîõ©ìÕÅ»µ¼áÒüºÒüÖÒÇéÚ½ÿÒü¥ÒéïÕè┤õ¢┐þ┤øõ║ëÒéäÚá╗þÖ║ÒüÖÒéïÕè┤Õâìµñ£µƒ╗Òü»ÒÇüµ│òµö╣µ¡úÒü«µ│óÒü½õ╣ùÒéèÚüàÒéîÒéïÒüôÒü¿Òü«Òâ¬Òé╣Òé»ÒüîµÑÁÒéüÒüªÚ½ÿÒüäÒüôÒü¿ÒéÆþñ║ÒüùÒüªÒüèÒéèÒÇüÒé│Òâ│ÒâùÒâ®ÒéñÒéóÒâ│Òé╣õ¢ôÕêÂÒéÆþÂÖþÂÜþÜäÒü½Þªïþø┤ÒüùÒÇüµƒöÞ╗ƒÒü½Õ»¥Õ┐£ÒüÖÒéïÒÇîÕïòþÜäÒü¬µ│òÕïÖþ«íþÉåÒÇìÒüîÕ┐àÚáêÒü¿Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÕÅ░µ╣¥Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òÒü«µö╣µ¡ú´╝ê2017Õ╣┤Òâ╗2018Õ╣┤´╝ë

2017Õ╣┤Òü«µö╣µ¡úÒü¿ÒÇîõ©Çõ¥ïõ©Çõ╝æÒÇìÒü«Õ░ÄÕàÑ
2016Õ╣┤12µ£êÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàÒü«ÚÇ▒õ╝æõ║îµùÑÕêÂÒéÆÕ¥╣Õ║òÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒéÆþø«þÜäÒü¿ÒüùÒüªÒÇîõ©Çõ¥ïõ©Çõ╝æÒÇì´╝êÚÇ▒õ╝æõ║îµùÑÕê´╝ëÒüîÕ░ÄÕàÑÒüòÒéîÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÒüôÒü«µö╣µ¡úÒüºÒü»ÒÇüõ╝æµü»µùÑÒü½ÒüèÒüæÒéﵫïµÑ¡õ╗úÒü«Þ¿êþ«ùµû╣µ│òÒüîÒÇüÕ«ƒÕè┤ÕâìµÖéÚûôÒüºÒü»Òü¬ÒüÅÒÇî4µÖéÚûôõ╗ÑÕåàÒü»4µÖéÚûôÒüºÞ¿êþ«ùÒÇü4µÖéÚûôÒéÆÞÂàÒüê8µÖéÚûôõ╗ÑÕåàÒü»8µÖéÚûôÒüºÞ¿êþ«ùÒÇü8µÖéÚûôÒéÆÞÂàÒüê12µÖéÚûôõ╗ÑÕåàÒü»12µÖéÚûôÒüºÞ¿êþ«ùÒÇìÒü¿ÒüäÒüåÕÄ│µá╝Òü¬ÒÇîµÖéÚûôÕìÿõ¢ìÕêçÒéèõ©èÒüƵû╣Õ╝ÅÒÇìÒüîµÄíþö¿ÒüòÒéîÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÒüôÒü«ÕêÂÕ║ªÒü»ÒÇüõ╝üµÑ¡Õü┤Òü½Òü»õ║║õ╗ÂÞ▓╗ÕóùÕèáÒü¿Õè┤ÕïÖþ«íþÉåÒü«µƒöÞ╗ƒµÇºµ¼áÕªéÒéƵïøÒüìÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàÕü┤Òü½Òü»õ╝æµü»µùÑÒü½ÕâìÒüŵ®ƒõ╝ÜÒüøÒéèÒÇüÕÅÄÕàÑÒüøÕ░æÒüùÒüƒÒüôÒü¿Òü½Õ»¥ÒüÖÒéïõ©ìµ║ÇÒéÆÒééÒüƒÒéëÒüùÒü¥ÒüùÒüƒÒÇé
ÒüôÒü«ÒéêÒüåÒü¬Õè┤õ¢┐ÕÅîµû╣ÒüïÒéëÒü«Õ╝ÀÒüäÕÅìþÖ║ÒéÆÕÅùÒüæÒÇüÕÅ░µ╣¥µö┐Õ║£Òü»ÒéÅÒüÜÒüï1Õ╣┤Õ¥îÒü«2017Õ╣┤11µ£êÒü½Õåìµö╣µ¡úµíêÒéƵÅÉÕç║ÒüùÒÇü2018Õ╣┤1µ£êÒü½ÕÅ»µ▒║ÒÇüÕÉîÕ╣┤3µ£ê1µùÑÒü½µû¢ÞíîÒüùÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÒüôÒü«õ©ÇÚÇúÒü«µ│òµö╣µ¡úÒü«µ¡┤ÕÅ▓Òü»ÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«Õè┤ÕâìþÆ░ÕóâÒüîÕìÿÒü¬Òéïµ│òõ╗ñÚüÁÕ«êÒéÆÞÂàÒüêÒüƒÒÇüÕïòþÜäÒüºµö┐µ▓╗þÜäÒü¬ÒâÉÒâ®Òâ│Òé╣Òü«õ©èÒü½µêÉÒéèþ½ïÒüúÒüªÒüäÒéïÒüôÒü¿ÒéÆþñ║ÒüùÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéµ│òÕ¥ïÒüîþÅ¥Õ«ƒÒü«þÁêµ┤╗ÕïòÒéäÕè┤ÕâìµàúÞíîÒü¿õ╣ûÚøóÒüÖÒéïÒü¿ÒÇüµäÅÕø│ÒüøÒü¼Õë»õ¢£þö¿ÒüîþöƒÒüÿÒÇüÒüØÒéîÒüîÞ┐àÚǃÒü¬Õåìµö╣µ¡úÒü½ÒüñÒü¬ÒüîÒéïÒü¿ÒüäÒüåÒéÁÒéñÒé»Òâ½Òü»ÒÇüµùÑþ│╗õ╝üµÑ¡ÒüîÕ©©Òü½µ£Çµû░Òü«µ│òÕïòÕÉæÒéƵ│¿ÞªûÒüÖÒéïÕ┐àÞªüÒüîÒüéÒéïÒüôÒü¿ÒéÆþñ║ÕöåÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé┬á
2018Õ╣┤Òü«Õåìµö╣µ¡úÒü¿ÒÇîÕøøõ©ìÕñëÒÇìÒÇîÕøøÕ╝¥µÇºÒÇì
2018Õ╣┤Òü«Õåìµö╣µ¡úÒü»ÒÇüÒÇîÕøøõ©ìÕñëÒÇì´╝굡úÕ©©ÕÀѵÖéÒÇüÚÇ▒õ╝æõ║îµùÑÕăÕëçÒÇüÕèáþÅ¡þÀÅÕÀѵÖéÒÇüÕèáþÅ¡Þ▓╗þÄç´╝ëÒü¿ÒÇîÕøøÕ╝¥µÇºÒÇì´╝êÕèáþÅ¡Õ╝¥µÇºÒÇüµÄÆþÅ¡Õ╝¥µÇºÒÇüÞ╝¬þÅ¡ÚûôÚÜöÕ╝¥µÇºÒÇüþë╣õ╝æÚüïþö¿Õ╝¥µÇº´╝ëÒéƵÄ▓ÒüÆÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàõ┐ØÞ¡ÀÒü«ÕăÕëçÒéÆþ¡µîüÒüùÒüñÒüñÒÇüõ╝üµÑ¡þÁîÕûÂÒü½õ©ÇÕ«ÜÒü«µƒöÞ╗ƒµÇºÒéƵîüÒüƒÒüøÒéïÒüôÒü¿ÒéÆþø«µîçÒüùÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÕàÀõ¢ôþÜäÒü¬Õñëµø┤þé╣Òü»õ╗Ñõ©ïÒü«ÚÇÜÒéèÒüºÒüÖÒÇéµ£êÒü«µ«ïµÑ¡õ©èÚÖÉÒü»ÕăÕëç46µÖéÚûôÒüºþ¡µîüÒüòÒéîÒü¥ÒüÖÒüîÒÇüÕè┤ÕâìþÁäÕÉêÒü¥ÒüƒÒü»Õè┤õ¢┐õ╝ÜÞ¡░Òü«ÕÉêµäÅÒüîÒüéÒéîÒü░ÒÇüÕìÿµ£êÒüº54µÖéÚûôÒü¥ÒüºÕ╗ÂÚòÀÕÅ»Þâ¢Òü¿Òü¬ÒéèÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÒüƒÒüáÒüùÒÇü3Òâµ£êÒü«þÀŵÖéÚûôÒü«õ©èÚÖÉÒü»138µÖéÚûôÒéÆÞÂàÒüêÒüªÒü»Òü¬ÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇéõ╝æµü»µùÑÒü½ÒüèÒüæÒéﵫïµÑ¡õ╗úÒü«Þ¿êþ«ùµû╣µ│òÒü»ÒÇüµùºµØÑÒü«ÒÇîµÖéÚûôÕìÿõ¢ìÕêçÒéèõ©èÒüƵû╣Õ╝ÅÒÇìÒüîµÆñÕ╗âÒüòÒéîÒÇüÕ«ƒÚÜøÒü«Õè┤ÕâìµÖéÚûôÒü½Õ┐£ÒüÿÒüƒÒÇîÕ«ƒÕè┤ÕâìµÖéÚûôÒâÖÒâ╝Òé╣ÒÇìÒü½Õø×Õ©░ÒüùÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéþë╣ÕêÑõ╝æµÜçÒü½ÒüñÒüäÒüªÒü»ÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàÒü¿õ¢┐þö¿ÞÇàÕÅîµû╣Òü«ÕÉêµäÅÒüîÒüéÒéîÒü░ÒÇüµ£¬µÂêÕîûÕêåÒéÆþ┐îÕ╣┤Õ║ªÒü½þ╣░ÒéèÞÂèÒüÖÒüôÒü¿ÒüîÕÅ»Þâ¢Òü½Òü¬ÒéèÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÒüƒÒüáÒüùÒÇüþ╣░ÒéèÞÂèÒüùÒüƒõ╝æµÜçÒüîþ┐îÕ╣┤Õ║ªµ£½Òü¥ÒüºÒü½µÂêÕîûÒüòÒéîÒü¬ÒüïÒüúÒüƒÕá┤ÕÉêÒÇüõ¢┐þö¿ÞÇàÒü»Þ│âÚçæÒü¿ÒüùÒüªÞ▓ÀÒüäÕÅûÒéïþ¥®ÕïÖÒüîþöƒÒüÿÒü¥ÒüÖÒÇéÞ╝¬þÅ¡ÕêÂÕïñÕïÖÒü«Õá┤ÕÉêÒÇüÕăÕëçÒü¿ÒüùÒüª11µÖéÚûôÒü«ÚÇúþÂÜõ╝æµü»µÖéÚûôÒüîÞªüµ▒éÒüòÒéîÒü¥ÒüÖÒüîÒÇüþë╣ÕêÑÒü¬þÉåþö▒ÒüîÒüéÒéïÕá┤ÕÉêÒü½Òü»ÒÇüÕ¢ôÕ▒ÇÒü«Þ¿▒ÕÅ»Òü¿Õè┤ÕâìþÁäÕÉêÒü¥ÒüƒÒü»Õè┤õ¢┐õ╝ÜÞ¡░Òü«ÕÉêµäÅÒéÆþÁîÒéïÒüôÒü¿ÒüºÒÇüõ╝æµü»µÖéÚûôÒéÆ8µÖéÚûôÒü¥Òüºþƒ¡þ©«ÒüºÒüìÒéïõ¥ïÕñûÞªÅÕ«ÜÒüîÞ¿¡ÒüæÒéëÒéîÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÒüôÒéîÒéëÒü«µö╣µ¡úÒü¿õ©ªÞíîÒüùÒüªÒÇüÕè┤Õâìµñ£µƒ╗Òü«Õ╝ÀÕîûÒü¿ÚüòÕÅìÚüĵûÖÒü«Õ╝òÒüìõ©èÒüÆÒüîÕ«ƒµû¢ÒüòÒéîÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéþë╣Òü½ÒÇüÕ¥ôµÑ¡ÕôíÒüî30õ║║õ╗Ñõ©èÒü«õ╝üµÑ¡Òü»ÒÇüµ«ïµÑ¡µÖéÚûôÒÇüÞ╝¬þÅ¡ÕêÂÕïñÕïÖÒÇüõ╝æµùÑÒü½ÚûóÒüÖÒéïÕñëµø┤Òü½ÒüñÒüäÒüªÒÇüõ©╗þ«íÕ«ÿÕ║üÒü©Òü«Õ▒èÒüæÕç║þ¥®ÕïÖÒüîµû░ÒüƒÒü½Þ┐¢ÕèáÒüòÒéîÒü¥ÒüùÒüƒÒÇé
ÕÅ░µ╣¥Òü«Õ░▒µÑ¡ÞªÅÕëç´╝êÕÀÑõ¢£ÞªÅÕëç´╝ëÒü¿µç▓µêÆÒâ╗ÞºúÚøç
Õ░▒µÑ¡ÞªÅÕëç´╝êÕÀÑõ¢£ÞªÅÕëç´╝ëÒü«µë┐Þ¬ìÕêÂÕ║ª
ÕÅ░µ╣¥Òü«Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òþ¼¼70µØíÒüèÒéêÒü│µû¢ÞíîÞªÅÕëçþ¼¼37µØíÒÇü38µØíÒü½ÒéêÒéïÒü¿ÒÇü30õ║║õ╗Ñõ©èÒü«Õè┤ÕâìÞÇàÒéÆÚøçþö¿ÒüÖÒéïõ╝üµÑ¡Òü»ÒÇüÒüØÒü«õ║ïµÑ¡Òü«µÇºÞ│¬Òü½Õ┐£ÒüÿÒüªÕ░▒µÑ¡ÞªÅÕëç´╝êÕÀÑõ¢£ÞªÅÕëç´╝ëÒéÆõ¢£µêÉÒüùÒÇü30µùÑõ╗ÑÕåàÒü½õ║ïµÑ¡µëÇÒü«µëÇÕ£¿Õ£░ÒéÆþ«íÞ¢äÒüÖÒéïõ©╗þ«íÕ«ÿÕ║üÒü½Õ▒èÒüæÕç║Òéïþ¥®ÕïÖÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüôÒüôÒüºþë╣Òü½µ│¿µäÅÒüÖÒü╣ÒüìÒü»ÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«Õ░▒µÑ¡ÞªÅÕëçÕêÂÕ║ªÒüîÒÇüµùѵ£¼Òü«Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûþøúþØúþ¢▓Òü©Òü«ÒÇîÕ▒èÕç║ÕêÂÒÇìÒü¿Òü»µ£¼Þ│¬þÜäÒü½þò░Òü¬ÒéïÒü¿ÒüäÒüåþé╣ÒüºÒüÖÒÇéÕÅ░µ╣¥ÒüºÒü»ÒÇüµÅÉÕç║ÒüòÒéîÒüƒÕ░▒µÑ¡ÞªÅÕëçÒü»õ©╗þ«íÕ«ÿÕ║üÒü½ÒéêÒéïÒÇîµá©ÕéÖÒÇìÒÇüÒüÖÒü¬ÒéÅÒüíÕ«ƒÞ│¬þÜäÒü¬µë┐Þ¬ìÒéÆÕ¥ùÒüªÕêØÒéüÒüªÕè╣ÕèøÒüîþÖ║þöƒÒüùÒü¥ÒüÖÒÇéõ©╗þ«íÕ«ÿÕ║üÒü»ÒÇüõ╝üµÑ¡Òüîõ¢£µêÉÒüùÒüƒÞªÅÕëçÒüîµ│òõ╗ñÒü½ÚüòÕÅìÒüùÒüªÒüäÒü¬ÒüäÒüïÒÇüÒü¥Òüƒõ©ìÕ¢ôÒü¬Õè┤ÕâìµØíõ╗ÂÒéÆÕɽÒéôÒüºÒüäÒü¬ÒüäÒüïÒéÆõ║ïÕëìÒü½þ▓¥µƒ╗ÒüÖÒéïÕ¢╣Õë▓ÒéƵïàÒüúÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒü«ÕêÂÕ║ªÒü»ÒÇüõ╝üµÑ¡Òé│Òâ│ÒâùÒâ®ÒéñÒéóÒâ│Òé╣ÒéÆþøúÞªûÒüùÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàõ┐ØÞ¡ÀÒéÆÕ«ƒÕè╣þÜäÒü½µïàõ┐ØÒüÖÒéïþø«þÜäÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÒüùÒüƒÒüîÒüúÒüªÒÇüµùѵ£¼Òü«Õ░▒µÑ¡ÞªÅÕëçÒéÆÕ«ëµÿôÒü½þ┐╗Þ¿│ÒüùÒüªÞ╗óþö¿ÒüÖÒéïÞíîþé║Òü»ÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«µ│òÕ¥ïÒéäµûçÕîûÒü½ÕÉêÞç┤ÒüùÒü¬ÒüäÕåàÕ«╣ÒüîÕñÜÒüÅÕɽÒü¥ÒéîÒüªÒüäÒéïÒüƒÒéüÒÇüµá©ÕéÖÒéÆÕ¥ùÒéëÒéîÒü¬ÒüäÒâ¬Òé╣Òé»ÒüîÚØ×Õ©©Òü½Ú½ÿÒüÅÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«ÕÄ│µá╝Òü¬Õè┤Õâìµñ£µƒ╗Òü½ÒüèÒüäÒüªþ¢░ÕëçÒü«Õ»¥Þ▒íÒü¿Òü¬ÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÚØ×Õ©©Òü½Ú½ÿÒüäÒüºÒüÖÒÇéµùÑþ│╗õ╝üµÑ¡Òü»ÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«µ│òÕ¥ïÒü¿Õ«ƒµâàÒü½þ▓¥ÚÇÜÒüùÒüƒÕ░éÚûÇÕ«ÂÒü«Õè®Þ¿ÇÒéÆÕ¥ùÒüªÒÇüõ©ÇÒüïÒéëÕ░▒µÑ¡ÞªÅÕëçÒéÆõ¢£µêÉÒüÖÒéïÒüôÒü¿Òüîõ©ìÕÅ»µ¼áÒüºÒüÖÒÇé┬á
ÕÅ░µ╣¥Òü«ÞºúÚøçµ│òþÉå
ÕÅ░µ╣¥ÒüºÒü»ÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàÒü»Õè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òÒü½ÒéêÒüúÒüªµëïÕÄÜÒüÅõ┐ØÞ¡ÀÒüòÒéîÒüªÒüèÒéèÒÇüµ│òÕ«ÜÒü«õ║ïþö▒ÒüîÒü¬ÒüæÒéîÒü░ÞºúÚøçÒü»Þ¬ìÒéüÒéëÒéîÒü¥ÒüøÒéôÒÇéÞºúÚøçÒü»ÕñºÒüìÒüÅÕêåÒüæÒüªõ║êÕæèÞºúÚøç´╝êÕè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òþ¼¼11µØíÒâ╗þ¼¼20µØí´╝ëÒü¿Õì│µÖéÞºúÚøç´╝êÕè┤ÕâìÕƒ║µ║ûµ│òþ¼¼12µØí´╝ëÒü«2þ¿«Úí×Òü½ÕêåÚí×ÒüòÒéîÒü¥ÒüÖÒÇéõ║êÕæèÞºúÚøçÒü»ÒÇüõ║ïµÑ¡Òü«ÚûëÚÄûÒÇüÞ¡▓µ©íÒÇüµÉìÕñ▒ÒÇüµÑ¡ÕïÖþ©«Õ░ÅÒÇüõ©ìÕÅ»µèùÕèøÒü½ÒéêÒéïõ║ïµÑ¡Õü£µ¡óÒÇüõ║ïµÑ¡µÇºÞ│¬Òü«Õñëµø┤Òü½ÒéêÒéïõ║║ÕôíÕë赩øÒÇüÒü¥ÒüƒÒü»Õè┤ÕâìÞÇàÒü«Þâ¢Õèøõ©ìÞÂ│Òü¿ÒüäÒüúÒüƒÒÇüõ©╗Òü½þÁîÕûÂõ©èÒü«õ║ïþö▒Òü½Õƒ║ÒüÑÒüÅÞºúÚøçÒüºÒüÖÒÇéÒüôÒü«Õá┤ÕÉêÒÇüÕïñþÂÜÕ╣┤µò░Òü½Õ┐£ÒüÿÒüªõ║êÕæèµ£ƒÚûôÒéÆþ¢«ÒüÅþ¥®ÕïÖÒüîÒüéÒéèÒÇü3Òâµ£êõ╗Ñõ©è1Õ╣┤µ£¬µ║ÇÒüº10µùÑÒÇü1Õ╣┤õ╗Ñõ©è3Õ╣┤µ£¬µ║ÇÒüº20µùÑÒÇü3Õ╣┤õ╗Ñõ©èÒüº30µùÑÒüºÒüÖÒÇéõ║êÕæèµ£ƒÚûôÒéÆþ¢«ÒüïÒü¬ÒüäÕá┤ÕÉêÒü»ÒÇüÒüØÒü«µ£ƒÚûôÕêåÒü«Þ│âÚçæÒéƵö»µëòÒüåÕ┐àÞªüÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéõ©Çµû╣ÒÇüÕì│µÖéÞºúÚøçÒü»ÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàÒü«ÚçìÕñºÒü¬ÚüÄÕñ▒ÒÇüÕàÀõ¢ôþÜäÒü½Òü»Õè┤ÕâìÕÑæþ┤äµÖéÒü«ÞÖÜÕü¢þö│ÕæèÒÇüµÜ┤ÞíîÒéäõ¥«Þ¥▒Þíîþé║ÒÇüõ╝Üþñ¥Òü«µ®ƒÕ»åµ╝ŵ┤®ÒÇüµ¡úÕ¢ôÒü¬þÉåþö▒Òü«Òü¬Òüäþäíµû¡µ¼áÕïñÒü¬Òü®ÒüîÒüéÒéïÕá┤ÕÉêÒü½ÒÇüõ║êÕæèµ£ƒÚûôÒéäÚÇÇÞüÀÚçæÒü¬ÒüùÒüºÕì│µÖéÒü½ÞºúÚøçÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒüîÕÅ»Þâ¢ÒüºÒüÖÒÇéÒüƒÒüáÒüùÒÇüÕì│µÖéÞºúÚøçÒü»õ║ïþö▒ÒéÆþƒÑÒüúÒüªÒüïÒéë30µùÑõ╗ÑÕåàÒü½ÞíîÒüåÕ┐àÞªüÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÕÅ░µ╣¥Òü«ÞºúÚøçÞªÅÕêÂÒü»ÒÇüµùѵ£¼Òü«Õêñõ¥ïµ│òþÉåÒü½Õƒ║ÒüÑÒüÅÒÇîÞºúÚø絿®µ┐½þö¿µ│òþÉåÒÇìÒéêÒéèÒééÒÇüµ│òÕ«Üõ║ïþö▒Òü«ÚÖÉÕ«ÜÒü¿ÕÄ│µá╝Òü¬µëïþÂÜÒüìÞªüõ╗ÂÒü½ÒéêÒüúÒüªÒÇüÒéêÒéèµÿÄþñ║þÜäÒü½Õè┤ÕâìÞÇàÒéÆõ┐ØÞ¡ÀÒüùÒüªÒüäÒéïÒü«Òüîþë╣Õ¥┤ÒüºÒüÖÒÇéµùѵ£¼ÒüºÒü»ÒÇîÕ«óÞª│þÜäÒü½ÕÉêþÉåþÜäÒü¬þÉåþö▒ÒÇìÒü¿ÒÇîþñ¥õ╝ÜÚÇÜÕ┐Áõ©èÒü«þø©Õ¢ôµÇºÒÇìÒü¿ÒüäÒüåµè¢Þ▒íþÜäÒü¬Õƒ║µ║ûÒüºÕêñµû¡ÒüòÒéîÒéïÒü«Òü½Õ»¥ÒüùÒÇüÕÅ░µ╣¥ÒüºÒü»µ│òÕ¥ïÒü½Õ«ÜÒéüÒéëÒéîÒüƒþë╣Õ«ÜÒü«õ║ïþö▒Òü½ÕÄ│Õ»åÒü½Þ®▓Õ¢ôÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒéÆõ╝üµÑ¡ÒüîÞ¿╝µÿÄÒüùÒü¬ÒüæÒéîÒü░Òü¬ÒéèÒü¥ÒüøÒéôÒÇéÒüôÒéîÒü½ÒéêÒéèÒÇüõ╝üµÑ¡Òü»Õ«ëµÿôÒü¬ÞºúÚøçÒüîÕè┤õ¢┐þ┤øõ║ëÒü½þø┤þÁÉÒüùÒÇüµòùÞ¿┤ÒüÖÒéîÒü░ÕñÜÚíìÒü«Þ▓╗þö¿Òü¿µÖéÚûôÒÇüÒüØÒüùÒüªÒâûÒâ®Òâ│ÒâëÒéñÒâíÒâ╝Òé©Òü«µ»ÇµÉìÒéƵïøÒüÅÒüôÒü¿ÒéƵÀ▒ÒüÅþÉåÞºúÒüÖÒéïÕ┐àÞªüÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÕòÅÚíîþñ¥ÕôíÒü©Òü«Õ»¥Õ┐£Òü»ÒÇüÞºúÚøçÒüºÒü»Òü¬ÒüÅÒÇüÒü¥ÒüÜÒü»ÒâæÒâòÒé®Òâ╝Òâ×Òâ│Òé╣µö╣ÕûäÞ¿êþö╗´╝êPIP´╝ëÒü«þ¡ûÕ«ÜÒéäÚàìþ¢«Þ╗óµÅøÒü¬Òü®ÒÇüÞºúÚøçõ╗ÑÕñûÒü«µëﵫÁÒéÆÕ░¢ÒüÅÒüÖÒüôÒü¿Òüîµ£ÇÕûäÒü«þ¡ûÒü¿Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé┬á
ÕñûÕø¢õ║║Úøçþö¿Òü«Þªüõ╗ÂÒü¿Õ«ƒÕïÖµëïþÂÜ
ÕÅ░µ╣¥ÒüºÕñûÕø¢õ║║ÒéÆÚøçþö¿ÒüÖÒéïÚÜøÒü«Õƒ║µ£¼µ│òÒü»ÒÇîÚøçþö¿ÒéÁÒâ╝ÒâôÒé╣µ│ò´╝êÕ░▒µÑ¡µ£ìÕïÖµ│ò´╝ëÒÇìÒüºÒüÖÒÇéÕăÕëçÒü¿ÒüùÒüªÒÇüÕñûÕø¢õ║║ÒéÆÚøçþö¿ÒüÖÒéïõ╝üµÑ¡Òü»ÒÇüõ║ïÕëìÒü½Õè┤ÕâìÚâ¿´╝êÕè┤ÕïòÕèøþÖ║Õ▒òþ¢▓´╝ëÒü½ÒÇîÕ░▒Õè┤Þ¿▒ÕÅ»ÒÇìÒéÆþö│Þ½ïÒüùÒÇüÞ¿▒ÕÅ»ÒéÆÕ¥ùÒéïÕ┐àÞªüÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÕ░▒Õè┤ÒüîÕÅ»Þâ¢Òü¬ÞüÀþ¿«Òü»ÒÇüÚøçþö¿ÒéÁÒâ╝ÒâôÒé╣µ│òþ¼¼46µØíþ¼¼1ÚáàÒü½Õ«ÜÒéüÒéëÒéîÒüªÒüèÒéèÒÇüÕ░éÚûÇÒâ╗µèÇÞíôÞüÀÒÇüÕñûÕø¢µèòÞ│çõ╝üµÑ¡Òü«Õ¢╣ÕôíÒâ╗þ«íþÉåÞÇàÒÇüµòÖÕ©½ÒÇüÒé╣ÒâØÒâ╝ÒâäÚü©µëïÒÇüÕ«ùµòÖÒâ╗Þè©ÞíôÒâ╗µ╝öÞè©ÞüÀÒü¬Òü®ÒÇüþë╣Õ«ÜÒü«ÕêåÚçÄÒü½ÚÖÉÕ«ÜÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒü¬ÒüèÒÇüõ©ÇÚâ¿Òü«ÞüÀþ¿«ÒüºÒü»µ£Çõ¢ÄÞ│âÚçæÒüîÚü®þö¿ÒüòÒéîÒéïÕá┤ÕÉêÒééÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÕÅ░µ╣¥Òü½ÒüèÒüæÒéïÕñûÕø¢õ║║Úøçþö¿Òü»ÒÇüõ©╗Òü½õ╗Ñõ©ïÒü«õ©ëµ«ÁÚÜÄÒü«µëïþÂÜÒüìÒéÆÚáåÒü½ÞíîÒüåÕ┐àÞªüÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÒü¥ÒüÜÒÇüÚøçþö¿õ©╗ÒüîÕè┤ÕâìÚâ¿´╝êÕè┤ÕâìÕèøþÖ║Õ▒òþ¢▓´╝ëÒü½Õ░▒Õè┤Þ¿▒ÕÅ»ÒéÆþö│Þ½ïÒüùÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒü«þö│Þ½ïÒü»ÕăÕëçÒü¿ÒüùÒüªÒé¬Òâ│Òâ®ÒéñÒâ│ÒüºÞíîÒüäÒÇüÕ»®µƒ╗µ£ƒÚûôÒü»ÚÇÜÕ©©7ÕûµѡµùÑÒü¿ÒüòÒéîÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéþ┤ÖÕ¬Æõ¢ôÒüºÒü«þö│Þ½ïÒü»12µùÑõ╗Ñõ©èÒüïÒüïÒéïÕá┤ÕÉêÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéµ¼íÒü½ÒÇüÕ░▒Õè┤Þ¿▒ÕÅ»ÕÅûÕ¥ùÕ¥îÒÇüÕ¢ôÞ®▓ÕñûÕø¢õ║║ÒüîÞç¬Õø¢Òü«ÕÅ░µ╣¥Õ£¿ÕñûÕà¼Úñ¿´╝êÕñûõ║ñÚâ¿Úáÿõ║ïÕ▒Ç´╝ëÒü½Õ▒àþòÖÒâôÒéÂÒéÆþö│Þ½ïÒüùÒü¥ÒüÖÒÇéµ£ÇÕ¥îÒü½ÒÇüÕ▒àþòÖÒâôÒéÂÒüºÕÅ░µ╣¥Òü½ÕàÑÕø¢Õ¥î15µùÑõ╗ÑÕåàÒü½ÒÇüÕåàµö┐Úâ¿þº╗µ░æþ¢▓Òü½Õ▒àþòÖÞ¿╝ÒéÆþö│Þ½ïÒüÖÒéïÕ┐àÞªüÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé
ÒüôÒü«ÕñûÕø¢õ║║Úøçþö¿ÒâùÒâ¡Òé╗Òé╣Òü»ÒÇüõ©ÇÞªïÒüÖÒéïÒü¿þà®ÚøæÒüºÒüÖÒüîÒÇüÕÉäÕ«ÿÕ║üÚûôÒü«Õ¢╣Õë▓ÕêåµïàÒüîµÿÄþó║Òü½Õ«ÜÒéüÒéëÒéîÒüªÒüèÒéèÒÇüµëïþÂÜÒüìÒü«ÒâçÒé©Òé┐Òâ½ÕîûÒééÚÇ▓ÒéôÒüºÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒüùÒüïÒüùÒÇüÒé¬Òâ│Òâ®ÒéñÒâ│þö│Þ½ïÒéÀÒé╣ÒâåÒâáÒü½Òü»µèÇÞíôþÜäÒü¬ÕêÂþ┤ä´╝êMacÚØ×Õ»¥Õ┐£Òü¬Òü®´╝ëÒéäÒÇüµø©Úí×Òü«õ©ìÕéÖÒü½ÒéêÒéïÕåìþö│Þ½ïÒüºÕñºÕ╣àÒü¬ÚüàÕ╗ÂÒüîþöƒÒüÿÒéïÒâ¬Òé╣Òé»ÒüîÕ¡ÿÕ£¿ÒüùÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒéîÒü»ÒÇüÒéÀÒé╣ÒâåÒâáÒüîÕè╣þÄçþÜäÒüºÒüéÒéïÕÅìÚØóÒÇüÚûôÚüòÒüäÒü½Õ»¥ÒüùÒüªÒü»ÚØ×Õ©©Òü½ÕÄ│ÒüùÒüäÒüôÒü¿ÒéÆþñ║ÕöåÒüùÒü¥ÒüÖÒÇéÒüùÒüƒÒüîÒüúÒüªÒÇüµëïþÂÜÒüìÒéÆÞç¬ÕÀ▒µÁüÒüºÚÇ▓ÒéüÒéïÒü«ÒüºÒü»Òü¬ÒüÅÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«Þíîµö┐µëïþÂÜÒüìÒü½þ▓¥ÚÇÜÒüùÒüƒÕ░éÚûÇի´╝êÒé│Òâ│ÒéÁÒâ½Òé┐Òâ│ÒâêÒéäµ│òÕ¥ïõ║ïÕïÖµëÇ´╝ëÒü«ÒéÁÒâØÒâ╝ÒâêÒéƵù®µ£ƒÒü½Õ¥ùÒéïÒüôÒü¿ÒüîÒÇüõ║êµ£ƒÒüøÒü¼ÚüàÕ╗ÂÒéÆÚÿ▓ÒüÄÒÇüÕååµ╗æÒü¬õ║║õ║ïÞ¿êþö╗Õ«ƒÞíîÒéÆÕÅ»Þâ¢Òü½ÒüÖÒéïÒüƒÒéüÒü«µ£ÇÕûäþ¡ûÒü¿Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇé┬á
ÕÅ░µ╣¥Òü«µùÑþ│╗õ╝üµÑ¡Òü½Òü¿ÒüúÒüªÒü«ÒâØÒéñÒâ│ÒâêÒü¿Õ»¥Õ┐£þ¡û
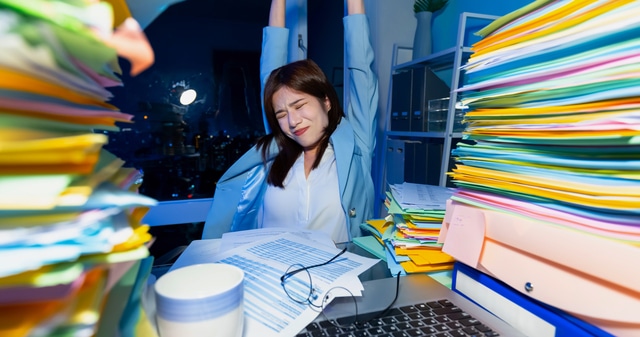
ÒÇîÒü┐Òü¬Òüùµ«ïµÑ¡ÒÇìÕêÂÕ║ª
ÕÅ░µ╣¥ÒüºÒü»ÒÇüµùѵ£¼Òü«Õè┤ÕâìµàúÞíîÒéäÕêñõ¥ïÒü½Õƒ║ÒüÑÒüÅÒÇîÒü┐Òü¬Òüùµ«ïµÑ¡ÒÇìÕêÂÕ║ªÒéÆÕ░ÄÕàÑÒüÖÒéïõ╝üµÑ¡ÒüîµùÑþ│╗õ╝üµÑ¡Òü½ÕñÜÒüÅÞªïÕÅùÒüæÒéëÒéîÒü¥ÒüÖÒüî ÒÇüÒüôÒéîÒü»Õè┤Õâìµ│òÚüòÕÅìÒüºÒüéÒéèÒÇüÚçìÕñºÒü¬þ¢░ÕëçÒü«Õ»¥Þ▒íÒü¿Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÒü¥ÒüƒÒÇüµùѵ£¼Òü«Õ░▒µÑ¡ÞªÅÕëçÒéÆÒüØÒü«Òü¥Òü¥þ┐╗Þ¿│ÒüùÒüªÞ╗óþö¿ÒüÖÒéïÞíîþé║ÒééÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«µ│òõ╗ñÒü½ÚüòÕÅìÒüÖÒéïÕåàÕ«╣ÒüîÕɽÒü¥ÒéîÒüªÒüäÒéïÒüƒÒéüÒÇüÕè┤ÕâìÕ▒ÇÒü«µá©ÕéÖÒéÆÕ¥ùÒéëÒéîÒüÜÒÇüÕòÅÚíîþÖ║þöƒµÖéÒü½µ│òþÜäÕè╣ÕèøÒéƵîüÒüƒÒü¬ÒüäÕì▒ÚÖ║µÇºÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÒüØÒü«õ╗ûÒü½ÒééÒÇüÞ│âÚçæÒüïÒéëÒü«Úüòþ┤äÚçæÒéäÞ│áÕäƒÚçæÒü«ÕëìµÄºÚÖñÒÇüÕ¥ôµÑ¡ÕôíÒü«ÕÉîµäÅÒü«Òü¬Òüäõ©Çµû╣þÜäÒü¬Õè┤ÕâìµØíõ╗ÂÒü«Õñëµø┤ÒÇüÕïñÕïÖÞ®òÕ«ÜÒü½ÒüèÒüæÒéïÒÇîÒüØÒü«õ╗ûÒÇìÒü¿ÒüäÒüúÒüƒÕîàµï¼þÜäÒüºõ©ìµÿÄþó║Òü¬ÞªÅÕ«ÜÒééþäíÕè╣Òü¿ÒüòÒéîÒü¥ÒüÖÒÇé
Õè┤Õâìþ┤øõ║ë
ÕÅ░µ╣¥Òü½ÒüèÒüæÒéïÕè┤ÕïÖÒâ¬Òé╣Òé»Òü«µá╣µ£¼Òü»ÒÇüµ│òÕ¥ïÒü«µØíµûçÒü«ÚüòÒüäÒüáÒüæÒüºÒü¬ÒüÅÒÇüµùÑÕÅ░Òü«Õè┤ÕâìµûçÕîûÒÇüþë╣Òü½Õè┤õ¢┐ÚûôÒü«ÒâæÒâ»Òâ╝ÒâÉÒâ®Òâ│Òé╣Òü¿Òé│Òâ│ÒâùÒâ®ÒéñÒéóÒâ│Òé╣Òü½Õ»¥ÒüÖÒéïµäÅÞ¡ÿÒü«ÚüòÒüäÒü½ÞÁÀÕøáÒüùÒü¥ÒüÖÒÇéÕÅ░µ╣¥ÒüºÒü»ÒÇüÕ░▒µÑ¡ÞªÅÕëçÒü«µá©ÕéÖÕêÂÕ║ªÒéäÕè┤Õâìþ┤øõ║ëÕçªþÉåÒâíÒé½ÒâïÒé║ÒâáÒüîµÿÄþó║Òü½µò┤ÕéÖÒüòÒéîÒüªÒüèÒéèÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàÕü┤Òüîõ╝üµÑ¡Õü┤Òü«õ©ìÕ¢ôÒü¬Þíîþé║Òü½Õ»¥ÒüùÒüªµ│òþÜäµëﵫÁÒü½Þ¿┤ÒüêÒéïÒüƒÒéüÒü«ÒéóÒé»Òé╗Òé╣ÒüîÚØ×Õ©©Òü½Õ«╣µÿôÒüºÒüÖÒÇéõ╝üµÑ¡Òüîµùѵ£¼Õ╝ŵàúÞíîÒéÆÕ«ëµÿôÒü½Úü®þö¿ÒüùÒüƒÕá┤ÕÉêÒÇüÕ¥ôµÑ¡ÕôíÒü»Þ║èÞ║çÒü¬ÒüÅÕè┤ÕâìÕ▒ÇÒü½ÚÇÜÕá▒ÒüùÒÇüþ┤øõ║ëÒü½þÖ║Õ▒òÒüÖÒéïÕÅ»Þ⢵ǺÒüîÚ½ÿÒüäÒüºÒüÖÒÇéÕ«ƒÚÜøÒÇü2022Õ╣┤Òü½Òü»23,319õ╗ÂÒü«Õè┤Õâìþ┤øõ║ëÒüîÕÅùþÉåÒüòÒéîÒüªÒüèÒéèÒÇüÕè┤õ¢┐ÚûôÒü«Õ»¥þ½ïÒüîµÀ▒Õê╗ÕîûÒüùÒüªÒüäÒéïÒüôÒü¿ÒüîÒüåÒüïÒüîÒüêÒü¥ÒüÖÒÇéÒüùÒüƒÒüîÒüúÒüªÒÇüµùÑþ│╗õ╝üµÑ¡Òü»ÒÇüµùѵ£¼Òü«µàúþ┐ÆÒéƵì¿ÒüªÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«µ│òÕêÂÕ║ªÒü¿µûçÕîûÒü½ÕÉêÒéÅÒüøÒüƒþï¼Þç¬Òü«Õè┤ÕïÖþ«íþÉåõ¢ôÕêÂÒéÆÒé╝Òâ¡ÒüïÒé뵺ïþ»ëÒüÖÒéïÕ┐àÞªüÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéþÁîÕûÂÞÇàÞç¬Þ║½Òüîµ│òÕ¥ïÒü«µªéÕ┐ÁÒéÆþÉåÞºúÒüùÒÇüþÅ¥Õ£░Òü«Õ░éÚûÇի´╝êµ│òÕ¥ïõ║ïÕïÖµëÇÒéäÒé│Òâ│ÒéÁÒâ½Òé┐Òâ│Òâê´╝ëÒü«Õè®Þ¿ÇÒéƵ▒éÒéüÒéïÒüôÒü¿ÒüîÒÇüµ│òþÜäÒâ¬Òé╣Òé»ÒéÆÞ╗¢µ©øÒüÖÒéïÕö»õ©ÇÒü«ÚüôÒüºÒüÖÒÇé
Þ┐æÕ╣┤ÒÇüÕÅ░µ╣¥ÒüºÒü»ÕñºÞªÅµ¿íÒü¬Òé╣ÒâêÒâ®ÒéñÒé¡ÒéäÞüÀÕá┤ÒüºÒü«ÒâÅÒâ®Òé╣ÒâíÒâ│ÒâêÒâ╗ÕÀ«ÕêÑÒü½ÚûóÒüÖÒéïþ┤øõ║ëÒüîÕñÜþÖ║ÒüùÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéþë╣Òü½µ│¿þø«ÒüÖÒü╣ÒüìÒü»ÒÇü2020Õ╣┤1µ£ê1µùÑÒü½µû¢ÞíîÒüòÒéîÒüƒÒÇîÕè┤Õâìõ║ïõ╗µ│òÒÇìÒüºÒüÖÒÇéÒüôÒü«µ│òÕ¥ïÒü»ÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàÒüîµ£ëÕê®Òü½Òü¬ÒéïÒéêÒüåÒü½Þ¿┤Þ¿ƒµëïþÂÜÒüìÒéÆþ░íþ┤áÕîûÒüùÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàÒü«þ½ïÞ¿╝Þ▓¼õ╗╗ÒéÆÞ╗¢µ©øÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒüºÒÇüÕè┤Õâìþ┤øõ║ëÒüîÞ¿┤Þ¿ƒÒü©Òü¿þÖ║Õ▒òÒüÖÒéïÒâÅÒâ╝ÒâëÒâ½ÒéÆÕèçþÜäÒü½õ©ïÒüÆÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÒüôÒü«µ│òÕ¥ïÒü«µû¢ÞíîÒü»ÒÇüõ╝üµÑ¡Òü½þ┤øõ║ëõ║êÚÿ▓Òü«ÚçìÞªüµÇºÒéÆÒüïÒüñÒüªÒü¬ÒüäÒü╗Òü®Ú½ÿÒéüÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒéîÒü¥ÒüºÕÅúÚá¡Òéäõ©ìµ¡úþó║Òü¬Þ¿ÿÚî▓Òüºµ©êÒü¥ÒüøÒüªÒüäÒüƒÕè┤ÕâìµØíõ╗´╝êÕè┤ÕâìµÖéÚûôÒÇüÞ│âÚçæÞ¿êþ«ùÒü¬Òü®´╝ëÒéÆÒÇüþ┤øõ║ëµÖéÒü«Þ¿╝µïáÒü¿ÒüùÒüªÚÇÜþö¿ÒüÖÒéïÕ¢óÒüºÒÇüµ¡úþó║ÒüïÒüñõ¢ôþ│╗þÜäÒü½Þ¿ÿÚî▓Òâ╗õ┐ØÕ¡ÿÒüÖÒéïÕ┐àÞªüµÇºÒüîÕóùÕñºÒüùÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÒüùÒüƒÒüîÒüúÒüªÒÇüÕìÿÒü½µ│òÕ¥ïÒéÆÚüÁÕ«êÒüÖÒéïÒüáÒüæÒüºÒü¬ÒüÅÒÇüµ│òÕ¥ïÒü½µ║ûµïáÒüùÒüªÒüäÒéïÒüôÒü¿ÒéÆÞ¿╝µÿÄÒüÖÒéïÒüƒÒéüÒü«ÒÇîÞ¿ÿÚî▓þ«íþÉåõ¢ôÕêÂÒÇìÒü«µºïþ»ëÒüîÒÇüÕè┤ÕïÖÒâ¬Òé╣Òé»Òâ×ÒâìÒé©ÒâíÒâ│ÒâêÒü«µû░ÒüƒÒü¬µ£ÇÚçìÞªüÞ¬▓ÚíîÒü¿Òü¬ÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÒüôÒéîÒü»ÒÇüÒé┐ÒéñÒâáÒé½Òâ╝ÒâëÒü«µ¡úþó║Òü¬þ«íþÉåÒéäÒÇüÕ░▒µÑ¡ÞªÅÕëçÒü©Òü«µÿÄþó║Òü¬Þ¿ÿÞ╝ëÒü¿ÒüäÒüúÒüƒÕàÀõ¢ôþÜäÒü¬Õ»¥þ¡ûÒü½þø┤þÁÉÒüùÒü¥ÒüÖÒÇé
Òü¥Òü¿Òéü
ÕÅ░µ╣¥õ║ïµÑ¡ÒéƵêÉÕèƒÒüòÒüøÒéïÒüƒÒéüÒü½Òü»ÒÇüÕ£░µö┐Õ¡ªÒâ¬Òé╣Òé»ÒéäÞç¬þäÂþü¢Õ«│Òâ¬Òé╣Òé»ÒüáÒüæÒüºÒü¬ÒüÅÒÇüÕè┤ÕïÖÒâ¬Òé╣Òé»ÒéƵ£ÇÚçìÞªüÞ¬▓ÚíîÒü¿µìëÒüêÒÇüõ╗Ñõ©ïÒü«ÕàÀõ¢ôþÜäÕ»¥Õ┐£þ¡ûÒéÆÞ¼øÒüÿÒéïÒü╣ÒüìÒüºÒüÖÒÇéµùѵ£¼Òü«ÞªÅÕëçÒéÆþ┐╗Þ¿│ÒüÖÒéïÒü«ÒüºÒü»Òü¬ÒüÅÒÇüÕÅ░µ╣¥Òü«µ│òõ╗ñÒü½Õ«îÕà¿Òü½µ║ûµïáÒüùÒüƒÕ░▒µÑ¡ÞªÅÕëçÒéÆÕ░éÚûÇÕ«ÂÒü¿Õà▒ÕÉîÒüºõ¢£µêÉÒüùÒÇüõ©╗þ«íÕ«ÿÕ║üÒü«µá©ÕéÖÒéÆþó║Õ«ƒÒü½Õ¥ùÒéïÕ┐àÞªüÒüîÒüéÒéèÒü¥ÒüÖÒÇéÕç║ÚÇÇÕïñÞ¿ÿÚî▓ÒÇüµ«ïµÑ¡µÖéÚûôÒÇüÞ│âÚçæÞ¿êþ«ùÒÇüõ╝æµùÑÕç║ÕïñÒü«Þ¿ÿÚî▓ÒéƵ¡úþó║Òü½þ«íþÉåÒâ╗õ┐ØÕ¡ÿÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒüîÕ┐àÚáêÒüºÒüÖÒÇéÒüôÒéîÒü»Õè┤Õâìµñ£µƒ╗Òü½ÒüèÒüäÒüªµ£ÇÒééÕÄ│ÒüùÒüÅÒâüÒéºÒââÒé»ÒüòÒéîÒéïÚáàþø«Òü«õ©ÇÒüñÒüºÒüÖÒÇéÕè┤õ¢┐õ╝ÜÞ¡░ÒéÆիܵ£ƒþÜäÒü½ÚûïÕé¼ÒüùÒÇüÕ¥ôµÑ¡ÕôíÒüïÒéëÒü«µäÅÞªïÒéäÞ蝹âàÒü½þ£ƒµæ»Òü½Õ»¥Õ┐£ÒüÖÒéïõ¢ôÕêÂÒéƵºïþ»ëÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒüºÒÇüþ┤øõ║ëÒü«þÖ║þöƒÒéƵ£¬þäÂÒü½Úÿ▓ÒüÉÒüôÒü¿ÒüîÒüºÒüìÒü¥ÒüÖÒÇéÕÅ░µ╣¥µ│òÕïÖÒâ╗Õè┤ÕïÖÒü½þ▓¥ÚÇÜÒüùÒüƒµ│òÕ¥ïõ║ïÕïÖµëÇÒéäÒé│Òâ│ÒéÁÒâ½Òé┐Òâ│ÒâêÒéÆÚíºÕòÅÒü¿ÒüùÒüªÞ┐ÄÒüêÒÇüþÂÖþÂÜþÜäÒü¬µ│òþÜäÕè®Þ¿ÇÒéÆÕ¥ùÒéïÒüôÒü¿ÒüîÒÇüõ║굩¼õ©ìÞâ¢Òü¬µ│òþÜäÒâ¬Òé╣Òé»ÒéÆÞ╗¢µ©øÒüÖÒéïõ©èÒüºõ©ìÕÅ»µ¼áÒüºÒüÖÒÇé
ÕÅ░µ╣¥Õè┤Õâìµ│òÒü»ÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàõ┐ØÞ¡ÀÒéƵá©Òü¿ÒüÖÒéïÕÄ│µá╝Òü¬ÞªÅÕêÂÒéÆõ╝üµÑ¡Òü½Þ¬▓ÒüùÒüªÒüèÒéèÒÇüÒüØÒü«Òé│Òâ│ÒâùÒâ®ÒéñÒéóÒâ│Òé╣Òü¿þñ¥õ╝ÜþÜäÞ▓¼õ╗╗ÒéÆÕÄ│ÒüùÒüÅÕòÅÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé2017Õ╣┤Òâ╗2018Õ╣┤Òü«Õñºµö╣µ¡úÒéäÕè┤Õâìõ║ïõ╗µ│òÒü«µû¢ÞíîÒü»ÒÇüÕè┤ÕâìÞÇàõ┐ØÞ¡ÀÒü«Õ╝ÀÕîûÒü¿Õè┤õ¢┐þ┤øõ║ëÒü«µ┤╗µÇºÕîûÒü¿ÒüäÒüåõ©ìÕÅ»ÚÇåþÜäÒü¬ÕñëÕîûÒéÆÒééÒüƒÒéëÒüùÒü¥ÒüùÒüƒÒÇéÕÅ░µ╣¥õ║ïµÑ¡Òü«µêÉÕèƒÒü»ÒÇüÕìÿÒü¬ÒéïÕ©éÕá┤µ®ƒõ╝ÜÒü«Þ┐¢µ▒éÒüáÒüæÒüºÒü¬ÒüÅÒÇüþÅ¥Õ£░Òü«µ│òþÜäÒâ╗µûçÕîûþÜäÒü¬þÆ░ÕóâÒü½µÀ▒ÒüÅÚü®Õ┐£ÒüùÒüƒÕ╝ÀÕø║Òü¬Õè┤ÕïÖþ«íþÉåõ¢ôÕêÂÒéƵºïþ»ëÒüºÒüìÒéïÒüïÒü½ÒüïÒüïÒüúÒüªÒüäÒü¥ÒüÖÒÇéµ£¼þ¿┐ÒüîÒÇüµùÑþ│╗õ╝üµÑ¡Òü«þÜ嵺ÿÒüîÕÅ░µ╣¥Òüºþø┤ÚØóÒüÖÒéïÒüºÒüéÒéìÒüåµ│òþÜäÞ¬▓ÚíîÒéÆÕàïµ£ìÒüùÒÇüµîüþÂÜÕÅ»Þâ¢Òü¬õ╝üµÑ¡ÚüïÕûÂÒéÆÕ«ƒþÅ¥ÒüÖÒéïÒüƒÒéüÒü«þ¥àÚçØþøñÒü¿Òü¬ÒéïÒüôÒü¿ÒéÆÚíÿÒüäÒü¥ÒüÖÒÇé
Òé½ÒâåÒé┤Òâ¬Òâ╝: ITÒâ╗ÒâÖÒâ│ÒâüÒâúÒâ╝Òü«õ╝üµÑ¡µ│òÕïÖ
Òé┐Òé░: ÕÅ░µ╣¥µÁÀÕñûõ║ïµÑ¡


































