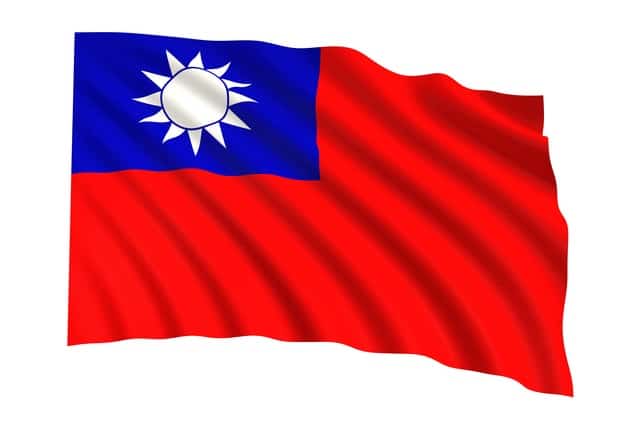ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃüīÕ«ÜŃéüŃéŗŃé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü©µ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©ł

ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü¦Ńü«ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗŃĆüńē╣Ńü½ńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║Ńü«Ķ©Łń½ŗŃéäM&AŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗķÜøŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīńø┤ķØóŃüÖŃéŗķćŹĶ”üŃü¬Ķ¬▓ķĪīŃü«õĖĆŃüżŃüīŃĆüŃé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«ķüĢŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüEUµīćõ╗żŃü«ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŚŃüæŃüżŃüżŃĆüÕż¦ķÖĖµ│Ģń│╗Ńü«õ╝ØńĄ▒Ńü«õĖŁŃü¦ńŗ¼Ķć¬Ńü«ńÖ║Õ▒ĢŃéÆķüéŃüÆŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüµŚźµ£¼µ│Ģ’╝łõ╝ÜńżŠµ│Ģ’╝ēŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗµ¤öĶ╗¤Ńü¬µ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃü«ķüĖµŖ×ĶéóŃéäŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü½Ķ¬▓ŃüĢŃéīŃéŗńŠ®ÕŗÖŃü«ń»äÕø▓Ńü¬Ńü®ŃĆüńĄīÕ¢ČŃü«µĀ╣Õ╣╣Ńü½ķ¢óŃéÅŃéŗķćŹĶ”üŃü¬ńøĖķüĢńé╣ŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢÕłČŃü«õĖŁµĀĖŃéÆŃü¬ŃüÖŃü«Ńü»ŃĆüÕĢåõ║ŗõ╝ÜńżŠµ│ĢÕģĖ (C├│digo das Sociedades ComerciaisŃĆüõ╗źõĖŗŃĆīCSCŃĆŹ) Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ÕŖĀŃüłŃü”ŃĆüõĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃéäÕģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüĶ©╝ÕłĖµ│ĢÕģĖ (C├│digo dos Valores Mobili├ĪriosŃĆüõ╗źõĖŗŃĆīCVMobŃĆŹ) ŃüīµāģÕĀ▒ķ¢ŗńż║ŃéäµĀ¬õĖ╗Ńü«µ©®Õł®Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ®│ń┤░Ńü¬Ķ”ÅÕłČŃéÆÕ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńē╣Ńü½µ│©ńø«ŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüµĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠ (SA – Sociedade An├│nima) Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗµ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃü«µ¤öĶ╗¤µĆ¦Ńü¦ŃüÖŃĆéCSCń¼¼278µØĪń¼¼1ķĀģŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«SAõ╝ÜńżŠŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńøŻµ¤╗ÕĮ╣õ╝ÜĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃü½õ╝╝Ńü¤õ╝ØńĄ▒ńÜäŃü¬ŃāóŃāćŃā½ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńøŻµ¤╗ńŁēÕ¦öÕōĪõ╝ÜĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃü¬Ńü®Ńü½Ķ┐æŃüäńøŻµ¤╗Õ¦öÕōĪõ╝ÜŃāóŃāćŃā½ŃĆüŃüØŃüŚŃü”ŃāēŃéżŃāäµ│ĢŃü½ķĪ×õ╝╝ŃüŚŃü¤õ║īÕ▒żµ¦ŗķĆĀŃāóŃāćŃā½Ńü©ŃüäŃüåŃĆü3ŃüżŃü«ńĢ░Ńü¬ŃéŗŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣ŃāóŃāćŃā½ŃüŗŃéēĶć¬ńżŠŃü«Õ«¤µāģŃü½ÕÉłŃüŻŃü¤ŃééŃü«ŃéÆķüĖµŖ×Ńü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃü«ķüĖµŖ×ĶéóŃüīµŚźµ£¼µ│ĢŃéłŃéŖŃééÕżÜµ¦śŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║Ńü«Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣õĮōÕłČŃéƵ¦ŗń»ēŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦µ£ĆÕłØŃü«ķćŹĶ”üŃü¬ÕłåÕ▓Éńé╣Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃü½ķ¢óŃüŚŃü”ŃééŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«ķćŹĶ”üŃü¬ķüĢŃüäŃüīĶ”ŗŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«CSCń¼¼64µØĪŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Õ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃü«õĖĆńÆ░Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüµĀ¬õĖ╗Ńü«ķĢʵ£¤ńÜäÕł®ńøŖŃü«Ńü┐Ńü¬ŃéēŃüÜŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃĆüķĪ¦Õ«óŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃü©ŃüäŃüŻŃü¤õ╗¢Ńü«Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝Ńü«Õł®ńøŖŃéÆŃééĶĆāµģ«ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéƵśÄµ¢ćŃü¦ńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüõĖ╗Ńü½ŃĆīµĀ¬õĖ╗Ńü«Õģ▒ÕÉīŃü«Õł®ńøŖŃĆŹŃü½ńä”ńé╣ŃéÆÕĮōŃü”ŃéŗµŚźµ£¼µ│ĢŃü«Ķ¦ŻķćłŃü©µ»öĶ╝āŃüŚŃü”ŃĆüŃéłŃéŖÕ║āń»äŃü¬Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝Ńā╗ŃéŁŃāŻŃāöŃé┐Ńā¬Ńé║ŃāĀŃüĖŃü«ķģŹµģ«ŃéƵ│ĢńÜäŃü½Ķ”üµ▒éŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü©Ķ©ĆŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
õĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ķ©╝ÕłĖÕĖéÕĀ┤Õ¦öÕōĪõ╝Ü (CMVM) Ńüīµē┐Ķ¬ŹŃüŚŃü¤Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńé│Ńā╝Ńāē’╝łńÅŠÕ£©Ńü»ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńā╗Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣ÕŹöõ╝Ü (IPCG) ŃüīńÖ║ĶĪīŃüÖŃéŗŃé│Ńā╝ŃāēŃüīõĖ╗µĄü’╝ēŃü«ķü®ńö©Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüµØ▒õ║¼Ķ©╝ÕłĖÕÅ¢Õ╝ĢµēĆŃü«Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńā╗Ńé│Ńā╝ŃāēŃü©ÕÉīµ¦śŃü«ŃĆīķüĄÕ«łŃüŠŃü¤Ńü»Ķ¬¼µśÄ (Comply or Explain)ŃĆŹÕĤÕēćŃüīµÄĪńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüķĆŵśÄµĆ¦Ńü«ķ½śŃüäµāģÕĀ▒ķ¢ŗńż║ŃüīµŖĢĶ│ćÕ«Čõ┐ØĶŁĘŃü«Ķ”│ńé╣ŃüŗŃéēķćŹĶ”¢ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü¦Ńü«õ║ŗµźŁķüŗÕ¢ČŃéÆńø«µīćŃüÖµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü«ńĄīÕ¢ČĶĆģŃéäµ│ĢÕŗÖµŗģÕĮōĶĆģŃü«ńÜ嵦śŃü½ÕÉæŃüæŃü”ŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü«Õ¤║µ£¼µ│ĢÕłČŃĆüńē╣Ńü½µŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«ķüĢŃüäŃüīķÜøń½ŗŃüżŃĆīµ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃü«3ŃüżŃü«ķüĖµŖ×ĶéóŃĆŹŃü©ŃĆīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃĆŹŃü½ńä”ńé╣ŃéÆÕĮōŃü”Ńü”ŃĆüĶ®│ŃüŚŃüÅĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü”ŃüäŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Õ¤║µ£¼µ│ĢÕłČ
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣ŃéÆĶ”ÅÕŠŗŃüÖŃéŗµ│ĢõĮōń│╗Ńü»ŃĆüõĖ╗Ńü½õ║īŃüżŃü«µ│ĢÕģĖŃü©ŃĆüĶ©╝ÕłĖÕĖéÕĀ┤Õ¦öÕōĪõ╝Ü’╝łCMVM’╝ēŃüīńøŻńØŻŃüÖŃéŗŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńé│Ńā╝ŃāēŃü½ŃéłŃüŻŃü”µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĢåõ║ŗõ╝ÜńżŠµ│ĢÕģĖ’╝łCSC’╝ēŃü©Ķ©╝ÕłĖµ│ĢÕģĖ’╝łCVMob’╝ē
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«õ╝ÜńżŠķüŗÕ¢ČŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ£ĆŃééÕ¤║µ£¼ńÜäŃü¬µ│ĢÕŠŗŃü»ÕĢåõ║ŗõ╝ÜńżŠµ│ĢÕģĖ (CSC) Ńü¦ŃüÖŃĆéCSCŃü»ŃĆüµĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠ (SA) Ńéäµ£ēķÖÉõ╝ÜńżŠ (Lda – Sociedade por Quotas) Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤õĖ╗Ķ”üŃü¬õ╝ÜńżŠÕĮóµģŗŃü«Ķ©Łń½ŗŃĆüķüŗÕ¢ČŃĆüµ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃĆüÕĮ╣ÕōĪŃü«Ķ▓¼õ╗╗ŃĆüĶ¦ŻµĢŻŃü½Ķć│ŃéŗŃüŠŃü¦ŃĆüõ╝ÜńżŠµ│ĢÕģ©Ķł¼Ńü«µ×ĀńĄäŃü┐ŃéÆÕ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼õ╝üµźŁŃüīńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║ŃéÆĶ©Łń½ŗŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«Õåģķā©ńĄ▒µ▓╗µ¦ŗķĆĀŃü»Õ¤║µ£¼ńÜäŃü½ŃüōŃü«CSCŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃü½ÕŠōŃüŻŃü”Ķ©ŁĶ©łŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüµĀ¬Õ╝ÅŃéÆõĖŖÕĀ┤ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗõ╝üµźŁŃéäŃĆüÕ║āŃüÅõĖĆĶł¼ŃüŗŃéēÕć║Ķ│ćŃéÆÕŗ¤ŃéŗÕģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüCSCŃü½ÕŖĀŃüłŃü”Ķ©╝ÕłĖµ│ĢÕģĖ (CVMob) Ńüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéCVMobŃü»ŃĆüĶ│ćµ£¼ÕĖéÕĀ┤Ńü«Õģ¼µŁŻµĆ¦Ńü©ķĆŵśÄµĆ¦ŃéÆńó║õ┐ØŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüµŖĢĶ│ćÕ«Čõ┐ØĶŁĘŃü«Ķ”│ńé╣ŃüŗŃéēŃĆüńÖ║ĶĪīĶĆģ’╝łõĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁ’╝ēŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ÕÄ│µĀ╝Ńü¬µāģÕĀ▒ķ¢ŗńż║ńŠ®ÕŗÖ’╝łõŠŗ’╝ÜĶ▓ĪÕŗÖµāģÕĀ▒ŃĆüķćŹĶ”üŃü¬ńĄīÕ¢ČµāģÕĀ▒ŃĆüÕĮ╣ÕōĪÕĀ▒ķģ¼Ńü¬Ńü®’╝ēŃéäŃĆüµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü«ķüŗÕ¢ČŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ®│ń┤░Ńü¬Ńā½Ńā╝Ńā½ŃéÆĶ¬▓ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńé│Ńā╝ŃāēŃü©ŃĆīķüĄÕ«łŃüŠŃü¤Ńü»Ķ¬¼µśÄŃĆŹÕĤÕēć
õĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃü»ŃĆüÕēŹĶ┐░Ńü«CSCŃüŖŃéłŃü│CVMobŃü©ŃüäŃüåµ│ĢÕŠŗ’╝łŃāÅŃā╝ŃāēŃā╗ŃāŁŃā╝’╝ēŃü½ÕŖĀŃüłŃĆüŃé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ”Åń»ä’╝łŃéĮŃāĢŃāłŃā╗ŃāŁŃā╝’╝ēŃü½Ńééµ£ŹŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü¦Ńü»ŃĆüCMVMŃü«µē┐Ķ¬ŹŃü«ŃééŃü©ŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńā╗Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣ÕŹöõ╝Ü (IPCG – Instituto Portugu├¬s de Corporate Governance) ŃüīńÖ║ĶĪīŃüÖŃéŗŃĆīŃé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńé│Ńā╝Ńāē (C├ōDIGO DE GOVERNO DAS SOCIEDADES)ŃĆŹŃüīŃĆüõĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃüīÕÅéńģ¦ŃüÖŃü╣ŃüŹõĖ╗Ķ”üŃü¬Ķ”Åń»äŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµ£Ćµ¢░ńēłŃü»2023Õ╣┤Ńü½µö╣Ķ©éŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüEUŃü«µ£Ćµ¢░ÕŗĢÕÉæŃéäŃéĄŃé╣ŃāåŃāŖŃāōŃā¬ŃāåŃ鯒╝łESG’╝ēŃüĖŃü«ķ¢óÕ┐āŃü«ķ½śŃüŠŃéŖŃéÆÕÅŹµśĀŃüŚŃü¤ÕåģÕ«╣Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ńé│Ńā╝ŃāēŃü«ķüŗńö©Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ķćŹĶ”üŃü¬Ńü«ŃüīŃĆüŃĆīķüĄÕ«łŃüŠŃü¤Ńü»Ķ¬¼µśÄ (Comply or Explain)ŃĆŹÕĤÕēćŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüõ╝üµźŁŃüīŃé│Ńā╝ŃāēŃü«ÕÉäµÄ©Õź©õ║ŗķĀģŃéÆŃĆīķüĄÕ«ł (Comply)ŃĆŹŃüÖŃéŗŃüŗŃĆüŃééŃüŚķüĄÕ«łŃüŚŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»ŃĆüŃüØŃü«ńÉåńö▒ŃéƵŖĢĶ│ćÕ«ČŃéäÕĖéÕĀ┤Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ÕÉłńÉåńÜäŃü½ŃĆīĶ¬¼µśÄ (Explain)ŃĆŹŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµØ▒õ║¼Ķ©╝ÕłĖÕÅ¢Õ╝ĢµēĆŃü«Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńā╗Ńé│Ńā╝Ńāē’╝łŃüōŃüĪŃéēŃééŃĆīŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃā╗Ńé¬ŃéóŃā╗Ńé©Ńé»Ńé╣ŃāŚŃā¼ŃéżŃā│ŃĆŹÕĤÕēćŃéƵÄĪńö©’╝ēŃü©ÕÉīµ¦śŃü«ŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüńö╗õĖĆńÜäŃü¬Ńā½Ńā╝Ńā½ŃéÆÕ╝ĘÕłČŃüÖŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕÉäńżŠŃü«õ║ŗµāģŃü½Õ┐£ŃüśŃü¤µ¤öĶ╗¤Ńü¬Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣õĮōÕłČŃü«µ¦ŗń»ēŃéÆõ┐āŃüŚŃüżŃüżŃĆüŃüØŃü«ķüĖµŖ×Ńü«ķĆŵśÄµĆ¦ŃéƵŗģõ┐ØŃüÖŃéŗõ╗ĢńĄäŃü┐Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńā╗Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼BŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣ÕŹöõ╝Ü’╝łIPCG’╝ēŃüīÕģ¼ķ¢ŗŃüÖŃéŗµ£Ćµ¢░Ńü«Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńé│Ńā╝Ńāē’╝ł2023Õ╣┤µö╣Ķ©éńēłŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ķ¬×’╝ēŃü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«PDFŃü¦ńó║Ķ¬ŹŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
https://cgov.pt/images/ficheiros/2023/cgs-revisao-de-2023-ebook.pdf
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«µĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠ’╝łSA’╝ēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃü«3ŃüżŃü«ķüĖµŖ×Ķéó

ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµ£ĆÕż¦Ńü«ńē╣ÕŠ┤Ńü«õĖĆŃüżŃüīŃĆüµĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠ (SA) Ńü«µ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃü«µ¤öĶ╗¤µĆ¦Ńü¦ŃüÖŃĆéCSCń¼¼278µØĪń¼¼1ķĀģŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃüīիܵ¼ŠŃü«Õ«ÜŃéüŃü½ŃéłŃéŖŃĆüõ╗źõĖŗŃü«3ŃüżŃü«Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣ŃāóŃāćŃā½ŃüŗŃéēŃüäŃüÜŃéīŃüŗŃéÆķüĖµŖ×Ńü¦ŃüŹŃéŗŃüōŃü©ŃéÆĶ”ÅÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃüīńøŻµ¤╗ÕĮ╣õ╝ÜĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃĆüńøŻµ¤╗ńŁēÕ¦öÕōĪõ╝ÜĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃĆüµīćÕÉŹÕ¦öÕōĪõ╝ÜńŁēĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃü«3ķĪ×Õ×ŗŃéÆÕ¤║µ£¼Ńü©ŃüŚŃüżŃüżŃééŃĆüŃüØŃü«µ¦ŗķĆĀŃüīµ»öĶ╝āńÜäÕÄ│µĀ╝Ńü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńü©Õż¦ŃüŹŃüÅńĢ░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŌæĀ õ╝ØńĄ▒ńÜäŃāóŃāćŃā½’╝łÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝Ü’╝ŗńøŻµ¤╗ÕĮ╣õ╝Ü’╝ē
ŃüōŃéīŃü»ŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü½ŃüŖŃüäŃü”õ╝ØńĄ▒ńÜäŃü½ÕżÜŃüŵÄĪńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüŹŃü¤ŃāóŃāćŃā½Ńü¦ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝Ü (Conselho de Administra├¦├Żo) ŃüīµźŁÕŗÖÕ¤ĘĶĪīŃéƵŗģŃüäŃĆüŃüØŃéīŃü©Ńü»ńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤µ®¤ķ¢óŃü¦ŃüéŃéŗńøŻµ¤╗ÕĮ╣õ╝Ü (Conselho Fiscal) ŃüīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«ĶüĘÕŗÖÕ¤ĘĶĪīŃéÆńøŻńØŻŃüÖŃéŗõĮōÕłČŃü¦ŃüÖŃĆé
ńøŻµ¤╗ÕĮ╣õ╝ÜŃü»ŃĆüµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü¦ķüĖõ╗╗ŃüĢŃéīŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«ŃāĪŃā│ŃāÉŃā╝ŃéÆÕģ╝õ╗╗ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃüŠŃüøŃéō’╝łCSCń¼¼414µØĪ’╝ēŃĆéŃüØŃü«µ©®ķÖÉŃü»CSCń¼¼420µØĪŃü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüĶ▓ĪÕŗÖµāģÕĀ▒Ńü«ń«ĪńÉåŃĆüÕåģķā©ńĄ▒ÕłČŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃü«ńøŻĶ”¢ŃĆüõ╝ÜĶ©łńøŻµ¤╗õ║║Ńü«ńŗ¼ń½ŗµĆ¦Ńü«ńøŻńØŻŃü¬Ńü®ŃĆüõ╝ÜĶ©łńøŻµ¤╗Ńü©µźŁÕŗÖńøŻµ¤╗Ńü«õĖĪµ¢╣ŃéÆÕɽŃéĆÕ║āń»äŃü¬ńøŻńØŻµ©®ķÖÉŃéƵ£ēŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ŃāóŃāćŃā½Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńøŻµ¤╗ÕĮ╣õ╝ÜĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠ’╝łõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼327µØĪń¼¼1ķĀģń¼¼2ÕÅĘ’╝ēŃü©µ¦ŗķĆĀńÜäŃü½µ£ĆŃééķĪ×õ╝╝ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńĄīÕ¢Č’╝łÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝Ü’╝ēŃüŗŃéēńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤µ®¤ķ¢ó’╝łńøŻµ¤╗ÕĮ╣õ╝Ü’╝ēŃüīńøŻµ¤╗Ńā╗ńøŻńØŻŃéƵŗģŃüåŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńü¦Õģ▒ķĆÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńøŻµ¤╗ÕĮ╣Ńüīõ╝ÜĶ©łńøŻµ¤╗õ║║Ńü«ķüĖõ╗╗ńŁēŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶŁ░µĪłÕåģÕ«╣µ▒║իܵ©®’╝łõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼344µØĪ’╝ēŃü©ŃüäŃüåÕ╝ĘÕŖøŃü¬µ©®ķÖÉŃéƵīüŃüżŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«ńøŻµ¤╗ÕĮ╣õ╝ÜŃü»õ╝ÜĶ©łńøŻµ¤╗õ║║Ńü«ķüĖõ╗╗ŃéƵĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü½ŃĆīµÅɵĪłŃüÖŃéŗŃĆŹµ©®ķÖÉ’╝łCSCń¼¼420µØĪ(f)ÕÅĘ’╝ēŃü¦ŃüéŃéŗŃü¬Ńü®ŃĆüń┤░ŃüŗŃü¬µ©®ķÖÉķģŹÕłåŃü½Ńü»ķüĢŃüäŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŌæĪ ńøŻµ¤╗Õ¦öÕōĪõ╝Üõ╗śÕŹśõĖĆÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃāóŃāćŃā½
ŃüōŃü«ŃāóŃāćŃā½Ńü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝Ü (Conselho de Administra├¦├Żo) ŃéÆĶ©ŁńĮ«ŃüŚŃĆüŃüØŃü«Õåģķā©Ńü½ńøŻµ¤╗Õ¦öÕōĪõ╝Ü (Comiss├Żo de Auditoria) ŃéÆĶ©ŁŃüæŃéŗõĮōÕłČŃü¦ŃüÖ’╝łCSCń¼¼278µØĪń¼¼1ķĀģ(b)ÕÅĘ’╝ēŃĆé
ńøŻµ¤╗Õ¦öÕōĪõ╝ÜŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«ŃāĪŃā│ŃāÉŃā╝Ńü«õĖŁŃüŗŃéēķüĖõ╗╗ŃüĢŃéīŃü¤ŃĆüµ£ĆõĮÄ3ÕÉŹŃü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü¦µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃüŠŃüÖ’╝łCSCń¼¼423µØĪ-B’╝ēŃĆéķćŹĶ”üŃü¬ńé╣Ńü»ŃĆüńøŻµ¤╗Õ¦öÕōĪõ╝ÜŃü«ŃāĪŃā│ŃāÉŃā╝Ńü»µźŁÕŗÖÕ¤ĘĶĪīµ®¤ĶāĮ (fun├¦├Ąes executivas) ŃéƵīüŃüżŃüōŃü©Ńüīń”üŃüśŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüżŃüŠŃéŖŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«Õåģķā©Ńü½ŃĆüķØ×µźŁÕŗÖÕ¤ĘĶĪīŃü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü½ńē╣Õī¢ŃüŚŃü¤ńøŻµ¤╗µ®¤ķ¢óŃéÆĶ©ŁńĮ«ŃüÖŃéŗŃāóŃāćŃā½Ńü¦ŃüÖŃĆéńøŻµ¤╗Õ¦öÕōĪõ╝ÜŃü«µ©®ķÖÉŃü»CSCń¼¼423µØĪ-FŃü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«µ┤╗ÕŗĢÕģ©Ķł¼Ńü«ńøŻńØŻ’╝łfiscaliza├¦├Żo da administra├¦├Żo da sociedade’╝ēŃü¬Ńü®ŃüīÕɽŃüŠŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ŃāóŃāćŃā½Ńü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃéÆńøŻńØŻŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńü¦ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńøŻµ¤╗ńŁēÕ¦öÕōĪõ╝ÜĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃéäµīćÕÉŹÕ¦öÕōĪõ╝ÜńŁēĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠ’╝łŃü½ŃüŖŃüæŃéŗńøŻµ¤╗Õ¦öÕōĪõ╝Ü’╝ēŃü©ķØ×ÕĖĖŃü½Ķ┐æŃüäńÖ║µā│Ńü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«ńøŻµ¤╗ńŁēÕ¦öÕōĪõ╝ÜĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃééŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣’╝łńøŻµ¤╗ńŁēÕ¦öÕōĪ’╝ēŃü¦µ¦ŗµłÉŃüĢŃéīŃéŗńøŻµ¤╗ńŁēÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃüīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ĶüĘÕŗÖÕ¤ĘĶĪīŃéÆńøŻµ¤╗ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéńĄīÕ¢ČŃü©ńøŻńØŻŃü«ÕĮ╣Õē▓ŃéÆÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜÕåģķā©Ńü¦ÕłåķøóŃā╗µśÄńó║Õī¢ŃüÖŃéŗŃĆüńÅŠõ╗ŻńÜäŃü¬Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣ŃāóŃāćŃā½Ńü«õĖĆŃüżŃü©Ķ©ĆŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
Ōæó õ║īÕ▒żµ¦ŗķĆĀŃāóŃāćŃā½’╝łńøŻńØŻÕ¦öÕōĪõ╝Ü’╝ŗÕ¤ĘĶĪīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝Ü’╝ē
ŃüōŃéīŃü»ŃĆüŃāēŃéżŃāäµ│ĢŃü«ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕ╝ĘŃüÅÕÅŚŃüæŃü¤ŃāóŃāćŃā½Ńü¦ŃĆüµ®¤ķ¢óŃéƵśÄńó║Ńü½ŃĆīńøŻńØŻŃĆŹŃü©ŃĆīµźŁÕŗÖÕ¤ĘĶĪīŃĆŹŃü½ÕłåķøóŃüÖŃéŗõĮōÕłČŃü¦ŃüÖ’╝łCSCń¼¼278µØĪń¼¼1ķĀģ(c)ÕÅĘ’╝ēŃĆé
ŃüōŃü«ŃāóŃāćŃā½Ńü¦Ńü»ŃĆüŃüŠŃüܵĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃüīńĘÅõ╝ÜŃā╗ńøŻńØŻÕ¦öÕōĪõ╝Ü (Conselho Geral e de Supervis├Żo) ŃéÆķüĖõ╗╗ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃĆüŃüōŃü«ńøŻńØŻÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃüīÕ¤ĘĶĪīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝Ü (Conselho de Administra├¦├Żo Executivo) Ńü«ŃāĪŃā│ŃāÉŃā╝ŃéÆķüĖõ╗╗Ńā╗Ķ¦Żõ╗╗ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ńøŻńØŻÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃü»ŃĆüÕ¤ĘĶĪīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«µ┤╗ÕŗĢŃéƵüÆõ╣ģńÜäŃü½ńøŻńØŻŃüŚ’╝łCSCń¼¼441µØĪ’╝ēŃĆüÕŖ®Ķ©ĆŃéÆõĖÄŃüłŃéŗÕĮ╣Õē▓ŃéƵŗģŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖƵ¢╣ŃĆüÕ¤ĘĶĪīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃüīµŚźÕĖĖŃü«µźŁÕŗÖÕ¤ĘĶĪīŃéÆÕ░éÕ▒×ńÜäŃü½µŗģÕĮōŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕ¤ĘĶĪīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«ŃāĪŃā│ŃāÉŃā╝Ńü»ńøŻńØŻÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃü«ŃāĪŃā│ŃāÉŃā╝ŃéÆÕģ╝ŃüŁŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃüÜŃĆüńøŻńØŻŃü©Õ¤ĘĶĪīŃüīõ║║ńÜäŃü½Ńé鵜Äńó║Ńü½ÕłåķøóŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«µ¦ŗķĆĀŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µīćÕÉŹÕ¦öÕōĪõ╝ÜńŁēĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃü©µ»öĶ╝āŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃüīÕ¤ĘĶĪīÕĮ╣ŃéÆķüĖõ╗╗Ńā╗ńøŻńØŻŃüŚ’╝łõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼416µØĪ’╝ēŃĆüÕ¤ĘĶĪīÕĮ╣ŃüīµźŁÕŗÖÕ¤ĘĶĪīŃéƵŗģŃüäŃüŠŃüÖ’╝łÕÉīń¼¼415µØĪ’╝ēŃĆéŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«õ║īÕ▒żµ¦ŗķĆĀŃāóŃāćŃā½Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µīćÕÉŹÕ¦öÕōĪõ╝ÜńŁēĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃĆīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝Ü’╝łŃü«ńøŻńØŻµ®¤ĶāĮ’╝ēŃĆŹŃüīŃĆīńøŻńØŻÕ¦öÕōĪõ╝ÜŃĆŹŃü½ŃĆüŃĆīÕ¤ĘĶĪīÕĮ╣ŃĆŹŃüīŃĆīÕ¤ĘĶĪīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃĆŹŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü©ńÉåĶ¦ŻŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃü¤ŃüĀŃüŚŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½µ│ĢŃü«µ¢╣ŃüīŃĆüńøŻńØŻµ®¤ķ¢ó’╝łńøŻńØŻÕ¦öÕōĪõ╝Ü’╝ēŃüīÕ¤ĘĶĪīµ®¤ķ¢ó’╝łÕ¤ĘĶĪīÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝Ü’╝ēŃü«ŃāĪŃā│ŃāÉŃā╝ŃéÆńø┤µÄźķüĖõ╗╗Ńā╗Ķ¦Żõ╗╗ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńü¦ŃĆüŃéłŃéŖµśÄńó║Ńü½ńøŻńØŻŃü©Õ¤ĘĶĪīŃü«õĖŖõĖŗķ¢óõ┐éŃü©ÕłåķøóŃéÆÕŠ╣Õ║ĢŃüŚŃü¤µ¦ŗķĆĀŃü¦ŃüéŃéŗŃü©Ķ©ĆŃüłŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«ńŠ®ÕŗÖŃü©Ķ”üõ╗Č
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü¦õ╝ÜńżŠŃéÆĶ©Łń½ŗŃā╗ķüŗÕ¢ČŃüÖŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║Ńü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü½µ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗµ│ĢńÜäńŠ®ÕŗÖŃéƵŁŻńó║Ńü½µŖŖµÅĪŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
Õ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃü©Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝Õł®ńøŖŃü«ĶĆāµģ«’╝łµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«ķćŹĶ”üŃü¬ńøĖķüĢńé╣’╝ē
ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Õ¤║µ£¼ńÜäŃü¬ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃĆüCSCń¼¼64µØĪŃü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕÉīµØĪń¼¼1ķĀģ(a)ÕÅĘŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīŃĆīĶ│óµśÄŃü¦ń¦®Õ║ÅŃüéŃéŗń«ĪńÉåĶĆģ (dilig├¬ncia de um gestor criterioso e ordenado)ŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”Ńü«µ│©µäÅńŠ®ÕŗÖ (Duty of Care) ŃéÆĶ▓ĀŃüåŃüōŃü©ŃéÆĶ”ÅÕ«ÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ│©µäÅńŠ®ÕŗÖŃéƵףŃü¤ŃüŚŃü¤ŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃü«Õłżµ¢ŁŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüÕŹüÕłåŃü¬µāģÕĀ▒Ńü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüÕÉłńÉåńÜäŃü¬ńĄīÕ¢ČÕłżµ¢ŁŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½Ńü»Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆÕĢÅŃéÅŃéīŃü¬ŃüäŃü©ŃüÖŃéŗŃĆīńĄīÕ¢ČÕłżµ¢ŁŃü«ÕĤÕēć (Business Judgment Rule)ŃĆŹŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖ’╝łCSCń¼¼72µØĪń¼¼2ķĀģ’╝ēŃĆéŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü«ķü®ńö©Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½µ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆ’╝łSupremo Tribunal de Justi├¦a’╝ēŃü«2013Õ╣┤5µ£ł22µŚźõ╗śÕłżµ▒║’╝łCase No. 2024/05.2TBAGD.C1.C1’╝ēŃü¬Ńü®ŃĆüÕłżõŠŗŃü«Ķōäń®ŹŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīńē╣Ńü½µ│©µäÅŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüÕÉīµØĪń¼¼1ķĀģ(b)ÕÅĘŃü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü¤Õ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖ (Duty of Loyalty) Ńü«ÕåģÕ«╣Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃüīŃĆīõ╝ÜńżŠŃü«Õł®ńøŖ (no interesse da sociedade)ŃĆŹŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ĶĪīÕŗĢŃüÖŃü╣ŃüŹńŠ®ÕŗÖŃéÆÕ«ÜŃéüŃéŗŃü©ÕÉīµÖéŃü½ŃĆüŃüØŃü«ķÜøŃĆüŃĆīµĀ¬õĖ╗Ńü«ķĢʵ£¤ńÜäÕł®ńøŖ (interesses de longo prazo dos s├│cios)ŃĆŹŃéÆõ╗śõĖÄŃüŚŃĆüŃüŗŃüżŃĆīõ╝ÜńżŠŃü«µīüńČÜÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńü½ķ¢óķĆŻŃüÖŃéŗõ╗¢Ńü«õĖ╗õĮō’╝łÕŖ┤ÕāŹĶĆģŃĆüķĪ¦Õ«óŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃü¬Ńü® (interesses de outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade, como sejam os seus trabalhadores, clientes e credores)’╝ēŃĆŹŃü«Õł®ńøŖŃéÆĶĆāµģ«ŃüÖŃéŗ (atendendo) ŃüōŃü©ŃéƵ▒éŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü«Ķ¦ŻķćłŃü©Õż¦ŃüŹŃüÅńĢ░Ńü¬Ńéŗńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Õ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖ’╝łõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼355µØĪ’╝ēŃü»ŃĆüõĖ╗Ńü½ŃĆīµĀ¬õĖ╗Ńü«Õģ▒ÕÉīŃü«Õł®ńøŖŃĆŹŃü«µ£ĆÕż¦Õī¢ŃéÆÕø│ŃéŗńŠ®ÕŗÖŃü©ŃüŚŃü”Ķ¦ŻķćłŃüĢŃéīŃéŗÕéŠÕÉæŃü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖ’╝łµ£ĆÕłżÕ╣│21.4.17Ńü¬Ńü®’╝ēŃĆéŃééŃüĪŃéŹŃéōŃĆüµŚźµ£¼Ńü¦ŃééķĢʵ£¤ńÜäŃü¬õ╝üµźŁõŠĪÕĆżÕÉæõĖŖŃü«Ńü¤ŃéüŃü½Ńü»Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝ŃüĖŃü«ķģŹµģ«ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüéŃéŗŃü©Ķ¬ŹĶŁśŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½µ│ĢŃü»ŃĆüµ│ĢÕŠŗŃü«µØĪµ¢ćõĖŖŃĆüµśÄńó║Ńü½ŃĆīÕŠōµźŁÕōĪŃĆüķĪ¦Õ«óŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃĆŹŃü©ŃüäŃüŻŃü¤µĀ¬õĖ╗õ╗źÕż¢Ńü«Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝Ńü«Õł®ńøŖŃéÆŃĆīĶĆāµģ«ŃüÖŃéŗŃĆŹŃüōŃü©ŃéÆÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«µ│ĢńÜäńŠ®ÕŗÖŃü«ÕåģÕ«╣Ńü©ŃüŚŃü”ÕÅ¢ŃéŖĶŠ╝ŃéōŃü¦ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü¦ńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║Ńü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣’╝łńē╣Ńü½µŚźµ£¼õ║║ķ¦ÉÕ£©ÕōĪŃü¬Ńü®’╝ēŃü½Õ░▒õ╗╗ŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕŹśŃü½Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃéäµĀ¬õĖ╗Ńü«µäÅÕÉæŃü½ÕŠōŃüåŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüńÅŠÕ£░Ńü«ÕŠōµźŁÕōĪŃĆüķĪ¦Õ«óŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢÕģłŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ÕżÜµ¦śŃü¬Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝Ńü«Õł®ńøŖŃü½ŃééķģŹµģ«ŃüŚŃü¤ńĄīÕ¢ČÕłżµ¢ŁŃéÆĶĪīŃüåŃüōŃü©ŃüīŃĆüµ│ĢÕŠŗõĖŖŃü«ńŠ®ÕŗÖŃü©ŃüŚŃü”µ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗńé╣Ńü½ŃĆüµ£ĆÕż¦ķÖÉŃü«ńĢÖµäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Ķ│ćµĀ╝Ķ”üõ╗Č
ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Ķ│ćµĀ╝Ķ”üõ╗ČŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Õģ▒ķĆÜŃüÖŃéŗńé╣ŃééÕżÜŃüäŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖķćŹĶ”üŃü¬µēŗńČÜŃüŹŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃüÜŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»Ķć¬ńäČõ║║Ńü¦ŃüéŃéīŃü░ŃéłŃüÅŃĆüµĀ¬õĖ╗Ńü¦ŃüéŃéŗÕ┐ģĶ”üŃü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«Õ▒ģõĮÅĶĆģŃü¦ŃüéŃéŗÕ┐ģĶ”üŃééŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½ÕøĮń▒ŹŃü¦ŃüéŃéŗÕ┐ģĶ”üŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆ鵌źµ£¼ŃüŗŃéēµ┤ŠķüŻŃüĢŃéīŃéŗķ¦ÉÕ£©ÕōĪŃüīŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü½Õ▒ģõĮÅŃüøŃüÜŃü½ķØ×Õ▒ģõĮÅĶĆģŃü«ŃüŠŃüŠńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║Ńü«ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü½Õ░▒õ╗╗ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńééµ│ĢńÜäŃü½Ńü»ÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüÖŃĆé
Ńü¤ŃüĀŃüŚŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃĆüµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¬Ķ”üõ╗ČŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃéīŃü»ŃĆüÕż¢ÕøĮõ║║ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«ń©ÄÕŗÖĶŁśÕłźńĢ¬ÕÅĘ (NIF – N├║mero de Identifica├¦├Żo Fiscal) ŃéÆÕÅ¢ÕŠŚŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕ┐ģķĀłŃü¦ŃüéŃéŗńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆéNIFŃü»ŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ń©ÄÕŗÖńö│ÕæŖŃĆüķŖĆĶĪīÕÅŻÕ║¦Ńü«ķ¢ŗĶ©ŁŃĆüÕźæń┤äŃü«ńĘĀńĄÉŃü¬Ńü®ŃĆüŃüéŃéēŃéåŃéŗńĄīµĖłµ┤╗ÕŗĢŃü«Õ¤║µ£¼Ńü©Ńü¬ŃéŗÕĆŗõ║║ĶŁśÕłźńĢ¬ÕÅĘŃü¦ŃüÖŃĆéÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü½Õ░▒õ╗╗ŃüŚŃĆüŃüØŃü«ĶüĘÕŗÖŃéÆķüéĶĪīŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüŃü¤Ńü©ŃüłķØ×Õ▒ģõĮÅĶĆģŃü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééŃĆüŃüŠŃüÜNIFŃéÆÕÅ¢ÕŠŚŃüÖŃéŗµēŗńČÜŃüŹŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü«ÕĮ╣Õē▓
µ£ĆÕŠīŃü½ŃĆüµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝Ü (Assembleia Geral) Ńü«ÕĮ╣Õē▓Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¦”ŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»µŚźµ£¼µ│ĢŃü©ķĪ×õ╝╝ŃüÖŃéŗńé╣ŃüīÕżÜŃüäŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüķ¢ŗÕé¼µÖéµ£¤Ńü½ŃüżŃüäŃü”µśÄńó║Ńü¬Õ«ÜŃéüŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠ (SA) ŃüŖŃéłŃü│µ£ēķÖÉõ╝ÜńżŠ (Lda) Ńü»ŃĆüÕ╣┤µ¼ĪµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃéÆķ¢ŗÕé¼ŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéCSCń¼¼376µØĪń¼¼1ķĀģŃü»ŃĆüŃüōŃü«Õ╣┤µ¼ĪńĘÅõ╝ÜŃéÆŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”õ╝ÜĶ©łÕ╣┤Õ║”µ£½ŃüŗŃéē3Ńāȵ£łõ╗źÕåģŃü½ķ¢ŗÕé¼ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃü©Õ«ÜŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝łŃü¤ŃüĀŃüŚŃĆüķĆŻńĄÉĶ©łń«ŚµøĖķĪ×ŃéÆõĮ£µłÉŃüÖŃéŗõ╝ÜńżŠńŁēŃü»5Ńāȵ£łõ╗źÕåģ’╝ēŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢŃüīիܵÖéµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆīµ»Äõ║ŗµźŁÕ╣┤Õ║”Ńü«ńĄéõ║åÕŠīõĖĆÕ«ÜŃü«µÖéµ£¤ŃĆŹ’╝łõ╝ÜńżŠµ│Ģń¼¼296µØĪń¼¼1ķĀģ’╝ēŃü©ŃüŚŃüŗÕ«ÜŃéüŃü”ŃüŖŃéēŃüÜŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃĆüµ│Ģõ║║ń©Äńö│ÕæŖµ£¤ķÖÉ’╝łÕĤÕēćõ║ŗµźŁÕ╣┤Õ║”µ£½ŃüŗŃéē2Ńāȵ£łŃĆüÕ╗ČķĢĘÕÅ»’╝ēŃü©Ńü«Õģ╝ŃüŁÕÉłŃüäŃü¦µ▒║ń«Śµē┐Ķ¬ŹńĘÅõ╝ÜŃüīķ¢ŗÕé¼ŃüĢŃéīŃéŗŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃéłŃéŖÕÄ│µĀ╝Ńü¬µ£¤ķÖÉĶ©ŁÕ«ÜŃü©Ķ©ĆŃüłŃüŠŃüÖŃĆé
Õ╣┤µ¼ĪńĘÅõ╝ÜŃü«õĖ╗Ķ”üŃü¬µ▒║ĶŁ░õ║ŗķĀģŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü©ÕÉīµ¦śŃĆüĶ©łń«ŚµøĖķĪ×’╝łńĄīÕ¢ČÕĀ▒ÕæŖµøĖŃĆüĶ▓ĖÕĆ¤Õ»Šńģ¦ĶĪ©ŃĆüµÉŹńøŖĶ©łń«ŚµøĖŃü¬Ńü®’╝ēŃü«µē┐Ķ¬ŹŃĆüÕł®ńøŖŃü«ķģŹÕłå’╝łķģŹÕĮōŃü¬Ńü®’╝ēŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣ŃéäńøŻµ¤╗ÕĮ╣’╝łõ╝Ü’╝ēŃü«µ┤╗ÕŗĢŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗĶ®ĢõŠĪŃĆüŃüŖŃéłŃü│ÕĮ╣ÕōĪŃü«ķüĖõ╗╗Ńā╗Ķ¦Żõ╗╗Ńü¬Ńü®Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Õģ▒ÕÆīÕøĮŃü«Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü«µ│ĢńÜäµ×ĀńĄäŃü┐Ńü©µ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüńē╣Ńü½ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü¦Ńü«ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗŃéƵż£Ķ©ÄŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü«ńÜ嵦śŃü½ÕÉæŃüæŃü”ŃĆüµŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«ńøĖķüĢńé╣ŃéÆõĖŁÕ┐āŃü½Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüEUŃü«µ×ĀńĄäŃü┐Ńü«õĖŁŃü¦ńÖ║Õ▒ĢŃüŚŃüżŃüżŃĆüńŗ¼Ķć¬Ńü«µ¤öĶ╗¤µĆ¦Ńü©ńē╣ÕŠ┤ŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ķćŹĶ”üŃü¬ńé╣Ńü»õ╗źõĖŗŃü«ķĆÜŃéŖŃü¦ŃüÖŃĆé
- ÕżÜµ¦śŃü¬µ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©ł: µĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠ (SA) Ńü»ŃĆüCSCń¼¼278µØĪŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ńøŻµ¤╗ÕĮ╣õ╝ÜĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃü½Ķ┐æŃüäŃĆīõ╝ØńĄ▒ńÜäŃāóŃāćŃā½ŃĆŹŃĆüńøŻµ¤╗ńŁēÕ¦öÕōĪõ╝ÜĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃü¬Ńü®Ńü½Ķ┐æŃüäŃĆīńøŻµ¤╗Õ¦öÕōĪõ╝Üõ╗śÕŹśõĖĆÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃāóŃāćŃā½ŃĆŹŃĆüŃüØŃüŚŃü”µīćÕÉŹÕ¦öÕōĪõ╝ÜńŁēĶ©ŁńĮ«õ╝ÜńżŠŃü©µ»öĶ╝āŃüĢŃéīŃéŗŃĆīõ║īÕ▒żµ¦ŗķĆĀŃāóŃāćŃā½ŃĆŹŃü«3ŃüżŃüŗŃéēŃĆüĶć¬ńżŠŃü«Õ«¤µāģŃü½ÕÉłŃüŻŃü¤õĮōÕłČŃéÆĶć¬ńö▒Ńü½ķüĖµŖ×Ńü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
- µśÄńó║Ńü¬Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝ķģŹµģ«ńŠ®ÕŗÖ: CSCń¼¼64µØĪŃü»ŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü«Õ┐ĀÕ«¤ńŠ®ÕŗÖŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüµĀ¬õĖ╗Ńü«ķĢʵ£¤ńÜäÕł®ńøŖŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃĆīÕŠōµźŁÕōĪŃĆüķĪ¦Õ«óŃĆüÕ饵©®ĶĆģŃĆŹŃü©ŃüäŃüŻŃü¤õ╗¢Ńü«Ńé╣ŃāåŃā╝Ńé»ŃāøŃā½ŃāĆŃā╝Ńü«Õł®ńøŖŃéÆŃééĶĆāµģ«ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéƵ│ĢńÜäŃü½ńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»µŚźµ£¼µ│ĢŃü«Ķ¦ŻķćłŃéłŃéŖŃééõĖƵŁ®ĶĖÅŃü┐ĶŠ╝ŃéōŃüĀĶ”ÅÕ«ÜŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüńÅŠÕ£░Ńü¦Ńü«ńĄīÕ¢ČÕłżµ¢ŁŃü½ŃüŖŃüäŃü”ķćŹĶ”üŃü¬µīćķćØŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńé│Ńā╝Ńāē: õĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃü»ŃĆüIPCGŃüīńÖ║ĶĪīŃüÖŃéŗŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńé│Ńā╝ŃāēŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüŃĆīķüĄÕ«łŃüŠŃü¤Ńü»Ķ¬¼µśÄŃĆŹÕĤÕēćŃü½ÕŠōŃüŻŃü¤µāģÕĀ▒ķ¢ŗńż║Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
- Õ«¤ÕŗÖõĖŖŃü«Ķ”üõ╗Č: Õż¢ÕøĮõ║║’╝łķØ×Õ▒ģõĮÅĶĆģ’╝ēŃü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃééÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü½Õ░▒õ╗╗Ńü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕ«¤ÕŗÖõĖŖŃĆüŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½ń©ÄÕŗÖĶŁśÕłźńĢ¬ÕÅĘ (NIF) Ńü«ÕÅ¢ÕŠŚŃüīÕ┐ģķĀłŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- µĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü«µ£¤ķÖÉ: Õ╣┤µ¼ĪµĀ¬õĖ╗ńĘÅõ╝ÜŃü»ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”õ╝ÜĶ©łÕ╣┤Õ║”µ£½ŃüŗŃéē3Ńāȵ£łõ╗źÕåģŃü½ķ¢ŗÕé¼ŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü½ķĆ▓Õć║ŃüÖŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”Ńü»ŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«ķüĢŃüäŃéƵŁŻńó║Ńü½ńÉåĶ¦ŻŃüŚŃĆüĶć¬ńżŠŃü«Ńé░ŃāŁŃā╝ŃāÉŃā½Ńü¬Ńé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣µ¢╣ķćØŃü©ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½µ│ĢŃü«Ķ”üµ▒éŃéƵĢ┤ÕÉłŃüĢŃüøŃü¬ŃüīŃéēŃĆüµ£Ćķü®Ńü¬ńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║Ńü«ńĄ▒µ▓╗õĮōÕłČŃéƵ¦ŗń»ēŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃĆüÕååµ╗æŃü¬õ║ŗµźŁķüŗÕ¢ČŃü©Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ńü«Õ¤║ńøżŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃüåŃüŚŃü¤ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«Ńé│Ńā╝ŃāØŃā¼Ńā╝ŃāłŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ│ĢÕłČÕ║”Ńü«Ķ¬┐µ¤╗ŃĆüńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║Ńü«µ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃĆüÕÉäń©«Ķ”ÅÕēćŃü«µĢ┤ÕéÖŃĆüŃüŠŃü¤µŚźµ£¼µ│ĢŃü©Ńü«µ»öĶ╝āµż£Ķ©ÄŃü¬Ńü®Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃéĄŃāØŃā╝ŃāłŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ńü«õ╝ÜńżŠµ│ĢÕłČŃéäŃé¼ŃāÉŃāŖŃā│Ńé╣õĮōÕłČŃü½ķ¢óŃüŚŃü”ŃüöõĖŹµśÄŃü¬ńé╣ŃéäŃüöńøĖĶ½ćŃüīŃüöŃü¢ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃéēŃĆüŃüŖµ░ŚĶ╗ĮŃü½ŃüŖÕĢÅŃüäÕÉłŃéÅŃüøŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ