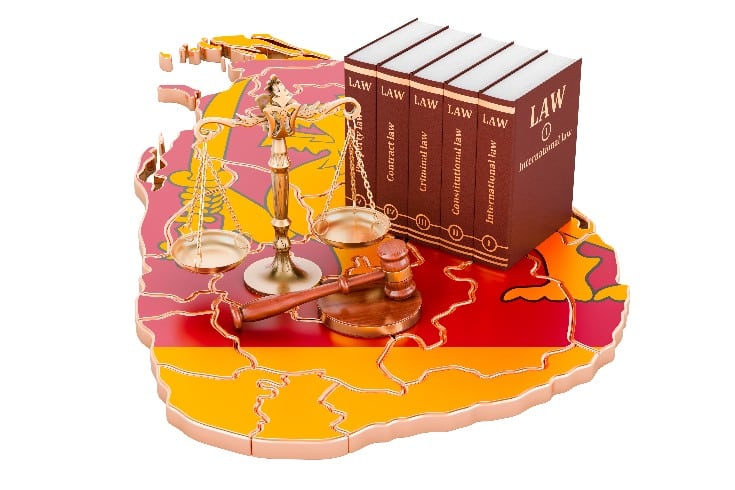デンマークの会社法が定めるコーポレートガバナンスを詳細に解説

デンマーク王国(以下、デンマーク)は、北欧諸国の一員として、国際的なビジネス環境において安定した法的枠組みを提供していますが、そのコーポレートガバナンス制度は、日本企業が通常運用する仕組みとは根本的に異なります。特に、公開有限会社(Aktieselskaber, A/S)の経営機構は、戦略と執行の構造的な分離を強く要求しており、執行役員会メンバーが取締役会の過半数を占めることを禁じる厳格な独立性要件が課されています。
さらに、デンマーク会社法(Selskabsloven)の最も特徴的な側面の一つが、一定規模以上の企業における従業員の経営参加、すなわち「共同決定権」を法定化した従業員代表取締役制度です。これは、企業統治におけるステークホルダー資本主義の強い現れであり、労働者の権利と影響力を重視する北欧モデルの中核を成しています。日本の経営層や法務部員がデンマークでの事業展開を成功させるためには、日本の会社法における慣行とのこれらの決定的な差異を深く理解し、適切な体制を構築することが不可欠となります。
本稿では、デンマーク会社法を根拠とし、取締役会構造、株主権の範囲、および役員責任に関する最新の法的枠組みを詳細に解説します。
この記事の目次
デンマーク会社法に基づく機関設計の選択肢:構造的独立性の強制
デンマーク会社法(DCA)は、企業形態に応じて異なるガバナンス構造の採用を認めていますが、特に公開有限会社(A/S)においては、戦略的意思決定と日常業務執行の分離を制度的に保証する構造が強制されています。
取締役会構造の法的選択肢
デンマークの会社は、規模や形態に応じて、主に以下の三つのガバナンスモデルから選択することができます。
一つ目は、取締役会(bestyrelse)と執行役員会(direktion)からなる二層構造です。この古典的なデンマークの経営システムでは、取締役会が企業全体の戦略的かつ包括的な経営に責任を負い、その監督の下で執行役員会を任命し、日常業務の管理を担当させます。
二つ目は、監督会(tilsynsråd)と執行役員会からなる二層構造です。この場合、監督会は執行役員会に対して純粋な監督機能のみを果たし、執行役員会が日常業務を管理します。
そして三つ目は、執行役員会のみによる一層構造ですが、これは非公開有限会社(Anpartsselskaber, ApS)のみに認められている簡素化されたガバナンス体制です。
公開有限会社(A/S)における戦略と執行の分離原則と独立性要件
公開有限会社(A/S)の場合、経営の中核を担う取締役会に関して、構造的な独立性を確保するための具体的な法的要件が課されています。まず、A/Sの取締役会は、最低3名の取締役で構成される必要があります。取締役は18歳以上の自然人であることが必須要件です。
さらに、A/Sの取締役会(戦略決定・監督機関)の独立性を担保するため、執行役員会(日常業務執行機関)のメンバーが取締役会の過半数を占めてはならないという明確な規定が存在します。この規定は、取締役会が執行役員会に対して有効に監督責任を果たすために、執行側からの影響力を排除することを目的としています。また、執行役員会のメンバーは、取締役会の議長または副議長を務めることも禁じられています。
この分離原則は、日本法におけるガバナンス構造との大きな違いを示しています。日本の会社法においては、特に監査役会設置会社や非上場企業において、代表取締役などの業務執行者が取締役会を主導することが一般的であり、戦略と執行のトップが同一の人間であるケースが多く見られます。しかし、デンマークのA/Sにおける独立性要件は、日本の指名委員会等設置会社に類似した機能的分離を、人数構成という客観的な基準によって強制していると解釈できます。
したがって、日本企業がデンマークで公開有限会社を設立し、親会社から幹部を派遣する場合、取締役会において非執行(執行役員会メンバーではない)の構成員を確実に過半数確保することが実務上の課題となります。親会社主導の体制を維持しつつも現地法令を遵守するためには、親会社側の人間ではない外部の独立した取締役を選任するなど、日本の慣行とは異なるアプローチが求められます。
北欧モデルの核心であるデンマーク:従業員代表取締役制度(共同決定権)

デンマークのコーポレートガバナンスにおける最も重要な構造的差異の一つは、従業員に取締役の選任権を付与する法定制度、すなわち共同決定権(co-determination)です。これは、企業統治を株主だけの利益に限定せず、労働者という主要なステークホルダーの利益も反映させるという、北欧モデルの強い理念を反映しています。
制度適用の法的要件と選任人数の計算
この従業員代表取締役制度は、すべての公開有限会社に適用されるわけではありませんが、一定規模を超えると自動的に義務化されます。具体的には、過去3年間で平均して35名以上の従業員を雇用しているA/Sでは、従業員は取締役会のメンバーを選任する法定の権利を有します。
この従業員数の算定には、デンマークの親会社だけでなく、デンマーク国内に登記された子会社、さらにはEU/EEA加盟国に所在する外国支店の従業員も含まれる場合があります。
従業員代表の選任人数は、株主によって選任された取締役会メンバーの半数(1/2)に相当する人数と規定されています。ただし、選出される従業員代表は最低2名以上でなければなりません。さらに、人数の計算結果が整数にならない場合、その数は切り上げて計算されることになります。
例えば、株主が選任した取締役が5名の場合、その半数は2.5名ですが、切り上げにより従業員代表は3名選出される権利を持つことになります。これにより、取締役会全体(8名)のうち3名(約37.5%)を従業員が占めることになり、その影響力は無視できません。
代表者の権限と経営戦略への影響
従業員代表取締役は、機密保持義務、利益相反規則、報酬など、他の株主選任の取締役と同一の権利と義務を負います。これは、彼らが単なる労働者の代弁者ではなく、会社全体の利益のために行動するフィデューシャリー・デューティー(受託者責任)を負うことを意味します。
日本の会社法では、従業員が取締役を選任する法定の権利は存在せず、労働者の意見は主に労働組合や労使協議会といった枠組みを通じて経営に反映されます。しかし、これらの機関の代表者は、一般的に取締役会の議決権を持つメンバーとして戦略的な意思決定に直接関与することはありません。
デンマークの共同決定権は、日本の進出企業に対し、経営戦略の策定、大規模な再編、投資計画などの重要な決定プロセスにおいて、従業員側の視点や利益を強く考慮に入れることを強制します。従業員代表が取締役会構成員の過半数に迫る、あるいはそれを超える(監督会の場合)構成になり得る構造は、企業が予期せぬリスクや交渉の長期化を避けるために、戦略の初期段階から従業員代表取締役との継続的な対話と合意形成の努力が必要であることを示しています。
デンマークの「全能の株主総会」と株主権の積極的な行使
デンマーク会社法における株主総会の地位と権限は、日本の会社法における最高意思決定機関としての機能とは異なる、独特の「全能性」原則に基づいています。
株主総会の権限(全能性)と日本法との対比
デンマーク法において、年次株主総会は「全能」(omnipotent)であると見なされています。この原則は、法律(Selskabsloven)または会社の定款によって、取締役会または執行役員会に権限が明示的に割り当てられていない限り、会社に関するあらゆる事項を株主総会が決定できることを意味します。
これは日本の会社法における株主総会の機能と決定的に対照的です。日本の会社法において株主総会は会社の最高意思決定機関ではありますが、日常的な業務執行に関する決定権限は、一般的に取締役会に包括的に委任されます(会社法第362条)。つまり、日本においては取締役会が業務執行の広範な決定権を持つのが一般的です。
しかし、デンマーク法では、取締役会の権限は、あくまで法律や定款による限定的な委任によって付与されるものとして解釈されます。委任されていない残余権限は、すべて株主が保持しているという構造的な違いが存在します。株主の総会への積極的な参加権は、欧州の株主権利指令(Shareholder Rights Directive:SRD IおよびSRD II)によっても規定されていますが、デンマークの会社法はこの指令が導入される以前から、歴史的に株主に対して非常に広範な権利を認めてきました。
定款の設計と業務の迅速性の確保
この「全能性」の原則は、実務において重大な影響を及ぼします。もし日本企業がデンマーク現地法人の定款を、日本の標準的な慣行に基づいて曖昧に、あるいは限定的に作成した場合、日常的な経営判断や、戦略的ながらも定款に明記されていない事項が、株主総会(すなわち親会社)の承認を必要とすることになり、業務の迅速性が著しく損なわれるリスクがあります。
したがって、デンマークに事業展開する日本企業は、現地法人の定款(vedtægter)を設計する際、取締役会または執行役員会に委任する業務執行権限の範囲を、日本の慣行よりも遥かに明確かつ広範に定義しておくことが不可欠となります。これにより、ガバナンス構造の効率性を高め、迅速な経営判断を可能にすることができます。
デンマーク会社法における役員の義務違反と責任の所在:Højesteretの厳格な判例分析
デンマーク会社法は、取締役に対して高い善管注意義務を課しており、義務違反に対する損害賠償責任の追及は厳格です。この責任追及の厳格さは、特に倒産事例や国際的なコンプライアンス事案において、最高裁判所(Højesteret)の判例によって裏付けられています。
取締役の一般的な責任と少数株主の保護
取締役会のメンバーは、職務遂行において故意または過失により会社、株主、または第三者に損害を与えた場合、それらの者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。取締役に対する訴訟提起の決定は、通常、株主の単純過半数によって行われます。
特筆すべきは、少数株主の権利保護です。全株式資本の少なくとも10%を保有する少数株主は、会社が取締役に対して責任免除決議(discharge)を可決したり、訴訟提起の権利を放棄する決議に反対したりした場合、会社に代わって取締役に対する訴訟(株主代表訴訟に類似)を提起できる権利を有します。この10%ルールは、取締役会の免責を容易にさせず、株主による監督機能を実質的に担保するための重要な仕組みです。
また、取締役は継続的に会社の事業継続の合理性を評価する義務があります。この合理性が失われたにもかかわらず、適時に解散、再建または破産の申請を行わなかった場合、取締役は倒産法上の責任を問われる可能性があります。
最高裁判所による個人責任の確認と租税濫用への対応
デンマークの最高裁判所(Højesteret)は、会社が責任を負う場合であっても、取締役個人が善管注意義務違反に基づいて第三者に対して個人責任を負う可能性を排除しないことを確認しています。例えば、2019年2月15日に下されたCapinordic Bankに関する管理責任訴訟判決や、それに続く複数の判例を通じて、取締役のデュー・デリジェンスの範囲が厳格に適用されています。
さらに、国際的なグループ企業における租税回避に対する最高裁の判断は、日本企業が最も留意すべき点の一つです。
Højesteret 2023年5月4日判決
事件名:Takeda A/S in voluntary liquidation vs. The Danish Ministry of Taxation (他1件)
この判例では、ルクセンブルクなどの外国グループ会社が関与したグループ内ローン利子に対する源泉徴収税の扱いが争点となりました。最高裁は、関連グループがスウェーデンやルクセンブルクに会社を追加した再編について、「包括的かつ事前に手配された租税手配」であると認定しました。
最高裁は、この再編において追加された会社を、EUの利子・ロイヤルティ指令や租税条約の保護を受けられないコンジット会社(導管会社)であると判断しました。そして、当該租税手配が「権利の濫用」に該当すると結論づけ、Takeda A/Sらは巨額の利子にかかる源泉徴収税(合計約11億8600万DKK)を怠っていたとして、追徴課税が課されました。
この判決は、デンマークにおける取締役の責任が、単に現地法人の日常的な法令遵守にとどまらず、国際的な企業グループ全体の構造、特に税務戦略や資金移動における実質的な合法性にまで及ぶことを明確に示しています。日本の親会社から派遣される取締役は、国際取引や構造再編を行う際、単なる形式的な合法性だけでなく、「権利の濫用」と見なされないかという観点から、高度なリスク評価と監督責任を負うことが求められます。
この判決に関する公式なプレスリリースは、デンマークの裁判所の公式ウェブサイトで確認することができます。
・デンマーク裁判所の公式ウェブサイト
https://www.domstol.dk/hoejesteret/decided-cases-eu-law/2023/5/taxation-of-interest-in-beneficial-ownership-cases/
デンマーク法と日本法のガバナンス構造の決定的な異同点(総括表)
日本の経営層や法務部員がデンマーク進出の計画を立てる際、最も重要なのは、両国のガバナンス構造の決定的な差異を一覧で把握することです。以下の表に、公開有限会社(A/S)と日本の株式会社の主要な制度上の違いをまとめます。
デンマーク(A/S)と日本(株式会社)のガバナンス構造決定的な差異
| 比較項目 | デンマーク公開有限会社 (A/S) | 日本株式会社 (会社法) | 相違点の法的・実務的意義 |
| 経営機構の分離 | 戦略決定機関(取締役会)と執行機関(執行役員会)の分離が法的要件。 | 一層構造が主流。執行側が取締役会を兼任することが一般的。 | 執行側からの監督機能の独立が客観的な構成要件により強制されます。 |
| 執行役員会の構成制限 | 執行役員会メンバーは取締役会の過半数を占めてはならない。議長・副議長兼任禁止。 | 厳格な構成制限なし(委員会設置会社を除く)。 | 取締役会の独立性を保つため、外部または非執行役員の登用が必須となります。 |
| 従業員代表制度 | 35名以上の平均雇用で、株主選任取締役の半数(最低2名)の選任権が法定で発生する。 | 法定制度なし。 | 労働者の戦略的意思決定への直接的かつ強制的な参画と、労働者側の利益を考慮した戦略の透明性が求められます。 |
| 株主総会の権限 | 法律等で明示的に委任されない限り、会社に関する「あらゆる事項を決定できる」(全能性)。 | 法律に規定された事項に限定され、日常業務は取締役会に委任されるのが一般的。 | 業務の迅速な遂行には、定款による取締役会への広範かつ明確な権限委任が不可欠です。 |
| 役員の個人責任 | 会社の責任とは独立して、故意・過失による第三者への損害賠償責任が厳格に追及されます。国際的な租税回避における監督責任も判例で明確化されています。 | 会社責任と個人責任は区別されますが、デンマーク法では国際的なコンプライアンスリスク管理において特に高度な注意義務が課されます。 |
まとめ
デンマークのコーポレートガバナンスは、伝統的な北欧モデルを背景に、強いステークホルダー重視の原則に基づいて構築されています。特に、公開有限会社(A/S)に強制される戦略機能と執行機能の構造的独立、そして一定規模以上の企業における従業員代表取締役の共同決定権は、日本の会社法に基づく慣行とは大きく異なり、事業展開を検討する日本企業に体制の根本的な見直しを要求します。
また、最高裁判所(Højesteret)が国際的なグループ構造における租税濫用について厳格な判断を下していることから明らかなように、デンマークの法環境下では、親会社から派遣された取締役であっても、国際コンプライアンス、特に税務戦略における実質的なリスク管理について高度な受託者責任を負うことになります。これらの法的枠組みを深く理解し、現地法人設立の初期段階から適切なガバナンス体制を設計することは、法的リスクの最小化と事業の効率的な運営にとって極めて重要です。
弊所モノリス法律事務所は、このような国際的な企業法務環境における構造設計、法令遵守、およびリスク管理について、お客様をサポートいたします。デンマーク進出におけるガバナンス体制の構築や、日本法との比較分析に関する専門的なサポートが必要な場合は、ぜひご相談ください。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務