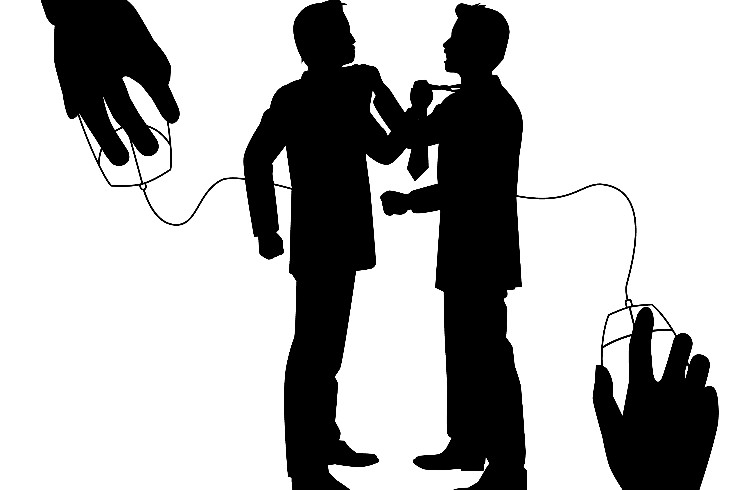م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®ه ±é…¬مپŒوœھو‰•مپ¨مپھمپ£مپںه ´هگˆمپ®و³•ه¾‹مپ¨مپ¯

م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®و¥ه‹™م‚’ه¼•مپچهڈ—مپ‘م‚‹مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپ«مپ¨مپ£مپ¦م€پمپ‚م‚‹و„ڈه‘³وœ€ه¤§مپ®مƒھم‚¹م‚¯مپ¨مپھم‚‹مپ®مپ¯م€پم€Œç´چه“پمپ—مپںمپ«م‚‚مپ‹مپ‹م‚ڈم‚‰مپڑم€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒه ±é…¬م‚’و”¯و‰•مپ£مپ¦مپڈم‚Œمپھمپ„م€چمپ¨مپ„مپ†ن؛‹و…‹مپ§مپ¯مپھمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹م€‚م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ«è¦پمپ™م‚‹م‚³م‚¹مƒˆمپ¯م€پمپمپ®ه¤ڑمپڈمپŒمƒ—مƒم‚°مƒ©مƒم‚’مپ¯مپکم‚پمپ¨مپ™م‚‹م‚¹م‚مƒ«م‚’م‚‚مپ£مپںن؛؛وگمپ¨مپھم‚‹مپ“مپ¨مپ‹م‚‰م€پن؛؛ن»¶è²»مپŒه¤ڑمپڈمپ‹مپ‹م‚‹ه ´هگˆمپŒه¤ڑمپ„م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚ه£²ن¸ٹمپ®ه›هڈژمپŒو»م‚‹مپ“مپ¨مپ¯مپ¨مپچمپ«و»و´»ه•ڈé،Œمپ¨م‚‚مپھم‚ٹمپ‹مپمپھمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚وœ¬è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€په ±é…¬مپ®و”¯و‰•مپ„مپ«مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒه؟œمپکمپھمپ„مپ¨مپ„مپ†ه ´هگˆم‚’وƒ³ه®ڑمپ—مپ¦م€پمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپŒو¤œè¨ژمپ™مپ¹مپچن؛‹é …مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پو³•ه¾‹çڑ„مپھ観点مپ‹م‚‰è§£èھ¬مپ—مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ™م€‚
مپ“مپ®è¨کن؛‹مپ®ç›®و¬،
مپ¾مپڑم€په ±é…¬è«‹و±‚مپŒهڈ¯èƒ½مپھçٹ¶و…‹مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’è¦پç¢؛èھچ
- مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپŒمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م€پوˆگوœç‰©م‚’ç´چه“پمپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ«م‚‚مپ‹مپ‹م‚ڈم‚‰مپڑم€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒç´چه“پم‚’هڈ—مپ‘ن»کمپ‘مپ¦مپڈم‚Œمپڑم€پمپمپ®مپ›مپ„مپ§ه ±é…¬مپ®è«‹و±‚و¥ه‹™مپ¾مپ§و»مپ£مپ¦مپ—مپ¾مپ£مپ¦مپ„م‚‹
- و¤œهڈژمپ¾مپ§çµ‚م‚ڈمپ£مپ¦مپ„مپںèھچèکمپ مپ£مپںمپ«م‚‚مپ‹مپ‹م‚ڈم‚‰مپڑم€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®èھچèکمپ¨مپ®é–“مپ«ن½•م‚‰مپ‹مپ®é½ں齬مپŒمپ‚م‚ٹم€په ±é…¬مپ®و”¯و‰•مپ„مپ«ه؟œمپکم‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپھمپ„
مپ¨مپ„مپ†ن؛‹و…‹مپ¯م€پçڈ¾ه®ںçڑ„مپ«م‚‚هچپهˆ†èµ·مپ“م‚ٹمپ†م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚
مپھمپٹم€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒه‡؛و¥ن¸ٹمپŒمپ£مپںم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®ن»•و§کم‚’点و¤œمپ—م€پç´چه“پم‚’هڈ—مپ‘ن»کمپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپ¯م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®ç”¨èھمپ§مپ¯م€پم€Œو¤œهڈژم€چمپ¨ه‘¼مپ°م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®م€پو¤œهڈژمپ¨مپ„مپ†م‚‚مپ®مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®و„ڈ義مپ¨م€پمپم‚Œمپ®é€²وچ—مپŒèٹ³مپ—مپڈمپھمپ„ه ´هگˆمپ«و¤œè¨ژمپ™مپ¹مپچن؛‹é …مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پن»¥ن¸‹مپ®è¨کن؛‹مپ«مپ¦è©³ç´°مپ«è§£èھ¬مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
関連è¨کن؛‹ï¼ڑم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®و¤œهڈژمپ¨مپ؟مپھمپ—و¤œهڈژو،é …مپ®éپ©ç”¨ه ´é¢مپ¨مپ¯
و¤œهڈژمپمپ®م‚‚مپ®مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®ه…¨ن½“çڑ„مپھèھ¬وکژمپ¯ن¸ٹè¨کè¨کن؛‹مپ«è²م‚ٹمپ¾مپ™مپŒم€پو³•ه¾‹ن¸ٹم€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®و¤œهڈژمپŒه®Œن؛†مپ—مپںمپ¨مپ„مپˆم‚‹مپ®مپ‹هگ¦مپ‹مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پم€Œمپ؟مپھمپ—و¤œهڈژو،é …م€چمپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®è¦ڈه®ڑم‚‚è¸ڈمپ¾مپˆمپ¦و¤œè¨ژم‚’è،Œمپ†ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ§مپ—مپںم€‚
مپ“مپ®ç‚¹م‚‚ه؟µé مپ«مپٹمپچمپ¤مپ¤م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒه ±é…¬مپ®و”¯و‰•مپ„م‚’è،Œمپ£مپ¦مپڈم‚Œمپھمپ„مپ¨مپ„مپ†ن؛‹و،ˆم‚’وƒ³ه®ڑمپ—مپ¦مپ¾مپڑ第ن¸€مپ«و¤œè¨ژمپ™مپ¹مپچ点مپ¨مپھم‚‹مپ®مپ¯ن»¥ن¸‹مپ®ç‚¹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
- مپم‚‚مپم‚‚ن»•ن؛‹مپŒه®Œوˆگمپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ‹م€پم‚‚مپ—مپڈمپ¯مپ¾مپ وœھه®Œوˆگمپھمپ®مپ‹
- ç‘•ç–µو‹…ن؟責ن»»ï¼ˆو°‘و³•ï¼–35و،)مپ®éپ©ç”¨مپ¯مپ•م‚Œمپ†م‚‹مپ®مپ‹هگ¦مپ‹
مپھمپœن¸ٹè¨کن؛Œç‚¹مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®ç¢؛èھچم‚’第ن¸€مپ«è،Œمپ†مپ¹مپچمپ‹مپ¨مپ„مپˆمپ°م€پمپم‚‚مپم‚‚ن»•ن؛‹مپŒه®Œوˆگمپ—مپ¦مپ„مپ¦م€پمپ‹مپ¤م€پç‘•ç–µو‹…ن؟責ن»»ï¼ˆو°‘و³•ï¼–35و،)مپ®éپ©ç”¨مپŒمپھمپ„مپ“مپ¨م‚’مپ‚م‚‰مپ‹مپکم‚پç¢؛èھچمپ—مپ¦مپٹمپ‹مپھمپ„مپ¨م€پمپ‹م‚ٹمپ«è¨´è¨ںم‚’èµ·مپ“مپ—مپںمپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€پçµگه±€ه ±é…¬مپ®و”¯و‰•مپ„مپ«ه؟œمپکمپ¦م‚‚م‚‰مپ†مپ“مپ¨مپŒوœںه¾…مپ§مپچمپھمپ„مپںم‚پمپ§مپ™م€‚
مپ§مپ¯م€په…·ن½“çڑ„مپ«م€پن¸ٹè¨کن؛Œç‚¹م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپںم‚پمپ«م€پمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپ®و‹…ه½“者مپ¯مپھمپ«م‚’èھ؟مپ¹م‚Œمپ°م‚ˆمپ„مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹م€‚ن»¥ن¸‹مپ«م€پç¢؛èھچمپ™مپ¹مپچو›¸é،مپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚‚مپ®مپŒمپ‚م‚‹مپ‹م‚’見مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ™م€‚
ه ±é…¬è«‹و±‚مپ®هڈ¯هگ¦م‚’èھ؟مپ¹م‚‹مپںم‚پمپ«ç¢؛èھچمپ™مپ¹مپچو›¸é،مپ¨مپ¯
| ç´چه“پو›¸ ç´چه“پو›¸مپŒمپھمپ„مپ¨مپ„مپ†ه ´هگˆمپ«مپ¯م€پç´چه“پمپ¾مپڑç´چه“پمپŒه®Œن؛†مپ—مپ¦مپٹم‚‰مپڑم€پن»•ن؛‹مپŒه®Œوˆگمپ—مپ¦مپ„مپھمپ„مپ¨مپ„مپ†وژ¨ه®ڑم‚’ه¼·م‚پم‚‹è¦پç´ مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚ |
| و¤œهڈژمپ®çµگوœم‚’é€ڑçں¥مپ™م‚‹و›¸é، ن»•ن؛‹مپŒه®Œوˆگمپ—مپںم‚‚مپ®مپ¨و‰±مپ£مپ¦م‚ˆمپ„مپ‹هگ¦مپ‹م‚’هˆ¤و–مپ™م‚‹éڑ›مپ«م€پم‚‚مپ£مپ¨م‚‚é‡چè¦پمپھ資و–™مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںهگˆم‚ڈمپ›مپ¦م€پم‚‚مپ—مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼éƒ½هگˆمپ§و¤œهڈژمپŒه…ˆه»¶مپ°مپ—مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م‚ˆمپ†مپھن؛‹و،ˆمپ§مپ‚م‚Œمپ°م€پم€Œمپ؟مپھمپ—و¤œهڈژو،é …م€چمپ®è¨ک載مپŒه¥‘ç´„و›¸ن¸ٹمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپںمپ®مپ‹م‚‚م€پمپ‚م‚ڈمپ›مپ¦ç¢؛èھچمپ—مپ¦مپٹمپڈمپ¨م‚ˆمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚ |
| èھ²é،Œç®،çگ†ن¸€è¦§è،¨ مپ“م‚Œمپ¾مپ§مپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھèھ²é،ŒمپŒمپ؟مپ¤مپ‹م‚ٹم€پمپمپ—مپ¦مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھه¯¾ه‡¦م‚’è،Œمپ£مپ¦مپچمپںمپ®مپ‹م‚’çں¥م‚‹مپںم‚پمپ®è³‡و–™مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پç´چه“پم‚’è،Œمپ£مپںه¾Œمپ«ç™؛è¦ڑمپ—مپںéڑœه®³مƒ»ن¸چه…·هگˆمپ®çٹ¶و³پمپ¨م€پمپم‚Œمپ«ه¯¾مپ™م‚‹ن؟®è£œçٹ¶و³پم‚’وٹٹوڈ،مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®è³‡و–™مپ¨م‚‚مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚ |
| è¦پن»¶ه®ڑ義و›¸مƒ»è¨è¨ˆو›¸مپٹم‚ˆمپ³ه¤‰و›´ç®،çگ†و›¸مƒ»هگ„種ن¼ڑè°è°ن؛‹éŒ²مپھمپ© مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ¨مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ§ه½“هˆمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھèھچèکم‚’وœ‰مپ—مپ¦مپ„مپںمپ‹م‚’وکژم‚‰مپ‹مپ«مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ«م‚ˆم‚ٹم€پمپھمپ«مپŒéڑœه®³مƒ»ن¸چه…·هگˆمپ¨ه‘¼مپ¶مپ¹مپچم‚‚مپ®مپھمپ®مپ‹م‚’وکژم‚‰مپ‹مپ«مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®è³‡و–™مپ¨مپھم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚ |
مپھمپٹم€پé–‹ç™؛مپ™مپ¹مپچم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®ن»•و§کمپ®ه¤‰و›´م‚’مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«ç®،çگ†مپ™م‚‹مپ‹م‚„م€په¤‰و›´ç®،çگ†و›¸مپ®ن½œوˆگو–¹و³•مپھمپ©مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پهˆ¥è¨کن؛‹مپ«مپ¦è©³ç´°مپھ解èھ¬م‚’è،Œمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
関連è¨کن؛‹ï¼ڑو³•ه¾‹çڑ„観点مپ‹م‚‰مپ؟مپںم€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ«مپٹمپ‘م‚‹ه¤‰و›´ç®،çگ†مپ®è،Œمپ„و–¹مپ¨مپ¯
| 解除é€ڑçں¥و›¸م‚‚مپ—مپڈمپ¯م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®و„ڈهگ‘م‚’è¨کمپ™و–‡و›¸ و¤œهڈژم‚’進م‚پم‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپھمپ„مپ“مپ¨ï¼ˆمپ‚م‚‹مپ„مپ¯ه ±é…¬مپ®و”¯و‰•مپ„مپ«ه؟œمپکمپھمپ„مپ“مپ¨ï¼‰مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھو„ڈه›³م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ‹م‚’çں¥م‚‹مپںم‚پمپ®و‰‹و®µمپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚ |
و¬،مپ«م€پمپ„مپڈم‚‰مپ®ه ±é…¬è«‹و±‚مپŒهڈ¯èƒ½مپھمپ®مپ‹م‚’ç¢؛èھچ

مپ„مپڈم‚‰مپ®è«‹و±‚مپŒهڈ¯èƒ½مپھمپ®مپ‹مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€په¥‘ç´„و›¸مپ«è¨ک載مپŒمپھمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ®مپŒهژںه‰‡مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پن؛‹ه¾Œمپ§ن»•و§کمپ®ه¤‰و›´ç‰مپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپںه ´هگˆمپ«مپ¯م€پمپچمپ،م‚“مپ¨مپ—مپںه¥‘ç´„و›¸ï¼ˆم‚„مپم‚Œمپ«و؛–مپڑم‚‹و–‡و›¸ï¼‰مپŒو®‹مپ£مپ¦مپ„مپھمپ„مپ¨مپ„مپ†ه ´هگˆم‚‚وƒ³ه®ڑمپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚ن»•و§کمپ®ه¤‰و›´مƒ»و©ں能مپ®è؟½هٹ ç‰مپ®ه¾Œç™؛çڑ„مپھçگ†ç”±مپ«هں؛مپ¥مپڈ見ç©چم‚ٹمپ®ه†چ計算مپ®م‚„م‚ٹو–¹مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پن»¥ن¸‹مپ®è¨کن؛‹مپ«مپ¦è©³ç´°مپ«è§£èھ¬م‚’è،Œمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
関連è¨کن؛‹ï¼ڑم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®è¦‹ç©چم‚ٹ金é،چمپ®ن؛‹ه¾Œه¢—é،چمپ¯هڈ¯èƒ½مپ‹
見ç©چم‚ٹمپ®ه†چ計算مپ®و–¹و³•مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯وœ¬è¨کن؛‹مپ®é€ڑم‚ٹمپ§مپ™مپŒم€پ特مپ«è«‹و±‚金é،چمپ®ه¢—é،چمپ®هڈ¯هگ¦م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ†è¦³ç‚¹مپ‹م‚‰مپ„مپ†مپھم‚‰مپ°م€پ
- è؟½هٹ é–‹ç™؛مƒ»و©ں能مپ®ن؟®و£مپ«é–¢مپ™م‚‹éƒ¨هˆ†مپ®è¦‹ç©چو›¸مپ®وœ‰ç„،مپ¨مپمپ®ه†…ه®¹
- 見ç©چو›¸مپ«ه¯¾مپ™م‚‹مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپ®هڈچه؟œمپ®ه†…ه®¹
- èھ²é،Œç®،çگ†ن¸€è¦§è،¨مپ«è¨ک載مپ•م‚Œم‚‹è؟½هٹ é–‹ç™؛مƒ»و©ں能مپ®ن؟®و£م‚’ç™؛ç”ںمپ•مپ›مپںçٹ¶و³پمپ¨م€پمپمپ®é،چمپ«é–¢مپ™م‚‹هگˆو„ڈمپ®وœ‰ç„،
مپ¨مپ„مپ£مپں点م‚’ن¸ه؟ƒمپ«مپ؟مپ¦مپ„مپڈمپ“مپ¨مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚è¦پمپ¯م€Œمپمپ®é‡‘é،چمپ§و¥ه‹™م‚’ç™؛و³¨مپ™م‚‹م€چمپ¨مپ„مپ†ç‚¹مپ«مپ¤مپچم€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپ¨مپ®و„ڈو€مپ®هگˆè‡´مپ¯مپ‚مپ£مپںمپ¨مپ„مپ£مپ¦م‚ˆمپ„مپ®مپ‹ï¼ˆمپ¤مپ¾م‚ٹمپ¯ه¥‘ç´„مپŒوˆگç«‹مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ„مپ£مپ¦م‚ˆمپ„مپ®مپ‹ï¼‰مپ¨مپ„مپ†ç‚¹م‚’èھ؟مپ¹مپ¦مپ„مپڈمپ¨مپ„مپ†وµپم‚Œمپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
وœ€ه¾Œمپ«م€په®ںéڑ›مپ«è¨´è¨ںم‚’è،Œمپ†ه ´هگˆمپ®و‡¸و،ˆن؛‹é …م‚’و¤œè¨ژ
逆مپ«هڈچ訴請و±‚مپŒمپھمپ•م‚Œم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپ«و³¨و„ڈ
م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ§مپ¯م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مƒ»مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ©مپ،م‚‰مپ‹ن¸€و–¹مپŒç›¸و‰‹و–¹مپ«è¨´è¨ںم‚’وڈگèµ·مپ™م‚‹مپ¨م€پ逆مپ«ç›¸و‰‹و–¹مپ‹م‚‰هڈچ訴مپ®وڈگèµ·مپŒمپھمپ•م‚Œم‚‹ه ´هگˆمپŒه°‘مپھمپڈمپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپ™مپھم‚ڈمپ،م€په ±é…¬مپ®و”¯و‰•مپ„مپ«ه؟œمپکمپھمپ„مپ¨مپ„مپ†çٹ¶و³پمپ«مپ¤مپچم€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ®هپ´مپ«م‚‚مپھمپ«مپ‹مپ—م‚‰مپ®è¨€مپ„هˆ†مپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ§مپ™م€‚
مپم‚‚مپم‚‚م‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ¯م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´م‚‚هگ„種هچ”هٹ›ç¾©ه‹™م‚’è² مپ„مپ¾مپ™مپŒم€پمپ¾مپڑه‰چوڈگمپ¨مپ—مپ¦م€پمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپŒم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ®ه°‚é–€ه®¶مپ¨مپ—مپ¦ه؛ƒç¯„مپھè£پé‡ڈمپ¨ه¤§مپچمپھ責ن»»م‚’è² مپ£مپ¦مپ„م‚‹ç‚¹م‚’ه؟کم‚Œمپ¦مپ¯مپھم‚‰مپھمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼هپ´مپŒم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ«ه¯¾مپ—مپ¦è² مپ£مپ¦مپ„م‚‹مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمƒمƒچم‚¸مƒ،مƒ³مƒˆç¾©ه‹™مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پن»¥ن¸‹مپ®è¨کن؛‹مپ§م‚‚詳細مپ«è§£èھ¬مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
関連è¨کن؛‹ï¼ڑم‚·م‚¹مƒ†مƒ é–‹ç™؛مپ«مپٹمپ‘م‚‹مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمƒمƒچم‚¸مƒ،مƒ³مƒˆç¾©ه‹™مپ¨مپ¯
مپ¤مپ¾م‚ٹم€پن¸€و–¹çڑ„مپ«ه ±é…¬م‚’و”¯و‰•م‚ڈمپھمپ„مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼هپ´مپ«ه¸°è²¬مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ§مپ‚م‚‹مپ®مپ‹مپ¨مپ„مپ†ç‚¹مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پن؛‹ه‰چمپ«م‚ˆمپڈو¤œè¨ژمپ—مپ¦مپٹمپڈه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ§مپ™م€‚éپژهژ»مپ®è£پهˆ¤ن¾‹م‚’見مپ¦م‚‚م€په½“هˆمƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ‹م‚‰ه ±é…¬è«‹و±‚م‚’و±‚م‚پمپ¦è¨´è¨ںم‚’وڈگèµ·مپ—مپںمپ®مپ«م€پمƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ‹م‚‰é€†مپ«م€پهژںçٹ¶ه›ه¾©ç¾©ه‹™م‚„وگچه®³è³ ه„ںè«‹و±‚مپŒمپھمپ•م‚Œمپںمپ¨مپ„مپ†ن؛‹و،ˆمپŒه¤ڑو•°ç¢؛èھچمپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚
ه–¶و¥ن¸ٹوœ¬ه½“مپ«مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپŒمپ‚م‚‹مپ‹مپ©مپ†مپ‹م‚‚è¦پو¤œè¨ژ
ن»®مپ«مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼مپ®è¨€مپ„هˆ†مپŒé€ڑم‚ٹم€په®ںéڑ›مپ«ه ±é…¬مپ®è«‹و±‚مپŒهڈ¯èƒ½مپھçٹ¶و…‹مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨مپŒè¨´è¨ںمپ§èھچم‚پم‚‰م‚Œمپںمپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€پ訴è¨ںمپ«مپ¾مپ§ن؛‹و…‹مپŒç´›ç³¾مپ™م‚‹مپھم‚‰مپ°م€پن»¥ه¾Œمپ®هڈ–ه¼•مپ®ç¶™ç¶ڑمپ¯ه®ںéڑ›ه•ڈé،Œه›°é›£مپ¨مپھم‚‹مپ“مپ¨مپŒن؛ˆوƒ³مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚هٹ مپˆمپ¦م€پ訴è¨ںمپ®مپ†مپˆمپ§è‡ھه·±مپ®è¨€مپ„هˆ†مپŒèھچم‚پم‚‰م‚Œمپںمپ¨مپ—مپ¦م‚‚م€په®ںéڑ›مپ«ه ±é…¬مپŒهڈ—é کمپ§مپچم‚‹مپ¾مپ§مپ«مپ‹مپھم‚ٹمپ®و™‚é–“مپŒمپ‹مپ‹م‚‹مپ“مپ¨م‚‚è¦ڑو‚ںمپ™مپ¹مپچمپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚訴è¨ںم‚’è،Œمپ†مپ“مپ¨مپ«مپ‹مپ‹م‚‹و‰‹é–“م‚„م‚³م‚¹مƒˆم‚‚و±؛مپ—مپ¦ه°ڈمپ•مپڈمپھمپ„مپ“مپ¨م‚‚考مپˆم‚‹مپھم‚‰مپ°م€پم‚€مپ—م‚چه¦¥هچ”点م‚’見ه‡؛مپ™هٹھهٹ›م‚’مپ™م‚‹مپ»مپ†مپŒç©ڈه½“مپ§è‰¯مپ„مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨م‚‚ه¤ڑمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
مپ¾مپ¨م‚پ
مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپŒه ±é…¬و”¯و‰•مپ„مپ«ه؟œمپکمپھمپ„ه ´هگˆمپ«م€پمپمپ®ه•ڈé،Œم‚’و³•çڑ„مپ«و¤œè¨ژمپ—م‚ˆمپ†مپ¨مپ™م‚‹مپ¨م€پ複و•°ç¨®é،مپ«م‚ڈمپںم‚‹و–‡و›¸مپ®ç¢؛èھچمپŒه؟…è¦پمپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںهٹ مپˆمپ¦م€پمپںمپ هچکمپ«و–‡و›¸ç®،çگ†مپŒه¾¹ه؛•مپ§مپچمپ¦مپ„م‚Œمپ°م‚ˆمپ„مپ¨مپ„مپ†م‚‚مپ®مپ§م‚‚مپھمپڈم€پوœ€çµ‚çڑ„مپ«è¨´è¨ںمپ«è¸ڈمپ؟هˆ‡مپ£مپںه ´هگˆمپ«çµ„ç¹”çڑ„مپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھمƒھم‚¹م‚¯مƒ»مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚’وٹ±مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھم‚‹مپ®مپ‹مپ¨مپ„مپ£مپں点مپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚‚و¤œè¨ژم‚’è¦پمپ—مپ¾مپ™م€‚
و—¥é ƒمپ®و–‡و›¸ç®،çگ†مپ®ه¾¹ه؛•مپ¨مپ„مپ£مپں点مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پمپںمپ—مپ‹مپ«çڈ¾ه ´مƒ¬مƒ™مƒ«مپ®و¥ه‹™مپ«ه±مپ™م‚‹ه ´هگˆمپŒé€ڑه¸¸مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پمپ„مپ–ن؟ç®،مپ•م‚Œمپںو–‡و›¸مƒ»è³‡و–™م‚’م‚‚مپ¨مپ«è¨´è¨ںمپ«è¸ڈمپ؟هˆ‡م‚‹مپ¨مپھم‚Œمپ°م€پمپم‚Œمپ¯é‡چه¤§مپھ経ه–¶هˆ¤و–مپ¨مپھم‚ٹمپ†م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚مپ“مپ†مپ—مپںم‚¤مƒ¬م‚®مƒ¥مƒ©مƒ¼ن؛‹و…‹مپ«مپ“مپم€پçڈ¾ه ´هپ´مپ¨çµŒه–¶هپ´مپ®çµگوںهٹ›مƒ»çµ„ç¹”هٹ›مپŒه•ڈم‚ڈم‚Œم‚‹مپ®مپ مپ¨مپ„مپ†ç‚¹مپ¨مپ¨م‚‚مپ«م€پن¸€é€£مپ®وµپم‚Œم‚’وژ´م‚“مپ§مپٹمپڈمپ¹مپچمپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚