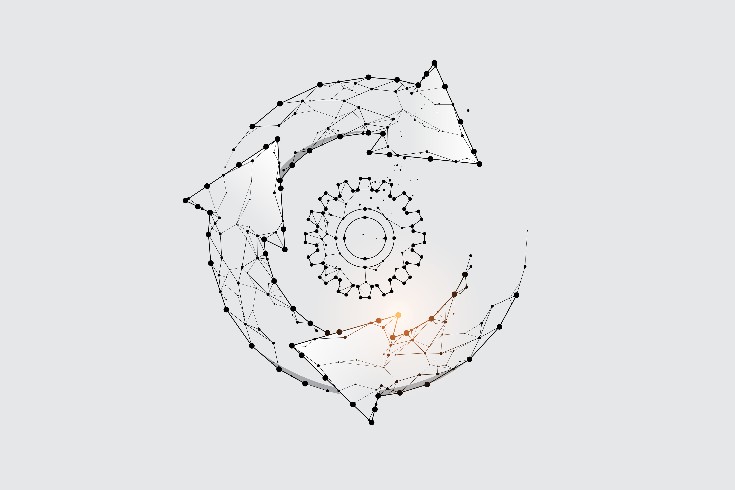ʧúÂèéÂæå„Å´„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„ÅƉ∏çÂÖ∑Âêà„ÅåÁô∫˶ö„Åó„ÅüÂÝ¥Âêà„ÅÆÂØæÂøúÁ≠ñ„Å®„ÅØ
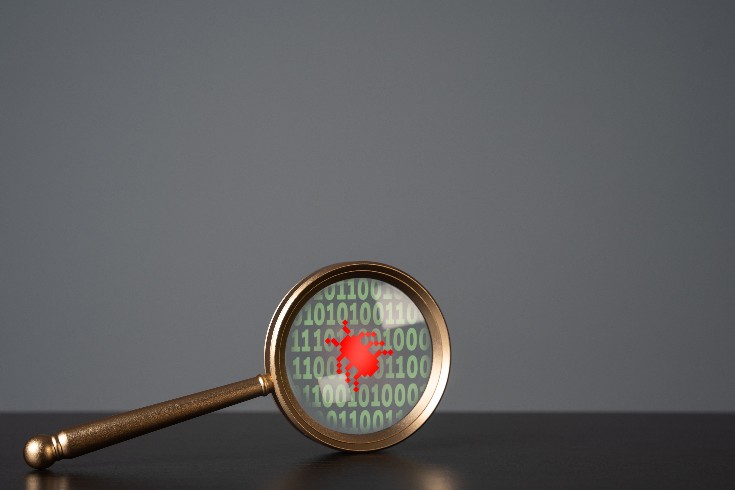
„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝÈñãÁô∫„ÅØ„Åî„Åè‰∏ÄËà¨Áöфř˩±„Å®„Åó„Ŷ„ÅØ„ÄÅ˶ʼnª∂ÂÆöÁæ©„Éï„Ç߄ɺ„Ç∫„Å´„Ŷʱ∫ÂÆö„Åï„Çå„ÅüÂÜÖÂÆπ„Å´Ê≤ø„Å£„Ŷ„Éó„É≠„Ç∞„É©„ÉÝ„ÅÆÂÆüË£Ö„ÅåÈÄ≤„ÇÅ„Çâ„Çå„ÄÅÊúÄÁµÇÁöÑ„Å´„Å؉ªïÊßòÈÄö„Çä„ÅƉªï‰∏ä„Åå„Çä„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åã„Å©„ÅÜ„Åã„Çí„ɶ„ɺ„Ç∂„ɺ„ɪ„Éô„É≥„ÉĄɺ„Å®„ÇÇ„Å´Á¢∫Ë™ç„Åó„ÄÅʧúÂèé„ÅÆÂêàÊݺ„Çí„ÇÇ„Å£„ŶÁµÇ‰∫Ü„Åô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ
„Åó„Åã„ÅóÁèæÂÆüÂïèÈ°å„ÄÅ„ÉÜ„Çπ„ÉàÂ∑•Á®ãÂèä„Å≥ʧúÂèé„ÅÆÂêàÊݺÊôÇ„Å´„ÅØÁô∫˶ã„Åß„Åç„Å™„Åã„Å£„Åü„Çà„ÅÜ„Å™„Éê„Ç∞„Çщ∏çÂÖ∑Âêà„Åå„ÄÅ„Åù„ÅÆÂæå„ÅÆÈÅãÁÉï„Ç߄ɺ„Ç∫„Å™„Å©„ÅßÁô∫˶ö„Åô„Çã„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Åì„Å®„ÅØÂÆüÈöõ„Å´ÂçÅÂàÜ˵∑„Åì„Çä„Åà„Åæ„Åô„Älj∏ÄÂ∫¶Á¥çÂìÅ„ÇíÂèó„Å뉪ò„Åë„Ŷ„Åó„Åæ„Å£„ÅüÂÝ¥Âêà„ÄÅÊ≥ïÂæã‰∏ä„Å©„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™„Åì„Å®„ÇíʱDŽÇÅ„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Çã„ÅÆ„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„Åã„ÄÇ
この記事の目次
ʧúÂèéÂêàÊݺÂæå„ÇÑ„ÉÜ„Çπ„ÉàÂ∑•Á®ãÂæå„Å´„ÇÇ„Éê„Ç∞„ÅØÊÆã„Å£„Ŷ„ÅфŶ‰∏çÊÄùË≠∞„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„ÄÄ
ÊäÄË°ìÁöфř˶≥ÁÇπ„Åã„Çâ„ÅÑ„ÅÜ„Å™„Çâ„Å∞„ÄÅ„Éô„É≥„ÉĄɺÂÅ¥„ÅÆÂêÑÁ®Æ„ÉÜ„Çπ„ÉàÂ∑•Á®ã„ÅÆÂÆå‰∫܄ɪ„ɶ„ɺ„Ç∂„ɺÂÅ¥„ÅÆʧúÂèé„ÅÆÂêàÊݺ„ÅÆÂæå„Å´„ÄÅÊßò„ÄÖ„Å™„Éê„Ç∞„Çщ∏çÂÖ∑Âêà„ÅåÁô∫˶ö„Åô„Çã„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Åì„Å®„ÅØʱ∫„Åó„ŶÁèç„Åó„ÅÑ„Åì„Å®„Åß„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄDŽɶ„ɺ„Ç∂„ɺ„ÅåʧúÂèé„ÅÆÂ∑•Á®ã„ÅßË°å„ÅÜ„Åì„Å®„ÅØÈÄöÂ∏∏„ÄÅÁîªÈù¢‰∏ä„Åã„ÇâÁ¢∫Ë™ç„Åó„ÅÜ„ÇãÂÖ•Âá∫Âäõ„ÅÆ„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØ„Åå‰∏≠ÂøÉ„Å®„Å™„Çã„Åì„Å®„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅIT„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„ÅØ„Äńɶ„ɺ„Ç∂„ɺÂÅ¥„Åã„ÇâÁ¢∫Ë™ç„Åß„Åç„ÇãÁîªÈù¢‰∏ä„ÅƧñ˶≥‰ª•‰∏ä„Å´„ÄÅËÉåÂæå„ÅÆ„Éá„ɺ„Çø„Éô„ɺ„Çπ„ÇÑ„ÄÅÂêÑÁ®Æ„ÅÆË®àÁÆó„ɪÂà∂Âæ°„ÇíÂè∏„Çã„Éó„É≠„Ç∞„É©„ÉÝ„ÅÆÈÉ®ÂàÜ„Åß„ÄÅ˧áÈõë„Å´Á¥∞„ÇÑ„Åã„Å™ÊßãÈÄÝ„ÇíÊúâ„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÇãÂÝ¥Âêà„Åå§ö„ÅÑ„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ„Åù„Çå„ÇÜ„Åà„Äńɶ„ɺ„Ç∂„ɺÁõÆÁ∑ö„Åß„ÅÆÁîªÈù¢‰∏ä„ÅÆÂÖ•Âá∫Âäõ„ÅÆ„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØ„Åã„ÇâË™ø„Åπ„Çâ„Çå„Çã„Åì„Å®„Å´„ÅØÂÖÉ„Åã„ÇâÈôêÁïå„Åå„ÅÇ„Çã„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ„Åó„Åü„Åå„Å£„Ŷ„ÄÅ„ÉÅ„Çß„ÉÉ„ÇØ„Åß„Åù„ÅÆÂæå„ÅÆÈÅãÁÉï„Ç߄ɺ„Ç∫„Åß˵∑„Åì„Çä„ÅÜ„Çã„Åô„Åπ„Ŷ„ÅƉ∏çÂÖ∑Âêà„ÅÆÂèØËÉΩÊÄß„ÇíÁ∂≤ÁæÖÁöфŴʧúË®º„ÅóÂ∞Ω„Åè„Åô„ÅÆ„ÅØ„ÇÄ„Åó„ÇçÁèæÂÆüÁöÑ„Åß„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ
‰ª•‰∏ä„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™‰∫ãÊÉÖ„ÅØ„ÄÅÈñãÁô∫Ê•≠Âãô„ÇíÂèó„ÅëÊåńŧ„Éô„É≥„ÉĄɺÂÅ¥„ÅÆÁõÆÁ∑ö„Åß„Åø„Ŷ„ÇÇ„ÄÅÂêåÊßò„ÅÆ„Åì„Å®„Åå„ÅÑ„Åà„Åæ„Åô„ÄÇ„Åü„Å®„Åà„Å∞„ÄÅÂÆüË£Ö„Åï„Çå„Åü„Éó„É≠„Ç∞„É©„ÉÝ„ÅÆÂÜÖÂÆπ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅ„Éê„Ç∞„Çщ∏çÂÖ∑Âêà„Åå„Å™„ÅÑ„Åã„Å©„ÅÜ„Åã„ÇíÁ¢∫Ë™ç„Åô„Çã„ÅÆ„ÅØ„Äå„ÉÜ„Çπ„ÉàÂ∑•Á®ã„Äç„Åß„Åô„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÉÜ„Çπ„ÉàÂ∑•Á®ã„Å´„Ŷ„ÄÅÊú¨ÂΩì„Å´„ÅÇ„Çä„Å®„ÅÇ„Çâ„ÇÜ„Çã„Éê„Ç∞„Çщ∏çÂÖ∑Âêà„ÅÆÂèØËÉΩÊÄß„ÅåʧúË®º„ÅóÂ∞Ω„Åè„Åõ„Çã„Åã„Å®„ÅÑ„Åà„Å∞„ÄÅÂøÖ„Åö„Åó„ÇÇ„Åù„ÅÜ„Åß„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇÈñãÁô∫„Åó„Åü„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„ÅåÊú¨ÊݺÁöÑ„Å´Ê•≠Âãô„ÅßÊ¥ªÁÅï„Çå„ÅÝ„Åó„Ŷ‰ª•Èôç„ÇÇ„ÄÅ„Éô„É≥„ÉĄɺÂÅ¥„Çlj∫àÊúü„Åó„Ŷ„ÅÑ„Å™„Åã„Å£„ÅüÊìç‰Ωú„ÅåË°å„Çè„Çå„Åü„Çä„ÄÅ„ÅÇ„Çã„ÅÑ„ÅاßÈáè„ÅÆ„Éá„ɺ„Çø„ÅåÂÆüÈöõ„Å´ÁôªÈå≤„Åï„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Ŷ„Åç„Åü„Çä„ÄÅ˧áÊï∞„ÅƄɶ„ɺ„Ç∂„ɺ„ÅåÂêåÊôÇ„Å´„Ç¢„Ç؄Ǫ„Çπ„Åô„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Ŷ„Åç„Åü„Çä„Åô„Çã„Å™„Åã„Åß„ÄÅ„Åù„Çå„Åß„ÇÇ„Å™„ÅäÊîØÈöú„Å™„ÅèÂãï„ÅçÁ∂ö„Åë„Çã„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„Çí‰Ωú„Çã„Åì„Å®„ÅØÊú¨Êù•ÂÑ™„Çå„ÅüÊäÄË°ìÂäõ„Çí˶ńÅô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ
ʧúÂèé„ÇÑ„ÉÜ„Çπ„Éà„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÊƵÈöé„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅ„ÅÇ„Çä„Å®„ÅÇ„Çâ„ÇÜ„Çã„Éê„Ç∞„Çщ∏çÂÖ∑Âêà„ÇíÁô∫˶ã„ÅóÂ∞Ω„Åè„Åô„Åì„Å®„ÅØÁèæÂÆüÁöÑ„Åß„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅÂÆüÈöõ„Å´‰Ωø„ÅÑÂßã„ÇńŶ„Åã„ÇâÊßò„ÄÖ„Å™ÂïèÈ°å„ÅåÁô∫˶ö„Åô„ÇãÂÝ¥Âêà„Åå„ÅÇ„Çã„ÅÆ„ÅåIT„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„ÅÝ„Å®„ÅÑ„ÅÜÁÇπ„Çí„Åæ„Åö„ÅØÁêÜËߣ„Åó„Ŷ„Åä„Åè„Åπ„Åç„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ
債務自体は履行済みという扱いを受けるのが通常 

„Åß„ÅØ„Åì„ÅÜ„Åó„Åü„Éà„É©„Éñ„É´„ÅåÂÆüÈöõ„Å´Áô∫˶ö„Åó„ÅüÂÝ¥Âêà„ÄÅ„Å©„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´ÂØæÂᶄÅô„Çå„Å∞„Çà„ÅÑ„ÅÆ„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„Åã„ÄÇÊ≥ïÂæãÁöÑ„Å™ÈÝÜÂ∫è„Å´Ê≤ø„Å£„ŶÊï¥ÁêÜ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åæ„Åö„Äʼn∫ãÂæåÁöÑ„Å´„Åß„ÅÇ„Çå„ÄÅÊßò„ÄÖ„Å™„Éê„Ç∞„Çщ∏çÂÖ∑Âêà„ÅåÁô∫˶ö„Åó„Åü„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çå„Å∞„Äńɶ„ɺ„Ç∂„ɺÂÅ¥„Åã„Çâ„ÅØ„ÄÅÊ•≠Âãô„Çí„Åì„Çå„Åæ„Å߉æùÈݺ„Åó„Ŷ„Åç„Åü„Éô„É≥„ÉĄɺ„Å´ÂØæ„Åó„ÄʼnΩï„Çâ„Åã„ÅÆË≤¨‰ªª„ÇíËøΩÂèä„Åó„Åü„ÅÑ„Å®ËÄÉ„Åà„Çã„Åì„Å®„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅÈÄöÂ∏∏„ÄÅ„ÇÇ„ÅÜ„Åô„Åß„Å´Á¥çÂìÅ„ÅåÂÆå‰∫Ü„Åó„ÄÅʧúÂèé„Åæ„ÅßÂêàÊݺ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çå„Å∞„ÄÅÂǵÂãô‰∏籕˰å„Å´Âü∫„Å•„ÅèË≤¨‰ªª„ÅÆËøΩÂèä„ÅØÂõ∞Èõ£„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„ÇãÂÝ¥Âêà„Åå§öÊï∞„Åß„Åô„ÄÇ
„Åù„ÇÇ„Åù„ÇÇ„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝÈñãÁô∫„Å´„Åä„Åë„Çã•ëÁ¥Ñ„ÅØ„ÄÅ„Å™„Å´„ÅãÁâπÊÆä„Å™Âèñ„Çäʱ∫„ÇÅ„ÅåÁî®ÊÑè„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Å™„ÅÑÈôê„Çä„ÄÅ„Éó„É≠„Ç∞„É©„ÉÝ„ÅÆÂÆüË£Ö„Å´Èñ¢„Åô„Çã˶èÂÆö„ÅØÊ∞ëÊ≥ï‰∏ä„ÅÆË´ãË≤Ý•ëÁ¥Ñ„ÅÆ˶èÂÆö„ÅåÂèä„Çì„Åß„Åè„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇË´ãË≤Ý•ëÁ¥Ñ„Åå„Å©„ÅÜ„ÅÑ„Å£„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„Åã„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„Äʼnª•‰∏ã„ÅÆË®ò‰∫ã„ÅßË©≥Á¥∞„Å´Ë™¨Êòé„ÇíË°å„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åù„Åó„Ŷ˴ãË≤Ý•ëÁ¥Ñ„Åß„ÅØ„ÄÅ„Ä剪ï‰∫ã„ÅÆÂÆåÊàê„Äç„Åå„ÄÅÂǵÂãô„ÅƱ•Ë°å˶ʼnª∂„Å®„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Åì„Åß„ÅÑ„ÅÜ„Ä剪ï‰∫ã„ÅÆÂÆåÊàê„Äç„ÅåÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´„Å™„Å´„ÇíÊÑèÂë≥„Åô„Çã„ÅÆ„Åã„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„Äʼnª•‰∏ã„ÅÆË®ò‰∫ã„ÅßË©≥Á¥∞„Å´Ëߣ˙¨„ÇíË°å„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åì„Åì„Åß„ÅØ„ÄÅÈÅéÂ骄ÅÆË£ÅÂ৉æã„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅË´ãË≤Ý•ëÁ¥Ñ„Å´„Åä„Åë„Çã„Ä剪ï‰∫ã„ÅÆÂÆåÊàê„Äç„Åå„ÄÅ„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝÈñãÁô∫„ÅÆÊñáËÑà„Å´Âç≥„Åó„ŶˮĄÅÜ„Å™„Çâ„ÄÅÈñãÁô∫Â∑•Á®ã„ÅÆÂÖ®Â∑•Á®ã„ÅÆÁµÇ‰∫Ü„ÇíÊÑèÂë≥„Åô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÇíËߣ˙¨„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åù„Åó„Ŷ„ÄÅÈñãÁô∫Â∑•Á®ã„ÅåÂÖ®ÈÉ®ÁµÇ‰∫Ü„Åó„ÅüÂæå„Å´„Åä„Åë„Çã„Éê„Ç∞„ɪ‰∏çÂÖ∑Âêà„Å™„Å©„ÅÆÂïèÈ°å„ÅØ„ÄÅË´ãË≤Ý•ëÁ¥Ñ„Å´„Åä„Åë„ÇãÁëïÁñµÊãÖ‰øùË≤¨‰ªª„ÅÆÂïèÈ°å„Å®„Å™„Çã„Åì„Å®„ÇíË™¨Êòé„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
Ë©±„Çí„Åæ„Å®„ÇÅ„Çã„Å®„Äʼn∏ÄÂ∫¶Á¥çÂìÅ„ÇíÂèó„Å뉪ò„Åë„ÄÅʧúÂèé„ÅÆÂêàÊݺ„Åæ„ÅßÂÆå‰∫Ü„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„Å®„Å™„Çå„Å∞„ÄÅÂǵÂãô„Åù„ÅÆ„ÇÇ„ÅÆ„ÅØ„Åô„Å߄Ŵ±•Ë°å„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„ÇíÂâçÊèê„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅ„Åù„ÅÆÂæå„ÅÆÂìÅË≥™‰øùË®º„ÅÆÂïèÈ°å„ÄÅ„Åô„Å™„Çè„Å°ÁëïÁñµÊãÖ‰øùË≤¨‰ªª„ÅÆËøΩÂèä„ÅÆÂèØÂ궄ÅåÂïèÈ°å„Å®„Å™„Çã„ÅÆ„ÅåÈÄöÂ∏∏„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Åì„Å®„Åß„Åô„ÄÇ
瑕疵担保責任に基づく責任追及を行う道筋
„Åß„ÅØ„ÄÅÁëïÁñµÊãÖ‰øùË≤¨‰ªª„Å´Âü∫„Å•„ÅфŶ„Éô„É≥„ÉĄɺ„Å´ÂØæÂøú„ÇíʱDŽÇÅ„ÇãÂÝ¥Âêà„ÄÅ„Å™„Å´„Çí„Å©„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™ÈÝÜÂ∫è„ÅßʧúË®é„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åë„Å∞„Çà„ÅÑ„ÅÆ„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„Åã„Äljª•‰∏ã„Å´Á¢∫Ë™ç„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åæ„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ
まずはバグや不具合の重大さ・深刻さの程度を確認 
バグや不具合が事後で発覚し、それが法律上の「瑕疵」であるとして何らかの保障を求める際には、バグや不具合の深刻さが問題となってきます。法律上の瑕疵の問題は、そもそも
- „Éê„Ç∞„Çщ∏çÂÖ∑Âêà„Å®„ÅÑ„Åà„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Å£„Ŷ„ÇÇ˪ΩÂæÆ„Å™„ÇÇ„ÅÆ„Å´„Åô„Åé„Åö„ÄÅÊ≥ïÂæã‰∏ä„ÅÆ„ÄåÁëïÁñµ„Äç„Å®„ÅØ„ÅÑ„Åà„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà
- Ê≥ïÂæã‰∏ä„ÅÆ„ÄåÁëïÁñµ„Äç„Å´„ÅØË©≤ÂΩì„Åô„Çã„Åå„ÄÅ•ëÁ¥Ñ„ÅÆÁõÆÁöÑ„ÅÆÈÅîÊàêËᙉΩì„ÅØÂèØËÉΩ„Åß„ÅÇ„ÇãÂÝ¥Âêà
- Ê≥ïÂæã‰∏ä„ÅÆ„ÄåÁëïÁñµ„Äç„Å´Ë©≤ÂΩì„Åó„ÄÅ„Åã„ŧ•ëÁ¥Ñ„ÅÆÁõÆÁöÑ„ÅÆÈÅîÊàêËᙉΩì„ÇÇÂèØËÉΩ„Åß„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà
の3パターンに分かれます。瑕疵担保責任に基づく責任追及の可否を分けているのが、1と2の境目で、瑕疵担保責任に基づいて契約の解除を行うことの可否を分けているのが2と3の境目となります。
第634条
1.‰ªï‰∫ã„ÅÆÁõÆÁöÑÁâ©„Å´ÁëïÁñµ„Åå„ÅÇ„Çã„Å®„Åç„ÅØ„ÄÅÊ≥®ÊñáËÄÖ„ÅØ„ÄÅË´ãË≤݉∫∫„Å´ÂØæ„Åó„ÄÅÁõ∏ÂΩì„ÅÆÊúüÈñì„ÇíÂÆö„ÇńŶ„ÄÅ„Åù„ÅÆÁëïÁñµ„ÅƉøÆË£ú„ÇíË´ãʱDŽÅô„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Çã„ÄÇ„Åü„ÅÝ„Åó„ÄÅÁëïÁñµ„ÅåÈáç˶ńÅß„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅ„Åù„ÅƉøÆË£ú„Å´ÈÅéÂàÜ„ÅÆË≤ªÁÇí˶ńÅô„Çã„Å®„Åç„ÅØ„ÄÅ„Åì„ÅÆÈôê„Çä„Åß„Å™„ÅÑ„ÄÇ
2.Ê≥®ÊñáËÄÖ„ÅØ„ÄÅÁëïÁñµ„ÅƉøÆË£ú„Å´‰ª£„Åà„Ŷ„ÄÅÂèà„ÅØ„Åù„ÅƉøÆË£ú„Å®„Å®„ÇÇ„Å´„ÄÅÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑü„ÅÆË´ãʱDŽÇí„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Çã„ÄÇ„Åì„ÅÆÂÝ¥Âêà„Å´„Åä„ÅфŶ„ÅØ„ÄÅÁ¨¨533Êù°„ÅÆ˶èÂÆö„ÇíÊ∫ñÁÅô„Çã
第635条
‰ªï‰∫ã„ÅÆÁõÆÁöÑÁâ©„Å´ÁëïÁñµ„Åå„ÅÇ„Çä„ÄÅ„Åù„ÅÆ„Åü„ÇńŴ•ëÁ¥Ñ„Çí„Åó„ÅüÁõÆÁöÑ„ÇíÈÅî„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Å™„ÅÑ„Å®„Åç„ÅØ„ÄÅÊ≥®ÊñáËÄÖ„ÅØ„ÄÅ•ëÁ¥Ñ„ÅÆËߣÈô§„Çí„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Çã„ÄÇ„Åü„ÅÝ„Åó„ÄŪ∫Áâ©„Åù„ÅƉªñ„ÅÆÂúüÂú∞„ÅÆÂ∑•‰ΩúÁâ©„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„ÄÅ„Åì„ÅÆÈôê„Çä„Åß„Å™„ÅÑ„ÄÇ
なお、こうした「瑕疵」の段階的な区別に関しては、以下の記事で詳細に解説を行なっています。
次にベンダーに要求すべき事柄を明確にする
„Åæ„Åüʨ°„Å´„ÄÅÁõ∏ÊâãÊñπ„Å´„Å™„Å´„Çí˶ÅʱDŽÅô„Åπ„Åç„Å™„ÅÆ„Åã„ÇíÊòéÁ¢∫„Å´„Åô„ÇãÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„ÇÇ„Åó•ëÁ¥Ñ„ÅÆËߣÈô§„ÇíË°å„ÅÑ„Åü„ÅÑÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„ÄÅ„Åù„Çå„ÅåÁëïÁñµ„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÅÝ„Åë„ÇíÁ´ãË®º„Åô„Çã„ÅÆ„Åß„ÅØË∂≥„Çä„Åö„ÄÅ„Åù„Çå„Åå„Äå•ëÁ¥Ñ„ÅÆÁõÆÁöÑ„ÇíÈÅî„Åô„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Å™„ÅÑ„Äç„Å®„ÅÑ„Åà„Çã„Ū„Å©„ÅÆ„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„ÇãÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Åì„Åß„ÅÑ„ÅÜ„ÄåÁõÆÁöÑ„Äç„ÅÆÂà§Êñ≠„Å´„ÅÇ„Åü„Å£„Ŷ„ÅØ„ÄÅ„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝÈñãÁô∫„Éó„É≠„Ç∏„Çß„ÇØ„ÉàÁô∫Ë∂≥ÂΩìÂàù„Å´Ë°å„Çè„Çå„Åü‰ºöË≠∞„ÅÆË≠∞‰∫ãÈå≤„ÇÑ„ÄʼnªïÊßòÊõ∏„ÅÆË®ò˺â‰∫ãÈÝÖ„Å™„Å©„ÅåÈáç˶ńřÊâã„Åå„Åã„Çä„Å®„Åï„Çå„Åæ„Åô„ÄÇʧúÂèéÂêàÊݺÂæå„Å´„ÇÇ„Éê„Ç∞„Çщ∏çÂÖ∑Âêà„Åå‰∫ãÂæåÁöÑ„Å´Áô∫˶ö„Åô„Çã„Çà„ÅÜ„Å™‰∫ãÊÖã„ÇÇ„ÅÇ„Çä„ÅÜ„Çã„Åü„ÇÅ„ÄÅÈñãÁô∫„Éó„É≠„Ç∏„Çß„ÇØ„Éà„ÅåÁµÇ‰∫ÜÂæå„ÇÇÂêÑÁ®Æ„Éâ„Ç≠„É•„É°„É≥„Éà„ÅƉøùÁÆ°„ÅØÂæπÂ∫ï„Åó„Ŷ„Åä„Åè„Åπ„Åç„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ
„Å™„Åä„ÄÅËߣÈô§‰ª•Â§ñ„Å´„ÅØ„ÄÅÁëïÁñµÊãÖ‰øùË≤¨‰ªª„ÅÆÂÜÖÂÆπ„Å®„Åó„ŶʱDŽÇÅ„ÅÜ„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Å´„ÅØ„ÄÅÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽÇÑÁëïÁñµ‰øÆË£úË´ãʱDŽř„Å©„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
その他の注意点

•ëÁ¥Ñ„ÅÆËߣÈô§„Å™„Å©„ÄÅÊ≥ïÂæãË°åÁÇ∫„ÇíË°å„ÅÜÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„ÄÅ„ÇÑ„ÇäÊñπ„Å´„ÇÇÊ≥®ÊÑè„ÄÄ
„ÇÇ„ÅóÁëïÁñµÊãÖ‰øùË≤¨‰ªª„ÅÆÂÜÖÂÆπ„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅ•ëÁ¥Ñ„ÅÆËߣÈô§„ÇíË°å„ÅÜÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„ÄÅËߣÈô§„ÇíË°å„ÅÜ„Åü„ÇÅ„ÅÆÊ≥ïÂæã‰∏ä„ÅƉ∫ãÂãôÊâãÁ∂ö„Åç„ÅÆ„ÇÑ„ÇäÊñπ„ÅÆÁü•Ë≠ò„ÇÇÂêà„Çè„Åõ„ŶË∫´„Å´„ŧ„Åë„Ŷ„Åä„Åè„Åπ„Åç„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ•ëÁ¥ÑËߣÈô§„ÅÆÂäπÊûú„ÇÑ„ÄÅÊúâÂäπ„Å™ÊÑèÊÄùË°®Á§∫„ÅÆ„ÇÑ„ÇäÊñπ„ÄÅÂæå„Å´„Éà„É©„Éñ„É´„Å´„Å™„Çâ„Å™„ÅÑ„Çà„ÅÜ„Å™ÈÄöÁü•„ÅÆË°å„ÅÑÊñπ„Å™„Å©„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„Äʼnª•‰∏ã„ÅÆË®ò‰∫ã„ÅßË©≥Á¥∞„Å´Ëߣ˙¨„ÇíË°å„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
紛争ではなく、交渉というかたちでの解決が望ましい 
„Åæ„Åü„ÄÅ„Åì„ÅÜ„Åó„Åü‰∏ÄÈÄ£„ÅÆÊ≥ïÂæãË´ñ„ÅØ„ÄÅÂøÖ„Åö„Åó„ÇÇË£ÅÂৄÅå˵∑„Åç„ÅüÂÝ¥Âêà„Å´„ÅÆ„ÅøÊÑèÂë≥„ÇíÊåńŧ„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅØ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇË£ÅÂৄŴ„Çà„ÇãÁ¥õ‰∫âËߣʱ∫„Å؉∏°ÂΩì‰∫ãËÄÖ„Å´„Å®„Å£„ŶÈùûÂ∏∏„Å´Ë≤ÝÊãÖ„Çǧ߄Åç„ÅÑ„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ„Åó„Åå„Åü„Å£„Ŷ„ÇÄ„Åó„Çç„ÄÅË£ÅÂৄŴ„ÅÑ„Åü„ÇãÂâçÊƵÈöé„ÅƉ∫§Ê∏âÊƵÈöé„Åß„Çǧ߄ÅÑ„Å´ÂΩπÁ´ã„Ŷ„Ŷ„ÅÑ„Åè„Åπ„ÅçÁü•Ë¶ã„Åß„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇË´∏„ÄÖ„ÅÆÊ≥ïÂæã‰∏ä„ÅÆÁü•Ë¶ã„Åå„ÄÅË£ÅÂ৉ª•Â§ñ„ÅƉ∫§Ê∏â„Å´„Åä„ÅфŶ„ÅÑ„Åã„Å™„ÇäÊÑèÁæ©„ÇíÊåńŧ„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„Åã„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„Äʼnª•‰∏ã„ÅÆË®ò‰∫ã„Å´„ŶËߣ˙¨„ÇíË°å„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
バグや不具合と、機能の不足は区別して考えるべき
ÂÆüË£Ö„Åó„Ŷ„Åç„ÅüÊ©üËÉΩ„ÇщªïÊßò„Å´„Éê„Ç∞„Çщ∏çÂÖ∑Âêà„Åå„ÅÇ„Çã„Çà„ÅÜ„Å™ÂÝ¥Âêà„Å®„ÄÅ„Åù„ÇÇ„Åù„ÇÇÂøÖ˶ńřÂÇô„Çè„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å™„ÅÑ„Çà„ÅÜ„Å™ÂÝ¥Âêà„Åß„ÅØ„ÄÅË≠∞Ë´ñ„ÅØÁï∞„Å™„Å£„Ŷ„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ„ÇÇ„ÅóÂøÖ˶ńřʩüËÉΩ„Åå„Å≤„Å®„Å®„Åä„ÇäÊèÉ„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å™„ÅÑ„Çà„ÅÜ„Å™ÂÝ¥Âêà„Åß„ÅÇ„Çå„Å∞„ÄÅ„Åù„ÇÇ„Åù„ÇÇË´ãË≤Ý•ëÁ¥Ñ„Å´„Åä„Åë„Çã„Ä剪ï‰∫ã„ÅÆÂÆåÊàê„Äç„ÅåË™ç„ÇÅ„Çâ„Çå„Åö„ÄÅÂǵÂãô„ÅƱ•Ë°å„ÇíË™ç„ÇÅ„Çâ„Çå„Å™„ÅÑÂèØËÉΩÊÄß„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åæ„Åü„ÄÅ„Åù„ÅÜ„Åó„ÅüÂøÖ˶ńřʩüËÉΩ„ÇщªïÊßò„ÇíÂÇô„Åà„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Å™„ÅÑ„Å®„Åó„Ŷ„ÇÇ„ÄÅ˶ʼnª∂ÂÆöÁæ©„ÅÆÊƵÈöé„Å߄ɶ„ɺ„Ç∂„ɺÂÅ¥„ÅåÈÅ©Âàá„Å™ÊÉÖÂݱÊèê‰æõ„ÇíË°å„Å™„Å£„Ŷ„Åì„Å™„Åã„Å£„ÅüÁµêÊûú„Å™„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çå„Å∞„ÄÅ„Åù„ÇÇ„Åù„ÇÇ•ëÁ¥ÑÂÜÖÂÆπ„ÅƉ∏ÄÈÉ®„Å®„Åø„Çã„Åì„Å®ËᙉΩì„Åå‰∏çÈÅ©ÂΩì„Åß„ÅÇ„Çã„Ů˩ï‰æ°„Åô„Åπ„ÅçÂÝ¥Âêà„ÇÇ„ÅÇ„Çä„ÅÜ„Çã„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÄÇ
まとめ
„Éó„É≠„Ç∏„Çß„ÇØ„Éà„ÅÆÂ∑•Á®ã„ÅÆ„Å™„Åã„ÅßÁîü„Åò„ÅüÂïèÈ°å„ÅØ„ÄÅ„Éó„É≠„Ç∏„Çß„ÇØ„Éà„ÅÆÈÄ≤Ë°å‰∏≠„Å´Áô∫˶ö„Åô„ÇãÂÝ¥Âêà„ÇÇ„ÅÇ„Çå„Å∞„ÄÅÈÅãÁî®ÊƵÈöé„Å™„Å©„Å߉∫ãÂæå„ÅßÁô∫˶ö„Åô„ÇãÂÝ¥Âêà„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇÁÑ°‰∫ã„Å´ÂÖ®ÈÉ®„ÅÆÂ∑•Á®ã„ÇíÁµÇ„Åà„Åü„Å®„Åó„Ŷ„ÇÇÂøÖ„Åö„Åó„ÇÇÂÆâÂøÉ„Åß„Åç„Å™„ÅÑ„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝÈñãÁô∫„Éó„É≠„Ç∏„Çß„ÇØ„Éà„ÅÆÁâπÂ楄ÅØ„ÄÅ„ÄåÁëïÁñµÊãÖ‰øùË≤¨‰ªª„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜÂà∂Â∫¶„Å´„Åì„Åù˱°Â楄Åï„Çå„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„Çà„ÅÜ„Å´ÊÄù„Çè„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝÈñãÁô∫„Éó„É≠„Ç∏„Çß„ÇØ„ÉàÁµÇ‰∫ÜÂæå„ÅÆ„Åì„Å®„Åæ„Åß˶ãÊçÆ„Åà„ÅüÊñáÊõ∏ÁÆ°ÁêÜ„ÅÆÂæπÂ∫ï„Çí„ÅØ„Åã„Çã„Å®„Å®„ÇÇ„Å´„ÄÅ„Åì„ÅÜ„Åó„Åü‰∏ÄÈÄ£„ÅÆʵńÇå„ÇíÊääÊè°„Åó„Ŷ„Åä„Åè„Åì„Å®„ÅåÈáç˶ńÅÝ„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務