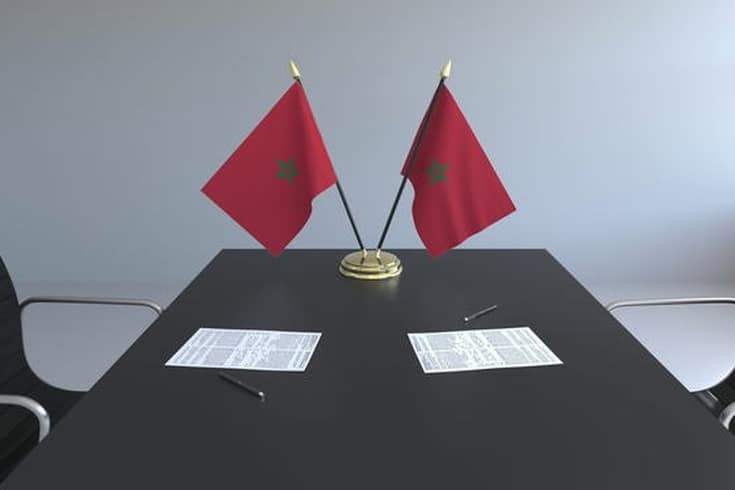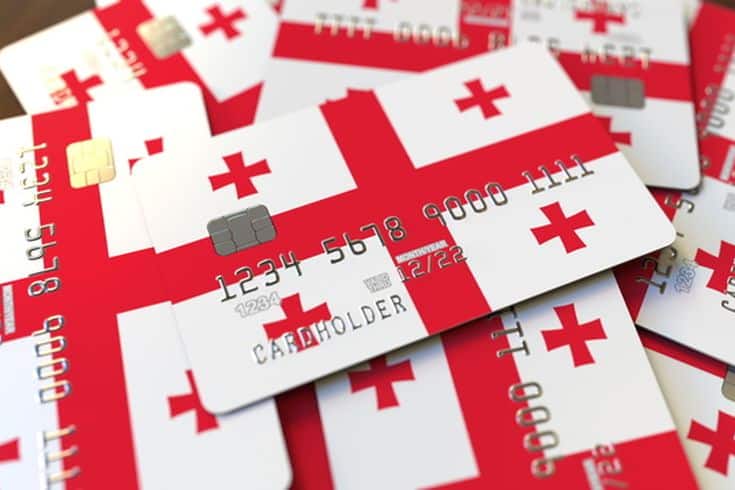台湾での契約書作成時に問題となる民法・契約法の解説
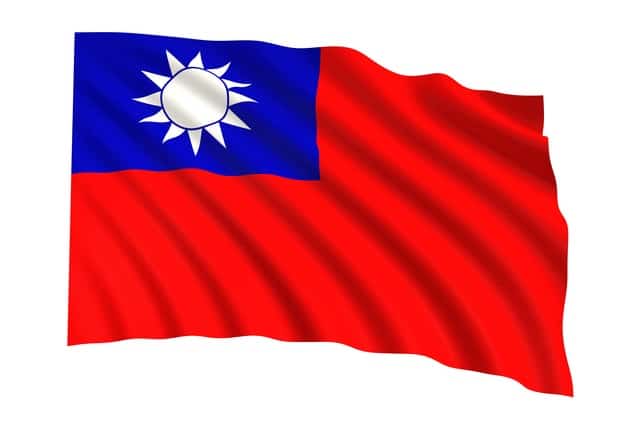
台湾の民法は、1929年の制定以来、主に1900年に施行されたドイツ民法を継受しており、その全体的な構成や債権・契約に関する基本的な考え方は、同じく大陸法を起源とする日本の民法と多くの共通点を有しています。この類似性は、台湾でのビジネス展開を検討する日本企業にとって、法制度への親和性を感じさせるかもしれません。しかし、類似しているからこそ見過ごされがちな、ビジネス上のリスクに直結する重要な相違点がいくつか存在します。
台湾の法制度は、日本統治時代を経て、中華民国が大陸で制定した法体系が適用された後、長期間にわたる戒厳令を経て1987年の民主化を契機に急速な法改革を遂げてきました。この歴史的経緯により、日本の法制度とは異なる独自の解釈や規定が形成されています。
本記事では、日本企業が台湾で企業間での契約書実務などを円滑に進行するために不可欠な、民法・契約法上の特有のルールや、日本法との決定的な違いを、具体的な法令と判例を根拠に深く解説します。
なお、台湾の包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
台湾民法の沿革と日本法との類似性
台湾の民法は、総則、債権、物権、親属、継承の五編から構成され、全1225条に及ぶ体系的な法典です。この五編構成は、ドイツの法学におけるパンデクテン・システムを継受したものであり、日本の民法も同様の体系を採用していることから、両国の民法は共通の骨格を有しています。
しかし、日本の民法と台湾の民法が類似しているのは、直接的な法継受関係にあるからではありません。中華民国政府が制定した民法は、主にドイツ民法を法源としており、この共通のルーツが両国の民法典に多くの類似点をもたらしています。日本の植民地時代(1895年〜1945年)には、日本の民法が台湾に適用された時期もありましたが、その後中華民国の法体制へと移行しています。特に知的財産法(専利法)のような分野では、日本統治時代の特許法を直接引き継いだものではなく、中華民国政府が独自に研究・制定した制度が発展してきた経緯があります。
また、台湾は1945年の第二次世界大戦終結後、中華民国の法体制へと移行しましたが、長期間にわたる戒厳令(1945年〜1987年)の下では、民主的な法制の多くが形骸化していました。1987年の戒厳令解除とそれに続く民主化以降、台湾は独自の司法改革を進め、憲法改正や民事・行政訴訟法の整備など、急速な法改革を遂げてきました。これにより、同じドイツ法を基礎としながらも、法解釈や特定の分野では台湾独自の発展を遂げており、日本とは異なる法概念や制度が確立されています。このような歴史的背景を理解することは、表面的な類似性にとどまらず、両国の法制度の相違点が生じる根本的な理由を把握する上で不可欠です。
台湾における契約の成立と「付随義務」
台湾の民法における契約の基本原則は、日本法とほぼ同様です。まず、契約は当事者が主要な条件に合意すれば成立し、口頭での合意も法的に認められます。ただし、契約書の作成は、後々のトラブルを防ぐ上で重要です。
意思表示の解釈においては、文言の字義に固執せず、当事者の真意を探求する旨が台湾民法第98条に明確に規定されています。総じて、台湾は、上記のような総合考慮的な真意探求の傾向が日本よりも強いと言われています。裁判実務においても、最高法院は、当事者間で真意に争いがある場合、意思表示が基づく原因事実、経済目的、社会通念、取引習慣、客観的情勢などを総合的に考慮して真意を探求すべきであると判断しています。また、定型化された契約については、経済的に弱い当事者に有利に解釈されるべきであるとの見解も示されています。これらの判例からは、契約書の作成段階で、単に条項を羅列するだけでなく、当事者の意図や背景をより詳細に、かつ明確に文書化しておくことの重要性が読み取れます。
また、契約上の「付随義務」の考え方も、ドイツ法および日本法と同様に通説・実務上採用されています。これは、契約関係において、当事者は信義誠実の原則に基づき、通知、警告、協力、秘密保持、保護といった義務を負うというものです。台湾の最高法院は、この付随義務が給付義務を履行し、または当事者の利益を保護するために、誠信原則に基づいて発生すると強調しています。付随義務の違反が原因で債権者が損害を被った場合、債務不履行として損害賠償を請求できるだけでなく、その違反が契約目的の達成に重大な影響を与えた場合には、契約を解除する根拠にもなりうると判示されています。この原則は、契約交渉段階(culpa in contrahendo)においても適用されると解釈されています。例えば、契約締結前の交渉において、一方の当事者が重要な情報を故意に開示しなかった場合、その不誠実な行為によって生じた相手方の損害に対し、賠償責任を負う可能性があるという考え方です。日本の判例においても同様の考え方が示されていますが、台湾ではこの考えがより明確に法制度に織り込まれていると言えます。
台湾の不動産取引における「登記発効主義」

日本の法律と台湾の法律との間で、ビジネス上のリスクに直結する最も重要な違いの一つが、不動産物権の変動に関するルールです。日本では「登記対抗主義」が採用されており、不動産の売買契約が成立すれば、所有権は当事者間で直ちに移行し、登記は第三者に対抗するための要件とされます。
これに対し、台湾では「登記発効主義」を採用しています。台湾民法第758条は、「物権因法律行為而取得、設定、喪失及変更者,非経登記,不生效力」(法律行為により取得、設定、喪失及び変更される不動産上の権利は、登記を経なければ効力を生じない)と明確に規定しています。これは、不動産の所有権が売買契約を締結しただけでは移転せず、不動産登記が完了して初めて法的に有効となることを意味します。
この原則は、台湾の裁判実務においても一貫して適用されています。例えば、不動産の二重売買において、先に契約を締結して不動産を占有していた買主がいても、後から契約を締結した買主が先に登記を完了させた場合、後者こそが正当な所有権者と認められるという最高法院の判例(19年上字第138号、83年台上字第3243号)が存在します。
これにより、売買契約を締結しても、登記が完了する前に売主が第三者に二重譲渡を試みたり、売主の他の債務者が当該不動産を差し押さえたりするリスクは、日本よりも髙いものと言えます。したがって、台湾で不動産を取得したり、担保を設定したりする際には、契約締結後、速やかに登記手続きを完了させることの絶対的な重要性を理解し、実務的なサポートを確保する必要があります。
不動産登記は、土地局(地政事務所)によって管理されており、オンラインで所有者情報などの公的記録を検索することも可能です。日本企業は、台湾で不動産取引を行う際、このような法制度の根本的な違いを認識した上で、取引先の調査や手続きを慎重に進めることが求められます。
台湾の知的財産権や消費者問題における懲罰的損害賠償
日本の民法は、原則として、加害者の行為によって被害者が実際に被った損害(現実の損失と逸失利益)を填補することを目的とする「填補的(補填的)損害賠償」の考え方を採用しており、制裁や抑止を目的とする「懲罰的損害賠償」は認められていません。
しかし、台湾ではこの原則に重大な例外が存在します。民法上の損害賠償は填補を目的としますが 、特定の法律において、加害行為の悪質性を考慮し、実際に生じた損害額を超える賠償を命じる「懲罰的損害賠償」が明文化されているのです。この概念は、特に知的財産権の侵害 や消費者保護関連の事案において顕著です。
例えば、台湾の専利法(特許法)第97条第2項は、故意による特許権侵害があった場合、裁判所は被害者の請求に基づき、証明された損害額の最大3倍までの賠償金を算定できると定めています。また、消費者保護法第51条は、事業者の故意による不法行為に対し、最大5倍の賠償を請求できると規定しています。特に消費者保護法においては、最高法院が過失(軽過失を含む)であっても懲罰的損害賠償責任が成立するとの見解を示しており、この点で事業者側の責任が厳格に問われる可能性があります。
日本企業にとって、この制度は予期せぬ巨額の賠償リスクをもたらす可能性があります。日本での法的感覚に基づけば、侵害行為によって得た利益や被害額の範囲で賠償額が算定されると想定しますが、台湾ではその数倍の額を請求される可能性があります。これは、台湾でのビジネス展開において、知的財産権の管理や消費者対応に関するコンプライアンスを、日本以上に厳格に管理する必要があることを意味します。特に、侵害の通知を受けた後も行為を継続すると、裁判所から「故意の侵害者」と認定される可能性が高まります。
台湾における契約履行不能と「情勢変更の原則」
契約の履行が不可能になった場合、台湾の民法では、その原因が債務者の責めに帰すべからざる事由(例:地震、戦争、台風などの不可抗力)によるものであれば、債務者は履行義務を免れます(台湾民法第225条)。この点は日本法と同様ですが、不可抗力とまではいえないような、債務者のせいとは言えない事由については、両国の法解釈に微妙な差異が生じることもあり得ると言えるでしょう。
さらに、台湾の民法には「情勢変更の原則」が明文化されています。台湾民法第227条の2は、「契約成立後に、当事者が予測できなかった事情変更により、元の給付を履行させることが公平の原則に反する場合、当事者が契約の変更または解除を請求できる」と規定しています。
この条文の適用について、最高法院は「予見可能性」を重視する立場を示しています。判例(106年度台上字第4号判決など)によれば、情勢変更の原則は、当事者が契約締結時に予測できなかった、客観的な状況の正常な発展を超えるような変動があった場合に適用を認めるべきであるとされています。例えば、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックによる家賃減額請求訴訟においては、予見可能性や当事者の利益を総合的に考慮した上で、請求を認めた裁判例と認めなかった裁判例の両方が存在します。このような判例の傾向は、長期的な取引契約において、予期せぬ事態に備えた再交渉条項や不可抗力条項をより慎重に検討する必要があることを示唆しています。
まとめ
本稿で解説したように、台湾の民法・契約法は、日本法と多くの共通点を持ちつつも、ビジネス上のリスクに直結する重要な相違点を内包しています。特に、不動産取引における「登記発効主義」は、所有権の概念そのものが日本とは異なることを意味します。また、知的財産権侵害や消費者保護といった特定分野で認められる「懲罰的損害賠償」は、日本のビジネスパーソンが予期せぬ巨額の賠償を回避するために深く理解しておくべき点です。さらに、契約交渉における「真意探求」の原則や、「情勢変更の原則」の明文化は、日本とは異なる契約実務上の注意点を浮き彫りにします。
こうした複雑な国際法務問題の解決には、現地の法制度に対する深い知見と、実務上の慣習を理解した専門家のサポートが不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務