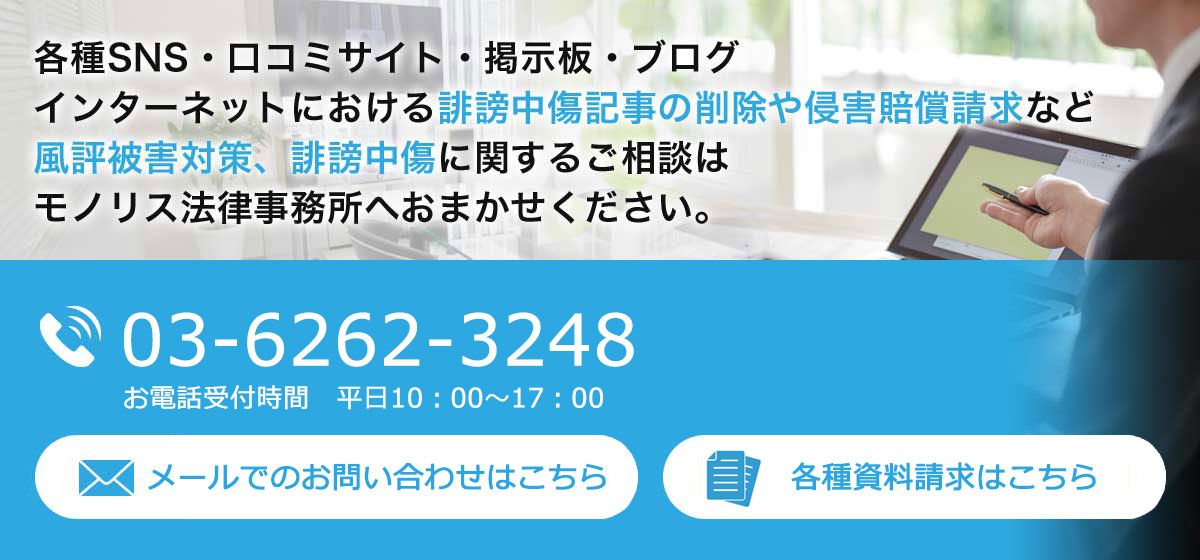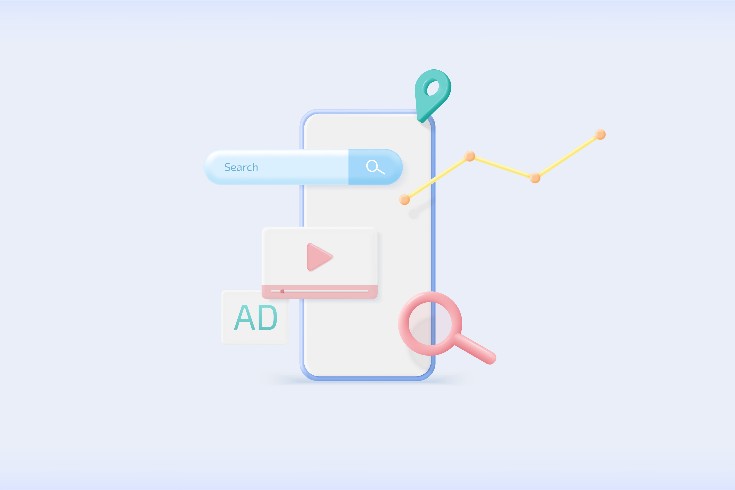„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„ÅÆÊÖ∞˨ùÊñô„ÅØ„ÅÑ„Åè„ÇâÔºüÂÆüÂãô‰∏ä„ÅÆÁõ∏ÂÝ¥„ÇíºÅË≠∑£´„ÅåËߣ˙¨

ÂêçË™âÊØÄÊêç„ÇÑ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„ÅƉæµÂÆ≥„ÅåË™ç„ÇÅ„Çâ„Çå„Çå„Å∞ÊÖ∞˨ùÊñô„ÅÆË´ãʱDŽÅåÂèØËÉΩ„Åß„Åô„ÄÇÊÖ∞˨ùÊñô„Å®„ÅØ„ÄÅ„ÄåÁâ©Ë≥™ÁöÑÊêçÂÆ≥„Åß„ÅØ„Å™„ÅèÁ≤æÁ•ûÁöÑÊêçÂÆ≥„Å´ÂØæ„Åô„ÇãË≥ÝÂÑü„ÄçÔºàÊúÄÈ´òË£ÅÂà§ÊâÄ„ÄÄÂπ≥Êàê6Âπ¥Ôºà1994Âπ¥Ôºâ2Êúà22Êó•Âà§Ê±∫Ôºâ„Å®„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„Åå„ÄÅËã¶Áóõ„ÅÆÁ®ãÂ∫¶„ÇíÂƢ˶≥ÁöфɪÊï∞ÈáèÁöÑ„Å´ÊääÊè°„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅØÂõ∞Èõ£„Å™„ÅÆ„Åß„ÄÅÊßò„Äքř˶ÅÁ¥Ý„ÇíËÄÉÊÖÆ„Åó„ŶÁÆóÂá∫„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åß„ÅØ„ÄÅÊÖ∞˨ùÊñô„ÅƉ∏ÄËà¨ÁöÑ„Å™Áõ∏ÂÝ¥„ÅØ„Å©„Çå„Åè„Çâ„ÅÑ„Å™„ÅÆ„Åß„Åó„Çá„ÅÜ„ÅãÔºü
ÂÆüÂãô‰∏ä„Åß„ÅØ„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„ÅƉæµÂÆ≥„ÅÆÊÖ∞˨ùÊñô„Å؉ΩéÈ°ç„Å™ÂÇæÂêë„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„Åå„ÄÅÊú¨Ë®ò‰∫ã„Åß„ÅØÂÆüÈöõ„ÅƉ∫ã‰æã„ÇíÂÖÉ„Å´„Åó„ŶÊÖ∞˨ùÊñô„ÅÆÁõ∏ÂÝ¥„ÇíËߣ˙¨„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ
この記事の目次
プライバシー侵害が成立する要件
„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„Å®„ÅØ„ÄåÁßÅÁîüÊ¥ª„Çí„Åø„ÅÝ„Çä„Å´ÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„Å™„ÅÑ„Å®„ÅÑ„ÅÜÊ≥ïÁöщøùÈöú„Å™„ÅÑ„ÅóÊ®©Âà©„Äç„ÇíÊåá„Åó„ÄÅÂÄã‰∫∫„ÅÆÂ∞äÂé≥„ÇíÂÆà„Çä‰∫∫Êݺ„ÇíÂ∞äÈáç„Åô„Çã„Åü„ÇÅ„ÅÆÈáç˶ńřʮ©Âà©„Åß„Åô„ÄÇÊÜ≤Ê≥ïÁ¨¨13Êù°„ÅåÊÝπÊãÝ„Å®„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„Åå„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺʮ©„Å®„ÅÑ„ÅÜÊñáˮĄÅù„ÅÆ„ÇÇ„ÅÆ„ÅØÊ≥§„Å´„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅ„Åï„Åæ„Åñ„Åæ„řʮ©Âà©„ÇíÂåÖÊ㨄Åó„ÅüʶÇÂøµ„Å®„Åó„ŶËߣÈáà„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÂÄã‰∫∫„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÊÉÖÂݱ„Çí„Ç≥„É≥„Éà„É≠„ɺ„É´„Åô„ÇãÊ®©Âà©„ÄÅËá™ÂàÜ„ÅÆÊÑèÊÄù„Å´Âèç„Åó„ŶÁßÅÁîüÊ¥ª‰∏ä„ÅƉ∫ãÂÆü„ÇíÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„Å™„ÅÑËá™ÁÄÅÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„ÅüÊÉÖÂݱ„ÅÆË®ÇÊ≠£„ÇÑÂâäÈô§„ÇíʱDŽÇÅ„ÇãÊ®©Âà©„ÇÇÂê´„Åø„Åæ„Åô„ÄÇ
プライバシー侵害が認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 私事性
- ÁßòÂåøÊÄß
- 非公知性
Áßʼn∫ãÊÄß„Å®„ÅØ„ÄÅÂÄã‰∫∫„ÅÆÁßÅÁîüÊ¥ª„Å´Èñ¢„Åô„Çã‰∫ãÂÆü„ÄÅ„Åæ„Åü„ÅØ„Åù„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´Âèó„ÅëÂèñ„Çâ„Çå„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„ÅÆ„ÅÇ„ÇãÂÜÖÂÆπ„ÇíÊåá„Åó„Åæ„Åô„ÄÇÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´„ÅØ„ÄʼnΩèÊâÄ„ÇÑÊ∞èÂêç„ÄÅ˪ä„ÅÆ„Éä„É≥„Éê„ɺ„Å™„Å©„ÅÆÂÄã‰∫∫„ÇíÁâπÂÆö„Åß„Åç„ÇãÊÉÖÂݱ„ÇÑ„ÄÅÂÄã‰∫∫ÁöÑ„Å™ÁµåÈ®ì„ÄÅË®òÈå≤„Å™„Å©„Åß„Åô„ÄÇ
ÁßòÂåøÊÄß„ÅØ„Äʼn∏ÄËਉ∫∫„ÅÆÊÑü˶ö„ÇíÂü∫Ê∫ñ„Å®„Åó„ŶÂà§Êñ≠„Åï„Çå„Åæ„Åô„Äljªñ‰∫∫„Å´„ÅØÁü•„Çâ„Çå„Åü„Åè„Å™„ÅÑÂÜÖÂÆπ„ÇÑ„ÄÅÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„ÅßÂøÉÁêÜÁöÑ„Å™Ë≤ÝÊãÖ„Çщ∏çÂÆâ„Çí˶ö„Åà„ÇãÊÉÖÂݱ„ÇíÊåá„Åó„Åæ„Åô„Äljæã„Åà„Å∞„ÄÅË∫´‰ΩìÁöÑÁâπÂ楄ÄÅÂâçÁßë„ɪÁäØÁΩ™Ê≠¥„ÄÅÁóÖÊ≠¥„ÄÅÈõ¢Â©ö„ÅÆÁµåÁ∑Ø„Å™„Å©„Åß„Åô„ÄÇ
ÈùûÂÖ¨Áü•ÊÄß„Å®„ÅØ„Äʼn∏ÄË਄ÅƉ∫∫„ÄÖ„Å´Â∫É„ÅèÁü•„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Å™„Åщ∫ãÊüÑ„ÅÆ„Åì„Å®„Åß„Åô„ÄÇ„Åü„ÅÝ„Åó„Äʼn∏ÄÂ∫¶„Å©„Åì„Åã„ÅßÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„ÅüÊÉÖÂݱ„Åß„ÅÇ„Å£„Ŷ„ÇÇ„ÄÅË™≠ËÄÖ±§„ÅåÁï∞„Å™„ÇãÂÝ¥Âêà„ÇÑÂÖ¨ÈñãÁØÑÂõ≤„ÇÇÈôêÂÆöÁöÑ„Åß„ÅÇ„ÇãÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„ÄÅ„Å™„Åä‰øùË≠∑„Åï„Çå„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇË©≤ÂΩì„Åô„Çã„ÅÆ„ÅØÁßÅÁöÑ„Å™„É°„ÉɄǪ„ɺ„Ç∏„ÅÆ„ÇÑ„ÇäÂèñ„ÇäÔºàLINE„ÄÅDM„ÄÅÊâãÁ¥ô„Å™„Å©Ôºâ„ÇÑ„ÄÅÁâπÂÆö„ÅÆÈõÜÂõ£ÂÜÖ„Åß„ÅÆ„ÅøÂÖ±Êúâ„Åï„Çå„ÅüÊÉÖÂݱ„Å™„Å©„Åß„Åô„ÄÇ
„Åì„Çå„Çâ3„ŧ„ÅÆ˶ʼnª∂„ÇíÊ∫Ä„Åü„ÅôÂÜÖÂÆπ„ÅåÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„ÄÅ„Åù„ÅÆÁµêÊûú„Å®„Åó„Ŷ‰∏çÂø´„ɪ‰∏çÂÆâ„ÅÆÂøµ„ÅåÁîü„Åò„ÅüÂÝ¥Âêà„Å´„ÄÅÊ≥ïÁöщøùË≠∑„ÅÆÂØæ˱°„Å®„Å™„Çã„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„ÅåÊàêÁ´ã„Åó„Åæ„Åô„ÄÇËøëÂπ¥„Åß„ÅØÁâπ„Å´SNS„ÅÆÊôÆÂèä„Å´„Çà„Çä„ÄÅÂÄã‰∫∫ÊÉÖÂݱ„ÅÆÂÖ¨Èñã„ÇÑÊã°ÊÅåÂÆπÊòì„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åü„ÇÅ„ÄÅ„Çà„Çä‰∏ı§„ÅÆÊ≥®ÊÑè„ÅåÂøÖ˶ńÅß„Åô„ÄÇ
„Å™„Åä„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„ÅåË™ç„ÇÅ„Çâ„Çå„ÅüÂÝ¥Âêà„ÄÅË¢´ÂÆ≥ËÄÖ„ÅØÂ∑ÆÊ≠¢Ë´ãʱDŽÇÑÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽř„Å©„ÅÆÊ≥ïÁöÑÊé™ÁΩÆ„ÇíÂèñ„Çã„Åì„Å®„ÅåÂèØËÉΩ„Åß„Åô„ÄÇ
名誉毀損とプライバシー侵害の違い

名誉毀損とプライバシー侵害は、個人の権利を侵害する行為として似ているように見えますが、その性質と法的な扱いには重要な違いがあります。
ÂêçË™âÊØÄÊêç„ÅØ„Ä剪ñ‰∫∫„ÅÆÂêçË™â„ÇíÂÇ∑„ŧ„Åë„Çã‰∏çÊ≥ïË°åÁÇ∫„ÇÑÁäØÁΩ™Ë°åÁÇ∫„Äç„Åß„Åô„Äljæã„Åà„Å∞„ÄÅ„ÅÇ„Çã‰∫∫„Å´„ŧ„ÅфŶ„Äå‰∏çÂÄ´„Çí„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„Äç„Å®„ÅÑ„Å£„Åü‰∫ãÂÆü„ÅÆÊúâÁÑ°„Å´„Åã„Åã„Çè„Çâ„Åö„ÄÅ„Åù„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™Áô∫ˮĄŴ„Çà„Å£„Ŷ„Åù„ÅƉ∫∫„ÅÆÁ§æ‰ºöÁöÑÂú∞‰Ωç„ÇÑÂêçË™â„ÅƉΩé‰∏ã„ÅåÊòé„Çâ„Åã„Å™ÂÝ¥Âêà„ÄÅÂêçË™âÊØÄÊêç„ÅåÊàêÁ´ã„Åó„Åæ„Åô„ÄÇÂêçË™âÊØÄÊêç„ÅØÂàë‰∫ãÁΩ∞„ÅÆÂØæ˱°„Å®„Å™„Çä„ÄÅÊúâÁΩ™„ÅÆÂÝ¥Âêà„ÅØ3Â𥉪•‰∏ã„ÅÆÊá≤ÂΩπ„ÇÇ„Åó„Åè„ÅØÁ¶ÅÈåÆ„ÄÅ„Åæ„Åü„ÅØ50‰∏áÂÜ܉ª•‰∏ã„ÅÆÁΩ∞Èáë„ÅåÁßë„Åï„Çå„Åæ„Åô„ÄÇÔºàÂàëÊ≥ïÁ¨¨230Êù°Ôºâ
‰∏ÄÊñπ„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„ÅƉæµÂÆ≥„ÅØ„ÄåÊú™ÂÖ¨Èñã„ÅÆÁßÅÁîüÊ¥ª„ÅÆÊÉÖÂݱ„ÇíÊú¨‰∫∫„ÅÆÊÑèÊÄù„Å´Âèç„Åó„ŶÁ¨¨‰∏âËÄÖ„Å´ÈñãÁ§∫„ÄÅÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„Äç„Åß„Åô„ÄÇ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„ÅƉæµÂÆ≥„Å´„ÅØÂàë‰∫ãÁΩ∞„ÅÆ˶èÂÆö„Åå„Å™„Åè„ÄÅÊ∞ë‰∫ãÁöÑ„Å™ÂØæÂøúÔºàÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱÇÔºâ„ÅÆ„Åø„ÅåÂèØËÉΩ„Åß„Åô„ÄÇ
„Åù„ÅÆÈöõ„ÄÅË¢´ÂÆ≥ËÄÖ„Åå„ÄåÁ´ãË®ºË≤¨‰ªª„Äç„ÇíË≤Ý„ÅÜ„Åì„Å®„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„ÅƉ∫ãÂÆü„ÇÑ„ÄÅ„Åù„Çå„Å´„Çà„Å£„Ŷˢ´„Å£„ÅüÁ≤æÁ•ûÁöфɪÁµåÊ∏àÁöÑÊêçÂÆ≥„ÅÆÂ≠òÂú®„Çí„ÄÅË¢´ÂÆ≥ËÄÖËá™Ë∫´„ÅåË®ºÊãÝ„ÇíÁ§∫„Åó„ŶˮºÊòé„Åó„Å™„Åë„Çå„Å∞„Å™„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ
ÂÆüÈöõ„ÅƉ∫ãÊ°à„Åß„ÅØ„ÄÅ„Åì„Çå„Çâ‰∫å„ŧ„ÅÆÊ®©Â੉æµÂÆ≥„ÅåÂêåÊôÇ„Å´Áô∫Áîü„Åô„Çã„DZ„ɺ„Çπ„ÇÇÂ∞ë„Å™„Åè„ÅÇ„Çä„Åæ„Åõ„Çì„Äljæã„Åà„Å∞„Äńǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà‰∏ä„ÅßÂÄã‰∫∫„ÅƉΩèÊâÄ„ÇÑÊ∞èÂêç„ÇíÂÖ¨Èñã„Åô„Çã„Å®ÂêåÊôÇ„Å´„ÄÅË™π˨ó‰∏≠ÂÇ∑„ÇíÊõ∏„ÅçË溄ÇÄ„Çà„ÅÜ„Å™ÂÝ¥Âêà„ÅØ„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„Å®ÂêçË™âÊØÄÊêç„ÅƉ∏°Êñπ„ÅåÊàêÁ´ã„Åô„ÇãÂèØËÉΩÊÄß„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™ÂÝ¥Âêà„ÄÅË¢´ÂÆ≥ËÄÖ„ÅØÊ∞ë‰∫ã‰∏ä„ÅÆÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽŴÂäÝ„Åà„Ŷ„ÄÅÂêçË™âÊØÄÊêç„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅÆÂàë‰∫ãÂëäË®¥„ÇÇÂèØËÉΩ„Åß„Åô„ÄÇ
プライバシーの侵害が認められた裁判例と慰謝料

乳がんの闘病記録の事例
病歴は、自身の健康状況や身体的な特徴などと密接に関わることがあり、誰しも不特定多数の人に知られたくないものです。本件で問題になったのは「若年性乳がん」の病歴です。
乳がんの闘病記録を記したブログを匿名で運営していた女性が、被告の投稿により氏名、年齢、勤務先等を特定され、若年性乳がんに罹患していた事実を一般の人に知られてしまい、プライバシーを侵害されたとして提訴した事例があります。
裁判所は、
「乳がんに罹患した事実や治療経過及び結果などは、私給与明細等を公開した事例生活上の事柄であり、また通常人の感受性を基準にしても公開されることを望まない事実であると解される」
東京地方裁判所 平成26年6月13日判決
とし、原告のプライバシー権の侵害を認定し、慰謝料120万円及び弁護士費用12万円、合計132万円の支払いを被告に命じました。
関連記事:ネット上の誹謗中傷行為とプライバシーの侵害
Èñ¢Èģˮò‰∫ãÔºöÁóÖÊ∞óÊÉÖÂݱ„Çí„Éç„ÉÉ„Éà„ÅßÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„Åü„Çâ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„ŮˮĄÅà„Çã„Åã
給与明細等を公開した事例
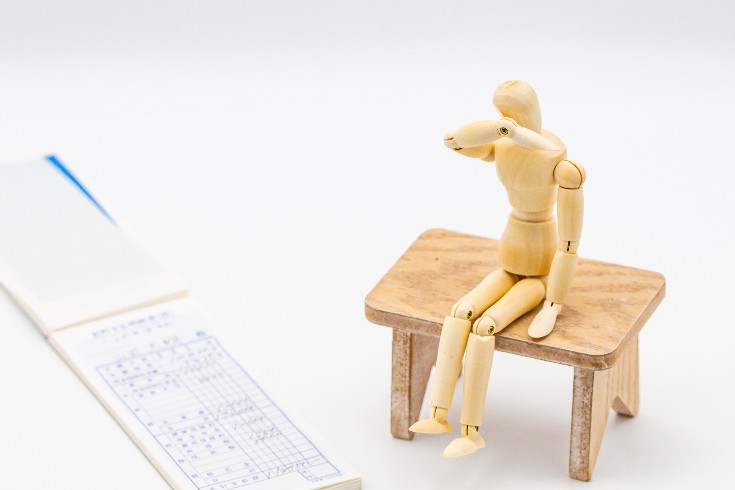
Áµ¶‰∏éÊòéÁ¥∞„ÇíÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„Åü„Å®„Åó„ŶWeb„ǵ„ǧ„ÉàÈÅãÂñ∂‰ºöÁ§æ„Å´ÂØæ„Åó„ÄÅÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑü„ÇíʱDŽÇÅ„Åü„DZ„ɺ„Çπ„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
Ë¢´Âë䉺öÁ§æ„Åå„ÄŧßÊâãÂá∫ÁâàÁ§æ„ÅÆÂݱÈÖ¨Ê∞¥Ê∫ñ„Å®‰∏ãË´ã„Åë„É©„ǧ„Çø„ɺ„ÇÑÁï∞Ê•≠Á®Æ„Å®„ÅÆË≥ÉÈáëÊݺÂ∑ÆÂïèÈ°å„ÇíË´ñ„Åö„Çã„Å®„Åó„Ŷ„Äńǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà‰∏ä„ÅßËᙄÇâ‰∏ªÂÆ∞„Åô„ÇãWeb„ǵ„ǧ„Éà„Å´Êé≤˺â„Åó„ÅüË®ò‰∫ã„Åå„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„Çí‰æµÂÆ≥„Åó„Åü„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅÂéüÂëä„ÅÆ•≥ÊÄßÁ§æÂì°„ÅåÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑü„ÇíʱDŽÇÅ„Åü‰∫ã‰æã„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
Ë¢´Âë䉺öÁ§æX„ÅƉª£Ë°®ÂèñÁ∑ÝÂΩπ„Åß„ÅÇ„ÇãË¢´ÂëäÔºπ„ÅØ„ÄÅX„Åå‰∏ªÂÆ∞„Åô„Çã„ǵ„ǧ„Éà„Å´„ÄåÂõΩÊ∞ë„ÅÆÂÉç„ÅèÊÑèʨ≤Ââä„Åê‚óã‚óãÁ§æ„ÅÆÁï∞Â∏∏Ë≥ÉÈáë„Äç„ŮȰå„Åô„ÇãË®ò‰∫ã„ÇíÊé≤˺â„Åó„ÄÅ„ÄåÂè≥Ë®ò„ÅØ„ÄÅ‚óã‚óãÁ§æ„ÅåÁô∫Ë°å„Åô„Çã•≥ÊÄßË™å„Äé‚ñ≥‚ñ≥Ë™å„ÄèÁ∑®ÈõÜÈÉ®„ÅÆ„ÄÅ28Ê≠≥•≥ÊÄßÁ§æÂì°„ÅÆÁµ¶‰∏éÊòéÁ¥∞„ÅÝ„Äç„Å®Âá∫ÁâàÁ§æÂêç„Å®ÈıÂàäË™åÂêç„Çí„ÅÇ„Åí„Ŷ„ÄÅ„Åì„ÅÆ•≥ÊÄßÁ§æÂì°„ÅÆ„ÄåÁµ¶‰∏éÊòéÁ¥∞Êõ∏„Äç„ÄÅ„ÄåÊ∫êÊ≥âÂæ¥ÂèéÁ•®„Äç„ÄÅ„ÄåÁâπÂà•Âå∫Ê∞ëÁ®é„ɪÈÉΩÊ∞ëÁ®éÔºèÁâπÂà•Âæ¥ÂèéÁ®éÈ°ç„ÅÆÈÄöÁü•Êõ∏„Äç„ÇíÂèéÈå≤„Åó„ÄÅ„Åì„ÅÆ•≥ÊÄßÁ§æÂì°„ÅÆÁµ¶‰∏é„Åå„Äå76‰∏áÂÜÜË∂Ö„Äç„Åß„ÅÇ„Çã„Ůˮò˺â„Åó„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
Ë®ò‰∫ã„Å´Êé≤˺â„Åï„Çå„ÅüÁµ¶‰∏éÊòéÁ¥∞Á≠â„ÅØ„ÄÅÁ§æÂì°Áï™Âè∑Âèä„Å≥Ê∞èÂêç„ÅØ˶ã„Åà„Å™„ÅÑ„Çà„ÅÜ„Å´ÂäÝÂ∑•Âá¶ÁêÜ„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÅÆ„Åß„Åô„Åå„ÄÅÊâıûÈÉ®ÁΩ≤„Åå„Äå‚ñ≥‚ñ≥Ë™å„Äç„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÅåË™≠„ÅøÂèñ„Çå„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ„Äå‚ñ≥‚ñ≥Ë™å„ÄçÁ∑®ÈõÜÈÉ®„ÅØ20„Åã„Çâ25‰∫∫„ÅßÊßãÊàê„Åï„Çå„ÄÅ„Åù„ÅÆ„ÅÜ„Å°Á§æÂì°„ÅØÁ¥Ñ10‰∫∫„Åß„ÄÅ20‰ª£Â•≥ÊÄßÁ§æÂì°„ÅØÂéüÂëä„ÅÝ„Åë„Åß„Åó„Åü„ÄDŽŧ„Åæ„Çä„ÄÅÂéüÂëä„ÅåÊâıû„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÇãÁ§æÂÜÖ„ÅÇ„Çã„ÅÑ„ÅØÂêåÊ•≠ËÄÖÁ≠â„ÅßÂéüÂëä„ÇíÁü•„ÇãËÄÖ„ÅÆÁõ∏ÂΩìÊï∞„ÅØË®ò‰∫ã„ÅƉ∫∫Áâ©„ÅåÂéüÂëä„Åß„ÅÇ„Çã„Å®ÂêåÂÆö„Åß„Åç„Åü„ÅÆ„Åß„Åô„ÄÇ
裁判所は、
「プライバシーの侵害は、必ずしもその態様が不特定多数の者への公表に限られるものではなく、特定集団あるいは特定人への開示もその侵害となり得るものである」
最高裁判所 平成15年3月14日判決
とし、また、
„Äå‰∏ÄÂÆöÁØÑÂõ≤„ÅƉªñËÄÖ„Å´„ÅØ„ÄÅÂΩìÁÑ∂ÈñãÁ§∫„Åô„Åπ„ÅçÂÄã‰∫∫ÊÉÖÂݱ„ÇÑÁâπ„Å´ÁßòÂåø„Åï„Çå„Çã„Åπ„Åç„ÇÇ„ÅÆ„Å®„ÅØ„ÅÑ„Åà„Å™„ÅÑÊÉÖÂݱ„Åß„ÅÇ„Å£„Ŷ„ÇÇ„ÄÅËá™Â∑±„Ååʨ≤„Åó„Å™„ÅщªñËÄÖ„Å´„ÅØ„Åì„Çå„ÇíÈñãÁ§∫„Åï„Çå„Åü„Åè„Å™„ÅÑ„Å®ËÄÉ„Åà„Çã„Åì„Å®„ÅØËá™ÁÑ∂„Å™„Åì„Å®„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅ„Åù„ÅÆ„Åì„Å®„Å∏„ÅÆÊúüÂæÖ„Å؉øùË≠∑„Åï„Çå„Çã„Åπ„Åç„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„Äç
最高裁判所 平成15年9月12日判決
原告を知る者の中に、本件記事を読んで、初めて原告の平成17年6月分の給料額や平成16年分の年収額を知り、あるいは初めて原告の支給明細書や源泉徴収票の実物の画像を目にした者も存在することが合理的に推認される。そして、特定の時点における原告の具体的な給与額、年収額や、給与明細等の資料の実物が一般人の感受性を基準にして公表を欲しない事柄に属することは明らかである。
東京地方裁判所 平成22年10月1日判決
として、プライバシーの侵害を認め、慰謝料50万円と弁護士費用5万円、合計55万円の支払いを命じました。
職業、診療所の住所・電話番号を公開した事例
ÁúºÁßëÂ媄Åå„ÄÅ„Éã„Éï„ÉÜ„Ç£„ÅÆÊé≤Á§∫Êùø„ÅßË´ñ‰∫â„Åó„Ŷ„ÅÑ„ÅüÁõ∏Êâã„Åã„Çâ„ÄÅËÅ∑Ê•≠„ÄÅË®∫ÁôÇÊâÄ„ÅƉΩèÊâĄɪÈõªË©±Áï™Âè∑„ÇíÊé≤Á§∫„Åï„Çå„Åü„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑü„ÇíʱDŽÇńŶˮ¥Ë®ü„ÇíÊèê˵∑„Åó„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
診療所の住所や電話番号は、地域別の職業別電話帳に広告掲載されており、純粋な私生活上の事柄であるとはいい難い面があったのですが、
裁判所は、
„ÄåÂÄã‰∫∫„ÅÆÊÉÖÂݱ„Çí‰∏ÄÂÆö„ÅÆÁõÆÁöÑ„ÅÆ„Åü„ÇÅ„Å´ÂÖ¨Èñã„Åó„ÅüËÄÖ„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅ„Åù„Çå„ÅåÂè≥ÁõÆÁöѧñ„Å´ÊÇ™ÁÅï„Çå„Å™„ÅÑ„Åü„ÇÅ„Å´„ÄÅÂè≥ÂÄã‰∫∫ÊÉÖÂݱ„ÇíÂè≥ÂÖ¨ÈñãÁõÆÁöÑ„Å®Èñ¢‰øÇ„ÅÆ„Å™„ÅÑÁØÑÂõ≤„Åæ„ÅßÁü•„Çâ„Çå„Åü„Åè„Å™„ÅфŮʨ≤„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅØʱ∫„Åó„Ŷ‰∏çÂêàÁêÜ„Å™„Åì„Å®„Åß„ÅØ„Å™„Åè„ÄÅ„Åù„Çå„ÇÇ„ÇÑ„ÅØ„Çä‰øù‰∏Ä„Åï„Çå„Çã„Åπ„ÅçÂà©Áõä„Åß„ÅÇ„Çã„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Åπ„Åç„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ„Åù„Åó„Ŷ„ÄÅ„Åì„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å´Ëá™Â∑±„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÊÉÖÂݱ„Çí„Ç≥„É≥„Éà„É≠„ɺ„É´„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅØ„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„ÅÆÊ®©Âà©„ÅÆÂü∫Êú¨ÁöѱûÊÄß„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅ„Åì„Çå„Å´Âê´„Åæ„Çå„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Å®Ëߣ„Åï„Çå„Çã„Äç
神戸地方裁判所 平成11年6月23日判決
„Å®„Åó„ÄÅÊÖ∞˨ùÊñô20‰∏áÂÜÜ„Äʼn∏çÁúÝÁóáÁ≠â„ÅÆÊ≤ªÁôÇË≤ª2380ÂÜÜ„ÄÅÂêàË®à20‰∏á2380ÂÜÜ„ÅÆÊîØÊâï„ÅÑ„ÇíË¢´Âëä„Å´ÂëΩ„Åò„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
配偶者らの氏名・住所、親族の氏名、親族の経営する会社の名称を公開した事例
ÂéüÂëä„Çâ„Åå„ÄÅ„ÄåÔºí„Å°„ÇÉ„Çì„Å≠„Çã„Äç„Å´„ÄÅÂéüÂëäÈÖçÂÅ∂ËÄÖ„Çâ„ÅÆÊ∞èÂêç„ɪ‰ΩèÊâÄ„ÄÅ˶™Êóè„ÅÆÊ∞èÂêç„ÄÅ˶™Êóè„ÅÆÁµåÂñ∂„Åô„Ç㉺öÁ§æ„ÅÆÂêçÁß∞„ÇíË®ò˺â„Åï„Çå„ÄÅÁ¨¨‰∏âËÄÖ„ÅåÈñ≤˶ßÂèØËÉΩ„Å™Áä∂Ê≥Å„Å´ÁΩÆ„ÅÑ„Åü„Å®‰∏ªÂºµ„Åó„Ŷ„ÄÅË¢´Âëä„Å´ÂØæ„Åó„ÄÅÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑü„ÇíʱDŽÇÅ„Åü‰∫ã‰æã„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
裁判所は、
„ÄåÂÄã‰∫∫„ÅÆÊ∞èÂêç„ÇщΩèÊâÄ„ÄʼnºöÁ§æÊâÄÂú®Âú∞„ÅÆÊÉÖÂݱ„ÅØ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„Å®„ÅÑ„Å܉ªñ‰∫∫„Å´Áü•„Çâ„Çå„Åü„Åè„Å™„Åщ∫ãÁÅÆÂØæ˱°Â§ñ„Åß„ÅÇ„Çã„Äç
とする被告の主張を退け、
Ôºà„ǶԺâ„ÄÄË¢´Âëä„ÅØ„ÄÅÂà•Á¥ô‰∫å„ÅÆÊõ∏„ÅçË溄ÅøÔºëÂèä„Å≥Ôºí„ÅÆ„Å®„Åä„Çä„ÄÅÂéüÂëä„Çâ„ÅƉΩèÊâÄ„ÄÅÂéüÂëä„Çâ„ÅÆ˶™Êóè„ÅÆÊ∞èÂêç„ÄÅ˶™Êóè„ÅÆÁµåÂñ∂„Åô„Ç㉺öÁ§æ„ÅÆÂêçÁß∞„ɪÊú¨ÊîØÂ∫ó„ÅÆÊâÄÂú®Âú∞„ɪÈõªË©±Áï™Âè∑„ÅØ„ÄÅÂπ≥Êàê‰∏ĉ∏ÉÂπ¥„Å´„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà‰∏ä„ÅßÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅÂ∫ÉÁØÑÂõ≤„Å´Âá∫Âõû„Å£„Ŷ„ÅÑ„ÅüÊÉÖÂݱ„Åß„ÅÇ„Çã„Åã„Çâ„ÄÅÊú¨‰ª∂Êõ∏„ÅçË溄Åø„Å´„Çà„ÇãÂéüÂëä„Çâ„ÅÆ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„ÅØ„Å™„ÅÑÊó®‰∏ªÂºµ„Åô„Çã„ÄÇ
„ÄÄ„Åó„Åã„Åó„Äʼn∏äË®ò‰∏ªÂºµ„ÇíË™ç„ÇÅ„Çã„Å´Ë∂≥„Çä„ÇãË®ºÊãÝ„ÅØ„Å™„ÅÑ„ÄljªÆ„Å´„ÄÅË¢´Âëä„Åå‰∏ªÂºµ„Åô„Çã„Å®„Åä„Çä„ÄÅ„Åã„Åã„ÇãÊÉÖÂݱ„Åå„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà‰∏ä„ÅßÂÖ¨Èñã„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„Å®„Åó„Ŷ„ÇÇ„ÄÅË¢´ÂëäËá™Ë∫´„ÄÅÂà•Á¥ô‰∫å„ÅÆÊõ∏„ÅçË溄ÅøÔºë„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØ„ÄńǶ„Çß„Éñ„ǵ„ǧ„ÉàËᙉΩì„ÅåÂâäÈô§„Åï„Çå„ÄÅÈñ≤˶߄Åô„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Å™„ÅÑ„Åì„Å®„ÇíËá™Ë™ç„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„Åã„Çâ„ÄÅÊú¨‰ª∂Êõ∏„ÅçË溄Åø„Å´„Çà„Å£„Ŷ„ÄÅÊñ∞„Åü„Å´ÂéüÂëä„Çâ„ÅÆ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„Çí‰æµÂÆ≥„Åô„Çã„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Åπ„Åç„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ
東京地方裁判所 平成21年1月21日判決
として、被告が新たに原告らのプライバシーを侵害したとして、被告に対し、原告とその妻にそれぞれ10万円と弁護士費用2万円、合計24万円の支払いを命じました。
ÂéüÂëä„ÇíË¢´ÁñëËÄÖ„Å®„Åô„ÇãÊçúÊüªÊÉÖÂݱ„Åå„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà„ÇíÈÄö„Åò„ŶʵÅÂá∫„Åó„Åü‰∫ã‰æã
Â∞ëÂπ¥„Åß„ÅÇ„ÇãÂéüÂëä„ÇíË¢´ÁñëËÄÖ„Å®„Åô„ÇãÈÅìË∑؉∫§ÈÄöÊ≥ïÈÅïÂèç‰∫㉪∂„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÄÅÊçúÊüªÈñ¢‰øÇÊñáÊõ∏„Çí‰ΩúÊàê„Åó„ÅüÂåóʵ∑ÈÅìË≠¶„ÅÆÂ∑°Êüª„ÅÆÁßÅÊúâ„Éë„ÇΩ„Ç≥„É≥„Åã„ÇâÊÉÖÂݱ„ÅåʵÅÂá∫„Åó„Åü‰∫ã‰æã„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
ÂéüÂëä„ÅƉΩèÊâÄ„ÄÅËÅ∑Ê•≠„ÄÅÊ∞èÂêç„ÄÅÁîüÂπ¥ÊúàÊó•„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÂÄã‰∫∫Ë≠òÂà•ÊÉÖÂݱ„Å®„Å®„ÇÇ„Å´„Äʼn∫㉪∂„ÅÆË©≥Á¥∞„Å™ÂÜÖÂÆπ„Åå„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà„ÇíÈÄö„Åò„Ŷ§ñÈÉ®„ŴʵÅÂá∫„Åó„Åü„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅÂéüÂëäÂ∞ëÂπ¥„ÅåÂåóʵ∑ÈÅì„Å´ÂØæ„Åó„ŶÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽÇíʱDŽÇÅ„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
捜査を担当した巡査がパソコンを使用して捜査関係文書を作成した際に、通達に反して作成途中の文書をパソコンのハードディスクに保存し、通達に反して同パソコンを自宅に持ち帰りました。
しかし、同パソコンがウイルスに汚染されていることに気づかず、インターネットに接続したため発生しました。
裁判所は、
Âêå‰∫ãÂÆü„ÅØÂ∞ëÂπ¥„ÅÆÈùûË°å‰∫ãÂÆü„Å®„Åó„ŶÂ∞ëÂπ¥„ÅÆÂÅ•ÂÖ®ËÇ≤Êàê„ÅÆ„Åü„ÇÅÁßòÂåø„Åï„Çå„Çã„Åπ„ÅçÊÉÖÂݱ„Åß„ÅÇ„Å£„Ŷ„ÄÅÔº°Â∑°Êüª„ÅƉ∏äË®òÂéüÂõÝË°åÁÇ∫„Å´„Çà„ÇäÊú¨‰ª∂ÊÉÖÂݱʵÅÂá∫„Å®„ÅÑ„ÅÜÊú¨Êù•„ÅÇ„Å£„Ŷ„ÅØ„Å™„Çâ„Å™„Åщ∫ãÊïÖ„ÅåÁô∫Áîü„Åó„ÄÅ„Åù„ÅÆÁµêÊûú„ÄÅÂéüÂëä„ÅÆÁßòÂåø„Åï„Çå„Çã„Åπ„ÅçÊÉÖÂݱ„Åå„Ƕ„ǧ„Éã„ɺ„ÇíÂà©ÁÅô„Çã‰∏çÁâπÂÆö§öÊï∞‰∫∫„ÅÆÈñ≤˶߄Ŵ‰æõ„Åï„Çå„Åü„Å∞„Åã„Çä„Åã„ÄÅ„Åù„ÅÆÊÉÖÂݱ„ÅØ„ÉĄǶ„É≥„É≠„ɺ„Éâ„Åï„Çå„ÄÅ„Éó„É™„É≥„Éà„Ç¢„Ƕ„Éà„Åï„Çå„Çã„Åì„Å®„Å´„Çà„Å£„Ŷ„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà„ÇíÂà©ÁÅó„Å™„Åщ∏ÄËਉ∫∫„Å´„Åæ„ÅßÂ∫É„ÅèÊö¥Èú≤„Åï„ÇåÂæó„ÇãÁä∂Ê≥Å„Å´Ëá≥„Å£„Åü„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅÂéüÂëä„ÅåÊú¨‰ª∂ÊÉÖÂݱʵÅÂá∫„Å´„Çà„Çä‰∫∫Êݺʮ©„Å´Âü∫„Å•„Åè„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺʮ©„Çí‰æµÂÆ≥„Åï„Çå„Åü„Åì„Å®„ÅØÊòé„Çâ„Åã„Å®„ÅÑ„ÅÜ„Åπ„Åç„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ
札幌地方裁判所 平成17年4月28日判決
„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅÈùûË°å‰∫ãÂÆü„Åß„ÅÇ„Å£„ŶÊØî˺ÉÁöÑ˪ΩÂæÆ„Å™‰∫ãÁäØ„Å´Èñ¢„Åô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÇíËÄÉÊÖÆ„Åó„ŧ„ŧ„ÄÅÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüÈáë„Å®„Åó„Ŷ40‰∏áÂÜÜ„ÅÆÊîØÊâï„ÅÑ„ÇíË¢´Âëä„Å´ÂëΩ„Åò„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
写真をX(旧Twitter)に無断転載した事例

最後に、写真をX(旧Twitter)上に無断転載した事例を紹介します。共同著作者がX(旧Twitter)に投稿した写真を無断で転載したことに対し、著作権侵害、プライバシー侵害、肖像権侵害として、著作権者である緊縛写真のモデル女性が裁判を提起した事例があります。
関連記事:承諾なしでの写真等の公表と著作権の関係
裁判所は、著作権(複製権及び公衆送信権)侵害、肖像権侵害を認めた上で、
本件写真は、「その内容に照らし、一般人の感受性を基準にして公開を欲しないものといえるから、このような写真を本人の許諾なく公開することはプライバシー権を侵害し得るものである」
東京地方裁判所 平成30年9月27日判決
とし、
Êú¨‰ª∂ÂÜôÁúü„ÅÆË¢´ÂÜô‰Ωì„ÅÆ•≥ÊÄß„ÅåÂéüÂëä„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÅØÊú™„ÅÝÁ§æ‰ºö„Å´Áü•„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Å™„Åã„Å£„Åü‰∫ãÂÆü„Å®„ÅÑ„Åà„Çã„Å®„Åì„Çç„ÄÅÊú¨‰ª∂Ë¢´ÂëäË°åÁÇ∫„Å´„Çà„Å£„ŶÂàù„ÇńŶˢ´ÂÜô‰Ωì„ÅÆ•≥ÊÄß„ÅåÂéüÂëä„Åß„ÅÇ„Çã„Å®„ÅÆÂêåÂÆö„ÅåÂèØËÉΩ„Å®„Å™„Çä„ÄÅÂêå‰∫ãÂÆü„ÅåÂÖ¨„Å´„Åï„Çå„Çã„Å´Ëá≥„Å£„Åü„ÇÇ„ÅƄŮ˙ç„ÇÅ„Çâ„Çå„Çã
東京地方裁判所 平成30年9月27日判決
„Å®„Åó„Ŷ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„ÅƉæµÂÆ≥„ÇíË™ç„ÇÅ„ÄÅÂêàË®à47‰∏á1500ÂÜÜ„ÅÆÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüÔºà„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺʮ©‰æµÂÆ≥„Å´ÂØæ„Åô„ÇãÊêçÂÆ≥30‰∏áÂÜÜ„ÇíÂê´„ÇÄÔºâ„ÅÆÊîØÊâï„ÅÑ„Çí„ÄÅË¢´Âëä„Å´ÂëΩ„Åò„Åæ„Åó„Åü„ÄÇ
„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„Å´ÈÅ≠„Å£„ÅüÂÝ¥Âêà„ÅÆÂØæÂøú

„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„Å´ÈÅ≠„Å£„ÅüÂÝ¥Âêà„ÄÅË¢´ÂÆ≥„ÅÆÊã°Â§ß„ÇíÈò≤„Åê„Åü„ÇÅ„Å´„ÅØËøÖÈÄü„Å™ÂØæÂøú„ÅåÈáç˶ńÅß„Åô„ÄÇÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´„ÅØ„ÄåÂâäÈô§‰æùÈݺ„Äç„Å®„ÄåÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽÄç„ÅÆ2„ŧ„ÅÆÂØæÂøú„ÅåÂèØËÉΩ„Åß„Åô„ÄÇ„Åì„Åì„Åß„ÅØ„ÄÅ„Åù„Çå„Åû„Çå„ÅÆÊâãÁ∂ö„Åç„ÅÆʵńÇå„Å®Ê≥®ÊÑèÁÇπ„Å´„ŧ„ÅфŶËߣ˙¨„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ
ÂâäÈô§‰æùÈݺ„Çí„Åô„Çã
„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà‰∏ä„Åß„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„Å´ÈÅ≠„Å£„ÅüÂÝ¥Âêà„ÄÅÊúÄÂàù„Å´Ë°å„ÅÜ„Åπ„Åç„Åì„Å®„ÅØË®ºÊãÝ„ÅƉøùÂÖ®„Åß„Åô„ÄÇÊäïÁ®øÂÜÖÂÆπ„ÅÆ„Çπ„ÇØ„É™„ɺ„É≥„Ç∑„Éß„ÉÉ„Éà„Çфǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà„Ç¢„ɺ„Ç´„ǧ„ÉñÔºàÈ≠öÊãì„ǵ„ǧ„ÉàÔºâ„Å™„Å©„ÇíÂà©ÁÅó„ŶˮòÈå≤„ÇíÊÆã„Åó„Ŷ„Åä„ÅèÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„Çå„ÅØÂæå„ÅÆÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽŴ„Åä„ÅфŶ„ÇÇÈáç˶ńřˮºÊãÝ„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
ÂâäÈô§‰æùÈݺ„ÅØ„ÄÅ„Åæ„ÅöÁô∫‰ø°ËÄÖÊú¨‰∫∫„Å´ÂØæ„Åó„Ŷ˰å„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Äå„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ„Åå‰æµÂÆ≥„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÅÆ„Åß„ÄÅÂâäÈô§„Åó„Ŷ„Åè„ÅÝ„Åï„ÅÑ„Äç„Å®ÂÖ∑‰ΩìÁöÑ„Å´‰æùÈݺ„Åó„Å™„Åë„Çå„Å∞„Å™„Çä„Åæ„Åõ„Çì„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅÂåøÂêçÊé≤Á§∫Êùø„Å™„Å©Áô∫‰ø°ËÄÖÊú¨‰∫∫„ÅåÁâπÂÆö„Åß„Åç„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà„ÇÑ„ÄÅÂâäÈô§‰æùÈݺ„Å´Âøú„Åò„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà„ÅØ„Äńǵ„ǧ„Éà„ÅÆÈÅãÂñ∂ËÄÖ„Å´ÂâäÈô§‰æùÈݺ„Åô„ÇãÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„ǵ„ǧ„ÉàÈÅãÂñ∂ËÄÖ„Å∏„ÅÆÂâäÈô§‰æùÈݺ„ÅØ„ÄÅÂêфǵ„ǧ„Éà„ÅÆ„ÅäÂïè„ÅÑÂêà„Çè„Åõ„Éï„Ç©„ɺ„ÉÝ„Åã„ÇâË°å„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÁÆ°ÁêÜËÄÖ„Å؉æùÈݺ„Åï„Çå„ÅüÂÜÖÂÆπ„ÇíÁ¢∫Ë™ç„Åó„Åü‰∏ä„ÅßÊäïÁ®øËÄÖ„Å´ÂâäÈô§„ÇíʱDŽÇÅ„Åæ„Åô„Åå„ÄÅÊäïÁ®øËÄÖ„ÅåÂâäÈô§„Å´Âøú„Åò„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà„ÅØ„ÄÅÁÆ°ÁêÜËÄÖ„ÅÆÂà§Êñ≠„ÅßÊõ∏„ÅçË溄Åø„ÅåÂâäÈô§„Åï„Çå„ÇãÂÝ¥Âêà„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Å™„Åä„ÄÅ„Éó„É≠„Éê„ǧ„ÉÄË≤¨‰ªªÂà∂ÈôêÊ≥ï„Å´„Çà„Çä„ÄÅ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„ÇíÂèó„Åë„ÅüË¢´ÂÆ≥ËÄÖ„Å´„ÅØ„ÄåÈÄʼnø°Èò≤Ê≠¢Êé™ÁΩÆË´ãʱÇÊ®©„Äç„ÅåË™ç„ÇÅ„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ„Åü„ÅÝ„Åó„ÄÅË°®Áèæ„ÅÆËá™Ář„Å©„ÇíÁêÜÁŴÂâäÈô§„Å´Âøú„Åò„Ŷ„ÇÇ„Çâ„Åà„Å™„ÅÑÂÝ¥Âêà„ÅØ„ÄÅË£ÅÂà§ÊâÄ„Å´ÂâäÈô§„ÅƉªÆÂá¶ÂàÜ„ÇíÁî≥„ÅóÁ´ã„Ŷ„Çã„Å™„Å©„ÅÆÊ≥ïÁöÑÊâãÁ∂ö„Åç„ÅåÂøÖ˶ńÅß„Åô„ÄÇÊ≥ïÁöÑÊâãÁ∂ö„Åç„ÅÆË©≥Á¥∞„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅغÅË≠∑£´„Å´„ÅîÁõ∏Ë´á„Åè„ÅÝ„Åï„ÅÑ„ÄÇ
関連記事:誹謗中傷対策において重要な「削除仮処分」とは
ÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽÇí„Åô„Çã
ÂâäÈô§‰æùÈݺ„Å®‰∏¶Ë°å„Åó„Ŷ„ÄÅ„Åæ„Åü„ÅØÂâäÈô§ÂÆå‰∫ÜÂæå„Å´ÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽÇíË°å„ÅÜ„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Åæ„Åô„ÄÇÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽÇíË°å„ÅÜ„Åü„ÇÅ„Å´„ÅØ„ÄÅ„Åæ„ÅöÊäïÁ®øËÄÖ„ÅÆÁâπÂÆö„ÅåÂøÖ˶ńÅß„Åô„ÄÇ„Åù„ÅÆ„Åü„ÇÅ„Å´Áô∫‰ø°ËÄÖÊÉÖÂݱÈñãÁ§∫Ë´ãʱDŽÇÑÁô∫‰ø°ËÄÖÊÉÖÂݱÈñãÁ§∫ÂëΩ‰ª§Áî≥Á´ã„Ŷ„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÊâãÁ∂ö„Åç„ÇíË°å„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
Èñ¢Èģˮò‰∫ãÔºö‰ª§Âíå4Âπ¥10Êúà1Êó•ÈñãÂßã„ÅÆ„ÄåÁô∫‰ø°ËÄÖÊÉÖÂݱÈñãÁ§∫ÂëΩ‰ª§‰∫㉪∂„Äç„ÇíËߣ˙¨ ÊäïÁ®øËÄÖÁâπÂÆö„ÅåËøÖÈÄüÂåñ„Åï„Çå„Çã
ÊäïÁ®øËÄÖ„ÅåÁâπÂÆö„Åß„Åç„ÅüÂÝ¥Âêà„ÄÅ„Åæ„Åö„ÅØË©±„ÅóÂêà„ÅÑ„Å´„Çà„ÇãËߣʱ∫„ÇíË©¶„Åø„Åæ„Åô„ÄÇ„Åì„ÅÆÈöõ„ÄÅÂÜçÁô∫Èò≤Ê≠¢„ÅÆ„Åü„ÇÅ„Å´Ë™ìÁ¥ÑÊõ∏„ÇíÂèñ„Ç䉪ò„Åë„ÄÅÈÅïÁ¥ÑÈáëÊù°ÈÝÖ„ÇíË®≠ÂÆö„Åô„Çã„ÅÆ„ÇÇÂäπÊûúÁöÑ„Åß„Åô„ÄÇË©±„ÅóÂêà„ÅÑ„Å´„Çà„ÇãËߣʱ∫„ÅåÂõ∞Èõ£„Å™ÂÝ¥Âêà„ÅØ„ÄÅË®¥Ë®ü„Å´„Çà„ÇãËߣʱ∫„ÇíÂõ≥„Çã„Åì„Å®„Å´„Å™„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„Å´„Çà„ÇãÊÖ∞˨ùÊñô„ÅÆÁõ∏ÂÝ¥„ÅØ„Äʼn∏ÄËà¨ÁöÑ„Å´10‰∏áÂÜÜ„Åã„Çâ50‰∏áÂÜÜÁ®ãÂ∫¶„Åß„Åô„ÄÇ„Åü„ÅÝ„Åó„ÄʼnæµÂÆ≥„ÅÆÊÖãÊßò„ÅåÁâπ„Å´ÊÇ™Ë≥™„Å™ÂÝ¥Âêà„Å´„ÅØ„ÄÅ100‰∏áÂÜ܉ª•‰∏ä„ÅÆÊÖ∞˨ùÊñô„ÅåË™ç„ÇÅ„Çâ„Çå„ÇãÂÝ¥Âêà„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åì„Çå„Çâ„ÅÆÊâãÁ∂ö„Åç„ÅØÂÄã‰∫∫„ÅßË°å„ÅÜ„Åì„Å®„ÅåÈõ£„Åó„Åè„ÄÅÁâπ„Å´„ǵ„ǧ„ÉàÁÆ°ÁêÜËÄÖ„Å®„ÅÆ„ÇÑ„ÇäÂèñ„Çä„ÇÑÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽÅØÂ∞ÇÈñÄÁöÑ„Å™Áü•Ë≠ò„ÅåÂøÖ˶ńÅß„Åô„ÄÇ„Åæ„Åü„ÄÅÂÄã‰∫∫„Åã„Çâ„ÅÆÁî≥„ÅóÂÖ•„Çå„ÅØÁѰ˶ñ„Åï„Çå„Ŷ„ÇÇ„ÄźÅË≠∑£´„Åã„Çâ„ÅÆÈÄ£Áµ°„Å´„ÅØËøÖÈÄü„Å´ÂØæÂøú„Åô„Çã„DZ„ɺ„Çπ„Çǧö„ÅÑ„Åü„ÇÅ„ÄÅÁµåÈ®ì˱äÂØå„řºÅË≠∑£´„Å´Áõ∏Ë´á„Åô„Çã„ÅÆ„Çí„Åä„Åô„Åô„ÇÅ„Åó„Åæ„Åô„ÄÇ
まとめ:プライバシー侵害への対応は迅速な削除と専門家への相談が重要
„Éç„ÉÉ„Éà„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥‰∫ãÊ°à„Åß„ÅØ„ÄÅË¢´ÂÆ≥„ÅÆÊã°ÊÇíÈò≤„Åê„Åü„ÇÅ„ÅÆËøÖÈÄü„Å™ÂØæÂøú„Åå‰Ωï„Çà„ÇäÈáç˶ńÅß„Åô„ÄÇ„Åæ„ÅöÊõ∏„ÅçË溄Åø„ÅÆË®ºÊãÝ„Çí‰øùÂÖ®„Åó„Åü‰∏ä„Åß„ÄÅÁô∫‰ø°ËÄÖÊú¨‰∫∫„Çфǵ„ǧ„ÉàÈÅãÂñ∂ËÄÖ„Å∏„ÅÆÂâäÈô§‰æùÈݺ„ÇíË°å„ÅÑ„ÄÅ„Éó„É≠„Éê„ǧ„ÉÄË≤¨‰ªªÂà∂ÈôêÊ≥ï„Å´Âü∫„Å•„Åè„ÄåÈÄʼnø°Èò≤Ê≠¢Êé™ÁΩÆË´ãʱÇÊ®©„Äç„ÇíË°å‰Ωø„Åß„Åç„Åæ„Åô„ÄÇ
ÂâäÈô§Ë´ãʱDŽى∏¶Ë°å„Åó„Ŷ„ÄÅ„Åæ„Åü„ÅØÂâäÈô§Âæå„Å´ÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽÇíʧúË®é„Åô„Çã„ÅÆ„ÇÇÂèØËÉΩ„Åß„Åô„ÄÇ„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺ‰æµÂÆ≥„Å´„Çà„ÇãÊÖ∞˨ùÊñô„Å؉∏ÄËà¨ÁöÑ„Å´10‰∏áÂÜÜ„Åã„Çâ50‰∏áÂÜÜÁ®ãÂ∫¶„Åß„ÄÅÊÇ™Ë≥™„Å™ÂÝ¥Âêà„ÅØ100‰∏áÂÜ܉ª•‰∏ä„Å´„Å™„ÇãÂÝ¥Âêà„ÇÇ„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇÂÆüÈöõ„ÅÆÂ৉æã„Åß„ÇÇ„ÄÅÁóÖÊ≠¥„ÅÆÂÖ¨Èñã„Åß132‰∏áÂÜÜ„ÄÅÁµ¶‰∏éÊòéÁ¥∞„ÅÆÂÖ¨Èñã„Åß55‰∏áÂÜÜ„Å™„Å©„Äʼn∫ãÊ°à„ÅÆÂÜÖÂÆπ„Å´Âøú„Åò„ŶË≥ÝÂÑüÈ°ç„ÅåË™çÂÆö„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
„Åü„ÅÝ„Åó„ÄÅ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆÊâãÁ∂ö„Åç„Å´„ÅØÂ∞ÇÈñÄÁöÑ„Å™Ê≥ïÁöÑÁü•Ë≠ò„ÅåÂøÖ˶ńÅß„Åô„ÄÇÂÄã‰∫∫„Åß„ÅÆÂØæÂøú„Å´„ÅØÈôêÁïå„Åå„ÅÇ„Çä„Åæ„Åô„ÄÇÁâπ„Å´ÊäïÁ®øËÄÖ„ÅÆÁâπÂÆö„ÇÑÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱDŽÅØ˧áÈõë„Å™ÊâãÁ∂ö„Åç„Çí˶ńÅô„Çã„Åü„ÇÅ„ÄÅÊó©Êúü„ÅÆÊƵÈöé„ÅߺÅË≠∑£´„Å´Áõ∏Ë´á„Åô„Çã„Å®„ÄÅ„Çà„ÇäÁ¢∫ÂÆü„řʮ©Â੉øùË≠∑„ÇíÂõ≥„Çå„Åæ„Åô„ÄÇ
関連記事:誹謗中傷対策において重要な「削除仮処分」とは
Èñ¢Èģˮò‰∫ãÔºöÂêçË™âÊØÄÊêç„ÅÆÊÖ∞˨ùÊñôË´ãʱDŽÅÆÁõ∏ÂÝ¥„Å®„ÅØÔºü
当事務所による対策のご案内
„É¢„Éé„É™„ÇπÊ≥ïÂæã‰∫ãÂãôÊâÄ„ÅØ„ÄÅIT„ÄÅÁâπ„Å´„ǧ„É≥„Çø„ɺ„Éç„ÉÉ„Éà„Å®Ê≥ïÂæã„ÅƉ∏°Èù¢„Åß˱äÂØå„Å™ÁµåÈ®ì„ÇíÊúâ„Åô„ÇãÊ≥ïÂæã‰∫ãÂãôÊâÄ„Åß„Åô„ÄÇËøëÂπ¥„ÄÅ„Éç„ÉÉ„Éà‰∏ä„Å´Êã°ÊÅï„Çå„ÅüÈ¢®Ë©ïË¢´ÂÆ≥„ÇÑË™π˨ó‰∏≠ÂÇ∑„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÊÉÖÂݱ„ÅØ„Äå„Éá„Ç∏„Çø„É´„Çø„Éà„Ç•„ɺ„Äç„Å®„Åó„ŶÊ∑±Â઄řˢ´ÂÆ≥„Çí„ÇÇ„Åü„Çâ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇÂΩì‰∫ãÂãôÊâÄ„Åß„ÅØ„Äå„Éá„Ç∏„Çø„É´„Çø„Éà„Ç•„ɺ„ÄçÂØæÁ≠ñ„ÇíË°å„ÅÜ„ÇΩ„É™„É•„ɺ„Ç∑„Éß„É≥Êèê‰æõ„ÇíË°å„Å£„Ŷ„Åä„Çä„Åæ„Åô„Älj∏ãË®òË®ò‰∫ã„Å´„Ŷ˩≥Á¥∞„ÇíË®ò˺â„Åó„Ŷ„Åä„Çä„Åæ„Åô„ÄÇ
モノリス法律事務所の取扱分野:デジタルタトゥー
カテゴリー: 風評被害対策
„Çø„Ç∞: X (Twitter)„Éó„É©„ǧ„Éê„Ç∑„ɺÊêçÂÆ≥Ë≥ÝÂÑüË´ãʱÇÈ¢®Ë©ïË¢´ÂÆ≥ÂØæÁ≠ñÔºöÂÜÖÂÆπÂà•