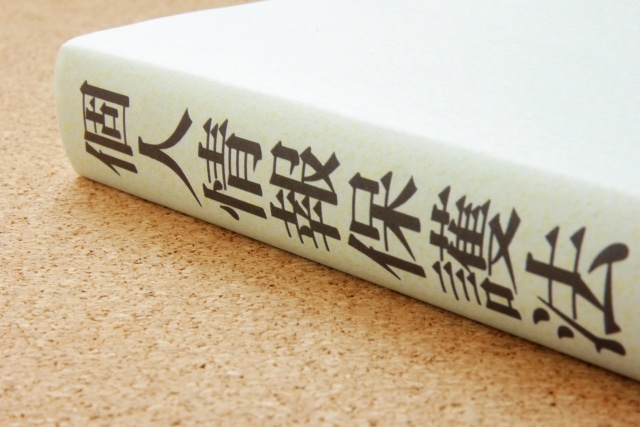台湾の薬事法による医薬品関連規制

台湾の医薬品関連市場は、日本企業にとって魅力的なビジネス機会を提供しています。しかし、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」)とは異なる独自の法体系、特に厳格な販売チャネル規制が存在しており、これを深く理解しないまま事業を進めると、意図しない法的リスクに直面する可能性があります。
本記事では、台湾の「薬事法」を軸に、医薬品の分類、オンライン販売の可否、そして日本にはない伝統漢方薬の法的位置付けといった重要な論点について、日本法との比較を交えながら詳細に解説します。この解説を通して、台湾市場における法的リスクを回避し、安全かつ円滑な事業展開に向けた確かな指針を得ていただけることでしょう。
なお、台湾の包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
台湾薬事法の全体像と規制当局
台湾における医薬品および医療機器の規制は、主要な法律である「薬事法」(Pharmaceutical Affairs Law, PAL)によって包括的に定められています。日本の薬機法と同様に、その核心的な目的は医薬品の製造、輸入、および販売を管理し、製品の安全性、有効性、そして品質を確保することにあると言えるでしょう。この法律は1970年8月17日に公布されて以来、幾度にもわたる改正が重ねられており、その変遷は、台湾の法制度が常に時代の要請に合わせて進化してきたことを示しています。
台湾の医薬品関連規制を主管する中央官庁は、衛生福利部食品薬物管理署(以下「TFDA」)です。TFDAは、日本の厚生労働省や独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に相当する役割を担っており、医薬品の承認プロセス、優良製造規範(GMP)への適合性確認、市場監視などを包括的に担当しています。
台湾の薬事法は、その改正の歴史から、医薬品の規制において一貫して公衆衛生と国民の安全を最優先する姿勢を強く示しています。たとえば、医薬品や医療機器の販売には、薬事法第27条に基づいて衛生主務機関からの許可を得ることが厳格に義務付けられており、無許可での販売に対しては、薬事法第92条に基づき、高額な罰金が科されることが明記されています。違法なオンライン販売に対する罰則が具体的に定められていることは、利便性重視で規制緩和が進む国々がある一方で、台湾が独自のバランスを保ち、国民の健康を守ることを最重要視していることを物語っていると言えるでしょう。
台湾医薬品の分類とオンライン販売規制

台湾の医薬品市場への参入を検討する日本企業にとって、医薬品の分類とオンライン販売に関する規制は、日本の薬機法との決定的な違いを理解すべき最も重要な論点です。この違いは、事業モデルや流通戦略を根本から見直す必要性を示唆します。
台湾における医薬品の分類
台湾の薬事法では、医薬品は主にその使用方法とリスクの程度に応じて、以下の3つのカテゴリーに分類されています。
- 処方薬(處方藥):医師の診断と処方箋に基づいてのみ、薬事専門家(薬剤師や薬事生)が調剤・供給できる医薬品です。日本の「医療用医薬品」に相当し、抗生物質など薬効が強く、リスクが高いと判断される薬がこれに該当します。
- 指示薬(指示藥):医師や薬事専門家の指導の下で、消費者が薬局で購入・使用する医薬品です。市販の総合感冒薬などが含まれ、処方薬に比べて薬効が穏やかでリスクが低いとされています。
- 成薬(成藥):医師や薬事専門家の指示なしに、消費者が自ら判断して購入・使用できる医薬品です。このカテゴリーはさらに薬事法で「甲類成薬」と「乙類成薬」に細分化されます。甲類成薬は薬局や小売薬商でのみ購入可能ですが、乙類成薬は百貨店、雑貨店などの一般通路でも販売が認められています。
日本の分類との比較とオンライン販売規制
日本の薬機法では、医薬品は「医療用医薬品」と「一般用医薬品」に大別されます。日本の「一般用医薬品」は、そのリスクに応じて「要指導医薬品」「第一類」「第二類」「第三類」に細分化されています。台湾の分類は、日本の「医療用医薬品」が「処方薬」に、そして日本の「一般用医薬品」が「指示薬」と「成薬」に相当すると解釈できるでしょう。
この分類において最も重要な相違点は、オンライン販売の可否にあります。日本においては、要指導医薬品および第一類医薬品を除き、第二類および第三類医薬品の通信販売が認められています。これにより、多くの市販のかぜ薬や解熱鎮痛剤、胃腸薬といった比較的リスクが高いとされる医薬品でも、オンラインで購入が可能です。
一方、台湾の薬事法は、流通チャネルに対する管理を極めて厳格にしています。台湾では、「乙類成薬」のみがオンラインでの小売販売を許可されており、それ以外の医薬品は通信販売が原則として禁止されています。つまり、日本ではオンライン販売が可能な多くの第二類・第三類医薬品(例:総合感冒薬)が、台湾ではオンラインで販売できないということです。
この線上販売規制の異同は、両国における法哲学の違いを示していると言えるでしょう。台湾の規制は、医薬品の流通チャネルそのものに対する厳格な管理を徹底することで公衆衛生を担保しようとする姿勢が強いことが分かります。一方で日本は、リスクの程度に応じて専門家による情報提供の義務を課すなど、対面販売の原則を維持しつつも、消費者利便性を考慮して流通経路に一定の柔軟性を持たせていることが分かります。
この違いは、越境EC(電子商取引)を検討している日本企業にとって、予期せぬ法的リスクの温床となり得ます。なぜなら、日本で合法的にオンライン販売している医薬品を、台湾の消費者向けに販売した場合、それは台湾の法律上は違法販売とみなされ、最高100万台湾ドル(約470万円)に及ぶ高額な罰金が科される可能性があるからです。台湾当局は、無許可での医薬品や医療機器のオンライン販売に対する監視と罰則の適用を強化していることからも、このリスクは決して軽視できるものではありません。
台湾の「医薬品的性質」の判断とビジネス上のリスク
台湾市場で健康食品や化粧品を扱う日本企業は、日本の制度には見られない、製品の「医薬品的性質」に関する台湾独自の厳格な規制に特に注意を払う必要があります。
台湾における「医薬品的性質」の定義と広告規制
台湾の薬事法では、製品が「診断、治療、軽減、または予防」の目的で使用される場合、その製品は医薬品として分類されます。さらに、台湾の当局は、食品の広告において「医療効能」を標榜することを厳しく禁じており、その認定基準を具体的に定めています。たとえば、「便秘を防止する」「肝臓の毒を抜く」「血管の弾性を増す」といった表現は、「医療効能」と判断され、食品衛生管理法に違反する可能性があります。これは、製品そのものの成分だけでなく、その表示や広告文言が法的リスクを生むことを意味しています。
また、ハイドロキノンといった特定の成分が、一定濃度を超えると化粧品から医薬品に分類されるという点も、当局の厳格な判断基準を示しています。
日本の制度との比較と越境ECにおけるリスク
日本には、2015年から導入された「機能性表示食品」制度があります。この制度の下では、科学的根拠に基づき、事業者の責任において「特定の保健の目的が期待できる」旨を表示することが合法的に認められています。
この違いは、台湾進出を検討する日本企業に重大なリスクをもたらす可能性があります。日本で「機能性表示食品」として合法的に販売されている製品が、台湾に輸出され、同様の広告文言を用いた場合、台湾では意図せず違法な「無許可医薬品」と見なされる可能性があるからです。したがって、台湾市場への進出を検討する企業は、製品の成分や製法だけでなく、マーケティング資料やウェブサイトの記載内容に至るまで、台湾の法規制に準拠しているか、徹底的なリーガルレビューを実施する必要があるということが言えるでしょう。
さらに、越境ECにおいては、錠剤やカプセルの形態をした食品に対して、台湾の税関が医薬品と同様の厳しい輸入規制を課しているという事実にも留意すべきです。これは、外見上医薬品と区別しにくい製品の不正な流通を未然に防ぐための措置であり、「医薬品的性質を持つ可能性のある食品」に対する当局の警戒心の高さを反映しています。
台湾の伝統漢方薬に与えられた法的地位

日本の法律には見られない、台湾の薬事法におけるユニークな規定の一つに、伝統漢方薬に与えられた独立した法的地位があります。
「固有処方製剤」という独自の分類
台湾の薬事法第10条は、「固有処方製剤」を「中央衛生主務機関が選定、公告した医療効能を有する伝統漢方薬の処方により調整(剤)する製剤」と定義しています。この規定は、伝統漢方薬が現代医薬品とは異なる独自の法的カテゴリーとして位置付けられ、独自の規制体系を与えられていることを示しています。これは、伝統医療の継承と発展を法的に支援する台湾の姿勢から生まれた、独自のアプローチと言えるでしょう。
日本における漢方薬の扱いとの比較
日本では、漢方薬の多くは、薬事法において医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」として扱われます。一部は「一般用医薬品」として薬局で販売されていますが、台湾のように「固有処方製剤」として現代医薬品とは区別された独立した法的カテゴリーを設ける規定は存在しません。
この違いから、台湾の薬事法は、単に医薬品の安全性を追求するだけでなく、伝統的な知恵である漢方薬を、科学的根拠に基づく現代医療システムの中に組み込むという、両者の融合を試みていることが分かります。この法制度は、台湾が伝統文化を公衆衛生の一部として位置付けるという、文化的・社会的な背景から生まれたものです。これは、伝統医療関連の製品を扱う日本企業にとって、台湾市場での新たなビジネス機会を示唆している可能性があります。
まとめ
台湾の医薬品関連法制度の厳格性と独自性を踏まえると、日本企業が安全に台湾市場へ参入するためには、以下の実践的対応策を講じることが不可欠です。
まず、台湾で医薬品や医療機器を販売するには、原則として現地の「薬商(医療機器取扱業)」許可が必要です。この許可は、外国企業が台湾に設立した現地法人を通じて、または起用した現地企業を代理人として取得することになります。日本の薬機法における「製造販売業者(MAH)」や「選任製造販売業者(DMAH)」の制度と同様に、台湾での事業展開には、現地の法律に精通した責任主体を確立することが不可欠であると言えるでしょう。
日本国内の大手製薬メーカー(武田、アステラス、塩野義など)が、すでに台湾に子会社や正規代理店を設立し、現地の医薬品市場に深く関与していることは、現地との密接な連携が台湾市場での成功に不可欠であることを示しています。また、台湾の製薬会社(Lotus Pharmaceutical)と日本の製薬会社(Fuji Pharma)が、共同開発したジェネリック医薬品を日本市場で申請・販売するなど、双方向の連携も活発化しています。さらに、日本の化学メーカーが台湾のバイオテクノロジー企業との協業を模索している動向は、今後の産業構造の変化を予見させます。これらの事例から、台湾市場への参入は、単に製品を輸出すればよいという段階を超え、「現地に根ざした事業展開」が成功の鍵を握るということが言えるでしょう。法的要件を満たすためだけでなく、現地市場の特性、流通網、消費者の嗜好を深く理解するためにも、信頼できる現地パートナーとの連携が極めて重要となります。
台湾での円滑なビジネス展開のためには、現地の法令を深く理解し、適切なリーガル・デューデリジェンスを実施することが不可欠であると言えるでしょう。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務