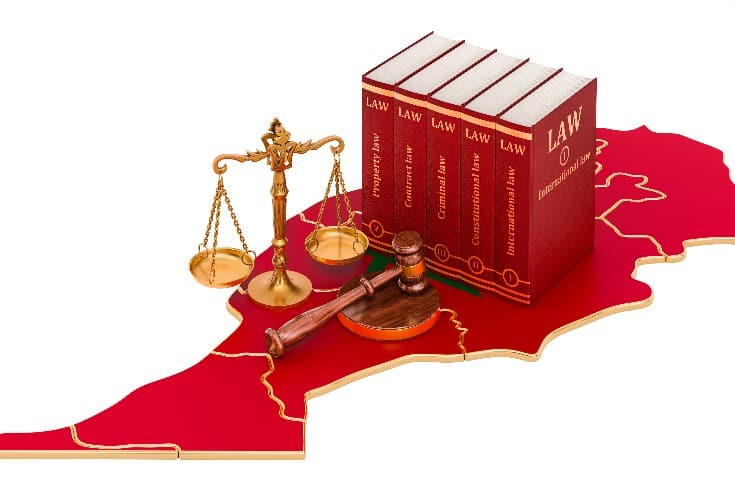ŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Õģ▒ÕÆīÕøĮŃü«µ©®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃü½ŃéłŃéŗµ£ēÕÉŹÕłżõŠŗŃĆīŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║ŃĆŹŃü«Ķ¦ŻĶ¬¼

ŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü»ŃĆüÕģ¼µ│ĢŃü©ń¦üµ│ĢŃü©ŃüäŃüåõ║īŃüżŃü«ńĢ░Ńü¬Ńéŗµ│ĢõĮōń│╗Ńü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”ŃĆüĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü©ÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆŃüīŃüØŃéīŃü×Ńéīńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü”ń«ĪĶĮ䵩®ŃéÆĶĪīõĮ┐ŃüÖŃéŗŃĆüńŗ¼ńē╣Ńü¬õ║īÕģāńÜäÕÅĖµ│ĢÕłČÕ║”ŃéƵōüŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüżŃüŠŃéŖŃĆüĶĪīµö┐Ńü©Ńü«õ║ēŃüäŃéÆÕć”ńÉåŃüÖŃéŗĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü©ŃĆüń¦üõ║║ķ¢ōŃü«õ║ēŃüäŃéÆÕć”ńÉåŃüÖŃéŗÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆŃüīŃĆüµśÄńó║Ńü½ŃüØŃü«ÕĮ╣Õē▓ŃéÆÕłåµŗģŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣ķØ®ÕæĮÕŠīŃü«1790Õ╣┤8µ£ł16µŚźŃüŖŃéłŃü│24µŚźŃü«µ│ĢÕŠŗŃü½ŃéłŃüŻŃü”ŃüØŃü«ÕĤÕ×ŗŃüīńó║ń½ŗŃüĢŃéīŃü¤µŁ┤ÕÅ▓ŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ│ĢõĮōń│╗Ńü«µĀ╣Õ║ĢŃü½Ńü»ŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«ĶĪīńé║ŃéÆń¦üõ║║Ńü©ÕÉīÕłŚŃü½µē▒ŃüäŃĆüÕÉīŃüśµ│ĢÕĤÕēćŃü¦ĶŻüŃüÅŃü╣ŃüŹŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüåµĆصā│ŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéĶĪīµö┐µ®¤ķ¢óŃü«ĶĪīÕŗĢŃü»ŃĆüÕģ¼Õģ▒Ńü«Õł®ńøŖŃü©ŃüäŃüåńē╣µ«ŖŃü¬ńø«ńÜäŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ĶĪīŃéÅŃéīŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃéīŃéåŃüłŃü½µ░æµ│ĢŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗńē╣ÕłźŃü¬µ│ĢńÉåŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ķ”ÅÕŠŗŃüĢŃéīŃéŗŃü╣ŃüŹŃüĀŃü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃü¤ŃüŗŃéēŃü¦ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«õ║īÕģāńÜäŃü¬ÕÅĖµ│ĢÕłČÕ║”ŃüīÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗŃéåŃüłŃü½ŃĆüŃüéŃéŗńē╣Õ«ÜŃü«ń┤øõ║ēŃüīÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäŃü½Õ▒×ŃüÖŃéŗŃü«ŃüŗŃĆüŃüØŃéīŃü©ŃééĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäŃü½Õ▒×ŃüÖŃéŗŃü«ŃüŗŃéÆÕĘĪŃéŗŃĆīµ©®ķÖÉŃü«ĶĪØń¬ü’╝łconflit de comp├®tence’╝ēŃĆŹŃüīńö¤ŃüśŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ÕĢÅķĪīŃéÆĶ¦Żµ▒║ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ŃĆü1872Õ╣┤5µ£ł24µŚźŃü«µ│ĢÕŠŗŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüµ©®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗Ę’╝łTribunal des conflits’╝ēŃüīĶ©Łń½ŗŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«µ│ĢÕ╗ĘŃü»ŃĆüõ║īŃüżŃü«µ│Ģń¦®Õ║ÅŃü«ķ¢ōŃü«Ķ¬┐Õü£ĶĆģŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüŃüØŃü«ń«ĪĶĮ䵩®Ńü«ÕóāńĢīńĘÜŃéƵśÄńó║Ńü½Õ«ÜŃéüŃéŗÕĮ╣Õē▓ŃéƵŗģŃüåŃüōŃü©Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
µ©®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃü»ŃĆüŃüØŃü«õĖŁń½ŗµĆ¦ŃéÆńó║õ┐ØŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüÕÅĖµ│Ģń¦®Õ║ÅŃü«µ£Ćķ½śµ®¤ķ¢óŃü¦ŃüéŃéŗńĀ┤µ»ĆķÖó’╝łCour de cassation’╝ēŃü«ŃāĪŃā│ŃāÉŃā╝4ÕÉŹŃü©ŃĆüĶĪīµö┐ń¦®Õ║ÅŃü«µ£Ćķ½śµ®¤ķ¢óŃü¦ŃüéŃéŗÕøĮÕŗÖķÖó’╝łConseil d’├ētat’╝ēŃü«ŃāĪŃā│ŃāÉŃā╝4ÕÉŹŃüŗŃéēŃü¬ŃéŗŃĆüõĖĪĶĆģÕ»ŠńŁēŃü¬µ¦ŗµłÉŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ķ©ŁĶ©łŃü»ŃĆüõĖƵ¢╣Ńü«µ│Ģń¦®Õ║ÅŃüīõ╗¢µ¢╣ŃéƵö»ķģŹŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆķś▓ŃüÄŃĆüõĖĪµ│ĢõĮōń│╗ŃüīÕģ¼Õ╣│Ńü¬Õ»ŠĶ®▒Ńü©õ║żµĖēŃéÆķĆÜŃüśŃü”ŃĆüÕģ▒ÕŁśŃü©ńÖ║Õ▒ĢŃéÆķüéŃüÆŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ķćŹĶ”üŃü¬ŃāĪŃé½ŃāŗŃé║ŃāĀŃü©ŃüŚŃü”µ®¤ĶāĮŃüŚŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ÕŗĢńÜäŃü¬ŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣ŃéÆĶ▒ĪÕŠ┤ŃüÖŃéŗŃĆüµ£ĆŃé鵣┤ÕÅ▓ńÜäŃü½ķćŹĶ”üŃü¬Õłżµ▒║Ńü«õĖĆŃüżŃüīŃĆü1873Õ╣┤2µ£ł8µŚźŃü½õĖŗŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║ŃĆŹŃü¦ŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«õ║īÕģāńÜäÕÅĖµ│ĢÕłČÕ║”Ńü«µĀ╣Õ╣╣Ńü½ŃüéŃéŗµ©®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃü«ÕĮ╣Õē▓Ńü©ŃĆüŃüØŃü«µŁ┤ÕÅ▓ŃéƵ▒║Õ«ÜŃüźŃüæŃü¤Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü«ńĄīńĘ»ŃĆüńó║ń½ŗŃüĢŃéīŃü¤µ│ĢÕĤÕēćŃĆüŃüØŃüŚŃü”ńÅŠõ╗ŻŃüĖŃü«ÕĮ▒ķ¤┐Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüÕģĘõĮōńÜäŃü½Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
Ńü¬ŃüŖŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«Õīģµŗ¼ńÜäŃü¬µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«µ”éĶ”üŃü»õĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”ŃüŠŃü©ŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
ŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣ŃĆīŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║ŃĆŹŃü«µ”éĶ”üŃü©õ║ēńé╣
õ║ŗõ╗ČŃü«õ║ŗÕ«¤ķ¢óõ┐é
Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü«µĀĖÕ┐āŃü½ŃüéŃéŗõ║ŗõ╗ČŃü»ŃĆü1871Õ╣┤11µ£ł3µŚźŃü½ŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«Ńā£Ńā½ŃāēŃā╝Ńü¦ńÖ║ńö¤ŃüŚŃü¤õ║ŗµĢģŃü¦ŃüÖŃĆéÕĮōµÖé5µŁ│Ńü«ŃéóŃāŗŃé©Ńé╣Ńā╗Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│ŃüīŃĆüŃé┐ŃāÉŃé│ĶŻĮķĆĀÕĘźÕĀ┤’╝łManufacture des tabacs de Bordeaux’╝ēŃü«ÕŠōµźŁÕōĪŃüīµōŹŃéŗÕÅ░Ķ╗Ŗ’╝łwagonnet’╝ēŃü½ĶĮóŃüŗŃéīŃü”Ķ▓ĀÕéĘŃüŚŃĆüŃüØŃü«ńĄÉµ×£ŃĆüńēćĶģĢŃéÆÕłćµ¢ŁŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåķćŹÕéĘŃéÆĶ▓ĀŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Ńé┐ŃāÉŃé│ĶŻĮķĆĀÕĘźÕĀ┤Ńü»ŃĆüÕĮōµÖéŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣µö┐Õ║£Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ķüŗÕ¢ČŃüĢŃéīŃéŗÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃéóŃāŗŃé©Ńé╣Ńü«ńłČŃéĖŃāŻŃā│Ńā╗Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Ńü»ŃĆüÕ©śŃü½ńö¤ŃüśŃü¤µÉŹÕ«│Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗĶ│ĀÕä¤ŃéƵ▒éŃéüŃü”ŃĆü1872Õ╣┤1µ£ł24µŚźŃü½Ńā£Ńā½ŃāēŃā╝µ░æõ║ŗĶŻüÕłżµēĆŃü½µÅÉĶ©┤ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Ķ©┤Ķ©¤Ńü»ŃĆüÕøĮÕ«ČŃüīÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃü«ķüŗÕ¢ČŃü½ŃéłŃüŻŃü”Õ╝ĢŃüŹĶĄĘŃüōŃüŚŃü¤µÉŹÕ«│Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüń¦üµ│ĢŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅĶ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüåŃü╣ŃüŹŃüŗŃü©ŃüäŃüåµ│ĢńÜäÕĢÅķĪīŃéƵÅÉĶĄĘŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
Ķ©┤Ķ©¤Ńü«ńĄīńĘ»Ńü©µ│ĢńÜäõ║ēńé╣
ŃéĖŃāŻŃā│Ńā╗Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│µ░ÅŃü«µÅÉĶ©┤Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃéĖŃāŁŃā│Ńāēń£īŃü«ń£īń¤źõ║ŗŃü»ŃĆü1872Õ╣┤4µ£ł29µŚźŃü½ŃĆīń«ĪĶĮ䵩®ń¦╗ķĆüńö│ń½ŗ’╝łd├®clinatoire de comp├®tence’╝ēŃĆŹŃéÆĶĪīŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń£īń¤źõ║ŗŃü»ŃĆüŃüōŃü«õ║ŗõ╗ČŃü»Õģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃü«µ┤╗ÕŗĢŃü½ķ¢óķĆŻŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”µ░æõ║ŗĶŻüÕłżµēĆŃü½Ńü»ń«ĪĶĮ䵩®ŃüīŃü¬ŃüäŃü©õĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüµ░æõ║ŗĶŻüÕłżµēĆŃü»ÕÉīÕ╣┤7µ£ł17µŚźŃü½ŃüōŃü«ńö│ń½ŗŃéÆÕŹ┤õĖŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃéīŃéÆÕÅŚŃüæŃü”ŃĆüń£īń¤źõ║ŗŃü»1872Õ╣┤7µ£ł22µŚźŃü½ŃĆīµ©®ķÖÉń½ČÕÉłµ▒║Õ«Ü’╝łarr├¬t├® de conflit’╝ēŃĆŹŃéÆõĖŗŃüŚŃĆüµŁŻÕ╝ÅŃü½µ£¼õ╗ČŃéƵ©®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃü½õ╗śĶ©ŚŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«µÖéńé╣Ńü¦ŃĆüŃüōŃü«õ║ŗõ╗ČŃü»ÕŹśŃü¬ŃéŗµÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ķ½ŗµ▒éŃéÆĶČģŃüłŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«õ║īÕģāńÜäŃü¬ÕÅĖµ│ĢÕłČÕ║”Ńü«µĀ╣Õ╣╣ŃéƵÅ║ŃéŗŃüīŃüÖµ│ĢńÜäõ║ēńé╣Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕģ¼µ©®ÕŖøŃü«ĶĪīõĮ┐Ńü½ĶĄĘÕøĀŃüÖŃéŗń┤øõ║ēŃüīŃĆüń¦üµ│ĢŃéÆÕÅĖŃéŗÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäŃü½µ£ŹŃüÖŃéŗŃü╣ŃüŹŃüŗŃĆüŃüØŃéīŃü©ŃééĶĪīµö┐µ│ĢŃéÆÕÅĖŃéŗĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäŃü½µ£ŹŃüÖŃéŗŃü╣ŃüŹŃüŗŃü©ŃüäŃüåÕĢÅķĪīŃü¦ŃüÖŃĆé
Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│µ░ÅÕü┤Ńü»ŃĆüÕøĮÕ«ČŃü©ŃüØŃü«õ╗ŻńÉåõ║║Ńü»µ░æµ│ĢÕģĖń¼¼1382µØĪŃüŗŃéē1384µØĪŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅõĖĆĶł¼ÕĖéµ░æŃü©ÕÉīŃüśõĖŹµ│ĢĶĪīńé║Ķ▓¼õ╗╗Ńü«Ķ”ÅÕēćŃü½µ£ŹŃüÖŃéŗŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆŃüīń«ĪĶĮ䵩®ŃéƵīüŃüżŃü©õĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüń£īń¤źõ║ŗÕü┤Ńü»ŃĆüÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃü«ķüŗÕ¢ČŃü½ĶĄĘÕøĀŃüÖŃéŗÕøĮÕ«ČĶ▓¼õ╗╗Ńü»ŃĆüµ░æµ│ĢÕģĖŃü«ÕĤÕēćŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗńē╣ÕłźŃü¬Ķ”ÅÕēćŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ķ”ÅÕŠŗŃüĢŃéīŃéŗŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃü«Õłżµ¢ŁŃü»ĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäŃü½Õ▒×ŃüÖŃéŗŃü©õĖ╗Õ╝ĄŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«õ║ŗõ╗ČŃü»ÕŹśŃü¬Ńéŗń«ĪĶĮ䵩®Ńü«Õē▓ŃéŖµī»ŃéŖŃéÆĶČģŃüłŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«ĶĪīńé║ŃéÆõĖĆĶł¼ÕĖéµ░æŃü©ÕÉīŃüśµ│ĢńÉåŃü¦ĶŻüŃüÅŃü╣ŃüŹŃüŗŃĆüŃüØŃéīŃü©Ńééńē╣ÕłźŃü¬µ│ĢńÉåŃü«µö»ķģŹŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃü╣ŃüŹŃüŗŃü©ŃüäŃüåŃĆüĶ┐æõ╗ŻÕøĮÕ«ČŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµ©®ÕŖøŃü©µ│ĢŃü«ķ¢óõ┐éŃéÆÕĢÅŃüåŃééŃü«Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆ鵩®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃüīõĖŗŃüÖµ▒║Õ«ÜŃü»ŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣ÕøĮÕ«ČŃüīŃü®Ńü«µ│ĢÕĤÕēćŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”ĶĪīÕŗĢŃüŚŃĆüĶ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüåŃüŗŃéƵ£ĆńĄéńÜäŃü½µ▒║Õ«ÜŃüÖŃéŗŃĆüµźĄŃéüŃü”ķćŹÕż¦Ńü¬µäÅÕæ│ŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣ŃĆīŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║ŃĆŹŃü«õĖ╗µ¢ćŃü©µ│ĢńÜäµĀ╣µŗĀ
Õłżµ▒║Ńü«Ķ”üńé╣
1873Õ╣┤2µ£ł8µŚźŃĆüµ©®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃü»ŃĆüń£īń¤źõ║ŗŃü«õĖ╗Õ╝ĄŃéÆĶ¬ŹŃéüŃĆüŃéóŃāŗŃé©Ńé╣Ńā╗Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Ńü½ńö¤ŃüśŃü¤µÉŹÕ«│Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗĶ©┤Ķ©¤Ńü»ŃĆüĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäŃü½Õ▒×ŃüÖŃéŗŃü©Õłżµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüÕŹśŃü½ń«ĪĶĮ䵩®ŃéƵ▒║Õ«ÜŃüŚŃü¤ŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃü«ŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣ĶĪīµö┐µ│ĢŃü«ńÖ║Õ▒ĢŃéƵ¢╣ÕÉæŃüźŃüæŃéŗõ║īŃüżŃü«ÕĤÕēćŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ÕøĮÕ«ČĶ▓¼õ╗╗Ńü«ńē╣ńĢ░µĆ¦Ńü©ĶĪīµö┐µ│ĢŃü«Ķć¬ÕŠŗµĆ¦
µ©®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃü»ŃĆüÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃü½ŃéłŃüŻŃü”Õ╝ĢŃüŹĶĄĘŃüōŃüĢŃéīŃü¤µÉŹÕ«│Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕøĮÕ«ČŃü«Ķ▓¼õ╗╗Ńü»ŃĆüµ░æµ│ĢÕģĖ’╝łCode civil’╝ēŃü«ÕĤÕēćŃü½ŃéłŃüŻŃü”µö»ķģŹŃüĢŃéīŃéŗŃééŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü©Õłżńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕłżµ▒║Ńü»ŃĆüŃüōŃü«Ķ▓¼õ╗╗Ńü»ŃĆīÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃü«Õ┐ģĶ”üµĆ¦ŃĆŹŃéäŃĆīÕøĮÕ«ČŃü«µ©®Õł®Ńü©ń¦üõ║║Ńü«µ©®Õł®ŃéÆĶ¬┐ÕÆīŃüĢŃüøŃéŗÕ┐ģĶ”üµĆ¦ŃĆŹŃü½Õ┐£ŃüśŃü”ÕżēÕŗĢŃüÖŃéŗŃĆīńē╣ÕłźŃü¬Ķ”ÅÕēćŃĆŹŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ķ”ÅÕŠŗŃüĢŃéīŃéŗŃü╣ŃüŹŃüĀŃü©Ķ┐░Ńü╣Ńü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Õłżńż║Ńü»ŃĆüĶĪīµö┐µ│ĢŃüīµ░æµ│ĢŃüŗŃéēńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤ŃĆüńŗ¼Ķć¬Ńü«µ│ĢõĮōń│╗Ńü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéÆÕłØŃéüŃü”µśÄńó║Ńü½µē┐Ķ¬ŹŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«Õłżµ▒║õ╗źÕēŹŃü»ŃĆüĶĪīµö┐Ńü«ĶĪīńé║ŃéÆńĄ▒ÕłČŃüÖŃéŗµ│ĢńÉåŃü»õĖŹµśÄńó║Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«µ┤╗ÕŗĢŃü½Ńü»ń¦üµ│ĢŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗńē╣ńĢ░µĆ¦ŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃĆüŃüØŃü«ńē╣ńĢ░µĆ¦Ńü½Ķ”ŗÕÉłŃüŻŃü¤ńŗ¼Ķć¬Ńü«µ│ĢÕĤÕēćŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåµĆصā│ŃéƵ│ĢńÜäŃü½ńó║ń½ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣µ│ĢÕłČÕ║”Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Õģ¼µ│ĢŃü©ń¦üµ│ĢŃüīµśÄńó║Ńü½ÕłåķøóŃüĢŃéīŃéŗĶ╗óµÅøńé╣Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃĆīµ©®ķÖÉŃü©µ│ĢńÉåŃü«ńĄÉÕÉł’╝łliaison de la comp├®tence et du fond’╝ēŃĆŹŃü«ÕĤÕēć
Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«õ║ŗõ╗ČŃü½ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗŃĆīµ│ĢńÉå’╝łfond’╝ēŃĆŹŃĆüŃüÖŃü¬ŃéÅŃüĪÕ«¤õĮōµ│ĢŃüīĶĪīµö┐µ│ĢŃü¦ŃüéŃéŗŃü¬ŃéēŃü░ŃĆüŃüØŃü«õ║ŗõ╗ČŃéÆĶŻüŃüÅŃĆīµ©®ķÖÉ’╝łcomp├®tence’╝ēŃĆŹŃééŃüŠŃü¤ĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü½ÕĖ░Õ▒×ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕĤÕēćŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü»ŃĆüÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗń┤øõ║ēŃü«Õģ©Ńü”ŃéÆĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäõĖŗŃü½ńĮ«ŃüÅŃüōŃü©ŃéäŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃü«ĶĪīµö┐µ│ĢŃü«ńÖ║Õ▒ĢŃü«µ¢╣ÕÉæµĆ¦ŃéƵ▒║Õ«ÜŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«ĶĪīµö┐µ│ĢŃüīŃĆīń½ŗµ│ĢŃĆŹŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüĶŻüÕłżµēĆŃĆüńē╣Ńü½ÕøĮÕŗÖķÖóŃü«ŃĆīÕłżõŠŗŃĆŹŃü½ŃéłŃüŻŃü”ÕĮóµłÉŃüĢŃéīŃéŗµĆ¦µĀ╝ŃéƵīüŃüżŃüōŃü©ŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║ŃüīĶĪīµö┐µ│ĢŃü«Õ¤║ńżÄŃéÆń»ēŃüäŃü¤Ńü©ŃüäŃüåŃüōŃü©Ńü»ŃĆüĶĪīµö┐µ│ĢŃüīķØÖńÜäŃü¬µ│ĢÕŠŗķøåŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕģĘõĮōńÜäŃü¬ń┤øõ║ēĶ¦Żµ▒║ŃéÆķĆÜŃüśŃü”ķĆ▓Õī¢ŃüŚńČÜŃüæŃéŗŃĆīńö¤ŃüŹŃü¤µ│ĢŃĆŹŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüÕŹśõĖĆŃü«õ║ŗõ╗ČŃü«Ķ¦Żµ▒║ŃéÆĶČģŃüłŃü”ŃĆüµ£¬µØźŃü«Õģ©Ńü”Ńü«ĶĪīµö┐µ│Ģń┤øõ║ēŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗµ│ĢńÜäŃü¬µ×ĀńĄäŃü┐ŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃĆüĶĪīµö┐ŃéÆÕ░éķ¢ĆŃü©ŃüÖŃéŗĶŻüÕłżÕ«śŃü½µ¢░Ńü¤Ńü¬µ│ĢÕĤÕēćŃéÆÕēĄķĆĀŃüÖŃéŗÕ║āń»äŃü¬µ©®ķÖÉŃü©Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆõĖÄŃüłŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ńé╣ŃüīŃĆüŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║ŃüīÕŹśŃü¬ŃéŗŃĆīÕłżõŠŗŃĆŹŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüŃĆīĶĪīµö┐µ│ĢŃü«Õ¤║ńżÄŃĆŹŃü©ń¦░ŃüĢŃéīŃéŗŃéåŃüłŃéōŃü¦ŃüÖŃĆé
Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ńó║ń½ŗŃüĢŃéīŃü¤µ│ĢÕĤÕēćŃü©ÕłØµ£¤Ńü«ÕĮ▒ķ¤┐

Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü½Õ║āń»äŃüŗŃüżķĢʵ£¤ńÜäŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆõĖÄŃüłŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Õłżµ▒║ŃüīŃééŃü¤ŃéēŃüŚŃü¤õĖ╗Ķ”üŃü¬ÕżēÕī¢Ńü»õ╗źõĖŗŃü«ķĆÜŃéŖŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕøĮÕ«ČńäĪĶ▓¼õ╗╗ÕĤÕēćŃüŗŃéēŃü«Ķä▒ÕŹ┤
Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║õ╗źÕēŹŃü»ŃĆüÕģ¼µ©®ÕŖøŃü«ĶĪīõĮ┐Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ńö¤ŃüśŃéŗµÉŹÕ«│Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”ÕøĮÕ«ČŃü»Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃéÅŃü¬ŃüäŃü©ŃüÖŃéŗŃĆīÕøĮÕ«ČńäĪĶ▓¼õ╗╗ÕĤÕēćŃĆŹŃüīµö»ķģŹńÜäŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü»ŃĆüÕøĮÕ«ČõĖ╗µ©®Ńü«ńĄČÕ»ŠµĆ¦ŃéÆÕēŹµÅÉŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüŃüōŃü«ÕĤÕēćŃéƵĀ╣µ£¼ńÜäŃü½Ķ”åŃüŚŃĆüÕøĮÕ«ČŃééŃüØŃü«Õģ¼ÕĮ╣ÕŗÖµ┤╗ÕŗĢŃü½ŃéłŃüŻŃü”Õ╝ĢŃüŹĶĄĘŃüōŃüŚŃü¤µÉŹÕ«│Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüåŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéƵśÄńó║Ńü½ńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüÕĖéµ░æŃüīÕøĮÕ«ČŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”µÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤ŃéƵ▒éŃéüŃéŗķüōŃéÆķ¢ŗŃüŹŃĆüÕøĮÕ«Čµ©®ÕŖøŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕĖéµ░æŃü«µ©®Õł®õ┐ØĶŁĘŃéÆÕ╝ĘÕī¢ŃüÖŃéŗķĆ▓µŁ®Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
Õģ¼ÕĮ╣ÕŗÖ’╝łservice public’╝ēÕ¤║µ║¢Ńü«ńó║ń½ŗ
Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮ䵩®Ńü©ĶĪīµö┐µ│ĢŃü«ķü®ńö©ŃéÆŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«ŃĆīÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃĆŹµ┤╗ÕŗĢŃü½ńĄÉŃü│ŃüżŃüæŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆÕĢÅŃüåĶŻüÕłżŃü«Õ¤║µ║¢Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆīÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃĆŹŃü©ŃüäŃüåµ”éÕ┐ĄŃüīńó║ń½ŗŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüĶĪīµö┐µ®¤ķ¢óŃü«ĶĪīńé║ŃüīÕģ¼ńÜäŃü¬ńø«ńÜäŃü«Ńü¤ŃéüŃü½ĶĪīŃéÅŃéīŃéŗŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”ŃĆüń«ĪĶĮ䵩®ŃéÆÕłżµ¢ŁŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåµśÄńó║Ńü¬Õ¤║µ║¢ŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«ÕĤÕēćŃü»ŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃĆüÕ£░µ¢╣Ķ欵▓╗õĮōŃü½ŃééµŗĪÕ╝ĄŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵩®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃü»1908Õ╣┤Ńü«FeutryÕłżµ▒║Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüĶĪīµö┐µ│ĢŃü«Ķ▓¼õ╗╗ÕĤÕēćŃüīÕ£░µ¢╣Ķ欵▓╗õĮōŃü½Ńééķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńó║Ķ¬ŹŃüŚŃĆüÕ£░µ¢╣Ńü«Õģ¼ÕĮ╣ÕŗÖµ┤╗ÕŗĢŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗń┤øõ║ēŃééĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäŃü½µ£ŹŃüÖŃéŗŃü©Õłżµ¢ŁŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüÕøĮÕŗÖķÖóŃüī1903Õ╣┤Ńü«TerrierÕłżµ▒║Ńü¦ŃüÖŃü¦Ńü½ńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤µ¢╣ķćØŃéÆĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃüīĶ┐ĮĶ¬ŹŃüÖŃéŗÕĮóŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüĶĪīµö┐µ│ĢŃü«ķü®ńö©ń»äÕø▓Ńü»õĖŁÕż«µö┐Õ║£ŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüÕ£░µ¢╣Ńü«Õģ¼Õģ▒ÕøŻõĮōŃü½ŃééÕÅŖŃüČŃüōŃü©Ńüīńó║ń½ŗŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µ©®ÕŖøńøŻĶ”¢Ńü«ŃāæŃā®ŃāēŃāāŃé»Ńé╣
Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüõĖƵ¢╣Ńü¦ÕøĮÕ«ČŃü«Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃĆüÕĖéµ░æŃü«µ©®Õł®õ┐ØĶŁĘŃéÆÕ╝ĘÕī¢ŃüŚŃü¤ŃéłŃüåŃü½Ķ”ŗŃüłŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüõ╗¢µ¢╣Ńü¦ŃĆüŃüØŃéīŃü»ÕøĮÕ«ČŃéÆõĖĆĶł¼Ńü«µ│ĢńÉå’╝łµ░æµ│Ģ’╝ēŃüŗŃéēÕłćŃéŖķøóŃüŚŃĆüŃĆīńē╣ÕłźŃü¬µ│ĢńÉå’╝łĶĪīµö┐µ│Ģ’╝ēŃĆŹŃü«µö»ķģŹõĖŗŃü½ńĮ«ŃüÅŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüÕøĮÕ«ČŃü½ńē╣ÕłźŃü¬Õ£░õĮŹŃéÆõĖÄŃüłŃü¤Ńü©ŃééŃüäŃüłŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«õ║īŃüżŃü«Õü┤ķØóŃü»ŃĆüÕĖéµ░æŃü«µ©®Õł®ŃéÆõ┐ØĶŁĘŃüŚŃüżŃüżŃééŃĆüÕøĮÕ«Čµ©®ÕŖøŃü«ńē╣ńĢ░µĆ¦ŃéÆńČŁµīüŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣ĶĪīµö┐µ│ĢŃü«ńŗ¼ńē╣Ńü¬ŃāæŃā®ŃāēŃāāŃé»Ńé╣ŃéÆÕĮóµłÉŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ńŖȵ│üŃü»ŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«Õģ¼µ│ĢÕŁ”Ńü«µĀ╣Õ║ĢŃü½ŃüéŃéŗŃĆīµ©®ÕŖøŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗõĖŹõ┐Īµä¤ŃĆŹŃü©ŃĆīÕøĮÕ«ČŃüĖŃü«õ┐ĪķĀ╝ŃĆŹŃü©ŃüäŃüåõ║īÕŠŗĶāīÕÅŹŃéÆÕÅŹµśĀŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüĶĪīµö┐Ńü«ĶĪīńé║ŃéÆńĄ▒ÕłČŃüÖŃéŗÕĮ╣Õē▓ŃéƵŗģŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüÕÉīµÖéŃü½ŃĆüŃüØŃü«ĶĪīµö┐Ńü«ńē╣µ©®ńÜäŃü¬Õ£░õĮŹŃéƵŁŻÕĮōÕī¢ŃüÖŃéŗÕĮ╣Õē▓Ńééµ×£Ńü¤ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüŃüōŃü«ķ¢óõ┐éŃéƵ│ĢńÜäŃü½Õ«ÜÕ╝ÅÕī¢ŃüŚŃü¤µ£ĆÕłØŃü«õ║ŗõŠŗŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕłżõŠŗµ│ĢŃü«ńÖ║Õ▒ĢŃü©Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü«õ┐«µŁŻŃā╗ńÖ║Õ▒Ģ
Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ńó║ń½ŗŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃĆŹÕ¤║µ║¢Ńü»ŃĆüŃüØŃü«ÕŠīń┤äÕŹŖõĖ¢ń┤ĆŃü½ŃéÅŃü¤ŃüŻŃü”ĶĪīµö┐µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŁÕ┐āńÜäŃü¬µ”éÕ┐ĄŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüńżŠõ╝ÜńĄīµĖłŃü«ÕżēÕī¢Ńü½õ╝┤ŃüäŃĆüŃüØŃü«µ”éÕ┐ĄŃü»õ┐«µŁŻŃā╗ńÖ║Õ▒ĢŃéÆķüéŃüÆŃéŗŃüōŃü©Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ńöŻµźŁŃā╗ÕĢåµźŁńÜäÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖ’╝łSPIC’╝ēŃü«µ”éÕ┐Ą
1921Õ╣┤1µ£ł22µŚźŃü«Soci├®t├® commerciale de l’Ouest africainÕłżµ▒║Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüµ©®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃü»ŃĆüõĖĆķā©Ńü«Õģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃüīń¦üõ╝üµźŁŃü©ÕÉīŃüśµØĪõ╗ČŃü¦ķüŗÕ¢ČŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃéÆĶ¬ŹŃéüŃĆüŃĆīńöŻµźŁŃā╗ÕĢåµźŁńÜäÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖ’╝łSPIC’╝ēŃĆŹŃü«µ”éÕ┐ĄŃéÆÕēĄĶ©ŁŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃü«µĆ¦Ķ│¬ŃüīÕŹśń┤öŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüŃüØŃü«ńĄīµĖłńÜäŃā╗ÕĢåµźŁńÜäÕü┤ķØóŃéÆĶĆāµģ«ŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüØŃéīŃüŠŃü¦Ńü«ŃĆīÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖ’╝ØĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕŹśń┤öŃü¬ÕĤÕēćŃü»ŃĆüŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ĶżćķøæŃü¬õĮōń│╗ŃüĖŃü©ń¦╗ĶĪīŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶĪīµö┐Ńü«µ┤╗ÕŗĢŃüīÕżÜĶ¦ÆÕī¢ŃüŚŃĆüµ░æķ¢ōõ╝üµźŁŃü©ń½ČÕÉłŃüÖŃéŗÕłåķćÄŃü½ķĆ▓Õć║ŃüÖŃéŗŃü½ŃüżŃéīŃü”ŃĆüµ│ĢÕĤÕēćŃééŃüØŃéīŃü½ÕÉłŃéÅŃüøŃü”ń┤░ÕłåÕī¢ŃüĢŃéīŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüSPICŃü«ķüŗÕ¢ČŃü½ŃéłŃüŻŃü”ńö¤ŃüśŃü¤µÉŹÕ«│Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗń┤øõ║ēŃü»ŃĆüµ░æµ│ĢŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”ÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäŃü½µ£ŹŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüĶĪīµö┐Ńü«µ┤╗ÕŗĢŃü«ŃĆīµĆ¦Ķ│¬ŃĆŹŃüīŃĆüŃüØŃü«µ┤╗ÕŗĢŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗń«ĪĶĮ䵩®ŃéƵ▒║Õ«ÜŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåµ¢░Ńü¤Ńü¬Õ¤║µ║¢ŃéÆÕ░ÄÕģźŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
1957Õ╣┤ń½ŗµ│ĢŃü½ŃéłŃéŗõ┐«µŁŻ
Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü«ÕģĘõĮōńÜäŃü¬ķü®ńö©ń»äÕø▓Ńü»ŃĆüń½ŗµ│ĢŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ńééńø┤µÄźńÜäŃü½õ┐«µŁŻŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéLoi n┬░ 57-1424 du 31 d├®cembre 1957 attribuant comp├®tence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilit├® des dommages caus├®s par tout v├®hicule et dirig├®s contre une personne de droit public’╝łÕģ¼ńö©Ķ╗ŖõĖĪŃü½ŃéłŃüŻŃü”Õ╝ĢŃüŹĶĄĘŃüōŃüĢŃéīŃü¤µÉŹÕ«│Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ▓¼õ╗╗Ķ©┤Ķ©¤Ńü«ń«ĪĶĮ䵩®ŃéÆÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆŃü½õ╗śõĖÄŃüÖŃéŗ1957Õ╣┤12µ£ł31µŚźõ╗śµ│ĢÕŠŗń¼¼57-1424ÕÅĘ’╝ēŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕģ¼ńö©Ķ╗ŖõĖĪŃü½ŃéłŃüŻŃü”Õ╝ĢŃüŹĶĄĘŃüōŃüĢŃéīŃü¤µÉŹÕ«│Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗń┤øõ║ēŃü«ń«ĪĶĮ䵩®Ńü»ŃĆüĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃüŗŃéēÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆŃüĖŃü©ń¦╗ń«ĪŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«µ│ĢÕŠŗŃü»ŃĆüŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü«µĀ╣Õ╣╣ŃéÆŃü¬ŃüÖõ║ŗÕ«¤ķ¢óõ┐éŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃĆüµśÄńó║Ńü¬ń½ŗµ│ĢõĖŖŃü«õ┐«µŁŻŃéÆÕŖĀŃüłŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃééŃüŚŃéóŃāŗŃé©Ńé╣Ńā╗Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Ńü«õ║ŗµĢģŃüīõ╗ŖµŚźĶĄĘŃüōŃüŻŃü¤Ńü©ŃüÖŃéīŃü░ŃĆüÕĮ╝Õź│Ńü«µÉŹÕ«│Ķ│ĀÕä¤Ķ½ŗµ▒éŃü»ŃĆüĶĪīµö┐µ│ĢŃü¦Ńü»Ńü¬Ńüŵ░æµ│ĢŃü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”ÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆŃü½ŃéłŃüŻŃü”Õ»®ńÉåŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õ╗źõĖŗŃü«ĶĪ©Ńü»ŃĆüŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü«ÕĤÕēćŃüīŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃü«ÕłżõŠŗŃéäń½ŗµ│ĢŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü½ńÖ║Õ▒ĢŃüŚŃĆüÕżēÕī¢ŃüŚŃü”ŃüŹŃü¤ŃüŗŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
| ńŖȵ│ü | ń«ĪĶĮ䵩® | µ│ĢńÜäµĀ╣µŗĀ | |
|---|---|---|---|
| 1873Õ╣┤ (Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║µÖé) | Õģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃü«ķüŗÕ¢ČŃü½ĶĄĘÕøĀŃüÖŃéŗÕøĮÕ«ČĶ▓¼õ╗╗Ńü»µ░æµ│ĢÕģĖŃü«ÕĤÕēćŃü½µ£ŹŃüĢŃü¬ŃüäŃĆé | ĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆ | Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║ (µ©®ķÖÉŃü©µ│ĢńÉåŃü«ńĄÉÕÉłŃü«ÕĤÕēć) |
| 1921Õ╣┤ (SPICŃü«ÕēĄĶ©ŁÕŠī) | Õģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃüīń¦üõ╝üµźŁŃü©ÕÉīŃüśµØĪõ╗ČŃü¦ķüŗÕ¢ČŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«Ķ▓¼õ╗╗Ńü»µ░æµ│ĢŃü½µ£ŹŃüÖŃéŗŃĆé | ÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆ | Soci├®t├® commerciale de l’Ouest africainÕłżµ▒║ (SPICŃü«µ”éÕ┐Ą) |
| 1957Õ╣┤ (µ│Ģµö╣µŁŻÕŠī) | Õģ¼ńö©Ķ╗ŖõĖĪŃü½ŃéłŃéŗµÉŹÕ«│Ńü«ń┤øõ║ēŃü»ŃĆüÕģ¼ÕĮ╣ÕŗÖŃü«µĆ¦Ķ│¬Ńü½ķ¢óŃéÅŃéēŃüܵ░æµ│ĢŃü½µ£ŹŃüÖŃéŗŃĆé | ÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆ | 1957Õ╣┤12µ£ł31µŚźŃü«µ│ĢÕŠŗ |
ŃüōŃü«ĶĪ©Ńüīńż║ŃüÖŃéłŃüåŃü½ŃĆüŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü«õ║ŗÕ«¤ķ¢óõ┐éĶć¬õĮōŃü»ŃĆüõ╗ŖµŚźŃü¦Ńü»ÕÅĖµ│ĢĶŻüÕłżµēĆŃü«ń«ĪĶĮäõĖŗŃü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║ŃüīµŁ┤ÕÅ▓ńÜäŃü½ķćŹĶ”üŃü¦ŃüéŃéŗńÉåńö▒Ńü»ŃĆüŃüØŃü«ńĄÉĶ½¢Ńü½ŃüéŃéŗŃü«Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕģ¼µ│Ģńŗ¼Ķć¬Ńü«ÕŁśÕ£©µäÅńŠ®ŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃü¤Ńü©ŃüäŃüåńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüÕŹśõĖĆŃü«õ║ŗõ╗ČŃü«Õłżµ▒║Ńü½ńĢÖŃüŠŃéēŃüÜŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«ĶĪīµö┐µ│ĢŃüīĶć¬ÕŠŗńÜäŃü¬µ│ĢõĮōń│╗Ńü©ŃüŚŃü”ńÖ║Õ▒ĢŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ķüōńŁŗŃéÆŃüżŃüæŃü¤ŃĆüµŁ┤ÕÅ▓ńÜäŃü¬Ķ╗óµÅøńé╣Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃü«ķü║ńöŻŃü»ŃĆüńÅŠõ╗ŻŃü«ŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣µ│ĢÕłČÕ║”Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«ńé╣Ńü¦µ░ĖńČÜńÜäŃü¬µäÅńŠ®ŃéƵīüŃüĪńČÜŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃüÜŃĆüŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»ŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣ĶĪīµö┐µ│ĢŃü«Õ¤║ńżÄŃéÆń»ēŃüŹŃĆüÕøĮÕ«ČŃüīŃüØŃü«Õģ¼ÕĮ╣ÕŗÖµ┤╗ÕŗĢŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüåŃü©ŃüäŃüåŃĆüĶ┐æõ╗ŻńÜäŃü¬ÕĤÕēćŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕĖéµ░æŃü»ÕøĮÕ«ČŃü«õĖŹµ│ĢŃü¬ĶĪīńé║Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”µ│ĢńÜäŃü¬µĢæµĖłŃéƵ▒éŃéüŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µ¼ĪŃü½ŃĆüŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü»ŃĆüĶĪīµö┐µ│ĢŃüīµ░æµ│ĢŃüŗŃéēńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤ŃĆüńŗ¼Ķć¬Ńü«µ│ĢõĮōń│╗Ńü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéƵśÄńó║Ńü½µē┐Ķ¬ŹŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüĶĪīµö┐Ńü«ńē╣ńĢ░µĆ¦ŃéƵ│ĢńÜäŃü½µŁŻÕĮōÕī¢ŃüŚŃĆüĶĪīµö┐ŃéÆńĄ▒ÕłČŃüÖŃéŗÕ░éķ¢ĆńÜäŃü¬µ│ĢõĮōń│╗Ńü«ńÖ║Õ▒ĢŃéÆõ┐āŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Õłżµ▒║õ╗źķÖŹŃĆüĶĪīµö┐ĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüÕŹśŃü¬ŃéŗĶĪīµö┐Õ║üŃü«Ķ½«ÕĢŵ®¤ķ¢óŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüĶĪīµö┐Ńü«ĶĪīÕŗĢŃéÆńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü”ńøŻĶ”¢ŃüŚŃĆüÕøĮÕ«ČĶ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ┐ĮÕÅŖŃüÖŃéŗńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤ÕÅĖµ│Ģµ®¤ķ¢óŃü©ŃüŚŃü”Ńü«Õ£░õĮŹŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µ£ĆÕŠīŃü½ŃĆüŃüōŃü«Õłżµ▒║Ńü»µ©®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃü«Ķ©Łń½ŗńø«ńÜäŃéƵŁŻÕĮōÕī¢ŃüŚŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃü«ÕĮ╣Õē▓ŃéƵ▒║Õ«ÜŃüźŃüæŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆ鵩®ķÖÉÕłåķģŹµ│ĢÕ╗ĘŃü»ŃĆüÕŹśŃü½µ©®ķÖÉŃü«ĶĪØń¬üŃéÆĶ¦Żµ▒║ŃüÖŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüÕłżõŠŗŃéÆķĆÜŃüśŃü”õĖĪµ│Ģń¦®Õ║ÅŃü«ÕóāńĢīńĘÜŃéÆń®ŹµźĄńÜäŃü½µ¦ŗń»ēŃüŚŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«ÕØćĶĪĪŃéÆõ┐ØŃüżõĖŖŃü¦õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¬ÕĮ╣Õē▓ŃéƵףŃü¤ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Ńā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü«õĖŁÕ┐āķā©ÕłåŃĆüŃüÖŃü¬ŃéÅŃüĪŃĆīÕøĮÕ«ČĶ▓¼õ╗╗ŃĆŹŃü©ŃĆīĶĪīµö┐µ│ĢŃü«Ķć¬ÕŠŗµĆ¦ŃĆŹŃü»õ╗ŖµŚźŃü¦Ńééµ£ēÕŖ╣Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃü«ÕłżõŠŗ’╝łõŠŗ’╝ÜSPICŃü«µ”éÕ┐Ą’╝ēŃéäń½ŗµ│Ģ’╝łõŠŗ’╝ÜÕģ¼Õģ▒Ķ╗ŖõĖĪµ│Ģ’╝ēŃü½ŃéłŃüŻŃü”õ┐«µŁŻŃüĢŃéīŃĆüŃéłŃéŖĶżćķøæŃü¬ŃééŃü«ŃüĖŃü©ķĆ▓Õī¢ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃā¢Ńā®Ńā│Ńé│Õłżµ▒║Ńü«ķü║ńöŻŃü»ŃĆüŃüØŃü«ÕģĘõĮōńÜäŃü¬ķü®ńö©ń»äÕø▓ŃéłŃéŖŃééŃĆüÕģ¼µ│Ģńŗ¼Ķć¬Ńü«ÕŁśÕ£©µäÅńŠ®ŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃü¤Ńü©ŃüäŃüåńé╣Ńü½ŃüōŃüØĶ”ŗÕć║ŃüĢŃéīŃéŗŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃüØŃéīŃü»ŃĆüÕøĮÕ«ČŃü«ĶĪīńé║ŃéÆńē╣µ«ŖŃü¬Õģ¼Õģ▒Ńü«Ķ½¢ńÉåŃü¦µŹēŃüłŃüżŃüżŃééŃĆüŃüØŃü«Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ┐ĮÕÅŖŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣ĶĪīµö┐µ│ĢŃü«µĀ╣µ£¼ńÜäŃü¬õ║īÕŠŗĶāīÕÅŹŃéÆÕģĘńÅŠÕī¢ŃüŚŃü¤ŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüōŃü«ŃāæŃā®ŃāēŃāāŃé»Ńé╣ŃüōŃüØŃüīŃĆüńÅŠõ╗ŻŃü«ŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣ĶĪīµö┐µ│ĢŃéÆńē╣ÕŠ┤ŃüźŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ