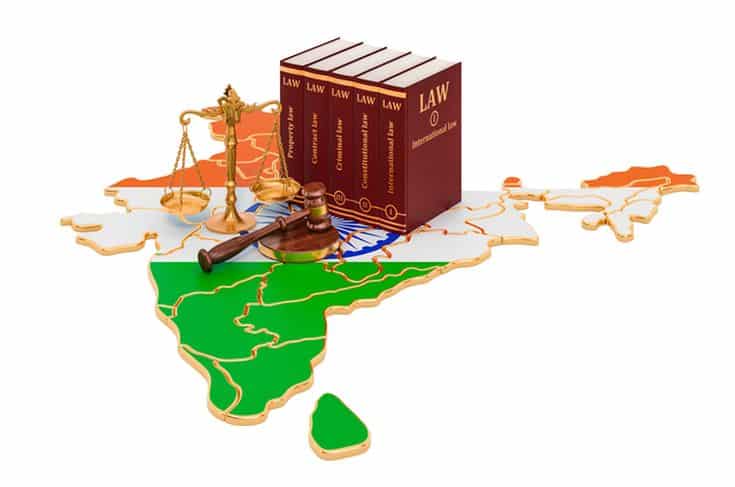フランス共和国における日本資本による現地法人の買収・M&Aを解説

フランス(正式名称、フランス共和国)は、技術力と産業基盤に強みを持つ欧州有数の経済大国であり、日本企業にとって魅力的な投資先です。M&Aは、フランス市場への参入や事業拡大を加速させる有効な手段であり、近年、ウクライナ侵攻や高金利の影響で欧州市場全体のM&A活動が減速する中でも、2024年には取引活動が増加するなど、堅調な動きが見られました。しかし、フランスのM&A実務は、日本法にはない独自の手続きや規制、そして近年の法改正や画期的な判例によって常に変化しており、日本企業の経営者や法務担当者が十分な注意を払う必要があります。
近年のフランスのM&A環境を理解する上で、特に重要なのは、公共の安全や秩序、そして国家の経済主権を保護するための一連の法改正です。外国投資規制の対象となる事業分野が拡大し、上場企業における議決権取得の閾値が10%に恒久的に引き下げられたことは、日本企業がM&Aを検討する際に、従来以上に慎重なデューデリジェンスを必要とすることを示しています。また、従業員の権利保護を重視するフランス労働法は、買収の成否やスケジュールに直接的な影響を及ぼす可能性があります。さらに、合併における刑事責任の承継や、表明保証違反に対する損害賠償に関する最新の判例法理を踏まえると、契約書作成やリスク評価において、日本とは異なるアプローチが求められると言えるでしょう。
本記事では、フランスにおけるM&Aの主要な法的側面を、特に日本企業が留意すべき外国投資規制、労働法、そして最新の判例法理に焦点を当てて、網羅的かつ詳細に解説します。
なお、フランスの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
フランスの買収スキームと主要な会社形態の概要
フランスにおける主要な会社形態
フランスでは、日本における株式会社や合同会社に相当する会社形態として、主に3つの形態が広く利用されています。
- SA (Société Anonyme):日本の株式会社に最も近い会社形態です。大規模事業や上場企業に適しており、最低株主数は2名、最低資本金は37,000ユーロと定められています。株式は原則として自由に譲渡可能ですが、定款によって譲渡を制限することもできます。
- SAS (Société par Actions Simplifiée):柔軟性の高さから、現在フランスで最も一般的な会社形態です。最低株主数は1名からで、最低資本金の定めはありません。定款自治が広く認められており、株式譲渡の承認(clause d’agrément)や先買権(clause de préemption)などの条項を自由に設定できる点が、日本の株式会社における株式譲渡制限の規律と類似しており、重要な点です。
- SARL (Société à Responsabilité Limitée):日本の合同会社に類似しており、家族経営や小規模事業でよく用いられる閉鎖的な会社形態です。株主数は1名から100名までと制限されており、株式の第三者への譲渡には、株式の過半数を保有する株主の承認が必要です。
株式譲渡、合併、事業譲渡
株式譲渡は、買収対象会社の株式を取得することで、その会社の支配権を獲得する最も一般的な方法です。この方法では、会社の資産や負債、契約関係は原則としてそのまま引き継がれます。
合併(Fusion)は、フランス商法典L236-1条で「1つまたは複数の会社がその全財産を既存の会社または新設会社に承継させる」ことと定義されています。日本の吸収合併に相当するスキームでは、被吸収会社は清算手続きなしに解散し、その全財産(資産および負債)は吸収会社に自動的かつ包括的に承継されます。この際、被吸収会社の株主は原則として吸収会社の株式を受け取りますが、現金による交付も限定的に認められています。特に、吸収会社が被吸収会社の議決権の90%以上を保有している場合、「簡略化された合併(Fusion simplifiée)」が利用可能となり、一部の法定手続きを省略できるため、グループ内再編で頻繁に用いられます。
事業譲渡(Cession de fonds de commerce)は、会社そのものではなく、特定の事業資産を譲渡するスキームです。フランス法上の「fonds de commerce」は、顧客という不可欠な要素を中心とする無形資産(商号、賃借権、特許、商標など)と、事業の運営に必要な有形資産(備品、在庫など)の集合体を指します。日本の営業譲渡が「営業」という概念を包括的に引き継ぐのに対し、フランスのfonds de commerce譲渡では、原則として不動産や債権債務は自動的には引き継がれません。このため、買収後の偶発債務リスクを低減できるメリットがある一方で、必要な契約や債務を個別に譲渡する手続きが必要となるため、実務上の複雑性が増す可能性があります。
フランスの外国投資規制(IEF:Investissements Étrangers en France)
フランスでは、外国からの投資は原則として自由であるとされていますが、公共の安全や秩序、国防といった国家の根幹に関わる特定の事業分野への投資については、経済・財務・産業・デジタル主権大臣による事前許可が必要とされています。この制度は、経済的安全保障を確保するために近年その適用範囲と厳格性が大幅に強化されており、日本企業がフランスM&Aを検討する上で最も重要な法的課題の一つとなっています。
規制のトリガーとなる3つの条件
事前許可が必要となるのは、以下の3つの条件がすべて満たされた場合です。
- 外国投資家であること:フランス法上の定義によれば、外国籍の自然人、フランスに住所を有しないフランス籍の自然人、外国法に準拠する法人、または外国人が支配権を有するフランス法人を指します。日本企業は非EU/EEA投資家に該当するため、この条件に該当します。
- 特定の投資行為であること
- フランス法に準拠する法人またはフランス国内に登記された外国法人の支店の「支配権の取得」。
- 事業部門の全部または一部の取得。
- 特定の議決権保有比率の閾値超過。
- 対象事業が機密性の高い分野に属すること:防衛・治安、エネルギー、交通、通信、公衆衛生、食料安全保障などが含まれます。
株式保有比率の閾値に関する最新動向と洞察
2023年12月28日付デクレ(政令)No. 2023-1293により、外国投資規制の適用範囲がさらに拡大・厳格化されました。特に、非EU/EEA投資家が上場企業に投資する場合の議決権取得の閾値が、従来の25%から10%に恒久的に引き下げられました。これは、新型コロナウイルス禍での一時的な措置が恒久化されたもので、経済危機下でもフランスの戦略的企業を外国資本の買収から保護するという政府の強い意図が反映されていると見ることができます。
この一連の動きは、フランス政府が経済的安全保障と主権を国家戦略の中核に据えていることを強く示唆しています。半導体、AI、バイオテクノロジー、そして近年の法改正で追加された刑務所の安全保障、重要原材料の採掘・加工・リサイクル、フォトニクスおよび低炭素エネルギー生産技術の研究開発といった分野への外国資本の流入を厳格に管理する姿勢が明確に見て取れます。
したがって、日本企業がM&Aを検討する際には、従来の財務・法務デューデリジェンスに加え、対象企業がこれらの戦略分野に該当しないか、より詳細に、そして子会社レベルまで精査する必要があることを意味します。
無許可投資に対する制裁
事前許可が必要な取引を無許可で実行した場合、経済・財務・産業・デジタル主権大臣は、以下のような重大な制裁措置を課すことができます。
- 取引の現状復帰命令。
- 投資額の2倍に相当する罰金。
- 法人の場合は最大500万ユーロ、または対象会社の売上高の10%に相当する罰金。
これは単なる行政罰に留まらず、M&A取引の実行を根本的に無効化する可能性を秘めており、買収完了後の予期せぬリスクとして、日本企業にとって重大な懸念事項となります。
| 外国投資家(非EU/EEA投資家) | |
|---|---|
| 上場企業 | 議決権の10%超過で事前通知が必要 |
| 非上場企業 | 支配権の取得(議決権の50%以上など)または事業部門の全部・一部の取得 |
フランスの競争法(Competition Law)

M&A取引は、外国投資規制に加え、競争法に基づく合併審査の対象となる可能性があります。取引の規模に応じて、フランスの競争当局(Autorité de la concurrence)またはEU委員会(European Commission)のいずれかに届出義務が生じます。
- フランス国内の審査:関係当事者すべての全世界での売上高合計が1億5,000万ユーロを超え、かつ少なくとも2つの会社がフランス国内で5,000万ユーロを超える売上高を計上している場合に、届出が必要です。
- EU委員会の審査:より大規模な案件(関係当事者すべての全世界での売上高合計が50億ユーロを超え、かつ少なくとも2つの会社がEU内で2億5,000万ユーロを超える売上高を計上している場合など)は、EU委員会の管轄となります。
近年、M&A取引に新たな影響を及ぼしているのが、EU外国補助金規則(EU Foreign Subsidies Regulation – FSR)です。FSRは、外国政府からの財政的貢献を受けた企業によるM&Aを審査の対象としており、これにより、フランスやEUの競争法上の審査に加え、新たなレイヤーの規制コンプライアンスが求められることになります。これは、買収スキーム検討段階で、対象会社が過去に何らかの外国政府補助金を受けていないかを確認する新たなデューデリジェンス項目として浮上していると言えます。
フランスの特定分野や状況で問題となる法制度
労働法
フランスでは、日本の労働法には見られない、従業員代表機関との厳格な情報提供・協議義務がM&A取引に課されています。この義務は、取引の成否やスケジュールに直接的な影響を与えるため、日本企業は特に注意を払う必要があります。
まず、従業員50人以上の企業において、M&Aなどの重大な事業再編を計画する際に、社会経済委員会(CSE:Comité Social et Économique)との情報提供および協議プロセスが義務付けられています。この協議プロセスは、拘束力のある合意書(binding agreement)または意向表明書(letter of intent)に署名する1〜3ヶ月前に開始する必要があります。CSEは取引そのものを阻止することはできませんが、情報提供・協議義務が適切に履行されていない場合、裁判所に取引の停止命令を求めることができます。また、公開買付の場合には、対象会社と買付提案者の双方がそれぞれのCSEを即座に招集し、情報提供を行う必要があります。対象会社のCSEは、公認会計士を選任して提案者の産業・財務政策や従業員への影響を評価するレポートを作成させることができます。この労働法上の義務は、日本のM&A実務とは大きく異なり、日本の法務担当者は特に注意深く管理する必要があります。
次に、従業員50人未満の中小企業を対象として、事業(fonds de commerce)または株式の50%以上を売却する場合、従業員に対し、売却の意図と買収提案を行う機会があることを事前に通知する、情報提供義務(Loi Hamon)が課されています。この通知は、拘束力のある契約締結の 少なくとも2ヶ月前に行う必要があります。この義務を怠った場合、売却価格の最大2%に相当する罰金が課される可能性があります。
事業譲渡(Cession de fonds de commerce)の特則
前述の通り、フランス法上の「fonds de commerce」は、日本の「営業」とは異なる概念であり、承継対象に注意が必要です。以下に、その重要な相違点と留意点をまとめます。
| フランス法 | 日本法 | |
|---|---|---|
| 法的概念 | 顧客という不可欠な要素を中心とする無形資産と有形資産の集合体 | 統一的な組織体として機能する財産および債務の集合体 |
| 承継対象 | 原則として、不動産、債権、債務は自動的に承継されない | 原則として、営業に関する財産、債務、契約関係を包括的に承継する |
| 公示手続き | 譲渡完了後15日以内に地元の法務官報と商業民事官報に公示義務あり | 商号の続用がない限り、債権者保護のための公告義務はない |
| 実務上の影響 | 必要な契約や債務を個別に承継する手続きが必要。買収後の偶発債務リスクを低減できるメリットあり | 包括的な承継のため、デューデリジェンスが重要。偶発債務リスクを負う可能性が高い |
また、事業譲渡においては、地元の法務官報(local legal gazette)および商業民事官報(BODACC)に、譲渡完了日から15日以内に公示することが義務付けられています。これは、日本の商法における公告とは異なり、債権者保護のための強制的な手続きです。
外国投資規制の対象となる事業分野(Sensitive Sectors)
前述の外国投資規制は、すべてのM&Aに適用されるわけではなく、特定の事業分野に限定されます。具体的には以下の主要なカテゴリーに分類されます。
- 国防・治安関連:軍事目的の武器、弾薬、爆薬、デュアルユース技術(軍民両用技術)など。
- 公衆衛生・食料安全保障:医薬品の供給確保、医療機器、重要医薬品の研究開発・生産など。
- 重要インフラ:エネルギー(電力、ガス、石油)、水道、交通、通信ネットワーク、宇宙開発。
- 先端技術:AI、ロボット工学、半導体、量子技術、再生可能エネルギー技術、バイオテクノロジーなど。
2023年の法改正で、このリストに「重要原材料の採掘、加工、リサイクル」や「低炭素エネルギー生産技術の研究開発」が追加されたことは、単なる軍事・治安分野だけでなく、サプライチェーンの強靭化やエネルギー転換といった新たな経済安全保障上の懸念が、規制の対象範囲を拡大させていることを示唆しています。このため、対象会社の事業内容を子会社レベルまで精査する、より詳細なデューデリジェンスの必要性が高まっています。
フランスのM&A関連最新判例
合併における刑事責任の承継
2024年5月22日付の最高裁判所(Cour de cassation)判決は、吸収合併における刑事責任の承継に関する重要な判断を示しました。従来の判例法理では、吸収合併により消滅した会社の法的独立性が失われるため、その刑事責任も消滅するとされていました。しかし、2020年11月25日付の判例でこの立場を転換し、特定の会社形態(SA、SASなど)に限って刑事責任の承継を認めました。
そして、2024年5月22日付の最新判決は、この法理をさらに拡大し、吸収合併における刑事責任の承継を、すべての会社形態(例:SARL)にも適用されると判断しました。最高裁は、この判決の理由として「被吸収会社の経済的・機能的な継続性」を挙げており、吸収会社と被吸収会社は同一性を有すると見なすべきであるという原則を打ち出しました。
この判例は、合併後の存続会社が被吸収会社の法的・行政的リスクを包括的に引き継ぐという考え方を強化するものです。したがって、M&Aにおけるデューデリジェンスでは、対象会社の過去のコンプライアンス違反や行政処分歴を、刑事罰の可能性まで含めて、より厳格に調査する必要性が高まっています。
株式譲渡契約における表明保証違反に関する損害賠償
2008年1月29日付の最高裁判所判例は、株式譲渡契約の表明保証に違反があった場合、たとえ買主が違反によって金銭的な損害を被っていなくても、賠償請求が認められる可能性があると判断しました。この判決の根拠は、フランス民法1134条(現1103条)の「合法的に締結された合意は、それを締結した当事者に対しては法律と同等の効力を有する」という原則にあります。
日本の実務では、賠償請求には原則として「損害の発生」が必要であるという考えが一般的ですが、フランスの裁判所は、契約の文言を文字通りに厳格に解釈する傾向が強いです。このため、契約で保証された事実と現実が異なるだけで、損害の有無にかかわらず、契約上の責任を追及する余地が生まれるのです。したがって、株式譲渡契約(SPA)の表明保証条項を起案する際には、その範囲と責任の限定を極めて慎重に行い、どのような場合に賠償を求めることができるのか(例:実際の損害が発生した場合のみ)を明確に記述する必要があります。
まとめ
フランスにおける現地法人の買収・M&Aは、株式譲渡、合併、事業譲渡といった多様なスキームを通じて実行可能です。しかし、これらの取引は、近年強化されている外国投資規制や、日本とは異なる独自の情報提供・協議プロセスを定める労働法など、複雑な法制度の網の目に置かれています。さらに、合併における刑事責任の承継や、表明保証違反に対する損害賠償に関する最新の判例は、デューデリジェンスの範囲と契約書作成の重要性を一層高めています。これらの法的環境の理解は、フランスでのM&Aを成功させるための鍵となります。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務