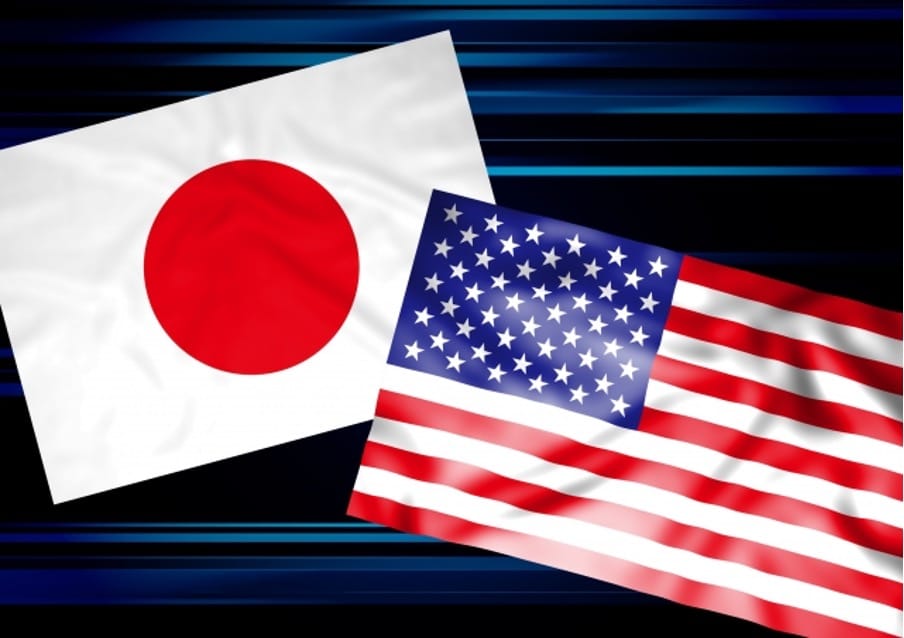イギリスにおける日本資本によるM&A・買収の法制度解説

イギリスは、長きにわたり国際的な金融の中心地であり、その法制度は成熟し確立されたものです。イギリスのM&A法制は、会社法(Companies Act 2006)という包括的な制定法を中核としつつ、コモン・ロー(Common Law)や、上場企業等の買収を規律するシティ・テイクオーバー・コード(The City Code on Takeovers and Mergers)が組み合わさって形成されています。日本の商法や会社法と似通った部分も多い一方で、買収スキーム、特に事業譲渡における従業員保護の仕組みや、近年の投資規制強化といった重要な違いが存在します。日本の経営者や法務担当者がイギリス市場で円滑にM&Aを進めるためには、これらの相違点を深く理解し、予見可能なリスクに備えることが不可欠です。
本稿では、イギリスM&Aの基本から、特定の産業分野に適用される最新の規制まで、網羅的に解説します。
この記事の目次
イギリスにおける会社形態と買収スキームの基本構造
イギリスの会社法制を理解する上で、まず重要となるのは、非公開有限責任会社(Private Limited Company、以下「LTD」)と公開有限責任会社(Public Limited Company、以下「PLC」)の区別です。イギリスの全法人数の約96%をLTDが占めており、日本資本による買収対象の大半はLTDとなります。
非公開会社(LTD)と公開会社(PLC)の特徴
LTDとPLCの最も根本的な違いは、株式の公開売却が可能か否かにあります。PLCは株式市場で株式を一般に公開して売却できますが、LTDはできません。この違いは、資金調達の容易さと、それに伴う法規制の厳格さの根本的な原因となります。PLCは最低5万ポンドの資本金が必要であり、そのうち4分の1以上が払込済みでなければなりません。また、少なくとも2名の取締役と資格を有する会社秘書役が必要とされます。これに対し、LTDは最低資本金の要件がなく、取締役も1名で足ります。
さらに、企業統治と情報開示の面でも大きな違いがあります。PLCには、より厳格な報告義務や企業統治(コーポレートガバナンス)に関する規則、情報開示要件が課されます。例えば、年次株主総会(AGM)の開催が義務付けられる一方、LTDは定款に規定がない限り、AGMの開催義務はありません。
これらの違いは、買収戦略に直接的な影響を与えます。PLCの厳格な情報開示義務は、買い手にとって詳細なデューデリジェンスを可能にする一方で、公開会社ゆえのテイクオーバー・コードや株主の公平性といった複雑なルールを遵守する必要が生じます。これに対し、LTDの買収は手続きが比較的簡素である反面、公的な情報が限られるため、より綿密な秘密保持契約(NDA)に基づく情報開示と、デューデリジェンスが不可欠となります。このことから、買収対象の会社形態によって、M&A戦略の初期段階から法務、財務、労務の各分野で取るべきアプローチが大きく異なることになります。日本の投資家は、まずこの根本的な違いを認識することが重要です。
株式取得と事業譲渡
買収対象となる会社形態を問わず、M&Aは主に「株式取得(Share Purchase)」または「事業譲渡(Asset Purchase)」の2つの手法で行われます。この部分は日本の法制度と基本的に同じです。
日本の法制度と最も大きな違いがあるのが、事業譲渡における従業員保護の仕組みです。日本では、事業譲渡に際して労働者の個別同意が必要となるのが一般的ですが、イギリスでは「Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 (TUPE)」という独自の法規制が存在します。TUPEは、事業の移転時に「組織全体または一部に割り当てられた」全従業員が、その雇用条件を維持したまま自動的に新雇用主(買い手)に引き継がれることを保護するものです。この原則は、日本の商法や会社法における事業譲渡の規律とは大きく異なります。日本の買い手は、事業譲渡を行う際、特定の従業員を選別して引き継ぐという日本の一般的な感覚で交渉を進めると、TUPE規則に抵触し、予期せぬ法的リスクや係争に発展する可能性があります。したがって、イギリスにおける事業譲渡を検討する日本の投資家は、買い手が従業員を「選ぶ」ことはできず、対象事業の従業員が自動的に承継されるというTUPEの原則を深く理解し、買収計画の初期段階から労務デューデリジェンスを徹底する必要があります。
イギリス会社法制に基づく買収手続と株式保有比率による要件
非公開会社(LTD)の買収は、主に売買当事者間の合意と契約(株式譲渡契約または資産譲渡契約)に基づいて進められます。これに対し、公開会社の買収は、会社法(Companies Act 2006)の枠組みを基盤としつつ、シティ・テイクオーバー・コード(The City Code on Takeovers and Mergers)という特殊なルールセットに厳格に規律されます。
公開会社の買収におけるシティ・テイクオーバー・コード
このコードの第一の目的は、買収対象会社の全ての株主が公平かつ平等に扱われることを保証することです。テイクオーバー・コードは、イギリスの準公的機関であるテイクオーバー・パネル(Takeover Panel)によって監督・執行されます。日本の証券取引所における公開買付(TOB)規制と類似していますが、パネルが広範な裁量権を持つという点で特異性があります。
契約上のオファーとスキーム・オブ・アレンジメント
公開会社の買収は、主に以下の二つの手法で行われます。
- 契約上のオファー(Contractual Offer): 買い手が、対象会社の株主一人ひとりに株式の買い取りを直接提案する手法です。買収成功の最低条件は、議決権の50%超の株式を取得することです。これにより、買い手は対象会社に対する支配権を確立できます。ただし、全株式(100%)を取得するためには、会社法に基づく「スクイーズ・アウト(Compulsory Squeeze-out)」手続を利用します。この手続には、公開買付(Offer)によって議決権の90%を取得することが条件となります。この手法は、対象会社の取締役会の協力を必ずしも必要としないため、敵対的買収に用いられることがあります。
- スキーム・オブ・アレンジメント(Scheme of Arrangement): 会社法(Companies Act 2006)に基づき、買収対象会社が主体となって、株主との間で「アレンジメント(合意)」を形成し、裁判所の承認を得る手法です。買収成功の要件は、対象会社の議決権株主のうち、人数ベースで過半数、かつ、議決権ベースで75%以上の賛成を得ることです。この条件が満たされ、裁判所が承認すれば、反対する株主も含め、全ての株主がその合意に法的に拘束されます。手続きの性質上、対象会社の取締役会が主導するため、友好的買収で主に利用されます。全株式の取得が比較的容易かつ迅速(通常2〜3ヶ月)である点が大きな利点です。
関連判例の紹介
イギリスのM&A法制は、制定法と判例法(コモン・ロー)が互いに影響し合い発展してきました。特に、スキーム・オブ・アレンジメントは、裁判所の裁量権が大きく、判例が重要な指針となります。
- Re SABMiller Plc EWHC 2153 (Ch):本件は、特定の株主グループを他の株主と「異なるクラス」として扱い、スキームの投票から除外することが裁判所によって認められた事例です。裁判所は、株主が自発的に投票権を放棄し、スキームに拘束されることに合意した場合、その株主は投票対象となる株主クラスから除外されるべきではないと判断しました。
- Re Uniq PLC EWHC 749 (Ch):この判例は、巨額の確定給付型年金債務を抱えていた企業が、年金債務の解消を目的とした事業再編に際し、スキーム・オブ・アレンジメントを活用した事例です。株主の持分が大幅に希薄化される内容でしたが、企業が差し迫った破産を回避するための唯一の選択肢として、裁判所がそのスキームを承認しました。
これらの判例は、スキーム・オブ・アレンジメントにおける裁判所の承認が、単なる形式的な手続きではないことを示しています。裁判所は、提案された合意が「公正かつ合理的」であるかを実質的に審査し、その際に株主間の議決権比率だけでなく、買収の目的、企業の財政状況、利害関係者(年金受給者など)への影響といった、より広範な要素を考慮して判断していることが読み取れます。これは日本の買収実務には見られない、イギリス法特有の重要なプロセスです。
特定分野におけるイギリスの投資規制と法的留意点

M&A取引において、買収対象の事業内容によっては、会社法制とは別に、特定の分野に適用される規制の遵守が求められます。
国家安全保障・投資法(National Security and Investment Act 2021:NSI Act)に基づく規制
2022年1月4日に施行されたNSI Actは、イギリスの安全保障に関わるM&A取引に対する政府の審査権限を大幅に強化するものです。これは、事業分野を問わず適用される会社法制とは異なり、買収対象の事業内容によって別途審査が義務付けられる「分野特化型規制」の最たる例です。
NSI Actは、特定の「必須届出対象分野(17分野)」に該当する事業を営むイギリス企業を買収する際、買収者がその議決権や株式の保有比率が25%、50%、75%を超える場合、または議決権のない株式を含め「支配権」を獲得する場合には、政府への事前届出が義務付けられています。この義務に違反して取引を完了した場合、その取引は無効となり、多額の罰金が課される可能性があります。
必須届出対象分野に該当しないM&Aであっても、政府は安全保障上の懸念があると判断した場合、その取引を審査対象として指定し、レビューを命じる「コールイン(call-in)」権限を有します。この権限は、取引完了後でも遡及的に行使される可能性があるため、注意が必要です。
| 分野名(日本語訳) | 分野名(英語) | 概要(例) |
|---|---|---|
| 高度素材 | Advanced Materials | 先端複合材、半導体、ナノテクノロジーなど |
| 高度ロボット工学 | Advanced Robotics | 自律的に環境と相互作用する物理的機械 |
| 人工知能 | Artificial Intelligence | 機械学習アプリケーション、ニューロモルフィック・プロセッサなど |
| 民間原子力 | Civil Nuclear | 原子力関連機器・サービスなど |
| 通信 | Communications | 通信ネットワークの提供など |
| コンピュータ・ハードウェア | Computing Hardware | AIアプリケーション用プロセッサの知的財産権や製造 |
| 政府への重要サプライヤー | Critical Suppliers to Government | 政府機関への物品、サービス、技術供給 |
| 暗号認証 | Cryptographic Authentication | 暗号技術や認証サービスの提供 |
| データ・インフラ | Data Infrastructure | 大規模なデータセンターなど |
| 防衛 | Defence | 軍事・防衛関連製品や技術 |
| エネルギー | Energy | 発電、送電、石油・ガス関連 |
| 軍事・軍民両用技術 | Military and Dual-Use | 軍事・民生双方に利用可能な技術 |
| 量子技術 | Quantum Technologies | 量子コンピュータ、量子暗号通信など |
| 衛星・宇宙技術 | Satellite and Space Technologies | 衛星関連システム・技術など |
| 救急サービスへのサプライヤー | Suppliers to the Emergency Services | 警察、消防、救急サービスへの供給 |
| 合成生物学 | Synthetic Biology | 研究開発、製品製造 |
| 輸送 | Transport | 主要な空港、港、駅など |
金融サービス・エネルギー分野における追加的規制
特定分野のM&Aでは、NSI Actとは別に、既存の規制当局への届出や承認が必要となる場合があります。
- 金融サービス: 金融機関、資産運用会社、フィンテック企業など、金融行為規制機構(Financial Conduct Authority:FCA)の監督下にある事業の買収は、金融サービス・市場法(Financial Services and Markets Act 2000)に基づき、FCAへの事前承認が求められます。この審査では、買収者が「適格かつ適正な人物(fit and proper person)」であるかが厳しく問われます。
- エネルギー: エネルギー産業の買収には、NSI Actに加えて、エネルギー法2023によって導入された新たな「エネルギー合併規制(Energy Mergers Regime)」が適用される可能性があります。この規制は、エネルギーネットワーク企業間の合併が、エネルギー規制庁(Ofgem)による比較分析と規制能力に悪影響を及ぼす可能性を審査することを目的としています。
これらの規制は、NSI Actを無効化するものではなく、既存の分野特化型規制の上に重ねて適用される追加的な規制レイヤーです。これにより、例えばエネルギー分野の買収案件が、競争・市場庁(CMA)、エネルギー規制庁(Ofgem)、そして国家安全保障・投資庁(Investment Security Unit)という複数の当局による審査を、並行して受ける可能性があることを意味します。このような多層的な審査プロセスは、M&Aの完了までの期間を長期化させ、取引の複雑性を増大させる結果を招くでしょう。
まとめ
イギリスM&Aは、非公開会社と公開会社で手続きが大きく異なり、株式取得と事業譲渡では、特に従業員の承継に関して日本とは異なるTUPE規則が存在する点が、日本の買収実務との重要な相違点です。また、近年の投資環境の変化により、NSI Actに代表される安全保障上の審査や、金融、エネルギーといった特定分野における厳格な規制が加わっており、買収の法的リスクを増大させています。
これらの複雑な法制度と多層的な規制を円滑に乗り越え、予期せぬリスクを回避するためには、イギリスの法実務に精通した専門家による法務サポートが不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務