2024е№ҙд»Ӣиӯ·е ұй…¬ж”№е®ҡгҒ«гӮҲгӮӢжёӣз®—гғӘгӮ№гӮҜеӣһйҒҝгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дёүеӨ§гӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№иҰҒ件гҒЁеҝ…иҰҒгҒӘжі•зҡ„еҜҫеҝң

2024е№ҙеәҰпјҲд»Өе’Ң6е№ҙеәҰпјүгҒ®д»Ӣиӯ·е ұй…¬ж”№е®ҡгҒҜгҖҒ3е№ҙгҒ«дёҖеәҰгҒ®еҲ¶еәҰиҰӢзӣҙгҒ—гҒ®дёӯгҒ§гӮӮгҖҒзү№гҒ«д»Ӣиӯ·гғ»зҰҸзҘүдәӢжҘӯдё»гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгҖҢжі•зҡ„гҒӘгғӘгӮ№гӮҜз®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶гҒ®зўәз«ӢгҖҚгӮ’еј·гҒҸиҝ«гӮӢз”»жңҹзҡ„гҒӘи»ўжҸӣзӮ№гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж”№е®ҡзҺҮиҮӘдҪ“гҒҜгғ—гғ©гӮ№гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®е®ҹж…ӢгҒҜгҖҒйҒӢе–¶еҹәжә–гҒ®зҫ©еӢҷеҢ–гӮ’еӨ§е№…гҒ«еј·еҢ–гҒ—гҖҒдҪ“еҲ¶гҒ®дёҚеӮҷгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒ«д»Ӣиӯ·е ұй…¬гҒҢжёӣз®—гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒзөҢе–¶гҒ«зӣҙзөҗгҒҷгӮӢиІЎеӢҷгғӘгӮ№гӮҜгӮ’зӣҙжҺҘзҡ„гҒ«зө„гҒҝиҫјгӮ“гҒ зӮ№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®иЎҢж”ҝжҢҮе°ҺгӮ„жҢҮе®ҡеҸ–ж¶ҲгҒ—гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…¬жі•дёҠгҒ®гғҡгғҠгғ«гғҶгӮЈгҒ«еҠ гҒҲгҖҒдәӢжҘӯжүҖгҒ®иІЎеӢҷгӮ’зӣҙж’ғгҒҷгӮӢж–°гҒҹгҒӘжі•зҡ„и„…еЁҒгҒЁгҒ—гҒҰиӘҚиӯҳгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
дәӢжҘӯдё»гҒҢзӣҙйқўгҒҷгӮӢдё»иҰҒгҒӘиӘІйЎҢгҒҜгҖҒжҘӯеӢҷз¶ҷз¶ҡиЁҲз”»пјҲBCPпјүгҒ®зӯ–е®ҡгҖҒй«ҳйҪўиҖ…иҷҗеҫ…йҳІжӯўжҺӘзҪ®гҖҒгҒқгҒ—гҒҰиә«дҪ“жӢҳжқҹзӯүгҒ®йҒ©жӯЈеҢ–гҒЁгҒ„гҒҶдёүгҒӨгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№иҰҒ件гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгӮ’зө„з№”зҡ„гҒ«е®ҹиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’е®ўиҰізҡ„гҒӘиЁҳйҢІгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЁјжҳҺгҒ§гҒҚгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒжёӣз®—гғӘгӮ№гӮҜгҒ«зӣҙйқўгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҲ©з”ЁиҖ…гҒЁгҒ®еҘ‘зҙ„жӣёгҖҒеҗ„зЁ®жҢҮйҮқгҖҒж—ҘгҖ…гҒ®иЁҳйҢІгҒҜгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„еҚҳгҒӘгӮӢеҪўејҸзҡ„гҒӘжӣёйЎһгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиЎҢж”ҝзӣЈжҹ»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҒӢе–¶еҹәжә–йҒөе®ҲгҒ®иЁјжҳҺжӣёгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдёҮгҒҢдёҖгҒ®дәӢж•…гӮ„гғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹйҡӣгҒ®жі•зҡ„йҳІеҫЎеЈҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жёӣз®—гғӘгӮ№гӮҜгӮ’еӣһйҒҝгҒ—гҖҒгҒҫгҒҹгҖҒжҢҮе®ҡеҸ–ж¶ҲгҒ—гӮ„иЁҙиЁҹгҒёгҒ®йҳІиЎӣгӮ’еӣігӮӢгҒҹгӮҒгҖҒ2024е№ҙж”№е®ҡгҒ®дёӯеҝғзҡ„гҒӘзҫ©еӢҷгҒЁгҖҒдәӢжҘӯдё»гҒҢзӣҙгҒЎгҒ«зқҖжүӢгҒҷгҒ№гҒҚе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№жҲҰз•ҘгӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
2024е№ҙд»Ӣиӯ·е ұй…¬ж”№е®ҡгҒ«гӮҲгӮӢгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гғӘгӮ№гӮҜгҒ®иІЎеӢҷеҢ–
д»ҠеӣһгҒ®ж”№е®ҡгҒ®жңҖеӨ§гҒ®з„ҰзӮ№гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·иҒ·е“ЎгҒ®еҮҰйҒҮж”№е–„пјҲ+0.98%пјүгӮ’еҗ«гӮҒгҒҹе…ЁдҪ“гҒ§+1.59%гҒ®ж”№е®ҡзҺҮгҒЁгҒ„гҒҶж§ӢйҖ гҒ®иЈҸеҒҙгҒ§гҖҒд»ҘдёӢгҒ®дёүгҒӨгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘйҒӢе–¶еҹәжә–зҫ©еӢҷеҢ–гҒ«дјҙгҒҶжёӣз®—жҺӘзҪ®гҒҢе°Һе…Ҙгғ»еј·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жҺӘзҪ®гҒҜгҖҒжі•д»ӨйҒөе®ҲгҒ®дёҚеӮҷгҒҢеҚіеә§гҒ«еҸҺзӣҠжёӣгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒеҺігҒ—гҒ„д»•зө„гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮжёӣз®—гҒҜгҖҒдҪ“еҲ¶дёҚеӮҷгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҹжңҲгҒ®зҝҢжңҲгҒӢгӮүгҖҒж”№е–„гҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢжңҲгҒҫгҒ§гҖҒеҲ©з”ЁиҖ…е…Ёе“ЎгҒ®жүҖе®ҡеҚҳдҪҚж•°гҒӢгӮүйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҖҒжңҖдҪҺгҒ§гӮӮ3гғ¶жңҲй–“гҒҜз¶ҷз¶ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жҘӯеӢҷз¶ҷз¶ҡиЁҲз”»пјҲBCPпјүжңӘзӯ–е®ҡжёӣз®—гҒ®еҺіж јеҢ–
зҒҪе®ігӮ„ж„ҹжҹ“з—Үзҷәз”ҹжҷӮгҒ«гӮӮгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®з¶ҷз¶ҡжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жҘӯеӢҷз¶ҷз¶ҡиЁҲз”»пјҲBCPпјүгҒ®зӯ–е®ҡгҒҜгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№дәӢжҘӯжүҖгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰзҫ©еӢҷеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮBCPгҒҢж„ҹжҹ“з—ҮеҜҫзӯ–гҒҠгӮҲгҒіиҮӘ然зҒҪе®іеҜҫзӯ–гҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜдёЎж–№гҒҢжңӘзӯ–е®ҡгҒ®е ҙеҗҲгҖҒжёӣз®—гҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жёӣз®—еҚҳдҪҚгҒҜгҖҒж–ҪиЁӯгғ»еұ…дҪҸзі»гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҜжүҖе®ҡеҚҳдҪҚж•°гҒ®3%гҒҢгҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҜ1%гҒҢжёӣз®—гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒиЁӘе•Ҹзі»гӮөгғјгғ“гӮ№гҖҒзҰҸзҘүз”Ёе…·иІёдёҺгҖҒеұ…е®…д»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»Өе’Ң7е№ҙ3жңҲ31ж—ҘгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҖҒжёӣз®—гҒ®йҒ©з”ЁгҒҢзҢ¶дәҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒBCPзӯ–е®ҡгҒ®зҫ©еӢҷгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜж—ўгҒ«зҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзҢ¶дәҲжңҹй–“зөӮдәҶгӮ’еҫ…гҒҹгҒҡгҒ«йҖҹгӮ„гҒӢгҒӘзӯ–е®ҡгҒЁе®ҹиЎҢдҪ“еҲ¶гҒ®ж§ӢзҜүгҒҢеҝ…й ҲгҒ§гҒҷгҖӮ
BCPгҒ®жңӘзӯ–е®ҡгҒҜгҖҒиЎҢж”ҝжҢҮе°ҺгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеӨ§иҰҸжЁЎзҒҪе®ізҷәз”ҹжҷӮгҒ«гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣгҒҢгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒЁгҒ®еҘ‘зҙ„иІ¬д»»пјҲе®үе…Ёй…Қж…®зҫ©еӢҷйҒ•еҸҚпјүгӮ’е•ҸгӮҸгӮҢгӮӢж°‘дәӢиЁҙиЁҹгғӘгӮ№гӮҜгҒ«гӮӮз№ӢгҒҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжёӣз®—еӣһйҒҝд»ҘдёҠгҒ®жі•зҡ„ж„Ҹзҫ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
й«ҳйҪўиҖ…иҷҗеҫ…йҳІжӯўжҺӘзҪ®жңӘе®ҹж–Ҫжёӣз®—гҒЁиә«дҪ“жӢҳжқҹйҒ©жӯЈеҢ–
й«ҳйҪўиҖ…иҷҗеҫ…гҒ®йҳІжӯўжҺӘзҪ®пјҲжҢҮйҮқзӯ–е®ҡгҖҒ委員дјҡиЁӯзҪ®гҖҒе®ҡжңҹзҡ„з ”дҝ®гҒ®е®ҹж–ҪпјүгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҜҶжҺҘгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢиә«дҪ“жӢҳжқҹзӯүгҒ®йҒ©жӯЈеҢ–гҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹжҺӘзҪ®гҒҜгҖҒдәәж је°ҠйҮҚзҫ©еӢҷгҒ®еұҘиЎҢгӮ’жӢ…дҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҒӢе–¶еҹәжә–дёҠгҒ®еҝ…й Ҳй …зӣ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҺӘзҪ®гҒҢйҒ©еҲҮгҒ«и¬ӣгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒгҖҢиҷҗеҫ…йҳІжӯўжҺӘзҪ®жңӘе®ҹж–Ҫжёӣз®—гҖҚгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®жёӣз®—гҒ®гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸгҖҒж–ҪиЁӯгғ»еұ…дҪҸзі»гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҜжүҖе®ҡеҚҳдҪҚж•°гҒ®10%гҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§гҒҜ1%гҒҢжёӣз®—гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«ж–ҪиЁӯзі»гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ10%гҒЁгҒ„гҒҶжёӣз®—зҺҮгҒҜзөҢе–¶гӮ’зӣҙж’ғгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдёҚйҒ©еҲҮгҒӘиә«дҪ“жӢҳжқҹгӮ„дёҚеҪ“гҒӘйҡ”йӣўиЎҢзӮәгҒҜгҖҒгҖҢдәәж је°ҠйҮҚзҫ©еӢҷйҒ•еҸҚгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰй«ҳйҪўиҖ…иҷҗеҫ…гҒЁиҰӢгҒӘгҒ•гӮҢгҖҒжҢҮе®ҡеҸ–ж¶ҲгҒ—еҮҰеҲҶгҒ«иҮігӮӢйҮҚеӨ§гҒӘгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжҢҮйҮқгҒ®зӯ–е®ҡгҒЁйҒӢз”ЁгҒҜгҖҒдәәжЁ©ж“Ғиӯ·гҒЁдәӢжҘӯз¶ҷз¶ҡгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жңҖйҮҚиҰҒиӘІйЎҢгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
| жҘӯеӢҷз¶ҷз¶ҡпјҲBCPпјүжңӘзӯ–е®ҡжёӣз®— | й«ҳйҪўиҖ…иҷҗеҫ…йҳІжӯўжҺӘзҪ®жңӘе®ҹж–Ҫжёӣз®— | иә«дҪ“жӢҳжқҹзӯүгҒ®йҒ©жӯЈеҢ– | |
|---|---|---|---|
| жҺӘзҪ®гҒ®зҫ©еӢҷеҢ–еҶ…е®№ | ж„ҹжҹ“з—ҮеҜҫзӯ–гҒҠгӮҲгҒіиҮӘ然зҒҪе®іеҜҫзӯ–гӮ’еҢ…еҗ«гҒ—гҒҹBCPгҒ®зӯ–е®ҡгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҹәгҒҘгҒҸжҺӘзҪ®гӮ’и¬ӣгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁ | иҷҗеҫ…йҳІжӯўжҢҮйҮқзӯ–е®ҡгҖҒ委員дјҡиЁӯзҪ®гҖҒе®ҡжңҹзҡ„з ”дҝ®гҒ®е®ҹж–Ҫ | иә«дҪ“жӢҳжқҹйҒ©жӯЈеҢ–гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жҢҮйҮқзӯ–е®ҡгҖҒ委員дјҡиЁӯзҪ®гҖҒз ”дҝ®гҒ®е®ҹж–Ҫ |
| жёӣз®—йҒ©з”ЁжҷӮжңҹпјҲзөҢйҒҺжҺӘзҪ®пјү | иЁӘе•Ҹзі»гӮөгғјгғ“гӮ№гҖҒзҰҸзҘүз”Ёе…·иІёдёҺгҖҒеұ…е®…д»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙгҒҜд»Өе’Ң7е№ҙ3жңҲ31ж—ҘгҒҫгҒ§зҢ¶дәҲпјҲзҫ©еӢҷиҮӘдҪ“гҒҜзҷәз”ҹпјү гҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒҜ2024е№ҙ4жңҲ1ж—ҘгӮҲгӮҠйҒ©з”Ё | еұ…е®…зҷӮйӨҠз®ЎзҗҶжҢҮе°ҺгҖҒзү№е®ҡзҰҸзҘүз”Ёе…·иІ©еЈІгӮ’йҷӨгҒҸе…ЁгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ§йҒ©з”Ёй–Ӣе§Ӣ | 2024е№ҙ4жңҲ1ж—ҘгӮҲгӮҠйҒ©з”Ё |
| жҺӘзҪ®жңӘе®ҹж–ҪгҒ®е ҙеҗҲгҒ®жёӣз®—еҚҳдҪҚ | ж–ҪиЁӯгғ»еұ…дҪҸзі»гӮөгғјгғ“гӮ№пјҡжүҖе®ҡеҚҳдҪҚж•°гҒ®3%жёӣз®— гҒқгҒ®д»–гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№пјҡжүҖе®ҡеҚҳдҪҚж•°гҒ®1%жёӣз®—гҖӮ | ж–ҪиЁӯгғ»еұ…дҪҸзі»гӮөгғјгғ“гӮ№пјҡжүҖе®ҡеҚҳдҪҚж•°гҒ®10%жёӣз®— гҒқгҒ®д»–гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№пјҡжүҖе®ҡеҚҳдҪҚж•°гҒ®1%жёӣз®— | ж–ҪиЁӯгғ»еұ…дҪҸзі»гӮөгғјгғ“гӮ№пјҡжүҖе®ҡеҚҳдҪҚж•°гҒ®10%жёӣз®— гҒқгҒ®д»–гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№пјҡжүҖе®ҡеҚҳдҪҚж•°гҒ®1%жёӣз®— |
жі•зҡ„йҳІеҫЎгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘд»Ӣиӯ·дәӢжҘӯжүҖгҒ®еҜҫеҝң

жёӣз®—гғӘгӮ№гӮҜгҖҒиЎҢж”ҝеҮҰеҲҶгғӘгӮ№гӮҜгҖҒгҒқгҒ—гҒҰиЁҙиЁҹгғӘгӮ№гӮҜгҒ®дёүж–№гҒӢгӮүдәӢжҘӯжүҖгӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдәӢжҘӯдё»гҒҜд»ҘдёӢгҒ®е…·дҪ“зҡ„гӮҝгӮ№гӮҜгӮ’зө„з№”зҡ„гҒ«е®ҹиЎҢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®иЁјжӢ гҒЁгҒӘгӮӢж–ҮжӣёгӮ’йҖҹгӮ„гҒӢгҒ«ж•ҙеӮҷгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
BCPзӯ–е®ҡеҫҢгҒ®иЁ“з·ҙгғ»иҰӢзӣҙгҒ—гҒ®еҫ№еә•
BCPгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«зӯ–е®ҡгҒҷгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжі•зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒзӯ–е®ҡгҒ—гҒҹBCPгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒӘиҰӢзӣҙгҒ—гҖҒиҒ·е“ЎгҒёгҒ®з ”дҝ®гҖҒгҒҠгӮҲгҒіиЁ“з·ҙгӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғӘгӮ№гӮҜз’°еўғпјҲиҮӘ然зҒҪе®ігҒ®й »зҷәеҢ–гҖҒгӮөгӮӨгғҗгғјж”»ж’ғгҒ®й«ҳеәҰеҢ–гҒӘгҒ©пјүгҒҜе№ҙгҖ…еӨүеҢ–гҒ—гҖҒзө„з№”гӮ„жҘӯеӢҷеҶ…е®№гӮӮеӨүгӮҸгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒBCPгӮ’е®ҡжңҹзҡ„гҒӘиҰӢзӣҙгҒ—пјҲдҫӢпјҡе№ҙ1еӣһгҒ®з·ҸзӮ№жӨңгӮ„гҖҒзҒҪе®ізҷәз”ҹеҫҢгҒ®еҚіжҷӮиҰӢзӣҙгҒ—пјүгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰжңҖж–°гҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒ«йҒ©еҝңгҒ•гҒӣгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒ®жңүеҠ№жҖ§гӮ’еӨұгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңәдёҠиЁ“з·ҙгӮ„е®ҹең°иЁ“з·ҙгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒеҫ“жҘӯе“ЎгҒҢз·ҠжҖҘжҷӮгҒ®жүӢй ҶгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒе®ҹиЎҢгҒ§гҒҚгӮӢдҪ“еҲ¶гӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҖҒгҒқгҒ®иЁҳйҢІгӮ’ж®ӢгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒиЎҢж”ҝзӣЈжҹ»гҒ§BCPгҒҢж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘиЁјжӢ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иә«дҪ“жӢҳжқҹзӯүгҒ®йҒ©жӯЈеҢ–гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дёүгҒӨгҒ®иЁјжӢ
иә«дҪ“жӢҳжқҹгҒ®йҒ©жӯЈеҢ–гҒ®жҺӘзҪ®гҒҜгҖҒжҢҮйҮқгҒ®еӯҳеңЁгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзө„з№”зҡ„гҒӘж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒЁе®ҹиЎҢдҪ“еҲ¶гҒ®иЁјжҳҺгҒҢиЎҢж”ҝжҢҮе°ҺгҒ®з„ҰзӮ№гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®дёүгҒӨгҒ®гҖҢзө„з№”зҡ„иЁјжӢ гҖҚгҒ®зўәз«ӢгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒиә«дҪ“жӢҳжқҹйҒ©жӯЈеҢ–гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жҢҮйҮқгӮ’зӯ–е®ҡгҒ—гҖҒжӢҳжқҹгҒҢеҺҹеүҮзҰҒжӯўгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҖҒгӮ„гӮҖгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ®еҺіж јгҒӘ3иҰҒ件пјҲеҲҮиҝ«жҖ§гғ»йқһд»ЈжӣҝжҖ§гғ»дёҖжҷӮжҖ§пјүгҒЁгҒқгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгӮ’жҳҺж–ҮеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҢйқһд»ЈжӣҝжҖ§гҖҚгҒ®з«ӢиЁјгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжӢҳжқҹгӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жӨңиЁҺгҒ—гҖҒе®ҹиЎҢгҒ—гҒҹе…ЁгҒҰгҒ®д»Јжӣҝзӯ–гҒЁгҒқгҒ®еҠ№жһңгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе…·дҪ“зҡ„гҒӘзҗҶз”ұгӮ’гҖҒжҢҮйҮқгҒ«иЈҸд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹжүӢз¶ҡгҒҚгҒЁгҒ—гҒҰж–ҮжӣёгҒ§и©ізҙ°гҒ«иЁҳйҢІгҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒиә«дҪ“жӢҳжқҹйҒ©жӯЈеҢ–жӨңиЁҺ委員дјҡгӮ’е№ҙ1еӣһд»ҘдёҠй–ӢеӮ¬гҒ—гҖҒжӢҳжқҹгҒ®е®ҹж–ҪзҠ¶жіҒгҒ®иӘҝжҹ»гӮ„еҖӢеҲҘдәӢдҫӢгҒ®жӨңиЁҺгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгҒқгҒ®иӯ°дәӢйҢІгӮ’дҪңжҲҗгғ»дҝқз®ЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ委員дјҡгҒҜгҖҒжҢҮйҮқгҒ®зҗҶеҝөгҒҢзө„з№”зҡ„гҒ«е®ҹиЎҢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘиЁјжӢ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖеҫҢгҒ«гҖҒе…Ёеҫ“жҘӯиҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒиҷҗеҫ…йҳІжӯўгғ»иә«дҪ“жӢҳжқҹгҒ®йҒ©жӯЈеҢ–гҒ«й–ўгҒҷгӮӢе®ҡжңҹзҡ„гҒӘз ”дҝ®гӮ’е№ҙ1еӣһд»ҘдёҠе®ҹж–ҪгҒ—гҖҒгҒқгҒ®е®ҹж–ҪиЁҳйҢІгӮ’дҝқз®ЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…й ҲгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®з ”дҝ®иЁҳйҢІгҒҜгҖҒе…ЁиҒ·е“ЎгҒёгҒ®е‘ЁзҹҘеҫ№еә•гҒ®иЁјжӢ гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжёӣз®—гӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҝ…й ҲиҰҒ件гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒзӯ–е®ҡгҒ—гҒҹжҢҮйҮқгӮ„йҒӢе–¶иҰҸзЁӢгҒӘгҒ©гҒ®йҮҚиҰҒдәӢй …гӮ’гӮҰгӮ§гғ–гӮөгӮӨгғҲзӯүгҒ§е…¬иЎЁгҒ—гҖҒеҲ©з”ЁиҖ…зӯүгҒҢиҮӘз”ұгҒ«й–ІиҰ§гҒ§гҒҚгӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҲ©з”ЁиҖ…еҘ‘зҙ„жӣёгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„иҰӢзӣҙгҒ—гҒЁгғӘгӮ№гӮҜеҜҫеҝң
еҲ©з”ЁиҖ…еҘ‘зҙ„жӣёгҒҜгҖҒиЎҢж”ҝзӣЈжҹ»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҒӢе–¶еҹәжә–йҒөе®ҲгҒ®иЁјжҳҺжӣёгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘжі•зҡ„ж–ҮжӣёгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒЁгҒ®еҘ‘зҙ„жӣёгҒ«гҖҒдәӢжҘӯиҖ…гҒ®зҫ©еӢҷгҒЁгҒ—гҒҰдәәжЁ©е°ҠйҮҚгӮ„иә«дҪ“жӢҳжқҹзҰҒжӯўгҒ®зҫ©еӢҷгҖҒд»Ӣиӯ·дәӢж•…зҷәз”ҹжҷӮгҒ®е®¶ж—Ҹгғ»иЎҢж”ҝгҒёгҒ®йҖҹгӮ„гҒӢгҒӘйҖЈзөЎзҫ©еӢҷгӮ’жҳҺж–ҮеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиЎҢж”ҝзӣЈжҹ»гҒёгҒ®йҳІеҫЎзӯ–гҒЁгҒӘгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒдәӢж•…зҷәз”ҹеҫҢгҒ®е®¶ж—Ҹгғ»иЎҢж”ҝгҒЁгҒ®дҝЎй јз¶ӯжҢҒгӮ’еј·еҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®йҒ©жӯЈжҖ§гӮ’жӢ…дҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҖӢеҲҘж”ҜжҸҙиЁҲз”»гҒ«еҹәгҒҘгҒҸе®ҡжңҹзҡ„гҒӘгғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°пјҲ6гҒӢжңҲгҒ«1еӣһд»ҘдёҠпјүгӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢж—ЁгӮ’еҘ‘зҙ„жӣёгҒ«жҳҺж–ҮеҢ–гҒ—гҖҒгҒқгҒ®е®ҹж–ҪиЁҳйҢІгӮ’еҫ№еә•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйҒӢе–¶еҹәжә–йҒөе®ҲгҒ®иЁјжҳҺгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒдәӢжҘӯиҖ…еҒҙгҒӢгӮүгҒ®еҘ‘зҙ„и§ЈйҷӨпјҲйҖҖжүҖпјүгҒ«гҒҜгҖҒжі•д»ӨгҒ«гӮҲгӮӢеҺігҒ—гҒ„еҲ¶зҙ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҘ‘зҙ„жӣёгҒ«гҖҢд»–гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢи‘—гҒ—гҒ„дәәжЁ©дҫөе®іиЎҢзӮәгҖҚгҖҢй•·жңҹй–“гҒ«гӮҸгҒҹгӮӢеҲ©з”Ёж–ҷгҒ®ж»һзҙҚгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒе…ёеһӢзҡ„гҒӘи§ЈйҷӨдәӢз”ұгӮ’жҳҺиЁҳгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒи§ЈйҷӨгҒ«йҡӣгҒ—гҒҰдәӢеүҚгҒ®еҚҒеҲҶгҒӘжҢҮе°ҺгҖҒж”№е–„ж©ҹдјҡгҒ®жҸҗдҫӣгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’еҺіж јгҒ«иёҸгҒҝгҖҒгҒқгҒ®зөҢйҒҺгӮ’иЁҳйҢІгҒ«ж®ӢгҒҷж—ЁгӮ’иҰҸе®ҡгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒдёҚеҪ“гҒӘжҸҗдҫӣжӢ’еҗҰгҒЁеҲӨж–ӯгҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е°ұеҠҙз¶ҷз¶ҡж”ҜжҸҙA/BеһӢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҠҙеӢҷгғӘгӮ№гӮҜгҒёгҒ®еҜҫеҝң
гҒӘгҒҠгҖҒе°ұеҠҙз¶ҷз¶ҡж”ҜжҸҙдәӢжҘӯжүҖгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢиіғйҮ‘гҖҚгҒЁгҖҢе·ҘиіғгҖҚгҒ®жі•зҡ„еҢәеҲҘгҒҢеҠҙеӢҷгғӘгӮ№гӮҜгҒ®ж ёеҝғгҒ§гҒҷгҖӮAеһӢпјҲйӣҮз”ЁеһӢпјүгҒҜеҠҙеғҚеҹәжә–жі•дёҠгҒ®гҖҢиіғйҮ‘гҖҚгӮ’ж”Ҝжү•гҒ„жңҖдҪҺиіғйҮ‘гҒҢдҝқйҡңгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒBеһӢпјҲйқһйӣҮз”ЁеһӢпјүгҒҜжҙ»еӢ•гҒ«еҝңгҒҳгҒҹгҖҢе·ҘиіғгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжңҖдҪҺиіғйҮ‘жі•гҒ®дҝқйҡңгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е°ұеҠҙз¶ҷз¶ҡж”ҜжҸҙAеһӢдәӢжҘӯжүҖгҒҜгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒЁгҒ®еҘ‘зҙ„жӣёгӮ„зөҰдёҺиҰҸзЁӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢиіғйҮ‘гҖҚгҒЁгҖҢе·ҘиіғгҖҚгҒ®з”ЁиӘһгӮ’еҺіж јгҒ«еҢәеҲҘгҒ—гҖҒйӣҮз”ЁеҘ‘зҙ„гҒ«еҹәгҒҘгҒҸиіғйҮ‘иҰҸзЁӢгҒЁгҒ—гҒҰжҳҺзўәгҒ«еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮAеһӢдәӢжҘӯиҖ…гҒҢиӘӨгҒЈгҒҰгҖҢе·ҘиіғгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶз”ЁиӘһгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒе®ҹж…ӢгҒҢйӣҮз”ЁеҘ‘зҙ„гҒЁиҰӢгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢжҙ»еӢ•гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮҠгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒжңҖдҪҺиіғйҮ‘дҝқйҡңзҫ©еӢҷйҒ•еҸҚгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒжңӘжү•гҒ„иіғйҮ‘гҒ®йҒЎеҸҠж”Ҝжү•пјҲгғҗгғғгӮҜгғҡгӮӨпјүгҒ«гӮҲгӮӢиҮҙе‘Ҫзҡ„гҒӘиІЎеӢҷгғӘгӮ№гӮҜгӮ’жӢӣгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
иЁҙиЁҹгғӘгӮ№гӮҜгҒ«еӮҷгҒҲгӮӢгҖҢжі•зҡ„иЁјжӢ гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®д»Ӣиӯ·дәӢжҘӯжүҖгҒ®иЁҳйҢІз®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶
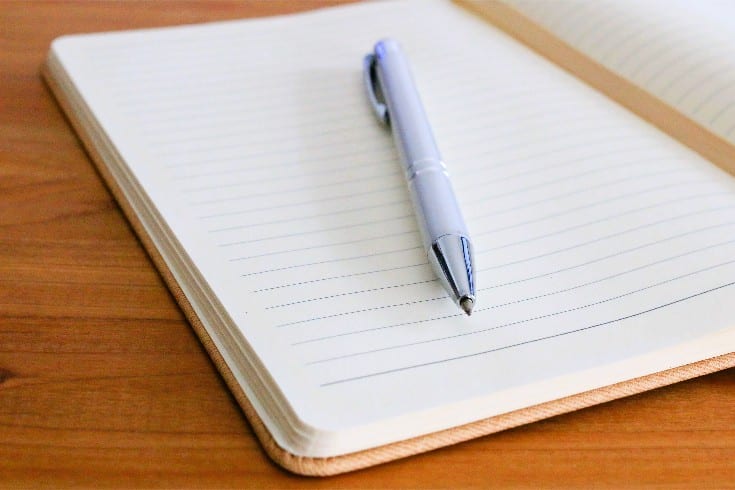
иЎҢж”ҝжҢҮе°ҺгӮ„жёӣз®—гғӘгӮ№гӮҜгҒ«еҠ гҒҲгҖҒд»Ӣиӯ·дәӢж•…иЁҙиЁҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж°‘дәӢдёҠгҒ®жҗҚе®іиі е„ҹиІ¬д»»гӮӮдәӢжҘӯз¶ҷз¶ҡгӮ’и„…гҒӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮиЁҙиЁҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰдәӢжҘӯиҖ…гҒҢе•ҸгӮҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒж°‘жі•дёҠгҒ®е®үе…Ёй…Қж…®зҫ©еӢҷгӮ’е°ҪгҒҸгҒ—гҒҹгҒӢгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҢдәӢж•…гҒ®дәҲиҰӢеҸҜиғҪжҖ§гҖҚгҒЁгҖҢзөҗжһңеӣһйҒҝзҫ©еӢҷгҖҚгҒ®жңүз„ЎгҒ§гҒҷгҖӮ
гғӘгӮ№гӮҜгӮўгӮ»гӮ№гғЎгғігғҲгҒЁеҜҫзӯ–иЁҳйҢІгҒ®йҖЈеӢ•
дәӢжҘӯиҖ…гҒҜгҖҒж—Ҙеёёзҡ„гҒ«гғӘгӮ№гӮҜгӮ’зү№е®ҡгҒ—гҖҒи»Ҫжёӣзӯ–гӮ’жұәе®ҡгҒҷгӮӢгҖҢгғӘгӮ№гӮҜгӮўгӮ»гӮ№гғЎгғігғҲгҖҚгӮ’е®ҡжңҹзҡ„гҒ«е®ҹж–ҪгҒ—гҖҒгҒқгҒ®зөҗжһңгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҹәгҒҘгҒҚи¬ӣгҒҳгҒҹе…·дҪ“зҡ„гҒӘе®үе…ЁеҜҫзӯ–гӮ’и©ізҙ°гҒ«иЁҳйҢІгҒ«ж®ӢгҒ•гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гҒ®иЁҳйҢІгҒ“гҒқгҒҢгҖҒдәӢжҘӯиҖ…гҒҢзөҗжһңеӣһйҒҝзҫ©еӢҷгӮ’еұҘиЎҢгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷжұәе®ҡзҡ„гҒӘжі•зҡ„иЁјжӢ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдәӢж•…зҷәз”ҹжҷӮгҒ®зөҢз·ҜгҖҒеҺҹеӣ гҖҒеҜҫзӯ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе…ЁиҒ·е“ЎгҒҢе…ұйҖҡиӘҚиӯҳгӮ’жҢҒгҒҰгӮӢгӮҲгҒҶдҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹдәӢж•…е ұе‘ҠжӣёгҒҜгҖҒж–ҪиЁӯгҒҢе®үе…Ёй…Қж…®зҫ©еӢҷгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ®еј·еҠӣгҒӘиЈҸд»ҳгҒ‘гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иә«дҪ“жӢҳжқҹдёӯгҒ®гҖҢеҠӘеҠӣгҒ®иЁјжӢ гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®иЁҳйҢІгҒ®иіӘ
иә«дҪ“жӢҳжқҹгҒ®дәӢдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒжӢҳжқҹгҒҢдҫӢеӨ–зҡ„гҒ«иЁұе®№гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҢдёҖжҷӮжҖ§гҖҚгҒҢжӢ…дҝқгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒ®гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮеҲӨдҫӢгҒҢзӨәгҒҷж•ҷиЁ“гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз·ҠжҖҘжҷӮгҒ®жӢҳжқҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒиҒ·е“ЎгҒҢж·ұеӨңгҒ«й•·жҷӮй–“гҒ«гӮҸгҒҹгӮҠд»ЈжӣҝеҠӘеҠӣпјҲгӮӘгғ гғ„дәӨжҸӣгҖҒж°ҙеҲҶиЈңзөҰгҖҒеЈ°гҒӢгҒ‘гҒӘгҒ©пјүгӮ’е°ҪгҒҸгҒ—гҖҒйҖҹгӮ„гҒӢгҒ«жӢҳжқҹгӮ’и§ЈйҷӨгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹдәӢе®ҹгҒҢгҖҒи©ізҙ°гҒӘиЁҳйҢІгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЁјжҳҺгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәӢжҘӯиҖ…гҒҢжҗҚе®іиі е„ҹиІ¬д»»гҒ®йҳІеҫЎжқҗж–ҷгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹдәӢдҫӢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҪўејҸзҡ„гҒӘжӢҳжқҹжҷӮй–“гҒ®иЁҳйҢІгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®й–“гҒ«е°ҪгҒҸгҒ•гӮҢгҒҹгӮұгӮўеҠӘеҠӣгҒЁд»Јжӣҝзӯ–гҒ®и©ҰиЎҢгӮ’и©ізҙ°гҒ«ж–ҮжӣёеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒжі•зҡ„гҒӘйҳІеҫЎгҒ®иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒпјҡд»Ӣиӯ·е ұй…¬жёӣз®—гғӘгӮ№гӮҜгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгӮ’
2024е№ҙеәҰд»Ӣиӯ·е ұй…¬ж”№е®ҡгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·жҘӯз•ҢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжі•д»ӨйҒөе®ҲгӮ’гҖҒдәӢжҘӯз¶ҷз¶ҡгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жңҖе„Әе…ҲгғӘгӮ№гӮҜгғһгғҚгӮёгғЎгғігғҲгҒёгҒЁдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘зӣҙгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮBCPгҒ®жңӘзӯ–е®ҡгҖҒиҷҗеҫ…йҳІжӯўжҺӘзҪ®гҒ®дёҚеӮҷгҖҒиә«дҪ“жӢҳжқҹгҒ®йҒӢз”ЁдёҚеҫ№еә•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№гҒ®ж¬ йҷҘгҒҜгҖҒд»ҠеҫҢгҖҒжёӣз®—гҒЁгҒ„гҒҶзӣҙжҺҘзҡ„гҒӘиІЎеӢҷгғӘгӮ№гӮҜгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдәӢжҘӯзөҢе–¶гӮ’зӣҙж’ғгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢжҘӯдё»гҒҢжҺЎгӮӢгҒ№гҒҚжҲҰз•ҘгҒҜгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…еҘ‘зҙ„жӣёгҖҒе·Ҙиіғж”ҜзөҰиҰҸзЁӢгҖҒиә«дҪ“жӢҳжқҹжҢҮйҮқгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…ЁгҒҰгҒ®жі•зҡ„ж–ҮжӣёгӮ’гҖҒжңҖж–°гҒ®жі•д»ӨгҒЁиЎҢж”ҝжҢҮе°ҺгҒ®еӢ•еҗ‘гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰж•ҙеӮҷгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҶ…е®№гӮ’зө„з№”гҒ®е®ҹеӢҷгҒ§е®ҹиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’и©ізҙ°гҒӘиЁҳйҢІгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЈҸд»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮиЁҳйҢІгҒ®еҪўйӘёеҢ–гҒҜгҖҒиЎҢж”ҝжҢҮе°ҺгӮ„жҢҮе®ҡеҸ–ж¶ҲгҒ—гҖҒиЁҙиЁҹгғӘгӮ№гӮҜгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢжңҖеӨ§гҒ®иҰҒеӣ гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж–ҮжӣёгҒЁе®ҹеӢҷгҒ®ж•ҙеҗҲжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒ—гҖҒжі•зҡ„гҒӘйҳІеҫЎгӮ’ж—©жңҹгҒ«еӣәгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒдәӢжҘӯгҒ®е®үе®ҡзҡ„гҒӘз¶ҷз¶ҡгҒЁжҲҗй•·гӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иҰҒи«ҰгҒ§гҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«гӮҲгӮӢеҜҫзӯ–гҒ®гҒ”жЎҲеҶ…
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®иӨҮйӣ‘еҢ–гҒҷгӮӢд»Ӣиӯ·гғ»йҡңе®ізҰҸзҘүеҲҶйҮҺгҒ®жі•д»ӨиҰҒ件гҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҢдәӢжҘӯз¶ҷз¶ҡгҒ«дёҺгҒҲгӮӢеҪұйҹҝгӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңҖж–°гҒ®жі•д»Өж”№жӯЈгӮ„иЎҢж”ҝгҒ®жҢҮе°ҺеӢ•еҗ‘гӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҖҒиІҙзӨҫгҒ®е®ҹжғ…гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹе®ҹеҠ№жҖ§гҒ®й«ҳгҒ„иҰҸзЁӢзӯ–е®ҡгҖҒеҘ‘зҙ„жӣёж•ҙеӮҷгҖҒгҒҠгӮҲгҒій–ўйҖЈж–ҮжӣёгҒ®ж•ҙеӮҷгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒжі•дәәе…ЁдҪ“гҒ®жі•зҡ„йҳІеҫЎгӮ’ж—©жңҹгҒ«зўәз«ӢгҒ—гҖҒдәӢжҘӯгҒ®е®үе®ҡзҡ„гҒӘз¶ҷз¶ҡгҒЁжҲҗй•·гӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮөгғқгғјгғҲгӮ’гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: д»Ӣиӯ·дәӢжҘӯд»Ӣиӯ·ж–ҪиЁӯ


































