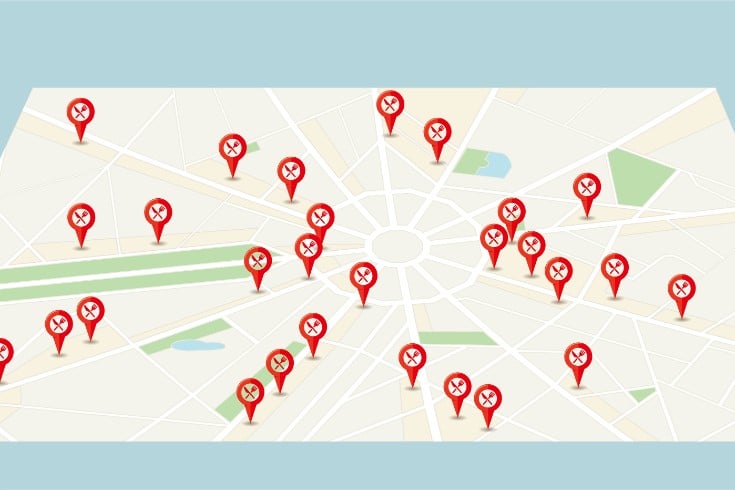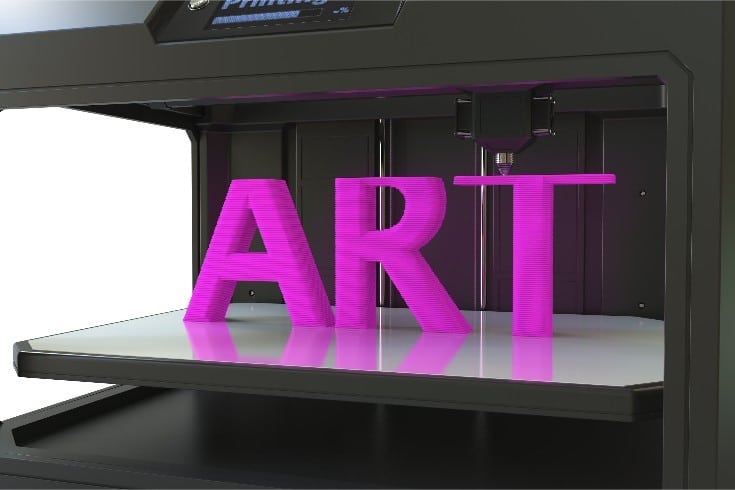量産される工業製品に著作性はあるのか?意匠法との関係も解説

美術が著作権の保護対象になる点は容易にイメージできると思います。ですが、一言で「美術」と言ってもその範囲は幅広く、様態も様々です。
「美術」という言葉は2つに分類されます。ひとつが、絵画、版画や彫刻などのように、鑑賞目的として創作される「純粋美術」、もうひとつが、美術を実用品に応用した「応用美術」です。
とはいえ、両者の峻別は容易ではありません。一例として、純粋美術と応用美術にも含まれるものとして、「美術工芸品」があります。
美術工芸品とは、実用性を備えつつ鑑賞性を重視した美術品のことで、仏像や装身具などがその例です。この美術工芸品は、著作権法第2条2項の、
この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする
によって、著作権法で保護されています。このように、「美術」の著作性の判断はかなり難しいのが現状です。
美術工芸品以外の工業製品などの応用美術に、著作権が発生するか否かが裁判で問題になることがあります。ここでは、応用美術は、著作権法ではどのように考えられているかを説明します。
この記事の目次
応用美術をめぐる裁判例

我が国の裁判例は、伝統的に、鑑賞の対象となる純粋美術にのみ著作物性が認められ、工業製品のような応用美術が著作物性を有するのは、著作権法上明示的に著作物性が認められている「美術工芸品」に限られるとの考えに立ってきました。
独立の鑑賞の対象にならない工業製品のデザインは、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」という要件を満たさないと考えられてきたのです。
その背景には、工業デザインなどは、意匠法によって保護されるべきであり、著作権法による70年という非常に長い保護には馴染まないという考え方があります。
意匠法の存続期間は、2020年4月1日以降の意匠登録出願からは、従来の20年から25年に延長されることとなりましたが、依然として著作権法による保護と比べると、圧倒的に短い期間です。
また、著作権法と意匠法の重複適用を緩くすると、意匠法の存在意義がなくなりかねないという見解も根強くありました。
赤とんぼ事件

応用美術品の著作物性が争われた裁判では、原告会社が多量に生産し販売することを目的として制作した彩色素焼き人形、「赤とんぼ」と題された博多人形を、石膏で型取りして複製物を作成し販売したとして、被告会社に対し、著作権侵害に基づき複製、販売停止等を求めて仮処分を申請した「赤とんぼ事件」があります。
被告会社は、本件人形は量産品として産業的な利用に供することを目的として創作されたものであるから著作物とはいえないと主張した。
しかし、裁判所は、人形「赤とんぼ」は同一題名の童謡から受けるイメージを造形物として表現したものであって、姿体、表情、着衣の絵柄、色彩から、感情の創作的表現を認めることができるとし、美術工芸的価値としての美術性を備えているとし、著作権法の保護対象であると認めました。
以下、判旨を見てみましょう。
美術的作品が、量産されて産業上利用されることを目的として製作され、現に量産されたということのみを理由としてその著作物性を否定すべきいわれはない。さらに、本件人形が一方で意匠法の保護の対象として意匠登録が可能であるからといつても、もともと意匠と美術的著作物の限界は微妙な問題であって、両者の重畳的存在を認め得ると解すべきであるから、意匠登録の可能性をもって著作権法の保護の対象から除外すべき理由とすることもできない。従って、本件人形は著作権法にいう美術工芸品として保護されるべきである。
長崎地方裁判所佐世保支部1973年2月7日決定
量産品として産業的な利用に供することを目的として創作されたということのみを理由として著作物性を否定することはできず、応用美術も美術工芸品であるなら著作物として認められるという判断です。
一方で、著作性が認められなかった事案もあります。それが世界的な工芸デザイナーである原告が、自己のデザインした椅子(ニーチェア)のコピー製品を台湾から輸入した被告に対し、著作権法違反を理由に製造販売禁止等を求めた「ニーチェア事件」です。
著作権法上の「美術」とは、原則として、専ら鑑賞の対象となる純粋美術のみをいい、実用を兼ねた美的創作物である応用美術でありながら著作権法上保護されるのは、同法2条2項により特に美術の著作物に含まれるものとされた美術工芸品に限られるのである。
大阪高等裁判所1990年2月14日判決
としました。その後、原告は最高裁へ上告しましたが、棄却されました。
これらの例からも明らかなように、従来の裁判においては、一品制作の美術工芸品に該当するか、あるいは純粋美術と同一視し得る程度に美的鑑賞の対象になるか否かを著作権の判断基準としており、応用美術に著作物性が認められるためには高いハードルが設けられていたといえます。
TRIPP TRAPP事件第一審

幼児用椅子であるTRIPP TRAPPの権利者である原告会社が、被告会社の製造、販売する椅子の形態がTRIPP TRAPPの形態に酷似しており、同製品の著作権(複製権又は翻案権)を侵害すると主張した事例があります。
第一審の東京地方裁判所は、応用美術を著作権法で保護するためには、
著作権法による保護と意匠法による保護との適切な調和を図る見地から、実用的な機能を離れて見た場合に、それが美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性を備えていることを要する。
東京地方裁判所2014年4月17日判決
として、従来の裁判例の流れに沿った基準に従って検討し、TRIPP TRAPPの著作物性を否定しました。著作権法による保護と意匠法による保護との適切な調和を図るという立場から、実用的な機能を離れて見た場合に、それが美的鑑賞の対象となり得るような美的創作性を備えているか否かを判断基準としたわけです。
これに対し、原告側は控訴しましたが、控訴審では、従来の考え方とは異なる基準が示されました。
TRIPP TRAPP 事件控訴審
控訴審において、知財高等裁判所は、著作権法第2条2項の「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする」につき、
同法第 2条 2項は、「美術の著作物」の例示規定にすぎず、例示に係る「美術工芸品」に該当しない応用美術であっても、同条1項 1号所定の著作物性の要件を充たすものについては、「美術の著作物」として、同法上保護されるものと解すべきである。
知財高等裁判所2015年4月14日判決
としました。著作権法の「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする」の「美術工芸品」はひとつの例にすぎず、著作権法第 2条 2項は美術工芸品以外の応用美術を除いているわけではないという解釈であり、さらに、応用美術に高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず、個別具体的に著作権法第2条1項が満たされているか否かを検討すべきであるとも判示しています。
そして、応用美術は意匠法で保護されるべきとの被告側の主張に対しては、
著作権法と意匠法とは、趣旨、目的を異にするものであり(著作権法第1条、意匠法第1条)、いずれか一方のみが排他的又は優先的に適用され、他方の適用を不可能又は劣後とするという関係は、明文上認められず、そのように解し得る合理的根拠も見出し難い。…応用美術につき、意匠法によって保護され得ることを根拠として、著作物としての認定を格別厳格にすべき合理的理由は、見出し難いというべきである。
同上
として、一定範囲の物に対しては両法の重複適用が認められるとしました。応用美術については他の表現物と同様に表現に作成者の何らかの個性が発揮されていれば創作性がある、として従来の基準と比べ緩やかに応用美術の著作物性を認める立場をとりました。
その上で、TRIPP TRAPPの著作物性を検討し、4本脚の椅子が多い乳幼児用ハイチェアにおいて、「左右一対の部材A」の2本脚であり、これと「部材B」の成す角度が約 66 度で類似製品に比しても小さく、また、部材Aが部材B前方の斜めに切断された端面でのみ結合され、直接床面に接している等といった形態的特徴は、幼児用椅子としての機能に係る制約により選択の余地なく必然的に導かれるものということはできず、作成者の個性が発揮されていて、創作的な表現というべきものであるので、TRIPP TRAPPは「美術の著作物」に該当するとして、著作物性を肯定しました。
なお、結論としては両社の製品は類似していないとの理由で、著作権侵害は認められていません。
まとめ
応用美術と美術工芸品との境界はあいまいであり、ニューヨーク近代美術館のように工業製品を展示している美術館も増えてきました。アーティストの制作の幅も広がりつつあります。
多量に生産し販売することを目的として制作した工業製品であることのみを理由に、美術の著作物であることを否定することには無理があるといえます。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務