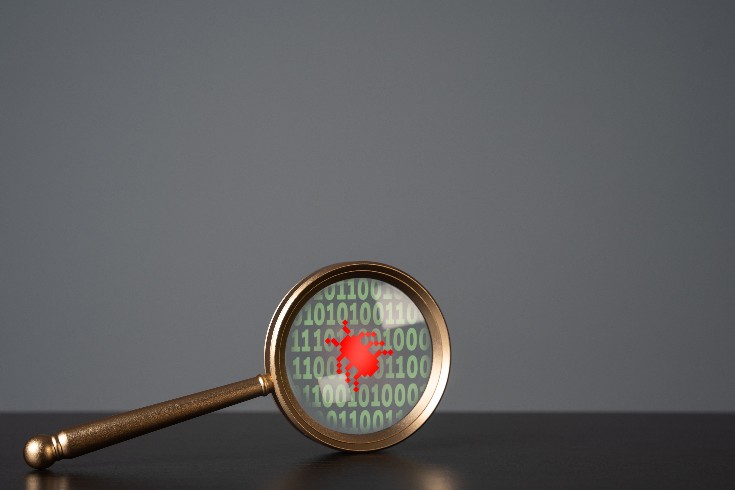„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Āß„Āģ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„Āč„āȄɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āł„ĀģŤ¨ĚÁĹ™„Āģś≥ēŚĺčšłä„ĀģśĄŹŚĎ≥„Ā®„ĀĮ

„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Āęťôź„āČ„Āö„ÄĀ„ĀĄ„āŹ„āÜ„āč„āĶ„Éľ„Éď„āĻś•≠„Ā®„ĀĄ„ĀÜś•≠śÖč„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„ĀäŚģĘśßė„Āč„āČŚĮĄ„Āõ„āČ„āĆ„āčŤč¶śÉÖ„Āł„ĀģŚĮĺŚŅú„ĀĮŤ®Ä„ĀÜ„Āĺ„Āß„āā„Ā™„ĀŹťá捶Ā„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„āā„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüŤ©Ī„ĀĮśĪļ„Āó„Ā¶šĺ茧Ė„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„ĀäŚģĘśßė„Āü„āč„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āč„āČŚĮĄ„Āõ„āČ„āĆ„āčŤč¶śÉÖ„Āę„ÄĀśäÄŤ°ď„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„ĀģśŹźšĺõ„āíśčÖ„ĀÜ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀĆŚĮĺŚŅú„āíŤŅę„āČ„āĆ„ā茆īťĚĘ„ĀĮťĖď„ÄÖ„Āā„āč„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā
šł°ŤÄÖ„Āģ„ā≥„Éü„É•„Éč„āĪ„Éľ„ā∑„Éß„É≥„āíŤČĮŚ•Ĺ„Āę„Ā®„āä„āā„Ā§„Āď„Ā®„āíťá捶Ė„Āô„āĆ„Āį„ÄĀÁõłśČč„ĀģŤ®Ä„ĀĄŚąÜ„āíŤĀě„ĀćŚÖ•„āĆŤ¨ĚÁĹ™„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚźąÁźÜÁöĄ„Ā™Ś†īŚźą„āā„Āā„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā„Āó„Āč„ĀóŚŹ£ť†≠„Āߍ¨ĚÁĹ™„ā퍰ƄĀ£„Āü„āä„ÄĀśĖáśõł„Āߍ¨ĚÁĹ™śĖá„ā휏źŚáļ„Āó„Āü„āä„Āó„ĀüÁĶźśěú„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀ„ɶ„Éľ„ā∂„ÉľŚĀī„ĀģÁźÜšłćŚįĹ„Ā™šłĽŚľĶ„ĀĆ„ĀĚ„Āģ„Āĺ„ĀĺśóĘśąźšļčŚģüŚĆĖ„Āó„Ā¶„Āó„Āĺ„ĀÜ„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āč„Ā®„ĀĄ„Āܜ᳌ŅĶ„āíśäĪ„ĀĄ„Āü„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜšļļ„āā„ĀĄ„āč„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Āč„Äā
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„Āč„āȄɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āł„Ā®„Ā™„Āē„āĆ„ĀüŤ¨ĚÁĹ™„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āā„Āģ„Āę„Éē„ā©„Éľ„āę„āĻ„Āó„Ā¶„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĆś≥ēŚĺčšłä„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™śĄŹŚĎ≥„āí„āā„Ā§„āā„Āģ„Ā®ÁźÜŤß£„Āē„āĆ„āč„Āģ„Āč„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ťß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļÁŹĺŚ†ī„Āß„Ā™„Āú„ÄĆŤ¨ĚÁĹ™„Äć„ĀĆŚēŹť°Ć„Ā®„Ā™„āč„Āģ„Āč
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„ĀĮ„āĶ„Éľ„Éď„āĻś•≠„ĀģšłÄÁ®ģ„Āß„Āā„āč
„ĀĚ„āā„ĀĚ„āā„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Ā®„ĀĄ„ĀÜś•≠Śčô„āí„ÄĀ„āĘ„ā¶„Éą„āĹ„Éľ„ā∑„É≥„āį„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āč„Āü„Ā°„Āߌ§ĖťÉ®ś•≠ŤÄÖ„ĀĆšĽčŚÖ•„Āô„ā茆īŚźą„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĮšłÄÁ®ģ„Āģ„ÄĆšľĀś•≠ŚźĎ„ĀĎ„Āģ„āĶ„Éľ„Éď„āĻś•≠„Äć„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„Āą„Āĺ„Āô„Äā„Āā„Āą„Ā¶ś≥ēŚĺčÁĒ®Ť™ě„āíśĆĀ„Ā°Śáļ„Āô„Ā™„āČ„Āį„ÄĀŤęčŤ≤†Ś•ĎÁīĄ„Āā„āč„ĀĄ„ĀĮśļĖŚßĒšĽĽŚ•ĎÁīĄ„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„Āč„Āü„Ā°„Āߌ•ĎÁīĄ„ĀģÁ∑†ÁĶź„āā„Ā™„Āē„āĆ„āč„Āģ„ĀĆťÄöŚłł„Āß„Āô„ÄāŤęčŤ≤†Ś•ĎÁīĄ„Ā®śļĖŚßĒšĽĽŚ•ĎÁīĄ„ĀģťĀē„ĀĄ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšĽ•šłč„ĀģŤ®ėšļč„Āę„Ā¶Ť©≥Áīį„ĀęŤß£Ť™¨„ā퍰ƄĀ£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
Ť©Ī„ĀģŤ¶ĀÁāĻ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ĀĄ„Āö„āĆ„ĀģŚ†īŚźą„ĀģŚ•ĎÁīĄ„Āę„Āó„āć„ÄĀšĽēšļč„ā팏ó„ĀĎ„āč„Éô„É≥„ÉÄ„ÉľŚĀī„ĀģšľĀś•≠„ĀĆśúČ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āčśäÄŤ°ďŚäõ„ÉĽ„Éě„É≥„ÉĎ„ÉĮ„ÉľÔľą„Ā®„ÄĀ„ĀĚ„ĀÜ„Āó„ĀüŚäõ„āíŤÉĆśôĮ„ĀęÁĒü„ĀŅŚáļ„Āē„āĆ„āč„Éó„É≠„ÉÄ„āĮ„ɹԾȄāí„āā„Ā®„ĀęŚ£≤šłä„āí„Ā†„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁāĻ„ĀꌧȄāŹ„āč„Ā®„Āď„āć„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Éô„É≥„ÉÄ„ÉľŚĀī„ĀęŚĪě„Āô„āč„ÄĆšļļ„Äć„ĀģŚäõ„Āę„āą„Ā£„Ā¶śŹźšĺõ„Āē„āĆ„āč„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„Ā®„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀęŚĮĺŚŅú„Āô„ā茆ĪťÖ¨„Āģšļ§śŹõ„āíśó®„Ā®„Āô„āčŚēÜŚŹĖŚľē„Āß„Āā„ā蚼•šłä„ÄĀIT„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀģťĖčÁôļ„Ā®„ĀĄ„ĀÜś•≠Śčô„ĀĮŚéüŚČá„ÄĀ„āĶ„Éľ„Éď„āĻś•≠„ĀģšłÄÁ®ģ„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„Āą„Āĺ„Āô„Äā
„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„ĀĆ„ÄĆ„ĀäŚģĘśßė„Äć„Āß„Āā„āč„ĀĆ„āÜ„Āą„ĀꍨĚÁĹ™„ĀĆśĪā„āĀ„Ā¶„ĀŹ„āč
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„ĀĆ„āĶ„Éľ„Éď„āĻś•≠„Āß„Āā„āč„Āč„āČ„Āę„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āď„Āß„ĀĮŤč¶śÉÖ„ÉĽ„āĮ„ɨ„Éľ„Ɇ„ĀƄɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āč„āČŚĮĄ„Āõ„āČ„āĆ„āč„Āď„Ā®„āāŚčŅŤęĖśÉ≥Śģö„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŚźĆśôā„Āę„ÄĀ„ĀĚ„ĀÜ„Āó„Āü„āĮ„ɨ„Éľ„Ɇ„ĀęÁöĄÁĘļ„ĀęŚĮĺŚŅú„Āô„āčŚäõ„āā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀęśĪā„āĀ„āČ„āĆ„āč„Āď„Ā®„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āü„Āó„Āč„ĀęŚģüťöõŚēŹť°Ć„ÄĀŚźĄÁ®ģ„āĮ„ɨ„Éľ„Ɇ„āĄŤč¶śÉÖ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀĆÁī≥Ś£ę„ĀꍨĚÁĹ™Á≠Č„ĀģŚĮĺŚŅú„ā퍰ƄĀÜ„Āď„Ā®„Āę„āą„Ā£„Ā¶„ÄĀŚÜćŚļ¶ŚćĒŚäõšĹ∂„ĀĆśßčÁĮČ„Āē„āĆ„ÄĀ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀĆśąźŚäü„ĀęŚįé„Āč„āĆ„āč„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„āā„Āā„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
„Āó„Āč„ĀóšłÄśĖĻ„Āß„ÄĀ„āā„Āó„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀĆ„ĀĚ„ĀģŚĺĆśú¨ŚĹď„ĀꝆďśĆę„Āó„Āü„āą„ĀÜ„Ā™Ś†īŚźą„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŤ£ĀŚą§„Āę„Āĺ„Āßšļčś°ą„ĀĆ„āā„Ā§„āĆ„āč„āą„ĀÜ„Ā™šļčśÖč„āíśÉ≥Śģö„Āó„Ā¶„ĀŅ„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„ĀĮ„Éô„É≥„ÉÄ„ÉľŚĀī„Āč„āČ„ĀģŤ¨ĚÁĹ™„ā휆Ļśč†„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀ„ÄĆ„Éô„É≥„ÉÄ„ÉľŚĀī„āāŚłįŤ≤¨šļčÁĒĪ„āíŤá™Ť™ć„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äć„Ā®šłĽŚľĶ„Āó„Ā¶„ĀŹ„āč„Āď„Ā®„ĀĆŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
„ĀĚ„āā„ĀĚ„āā„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„ĀĮ„Ā©„Āď„Āĺ„Āß„ĀäŚģĘśßė„Āß„ĀĄ„āČ„āĆ„āč„Āģ„Āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚēŹť°Ć
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀĮ„ÄĀ„Āü„Āó„Āč„Āę„Āā„ā蚳ĝĚĘ„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆ„ĀäŚģĘśßė„Äć„Ā®„Āó„Ā¶„Āģ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Ā®„ÄĀ„ÄĆŚ§ĖťÉ®„Āģś•≠ŤÄÖ„Āē„āď„Äć„Ā®„Āó„Ā¶„Āģ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„Ā®„ĀĄ„ĀÜšļĆŤÄÖťĖď„Āßšļ§„āŹ„Āē„āĆ„āčŚēÜŚŹĖŚľē„Āß„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüťĖĘšŅāśÄß„ĀęÁīć„Āĺ„āČ„Ā™„ĀĄŤ§áťõĎ„Āē„āíśĆĀ„Ā§„āā„Āģ„ĀĆ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Āę„Āĺ„Ā§„āŹ„ā茕ĎÁīĄ„ĀģÁČĻŚĺī„Āß„Āô„Äā„Āô„Ā™„āŹ„Ā°„ÄĀ„ĀäŚģĘśßė„Āü„āč„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„āā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀģÁĺ©Śčô„ĀęŚćĒŚäõ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āč„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀĮŚąįŚļēŚģĆšļÜ„Āß„Āć„āč„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„ɶ„Éľ„ā∂„ÉľŚĀī„Āę„āāšłÄŚģö„ĀģŚćĒŚäõÁĺ©Śčô„ĀĆŤ™≤„Āē„āĆ„ÄĀšł°ŤÄÖ„ĀĆŚćĒŚÉćťĖĘšŅā„ĀęÁęč„Ā£„Ā¶„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„āíťÄ≤„āĀ„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„ĀĻ„Āć„āā„Āģ„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀťĀéŚéĽ„ĀģŤ£ĀŚą§šĺč„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„āāśĆáśĎė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā
„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„Āč„āȄɶ„Éľ„ā∂„Éľ„ĀęŚĮĺ„Āô„āč„ÄĆŤ¨ĚÁĹ™„Äć„āí„āĀ„Āź„āčś≥ēŚĺčŚēŹť°Ć„āíŤÄÉŚĮü„Āô„āčťöõ„Āę„ÄĀ„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüťĖĘšŅāśÄß„ĀģŤ§áťõĎ„Āē„ā퍙ćŤ≠ė„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĮŚ§ßŚąá„Ā™„Āď„Ā®„Āß„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Ā®„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀģťĖď„ĀģťĖĘšŅā„ĀĮ„ÄĀŚĮĺÁ≠Č„Ā™„ÉĎ„Éľ„Éą„Éä„Éľ„ā∑„ÉÉ„Éó„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀŚĀ•ŚÖ®„Ā™„Āč„Āü„Ā°„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀŹŚ†īŚźą„āā„Āā„āĆ„Āį„ÄĀ„ÄĆśēį„Āā„āčŚáļŚÖ•„āäś•≠ŤÄÖ„ĀģšłÄ„Ā§„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŤ¶čśĖĻ„āí„Āē„āĆ„Āó„Āĺ„ĀÜ„Āď„Ā®„āāŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„āāŚćĒŚäõ„Āó„ÄĀ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀģťĀĒśąź„āíÁõģśĆá„Āó„Ā¶ŚćĒŚÉć„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮś≥ēŚĺčšłä„ĀģÁĺ©Śčô„Āß„āā„Āā„āč„Āģ„Ā†„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚ§ßŚČ朏ź„ĀĆŚŅė„āƌ鼄āČ„āĆ„Āü„Ā®„Āć„ĀęŚĺÄ„ÄÖ„Āę„Āó„Ā¶ť°ēŚú®ŚĆĖ„Āô„āč„Āģ„ĀĆ„ÄĀšłćŚĹď„Ā™Ť¨ĚÁĹ™Ť¶ĀśĪā„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚēŹť°Ć„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„Āą„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģÁāĻ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģšĽĖ„Āģ„āĶ„Éľ„Éď„āĻś•≠„Āę„ĀĮ„Āā„Āĺ„āä„ĀŅ„āČ„āĆ„Ā™„ĀĄ„ÄĀ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Ā®„ĀĄ„ĀÜś•≠Śčô„ĀęŚõļśúČ„ĀģÁČĻŚĺī„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„Āą„Āĺ„Āô„Äā
Ť£ĀŚą§śČÄ„ĀĮ„ÄĆŤ¨ĚÁĹ™„Äć„āí„Ā©„ĀÜŤ¶č„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„Āč

„Āß„ĀĮŚģüťöõ„Āę„ÄĀ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„āí„āĀ„Āź„āčŤ£ĀŚą§„Āß„ÄĀ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„Āč„āČ„ĀģŤ¨ĚÁĹ™„ĀĮ„Ā©„ĀģÁ®čŚļ¶ś≥ēŚĺ蚳䜥ŹŚĎ≥„āíśĆĀ„Ā§„āā„Āģ„Ā®„Āó„Ā¶śČĪ„āŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„Āč„ā횼•šłč„Āꍶč„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āď„Ā®„Āę„Āó„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā
Ť¨ĚÁĹ™„āí„āĀ„Āź„āčŤ£ĀŚą§šĺčÔľĎÔľö„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āč„āČ„ĀģŚúüšłčŚļß„ĀģŤ¶ĀśĪā
śú¨šĽ∂„Āß„ĀĮ„ÄĀŚĺĻŚ§úšĹúś•≠Á©ļ„ĀĎ„Āę„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āģ„āā„Ā®„Āł„Ā®Ť®™„Ā≠„Āüťöõ„Āę„ÄĀ„Éá„Éľ„āŅ„āíś∂ą„Āó„Āü„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āč„Ā®„ĀģťĚěťõ£„ĀĆ„Ā™„Āē„āĆ„ÄĀŚúüšłčŚļß„Āē„Āõ„āČ„āĆ„ĀüŚĺĆ„Āę„ÄĀ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„ĀģŤ®Ä„ĀĄŚąÜ„Āęś≤Ņ„Ā£„Ā¶Ť¨ĚÁĹ™śĖá„ā휏źŚáļ„Āó„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁĶĆÁ∑Į„Āģ„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā„Āó„Āč„ĀóŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āď„Āß„ĀģŤ¨ĚÁĹ™śĖá„ĀęÁúüśĄŹ„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀģŤ¶čŤß£„āíÁ§ļ„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā
Ôľ®„ĀĮ„ÄĀ„Āď„ĀģÁāĻ„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶Ť®ėŤľČ„Āģ„Āā„ā荨ĚÁĹ™śĖá„āíšĹúśąź„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĮ„ÄĀŚĺĻŚ§úšĹúś•≠„ĀģŚĺĆ„Āę„ÄĀŚĻ≥śąźÔľĎÔľďŚĻīÔľĎÔľźśúąÔľĒśó•„ÄĀŚéüŚĎäšļčŚčôśČÄ„ā퍮™„āĆ„Āüťöõ„ÄĀšłÄśĖĻÁöĄ„ĀęŚé≥„Āó„ĀŹťĚěťõ£„Āē„āĆ„ÄĀŚúüšłčŚļß„Āē„Āõ„āČ„āĆ„ĀüŚĺĆ„ÄĀŚéüŚĎä„ĀģŤ¶ĀśĪā„ĀęŚĺď„ĀĄ„ÄĀ„ĀĄ„Ā£„Āü„āďŚéüŚĎäŚĹĻŚď°„āČ„ĀģśÄí„āä„āíś≤ąťĚôŚĆĖ„Āô„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤ®Ä„ĀĄŚąÜ„ĀęŚĺď„Ā£„Ā¶šĹúśąź„Āó„Āü„āā„Āģ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„ÄĀÔľ®„ĀģÁúüśĄŹ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āó„ÄĀŚźĆśßė„ĀęÔľģ„ĀģšĹúśąź„Āó„ĀüŤ¨ĚÁĹ™śĖá„ĀģŤ∂£śó®„āāÔľģ„ĀģÁúüśĄŹ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Äā
śĚĪšļ¨ŚúįŚą§ŚĻ≥śąźÔľĎÔľĖŚĻīÔľĒśúąÔľíÔľďśó•
ťĚěťõ£„ĀĆ„ÄĆšłÄśĖĻÁöĄ„Äć„Āß„Āā„Ā£„ĀüÁāĻ„ÄĀ„ÄĆśÄí„āä„āíś≤ąťĚôŚĆĖ„Äć„ÄĀ„ÄĆÁúüśĄŹ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„Āč„Āü„Ā°„Āß„ÄĀŚĹďšļčŤÄÖ„ĀģŚŅÉśÉÖ„ā팏Ė„āäŚÖ•„āĆ„ĀüŚą§śĖ≠„ā퍰ƄĀ£„Ā¶„ĀĄ„āčÁāĻ„ĀĆÁČĻŚĺī„Ā†„Ā®„ĀĄ„Āą„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
Ť¨ĚÁĹ™„āí„āĀ„Āź„āčŤ£ĀŚą§šĺčÔľíÔľöŤ©ę„Ā≥Áä∂„āíśõł„ĀŹ„Āč2000šłáŚÜÜśČē„ĀÜ„Āč„ĀģťĀłśäě
„Āĺ„ĀüšĽ•šłč„Āģšļčś°ą„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ā®„É≥„ÉȄɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Āę„āā„Āü„āČ„Āē„āĆ„āčśźćŚģ≥„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŤ©ę„Ā≥Áä∂„āíśõł„ĀŹ„Āď„Ā®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀĆŚźąśĄŹ„Āó„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„āā„ÄĀś≥ēŚĺčšłä„ĀģŤ≤¨šĽĽ„ĀĆ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀꌳįŤ≤¨„Āē„āĆ„āč„ĀĻ„Āć„āā„Āģ„Āß„Āā„āč„Āč„ĀģŤ©Ī„Ā®„ĀĮŚĆļŚą•„Āô„ĀĻ„Āć„Ā®„ĀģŚą§śĖ≠„ĀĆšłč„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā
ŚéüŚĎä„ĀģšĽ£Ť°®ŤÄÖ„ĀĮ„ÄĀŚŹ≥Ś†ĪŚĎäśõł„ā팏ó„ĀĎŚŹĖ„Ā£„ĀüŚĺĆ„ÄĀ„ÄĆ„Āď„āĆ„ĀßEÁ§ĺ„ĀĆśā™„ĀĄ„Āď„Ā®„ĀĆ„ĀĮ„Ā£„Āć„āä„Āó„Āü„Āģ„Āß„ÄĀŤ©ę„Ā≥Áä∂„āíśõł„ĀŹ„Āč„ÄĀ„āĹ„Éē„Éą„ā¶„āß„āĘ„ĀģťĖčÁôļŤ≤ĽšļĆ„Äá„Äá„ÄášłáŚÜÜ„āíŤ≤†śčÖ„Āô„āč„Āč„Āģ„Ā©„Ā°„āČ„Āč„Āę„Āõ„āą„Äā„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ∂£śó®„Āģ„Āď„Ā®„ā퍮ĄĀĄŚáļ„Āó„Āü„ÄāťĀé„ĀéŤĘęŚĎä„ĀĮ„ÄĀŚŹ≥Ť¶ĀśĪā„ĀęŚĺď„ĀĄ„ÄĀŚźĆŚĻīšłÄśúąšłÄšĻ̜󕚼ė„Āß„ÄĀŚŹ≥šłćŚÖ∑Śźą„ĀģÁôļÁĒü„Āę„āą„āäŚéüŚĎä„ĀęŤŅ∑śÉĎ„āíśéõ„ĀĎ„Āü„Āď„Ā®„ā퍩ę„Ā≥„āčŤ∂£śó®„Āģ„ÄĆŤ©ę„Ā≥Áä∂„Äć„āíšĹúśąź„Āó„ÄĀ„Āď„āĆ„āíŚéüŚĎä„Āęśł°„Āó„Āü„Äā
Ôľąšł≠Áē•ÔľČ
EÁ§ĺŤ£ĹŚďĀ„ĀģŤ≤©Ś£≤ŤÄÖ„Ā®„Āó„Ā¶„Āß„Āć„āčťôź„āä„ĀģŚĮĺŚŅú„āí„Āó„Āü„āā„Āģ„Ā®„ĀŅ„āč„ĀĻ„Āć„Āß„Āā„āä„ÄĀ„ĀĚ„āĆšĽ•šłä„ĀģŚĮĺŚŅú„āí„Āó„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āď„Ā®„āí„āā„Ā£„Ā¶„ÄĀÁõī„Ā°„ĀęŤĘęŚĎä„ĀĆśú¨šĽ∂Ś£≤Ť≤∑Śüļśú¨Ś•ĎÁīĄ„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹŤĘęŚĎä„ĀģŚāĶŚčô„āíśÄ†„Ā£„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„Āß„Āć„Ā™„ĀĄ„Äā
śĚĪšļ¨ŚúįŚą§ŚĻ≥śąźÔľėŚĻīÔľóśúąÔľĎԾϜó•
ŚĹĘŚľŹÁöĄ„Ā™Ť©ę„Ā≥Áä∂„ĀģŚģõŚźć„ā퍙į„Āę„Āô„āč„Āč„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüÁāĻ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀŚģüŚčô„Āģ„Āā„āäśĖĻ„Āģ„ĀĽ„ĀÜ„āíťá捶Ė„Āó„Āü„ĀÜ„Āą„ĀߌłįŤ≤¨„Āô„āčŚĮĺŤĪ°„ā퍶čŚģö„āĀ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤÄÉ„ĀąśĖĻ„ĀĆŚą§śĪļśĖá„Āč„āČ„āāŤ™≠„ĀŅŚŹĖ„āĆ„āč„āā„Āģ„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
šłäŤ®ėŤ£ĀŚą§šĺč„ĀęŚÖĪťÄö„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āą„āč„Āď„Ā®
šłäŤ®ė„ĀģŤ£ĀŚą§šĺč„Āč„āČ„ĀĄ„Āą„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀ„Āü„Ā®„Āą„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀĆŚĹĘŚľŹÁöĄ„ĀꍨĚÁĹ™„ĀģŤ¶ĀŤęč„ĀęŚŅú„Āė„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„āā„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĆÁŹĺŚģü„ĀģŤ£ĀŚą§„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶ŚŅÖ„Āö„Āó„āāśĪļŚģöÁöĄ„Ā™śĄŹŚĎ≥„āíśĆĀ„Ā§„āŹ„ĀĎ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„Āô„ÄāŤ¨ĚÁĹ™„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„āčÁźÜÁĒĪ„ĀĆ„Éď„āł„Éć„āĻšłä„āā„ÄĀÁČ©šļč„āíŚČć„ĀęťÄ≤„āĀ„āč„Āü„āĀ„ĀģšĺŅŚģúšłä„Āģ„āā„Āģ„Āę„Āô„Āé„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„ĀĆŚ§ö„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁāĻ„ĀĮ„ÄĀŤ£ĀŚą§„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„āāŚćĀŚąÜśĖüťÖĆ„Āē„āĆ„āčšļčśÉÖ„Āß„Āā„āč„Ā®ŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„āÄ„Āó„āć„ĀĚ„ĀÜ„Āó„ĀüŚĹĘŚľŹÁöĄ„Ā™Ť¨ĚÁĹ™„ĀģśúČÁĄ°„āą„āä„ĀĮ„ÄĀŤ¨ĚÁĹ™„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„ĀüÁĶĆÁ∑Į„āĄ„ÄĀŤ¨ĚÁĹ™śĖá„ĀĆśõł„Āč„āĆ„ĀüÁĶĆÁ∑Į„ā퍳Ź„Āĺ„Āą„Ā¶„ÄĀ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„Ā®„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀģťĖď„Āß„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™šļļťĖďťĖĘšŅā„ĀĆśßčÁĮČ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āč„Ā™„Ā©„āāŚŹĖ„āäŚÖ•„āĆ„Āü„ĀÜ„Āą„ĀßÁ∑ŹŚźąÁöĄ„Ā™Śą§śĖ≠„ā퍰ƄĀ£„Ā¶„ĀĄ„Āď„ĀÜ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„ĀĆŤ£ĀŚą§śČÄ„Āģ„āĻ„āŅ„É≥„āĻ„Ā†„Ā®„ĀŅ„āč„ĀĻ„Āć„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
„ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„āā„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀęŚćĒŚäõ„Āô„āčÁĺ©Śčô„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„āā„ĀĚ„āāŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĆÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„ā荶čŤß£„Āß„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„ĀĆ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀꌹįŚļēŚćĒŚäõÁöĄ„Āß„Āā„Ā£„Āü„Ā®„ĀĮŤ®Ä„ĀĄťõ£„ĀĄ„āą„ĀÜ„Ā™śĒĮťÖćÁöĄ„ÉĽťęėŚúßÁöĄ„Ā™ťĖĘšŅā„ĀĆ„Āā„Ā£„Āü„Ā®„ĀŅ„āČ„āĆ„āčšļčś°ą„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚįöśõīŤ¨ĚÁĹ™„ĀĮ„Āč„Āü„Ā°„Ā†„ĀĎ„Āģ„āā„Āģ„Ā®śČĪ„āŹ„āĆ„āĄ„Āô„ĀŹ„Ā™„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
ŚģČśėď„ĀꍨĚÁĹ™„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶„ĀĄ„ĀĄ„āŹ„ĀĎ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āģ„Āßś≥®śĄŹ
„āā„Ā£„Ā®„āā„ÄĀ„ĀĄ„ĀĖŤ£ĀŚą§„Āę„Ā™„Ā£„Āüťöõ„Āę„ÄĀŤ¨ĚÁĹ™„ĀĆ„ĀĚ„āĆŚćėšĹď„ĀßśĪļŚģöÁöĄ„Ā™Ť®ľśč†„Ā®„Ā™„ā茆īŚźą„ĀĆŚįĎ„Ā™„ĀĄ„Āč„āČ„Ā®„ĀĄ„Ā£„Ā¶„ÄĀŚģČśėď„ĀꍨĚÁĹ™„ā퍰ƄĀ£„Ā¶„ĀĄ„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„ÄāŚģČśėď„Ā™Ť¨ĚÁĹ™„ĀĮ„ÄĀŤ£ĀŚą§„ĀęŤá≥„āč„Āĺ„Āß„Āģšļ§śłČŚ†īťĚĘ„Āß„āā„ÄĀ„ɶ„Éľ„ā∂„ÉľŚĀī„Āč„āČť†Ď„Ā™„Ā™śÖčŚļ¶„ā팾ē„ĀćŚáļ„Āó„Ā¶„Āó„Āĺ„ĀÜ„É™„āĻ„āĮ„Āę„āā„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŤ£ĀŚą§„ĀģŚąĚśúü„ĀģśģĶťöé„Āß„ÄĀŤ£ĀŚą§Śģė„ĀĆŤ¨ĚÁĹ™śĖá„āíšł≠ŚŅÉ„ĀęŚŅÉŤĪ°„āíŚĹĘśąź„Āó„Ā¶„Āó„Āĺ„Āą„Āį„ÄĀŤ™§Ťß£„āíŤß£„ĀŹ„Āģ„Āꌧö„ĀŹ„ĀģśČčťĖď„āĄśôāťĖď„ā퍶Ā„Āô„āč„Āď„Ā®„Āę„āā„Ā™„āä„Āč„Ā≠„Ā™„ĀĄÁāĻ„āāś≥®śĄŹ„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„ĀĻ„Āć„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā„Āĺ„Āü„Āē„āČ„ĀꚼėŤ®Ä„Āô„āč„Ā®„ÄĀŚćė„ĀꍨĚÁĹ™„ĀģśĄŹ„āíÁ§ļ„Āô„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁāĻ„Āę„Ā®„Ā©„Āĺ„āČ„Āö„ÄĀŤ¨ĚÁĹ™ŚÜÖŚģĻ„āĄŤ¨ĚÁĹ™śĖá„ĀģŤ®ėŤľČŚÜÖŚģĻ„ĀĆ„Éô„É≥„ÉÄ„Éľ„ĀģŤźĹ„Ā°Śļ¶„āíŚÖčśėé„ĀęśĆáśĎė„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„āą„ĀÜ„Ā™Ś†īŚźą„Āę„ĀĮ„ÄĀšļčŚģüŤ™ćŚģö„ĀģśģĶťöé„ĀßšłćŚą©„Ā™Ťß£ťáą„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„ā荶ĀÁī†„Ā®„āā„Ā™„āä„Āą„Āĺ„Āô„Äā
„ĀĄ„Āö„āĆ„Āę„Āõ„āą„ÄĀŤč¶śÉÖŚĮĺŚŅú„ÉĽ„āĮ„ɨ„Éľ„ɆŚĮĺŚŅú„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚēŹť°Ć„ĀĚ„āƍᙚĹď„āāś≥ēŚčô„ĀģŚēŹť°Ć„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ™ćŤ≠ė„āí„āā„Ā£„Āü„ĀÜ„Āą„Āß„ÄĀ„ĀĄ„Āč„Āę„Āó„Ā¶Ť¨ĚÁĹ™„ā퍰ƄĀÜ„ĀĻ„Āć„Āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚēŹť°Ć„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„āā„ÄĀŚ§ĖťÉ®ŚįāťĖÄŚģ∂„ĀģśīĽÁĒ®„āíÁ©ćś•ĶÁöĄ„ĀꜧúŤ®é„Āô„ĀĻ„Āć„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
„ÄÄ
„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ: IT„ÉĽ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀģšľĀś•≠ś≥ēŚčô
„āŅ„āį: „ā∑„āĻ„É܄ɆťĖčÁôļ