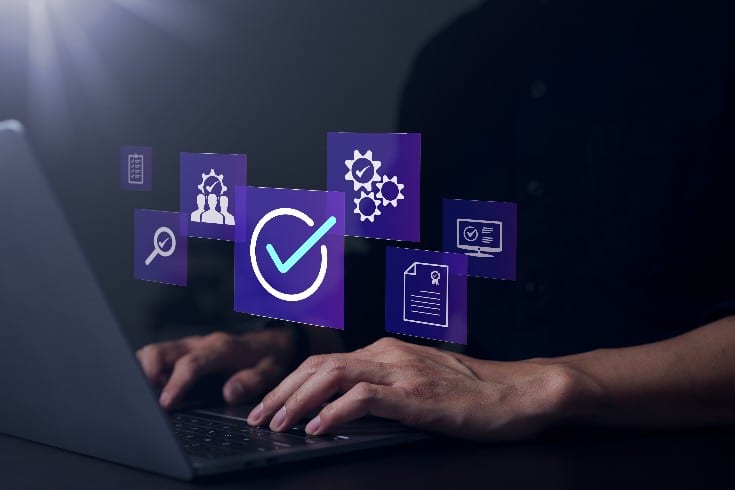„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀģÁīõšļČŤß£śĪļ„É°„āę„Éč„āļ„Ɇ„Ā®ŚäīŚÉćÁīõšļČŤß£śĪļ„ĀģŚģüŚčô
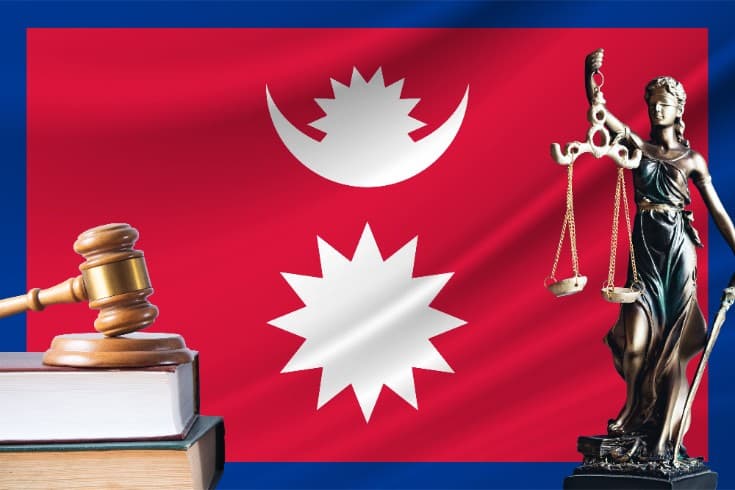
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀģÁīõšļČŤß£śĪļ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀĮ„ÄĀŚŹ§„ĀŹ„Āč„āČ„ĀģšľĚÁĶĪÁöĄ„Ā™śÖ£ÁŅí„Ā®ŤŅĎšĽ£ÁöĄ„Ā™ś≥ēšĹďÁ≥Ľ„ĀĆŤě挟ą„Āó„ÄĀÁ訍ᙄĀģÁôļŚĪē„āíťĀā„Āí„Ā¶„Āć„Āĺ„Āó„Āü„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀŤ®īŤ®ü„Āꚼ£„āŹ„ā蚼£śõŅÁöĄÁīõšļČŤß£śĪļÔľąADRԾȄĀĆťá捶Ā„Ā™ŚĹĻŚČ≤„āíśčÖ„Ā£„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĮŚĺďśĚ•„ĀģŤ£ĀŚą§śČčÁ∂ö„Āć„Āęšľī„ĀÜśôāťĖď„ÄĀŤ≤ĽÁĒ®„ÄĀŚÖ¨ťĖčśÄß„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ŚįāťĖÄśÄß„ĀģŤ™≤ť°Ć„āíŚÖčśúć„Āó„ÄĀ„āą„āäśüĒŤĽü„Āč„Ā§ŚäĻśěúÁöĄ„Ā™Ťß£śĪļÁ≠Ė„ā휏źšĺõ„Āô„āč„Āď„Ā®„āíÁõģÁöĄ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ś≠īŚŹ≤„āíÁīźŤß£„ĀŹ„Ā®„ÄĀ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āß„ĀĮ„Āč„Ā§„Ā¶„ÄĀŚúįŚüüÁ§ĺšľö„Ā꜆Ļ„ĀĖ„Āó„Āü„ÄĆ„ÉĎ„É≥„ÉĀ„É£„ɧ„ÉÉ„Éą„Äć„āĄ„ÄĆ„ÉĎ„É≥„ÉĀ„É£„É™„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüťĚěŚÖ¨ŚľŹ„Ā™ÁīõšļČŤß£śĪļŚą∂Śļ¶„ĀĆ„ĀĚ„ĀģŚüļÁõ§„āíŚĹĘśąź„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āď„āĆ„āČ„ĀģŚą∂Śļ¶„ĀĮ„ÄĀŤćČ„Āģś†Ļ„ɨ„Éô„Éę„Āß„ĀģÁīõšļČ„āíŤß£śĪļ„Āô„āčšłä„Āßťá捶Ā„Ā™ś©üŤÉĹ„āíśěú„Āü„Āó„Ā¶„Āć„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀśôāšĽ£„ĀģŚ§ČťĀ∑„Ā®ŚÖĪ„Āę„ÄĀšĽ≤Ť£Āś≥ē2055ŚĻīÔľąŤ•Ņśö¶1998ŚĻīԾȄĀģ„āą„ĀÜ„Ā™ŤŅĎšĽ£ÁöĄ„Ā™ś≥ēŚĺč„ĀĆśēīŚāô„Āē„āĆ„ÄĀADR„ĀĮ„āą„āäÁĶĄÁĻĒŚĆĖ„Āē„āĆ„ÄĀ„āĘ„āĮ„āĽ„āĻ„Āó„āĄ„Āô„ĀĄśČčÁ∂ö„Āć„Āł„Ā®ťÄ≤ŚĆĖ„Āó„Āĺ„Āó„Āü„ÄāÁŹĺšĽ£„Āģ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éęś≥ēŚą∂Śļ¶„Āß„ĀĮ„ÄĀšļ§śłČ„ÄĀŤ™ŅŚĀú„ÄĀšĽ≤Ť£Ā„ĀĆšłĽŤ¶Ā„Ā™ADRśČčś≥ē„Ā®„Āó„Ā¶šĹćÁĹģ„Ā•„ĀĎ„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áśäÄŤ°ďÁ߼ŤĽĘś≥ē„āĄťĖčÁôļŚßĒŚď°šľöś≥ē„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüťĖĘťÄ£ś≥ēŤ¶Ź„āā„ÄĀADR„āíťÄö„Āė„ĀüÁīõšļČŤß£śĪļ„āíšĹďÁ≥ĽÁöĄ„ĀęśĒĮśŹī„Āô„āčśĚ°ť†Ö„ā팟ę„āď„Āß„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Éď„āł„Éć„āĻśīĽŚčē„ĀĆśó•„ÄÖŤ§áťõĎŚĆĖ„Āô„āčÁŹĺšĽ£„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀÁīõšļČ„ĀĮťĀŅ„ĀĎ„āČ„āĆ„Ā™„ĀĄŤ¶ĀÁī†„Āß„Āā„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤŅÖťÄü„Ā™Ťß£śĪļ„ĀĮšļčś•≠„ĀģÁ∂ôÁ∂öśÄß„Ā®ÁôļŚĪē„Āģ„Āü„āĀ„Āꌾ∑„ĀŹśĪā„āĀ„āČ„āĆ„āč„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā
„Ā™„Āä„ÄĀ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āß„ĀĮ„ÄĀŤ•Ņśö¶„Ā®„ĀĮŚą•„Āę„Éď„āĮ„É©„Ɇśö¶„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁ訍ᙄĀģśö¶„ĀĆšĹŅ„āŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Éď„āĮ„É©„Ɇśö¶„ĀĮÁīÄŚÖÉŚČć57ŚĻī„āíŤĶ∑ŚĻī„Ā®„Āó„ÄĀŤ•Ņśö¶„Āģ4śúąŚćä„Āį„āíśĖįŚĻī„Ā®„Āó„Āĺ„Āô„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀŤ•Ņśö¶1998ŚĻī„ĀĮ„Éď„āĮ„É©„Ɇśö¶„Āß„ĀĮ2054ŚĻīŚŹą„ĀĮ2055ŚĻī„Āß„Āô„ÄāŚÖąŤŅį„Āó„Āü„ÄĆšĽ≤Ť£Āś≥ē2055ŚĻīÔľąŤ•Ņśö¶1998ŚĻīԾȄÄć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ°®Ť®ė„ĀĮ„ÄĀ„Āď„Āģ„Éď„āĮ„É©„Ɇśö¶„Āę„āą„āč„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀģÁīõšļČŤß£śĪļ„É°„āę„Éč„āļ„Ɇ„ÄĀÁČĻ„ĀęšľĀś•≠„Ā®ŚäīŚÉćŤÄÖťĖď„ĀģŚäīŚÉćÁīõšļČŤß£śĪļ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ť©≥„Āó„ĀŹŤß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āģś≥ēŚĺč„ĀģŚÖ®šĹďŚÉŹ„Ā®„ĀĚ„Āģś¶āŤ¶Ā„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ĀĮšĽ•šłč„ĀģŤ®ėšļč„ĀßŤß£Ť™¨„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀģÁīõšļČŤß£śĪļŚą∂Śļ¶„ĀģŚÖ®šĹďŚÉŹ

Ť£ĀŚą§Śą∂Śļ¶„ĀģśßčťÄ†„Ā®ŚĹĻŚČ≤
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀģŚŹłś≥ēŚą∂Śļ¶„ĀĮ„ÄĀśúÄťęėŤ£ĀŚą§śČÄ„āíśúÄťęėšĹć„Ā®„Āó„ÄĀ„ĀĚ„Āģšłč„Āę7„Ā§„ĀģťęėÁ≠ČŤ£ĀŚą§śČÄ„Ā®77„ĀģŚúįśĖĻŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĆťÖćÁĹģ„Āē„āĆ„ā蚳ȌĮ©Śą∂„āíśé°ÁĒ®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģśßčťÄ†„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„ā팟ę„āÄŚ§ö„ĀŹ„ĀģŤŅĎšĽ£ŚõĹŚģ∂„ĀģŚŹłś≥ē„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Ā®ť°ěšľľ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
śúÄťęėŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĮ„ÄĀťęėÁ≠ČŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģśĪļŚģö„ĀęŚĮĺ„Āô„ā蚳䍮īÁģ°ŤĹĄś®©„āíśúČ„Āó„ÄĀ„Āĺ„ĀüŤ≠įšľö„ĀĆŚą∂Śģö„Āó„Āüś≥ēŚĺč„ĀĆśÜ≤ś≥ē„ĀęÁüõÁõĺ„Āô„ā茆īŚźą„Āę„ĀĚ„Āģś≥ēŚĺč„āíÁĄ°ŚäĻ„Ā®Śģ£Ť®Ä„Āô„āč„Ā™„Ā©„ĀģÁČĻŚą•„Ā™ŚéüŚą§śĪļÁģ°ŤĹĄś®©„ā퍰ƚĹŅ„Āó„Āĺ„Āô„ÄāŚúįśĖĻŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĮÁ¨¨šłÄŚĮ©„ĀģŤ£ĀŚą§śČÄ„Ā®„Āó„Ā¶ś©üŤÉĹ„Āó„ÄĀŚźĄŚúįŚĆļ„Āģśú¨ťÉ®„Āꍮ≠ÁĹģ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāťęėÁ≠ČŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĮŚúįśĖĻŤ£ĀŚą§śČÄ„Āč„āČ„ĀģšłäŤ®ī„āíŚĮ©ÁźÜ„Āó„ÄĀŚüļśú¨ÁöĄšļļś®©„āíšŅĚŤ≠∑„Āô„āčŚĹĻŚČ≤„āāśčÖ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀģŤ£ĀŚą§śČÄ„ā∑„āĻ„É܄ɆŤá™šĹď„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„Ā®ŚźĆśßė„ĀģťöéŚĪ§śßčťÄ†„āíśĆĀ„Ā§„āā„Āģ„Āģ„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áŚģ∂„ĀĆÁõīťĚĘ„Āô„ā荙≤ť°Ć„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĆŤ£ĀŚą§Śą∂Śļ¶„ĀĆťĀÖ„ĀŹ„ÄĀšļąśł¨šłćŚŹĮŤÉĹ„Äć„Āß„Āā„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜśĆáśĎė„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀŚŹłś≥ēŚą∂Śļ¶„ĀģśßčťÄ†Ťá™šĹď„ĀĮś®ôśļĖÁöĄ„Āß„Āā„āč„Āę„āā„Āč„Āč„āŹ„āČ„Āö„ÄĀ„ĀĚ„ĀģťĀčÁĒ®ťĚĘ„Āߍ™≤ť°Ć„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āô„āč„Āď„Ā®„Āę„āą„āč„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™Ť™≤ť°Ć„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āô„āč„Āü„āĀ„ÄĀADR„ĀĆ„ÄĆŤŅÖťÄü„Ā™Ťß£śĪļ„Äć„ĀģšĽ£śõŅśČčśģĶ„Ā®„Āó„Ā¶Śľ∑Ť™Ņ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
šĽ£śõŅÁöĄÁīõšļČŤß£śĪļÔľąADRԾȄĀģÁôļŚĪē„Ā®šłĽŤ¶Ā„Ā™śČčś≥ē
šĽ£śõŅÁöĄÁīõšļČŤß£śĪļÔľąADRԾȄĀĮ„ÄĀŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŚ§Ė„Āßšł≠ÁęčÁöĄ„Ā™Á¨¨šłČŤÄÖ„ĀģśĒĮśŹī„āíŚĺó„Ā¶ÁīõšļČ„āíŤß£śĪļ„Āô„āč„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Ā®„Āó„Ā¶ťá捶ĀśÄß„ĀĆŚĘó„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ĀĚ„Āģś≥ēÁöĄśě†ÁĶĄ„ĀŅ„āāśēīŚāô„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āę„Āä„ĀĎ„āčADR„ĀĮ„ÄĀšĽ≤Ť£Āś≥ē2055ŚĻīÔľąArbitration Act, 2055ԾȄĀę„āą„Ā£„Ā¶šĹďÁ≥ĽÁöĄ„Ā™ś≥ēÁöĄśě†ÁĶĄ„ĀŅ„ĀĆśŹźšĺõ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģś≥ēŚĺč„ĀĮ„ÄĀšĽ≤Ť£Āšļļ„ĀĆÁīõšļČŤß£śĪļ„Āģ„Āü„āĀ„Āꍮľśč†ŚŹéťõÜ„ÄĀŤ®ľšļļŚĖöŚēŹ„ÄĀśĖáśõłśŹźŚáļŚĎĹšĽ§„Ā™„Ā©„Āģś®©ťôź„āíśúČ„Āô„āč„Āď„Ā®„āíśėéÁĘļ„ĀęŚģö„āĀ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤ£ĀŚģö„ĀĆŚĹďšļčŤÄÖ„āíśčėśĚü„Āô„āč„Āď„Ā®„ā퍶ŹŚģö„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšĽ≤Ť£Āšļļ„ĀģśĪļŚģö„ĀĮśúÄÁĶāÁöĄ„Ā™„āā„Āģ„Āß„Āā„āä„ÄĀšł°ŚĹďšļčŤÄÖ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶Śľ∑Śą∂Śäõ„āíśĆĀ„Ā§„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āē„āČ„Āę„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áśäÄŤ°ďÁ߼ŤĽĘś≥ēÔľąForeign Investment and Technology Transfer Act: FITTAԾȄāĄPPP„ÉĽśäēŤ≥áś≥ēÔľąPublic Private Partnership and Investment ActԾȄĀ®„ĀĄ„Ā£„Āüťá捶Ā„Ā™Áęčś≥ēśě†ÁĶĄ„ĀŅ„āā„ÄĀADR„āíťÄö„Āė„ĀüŚēŹť°ĆŤß£śĪļ„āíšĹďÁ≥ĽÁöĄ„ĀęśĒĮśŹī„Āô„āčśĚ°ť†Ö„ā팟ę„āď„Āß„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀťĖčÁôļŚßĒŚď°šľöś≥ēÁ¨¨95śĚ°„ĀĮ„ÄĀśĒŅŚļúś©üťĖĘ„Ā®šľĀś•≠„ĀģťĖď„ĀģÁīõšļČ„ĀĆŤß£śĪļ„Āß„Āć„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„ÄĀšł°ŚĹďšļčŤÄÖ„ĀģŚźąśĄŹ„ĀĆ„Āā„āĆ„ĀįšĽ≤Ť£Ā„ĀꚼėŤ®ó„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„ā퍶ŹŚģö„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀšĽ≤Ť£Āšļļ„ĀĮŤ£ĀŚą§śČÄ„Ā®ť°ěšľľ„Āó„Āüś®©ťôź„āíśĆĀ„Ā§„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ADR„Āģś≥ēÁöĄśě†ÁĶĄ„ĀŅ„ĀĆśēīŚāô„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀ„Éć„ÉĎ„Éľ„ÉęśĒŅŚļú„ĀĆŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥ፙėŤáī„Āģ„Āü„āĀ„ĀęÁīõšļČŤß£śĪļ„ĀģŚäĻÁéáŚĆĖ„āíŚõ≥„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āčśĒŅÁ≠ĖÁöĄ„Ā™śĄŹŚõ≥„Āę„āą„āč„āā„Āģ„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀŚģüťöõ„ĀģťĀčÁĒ®„Āß„ĀĮ„ÄĀŚõĹťöõÁöĄ„Ā™„Éď„āł„Éć„āĻśÖ£Ť°Ć„Āł„ĀģÁźÜŤß£šłćŤ∂≥„āĄÁÖ©ťõĎ„Ā™ŚģėŚÉöšłĽÁĺ©„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŤ™≤ť°Ć„ĀĆśģč„āč„Āď„Ā®„āāśĆáśĎė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āü„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ÄĀŚ•ĎÁīĄśõłšĹúśąźśôā„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀÁīõšļČŤß£śĪļśĚ°ť†Ö„Āꚼ≤Ť£ĀÔľąÁČĻ„ĀęŚõĹťöõšĽ≤Ť£ĀԾȄāíśė鍮ė„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„ÄĀŚįܜ̕ÁöĄ„Ā™ÁīõšļČ„É™„āĻ„āĮ„āíÁģ°ÁźÜ„Āô„āčšłä„Āßś•Ķ„āĀ„Ā¶ťá捶Ā„Āß„Āā„āč„Ā®Ť®Ä„Āą„Āĺ„Āô„Äā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āģś≥ēŚą∂Śļ¶„ĀĆŚõĹťöõÁöĄ„Ā™śÖ£Ť°Ć„Ā®ŚģĆŚÖ®„ĀęśēīŚźą„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„āŹ„ĀĎ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āü„āĀ„ÄĀšĽ≤Ť£ĀśĚ°ť†Ö„ĀģŚÖ∑šĹďśÄß„āĄšĽ≤Ť£ĀŚúį„ĀģťĀłŚģö„Āę„ĀĮśÖéťáć„Ā™ś§úŤ®é„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āę„Āä„ĀĎ„āčšľĀś•≠„Ā®ŚäīŚÉćŤÄÖťĖď„ĀģÁīõšļČŤß£śĪļ
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āę„Āä„ĀĎ„āčšľĀś•≠„Ā®ŚäīŚÉćŤÄÖťĖď„ĀģÁīõšļČŤß£śĪļ„ĀĮ„ÄĀšłĽ„Āę2017ŚĻī„ĀęśĖĹŤ°Ć„Āē„āĆ„ĀüŚäīŚÉćś≥ē2074ÔľąLabour Act, 2074ԾȄĀę„āą„Ā£„Ā¶Ť¶ŹŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģś≥ēŚĺč„ĀĮ„ÄĀŚäīŚÉćŤÄÖ„Āģś®©Śą©šŅĚŤ≠∑„ÄĀŚäīšĹŅťĖĘšŅā„ĀģŚľ∑ŚĆĖ„ÄĀŚäīŚÉ期匏Ė„Āģśéíťô§„āíÁõģÁöĄ„Ā®„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀťõáÁĒ®Ś•ĎÁīĄ„ÄĀŚäīŚÉćśôāťĖď„ÄĀŤ≥ÉťáĎ„ÄĀšľĎśöá„ÄĀÁ§ĺšľöšŅĚťöú„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ÁīõšļČŤß£śĪļ„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚĆÖśč¨ÁöĄ„Ā™Ť¶ŹŚģö„ā퍮≠„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ŚäīŚÉćś≥ē2074Ôľą2017ŚĻīԾȄĀģś¶āŤ¶Ā„Ā®ťĀ©ÁĒ®ÁĮĄŚõ≤
ŚäīŚÉćś≥ē2074„ĀĮ„ÄĀšľĀś•≠„ÄĀŚÄčšļļšļčś•≠šłĽ„ÄĀ„ÉĎ„Éľ„Éą„Éä„Éľ„ā∑„ÉÉ„Éó„ÄĀŚćĒŚźĆÁĶĄŚźą„ÄĀ„ĀĚ„ĀģšĽĖ„ĀģŚĖ∂Śą©„ÉĽťĚěŚĖ∂Śą©ÁĶĄÁĻĒ„ā팟ę„āÄ„ÄĀšļčś•≠„ā퍰ƄĀÜŚÖ®„Ā¶„Āģšļčś•≠šĹď„ĀęťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŚźĆś≥ē„ĀĮ„ÄĀŚľ∑Śą∂ŚäīŚÉć„āĄŚÖźÁę•ŚäīŚÉć„ĀģÁ¶Āś≠Ę„ÄĀŚ∑ģŚą•śí§ŚĽÉ„ÄĀŚÖ¨ś≠£„Ā™Ś†ĪťÖ¨„ÄĀŚäīŚÉćÁĶĄŚźąÁĶźśąź„Āģś®©Śą©„Ā™„Ā©„āíšŅĚťöú„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšĽ•ŚČć„ĀģŚäīŚÉćś≥ē2048Ôľą1992ŚĻīԾȄĀ®„ĀĮÁēį„Ā™„āä„ÄĀťĀ©ÁĒ®ÁĮĄŚõ≤„ĀĆśč°Ś§ß„Āē„āĆ„Āü„Āď„Ā®„Āß„ÄĀšł≠ŚįŹšľĀś•≠„ā팟ę„āÄ„āą„āäŚļÉÁĮĄ„Ā™šļčś•≠šĹď„ĀĆŚäīŚÉćś≥ē„ĀģŤ¶ŹŚą∂ŚĮĺŤĪ°„Ā®„Ā™„āä„ÄĀŚäīŚÉćŤÄÖ„ĀģšŅĚŤ≠∑„ĀĆŚľ∑ŚĆĖ„Āē„āĆ„Āĺ„Āó„Āü„Äā
ŚÄ茹•ÁīõšļČ„ĀģŤß£śĪļ„Éó„É≠„āĽ„āĻ
„Éć„ÉĎ„Éľ„ÉęŚäīŚÉćś≥ē„ĀĮ„ÄĀŚÄ茹•ŚäīŚÉćÁīõšļČ„ĀģŤß£śĪļ„Āģ„Āü„āĀ„ĀęśģĶťöéÁöĄ„Ā™„Éó„É≠„āĽ„āĻ„āíŚģö„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Āö„ÄĀŚäīŚÉćś≥ē„ĀĮ„ÄĀšłÄŚģöśēį„ĀģŚĺďś•≠Śď°„āíśäĪ„Āą„āčšľĀś•≠„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀŚÜ֝ɮŤč¶śÉÖŚá¶ÁźÜ„É°„āę„Éč„āļ„Ɇ„ĀģÁĘļÁęč„āíÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚĺďś•≠Śď°„ĀĮ„ÄĀŚēŹť°Ć„āí„Āĺ„ĀöÁõīŚĪě„ĀģšłäŚŹł„Āĺ„Āü„ĀĮśĆáŚģö„Āē„āĆ„ĀüŤč¶śÉÖŚá¶ÁźÜŚßĒŚď°šľö„Ā꜏źŤĶ∑„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚ•®ŚäĪ„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀÁīõšļČ„ĀģŚąĚśúüśģĶťöé„Āß„ĀģŤŅÖťÄü„Ā™Ťß£śĪļ„āíšŅÉ„Āó„ÄĀŚ§ĖťÉ®ś©üťĖĘ„Āł„Āģ„ā®„āĻ„āę„ɨ„Éľ„ā∑„Éß„É≥„āíťĀŅ„ĀĎ„āč„Āü„āĀ„Āģśé™ÁĹģ„Āß„Āô„Äā
ŚÜ֝ɮ„Āß„ĀģŤß£śĪļ„ĀĆŚõįťõ£„Ā™Ś†īŚźą„ÄĀŚĺďś•≠Śď°„Āĺ„Āü„ĀĮ„ĀĚ„ĀģšĽ£Ť°®ŤÄÖ„ĀĮ„ÄĀŚúįśĖĻ„ĀģŚäīŚÉćŚĪÄÔľąŚäīŚÉć„ÉĽťõáÁĒ®„ÉĽÁ§ĺšľöšŅĚťöúÁúĀ„ĀģšłčšĹćś©üťĖĘԾȄĀęÁõīśé•Ťč¶śÉÖ„āíÁĒ≥„ĀóÁęč„Ā¶„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„ÄāŚäīŚÉćŚĪÄ„ĀĮ„ÄĀŤ™ŅŚĀú„ā퍩¶„ĀŅ„Āü„āä„ÄĀšļčś°ą„ĀģŤ™ŅśüĽ„āíťĖčŚßč„Āó„Āü„āä„Āô„āčś®©ťôź„āíśúČ„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģśģĶťöé„ĀĮ„ÄĀšł≠ÁęčÁöĄ„Ā™Á¨¨šłČŤÄÖ„ĀģšĽčŚÖ•„Āę„āą„āä„ÄĀŚĹďšļčŤÄÖťĖď„ĀģŚĮ卩Ī„āíšŅÉťÄ≤„Āó„ÄĀŚźąśĄŹŚĹĘśąź„āíśĒĮśŹī„Āô„āč„Āď„Ā®„āíÁõģÁöĄ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
śú™Ťß£śĪļ„ĀģŚēŹť°Ć„āĄťá挧߄Ā™ťĀēŚŹć„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚĺďś•≠Śď°„ĀĮŚäīŚÉćŤ£ĀŚą§śČÄÔľąLabor CourtԾȄĀ꜏źŤ®ī„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„ÄāŚäīŚÉćŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀĮ„ÄĀŚäīŚÉćŚēŹť°Ć„ĀęťĖĘ„Āô„āčšłĽŤ¶Ā„Ā™ŚŹłś≥ēś©üťĖĘ„Āß„Āā„āä„ÄĀŚÄčšļļ„Āä„āą„Ā≥ťõÜŚõ£„ĀģŚäīŚÉćÁīõšļČ„āíŚĮ©ÁźÜ„Āó„ÄĀšłčšĹć„ĀģŤ°ĆśĒŅśĪļŚģö„ĀęŚĮĺ„Āô„āčśéߍ®ī„āāŚŹó„ĀĎšĽė„ĀĎ„Āĺ„Āô„ÄāŚäīŚÉćŤ£ĀŚą§śČÄ„ĀģŚą§śĪļ„ĀĮś≥ēÁöĄśčėśĚüŚäõ„āíśĆĀ„Ā°„Āĺ„Āô„Äā
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚÄ茹•ŚäīŚÉćÁīõšļČ„ĀģŤß£śĪļ„Éó„É≠„āĽ„āĻ„ĀĮ„ÄĀŚÜ֝ɮŚá¶ÁźÜ„ÄĀŚäīŚÉćŚĪÄ„ÄĀŚäīŚÉćŤ£ĀŚą§śČÄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚ§öśģĶťöé„Āģ„āĘ„Éó„É≠„Éľ„ÉĀ„ĀĆŤ®≠„ĀĎ„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĮśó•śú¨„ĀģŚäīŚÉćÁīõšļČŤß£śĪļ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ÄĀšľĀś•≠ŚÜÖ„Āß„ĀģŤ©Ī„ĀóŚźą„ĀĄ„ÄĀŚäīŚÉćŚüļśļĖÁõ£ÁĚ£ÁĹ≤„ĀģŚä©Ť®Ä„ÉĽśĆáŚįé„āĄÁīõšļČŤß£śĪļ„Āā„Ā£„Āõ„āď„ÄĀŚäīŚÉćŚĮ©Śą§„āĄŤ®īŤ®ü„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüśģĶťöé„Ā®ť°ěšľľ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āę„ĀĮ„ÄĆŚäīŚÉćŤ£ĀŚą§śČÄ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚįāťĖÄ„ĀģŚŹłś≥ēś©üťĖĘ„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āô„āčÁāĻ„ĀĆśó•śú¨„Ā®Áēį„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āü„Ā†„ÄĀ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀģŤ£ĀŚą§Śą∂Śļ¶ŚÖ®šĹď„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„ÄĆťĀÖ„ĀŹ„ÄĀšļąśł¨šłćŚŹĮŤÉĹ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜśĆáśĎė„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁīõšļČÁôļÁĒüśôā„Āę„ĀĮ„Āĺ„ĀöŚÜ֝ɮ„Āß„ĀģŤß£śĪļ„ā퍩¶„ĀŅ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀęŚäīŚÉćŚĪÄ„ĀģŤ™ŅŚĀú„Éó„É≠„āĽ„āĻ„āíÁ©ćś•ĶÁöĄ„ĀęśīĽÁĒ®„Āô„ĀĻ„Āć„Āß„Āô„Äā
ťõÜŚõ£ÁīõšļČ„ĀģŤß£śĪļ„Éó„É≠„āĽ„āĻ
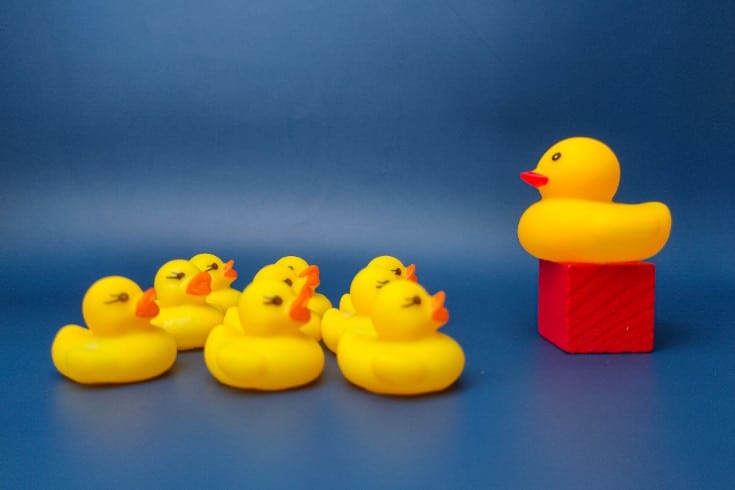
ťõÜŚõ£ŚäīŚÉćÁīõšļČ„ĀģŤß£śĪļ„āā„ÄĀŚäīŚÉćś≥ē2074„Āę„āą„Ā£„Ā¶Ť©≥Áīį„Ā™śČčÁ∂ö„Āć„ĀĆŚģö„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ŚäīŚÉćś≥ē2074„ĀĮ„ÄĀšľĀś•≠„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶ŚäīŚÉćŤÄÖ„ĀģšĽ£Ť°®„Ā®„Āó„Ā¶Śõ£šĹďšļ§śłČŚßĒŚď°šľöÔľąCollective Bargaining Committee: CBCԾȄāíÁĶĄÁĻĒ„Āô„āč„Āď„Ā®„āíÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„ĀôÔľąŚäīŚÉćś≥ēÁ¨¨116śĚ°ÔľČ„Äā„Āď„ĀģŚßĒŚď°šľö„ĀĮ„ÄĀŚÖ¨Ť™ć„Āē„āĆ„ĀüŚäīŚÉćÁĶĄŚźą„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĮŤ§áśēį„ĀģŚäīŚÉćÁĶĄŚźąťĖď„ĀģŚźąśĄŹ„ÄĀ„Āā„āč„ĀĄ„ĀĮŚäīŚÉćŤÄÖ„Āģ60%šĽ•šłä„ĀģÁĹ≤Śźć„Āę„āą„Ā£„Ā¶śßčśąź„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāCBC„ĀĮ„ÄĀŤ≥ÉťáĎ„ÄĀŚäīŚÉćśôāťĖď„ÄĀšľĎśöá„ÄĀŚäīŚÉćśĚ°šĽ∂„ÄĀŚģČŚÖ®Ť°õÁĒü„Ā™„Ā©„ÄĀŚäīŚÉćŤÄÖ„ĀģŚą©Áõä„ĀęťĖĘ„Āô„āčťõÜŚõ£ÁöĄ„Ā™Ť¶ĀśĪā„āĄšłĽŚľĶ„āíśĖáśõł„ĀßťõáÁĒ®šłĽ„Ā꜏źŚáļ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„ÄāŤ¶ĀśĪāśŹźŚáļŚĺĆ„ÄĀťõáÁĒ®šłĽ„ĀĮ7śó•šĽ•ŚÜÖ„Āęšļ§śłČ„āíťĖčŚßč„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āďÔľąŚäīŚÉćś≥ēÁ¨¨117śĚ°ÔľČ„ÄāŚõ£šĹďšļ§śłČ„ĀĮ„ÄĆŤ™†Śģü„Äć„ĀꍰƄāŹ„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„ĀôÔľąŚäīŚÉćś≥ēÁ¨¨129śĚ°ÔľČ„Äā
Śõ£šĹďšļ§śłČ„ĀĆŚźąśĄŹ„ĀęŤá≥„āČ„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„ÄĀÁīõšļČ„ĀĮŚäīŚÉćŚĪÄ„ĀģÁõ£ÁĚ£šłč„Āߍ™ŅŚĀú„Āĺ„Āü„ĀĮšĽ≤Ť£Ā„Éó„É≠„āĽ„āĻ„Āꚼė„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀŤ™ŅŚĀú„ĀĆšłćśąźŚäü„ĀęÁĶā„āŹ„Ā£„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀŚĹďšļčŤÄÖťĖď„ĀģŚźąśĄŹ„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĮŚŅÖť†ą„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„ā휏źšĺõ„Āô„āčšľĀś•≠„ÄĀÁČĻŚą•ÁĶĆśłąŚĆļŚÜÖ„ĀģšľĀś•≠„Āę„Āä„ĀĎ„āčÁīõšļČ„ÄĀ„Āā„āč„ĀĄ„ĀĮŚäīŚÉćÁúĀ„ĀĆŚõĹ„ĀģŤ≤°śĒŅŚćĪś©ü„āĄ„āĻ„Éą„É©„ā§„ā≠„ÉĽ„É≠„ÉÉ„āĮ„āĘ„ā¶„Éą„ĀģŚŹĮŤÉĹśÄß„āíÁźÜÁĒĪ„ĀęŚŅÖŤ¶Ā„Ā®Śą§śĖ≠„Āó„ĀüŚ†īŚźą„Āę„ÄĀšĽ≤Ť£Ā„ĀĆÁĺ©ŚčôšĽė„ĀĎ„āČ„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„ĀôÔľąŚäīŚÉćś≥ēÁ¨¨119śĚ°Á¨¨1ť†Ö„ÄĀÁ¨¨2ť†ÖԾȄÄāŚäīŚÉćÁúĀ„ĀĮ„ÄĀŚäīŚÉćŤÄÖ„ÄĀťõáÁĒ®šłĽ„ÄĀśĒŅŚļú„ĀģšĽ£Ť°®„Āč„āČ„Ā™„ā蚼≤Ť£ĀŚßĒŚď°šľö„ā퍮≠ÁĹģ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤ≤ĽÁĒ®„ĀĮśĒŅŚļú„ĀĆŤ≤†śčÖ„Āó„Āĺ„ĀôÔľąŚäīŚÉćś≥ēÁ¨¨119śĚ°Á¨¨3ť†Ö„ÄĀÁ¨¨4ť†ÖԾȄÄāšĽ≤Ť£Āšļļ„ĀĮ„ÄĀŤ£ĀŚą§śČÄ„Ā®ŚźĆśßė„ĀģŤ®ľśč†ŚŹéťõÜ„āĄŤ®ľšļļŚĖöŚēŹ„Āģś®©ťôź„āíśĆĀ„Ā°„ÄĀťÄöŚłł30śó•šĽ•ŚÜÖ„ĀęŤ£ĀŚģö„āíšłč„Āó„Āĺ„ĀôÔľąŚäīŚÉćś≥ēÁ¨¨119śĚ°Á¨¨9ť†Ö„ÄĀÁ¨¨10ť†ÖԾȄÄāšĽ≤Ť£ĀŤ£ĀŚģö„ĀĮś≥ēÁöĄśčėśĚüŚäõ„āíśĆĀ„Ā°„ÄĀÁôĽťĆ≤„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āߌ֨ŚľŹ„ĀꍙćŤ≠ė„Āē„āĆ„ÄĀŚü∑Ť°Ć„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
ŚäīŚÉćś≥ē2074„ĀĮ„ÄĀťõÜŚõ£šļ§śłČŚßĒŚď°šľö„ĀĆÁČĻŚģö„ĀģÁä∂ś≥Āšłč„Āß„āĻ„Éą„É©„ā§„ā≠„āíÁĶĄÁĻĒ„Āô„āčś®©Śą©„ā퍙ć„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„ĀôÔľąŚäīŚÉćś≥ēÁ¨¨121śĚ°Á¨¨1ť†ÖԾȄÄā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀ„āĻ„Éą„É©„ā§„ā≠ťĖčŚßč„Āģ30śó•ŚČć„Āĺ„Āß„ĀęťõáÁĒ®šłĽ„Āł„ĀģśõłťĚĘťÄöÁü•„Ā®„ÄĀŚúįśĖĻŤ°ĆśĒŅś©üťĖĘ„Āł„ĀģśÉÖŚ†ĪśŹźšĺõ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„ĀôÔľąŚäīŚÉćś≥ēÁ¨¨121śĚ°Á¨¨2ť†ÖԾȄÄā„Āĺ„Āü„ÄĀŚäīŚÉćÁúĀ„ĀĆšĽ≤Ť£Ā„Āę„āą„āčÁīõšļČŤß£śĪļ„āíŚĎĹ„Āė„ĀüŚ†īŚźą„ÄĀ„āĻ„Éą„É©„ā§„ā≠„ĀĮŚĽ∂śúü„Āē„āĆ„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āďÔľąŚäīŚÉćś≥ēÁ¨¨121śĚ°Á¨¨3ť†ÖԾȄÄā
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀģŚäīŚÉćÁĶĄŚźą„ĀĮ„ÄĀ„Āó„Āį„Āó„ĀįśĒŅŚÖö„āĄ„ĀĚ„ĀģśīĺťĖ•„Ā®ťĖĘťÄ£„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®śĆáśĎė„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĮśó•śú¨„ĀģšľĀś•≠ŚÜÖÁĶĄŚźą„ĀĆšłĽśĶĀ„Āß„Āā„āčÁä∂ś≥Ā„Ā®„ĀĮŚ§ß„Āć„ĀŹÁēį„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀÁīõšļČ„ĀĆÁīĒÁ≤č„Ā™ŚäīšĹŅŚēŹť°Ć„ĀęÁēô„Āĺ„āČ„Āö„ÄĀśĒŅś≤ĽÁöĄ„Ā™Śčēś©ü„āĄŚ§ĖťÉ®„Āč„āČ„ĀģŚĹĪťüŅ„ā팏ó„ĀĎ„āĄ„Āô„ĀŹ„Ā™„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äāśó•śú¨šľĀś•≠„ĀĮ„ÄĀ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āßšļčś•≠„ā퍰ƄĀÜťöõ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚäīŚÉćÁĶĄŚźą„Ā®„ĀģťĖĘšŅāśßčÁĮČ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĚ„ĀģśĒŅś≤ĽÁöĄŤÉĆśôĮ„āíÁźÜŤß£„Āó„ÄĀ„Éá„É™„āĪ„Éľ„Éą„Ā™ŚĮĺŚŅú„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„āč„Āď„Ā®„ā퍙ćŤ≠ė„Āô„ĀĻ„Āć„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„āĻ„Éą„É©„ā§„ā≠„Āģ„É™„āĻ„āĮ„āíŤÄÉśÖģ„Āó„Āüšļčś•≠Á∂ôÁ∂öŤ®ąÁĒĽÔľąBCPԾȄĀģÁ≠ĖŚģö„āāťá捶Ā„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Ā®„āĀ
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀĮ„ÄĀšľĚÁĶĪÁöĄ„Ā™ADRśČčś≥ē„Ā®ÁŹĺšĽ£ÁöĄ„Ā™ŚŹłś≥ēŚą∂Śļ¶„āíÁĶĄ„ĀŅŚźą„āŹ„Āõ„ĀüÁ訍ᙄĀģÁīõšļČŤß£śĪļ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„āíśúČ„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀÁČĻ„ĀęŚäīŚÉćÁīõšļČ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚÜ֝ɮŤč¶śÉÖŚá¶ÁźÜ„Āč„āČŚäīŚÉćŚĪÄ„Āę„āą„ā荙ŅŚĀú„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ŚäīŚÉćŤ£ĀŚą§śČÄ„Āł„Ā®ťÄ≤„āÄŚ§öśģĶťöé„Āģ„Éó„É≠„āĽ„āĻ„ĀĆÁĘļÁęč„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āü„Ā†„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áŚģ∂„ĀĮ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀģŤ£ĀŚą§Śą∂Śļ¶ŚÖ®šĹď„āí„ÄĆťĀÖ„ĀŹ„ÄĀšļąśł¨šłćŚŹĮŤÉĹ„Äć„Ā®Ť©ēšĺ°„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„Āß„ĀģŚäīŚÉćÁīõšļČ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚäīŚÉćŤ£ĀŚą§śČÄ„Āł„ĀģśŹźŤ®ī„ĀĮśúÄÁĶāśČčśģĶ„Ā®šĹćÁĹģ„Ā•„ĀĎ„ÄĀŚŹĮŤÉĹ„Ā™ťôź„āäŚÜ֝ɮŤß£śĪļ„āĄŚäīŚÉćŚĪÄ„āíťÄö„Āė„ĀüŤ™ŅŚĀú„ÉĽšĽ≤Ť£ĀÔľąADRԾȄĀßśó©śúüŤß£śĪļ„āíŚõ≥„āč„Āď„Ā®„ĀĆŤ≥Ęśėé„Āß„Āô„Äāśó•śú¨„ĀģŚäīŚÉćŚĮ©Śą§„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ŤŅÖťÄü„Ā™Ťß£śĪļ„ĀĆ„ÄĀ„Éć„ÉĎ„Éľ„Éę„ĀģŚäīŚÉćŤ£ĀŚą§śČÄ„Āߌłł„ĀęśúüŚĺÖ„Āß„Āć„āč„āŹ„ĀĎ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„āíÁźÜŤß£„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āč„Ā®Ť®Ä„Āą„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
ťĖĘťÄ£ŚŹĖśČĪŚąÜťáéÔľöŚõĹťöõś≥ēŚčô„ÉĽśĶ∑Ś§Ėšļčś•≠
„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ: IT„ÉĽ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀģšľĀś•≠ś≥ēŚčô
„āŅ„āį: „Éć„ÉĎ„Éľ„ÉęśĶ∑Ś§Ėšļčś•≠