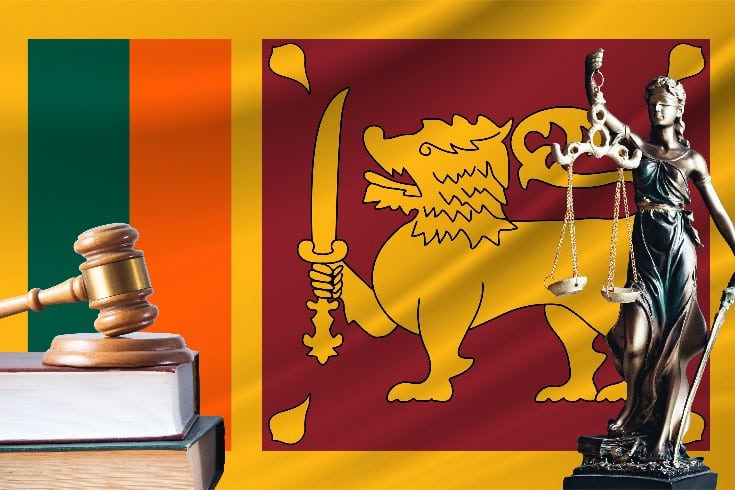オーストリア共和国の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

オーストリアは、中央ヨーロッパに位置する連邦共和制国家であり、高度に発展した工業国です。特に、経済全体に占めるサービス産業の割合が高いことが特徴で、機械、鉄鋼、自動車産業なども主要な工業部門を形成しています。一方で、近年は高インフレと個人消費の低迷が続き、2024年の実質GDP成長率はマイナス1.2%となるなど、第二次世界大戦後最長の景気後退に直面しているとされています。しかし、2025年第1四半期には工業生産の回復が見られ、経済の持ち直しの兆しも見え始めています。
日本の法律と多くの共通点を持つオーストリアの法制度ですが、その背景にはEU法という共通の法的枠組みが存在しており、これが事業活動に大きな影響を与えます。
本記事では、オーストリアの法体系やビジネスに関わる主要な法律の概要について解説します。
この記事の目次
オーストリアの法体系と司法制度の全体像
法体系の基礎と日本の法との比較
オーストリアの法体系は、日本と同様にローマ法を起源とする大陸法系に属し、成文法が主要な法源で、段階的な構造を特徴としています。その最上位には、オーストリア連邦憲法、個々の憲法律、そしてEU加盟条約が位置付けられ、その下に、その他の連邦法や州法が続く構造です。この構造自体も日本の法体系と類似していると言えますし、また、日本の民法典の制定にも影響を与えたとされる「オーストリア一般民法典(ABGB)」は、1804年のフランス民法典と並び、200年以上を経た現在も適用されている現行法です。
日本の法体系との重要な違いとして、オーストリアの法制度には、日本の判例法のように「法的拘束力を持つ判例」は存在しません。判決や解釈は裁判官の自由裁量に委ねられており、過去の判例はあくまで論拠として引用されるに留まります。このことは、裁判官個々の判断の幅がより広いことを意味しており、日本の裁判官が判例を重んじる傾向があるのに対し、オーストリアではより裁判官の裁量に重きが置かれる傾向があると言えるでしょう。
裁判所の種類と構造
オーストリアの司法制度は、通常裁判所に加え、独立した憲法裁判所と行政裁判所が存在する点が日本と大きく異なります。日本の裁判所が行政事件や憲法判断も行うのに対し、オーストリアではこれらの権限が専門の裁判所に集中しています。
通常裁判所の構造においては、民事訴訟は紛争の内容や請求額に応じて、第一審裁判所の管轄が決定されます。紛争金額が1万5,000ユーロ以下の場合は地方裁判所(Bezirksgericht)が、これを超える場合は州裁判所(Landesgericht)が第一審の管轄権を有します。さらに、ウィーンには、商業登記簿に登記された事業者・団体を被告とする紛争、株式会社法(Aktiengesetz)や有限責任会社法(GmbH-Gesetz)に基づく紛争、製造物責任法(Produkthaftungsgesetz)に基づく紛争などを専門的に扱う商事裁判所が設置されています。
オーストリアでのビジネス展開における主要な法律分野の解説

会社設立とコーポレートガバナンス
オーストリアの法人法は、個人事業、人的会社、資本会社に大別されます。日本の法人形態に相当する資本会社では、有限会社(GmbH)が最も一般的であり、株式会社(AG)は特に上場企業にとって必須の形態とされています。有限会社は、設立費用が比較的安価で、形式要件が少ないため、多くの投資家が選択する傾向にあります。
設立手続きには、二段階のプロセスが存在します。まず、有限会社の場合、定款を公正証書の形式で作成する必要があります。次に、この公正証書や業務執行取締役の署名証明書などの書類を添付して、商業登記簿(Firmenbuch)に申請します。この登記手続きは通常、1週間から2週間程度で完了します。
日本の法体系との重要な違いとして、商業登記簿への登録が完了しただけでは、事業を開始できない場合がある点が挙げられます。ほとんどの事業活動には、商業登記とは別に、商法に基づく事業ライセンス(Gewerbeberechtigung)の取得が必要です。ライセンス取得には、商法に基づく事業許可責任者(Gewerberechtlicher Geschäftsführer)を登録する必要があり、この人物は必ずしも法人の業務執行取締役と同一人物である必要はありません。
この、会社法上の業務執行責任者と、商法上の事業許可責任者を同一人物にする必要がないという事実は、法人の行政規制遵守における責任と、特定の事業活動に関する専門的責任を分離していることを示しています。これは、事業の種類に応じて、その分野の専門的知識や資格を持つ人物が、法人の経営責任者とは別に、事業の法的・技術的な側面を監督するという、より専門性を重視したガバナンスを要求していると考えられます。日本企業がオーストリアで事業を行う際には、事業の種類に応じた追加的な資格要件と、それを満たす責任者の任命が必要となるため、日本にはない新たなコンプライアンス要件として注意を払う必要があります。
海外投資規制
オーストリアは、欧州経済領域(EEA)外の企業による自国企業買収に対し、厳格な事前審査制度を導入しています。この規制は、2020年7月に発効した投資規制法(ICA)によって強化されました。
日本企業への直接的な影響として、EU加盟国以外の企業がオーストリア企業を買収する際、議決権の25%以上、または50%以上を取得する場合は、デジタル経済担当大臣への届け出と許可が必要です。特に注意すべきは、国防、エネルギー、水、デジタルインフラ、医療関連の研究開発など、「機密性の高い分野」の事業を行う企業の場合、議決権の取得比率が10%以上で事前審査の対象となる点です。従業員10人未満、年間売上高200万ユーロ未満の零細企業やスタートアップ企業は、この規制の対象外となります。
このような低い閾値で事前審査を課す制度は、単なる外国資本規制にとどまらず、より広範な経済安全保障上の懸念を背景にしています。インフラ分野や重要産業への外国企業の影響力拡大への警告として、この法改正が位置付けられています。これは、オーストリアおよびEU全体が、自国の基幹インフラや技術、データ主権といった公共の利益を、海外資本から積極的に保護しようとする強い政治的意思の表れと解釈すべきでしょう。
労働法
オーストリアの労働市場では、書面による雇用契約が一般的ですが、いくつかの例外(見習い職や公共部門の一部など)を除き、口頭契約も有効です。
日本の労働基準法第15条に基づく「労働条件の明示義務」と類似した制度として、オーストリアでは口頭で雇用契約を締結した場合、雇用主は従業員に対し、雇用開始時にDienstzettelと呼ばれる雇用条件の要約書を交付する義務があります。この書面には、雇用主・従業員の氏名住所、雇用開始日、給与、労働時間、休暇など、重要な契約条件が明記されなければなりません。これは、口頭契約の有効性を前提としつつ、その内容を事後的に書面で補完するという点で、日本の労働慣行とは異なるアプローチであると言えます。
また、オーストリアの労働慣行として、1年に12ヶ月の月給に加え、13ヶ月目と14ヶ月目にあたる特別給与(休暇手当とクリスマスボーナス)が支給されるという慣習があります。この特別給与は、低い税率が適用されるという税制上の優遇も受けます。この制度は法律で一律に義務付けられているものではありませんが、多くの労働協約で定められ、社会的な慣習として定着しています。これは、オーストリアの労働法が、単なる成文法だけでなく、歴史的に形成された社会慣習や労働組合の力学によっても大きく規定されていることを示唆しています。
広告・表示規制
オーストリアの競争法制は、日本の景品表示法に相当する「不公正競争防止法(UWG:Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb)」や「カルテル法(Kartellgesetz)」などから構成されています。UWGは、不公正な商行為や誤解を招く広告を禁止しており、これに違反すると罰金などの行政処分が科される可能性があります。この枠組みは日本の景品表示法と目的を同じくすると言えるでしょう。
特に、日本の医療広告ガイドラインとの決定的な違いとして、オーストリアの医療広告規制はより厳格です。オーストリアの医薬品法(AMG)では、医薬品および医療機器の広告について厳格な規制が設けられており、特に処方箋医薬品の一般消費者向け広告は原則として禁止されています。一般消費者向けの広告には、誇張や成功の保証、副作用がないという主張を含めることが禁じられており、また、不正確な自己診断を促すような詳細な病状の説明も許されません。
AI法とGDPR
オーストリアはEU加盟国であるため、EUで可決された「AI法(AI Act)」が国内でも直接適用されます。この法律は、AIの利用がもたらすリスクを4段階に分類し、それぞれ異なる要件を課します。
日本企業が直面する最大の課題は、AI法の「域外適用」です。AI法は、EU域内にAIシステムを提供する域外企業にも適用されることが明示されており、日本に本社を置く企業であっても、そのAIサービスがオーストリアの消費者や企業に利用される場合、AI法の規制対象となります。
また、同様に、オーストリアでは、EUの一般データ保護規則(GDPR)が国内法として直接適用されます。日本の個人情報保護法よりも厳格なデータ処理要件が課せられる点が、日本企業にとって重要な考慮事項となります。
まとめ
オーストリアは、日本と共通の法体系を基盤としながらも、EU法という上位の枠組みの中で、独自の厳格な規制を形成しています。特に、海外投資、医療広告、そして最先端のAI技術といった分野における規制は、日本と比較してより厳格かつ保護主義的な側面を持っており、これらの法務課題への適切な対応が事業成功の鍵を握ります。
会社設立の手続きにおける事業ライセンスの取得、現地慣習に合わせた労働契約の締結、そしてAI法やGDPRといったEU法への継続的なコンプライアンス維持など、オーストリアでのビジネス展開には多岐にわたる専門知識が求められます。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務