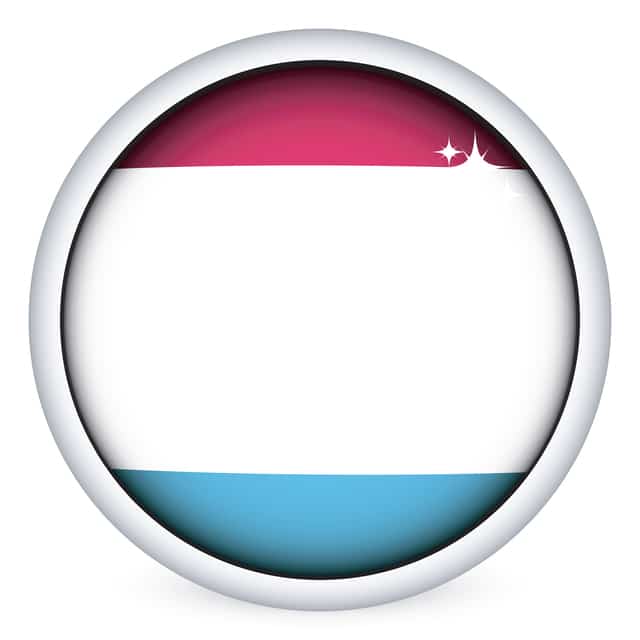„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ„Āę„Āä„ĀĎ„ā茧ĖŚõĹšļļ„Āę„āą„āčšłćŚčēÁĒ£Śą©ÁĒ®„Ā®ŚúüŚúįś≥ē„Āę„āą„āčŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©

śó•śú¨„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮŚúüŚúį„ĀģÁßĀśúČ„ĀĆŚļÉ„ĀŹŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„ÄĀŚ§ĖŚõĹšļļ„āāŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶ŚúüŚúį„āíśČÄśúČ„Āß„Āć„āč„Āģ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹśÜ≤ś≥ē„ĀĮ„ÄĀŚÖ®„Ā¶„ĀģŚúüŚúį„ĀĆŚõĹŚģ∂„ĀģśČÄśúČ„ĀęŚĪě„Āô„āč„Ā®Ť¶ŹŚģö„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áŚģ∂„ĀĆ„ÉĘ„É≥„āī„Éę„ĀßšłćŚčēÁĒ£„ā팹©ÁĒ®„Āô„āčťöõ„ĀꌏĖŚĺóŚŹĮŤÉĹ„Ā™„Āģ„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆśČÄśúČś®©„Äć„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĆŚą©ÁĒ®ś®©„Äć„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āô„Ā™„āŹ„Ā°„ÄĀŚ§ĖŚõĹ„Āģś≥ēšļļ„āĄŚÄčšļļ„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúį„āíÁõīśé•śČÄśúČ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„Āß„Āć„Āö„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģÁõģÁöĄ„Āģ„Āü„āĀ„ĀęŚúüŚúį„āí„Äƌ憜úČ„Äć„Āó„ÄĆŚą©ÁĒ®„Äć„Āô„āčś®©Śą©„āí„ÄĀŚõĹŚģ∂„Ā®„ĀģŚ•ĎÁīĄ„ĀęŚüļ„Ā•„Ā挏ĖŚĺó„Āô„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„Äƌ憜úČś®©„Äć„Āä„āą„Ā≥„ÄĆŚą©ÁĒ®ś®©„Äć„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„ĀģŚúįšłäś®©„āĄŤ≥ÉŚÄüś®©„Āęť°ěšľľ„Āô„āčŚĀīťĚĘ„āíśĆĀ„Ā§šłÄśĖĻ„Āß„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęÁ訍ᙄĀģś≥ēšĹďÁ≥Ľ„Āģšłč„ĀßťĀčÁĒ®„Āē„āĆ„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤ©≥Áīį„Ā™ŚÜÖŚģĻ„ÄĀŚŹĖŚĺóśĖĻś≥ē„ÄĀśúüťĖď„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ś®©Śą©„ĀģÁ߼ŤĽĘŚŹĮŤÉĹśÄß„Ā™„Ā©„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶ś≠£ÁĘļ„Ā™ÁźÜŤß£„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀŚ§ĖŚõĹšļļ„ĀĆ„ÉĘ„É≥„āī„Éę„ĀߌúüŚúį„āíśČÄśúČ„Āß„Āć„Ā™„ĀĄś≥ēÁöĄś†Ļśč†„ÄĀŚ§ĖŚõĹšļļ„Āꍙć„āĀ„āČ„āĆ„āčŚúüŚúį„ĀģŚć†śúČś®©„Āä„āą„Ā≥Śą©ÁĒ®ś®©„ĀģŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™ŚÜÖŚģĻ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚŹĖŚĺóśČčÁ∂ö„āĄŤ®ĪŚģĻ„Āē„āĆ„ā茹©ÁĒ®śúüťĖď„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ś®©Śą©„ĀģÁ߼ŤĽĘ„āĄśčÖšŅĚŤ®≠Śģö„ĀģŚŹĮŤÉĹśÄß„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŤęĖÁāĻ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ťß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„ĀģÁõģś¨°
„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚúüŚúįśČÄśúČ„ĀģŚéüŚČá„Ā®Ś§ĖŚõĹšļļ„ĀģŚúüŚúįśČÄśúČŚą∂ťôź
„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ„Āę„Āä„ĀĎ„āčšłćŚčēÁĒ£„ĀęťĖĘ„Āô„āčś≥ēŚą∂Śļ¶„āíÁźÜŤß£„Āô„āčšłä„Āß„ÄĀśúÄ„āāś†ĻŚĻĻ„Ā®„Ā™„āč„Āģ„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚúüŚúįśČÄśúČ„ĀģŚéüŚČá„Āß„Āô„Äāśó•śú¨„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀśÜ≤ś≥ē„ĀĆŤ≤°ÁĒ£ś®©„āíšŅĚťöú„Āó„ÄĀŚúüŚúį„ĀģÁßĀśúČ„ĀĆŚļÉ„ĀŹŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ„Āß„ĀĮŚúüŚúį„ĀģŚõĹŚģ∂śČÄśúČ„ĀĆśÜ≤ś≥ēšłä„ĀģŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶ÁĘļÁęč„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹśÜ≤ś≥ēÁ¨¨6śĚ°Á¨¨1ť†Ö„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ„ĀģŚúüŚúį„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚúįšłč„ÄĀś£ģśěó„ÄĀśįīŤ≥áśļź„ÄĀŚčēś§ćÁČ©ŚŹä„Ā≥„ĀĚ„ĀģšĽĖ„ĀģŚ§©ÁĄ∂Ť≥áśļź„ĀĮ„ÄĀŚõĹŚģ∂„ĀģŤ≤°ÁĒ£„Āß„Āā„āč„Äć„Ā®Ť¶ŹŚģö„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģŤ¶ŹŚģö„ĀĮ„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹŚÜÖ„ĀģŚÖ®„Ā¶„ĀģŚúüŚúį„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŤ°®ťĚĘ„ÄĀŚúįšłč„ÄĀŚúüŚ£Ć„ā팟ę„āĀ„ÄĀŚõĹŚģ∂„ĀģśČÄśúČ„ĀęŚĪě„Āô„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚéüŚČá„āíÁ§ļ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģŚéüŚČá„ĀĮ„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚúüŚúįś≥ēÁ¨¨3śĚ°Á¨¨3ť†ÖÁ¨¨1ŚŹ∑„Āę„āą„Ā£„Ā¶„āāŚÜćÁĘļŤ™ć„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
šłÄśĖĻ„Āß„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹśÜ≤ś≥ēÁ¨¨6śĚ°Á¨¨2ť†Ö„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆśĒĺÁČߌúįŚŹä„Ā≥ÁČߍćČŚúį„āíťô§„ĀŹŚúüŚúį„ĀĮ„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹŚłāśįĎ„ĀęÁßĀśúČŤ≤°ÁĒ£„Ā®„Āó„Ā¶šłé„Āą„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Äć„Ā®Śģö„āĀ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹśįĎ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ĀĮšłÄŚģö„ĀģśĚ°šĽ∂„Āģšłč„ĀߌúüŚúį„ĀģÁßĀśúČ„ĀĆŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹśįĎ„ĀĆ„ÄĆŚúüŚúįśČÄśúČś®©„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĀś≥ēŚĺč„Āߌģö„āĀ„āČ„āĆ„ĀüÁĮĄŚõ≤ŚÜÖ„ĀߌúüŚúį„āíŚć†śúČ„ÄĀŚą©ÁĒ®„ÄĀŚá¶ŚąÜ„Āô„āčś®©Śą©„āíśĆĀ„Ā§„Āď„Ā®„ā휥ŹŚĎ≥„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Āó„Āč„Āó„ÄĀŚ§ĖŚõĹ„Āģś≥ēšļļ„āĄŚÄčšļļ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„Āď„ĀģŚõĹśįĎ„Āꍙć„āĀ„āČ„āĆ„āčŚúüŚúįśČÄśúČś®©„ĀĮšłÄŚąášĽėšłé„Āē„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„Äā„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚúüŚúįś≥ēÁ¨¨3śĚ°Á¨¨3ť†ÖÁ¨¨3ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆŚ§ĖŚõĹ„ĀģŚõĹŚģ∂„ÄĀŚõĹťöõś©üťĖĘ„ÄĀŚ§ĖŚõĹ„Āģś≥ēšļļŚŹä„Ā≥Ś§ĖŚõĹ„ĀģŚłāśįĎ„ĀĮ„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶ŚúüŚúį„āíśČÄśúČ„Āô„āč„Āď„Ā®„āíÁ¶Āś≠Ę„Āē„āĆ„āč„Äć„Ā®śėéÁĘļ„ĀꍶŹŚģö„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚ§ĖŚõĹšļļ„ĀĆ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹŚÜÖ„ĀߌúüŚúį„āíÁõīśé•śČÄśúČ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮś≥ēÁöĄ„ĀęÁ¶Ā„Āė„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŚúüŚúį„ĀģŚõĹŚģ∂śČÄśúČŚéüŚČá„Ā®Ś§ĖŚõĹšļļ„ĀģŚúüŚúįśČÄśúČŚą∂ťôź„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„ĀģšłćŚčēÁĒ£ś≥ēŚą∂„Ā®„ĀģśúÄ„āāť°ēŤĎó„Ā™ÁõłťĀēÁāĻ„Āß„Āā„āä„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„Éę„Āł„ĀģśäēŤ≥á„ā휧úŤ®é„Āô„āčśó•śú¨šľĀś•≠„ĀĆśúÄŚąĚ„ĀęÁźÜŤß£„Āô„ĀĻ„Āć„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äāśó•śú¨ś≥ē„Āß„ĀĮ„ÄĀŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶Ś§ĖŚõĹšļļ„āāśó•śú¨šļļ„Ā®ŚźĆśßė„ĀęŚúüŚúį„ĀģśČÄśúČś®©„ā팏ĖŚĺó„Āß„Āć„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„Éę„Āß„ĀĮ„ĀĚ„āĆ„ĀĆŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„Ā™„ĀĄ„Āü„āĀ„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áŚģ∂„ĀĮŚúüŚúį„ĀģŚą©ÁĒ®ś®©„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚĹĘ„ĀßšłćŚčēÁĒ£„Āę„āĘ„āĮ„āĽ„āĻ„Āô„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Āü„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹśÜ≤ś≥ēÁ¨¨6śĚ°Á¨¨1ť†Ö„ĀĆ„ÄĆŚúüŚúį„Äć„ĀģŚģöÁĺ©„Āę„ÄĆŚúįšłč„Äć„ā팟ę„āÄ„Ā®śė鍮ė„Āó„Ā¶„ĀĄ„āčÁāĻ„ĀĮ„ÄĀťČĪś•≠„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Ā®„ĀģťĖĘšŅā„Āß„ĀĮťá捶Ā„Ā™śĄŹŚĎ≥„āíśĆĀ„Ā°„Āĺ„Āô„Äā„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚúüŚúįś≥ēÁ¨¨3śĚ°Á¨¨2ť†ÖÁ¨¨2ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĀŚúįšłč„Āä„āą„Ā≥„ĀĚ„ĀģŤ≥áśļź„ĀģśČÄśúČ„ÄĀŚć†śúČ„ÄĀŚą©ÁĒ®„ĀęťĖĘ„Āô„āčťĖĘšŅā„ĀĆŚą•ťÄĒ„Āģś≥ēŚĺč„Āę„āą„Ā£„Ā¶Ť¶ŹŚĺč„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„ā퍶ŹŚģö„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áŚģ∂„ĀĆťČĪś•≠„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀęťĖĘ„āŹ„ā茆īŚźą„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúį„ĀģŚą©ÁĒ®ś®©„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀťČĪś•≠ś≥ē„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹśé°śéėś®©„Ā™„Ā©„ĀģŚą•ťÄĒ„Āģś®©Śą©ŚŹĖŚĺó„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āč„Āď„Ā®„ÄĀ„Āô„Ā™„āŹ„Ā°„ÄĀŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀĆŚúįšłčŤ≥áśļź„ĀģŚą©ÁĒ®ś®©„ā팟ę„Āĺ„Ā™„ĀĄ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĀŚúüŚúį„Ā®ŚúįšłčÔľąŚúįšłčŤ≥áśļźÔľČ„ĀģŚĆļŚą•„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„āŹ„ĀĎ„Āß„Āô„Äā„Āó„Āü„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ÄĀśó•śú¨šľĀś•≠„ĀĆ„ÉĘ„É≥„āī„Éę„Āߍ≥áśļźťĖčÁôļ„āĄ„ÄĀŚúįšłčŚą©ÁĒ®„āíšľī„ĀÜ„ā§„É≥„Éē„É©„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„ÉąÔľąšĺč„Āą„Āį„ÄĀ„Éą„É≥„Éć„Éę„āĄŚúįšłč„ÉĎ„ā§„Éó„É©„ā§„É≥„Ā™„Ā©ÔľČ„ā휧úŤ®é„Āô„āčťöõ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀģŚŹĖŚĺó„ĀęŚä†„Āą„Ā¶„ÄĀťĖĘťÄ£„Āô„āčŚúįšłčŤ≥áśļźś≥ē„āĄťČĪś•≠ś≥ē„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹŤŅŌ䆄ĀģŤ®ĪŤ™ćŚŹĮ„āĄś®©Śą©ŚŹĖŚĺó„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āč„Āď„Ā®„āíŚČ朏ź„Āę„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶Ś§ĖŚõĹšļļ„Āꍙć„āĀ„āČ„āĆ„āčŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀģśÄߍ≥™„Ā®Á®ģť°ě

„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶Ś§ĖŚõĹšļļ„ĀĆŚúüŚúį„Āę„āĘ„āĮ„āĽ„āĻ„Āô„āčŚĒĮšłÄ„ĀģśČčśģĶ„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúį„ĀģśČÄśúČś®©„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„Äƌ憜úČś®©„Äć„Āä„āą„Ā≥„ÄĆŚą©ÁĒ®ś®©„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ā팏ĖŚĺó„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā„Āď„āĆ„āČ„Āģś®©Śą©„ĀĮ„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚúüŚúįś≥ē„Āä„āą„Ā≥śäēŤ≥áś≥ē„ĀęŚüļ„Ā•„Āć„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģÁõģÁöĄ„Ā®śúüťĖď„Āęťôź„ā䚼ėšłé„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚúüŚúįś≥ēÁ¨¨3śĚ°Á¨¨3ť†ÖÁ¨¨4ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆŚ§ĖŚõĹ„Āģś≥ēšļļŚŹä„Ā≥ŚłāśįĎ„ĀĮ„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀęŚüļ„Ā•„ĀćŚúüŚúį„āíŚć†śúČ„Āó„ÄĀŚą©ÁĒ®„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Äć„Ā®śė鍮ė„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĆŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áŚģ∂„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶„ĀģŚúüŚúįŚą©ÁĒ®„Āģś≥ēÁöĄś†Ļśč†„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āď„Āß„ĀĄ„ĀÜ„Äƌ憜úČ„Äć„Ā®„ĀĮ„ÄĀś≥ēŚĺč„Āä„āą„Ā≥ťĖĘťÄ£Ś•ĎÁīĄ„ĀģÁĮĄŚõ≤ŚÜÖ„Āß„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģÁõģÁöĄ„Āģ„Āü„āĀ„ĀęŚúüŚúį„āíÁģ°ÁźÜ„Āó„ÄĀŚć†śúČ„Āô„āčś®©Śą©„āíśĆá„Āó„ÄĀšłÄśĖĻ„ÄĆŚą©ÁĒ®„Äć„Ā®„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúį„ĀģśúČÁĒ®„Ā™ÁČĻśÄß„āí„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚéüÁä∂„ā팧Ȝõī„Āô„āč„Āď„Ā®„Ā™„ĀŹŚą©ÁĒ®„Āô„āčśīĽŚčē„ā퍰ƄĀÜś®©Śą©„ā휥ŹŚĎ≥„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„āČ„ĀģŚģöÁĺ©„Āč„āČ„ÄĀŚć†śúČś®©„Ā®Śą©ÁĒ®ś®©„ĀĆÁĶĄ„ĀŅŚźą„āŹ„Āē„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŚ§ĖŚõĹšļļ„ĀĮŚúüŚúį„āíÁČ©ÁźÜÁöĄ„ĀęśĒĮťÖć„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģÁĶĆśłąÁöĄšĺ°ŚÄ§„āíšļꌏó„Āß„Āć„āč„Āď„Ā®„ĀĆÁźÜŤß£„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„āĆ„āČ„ĀģŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀĮ„ÄĀŚõĹŚģ∂Ť°ĆśĒŅś©üťĖĘ„Āę„āą„Ā£„Ā¶šĽėšłé„Āē„āĆ„ÄĀ„ĀĚ„Āģś®©Śą©„ĀĮŚúüŚúįŚŹįŚł≥„ĀęÁôĽťĆ≤„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āßś≥ēÁöĄ„Ā™ŚäĻŚäõ„āíśĆĀ„Ā°„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģÁôĽťĆ≤Śą∂Śļ¶„ĀĮ„ÄĀś®©Śą©„ĀģŚÖ¨Á§ļ„Ā®šŅĚŤ≠∑„ĀģŤ¶≥ÁāĻ„Āč„āČťĚ쌳ł„Āęťá捶Ā„Āß„Āā„āä„ÄĀśó•śú¨„ĀģšłćŚčēÁĒ£ÁôĽŤ®ėŚą∂Śļ¶„Ā®ŚźĆśßė„Āę„ÄĀÁ¨¨šłČŤÄÖŚĮĺśäóŤ¶ĀšĽ∂„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģŚĹĻŚČ≤„āíśěú„Āü„Āó„Āĺ„Āô„Äā
ŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„Āę„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģśÄߍ≥™šłä„ÄĀšĽ•šłč„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ÁČĻŚĺī„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
- ÁõģÁöĄ„ĀģÁČĻŚģöśÄß: ŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀĮ„ÄĀŚŅÖ„ĀöÁČĻŚģö„ĀģÁõģÁöĄ„Āģ„Āü„āĀ„Āꚼėšłé„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀŚ∑•ś•≠ÁĒ®Śúį„ÄĀŚēÜś•≠ÁĒ®Śúį„ÄĀšĹŹŚģÖÁĒ®Śúį„ÄĀŤĺ≤ś•≠ÁĒ®Śúį„Ā™„Ā©„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„Āߌģö„āĀ„āČ„āĆ„ĀüÁĒ®ťÄĒšĽ•Ś§Ė„ĀęŚúüŚúį„ā팹©ÁĒ®„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶„Āß„Āć„Āĺ„Āõ„āď„ÄāÁĒ®ťÄĒŚ§Čśõī„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā™Ś†īŚźą„ĀĮ„ÄĀśĖį„Āü„Ā™Ś•ĎÁīĄÁ∑†ÁĶź„āĄśóĘŚ≠ėŚ•ĎÁīĄ„ĀģŚ§ČśõīśČčÁ∂ö„Āć„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
- śúüťĖď„ĀģŚą∂ťôź: ŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀĮ„ÄĀśúüťĖď„ĀĆťôźŚģö„Āē„āĆ„Āüś®©Śą©„Āß„Āô„ÄāšłÄŤą¨ÁöĄ„Ā™ŚúüŚúį„ĀģŚć†śúČ„ÉĽŚą©ÁĒ®ś®©„ĀģŚąĚśúüśúüťĖď„ĀĮśúÄťē∑15ŚĻī„Ā®„Āē„āĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ10ŚĻī„ĀĒ„Ā®„ĀģŚĽ∂ťē∑„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀÁ∑ŹśúüťĖď„ĀĮ40ŚĻī„āíŤ∂Ö„Āą„Ā¶„ĀĮ„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥á„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„āą„āäťē∑śúü„ĀģŚą©ÁĒ®„ĀĆŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāśäēŤ≥áś≥ēÁ¨¨7śĚ°Á¨¨2ť†Ö„Āä„āą„Ā≥ŚúüŚúįś≥ēÁ¨¨3śĚ°Á¨¨6ť†ÖÁ¨¨3ŚŹ∑„ĀęŚüļ„Ā•„Āć„ÄĀ„ÄĆŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥á„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀģŚģüśĖĹ„Āģ„Āü„āĀ„ĀęŚúüŚúį„āíŚć†śúČ„Āó„ÄĀŚą©ÁĒ®„Āô„āčśúüťĖď„ĀĮ„ÄĀśúÄťē∑60ŚĻī„Ā®„Āó„ÄĀ„Āē„āČ„ĀęśúÄťē∑40ŚĻī„Āĺ„ĀߌĽ∂ťē∑„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„āč„Äā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀÁ∑ŹśúüťĖď„ĀĮ100ŚĻī„āíŤ∂Ö„Āą„Ā¶„ĀĮ„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Äć„Ā®Ť¶ŹŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚ§ßŤ¶Źś®°„Ā™ťē∑śúüśäēŤ≥á„ā퍙ėŤáī„Āô„āč„Āü„āĀ„ĀģŚĄ™ťĀáśé™ÁĹģ„ĀĆŤ¨õ„Āė„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāťČĪŚĪĪťĖčÁôļ„āĄŚ§ßŤ¶Źś®°„Ā™Ś∑•Ś†īŚĽļŤ®≠„ÄĀ„ā§„É≥„Éē„É©śēīŚāô„Ā™„Ā©„ÄĀŚąĚśúüśäēŤ≥á„ĀĆŚ§ß„Āć„ĀŹŚõ쌏é„Āęťē∑śúüťĖď„ā퍶Ā„Āô„āč„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶„ÄĀŚćĀŚąÜ„Ā™šļčś•≠Á∂ôÁ∂öśÄß„āíšŅĚŤ®ľ„Āô„āč„Āü„āĀ„Āģśé™ÁĹģ„Ā†„Ā®Ť®Ä„Āą„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
- Ś•ĎÁīĄ„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹšĽėšłé: ŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀĮ„ÄĀŚõĹŚģ∂Ť°ĆśĒŅś©üťĖĘ„Ā®Śą©ÁĒ®ŚłĆśúõŤÄÖ„Ā®„ĀģťĖď„ĀßÁ∑†ÁĶź„Āē„āĆ„ā茕ĎÁīĄ„ĀęŚüļ„Ā•„ĀĄ„Ā¶šĽėšłé„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģŚ•ĎÁīĄ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúį„ĀģÁõģÁöĄ„ÄĀśúüťĖď„ÄĀťĚĘÁ©ć„ÄĀŚ†īśČÄ„ÄĀŚą©ÁĒ®śĚ°šĽ∂„ÄĀŚĹďšļčŤÄÖ„Āģś®©Śą©Áĺ©Śčô„ÄĀŤ≤¨šĽĽ„Ā™„Ā©„ĀĆŤ©≥Áīį„ĀꍶŹŚģö„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
- Á߼ŤĽĘŚŹĮŤÉĹśÄß„Ā®śčÖšŅĚŤ®≠Śģö: ťá捶Ā„Ā™ÁāĻ„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀŚúüŚúį„ĀģŚć†śúČś®©„Āä„āą„Ā≥Śą©ÁĒ®ś®©„ĀĮ„ÄĀś≥ēŚĺč„ĀģŤ¶ŹŚģö„ĀęŚĺď„Ā£„Ā¶„ÄĀŤ≠≤śł°„ÄĀśäĶŚĹďś®©Ť®≠Śģö„ÄĀÁõłÁ∂ö„ÄĀ„Āĺ„Āü„ĀĮśčÖšŅĚ„Ā®„Āó„Ā¶Śą©ÁĒ®„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„Äā„Āď„ĀģŤ¶ŹŚģö„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀĆŚćė„Ā™„āčšĹŅÁĒ®ś®©„ĀęÁēô„Āĺ„āČ„Āö„ÄĀšłÄŚģö„ĀģśĶĀŚčēśÄß„Ā®Ť≥áÁĒ£šĺ°ŚÄ§„āíśĆĀ„Ā§„Āď„Ā®„ā휥ŹŚĎ≥„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Éē„ā°„ā§„Éä„É≥„āĻ„Āę„Āä„ĀĎ„āčśčÖšŅĚ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģŚą©ÁĒ®„āĄ„ÄĀšļčś•≠Ś£≤Śćī„ÉĽśČŅÁ∂ôśôā„Āģś®©Śą©Á߼ŤĽĘ„ĀĆś≥ēÁöĄ„ĀꌏĮŤÉĹ„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀŚćė„Ā™„āčŤ≥ÉŚÄüś®©„ĀęÁēô„Āĺ„āČ„Āö„ÄĀśó•śú¨„Āģ„ÄĆŚúįšłäś®©„Äć„āĄ„ÄĆśįłŚįŹšĹúś®©„Äć„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüÁČ©ś®©„ĀęŤŅĎ„ĀĄ„ÄĀ„āą„ā䌾∑Śäõ„Ā™śÄߍ≥™„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„ÉĘ„É≥„āī„ÉęśäēŤ≥áś≥ē„ĀĮ„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áŚģ∂„ĀĆ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹŚÜÖ„Āßšļčś•≠śīĽŚčē„ā퍰ƄĀÜ„Āü„āĀ„Āģś≥ēÁöĄ„Ā™śě†ÁĶĄ„ĀŅ„ā휏źšĺõ„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ĀĚ„Āģšł≠„ĀߌúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀģŚŹĖŚĺó„ĀęťĖĘ„Āô„ā荶ŹŚģö„āāÁĒ®śĄŹ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāśäēŤ≥áś≥ēÁ¨¨3śĚ°Á¨¨1ť†ÖÁ¨¨5ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥á„Āę„āą„Ā£„Ā¶Ť®≠Áęč„Āē„āĆ„Āüś≥ēšļļ„āí„ÄĆśäēŤ≥ášľĀś•≠„Äć„Ā®ŚģöÁĺ©„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„Āď„āĆ„āČ„ĀģśäēŤ≥ášľĀś•≠„ĀĆŚúüŚúįś≥ē„ĀęŚĺď„Ā£„Ā¶ŚúüŚúį„ĀģŚć†śúČś®©„Āä„āą„Ā≥Śą©ÁĒ®ś®©„ā팏ĖŚĺó„Āß„Āć„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„ÄĀśäēŤ≥áś≥ēÁ¨¨7śĚ°Á¨¨1ť†Ö„Āߍ¶ŹŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥áŚģ∂„ĀĮ„ÄĀś≥ēŚĺč„ĀßÁ¶Āś≠Ę„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄťôź„āä„ÄĀ„ĀĄ„Āč„Ā™„ā茹ܝáé„Āę„āāśäēŤ≥á„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„ÄĀŚõĹŚÜÖśäēŤ≥áŚģ∂„Ā®ŚéüŚČá„Ā®„Āó„Ā¶ŚźĆÁ≠Č„Āģś®©Śą©Áĺ©Śčô„āíśĆĀ„Ā§„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ„ĀģŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀęťĖĘťÄ£„Āô„ā茕ĎÁīĄŚģüŚčô„Ā®ÁēôśĄŹÁāĻ

„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀģŚŹĖŚĺó„ĀĮ„ÄĀŚõĹŚģ∂Ť°ĆśĒŅś©üťĖĘ„Ā®„ĀģťĖď„ĀßÁ∑†ÁĶź„Āē„āĆ„ā茕ĎÁīĄ„ĀĆ„ĀĚ„ĀģŚüļÁõ§„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģŚ•ĎÁīĄŚģüŚčô„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀśó•śú¨„ĀģŚ•ĎÁīĄśÖ£Ť°Ć„Ā®„ĀĮÁēį„Ā™„āčÁēôśĄŹÁāĻ„ĀĆ„ĀĄ„ĀŹ„Ā§„ĀčŚ≠ėŚú®„Āó„Āĺ„Āô„Äā
ŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀģšĽėšłé„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúįś≥ēÁ¨¨3śĚ°Á¨¨7ť†ÖÁ¨¨1ŚŹ∑„ĀęŚüļ„Ā•„Āć„ÄĀŚõĹŚģ∂Ť°ĆśĒŅś©üťĖĘ„Ā®ŚúüŚúį„ĀģŚć†śúČŤÄÖ„Āĺ„Āü„ĀĮŚą©ÁĒ®ŤÄÖ„Ā®„ĀģťĖď„Āߌ•ĎÁīĄ„ĀĆÁ∑†ÁĶź„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āę„āą„Ā£„Ā¶Ť°Ć„āŹ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģŚ•ĎÁīĄ„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúį„ĀģŚą©ÁĒ®ÁõģÁöĄ„ÄĀśúüťĖď„ÄĀťĚĘÁ©ć„ÄĀŚ†īśČÄ„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶Śą©ÁĒ®„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™śĚ°šĽ∂„ÄĀŚĹďšļčŤÄÖ„Āģś®©Śą©„ÄĀÁĺ©Śčô„ÄĀŤ≤¨šĽĽ„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āüťá捶Ā„Ā™šļ蝆քā퍩≥Áīį„ĀꍶŹŚģö„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
Ś•ĎÁīĄÁ∑†ÁĶź„Āęťöõ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšĽ•šłč„ĀģÁāĻ„ĀęÁČĻ„ĀęÁēôśĄŹ„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
Śą©ÁĒ®ÁõģÁöĄ„ĀģśėéÁĘļŚĆĖ„Ā®ťĀĶŚģą
ŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀĮÁČĻŚģöÁõģÁöĄ„Āę„Āģ„ĀŅšĽėšłé„Āē„āĆ„āč„Āü„āĀ„ÄĀŚ•ĎÁīĄśõł„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶Śą©ÁĒ®ÁõģÁöĄ„āíś•Ķ„āĀ„Ā¶śėéÁĘļ„ĀęŚģö„āĀ„āč„Āď„Ā®„ĀĆťá捶Ā„Āß„Āô„ÄāŚą©ÁĒ®ÁõģÁöĄ„ĀĆŚé≥ś†ľ„ĀęŚģö„āĀ„āČ„āĆ„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀšļčś•≠Ť®ąÁĒĽ„ĀģśüĒŤĽüśÄß„ĀĆŚą∂ÁīĄ„Āē„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Āď„Ā®„ā휥ŹŚĎ≥„Āó„Āĺ„Āô„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀŚĹ̄ĀģŚ∑•Ś†īŚĽļŤ®≠„Āč„āČ„ÄĀŚįܜ̕ÁöĄ„ĀęŚÄČŚļę„āĄŚēÜś•≠śĖĹŤ®≠„Āł„ĀģŤĽĘÁĒ®„āíŤÄÉ„Āą„ā茆īŚźą„ÄĀŚ•ĎÁīĄ„ĀģŚÜćšļ§śłČ„āĄŤŅŌ䆄ĀģŤ®ĪŤ™ćŚŹĮ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āč„É™„āĻ„āĮ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚįܜ̕ÁöĄ„Āꌹ©ÁĒ®ÁõģÁöĄ„ā팧Ȝõī„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„ā茆īŚźą„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚ§ČśõīśČčÁ∂ö„Āć„āĄśĚ°šĽ∂„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„āāŚ•ĎÁīĄ„ĀęÁõõ„āäŤĺľ„āÄ„Āč„ÄĀšļčŚČć„ĀęÁĘļŤ™ć„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁõģÁöĄŚ§ĖŚą©ÁĒ®„ĀĮ„ÄĀś®©Śą©„ĀģŤß£ťô§šļčÁĒĪ„Ā®„Ā™„āäŚĺó„Āĺ„Āô„Äā
śúüťĖ≠Śģö„Ā®ŚĽ∂ťē∑śČčÁ∂ö
Ś•ĎÁīĄśúüťĖď„ĀĮ„ÄĀ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀģśÄߍ≥™„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶śÖéťáć„Āꍮ≠Śģö„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥á„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„ĀģŚ†īŚźą„ÄĀśúÄťē∑60ŚĻī„ĀģŚąĚśúüśúüťĖď„Ā®śúÄťē∑40ŚĻī„ĀģŚĽ∂ťē∑ÔľąŚźąŤ®ą100ŚĻīԾȄĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĮŤá™ŚčēÁöĄ„Āꚼėšłé„Āē„āĆ„āč„āā„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀÁĒ≥Ťęč„Ā®śČŅŤ™ć„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„Äā
śúüťĖ≠Śģö„ĀĮ„ÄĀšļčś•≠„Āģ„É©„ā§„Éē„āĶ„ā§„āĮ„Éę„Ā®ŚĮÜśé•„ĀęťÄ£śźļ„Āē„Āõ„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀÁČĻ„Āęťē∑śúü„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ100ŚĻī„Ā®„ĀĄ„ĀÜśúÄŚ§ßśúüťĖď„āíśúÄŚ§ßťôź„ĀęśīĽÁĒ®„Āô„āč„Āü„āĀ„Āģśą¶Áē•ÁöĄ„Ā™Ś•ĎÁīĄšļ§śłČ„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŚĽ∂ťē∑śČčÁ∂ö„Āć„ĀģŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™Ť¶ĀšĽ∂„āĄ„āŅ„ā§„Éü„É≥„āį„ā팕ĎÁīĄśõł„Āęśė鍮ė„Āó„ÄĀŤ®ąÁĒĽÁöĄ„ĀęŚĮĺŚŅú„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāśúüťĖďśļÄšļÜśôā„ĀģŚúüŚúį„ĀģŤŅĒťāĄÁĺ©Śčô„āĄ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģśôāÁāĻ„Āß„ĀģśĖĹŤ®≠„ÉĽŤ®≠Śāô„ĀģŚŹĖ„āäśČĪ„ĀĄ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„āā„ÄĀšļčŚČć„ĀęśėéÁĘļ„Ā™ŚŹĖ„āäśĪļ„āĀ„āí„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĆ„ÄĀŚįܜ̕ÁöĄ„Ā™ÁīõšļČ„āíťĀŅ„ĀĎ„āčšłä„Āßś•Ķ„āĀ„Ā¶ťá捶Ā„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
ś®©Śą©„ĀģÁôĽťĆ≤
ŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúįŚŹįŚł≥„Āł„ĀģÁôĽťĆ≤„Āę„āą„Ā£„Ā¶„ĀĚ„ĀģŚäĻŚäõ„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„ÄĀÁ¨¨šłČŤÄÖ„ĀęŚĮĺśäó„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚ•ĎÁīĄÁ∑†ÁĶźŚĺĆ„ÄĀťÄü„āĄ„Āč„ĀęÁôĽťĆ≤śČčÁ∂ö„Āć„ā퍰ƄĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆ„ÄĀś®©Śą©šŅĚŚÖ®„Āģ„Āü„āĀ„Āꚳ挏Įś¨†„Āß„Āô„Äā
ś®©Śą©„ĀģÁ߼ŤĽĘ„ÉĽśčÖšŅĚŤ®≠Śģö„ĀęťĖĘ„Āô„āčśĚ°ť†Ö
ŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀĮŤ≠≤śł°„āĄśčÖšŅĚŤ®≠Śģö„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āā„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„Āď„āĆ„āČ„ĀģŤ°ĆÁāļ„ā퍰ƄĀÜťöõ„ĀģśĚ°šĽ∂„āĄśČčÁ∂ö„Āć„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„āāŚ•ĎÁīĄśõł„Āęśė鍮ė„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĆśúõ„Āĺ„Āó„ĀĄ„Āß„Āô„Äā„Āď„ĀģŤ¶ŹŚģö„ĀĮ„ÄĀ„Éó„É≠„āł„āß„āĮ„Éą„Éē„ā°„ā§„Éä„É≥„āĻ„Āę„Āä„ĀĎ„āčśčÖšŅĚ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģŚą©ÁĒ®„āĄ„ÄĀšļčś•≠Ś£≤Śćī„ÉĽśČŅÁ∂ôśôā„Āģś®©Śą©Á߼ŤĽĘ„ĀĆś≥ēÁöĄ„ĀꌏĮŤÉĹ„Ā®„Ā™„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜś©üšľö„āí„āā„Āü„āČ„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Āü„Ā†„Āó„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„Éę„ĀģťáĎŤěćś©üťĖĘ„ĀĆ„Āď„āĆ„āČ„Āģś®©Śą©„āí„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Āꍩēšĺ°„Āó„ÄĀśčÖšŅĚ„Ā®„Āó„Ā¶ŚŹó„ĀĎŚÖ•„āĆ„āč„Āč„ÄĀ„Āĺ„Āü„ÄĀŤ≠≤śł°„Āęťöõ„Āó„Ā¶ŚõĹŚģ∂„ĀģśČŅŤ™ć„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āč„Ā茟¶„Āč„Ā™„Ā©„ÄĀŚģüŚčôšłä„ĀģŤ©≥Áīį„Ā™ÁĘļŤ™ć„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÄĀśäĶŚĹďś®©„ā퍮≠Śģö„Āó„Ā¶Ť≥áťáĎŤ™ŅťĀĒ„ā퍰ƄĀÜŚ†īŚźą„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„Āģś®©Śą©„ĀĆ„ÉĘ„É≥„āī„Éęś≥ē„Āģšłč„ĀßťĀ©Śąá„ĀęšŅĚŤ≠∑„Āē„āĆ„āč„Āč„ÄĀťáĎŤěćś©üťĖĘ„Ā®„ĀģťĖď„ĀߌćĀŚąÜ„Ā™ÁĘļŤ™ć„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„Äā
Ś•ĎÁīĄŤß£ťô§šļčÁĒĪ„Ā®Ť£úŚĄü
ŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„ĀĮ„ÄĀŚą©ÁĒ®ÁõģÁöĄ„ĀģšłćťĀĒśąź„ÄĀ2ŚĻīšĽ•šłä„ĀģšłćšĹŅÁĒ®„ÄĀśúüťĖďśļÄšļÜ„Ā™„Ā©„ÄĀÁČĻŚģö„ĀģšļčÁĒĪ„Āę„āą„Ā£„Ā¶Ťß£ťô§„Āē„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„āČ„ĀģŤß£ťô§šļčÁĒĪ„ÄĀÁČĻ„ĀęŚõĹŚģ∂„Āę„āą„āčŚÖ¨ŚÖĪ„ĀģŚŅÖŤ¶ĀśÄß„ĀęŚüļ„Ā•„ĀŹśó©śúüŤß£ťô§„ĀģŚ†īŚźą„Āę„ĀĮ„ÄĀŚúüŚúįśĒĻŤČĮÁČ©„ĀęŚĮĺ„Āô„āčŤ£úŚĄü„ĀĆŤ¶ŹŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀŤ£úŚĄü„ĀģÁĮĄŚõ≤„āĄŤ©ēšĺ°śĖĻś≥ē„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŚ•ĎÁīĄśõł„ĀßśėéÁĘļ„Āę„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĆťá捶Ā„Āß„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀśäēŤ≥áś≥ē„ĀĮ„ÄĀŚ§ĖŚõĹśäēŤ≥á„ĀęŚĮĺ„Āô„āčťĚ쌏éÁĒ®„Ā®ś≥ēÁöĄÁíįŚĘÉ„ĀģŚģČŚģöśÄß„āíšŅĚŤ®ľ„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀÁīõšļČŤß£śĪļśČčśģĶ„Ā®„Āó„Ā¶šļ§śłČ„ÄĀŤ™ŅŚĀú„ÄĀšĽ≤Ť£Ā„ĀĆŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„āČ„ĀģšŅĚŤ≠∑śé™ÁĹģ„āíÁźÜŤß£„Āó„ÄĀśīĽÁĒ®„Āô„āč„Āď„Ā®„āāťá捶Ā„Āß„Āô„Äā
„Āĺ„Ā®„āĀ
śó•śú¨šľĀś•≠„ĀĮ„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„Éę„Āß„Āģšļčś•≠Ť®ąÁĒĽ„āíÁ≠ĖŚģö„Āô„ā茹̜úüśģĶťöé„Āč„āČ„ÄĀŚúüŚúį„ĀģŚą©ÁĒ®ÁõģÁöĄ„Ā®śúüťĖď„āíŚÖ∑šĹďÁöĄ„ĀęśÉ≥Śģö„Āó„ÄĀŚįܜ̕ÁöĄ„Ā™šļčś•≠ŚĪēťĖč„ĀģŚŹĮŤÉĹśÄß„āāŤ¶Ėťáé„ĀęŚÖ•„āĆ„Āüšłä„Āß„ÄĀŚ•ĎÁīĄśõł„Āģ„ÉČ„É©„Éē„Éą„ĀęŤá®„āÄ„ĀĻ„Āć„Āß„Āô„ÄāŚćė„ĀęÁŹĺśôāÁāĻ„ĀģŚŅÖŤ¶ĀśÄß„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀśč°ŚľĶśÄß„āĄŤĽĘÁĒ®ŚŹĮŤÉĹśÄß„āāŤÄÉśÖģ„ĀęŚÖ•„āĆ„Āü„ÄĀśüĒŤĽüśÄß„āíśĆĀ„Āü„Āõ„āč„Āü„āĀ„ĀģśĚ°ť†ÖÔľąšĺč„Āą„Āį„ÄĀÁõģÁöĄŚ§Čśõī„ĀęťĖĘ„Āô„āčŚćĒŤ≠įśĚ°ť†Ö„āĄŚĄ™ŚÖąšļ§śłČś®©„Ā™„Ā©ÔľČ„ā휧úŤ®é„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„āā„Āā„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŚúüŚúįŚą©ÁĒ®ś®©„āíŚćė„Ā™„āč„ā≥„āĻ„Éą„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„Éź„É©„É≥„āĻ„ā∑„Éľ„Éąšłä„ĀģŤ≥áÁĒ£„Ā®„Āó„Ā¶Ť™ćŤ≠ė„Āó„ÄĀŤ≥áťáĎŤ™ŅťĀĒśą¶Áē•„āĄŚáļŚŹ£śą¶Áē•ÔľąM&A„ÄĀšļčś•≠Ś£≤Śćī„Ā™„Ā©ÔľČ„ĀęÁĶĄ„ĀŅŤĺľ„āÄ„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚģüÁŹĺŚŹĮŤÉĹśÄß„Ā®śĚ°šĽ∂„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ÉĘ„É≥„āī„Éę„ĀģšłćŚčēÁĒ£ŚłāŚ†ī„āĄťáĎŤěćśÖ£Ť°Ć„Āꍩ≥„Āó„ĀĄŚįāťĖÄŚģ∂„Ā®„ĀģťÄ£śźļ„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Ā†„Ā®Ť®Ä„Āą„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā
ťĖĘťÄ£ŚŹĖśČĪŚąÜťáéÔľöŚõĹťöõś≥ēŚčô„ÉĽ„ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹ
„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ: IT„ÉĽ„Éô„É≥„ÉĀ„É£„Éľ„ĀģšľĀś•≠ś≥ēŚčô
„āŅ„āį: „ÉĘ„É≥„āī„ÉęŚõĹśĶ∑Ś§Ėšļčś•≠