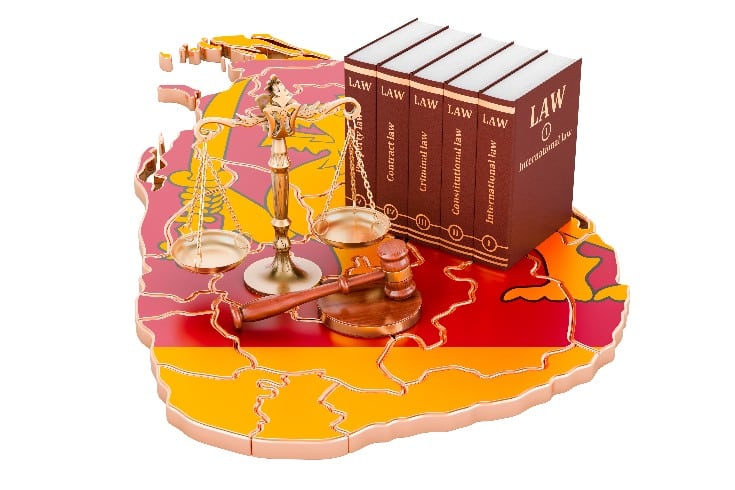еҸ°ж№ҫгҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•пјҲPDPAпјүи§ЈиӘ¬

еҸ°ж№ҫгҒ§гҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№еұ•й–ӢгӮ’жӨңиЁҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж—Ҙжң¬гҒ®зөҢе–¶иҖ…гӮ„жі•еӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒ®зҡҶж§ҳгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒзҸҫең°гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•пјҲPersonal Data Protection Act, PDPAпјүгҒёгҒ®зҗҶи§ЈгҒҜдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮеҸ°ж№ҫPDPAгҒҜгҖҒEUгҒ®дёҖиҲ¬гғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·иҰҸеүҮпјҲGDPRпјүгҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҹеҺіж јгҒӘеҺҹеүҮгӮ’жҺІгҒ’гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзү№гҒ«2023е№ҙгҒ®еӨ§е№…гҒӘж”№жӯЈгӮ’зөҢгҒҰгҖҒгҒқгҒ®иҰҸеҲ¶гҒҜгҒ•гӮүгҒ«еҺіж јеҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҸ°ж№ҫгҒ®PDPAгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®жұәе®ҡзҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒдҝқиӯ·еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҖҢеҖӢдәәиіҮж–ҷгҖҚгҒ®е®ҡзҫ©гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гҖҢеҖӢдәәжғ…е ұгҖҚгӮ„гҖҢеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҖҚгӮҲгӮҠгӮӮеҢ…жӢ¬зҡ„гҒ§гҖҒгӮҲгӮҠеәғзҜ„гҒӘжғ…е ұгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§еҗ„зңҒеәҒгҒ«еҲҶж•ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹзӣЈзқЈжЁ©йҷҗгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·е§”е“ЎдјҡпјҲPPCпјүгҒЁеҗҢж§ҳгҒ®зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢеҖӢдәәиіҮж–ҷдҝқиӯ·е§”е“ЎдјҡпјҲPDPCпјүгҒ«дёҖе…ғеҢ–гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹзӣЈзқЈж©ҹй–ўгҒ®иЁӯз«ӢгҒҜгҖҒжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәгӮ’еҘ‘ж©ҹгҒЁгҒҷгӮӢгҖҒеҸ°ж№ҫж”ҝеәңгҒ®гғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·еј·еҢ–гҒёгҒ®еј·гҒ„ж„Ҹеҝ—гҒ®иЎЁгӮҢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҒ®и¶Ҡеўғ移転гҒҜгҖҢеҺҹеүҮиЁұеҸҜгҖҚгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒдё»з®Ўе®ҳеәҒгҒ®иЈҒйҮҸгҒ«гӮҲгӮҠзӘҒ然еҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгӮ’еҶ…еҢ…гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҳҺзўәгҒӘгғ«гғјгғ«гҒ«ж…ЈгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜдәҲжңҹгҒӣгҒ¬гғӘгӮ№гӮҜгҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮеҠ гҒҲгҒҰгҖҒйҒ•еҸҚгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзҪ°еүҮгҒҜгҖҒй«ҳйЎҚгҒӘиЎҢж”ҝзҪ°йҮ‘гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒжҮІеҪ№еҲ‘гӮ’еҗ«гӮҖеҲ‘дәӢзҪ°гӮ„гҖҒйӣҶеӣЈиЁҙиЁҹгҒ«гӮҲгӮӢй«ҳйЎҚгҒӘжҗҚе®іиі е„ҹи«ӢжұӮгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒ«жҜ”гҒ№гҒҰгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«еҺіж јгҒӘдҪ“зі»гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®йҒ•гҒ„гҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжі•д»ӨзҹҘиӯҳгӮ’и¶…гҒҲгҒҹгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒЁгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№дёҠгҒ®иӘІйЎҢгӮ’и©ізҙ°гҒ«жҺҳгӮҠдёӢгҒ’гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮВ
гҒӘгҒҠгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
В
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
еҸ°ж№ҫеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•пјҲPDPAпјүгҒ®еҹәжң¬еҺҹеүҮгҒЁгҖҢеҖӢдәәиіҮж–ҷгҖҚгҒ®е®ҡзҫ©
еҸ°ж№ҫPDPAгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢеҖӢдәәиіҮж–ҷгҖҚгҒ®жҰӮеҝө
еҸ°ж№ҫгҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒҜгҖҒгҒқгҒ®ж №е№№гӮ’гҒӘгҒҷжҰӮеҝөгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢеҖӢдәәиіҮж–ҷгҖҚпјҲPersonal DataпјүгӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒиҮӘ然дәәгӮ’зӣҙжҺҘзҡ„гҒҫгҒҹгҒҜй–“жҺҘзҡ„гҒ«иӯҳеҲҘгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢжғ…е ұе…ЁиҲ¬гӮ’жҢҮгҒ—гҖҒж°ҸеҗҚгҖҒз”ҹе№ҙжңҲж—ҘгҖҒиә«еҲҶиЁјз•ӘеҸ·гҖҒгғ‘гӮ№гғқгғјгғҲз•ӘеҸ·гҖҒз—…жӯҙгҖҒеҢ»зҷӮиЁҳйҢІгҖҒзҠҜзҪӘиЁҳйҢІгҒӘгҒ©гҒ®жғ…е ұгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬жі•гҒҜгҖҒгҖҢеҖӢдәәжғ…е ұгҖҚпјҲж°ҸеҗҚгҒӘгҒ©зү№е®ҡгҒ®еҖӢдәәгӮ’иӯҳеҲҘгҒ§гҒҚгӮӢжғ…е ұпјүгҒЁгҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒЎйӣ»еӯҗеҢ–гҒ•гӮҢжӨңзҙўеҸҜиғҪгҒӘгҖҢеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҖҚгӮ’еҢәеҲҘгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«з•°гҒӘгӮӢзҫ©еӢҷгӮ’иӘІгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒеҸ°ж№ҫPDPAгҒ§гҒҜгҖҒдёӯеӣҪиӘһгҒ®еҺҹж–ҮгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеҖӢдәәиіҮж–ҷгҖҚгҒ®гҒҝгӮ’жҰӮеҝөгҒЁгҒ—гҒҰжүұгҒ„гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҢеҖӢдәәжғ…е ұгҖҚгҒЁгҖҢеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҖҚгӮ’дҪҝгҒ„еҲҶгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҖӢдәәиіҮж–ҷгҒ®еҸҺйӣҶгҖҒеҮҰзҗҶгҖҒеҲ©з”ЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҹәжң¬еҺҹеүҮ
еҸ°ж№ҫPDPA第5жқЎгҒҜгҖҒеҖӢдәәиіҮж–ҷгҒ®еҸҺйӣҶгҖҒеҮҰзҗҶгҖҒеҲ©з”ЁгҒҜгҖҒиӘ е®ҹгҒӢгҒӨдҝЎзҫ©гҒ«еүҮгҒЈгҒҹж–№жі•гҒ§гҖҒгғҮгғјгӮҝдё»дҪ“гҒ®жЁ©еҲ©еҲ©зӣҠгӮ’е°ҠйҮҚгҒ—гҖҒзү№е®ҡгҒ®зӣ®зҡ„гҒ®еҝ…иҰҒзҜ„еӣІгӮ’и¶…гҒҲгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁе®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҸҺйӣҶжҷӮгҒ«гҒҜгҖҒгғҮгғјгӮҝдё»дҪ“гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҸҺйӣҶзӣ®зҡ„гҖҒеҖӢдәәиіҮж–ҷгҒ®зЁ®йЎһгҖҒеҲ©з”Ёжңҹй–“гҖҒең°еҹҹгҖҒгғҮгғјгӮҝдё»дҪ“гҒ®жЁ©еҲ©пјҲй–ІиҰ§гҖҒиӨҮиЈҪгҖҒиЁӮжӯЈгҖҒеҲ©з”ЁеҒңжӯўгҖҒеүҠйҷӨгҒ®жЁ©еҲ©гҒӘгҒ©пјүгӮ’жҳҺзўәгҒ«йҖҡзҹҘгҒҷгӮӢзҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йҖҡзҹҘзҫ©еӢҷгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒ®гҖҢеҲ©з”Ёзӣ®зҡ„гҒ®зү№е®ҡгғ»е…¬иЎЁгҖҚгҒЁйЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҸ°ж№ҫPDPAгҒ§гҒҜгҖҢеҸҺйӣҶжҷӮгҖҚгҒ®гҖҢжҳҺзӨәзҡ„гҒӘйҖҡзҹҘгҖҚгҒҢеҺҹеүҮгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮҲгӮҠз©ҚжҘөзҡ„гҒӘжғ…е ұжҸҗдҫӣгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгғҮгғјгӮҝдё»дҪ“гҒҢеҖӢдәәиіҮж–ҷгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ®жЁ©еҲ©гғ»еҲ©зӣҠгҒёгҒ®еҪұйҹҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮйҖҡзҹҘгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гғ—гғ©гӮӨгғҗгӮ·гғјгғқгғӘгӮ·гғјгӮ’еҚҳзҙ”гҒ«зҝ»иЁігҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®жі•иҰҒ件гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгғӯгғјгӮ«гғ©гӮӨгӮәгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеҸ°ж№ҫгҒ§гӮҰгӮ§гғ–гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„гӮўгғ—гғӘгӮ’еұ•й–ӢгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјзҷ»йҢІжҷӮгҒӘгҒ©гҒ«гҖҒPDPA第8жқЎгҒ«жә–жӢ гҒ—гҒҹйҖҡзҹҘз”»йқўгӮ„ж–Үз« гӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮВ В
ж©ҹеҫ®гҒӘеҖӢдәәиіҮж–ҷгҒ®еҸ–гӮҠжүұгҒ„
еҸ°ж№ҫPDPA第6жқЎгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮиЁҳйҢІгҖҒгғҳгғ«гӮ№гӮұгӮўгғҮгғјгӮҝгҖҒйҒәдјқеӯҗгғҮгғјгӮҝгҖҒжҖ§з”ҹжҙ»гҖҒеҒҘеә·иЁәж–ӯгҖҒзҠҜзҪӘиЁҳйҢІгҒӘгҒ©гҒ®ж©ҹеҫ®гҒӘеҖӢдәәиіҮж–ҷгҒ®еҸҺйӣҶгҖҒеҮҰзҗҶгҖҒеҲ©з”ЁгӮ’еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰзҰҒжӯўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒEUгҒ®GDPRгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢзү№еҲҘгӮ«гғҶгӮҙгғӘгғјгҒ®еҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҖҚгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒзү№гҒ«еҺіж јгҒӘдҝқиӯ·гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢжғ…е ұгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢеӨ–зҡ„гҒ«иЁұе®№гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгҖҢжі•еҫӢгҒ§жҳҺзӨәзҡ„гҒ«е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҚгӮ„гҖҢеҪ“дәӢиҖ…гҒ®жӣёйқўгҒ«гӮҲгӮӢеҗҢж„ҸгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒзү№е®ҡгҒ®жқЎд»¶гҒҢжәҖгҒҹгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒ«йҷҗгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒ§гӮӮгҖҒдәәзЁ®гҖҒдҝЎжқЎгҖҒз—…жӯҙгҒӘгҒ©гҒ®гҖҢиҰҒй…Қж…®еҖӢдәәжғ…е ұгҖҚгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–еҫ—гҒҢеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёЎжі•гҒЁгӮӮеҗҢж§ҳгҒ®дҝқиӯ·гғ¬гғҷгғ«гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮВ В
2023е№ҙгҒ®еҸ°ж№ҫPDPAж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮӢзӣЈзқЈдҪ“еҲ¶гҒ®еј·еҢ–

зӣЈзқЈжЁ©йҷҗгҒ®PDPCгҒёгҒ®дёҖе…ғеҢ–
2023е№ҙ5жңҲгҒ®PDPAж”№жӯЈгҒҜгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·гӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гӮ’ж №жң¬зҡ„гҒ«еӨүгҒҲгӮӢгҖҒжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘеӨүеҢ–гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§еҗ„дәӢжҘӯеҲҶйҮҺгҒ®дё»з®Ўе®ҳеәҒпјҲдҫӢпјҡйҮ‘иһҚзӣЈзқЈз®ЎзҗҶ委員дјҡгҖҒдәӨйҖҡйғЁгҒӘгҒ©пјүгҒҢжӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹзӣЈзқЈжЁ©йҷҗгҒҢгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹзӣЈзқЈж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеҖӢдәәиіҮж–ҷдҝқиӯ·е§”е“ЎдјҡпјҲPDPCпјүгҖҚгҒ«дёҖе…ғеҢ–гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еӨүжӣҙгҒҜгҖҒеӣҪ家еҒҘеә·дҝқйҷәз ”з©¶гғҮгғјгӮҝгғҷгғјгӮ№дәӢ件гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҸ°ж№ҫжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨжұәпјҲ111е№ҙжҶІеҲӨеӯ—第13иҷҹеҲӨжұәпјүгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҲӨжұәгҒҜгҖҒеҖӢдәәжғ…е ұгҒЁгғ—гғ©гӮӨгғҗгӮ·гғјгҒ®жҶІжі•дёҠгҒ®жЁ©еҲ©гӮ’дҝқиӯ·гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹгғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·гғЎгӮ«гғӢгӮәгғ гӮ’зўәз«ӢгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®зңҒеәҒгҒ«еұһгҒ•гҒӘгҒ„зӢ¬з«ӢжҖ§гҒЁе°Ӯй–ҖжҖ§гӮ’жҢҒгҒӨж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·е§”е“ЎдјҡпјҲPPCпјүгҒ®иЁӯз«ӢзөҢз·ҜгҒЁи»ҢгӮ’дёҖгҒ«гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҸ°ж№ҫгҒҢж—Ҙжң¬гҒ®гғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·гӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гҒ®гғўгғҮгғ«гӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒҶгҒӢгҒҢгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮзӣЈзқЈж©ҹй–ўгҒҢдёҖгҒӨгҒ«гҒҫгҒЁгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәӢжҘӯиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣе…ҲгҒҢжҳҺзўәгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢдёҖж–№гҖҒе°Ӯй–Җж©ҹй–ўгҒ«гӮҲгӮӢеҺіж јгҒӘзӣЈзқЈгҒЁеҲ¶иЈҒгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮPDPCгҒҜгҖҒгғҮгғјгӮҝдҫөе®ідәӢ件гҒ®е ұе‘ҠгӮ’дёҖе…ғзҡ„гҒ«еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҖҒиҝ…йҖҹгҒӘиӘҝжҹ»гҒЁеҜҫеҝңгӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
PDPCгҒ«гӮҲгӮӢд»ҠеҫҢгҒ®зӣЈзқЈеј·еҢ–гҒЁз§»иЎҢжңҹй–“
PDPCгҒ®иЁӯз«ӢгҒҜгҖҒгғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·иІ¬д»»иҖ…пјҲDPOпјүгҒ®д»»е‘Ҫзҫ©еӢҷеҢ–пјҲе…¬еӢҷйғЁй–ҖпјүгӮ„гҖҒгғҮгғјгӮҝдҫөе®іжҷӮгҒ®е ұе‘Ҡзҫ©еӢҷеҢ–гҖҒй«ҳгғӘгӮ№гӮҜз”ЈжҘӯгҒёгҒ®е„Әе…Ҳзҡ„гҒӘжӨңжҹ»гҒӘгҒ©гҖҒж–°гҒҹгҒӘгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№зҫ©еӢҷгҒ®е°Һе…ҘгӮ’дјҙгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж°‘й–“йғЁй–ҖгҒёгҒ®зӣЈзқЈжЁ©йҷҗгҒ®з§»з®ЎгҒ«гҒҜгҖҒ6е№ҙй–“гҒ®з§»иЎҢжңҹй–“гҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢдәҲе®ҡгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®з§»иЎҢжңҹй–“гҒҜгҖҒдјҒжҘӯгҒ«жә–еӮҷжңҹй–“гӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁи§ЈйҮҲгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ6е№ҙгҒЁй•·жңҹгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№еҜҫеҝңгӮ’е…Ҳ延гҒ°гҒ—гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜиіўжҳҺгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮPDPCгҒ®зұҢеӮҷиҷ•пјҲPreparatory OfficeпјүгҒҜгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«жі•иҰҸгҒ®ж”№жӯЈгӮ„и§ЈйҮҲгҖҒзӣЈзқЈдҪ“еҲ¶гҒ®дјҒз”»гҖҒеӣҪйҡӣеҚ”еҠӣгҒӘгҒ©гҖҒеәғзҜ„гҒӘжҘӯеӢҷгӮ’жҺҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒPDPCгҒҢжң¬ж јзЁјеғҚгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ«гҖҒзӣЈзқЈдҪ“еҲ¶гӮ„гӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғігҒҢзқҖгҖ…гҒЁж•ҙеӮҷгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҸ°ж№ҫж”ҝеәңгҒҜгҖҒGDPRгҒЁгҒ®гҖҢзӣёдә’зҡ„йҒ©жӯЈжҖ§пјҲadequacyпјүгҖҚгҒ®зҚІеҫ—гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹзӣЈзқЈж©ҹй–ўгҒ®иЁӯз«ӢгӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еӢ•еҗ‘гҒҜгҖҒеҸ°ж№ҫгҒҢеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘгғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·еҹәжә–гҒ«жә–жӢ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶеј·гҒ„ж„Ҹеҝ—гҒ®иЎЁгӮҢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒд»ҠеҫҢгҖҒеҸ°ж№ҫжі•гҒҢгӮҲгӮҠGDPRгҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҹеҺіж јгҒӘж–№еҗ‘гҒёгҒЁйҖІеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒЁиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸ°ж№ҫгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢи¶ҠеўғгғҮгғјгӮҝ移転гҒ®еҲ¶йҷҗ
еҸ°ж№ҫгҒ§гҒҜгҖҒеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҒ®еӣҪйҡӣ移転гҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰзҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдёҖиҰӢгҒҷгӮӢгҒЁеҲ©дҫҝжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒPDPA第21жқЎгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®4гҒӨгҒ®зҠ¶жіҒдёӢгҒ§гҒҜгҖҒдёӯеӨ®зӣ®зҡ„дәӢжҘӯдё»з®Ўе®ҳеәҒгҒҢгғҮгғјгӮҝ移転гӮ’еҲ¶йҷҗгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁиҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- йҮҚиҰҒгҒӘеӣҪ家еҲ©зӣҠгҒ«й–ўгӮҸгӮӢе ҙеҗҲ
- еӣҪйҡӣжқЎзҙ„гӮ„еҚ”е®ҡгҒ«зү№еҲҘгҒӘиҰҸе®ҡгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲ
- еҸ—й ҳеӣҪгҒ«йҒ©еҲҮгҒӘдҝқиӯ·иҰҸеҲ¶гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒгғҮгғјгӮҝдё»дҪ“гҒ®жЁ©еҲ©гғ»еҲ©зӣҠгӮ’дҫөе®ігҒҷгӮӢжҒҗгӮҢгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲ
- жі•еҫӢгӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒиҝӮеӣһзҡ„гҒӘж–№жі•гҒ§з¬¬дёүеӣҪгҒёгғҮгғјгӮҝгӮ’移転гҒҷгӮӢе ҙеҗҲ
ж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒ§гҒҜгҖҒеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҒ®и¶Ҡеўғ移転гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ(1) еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·е§”е“ЎдјҡпјҲPPCпјүгҒ«гӮҲгӮӢеҚҒеҲҶжҖ§иӘҚе®ҡеӣҪгҒёгҒ®з§»и»ўгҖҒ(2) гғҮгғјгӮҝдё»дҪ“гҒӢгӮүгҒ®еҗҢж„ҸгҖҒ(3) PPCиҰҸеүҮгҒҢе®ҡгӮҒгӮӢеҹәжә–гҒ«йҒ©еҗҲгҒҷгӮӢжҺӘзҪ®пјҲдҫӢпјҡAPEC CBPRгӮ·гӮ№гғҶгғ иӘҚе®ҡгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ«гӮҲгӮӢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гҒӘгҒ©пјүгӮ’и¬ӣгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶжҳҺзўәгҒӘиҰҒ件гҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®з¬¬21жқЎгҒҜгҖҒжҳҺзўәгҒӘжі•зҡ„еҹәжә–гҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒгғӘгӮ№гӮҜгҒ«еҹәгҒҘгҒҸгҖҢеҲ¶йҷҗжЁ©йҷҗгҖҚгӮ’иҰҸеҲ¶еҪ“еұҖгҒ«дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҒҙйқўгҒҢеј·гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҖҢеҺҹеүҮиЁұеҸҜгҖҒдҫӢеӨ–зҰҒжӯўгҖҚгҒ®гғ«гғјгғ«гҒҜгҖҒе®ҹеӢҷзҡ„гҒ«гҒҜгҖҢгӮ°гғ¬гғјгӮҫгғјгғігҖҚгӮ„гҖҢдёҚзўәе®ҹжҖ§гҖҚгӮ’еҶ…еҢ…гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒеҪ“еұҖгҒҢгҖҢеҸ—й ҳеӣҪгҒ«йҒ©еҲҮгҒӘдҝқиӯ·иҰҸеҲ¶гҒҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒ移転гҒҢзӘҒ然еҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе®ҹйҡӣгҒ«гҖҒеҠҙеғҚйғЁгҒҢдәәеҠӣд»Ід»ӢжҘӯиҖ…гҒ®еҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгӮ’дёӯеӣҪеӨ§йҷёгҒёз§»и»ўгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еҲ¶йҷҗгҒ—гҒҹдәӢдҫӢгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒжҠҪиұЎзҡ„гҒӘжқЎж–ҮгҒҢе…·дҪ“зҡ„гҒӘиЎҢж”ҝеҮҰеҲҶгҒ«з№ӢгҒҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«жі•еҫӢгҒҢзҰҒжӯўгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒЁе®үжҳ“гҒ«гғҮгғјгӮҝгӮ’еҸ°ж№ҫеӨ–гҒ«з§»и»ўгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиҮӘзӨҫгҒ®дәӢжҘӯеҲҶйҮҺгӮ’з®ЎиҪ„гҒҷгӮӢдё»з®Ўе®ҳеәҒгҒ«дәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгӮ’иЎҢгҒҶгҒӘгҒ©гҖҒж…ҺйҮҚгҒӘеҜҫеҝңгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
| еҸ°ж№ҫгҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі• | ж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі• | |
|---|---|---|
| еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢжҰӮеҝө | гҖҢеҖӢдәәиіҮж–ҷгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҢ…жӢ¬зҡ„жҰӮеҝө | гҖҢеҖӢдәәжғ…е ұгҖҚгҒЁгҖҢеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҖҚгҒ®еҢәеҲҘ |
| зӣЈзқЈж©ҹй–ў | зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹеҖӢдәәиіҮж–ҷдҝқиӯ·е§”е“ЎдјҡпјҲPDPCпјүгҒёгҒ®дёҖе…ғеҢ–пјҲ移иЎҢжңҹй–“гҒӮгӮҠпјү | зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·е§”е“ЎдјҡпјҲPPCпјүгҒ«гӮҲгӮӢдёҖе…ғеҢ– |
| зҪ°еүҮдҪ“зі» | иЎҢж”ҝзҪ°гҖҒеҲ‘дәӢзҪ°гҖҒж°‘дәӢиі е„ҹгҒ®дёүжң¬з«ӢгҒҰ | иЎҢж”ҝжҢҮе°Һгғ»е‘Ҫд»Өгғ»еӢ§е‘ҠгҒҢдё»дҪ“пјҲеҲ‘дәӢзҪ°гҒҜйҷҗе®ҡзҡ„пјү |
| и¶ҠеўғгғҮгғјгӮҝ移転гғ«гғјгғ« | еҺҹеүҮиЁұеҸҜгҖҒдҫӢеӨ–еҲ¶йҷҗпјҲдё»з®Ўе®ҳеәҒгҒ®иЈҒйҮҸпјү | еҚҒеҲҶжҖ§иӘҚе®ҡеӣҪгҒёгҒ®з§»и»ўгҖҒжң¬дәәеҗҢж„ҸгҖҒеҘ‘зҙ„зҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гҒӘгҒ©жҳҺзўәгҒӘгғ«гғјгғ« |
еҸ°ж№ҫPDPAгҒ®зҪ°еүҮгҒЁе®ҹдҫӢ

иЎҢж”ҝзҪ°гғ»еҲ‘дәӢзҪ°гғ»ж°‘дәӢиі е„ҹ
еҸ°ж№ҫPDPAгҒ®жңҖгӮӮеҺіж јгҒӘеҒҙйқўгҒ®дёҖгҒӨгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢзҪ°еүҮдҪ“зі»гҒ§гҒҷгҖӮйҒ•еҸҚиҖ…гҒ«гҒҜгҖҒиЎҢж”ҝзҪ°гҖҒеҲ‘дәӢзҪ°гҖҒгҒқгҒ—гҒҰж°‘дәӢиі е„ҹгҒ®дёүгҒӨгҒ®жі•зҡ„иІ¬д»»гҒҢеҗҢжҷӮгҒ«з§‘гҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- иЎҢж”ҝзҪ°пјҡйҒ©еҲҮгҒӘе®үе…Ёз®ЎзҗҶжҺӘзҪ®гӮ’жҖ гҒЈгҒҹдәӢжҘӯиҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒжғ…зҠ¶гҒҢйҮҚеӨ§гҒӘе ҙеҗҲгҖҒзӣҙжҺҘ15дёҮгҖң1,500дёҮеҸ°ж№ҫгғүгғ«пјҲзҙ„70дёҮгҖң7,000дёҮеҶҶпјүгҒ®й«ҳйЎҚгҒӘзҪ°йҮ‘гҒҢ科гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
- еҲ‘дәӢзҪ°пјҡйҒ•жі•гҒӘеҲ©зӣҠгӮ’еҫ—гӮӢзӣ®зҡ„гӮ„гҖҒд»–дәәгҒ®еҲ©зӣҠгӮ’жҗҚгҒӘгҒҶзӣ®зҡ„гҒ§еҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгӮ’дёҚжӯЈгҒ«еҸ–еҫ—гҖҒеҮҰзҗҶгҖҒеҲ©з”ЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒжңҖеӨ§гҒ§5е№ҙгҒ®жҮІеҪ№еҲ‘гҒҠгӮҲгҒі/гҒҫгҒҹгҒҜ100дёҮеҸ°ж№ҫгғүгғ«пјҲзҙ„470дёҮеҶҶпјүд»ҘдёӢгҒ®зҪ°йҮ‘гҒҢ科гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- ж°‘дәӢиі е„ҹпјҡиў«е®іиҖ…гҒҜгҖҒиЁјжҳҺгҒҢеӣ°йӣЈгҒӘе ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒ1дәәгҒӮгҒҹгӮҠ500гҖң20,000еҸ°ж№ҫгғүгғ«гҒ®жі•е®ҡжҗҚе®іиі е„ҹгӮ’и«ӢжұӮгҒ§гҒҚгҖҒйӣҶеӣЈиЁҙиЁҹгҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒз·ҸйЎҚ2е„„еҸ°ж№ҫгғүгғ«пјҲзҙ„9.4е„„еҶҶпјүгҒҫгҒ§гҒ®иі е„ҹйЎҚгӮ’и«ӢжұӮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®зҪ°еүҮдҪ“зі»гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒЁгҒ®жұәе®ҡзҡ„гҒӘйҒ•гҒ„гӮ’жө®гҒҚеҪ«гӮҠгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒ§гҒҜгҖҒеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·е§”е“ЎдјҡгҒ«гӮҲгӮӢе‘Ҫд»ӨйҒ•еҸҚгӮ„иҷҡеҒҪе ұе‘ҠгҒӘгҒ©гҖҒйҷҗе®ҡзҡ„гҒӘе ҙеҗҲгҒ«гҒ®гҒҝеҲ‘дәӢзҪ°гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдёҚжӯЈгҒӘгғҮгғјгӮҝеҸ–еҫ—гғ»еҲ©з”ЁгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«жҮІеҪ№еҲ‘гӮ’科гҒҷиҰҸе®ҡгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®PPCгҒ«гҒҜгҖҒиЎҢж”ҝзҪ°гҒЁгҒ—гҒҰзӣҙжҺҘй«ҳйЎҚгҒӘзҪ°йҮ‘гӮ’科гҒҷжЁ©йҷҗгҒҢгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒдёҚжӯЈиЎҢзӮәгҒ«гҒҜгҒҫгҒҡжҢҮе°ҺгӮ„еӢ§е‘ҠгҖҒе‘Ҫд»ӨгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиЎҢж”ҝеҮҰеҲҶгҒҢе…ҲиЎҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҸ°ж№ҫгҒ§гҒҜйҮҚеӨ§гҒӘйҒ•еҸҚгҒ®е ҙеҗҲгҖҒзӣҙжҺҘй«ҳйЎҚгҒӘзҪ°йҮ‘гҒҢ科гҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зҪ°еүҮдҪ“зі»гҒҜгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ§гҒ®гӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№йҒ•еҸҚгҒҢгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢдјҒжҘӯгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒ«з•ҷгҒҫгӮүгҒҡгҖҒзҸҫең°гҒ®иІ¬д»»иҖ…гӮ„жӢ…еҪ“иҖ…гҒ®гҖҢеҖӢдәәгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҖҚгҒ«зӣҙзөҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒж•…ж„ҸгӮ„дёҚжӯЈзӣ®зҡ„гҒ®йҒ•еҸҚгҒ«гҒҜжҮІеҪ№еҲ‘гҒҢ科гҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жң¬зӨҫгҒҜгҖҒеҸ°ж№ҫеӯҗдјҡзӨҫгӮ„зҸҫең°гҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№ж•ҷиӮІгҒЁз®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶гӮ’гҖҒж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…гҒ®еҹәжә–гӮҲгӮҠгӮӮеҺіж јгҒ«ж§ӢзҜүгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеј·гҒ„зӨәе”ҶгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
| еҜҫиұЎ | зҪ°еүҮеҶ…е®№ | |
|---|---|---|
| иЎҢж”ҝзҪ° | йҒ©еҲҮгҒӘе®үе…Ёз®ЎзҗҶжҺӘзҪ®гӮ’жҖ гҒЈгҒҹдәӢжҘӯиҖ… | жңҖй«ҳ1,500дёҮеҸ°ж№ҫгғүгғ«пјҲзҙ„7,000дёҮеҶҶпјүгҒ®зҪ°йҮ‘ |
| еҲ‘дәӢзҪ° | йҒ•жі•гҒӘеҲ©зӣҠгӮ’еҫ—гӮӢзӣ®зҡ„гӮ„гҖҒд»–дәәгҒ®еҲ©зӣҠгӮ’жҗҚгҒӘгҒҶзӣ®зҡ„гҒ§еҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгӮ’дёҚжӯЈгҒ«еҸ–еҫ—гғ»еҮҰзҗҶгғ»еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲ | жңҖеӨ§5е№ҙгҒ®жҮІеҪ№гҒҠгӮҲгҒі/гҒҫгҒҹгҒҜ100дёҮеҸ°ж№ҫгғүгғ«пјҲзҙ„470дёҮеҶҶпјүд»ҘдёӢгҒ®зҪ°йҮ‘ |
| ж°‘дәӢиі е„ҹ | йҒ•жі•гҒӘеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҒ®еҲ©з”ЁгҒ«гӮҲгӮҠиў«е®ігӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгғҮгғјгӮҝдё»дҪ“ | 1дәәгҒӮгҒҹгӮҠ500гҖң20,000еҸ°ж№ҫгғүгғ«гҒ®жі•е®ҡжҗҚе®іиі е„ҹгҖҒйӣҶеӣЈиЁҙиЁҹгҒ§гҒҜз·ҸйЎҚ2е„„еҸ°ж№ҫгғүгғ«пјҲзҙ„9.4е„„еҶҶпјүгҒҫгҒ§ |
еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•йҒ•еҸҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢе®ҹдҫӢ
еҸ°ж№ҫгҒ§гҒҜгҖҒеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•йҒ•еҸҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢе®ҹдҫӢгҒҢгҒҷгҒ§гҒ«еӨҡгҒҸеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдәәж°—YouTuberгҒҢе…ғеӨ«гҒ®еҢ»зҷӮиЁҳйҢІгӮ’дёҚжӯЈгҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒ—гҒҰеҲ‘дәӢе‘ҠзҷәгҒ•гӮҢгҒҹдәӢдҫӢгӮ„ гҖҒгғҮгғјгӮҝжјҸжҙ©гҒ«гӮҲгӮҠгӮ«гғјгӮ·гӮ§гӮўгғӘгғігӮ°гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„ECдәӢжҘӯиҖ…гҒҢиЎҢж”ҝзҪ°гӮ’科гҒ•гӮҢгҒҹдәӢдҫӢгҒҜгҖҒгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№йҒ•еҸҚгҒҢдәӢжҘӯгҒ«дёҺгҒҲгӮӢеҪұйҹҝгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®дәӢдҫӢгҒҜгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®иҰҸеҲ¶еҪ“еұҖгҒҢгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢеҪўејҸзҡ„гҒӘйҒ•еҸҚгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғҮгғјгӮҝдҫөе®ігӮ„дёҚжӯЈеҲ©з”ЁгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе®ҹиіӘзҡ„гҒӘгғӘгӮ№гӮҜгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰеҺіж јгҒӘе§ҝеӢўгҒ§иҮЁгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зү©иӘһгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮВ В
гҒҫгҒЁгӮҒ
2023е№ҙгҒ®ж”№жӯЈгӮ’зөҢгҒҰгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒгӮҲгӮҠеҺіж јгҒ§зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹзӣЈзқЈдҪ“еҲ¶гҒёгҒЁз§»иЎҢгҒ—гҖҒй«ҳйЎҚгҒӘиЎҢж”ҝзҪ°гӮ„гҖҒжҷӮгҒ«гҒҜжҮІеҪ№еҲ‘гӮ’дјҙгҒҶеҲ‘дәӢзҪ°гӮ’科гҒҷгҒӘгҒ©гҖҒгҒқгҒ®жі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’еӨ§е№…гҒ«й«ҳгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒи¶ҠеўғгғҮгғјгӮҝ移転гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеҪўејҸзҡ„гҒӘиЁұеҸҜеҲ¶гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒдё»з®Ўе®ҳеәҒгҒ®иЈҒйҮҸгҒ«гӮҲгӮӢеҲ¶йҷҗгғӘгӮ№гӮҜгӮ’еёёгҒ«иҖғж…®гҒ«е…ҘгӮҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸ°ж№ҫгҒ®PDPAгҒҜгҖҒдҝқиӯ·еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҖҢеҖӢдәәиіҮж–ҷгҖҚгҒ®зҜ„еӣІгҒҢеәғгҒҸгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒ2023е№ҙгҒ®ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹзӣЈзқЈж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢPDPCгҒҢиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§еҗ„зңҒеәҒгҒ«еҲҶж•ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹзӣЈзқЈжЁ©йҷҗгҒҢдёҖе…ғеҢ–гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®PPCгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒгӮҲгӮҠе°Ӯй–Җзҡ„гҒӢгҒӨеҺіж јгҒӘзӣЈзқЈгҒЁеҹ·иЎҢгҒҢжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒи¶ҠеўғгғҮгғјгӮҝ移転гҒҜгҖҒеҸ—й ҳеӣҪгҒ«йҒ©еҲҮгҒӘдҝқиӯ·жі•иҰҸгҒҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ«еҪ“еұҖгҒҢеҲ¶йҷҗгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҳҺзўәгҒӘгғ«гғјгғ«гҒҢгҒӮгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе®ҹеӢҷдёҠгҒҜгӮҲгӮҠй«ҳгҒ„дёҚзўәе®ҹжҖ§гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘзӮ№гҒҜгҖҒйҒ•еҸҚгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®зҪ°еүҮгҒҢжҘөгӮҒгҒҰеҺігҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮжңҖй«ҳ1,500дёҮеҸ°ж№ҫгғүгғ«пјҲзҙ„7,000дёҮеҶҶпјүгҒ®иЎҢж”ҝзҪ°йҮ‘гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒдёҚжӯЈзӣ®зҡ„гҒ®гғҮгғјгӮҝеҲ©з”ЁгҒ«гҒҜжңҖеӨ§5е№ҙгҒ®жҮІеҪ№еҲ‘гҒҢ科гҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒ«гҒҜгҒӘгҒ„гҖҒеҖӢдәәгӮ’зӣҙжҺҘеҜҫиұЎгҒЁгҒҷгӮӢйҮҚгҒ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·жі•гҒ«жә–жӢ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒеҸ°ж№ҫгҒ§гӮӮе®үе…ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒҜйҷҗгӮүгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶжҳҺзўәгҒӘиӯҰйҗҳгҒ§гҒҷгҖӮеҸ°ж№ҫгҒ§гҒ®дәӢжҘӯгӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еҹәжә–гӮ’дёҠеӣһгӮӢгҖҒзҸҫең°гҒ®жі•иҰҸеҲ¶гҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹеҺіж јгҒӘгӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№дҪ“еҲ¶гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: еҸ°ж№ҫжө·еӨ–дәӢжҘӯ