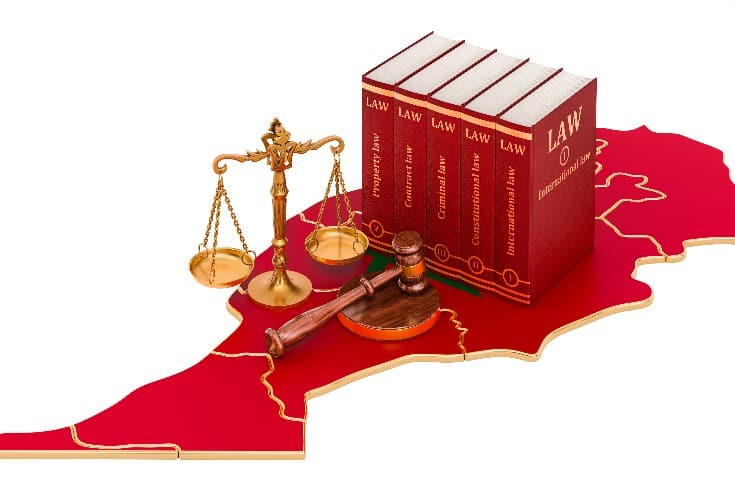Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«µ│ĢÕŠŗŃü«Õģ©õĮōÕāÅŃü©ŃüØŃü«µ”éĶ”üŃéÆÕ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüīĶ¦ŻĶ¬¼

Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½’╝łµŁŻÕ╝ÅÕÉŹń¦░ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ķĆŻķé”Õģ▒ÕÆīÕøĮ’╝ēŃü»ŃĆüÕŹŚń▒│µ£ĆÕż¦Ńü«ńĄīµĖłÕż¦ÕøĮŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüØŃü«Õ║āÕż¦Ńü¬ÕøĮÕ£¤Ńü©ń┤ä2Õää2,000õĖćõ║║Ńü«õ║║ÕÅŻŃüīÕĮóµłÉŃüÖŃéŗÕĘ©Õż¦Ńü¬ÕĖéÕĀ┤Ńü»ŃĆüÕżÜŃüÅŃü«µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ķŁģÕŖøńÜäŃü¬ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣µ®¤õ╝ÜŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ŃüĖŃü«õ║ŗµźŁÕ▒Ģķ¢ŗŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦ŃĆüŃüØŃü«µ│ĢÕłČÕ║”ŃüīµŚźµ£¼Ńü©ÕżÜŃüÅŃü«ńé╣Ńü¦ńĢ░Ńü¬ŃéŗŃüōŃü©ŃéƵĘ▒ŃüÅńÉåĶ¦ŻŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆéŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü»1822Õ╣┤Ńü½ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½ŃüŗŃéēńŗ¼ń½ŗŃüŚŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃĆüµŚźµ£¼Ńü©ÕÉīµ¦śŃü½µłÉµ¢ćµ│ĢŃéÆõĖŁµĀĖŃü©ŃüÖŃéŗÕż¦ķÖĖµ│Ģń│╗Ńü«µ│ĢõĮōń│╗ŃéÆńÖ║Õ▒ĢŃüĢŃüøŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüØŃü«µŁ┤ÕÅ▓ńÜäĶāīµÖ»ŃéäńżŠõ╝ÜńĄīµĖłńÜ䵦ŗķĆĀŃü«ķüĢŃüäŃüŗŃéēŃĆüńē╣Ńü½ÕŖ┤ÕāŹµ│ĢŃéäń©Äµ│ĢŃĆüÕÅĖµ│ĢÕłČÕ║”Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü©Ńü»Õż¦ŃüŹŃüÅńĢ░Ńü¬Ńéŗńŗ¼Ķć¬Ńü«õ╗ĢńĄäŃü┐ŃéƵ¦ŗń»ēŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńē╣Ńü½µ│©µäÅŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüÕŖ┤ÕāŹĶĆģõ┐ØĶŁĘŃéÆÕ╝ĘŃüÅÕ┐ŚÕÉæŃüÖŃéŗµ│ĢÕłČÕ║”ŃéäŃĆüÕżÜÕ▒żńÜäŃü¦ĶżćķøæŃü¬ń©ÄÕłČŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü»ŃĆüõ║łµ£¤ŃüøŃü¼Ńé│Ńé╣ŃāłŃéäŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü©ŃüŚŃü”ŃĆüķĆ▓Õć║ŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗõ╝üµźŁŃü«ĶČ│ŃüŗŃüøŃü©Ńü¬ŃéŖÕŠŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüĶ┐æÕ╣┤Ńü¦Ńü»ŃĆüÕøĮķÜøńÜäŃü¬µĮ«µĄüŃü½ÕÉłŃéÅŃüøŃü¤ń¦╗Ķ╗óõŠĪµĀ╝ń©ÄÕłČŃü«µŁ┤ÕÅ▓ńÜäŃü¬Õż¦µö╣µŁŻŃéäŃĆüõĖŁÕż«ķŖĆĶĪīõĖ╗Õ░ÄŃü«ÕŹ│µÖéµ▒║µĖłŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃĆīPixŃĆŹŃü«µĆźķƤŃü¬µÖ«ÕÅŖŃü¬Ńü®ŃĆüŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ńÆ░ÕóāŃéƵĀ╣µ£¼ŃüŗŃéēÕżēŃüłŃéŗŃéłŃüåŃü¬ÕŗĢŃüŹŃééµ┤╗ńÖ║Ńü¦ŃüÖŃĆé
µ£¼Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü«ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Õ▒Ģķ¢ŗŃéƵż£Ķ©ÄŃüŚŃü”ŃüäŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½ÕÉæŃüæŃü”ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½µ│ĢÕłČÕ║”Ńü«Õģ©õĮōÕāÅŃéÆÕ░éķ¢ĆńÜäŃü½Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃĆüńē╣Ńü½µŚźµ£¼µ│ĢŃü©µ»öĶ╝āŃüŚŃü”µ│©µäÅŃüÖŃü╣ŃüŹµ│ĢÕŠŗŃéäÕłČÕ║”Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ķ®│ŃüŚŃüÅµÄśŃéŖõĖŗŃüÆŃü”ŃüäŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«µ│ĢõĮōń│╗Ńü©ÕÅĖµ│Ģµ¦ŗķĆĀ
ķĆŻķé”ÕłČŃü©Õż¦ķÖĖµ│Ģń│╗Ńü«µ│ĢõĮōń│╗
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü©ÕÉīµ¦śŃü½ŃĆüŃāŁŃā╝Ńā×µ│ĢŃéÆĶĄĘµ║ÉŃü©ŃüÖŃéŗŃĆīÕż¦ķÖĖµ│Ģń│╗ŃĆŹŃü½Õ▒×ŃüŚŃĆüµå▓µ│ĢŃéäµ│ĢÕŠŗŃü©ŃüäŃüŻŃü¤µłÉµ¢ćµ│ĢŃüīµ│ĢõĮōń│╗Ńü«õĖŁÕ┐āŃéÆÕŹĀŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ńé╣Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüÕłżõŠŗµ│ĢõĖ╗ńŠ®ŃéÆÕ¤║µ£¼Ńü©ŃüÖŃéŗĶŗ▒ń▒│µ│Ģń│╗Ńü©Ńü»Õż¦ŃüŹŃüÅńĢ░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüµŚźµ£¼Ńü©Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«µ£ĆŃééµĀ╣µ£¼ńÜäŃü¬ķüĢŃüäŃü»ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ŃüīŃĆīķĆŻķé”Õģ▒ÕÆīÕłČŃĆŹŃéƵÄĪńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗńé╣Ńü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüµ│ĢõĮōń│╗Ńü»ķĆŻķ锵│ĢŃĆüÕĘ×µ│ĢŃĆüÕĖéńö║µØæµØĪõŠŗŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ÕżÜÕ▒żńÜäŃü¬µ¦ŗķĆĀŃéƵīüŃüĪŃĆüõ║ŗµźŁµ┤╗ÕŗĢŃéÆĶĪīŃüåÕĘ×ŃéäÕĖéŃü½ŃéłŃüŻŃü”ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗµ│ĢÕŠŗŃéäĶ”ÅÕłČŃüīńĢ░Ńü¬ŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«µ│ĢÕŠŗŃü»ÕøĮÕģ©õĮōŃü½õĖĆÕŠŗŃü½ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕĤÕēćŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü»ķĆŻķ锵│ĢŃüīõĖ╗Ķ”üŃü¬µ│ĢÕŠŗÕłåķćÄŃéÆĶ”ÅÕ«ÜŃüŚŃüżŃüżŃééŃĆüÕĘ×ŃéäÕĖéŃüīńŗ¼Ķć¬Ńü«ń½ŗµ│Ģµ©®ŃéÆĶĪīõĮ┐Ńü¦ŃüŹŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüÕ£░Õ¤¤ŃüöŃü©Ńü«µ│ĢńÜäńÆ░ÕóāŃéƵŖŖµÅĪŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õ║īķ揵¦ŗķĆĀŃü«ÕÅĖµ│ĢÕłČÕ║”Ńü©ńē╣ÕłźŃü¬ĶŻüÕłżµēĆ
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ÕÅĖµ│ĢÕłČÕ║”ŃééŃüŠŃü¤ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ŃüØŃéīŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗńŗ¼ńē╣Ńü¬µ¦ŗķĆĀŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«ĶŻüÕłżµēĆŃüīµ£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃéÆķĀéńé╣Ńü©ŃüÖŃéŗÕŹśõĖĆŃü«ķÜÄÕ▒żµ¦ŗķĆĀŃü¦ŃüéŃéŗŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü»ķĆŻķ锵£Ćķ½śĶŻüÕłżµēĆŃéÆķĀéńé╣Ńü©ŃüÖŃéŗŃĆīķĆŻķé”ĶŻüÕłżµēĆń│╗ÕłŚŃĆŹŃü©ŃĆüÕÉäÕĘ×Ńü½Ķ©ŁńĮ«ŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīÕĘ×ĶŻüÕłżµēĆń│╗ÕłŚŃĆŹŃü½Õż¦ŃüŹŃüÅÕłåŃüŗŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕĘ×ĶŻüÕłżµēĆŃü»õĖĆĶł¼ńÜäŃü¬µ░æõ║ŗĶ©┤Ķ©¤ŃéäÕłæõ║ŗĶ©┤Ķ©¤ŃéÆń«ĪĶĮäŃüÖŃéŗõĖƵ¢╣ŃĆüķĆŻķé”ĶŻüÕłżµēĆŃü»ķĆŻķ锵ö┐Õ║£ŃüīÕĮōõ║ŗĶĆģŃü©Ńü¬Ńéŗõ║ŗõ╗ČŃéäµå▓µ│ĢÕĢÅķĪīŃéƵē▒ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃéēŃü½ÕŖĀŃüłŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü½Ńü»ŃĆīÕŖ┤ÕāŹŃĆŹŃĆīķüĖµīÖŃĆŹŃĆīĶ╗Źõ║ŗŃĆŹŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ńē╣Õ«ÜÕłåķćÄŃéÆÕ░éķ¢ĆŃü½µē▒Ńüåńē╣ÕłźŃü¬ķĆŻķé”ĶŻüÕłżµēĆŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüÕŖ┤ÕāŹĶĆģŃü©õĮ┐ńö©ĶĆģķ¢ōŃü«ń┤øõ║ēŃéÆÕ░éķ¢ĆŃü½µē▒ŃüåŃĆīÕŖ┤ÕāŹĶŻüÕłżµēĆŃĆŹŃü»ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīµ£ĆŃééķ¢óŃéÅŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńüīķ½śŃüäĶŻüÕłżµēĆŃü«õĖĆŃüżŃü¦ŃüÖŃĆé
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ÕŖ┤ÕāŹĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüÕŹśŃü½ÕŖ┤ÕāŹń┤øõ║ēŃéƵē▒ŃüåÕ░éķ¢ĆŃü«ĶŻüÕłżµēĆŃü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüŃüØŃü«ķüŗńö©µĆصā│Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ķćŹĶ”üŃü¬ńē╣ÕŠ┤ŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ÕŖ┤ÕāŹµ│ĢŃü»ŃĆīńĄ▒ÕÉłÕŖ┤ÕāŹµ│Ģ’╝łCLT’╝ēŃĆŹŃéƵĀ╣Õ╣╣Ńü©ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüōŃü«µ│ĢÕŠŗŃü»ÕŖ┤ÕāŹĶĆģŃéÆńżŠõ╝ÜńÜäÕ╝▒ĶĆģŃĆüõĮ┐ńö©ĶĆģŃéƵɊÕÅ¢ĶĆģŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüÖÕ╝ĘŃüäÕŖ┤ÕāŹĶĆģõ┐ØĶŁĘŃü«µĆصā│Ńü½Õ¤║ŃüźŃüäŃü”ÕłČÕ«ÜŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕŖ┤ÕāŹĶŻüÕłżµēĆŃü»ŃĆüŃüōŃü«CLTŃü«µĆصā│Ńü½Õ¤║ŃüźŃüŹĶŻüÕłżŃéÆķüŗńö©ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüÕŖ┤ÕāŹĶ©┤Ķ©¤Ńü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»õ╝üµźŁÕü┤ŃüīõĖŹÕł®Ńü¬ń½ŗÕĀ┤Ńü½ńĮ«ŃüŗŃéīŃéäŃüÖŃüäŃü©ŃüäŃü嵦ŗķĆĀńÜäŃü¬ÕĢÅķĪīŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«µ¦ŗķĆĀŃü»ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗÕŖ┤ÕāŹń┤øõ║ēŃüīŃĆüµŚźµ£¼Ńü«õĖĆĶł¼ńÜäŃü¬ĶŻüÕłżŃü©Ńü»ÕłćŃéŖķøóŃüĢŃéīŃü¤ŃĆüńŗ¼Ķć¬Ńü«µ│ĢõĮōń│╗Ńü©ÕÅĖµ│ĢŃéżŃā│ŃāĢŃā®Ńü«õĖŁŃü¦Õć”ńÉåŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüõ╝üµźŁŃü»ÕŖ┤ÕāŹÕĢÅķĪīŃéÆõĖĆĶł¼ńÜäŃü¬µ│ĢÕŗÖŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü©ŃüŚŃü”Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕ░éķ¢ĆńÜäŃüŗŃüżķćŹÕż¦Ńü¬Ńā¬Ńé╣Ńé»Ńü©ŃüŚŃü”µŹēŃüłŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéĶ©┤Ķ©¤õ╗ȵĢ░ŃüīķØ×ÕĖĖŃü½ÕżÜŃüÅŃĆüĶŻüÕłżÕ«śŃü«õĖŹĶČ│Ńü½ŃéłŃéŗĶ©┤Ķ©¤Ńü«ķĢʵ£¤Õī¢ŃééÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü»ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü«õ║║õ║ŗŃā╗ÕŖ┤ÕŗÖµł”ńĢźŃéÆńŁ¢Õ«ÜŃüÖŃéŗķÜøŃü½Ńü»ŃĆüĶ©┤Ķ©¤Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéƵ£ĆÕ░ÅÕī¢ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«õ║ŗÕēŹÕ»ŠńŁ¢ŃéÆĶ¼øŃüśŃéŗŃüōŃü©ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
Ķ©┤Ķ©¤µ¢ćÕī¢Ńü©µēŗńČÜŃü«ńē╣ÕŠ┤
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü»Ķ©┤Ķ©¤Ńü«µĢ░ŃüīķØ×ÕĖĖŃü½ÕżÜŃüÅŃĆüń¼¼õĖĆÕ»®Ńü«ĶŻüÕłżŃüīńĄéõ║åŃüÖŃéŗŃüŠŃü¦Ńü½3Õ╣┤ÕēŹÕŠīŃüŗŃüŗŃéŗŃüōŃü©ŃééńÅŹŃüŚŃüÅŃü¬ŃüÅŃĆüµĪłõ╗ČŃü½ŃéłŃüŻŃü”Ńü»20Õ╣┤ńČÜŃüÅŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ķ©┤Ķ©¤ķüģµ╗×Ńü«ÕĢÅķĪīŃü»ŃĆüń┤øõ║ēÕĮōõ║ŗĶĆģÕÅīµ¢╣Ńü½Ńü©ŃüŻŃü”Õż¦ŃüŹŃü¬õĖŹÕł®ńøŖŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüÕÆīĶ¦ŻŃüīÕ║āŃüÅÕł®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗÕéŠÕÉæŃü½ŃüéŃéŖŃĆü2016Õ╣┤Ńü½µ¢ĮĶĪīŃüĢŃéīŃü¤µ¢░µ░æõ║ŗĶ©┤Ķ©¤µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüĶ©┤Ķ©¤µÅÉĶĄĘÕŠīŃü½ŃüŠŃüÜÕĮōõ║ŗĶĆģķ¢ōŃü«Ķ¬┐Õü£µēŗńČÜŃüŹŃüīĶ©ŁÕ«ÜŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü»ŃĆīÕ╝üĶŁĘÕŻ½Ķ▓╗ńö©µĢŚĶ©┤ĶĆģĶ▓ĀµŗģŃĆŹÕłČÕ║”ŃüīµÄĪńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµĢŚĶ©┤ŃüŚŃü¤ÕĮōõ║ŗĶĆģŃüīńøĖµēŗµ¢╣Ńü«Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ķ▓╗ńö©ŃéƵö»µēĢŃüåńŠ®ÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåŃü©ŃüäŃüåŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃüōŃü«Ķ▓╗ńö©Ńü»ŃĆüµĢŚĶ©┤ķĪŹŃü«10%ŃüŗŃéē20%Ńü«ķ¢ōŃü¦ĶŻüÕłżµēĆŃüīµ▒║Õ«ÜŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüĶ©┤Ķ©¤Ńā¬Ńé╣Ńé»Ńü«Ķ®ĢõŠĪŃéƵĀ╣µ£¼ńÜäŃü½ÕżēŃüłŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü»ŃĆüµ£¼µĪłŃü«Ķ│ĀÕä¤ķĪŹŃü½ÕŖĀŃüłŃü”ŃĆüńøĖµēŗµ¢╣Ńü«Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ķ▓╗ńö©Ńü©ŃüäŃüåĶ┐ĮÕŖĀŃé│Ńé╣ŃāłŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆĶĆāµģ«ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüĶ©┤Ķ©¤Ńü«ķĢʵ£¤Õī¢Ńü½õ╝┤ŃüäŃĆüÕłżµ▒║µÖéŃü«Ķ¬ŹÕ«ÜķćæķĪŹŃüīÕĮōÕłØŃü«Ķ½ŗµ▒éķćæķĪŹŃü©Õż¦ŃüŹŃüÅńĢ░Ńü¬ŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃĆüµ░æõ║ŗõ║ŗõ╗ČŃü¦Ńü»µ£łŃü½1%Ńü«µ│ĢÕ«ÜÕł®ÕŁÉŃüīÕŖĀń«ŚŃüĢŃéīŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµĢŚĶ©┤µÖéŃü«ķćæķŖŁńÜäĶ▓ĀµŗģŃü»ŃüĢŃéēŃü½ÕóŚÕż¦ŃüÖŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü»ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü«ń┤øõ║ēŃü½ķÜøŃüŚŃü”ŃĆüÕŗØĶ©┤Ńü«ńó║Õ«¤µĆ¦ŃüīõĮÄŃüäµĪłõ╗ČŃü¦Ńü»ŃĆüĶ©┤Ķ©¤Ķ▓╗ńö©Ńü©µĢŚĶ©┤Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéƵģÄķćŹŃü½µ»öĶ╝āµż£Ķ©ÄŃüŚŃĆüÕÆīĶ¦ŻŃéÆķüĖµŖ×ĶéóŃü©ŃüŚŃü”Õ╝ĘŃüÅĶĆāµģ«ŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½ŃüĖŃü«µĄĘÕż¢õ╝üµźŁŃü«ķĆ▓Õć║ÕĮóµģŗŃü©õ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗ

ńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║Ķ©Łń½ŗŃü«Õ┐ģĶ”üµĆ¦
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½ŃüĖŃü«õ║ŗµźŁķĆ▓Õć║Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīķüĖµŖ×Ńü¦ŃüŹŃéŗÕĮóµģŗŃü»ķÖÉŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü½Ńü»ŃĆüķ¦ÉÕ£©ÕōĪõ║ŗÕŗÖµēĆŃü©ŃüäŃüåµ│ĢńÜäµ”éÕ┐ĄŃüīÕŁśÕ£©ŃüøŃüÜŃĆüŃüŠŃü¤ŃĆüÕż¢ÕøĮõ╝üµźŁŃü«µö»Õ║ŚĶ©Łń½ŗŃü½Ńü»ķĆŻķ锵ö┐Õ║£Ńü½ŃéłŃéŗõ║ŗÕēŹĶ¬ŹÕÅ»ŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©ŃüĢŃéīŃĆüńē╣ÕłźŃü¬Ńé▒Ńā╝Ńé╣ŃéÆķÖżŃüäŃü”Ķ¬ŹÕÅ»ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ńü╗Ńü©ŃéōŃü®ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü½ķĆ▓Õć║ŃüÖŃéŗµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü«Ńü╗Ńü©ŃéōŃü®ŃüīŃĆüńÅŠÕ£░µ│Ģõ║║ŃéÆĶ©Łń½ŗŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕĮóµģŗŃéÆķüĖµŖ×ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õĖ╗µĄüŃü©Ńü¬Ńéŗõ╝ÜńżŠŃü«ÕĮóµģŗ
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½µ│ĢõĖŖŃĆüµ£ĆŃééõĖĆĶł¼ńÜäŃü½Õł®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗõ╝ÜńżŠŃü«ÕĮóµģŗŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ÕÉłÕÉīõ╝ÜńżŠŃü½ńøĖÕĮōŃüÖŃéŗŃĆīµ£ēķÖÉõ╝ÜńżŠ’╝łSociedade Limitada’╝ÜLTDA’╝ēŃĆŹŃü©ŃĆüµĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠŃü½ńøĖÕĮōŃüÖŃéŗŃĆīµĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠ’╝łSociedade An├┤nima’╝ÜS.A.’╝ēŃĆŹŃü¦ŃüÖŃĆé
- µ£ēķÖÉõ╝ÜńżŠ’╝łLTDA’╝ē’╝ÜĶ©Łń½ŗµēŗńČÜŃüŹŃüīµ»öĶ╝āńÜäÕŹśń┤öŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüĶ©Łń½ŗŃé│Ńé╣ŃāłŃééõĮÄŃüÅŃĆüõ╝ÜńżŠŃü«µ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃü«µ¤öĶ╗¤µĆ¦Ńüīķ½śŃüäŃü¤ŃéüŃĆüńē╣Ńü½õĖŁÕ░ÅĶ”ŵ©ĪŃü«õ╝üµźŁŃü½ķü®ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü½Ķ©Łń½ŗŃüĢŃéīŃü¤µŚźń│╗ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«Õż¦ķā©ÕłåŃü»ŃüōŃü«ÕĮóµģŗŃéÆŃü©ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµ£ĆõĮÄĶ│ćµ£¼ķćæŃü«Ķ”ÅÕ«ÜŃü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”Õć║Ķ│ćĶĆģ2ÕÉŹŃü¦Ķ©Łń½ŗŃü¦ŃüŹŃĆüÕć║Ķ│ćĶĆģŃü«Ķ▓¼õ╗╗Ńü»Õć║Ķ│ćķĪŹŃü½ķÖÉÕ«ÜŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣Ńü»1ÕÉŹŃü¦ŃéłŃüÅŃĆüÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü«Ķ©ŁńĮ«Ńü»õ╗╗µäÅŃü¦ŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕēŹÕ╣┤Ńü«ńĘÅĶ│ćńöŻŃüī2Õää4,000õĖćŃā¼ŃéóŃā½ĶČģŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Õ╣┤ķ¢ōÕŻ▓õĖŖķ½śŃüī3ÕääŃā¼ŃéóŃā½ĶČģŃü«ŃĆīÕż¦Ķ”ŵ©Īµ£ēķÖÉõ╝ÜńżŠŃĆŹŃéÆķÖżŃüŹŃĆüĶ▓ĪÕŗÖĶ½ĖĶĪ©Ńü«ķ¢ŗńż║ńŠ®ÕŗÖŃü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
- µĀ¬Õ╝Åõ╝ÜńżŠ’╝łS.A.’╝ē’╝ÜÕż¦Ķ”ŵ©ĪŃü¬Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü½ķü®ŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü»ÕÅ¢ńĘĀÕĮ╣õ╝ÜŃü©ńĄīÕ¢ČÕ»®ĶŁ░õ╝ÜŃü«Ķ©ŁńĮ«ŃüīńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéķØ×Õģ¼ķ¢ŗõ╝ÜńżŠŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüµ®¤ķ¢óĶ©ŁĶ©łŃüīŃéłŃéŖµ¤öĶ╗¤Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃüĪŃéēŃééµ£ĆõĮÄĶ│ćµ£¼ķćæŃü«ÕłČķÖÉŃü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüµĀ¬õĖ╗Ńü«µ£ĆõĮÄõ║║µĢ░Ńü»2ÕÉŹŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗµēŗńČÜŃü«ńŗ¼Ķć¬Ķ”üõ╗Č
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦õ╝ÜńżŠŃéÆĶ©Łń½ŗŃüÖŃéŗķÜøŃü½Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗńŗ¼Ķć¬Ńü«Ķ”üõ╗ČŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½µ│©µäÅŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüŃĆīµ│ĢÕ«Üõ╗ŻńÉåõ║║ŃĆŹŃü«ńÖ╗ķī▓ńŠ®ÕŗÖŃü©ŃĆüŃĆīĶ”¬õ╝ÜńżŠŃü«ń©ÄÕŗÖŃĆŹŃü«ńÖ╗ķī▓ńŠ®ÕŗÖŃü¦ŃüÖŃĆé
- µ│ĢÕ«Üõ╗ŻńÉåõ║║’╝łLegal Representative’╝ēŃü«µīćÕÉŹ’╝ÜŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü½µ│Ģõ║║ŃéÆĶ©Łń½ŗŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüńÅŠÕ£░Õ▒ģõĮŵ©®ŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃéŗĶĆģŃéÆŃĆīµ│ĢÕ«Üõ╗ŻńÉåõ║║ŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”Õ┐ģŃüÜńÖ╗ķī▓ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃü«µ│ĢÕ«Üõ╗ŻńÉåõ║║Ńü»ŃĆüÕż¢ÕøĮŃü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃü½õ╗ŻŃéÅŃüŻŃü”ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ÕøĮÕåģŃü¦µ│ĢńÜäŃü¬Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüåń¬ōÕÅŻŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕżÜŃüÅŃü«µŚźń│╗õ╝üµźŁŃü¦Ńü»ŃĆüĶĄ┤õ╗╗ŃüÖŃéŗķ¦ÉÕ£©ÕōĪŃüīµ░ĖõĮÅŃāōŃéČŃéÆÕÅ¢ÕŠŚŃüŚŃü”µ│ĢÕ«Üõ╗ŻńÉåõ║║Ńü©Ńü¬ŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕżÜŃüäŃü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
- Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃü«CNPJ’╝łń©ÄÕŗÖńÖ╗Ķ©śńĢ¬ÕÅĘ’╝ēÕÅ¢ÕŠŚ’╝Ü2002Õ╣┤õ╗źķÖŹŃĆüÕż¢ÕøĮĶ│ćµ£¼Ńü«õ╝üµźŁŃéÆŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü½Ķ©Łń½ŗŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃééŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ń©ÄÕŗÖńÖ╗Ķ©śńĢ¬ÕÅĘŃĆīCNPJ’╝łCadastro Nacional da Pessoa Jur├Łdica’╝ēŃĆŹŃéÆÕÅ¢ÕŠŚŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃéēŃü«Ķ”üõ╗ČŃü»ŃĆüÕŹśŃü¬ŃéŗµēŗńČÜŃüŹõĖŖŃü«ÕĮóÕ╝ÅŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü»ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ÕĮōÕ▒ĆŃüīÕż¢ÕøĮµŖĢĶ│ćÕ«ČŃéÆÕøĮÕåģµ│ĢõĮōń│╗Ńü«õĖŗŃü½µśÄńó║Ńü½õĮŹńĮ«ŃüźŃüæŃĆüŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ŃéÆŃéłŃéŖÕÄ│µĀ╝Ńü½ń«ĪńÉåŃüŚŃéłŃüåŃü©ŃüÖŃéŗµäÅÕø│Ńü«ĶĪ©ŃéīŃü©Ķ¦ŻķćłŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéµ│ĢÕ«Üõ╗ŻńÉåõ║║Ńü«ńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃü»ŃĆüµĄĘÕż¢Ńü«Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃü½õ╗ŻŃéÅŃéŖŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ÕøĮÕåģŃü¦µ│ĢńÜäŃü¬Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüåń¬ōÕÅŻŃéÆńó║õ┐ØŃüÖŃéŗńø«ńÜäŃüīŃüéŃéŗŃü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüĶ”¬õ╝ÜńżŠŃü½CNPJÕÅ¢ÕŠŚŃéÆńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½µö┐Õ║£Ńü»Ķ”¬õ╝ÜńżŠŃü©ÕŁÉõ╝ÜńżŠŃü«ķ¢óõ┐éŃéÆń©ÄÕŗÖõĖŖŃĆüŃéłŃéŖÕÄ│µĀ╝Ńü½ń«ĪńÉåŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü»ŃĆüŃüōŃü«ńŗ¼Ķć¬Ńü«Ķ”üõ╗ČŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüŚŃĆüõ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗŃü«ÕłØµ£¤µ«ĄķÜÄŃüŗŃéēńÅŠÕ£░Ńü«Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ńéäõ╝ÜĶ©łÕŻ½Ńü©ķĆŻµÉ║ŃüŚŃĆüÕ┐ģĶ”üŃü¬µēŗńČÜŃüŹŃéƵ╝ÅŃéīŃü¬ŃüÅķĆ▓ŃéüŃéŗŃüōŃü©ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüĶ”¬õ╝ÜńżŠŃü«ńÖ╗Ķ©śń░┐Ķ¼äµ£¼Ńéäիܵ¼ŠŃü«Õģ¼Ķ©╝Ńā╗Ķ¬ŹĶ©╝ŃĆüŃüØŃüŚŃü”ŃāØŃā½ŃāłŃé¼Ńā½Ķ¬×ŃüĖŃü«Õģ¼ńÜäń┐╗Ķ©│Ńü¬Ńü®ŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃüīõĖŹµģŻŃéīŃü¬µēŗńČÜŃüŹŃüīÕżÜŃüÅÕŁśÕ£©ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüÕ░éķ¢ĆÕ«ČŃü«ŃéĄŃāØŃā╝ŃāłŃü»Õ┐ģķĀłŃü©Ķ©ĆŃüłŃüŠŃüÖŃĆé
ÕŖ┤ÕāŹĶĆģõ┐ØĶŁĘŃéÆÕ╝ĘŃüÅÕ┐ŚÕÉæŃüÖŃéŗŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ÕŖ┤ÕāŹµ│ĢÕłČ
ÕŖ┤ÕāŹµ│Ģ’╝łCLT’╝ēŃü«µŁ┤ÕÅ▓ńÜäĶāīµÖ»
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ÕŖ┤ÕāŹµ│ĢŃü»ŃĆü1943Õ╣┤Ńü½ÕłČÕ«ÜŃüĢŃéīŃü¤ŃĆīConsolida├¦├Żo das Leis do Trabalho’╝łCLT’╝ēŃĆŹŃüīµĀ╣Õ╣╣Ńü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéCLTŃü»ŃĆüÕłČÕ«ÜÕĮōµÖéŃüŗŃéēÕŖ┤ÕāŹĶĆģõ┐ØĶŁĘŃéÆÕ╝ĘŃüÅÕ┐ŚÕÉæŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕŖ┤õĮ┐Õ»Šń½ŗŃü«ńĘ®ÕÆīŃéäÕĘźµźŁÕī¢Ńü«µÄ©ķĆ▓ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüØŃü«µĆصā│Ńü»ķĢĘŃéēŃüÅÕżēŃéÅŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü1990Õ╣┤õ╗źķÖŹŃü«ńĄīµĖłĶć¬ńö▒Õī¢Ńü©Ńé░ŃāŁŃā╝ŃāÉŃā½Õī¢Ńü«õĖŁŃü¦ŃĆüŃüØŃü«ńĪ¼ńø┤µĆ¦ŃüīńĄīµĖłµłÉķĢĘŃéÆķś╗Õ«│ŃüÖŃéŗŃĆīŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńé│Ńé╣ŃāłŃĆŹŃü«õĖĆŃüżŃü©ŃüŚŃü”µē╣ÕłżŃü½µÖÆŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃüåŃüŚŃü¤ĶāīµÖ»ŃüŗŃéēŃĆü2017Õ╣┤Ńü½Ńü»Õż¦Õ╣ģŃü¬µö╣µŁŻŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃĆüÕĆŗÕłźŃü«ÕŖ┤ÕāŹÕźæń┤äŃéäÕŖ┤ÕāŹÕŹöń┤äŃüīµ│ĢÕŠŗŃü½Õä¬ÕģłŃüÖŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŗŃü¬Ńü®ŃĆüõĖĆķā©Ńü¦ÕŖ┤ÕāŹµØĪõ╗ČŃü«µ¤öĶ╗¤Õī¢ŃüīķĆ▓Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
Ķ¦ŻķøćÕłČÕ║”
µŚźµ£¼Ńü«ÕŖ┤ÕāŹÕźæń┤äµ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüÕ«óĶ”│ńÜäŃü½ÕÉłńÉåńÜäŃü¬ńÉåńö▒ŃéƵ¼ĀŃüŹŃĆüńżŠõ╝ÜķĆÜÕ┐ĄõĖŖńøĖÕĮōŃü©Ķ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü¬ŃüäĶ¦ŻķøćŃü»ńäĪÕŖ╣Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõĖƵ¢╣ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü»ŃĆüµŁŻÕĮōŃü¬ńÉåńö▒ŃüīŃü¬ŃüäĶ¦Żķøć’╝łõĖŹÕĮōĶ¦Żķøć’╝ēŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüķøćńö©õĖ╗ŃüīŃĆīÕŗżńČÜÕ╣┤µĢ░õ┐ØĶ©╝Õ¤║ķćæ’╝łFGTS’╝ēŃĆŹŃü«µ«ŗķ½śŃü½40%Ńü«Ķ┐ĮÕŖĀńĮ░ķćæŃéÆõĖŖõ╣ŚŃüøŃüŚŃü”µö»µēĢŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«FGTSÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ķĆĆĶüĘķćæÕłČÕ║”Ńü©Ńü»Õģ©ŃüÅńĢ░Ńü¬ŃéŗµĆ¦Ķ│¬ŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü¦Ńü»õ╝üµźŁŃüīķĆĆĶüĘķćæÕłČÕ║”ŃéÆõ╗╗µäÅŃü¦Ķ©ŁŃüæŃĆüķĆĆĶüʵÖéŃü½µö»µēĢŃüåŃüōŃü©ŃüīõĖĆĶł¼ńÜäŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü»ŃĆüķøćńö©õĖ╗Ńüīµ»Äµ£łŃĆüÕŖ┤ÕāŹĶĆģŃü«ńĄ”õĖÄŃü«õĖĆÕ«ÜÕē▓ÕÉłŃéÆFGTSÕÅŻÕ║¦Ńü½Õ╝ĘÕłČńÜäŃü½ń®ŹŃü┐ń½ŗŃü”ŃéŗŃüōŃü©ŃüīńŠ®ÕŗÖõ╗śŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃüŚŃü”ŃĆüµŁŻÕĮōŃü¬ńÉåńö▒Ńü«Ńü¬ŃüäĶ¦ŻķøćŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüķøćńö©õĖ╗Ńü»µŚóŃü½ń®ŹŃü┐ń½ŗŃü”Ńü¤ķćæķĪŹŃü©Ńü»ÕłźŃü½ŃĆüFGTSÕÅŻÕ║¦Ńü«ńĘŵ«ŗķ½śŃü«40%Ńü½ńøĖÕĮōŃüÖŃéŗĶ┐ĮÕŖĀĶ▓╗ńö©ŃéƵö»µēĢŃüåŃüōŃü©ŃüīĶ”üµ▒éŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ŃĆīFGTSŃü«40%ńĮ░ķćæŃĆŹŃü»ŃĆüõ║║ÕōĪŃü«µ¢░ķÖ│õ╗ŻĶ¼ØŃéÆÕø│ŃéŗķÜøŃü«Õż¦ŃüŹŃü¬ķÜ£ÕŻüŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüõ╝üµźŁŃü½Ķ¦ŻķøćŃéÆŃü¤ŃéüŃéēŃéÅŃüøŃéŗÕŖ╣µ×£ŃéÆńö¤Ńü┐Õć║ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ŃüĖŃü«ķĆ▓Õć║ŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗõ╝üµźŁŃüīŃĆüõ║║ÕōĪĶ©łńö╗Ńéäõ║ŗµźŁµÆżķĆĆŃü«ÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗõĖŖŃü¦ŃĆüµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¬Ķ”üń┤ĀŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéÕ«ēµśōŃü¬õ║║ÕōĪÕēŖµĖøŃü»ķćŹÕż¦Ńü¬Ķ▓ĪÕŗÖŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆõ╝┤ŃüåŃü¤ŃéüŃĆüµÄĪńö©ŃüŗŃéēµģÄķćŹŃü¬Ķ©łńö╗Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃü¬ŃüŖŃĆüµć▓µłÆĶ¦Żķøć’╝łµŁŻÕĮōŃü¬ńÉåńö▒Ńü«ŃüéŃéŗĶ¦Żķøć’╝ēŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃü»Ķ¦Żķøćõ║łÕæŖµēŗÕĮōŃéäFGTSŃü«Õ╝ĢŃüŹÕć║ŃüŚŃĆü40%Ńü«ńĮ░ķćæŃü¬Ńü®ŃéÆÕÅŚŃüæÕÅ¢Ńéŗµ©®Õł®ŃéÆÕż▒ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃüØŃü«Ķ”üõ╗ČŃü»CLTń¼¼482µØĪŃü½ÕÄ│µĀ╝Ńü½Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
ŃüØŃü«õ╗¢Ńü«ÕŖ┤ÕāŹµØĪõ╗Č
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü»ŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃü½Ńü»ÕŗżńČÜ12Ńāȵ£łŃü¦30µŚźķ¢ōŃü«Õ╣┤µ¼Īµ£ēńĄ”õ╝æµÜćŃüīõ╗śõĖÄŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«Õ╣┤ķ¢ōµ£ēńĄ”õ╝æµÜćõ╗śõĖĵŚźµĢ░’╝łµ£ĆÕż¦20µŚź’╝ēŃü©µ»öŃü╣Ńü”ÕżÜŃüäŃü«Ńüīńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆéµ£ēńĄ”õ╝æµÜćŃü»µ¼ĀÕŗżµŚźµĢ░Ńü½ŃéłŃüŻŃü”µŚźµĢ░ŃüīÕżēÕŗĢŃüÖŃéŗõ╗ĢńĄäŃü┐Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃĆü1Õ╣┤ķ¢ōŃü«µ¼ĀÕŗżŃüī5Õø×õ╗źõĖŗŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃü»30µŚźŃĆü24Õø×ŃüŗŃéē32Õø×Ńü«µ¼ĀÕŗżŃüīŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»12µŚźķ¢ōŃü½µĖøŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ń©Äµ│ĢŃü©Ķ│ćķćæµ▒║µĖłµ│Ģ

ķĆŻķé”Ńā╗ÕĘ×Ńā╗ÕĖéńö║µØæń©ÄŃü½ŃéłŃéŗń©ÄÕłČÕ║”
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ń©ÄÕłČŃü»ŃĆüķĆŻķé”ŃĆüÕĘ×ŃĆüÕĖéńö║µØæŃüīŃüØŃéīŃü×Ńéīń©ÄŃéÆĶ¬▓ŃüÖŃü©ŃüäŃüåķØ×ÕĖĖŃü½ĶżćķøæŃü¬µ¦ŗķĆĀŃéƵīüŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«ń©ÄÕłČŃüīÕøĮń©ÄŃü©ŃüŚŃü”õĖƵ£¼Õī¢ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü©Ńü»Õ»Šńģ¦ńÜäŃü¦ŃüÖŃĆé
õĖ╗Ķ”üŃü¬ń©ÄķćæŃü½Ńü»ŃĆüÕ«¤Ķ│¬Õł®ńøŖŃü½Ķ¬▓ń©ÄŃüĢŃéīŃéŗµ│Ģõ║║µēĆÕŠŚń©Ä’╝łIRPJ’╝ēŃü©ŃĆüµ│Ģõ║║Õł®ńøŖŃü½Ķ¬▓ŃüĢŃéīŃéŗńżŠõ╝ÜĶ▓Āµŗģķćæ’╝łCSLL’╝ēŃüīŃüéŃéŖŃĆüŃüōŃéīŃéēŃéÆÕÉłŃéÅŃüøŃü¤Õ«¤Ķ│¬ńÜäŃü¬µ│Ģõ║║ń©ÄńÄćŃü»ŃĆüÕżÜŃüÅŃü«õ╝üµźŁŃü¦34%Ńü½ķüöŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ńü╗ŃüŗŃĆüÕĘźµźŁĶŻĮÕōüŃü«ķĆÜķ¢óŃéäĶŻĮķĆĀµ¢ĮĶ©ŁŃüŗŃéēŃü«µÉ¼Õć║µÖéŃü½Ķ¬▓ń©ÄŃüĢŃéīŃéŗÕĘźµźŁĶŻĮÕōüń©Ä’╝łIPI’╝ēŃéäŃĆüõ╝üµźŁŃü«ńĘÅÕÅÄÕģźŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ķ¬▓ń©ÄŃüĢŃéīŃéŗńżŠõ╝ÜńĄ▒ÕÉłÕ¤║ķćæ’╝łPIS’╝ēŃüŖŃéłŃü│ńżŠõ╝Üõ┐ØķÖ║Ķ׏Ķ│ćĶ▓Āµŗģķćæ’╝łCOFINS’╝ēŃü¬Ńü®ŃĆüÕżÜÕ▓ÉŃü½ŃéÅŃü¤Ńéŗń©ÄķćæŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«ÕżÜÕ▒żńÜäŃü¬ń©ÄÕłČŃü»ŃĆüÕŹśŃü½ń©ÄńÄćŃüīķ½śŃüäŃü©ŃüäŃüåÕĢÅķĪīŃü½ńĢÖŃüŠŃéēŃüÜŃĆüńĄīńÉåŃā╗ń©ÄÕŗÖŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ńü«ĶżćķøæŃüĢŃéÆÕŖćńÜäŃü½ÕóŚÕż¦ŃüĢŃüøŃĆüÕż¢ÕøĮõ╝üµźŁŃü½õ║łµ£¤ŃüøŃü¼ĶĪīµö┐Ńé│Ńé╣ŃāłŃéäŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéõ╝üµźŁŃü»ŃĆüÕŹśõĖĆŃü«ń©Äµ│ĢŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüĶżćµĢ░Ńü«ń«ĪĶĮäÕī║Õ¤¤Ńü«ńĢ░Ńü¬Ńéŗń©Äµ│ĢŃü©Ķ”ÅÕłČŃéÆÕÉīµÖéŃü½ķüĄÕ«łŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüńĄīńÉåŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃü«µ¦ŗń»ēŃĆüń©ÄÕŗÖńö│ÕæŖŃĆüńøŻµ¤╗ŃĆüŃüØŃüŚŃü”Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ń«ĪńÉåŃüīķØ×ÕĖĖŃü½ńģ®ķøæŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½PIS/COFINSŃü«ŃéłŃüåŃü¬õ╗śÕŖĀõŠĪÕĆżń©ÄńÜäŃü¬µĆ¦µĀ╝ŃéƵīüŃüżń©ÄķćæŃü»ŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢŃüöŃü©Ńü½ńĢ░Ńü¬ŃéŗĶ©łń«ŚŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀµŖĢĶ│ćŃéäÕ░éķ¢Ćõ║║µØÉŃü«ńó║õ┐ØŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼õ╝üµźŁŃü»ŃĆüõ║ŗµźŁĶ©łńö╗µ«ĄķÜÄŃüŗŃéēŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ń©ÄÕŗÖÕ░éķ¢ĆÕ«ČŃü©Õ»åŃü½ķĆŻµÉ║ŃüŚŃĆüŃü®Ńü«ÕĘ×Ńü¦õ║ŗµźŁŃéÆÕ▒Ģķ¢ŗŃüÖŃéŗŃüŗŃĆüŃü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬ń┤Źń©Äµ¢╣Õ╝ÅŃéÆķüĖµŖ×ŃüÖŃéŗŃüŗŃü©ŃüäŃüŻŃü¤µł”ńĢźńÜäŃü¬µäŵĆص▒║Õ«ÜŃéÆĶĪīŃüåÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ń¦╗Ķ╗óõŠĪµĀ╝ń©ÄÕłČ
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü»ķĢĘŃéēŃüÅŃĆüńĄīµĖłÕŹöÕŖøķ¢ŗńÖ║µ®¤µ¦ŗ’╝łOECD’╝ēŃü«ńŗ¼ń½ŗõ╝üµźŁÕĤÕēć’╝łArm’s Length Principle’╝ēŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗńŗ¼Ķć¬Ńü«ń¦╗Ķ╗óõŠĪµĀ╝ń©ÄÕłČŃéƵÄĪńö©ŃüŚŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüÕżÜŃüÅŃü«µŚźµ£¼õ╝üµźŁŃéÆÕɽŃéĆÕż¢ÕøĮõ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüń©ÄÕŗÖŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü©Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣õĖŖŃü«Ķ¬▓ķĪīŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüń▒│ÕøĮŃü¬Ńü®Ńü¦Ńü«Õż¢ÕøĮń©ÄķĪŹµÄ¦ķÖżŃü«Ķ¬ŹĶŁśŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗÕż¦ŃüŹŃü¬ķÜ£ÕŻüŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ķĆŻķ锵Ł│ÕģźÕ║üŃü©OECDŃü©Ńü«µĢ░Õ╣┤Ńü½ŃéÅŃü¤ŃéŗÕģ▒ÕÉīõĮ£µźŁŃéÆńĄīŃü”ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü»2024Õ╣┤1µ£ł1µŚźŃüŗŃéēŃĆüOECDŃü«ÕĤÕēćŃü½µ║¢µŗĀŃüŚŃü¤µ¢░ń¦╗Ķ╗óõŠĪµĀ╝ń©ÄÕłČŃéÆÕ╝ĘÕłČķü®ńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Õż¦µö╣µŁŻŃü»ŃĆüÕŹśŃü¬Ńéŗń©ÄÕłČÕżēµø┤Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ŃüīÕøĮķÜøńÜäŃü¬ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Ķ”Åń»äŃü½ķü®ÕÉłŃüŚŃĆüŃéłŃéŖŃé░ŃāŁŃā╝ŃāÉŃā½Ńü¬µŖĢĶ│ćŃéÆĶ¬śĶć┤ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ÕøĮÕ«Čµł”ńĢźŃü«õĖĆńÆ░Ńü©Ķ¦ŻķćłŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéµ¢░µ│ĢŃü«ńø«ńÜäŃü½Ńü»ŃĆüõ║īķćŹĶ¬▓ń©ÄŃü©õ║īķćŹķØ×Ķ¬▓ń©ÄŃü«Õø×ķü┐ŃéäŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«Ńé░ŃāŁŃā╝ŃāÉŃā½ńĄīµĖłÕĤÕēćŃüĖŃü«ÕÅéÕŖĀõ┐āķĆ▓Ńü¬Ńü®ŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«µö╣µŁŻŃü»ŃĆüÕŠōµØźŃü«ÕłČÕ║”ŃüīķĆåŃü½Õż¢ÕøĮõ╝üµźŁŃü«ķĆ▓Õć║µäŵ¼▓ŃéÆÕēŖŃüÄŃĆüÕøĮķÜøńÜäŃü¬µæ®µō”ŃéÆńö¤Ńü┐Õć║ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃéÆŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½µö┐Õ║£ŃüīĶ¬ŹĶŁśŃüŚŃü¤ńĄÉµ×£Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéµ¢░µ│ĢŃüĖŃü«ń¦╗ĶĪīŃü»ŃĆüń¤Łµ£¤ńÜäŃü¬ń©ÄÕÅÄŃéłŃéŖŃééŃĆüķĢʵ£¤ńÜäŃü¬Õż¢ÕøĮµŖĢĶ│ćŃü«ÕóŚÕŖĀŃü©ŃĆüÕøĮķÜøńżŠõ╝ÜŃü¦Ńü«õ┐ĪķĀ╝µĆ¦ÕÉæõĖŖŃéÆÕä¬ÕģłŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåµł”ńĢźńÜäÕłżµ¢ŁŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüµŚźµ£¼õ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½õ║ŗµźŁŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕøĮķÜøń©ÄÕŗÖŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆń«ĪńÉåŃüŚŃéäŃüÖŃüÅŃü¬ŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīÕć║Ńü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüµ¢░Ńā½Ńā╝Ńā½ŃüĖŃü«ń¦╗ĶĪīŃü½õ╝┤Ńüåµ¢░Ńü¤Ńü¬Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣Ķ”üõ╗Č’╝łµ¢ćµøĖÕī¢ŃĆüĶ¬┐µĢ┤µēŗńČÜŃüŹŃü¬Ńü®’╝ēŃü½Ķ┐ģķƤŃü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ķ│ćķćæµ▒║µĖłµ│ĢŃü©Pix
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½õĖŁÕż«ķŖĆĶĪīŃüī2020Õ╣┤Ńü½Õ░ÄÕģźŃüŚŃü¤Ńā¬ŃéóŃā½Ńé┐ŃéżŃāĀµ▒║µĖłŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃĆīPixŃĆŹŃü»ŃĆüĶ┐ģķƤŃüŗŃüżµēŗµĢ░µ¢ÖńäĪµ¢ÖŃü«Õł®õŠ┐µĆ¦ŃüŗŃéēµĆźķƤŃü½µÖ«ÕÅŖŃüŚŃĆüõ╗ŖŃéäŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ÕøĮÕåģŃü«õĖ╗Ķ”üŃü¬µ▒║µĖłµēŗµ«ĄŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé2024Õ╣┤ń¼¼2ÕøøÕŹŖµ£¤Ńü½Ńü»ŃĆüµ▒║µĖłŃéĘŃé¦ŃéóŃü«45%ŃéÆÕŹĀŃéüŃĆüŃé»Ńā¼ŃéĖŃāāŃāłŃé½Ńā╝ŃāēŃéäŃāćŃāōŃāāŃāłŃé½Ńā╝ŃāēŃéÆÕż¦ŃüŹŃüÅõĖŖÕø×ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼õ╝üµźŁŃüīŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦ECŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Ńü¬Ńü®ŃéÆÕ▒Ģķ¢ŗŃüÖŃéŗķÜøŃü½Ńü»ŃĆüŃüōŃü«PixŃüĖŃü«Õ»ŠÕ┐£ŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüµÜŚÕÅĘĶ│ćńöŻŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃééŃĆüµ▒║µĖłµēŗµ«ĄŃü©ŃüŚŃü”Ńü«µ│ĢńÜäµĀ╣µŗĀŃüīõĖÄŃüłŃéēŃéīŃĆüõĖŁÕż«ķŖĆĶĪīŃü½ŃéłŃéŗńøŻńØŻŃüīõ║łÕ«ÜŃüĢŃéīŃéŗŃü¬Ńü®ŃĆüĶ”ÅÕłČńÆ░ÕóāŃüīµĢ┤ÕéÖŃüĢŃéīŃüżŃüżŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«µ¢░Ńü¤Ńü¬ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ķĀśÕ¤¤Ńü©Ķ©▒Ķ¬ŹÕÅ»Ńā╗Ķ”ÅÕłČ
ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒õ┐ØĶŁĘµ│Ģ’╝łLGPD’╝ē
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒õ┐ØĶŁĘµ│ĢŃĆīLei Geral de Prote├¦├Żo de Dados’╝łLGPD’╝ēŃĆŹŃü»ŃĆüEUŃü«GDPRŃü½Õ╝ĘŃüäÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŚŃüæŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüµŚźµ£¼Ńéäń▒│ÕøĮŃéłŃéŖŃééÕÄ│ŃüŚŃüäÕåģÕ«╣Ńü©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéLGPDŃü»ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½ÕøĮÕåģŃü¦ÕĆŗõ║║ŃāćŃā╝Ńé┐Ńü«Õć”ńÉåŃüīĶĪīŃéÅŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½ÕøĮÕåģŃü«ÕĆŗõ║║ŃéÆÕ»ŠĶ▒ĪŃü©ŃüÖŃéŗÕĢåÕōüŃā╗ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«µÅÉõŠøŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüÖŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½ķü®ńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆ鵌źµ£¼Ńü«ÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒õ┐ØĶŁĘµ│ĢŃüīŃĆüŃüØŃéīÕŹśõĮōŃü¦Ńü»ÕĆŗõ║║ŃéÆńē╣Õ«ÜŃü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃé»ŃāāŃéŁŃā╝Ńü¬Ńü®ŃéÆÕĆŗõ║║µāģÕĀ▒Ńü©ŃüŚŃü”µē▒ŃéÅŃü¬ŃüäŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŗŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüLGPDŃü»ŃéłŃéŖÕÄ│µĀ╝Ńü¬Õ¤║µ║¢ŃéÆĶ©ŁŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
LGPDŃü½ķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«ńĮ░ÕēćŃü»ŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü«Õ╣┤ķ¢ōÕŻ▓õĖŖķ½śŃü«2%õ╗źÕåģŃĆüŃüŠŃü¤Ńü»õĖŖķÖÉ5,000õĖćŃā¼ŃéóŃā½’╝łń┤ä15ÕääÕåå’╝ēŃü«ŃüäŃüÜŃéīŃüŗķ½śŃüäµ¢╣Ńü©Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüGDPRŃü«ńĮ░ķćæŃéłŃéŖŃü»Õ░æŃü¬ŃüäŃééŃü«Ńü«ŃĆüķ½śķĪŹŃü¬ÕłČĶŻüķćæŃüīĶ¬▓ŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé┬Ā
Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃā╗Õī╗ńÖéµ®¤ÕÖ©ķ¢óķĆŻµ│Ģ’╝łANVISA’╝ē
µŚźµ£¼Ńü«Ķ¢¼µ®¤µ│ĢŃü½ńøĖÕĮōŃüÖŃéŗŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«Õī╗Ķ¢¼ÕōüŃā╗Õī╗ńÖéµ®¤ÕÖ©ķ¢óķĆŻµ│ĢŃü»ŃĆüÕøĮÕ«ČĶĪøńö¤ńøŻńØŻÕ║ü’╝łAg├¬ncia Nacional de Vigil├óncia Sanit├Īria’╝ÜANVISA’╝ēŃüīń«ĪĶĮäŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«ÕłåķćÄŃü¦Ńü«õ║ŗµźŁÕ▒Ģķ¢ŗŃü½Ńü»ŃĆüANVISAŃü«Ķ©▒Ķ¬ŹÕÅ»’╝łANVISAŃā®ŃéżŃé╗Ńā│Ńé╣’╝ēŃü«ÕÅ¢ÕŠŚŃüīõĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüÖŃĆé
ANVISAŃü«Ķ”ÅÕłČŃü»ŃĆüÕŹśŃü½ĶŻĮÕōüŃü«Õ«ēÕģ©µĆ¦ŃéÆÕ»®µ¤╗ŃüÖŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüÕż¢ÕøĮõ╝üµźŁŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½ÕøĮÕåģŃü½µüÆõ╣ģńÜäŃü¬µ│ĢńÜäõĖ╗õĮōŃéÆńó║ń½ŗŃüŚŃĆüŃā¬Ńé╣Ńé»Ńü½Õ┐£ŃüśŃü¤ÕÄ│µĀ╝Ńü¬µēŗńČÜŃüŹŃéÆĶĖÅŃéĆŃüōŃü©ŃéÆĶ”üµ▒éŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü½µŗĀńé╣ŃéÆńĮ«ŃüŗŃü¬ŃüäÕż¢ÕøĮŃü«Õī╗ńÖéµ®¤ÕÖ©ĶŻĮķĆĀµźŁĶĆģŃü»ŃĆüÕ┐ģŃüÜŃĆīBrazil Registration Holder’╝łBRH’╝ēŃĆŹŃéƵīćÕÉŹŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéBRHŃü»ŃĆüANVISAŃü©Ńü«ķĆŻńĄĪń¬ōÕÅŻŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüµ®¤ÕÖ©ńÖ╗ķī▓ŃéÆń«ĪńÉåŃüŚŃĆüĶŻĮķĆĀµźŁĶĆģŃü½õ╗ŻŃéÅŃüŻŃü”ANVISAŃü«Õ«¤Õ£░ńøŻµ¤╗Ńü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗĶ▓¼õ╗╗ŃéÆĶ▓ĀŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüANVISAŃüīńē®ńÉåńÜäŃü¬µŗĀńé╣ŃéÆõ╝┤ŃüåµśÄńó║Ńü¬Ķ▓¼õ╗╗õĖ╗õĮōŃéÆÕøĮÕåģŃü½µ▒éŃéüŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéĶ▓®ÕŻ▓õ╗ŻńÉåÕ║ŚŃü©Ńü»ńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤ń¼¼õĖēĶĆģŃéÆBRHŃü½µīćÕÉŹŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīµÄ©Õź©ŃüĢŃéīŃéŗńé╣ŃüŗŃéēŃééŃĆüÕĮōÕ▒ĆŃüīĶ▓¼õ╗╗Ńü«µēĆÕ£©ŃéƵśÄńó║Ńü½ŃüŚŃü¤ŃüäŃü©ŃüäŃüåµäÅÕø│ŃüīĶ”ŗŃü”ÕÅ¢ŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ĶŻĮÕōüŃü»Ńā¬Ńé╣Ńé»ÕłåķĪ×ŃüĢŃéīŃĆüõĮÄŃā¬Ńé╣Ńé»’╝łŃé»Ńā®Ńé╣ŌģĀ/ŌģĪ’╝ēŃü»ŃĆīķĆÜń¤ź’╝łNotifica├¦├Żo’╝ēŃĆŹŃĆüķ½śŃā¬Ńé╣Ńé»’╝łŃé»Ńā®Ńé╣Ōģó/ŌģŻ’╝ēŃü»ŃĆīńÖ╗ķī▓’╝łRegistro’╝ēŃĆŹŃü©ŃüäŃüåńĢ░Ńü¬ŃéŗµēŗńČÜŃüŹŃüīÕ┐ģĶ”üŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéķ½śŃā¬Ńé╣Ńé»ĶŻĮÕōüŃü«ńÖ╗ķī▓Ńü»10Õ╣┤ķ¢ōŃü¦µ£¤ķÖÉŃüīÕłćŃéīŃüŠŃüÖŃüīŃĆüõĮÄŃā¬Ńé╣Ńé»ĶŻĮÕōüŃü»µ£¤ķÖÉŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃüōŃü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃāÖŃā╝Ńé╣Ńü«Ķ¬ŹĶ©╝ÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüÕ«ēÕģ©µĆ¦Ńü«ķ½śŃüäĶŻĮÕōüŃü½Ńü»Ķ┐ģķƤŃü¬ÕĖéÕĀ┤µŖĢÕģźŃéÆõ┐āŃüÖõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüķ½śŃā¬Ńé╣Ńé»ĶŻĮÕōüŃü½Ńü»ķĢʵ£¤Ńü½ŃéÅŃü¤ŃéŗÕÄ│µĀ╝Ńü¬Õ»®µ¤╗ŃéÆĶ¬▓ŃüÖŃééŃü«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüµÖéķ¢ōŃü©Ńé│Ńé╣ŃāłŃéÆĶ”üŃüÖŃéŗµēŗńČÜŃüŹŃéÆĶ”üµ▒éŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüÕī╗ńÖéŃā╗ŃāśŃā½Ńé╣Ńé▒ŃéóÕłåķćÄŃü¦Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½ķĆ▓Õć║ŃéƵż£Ķ©ÄŃüÖŃéŗõ╝üµźŁŃü»ŃĆüõ║ŗµźŁµł”ńĢźŃü«ÕłØµ£¤µ«ĄķÜÄŃüŗŃéēBRHŃü«ķüĖÕ«ÜŃü©ĶŻĮÕōüŃü«µŁŻńó║Ńü¬Ńā¬Ńé╣Ńé»ÕłåķĪ×ŃéÆĶĪīŃüäŃĆüķĢʵ£¤ńÜäŃü¬ńÖ╗ķī▓Ķ©łńö╗ŃéÆń½ŗŃü”ŃéŗÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
AIµŖĆĶĪōŃü©Õ║āÕæŖĶ”ÅÕłČŃü«ÕŗĢÕÉæ
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü¦Ńü»ŃĆüEUŃü«AIĶ”ÅÕłČŃü½ķĪ×õ╝╝ŃüŚŃü¤ŃĆīŃā¬Ńé╣Ńé»ŃāÖŃā╝Ńé╣ŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃĆŹŃéƵÄĪńö©ŃüÖŃéŗAIĶ”ÅÕłČµ│ĢµĪłŃüīŃĆüõĖŖķÖóŃü¦µē┐Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃĆüńÅŠÕ£©ŃĆüõĖŗķÖóŃü¦Õ»®ĶŁ░ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«µ│ĢµĪłŃü»ŃĆüķüÄÕ║”Ńü¬Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéƵīüŃüżAIŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃéÆń”üµŁóŃüŚŃĆüķ½śŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃü½Ńü»Ķ┐ĮÕŖĀŃü«Õ«ēÕģ©Ķ”üõ╗ČŃéÆĶ¬▓ŃüÖŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüAIŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃü«õĮ┐ńö©ĶĆģŃüīÕģ¼µŁŻµĆ¦ŃĆüķĆŵśÄµĆ¦ŃĆüńÉåĶ¦ŻŃü«Õ«╣µśōŃüĢŃéÆńó║õ┐ØŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆĶ”üµ▒éŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«ńĮ░ÕēćŃü»ŃĆüõ╝üµźŁŃü«Õ╣┤ķ¢ōÕŻ▓õĖŖķ½śŃü«2%ŃüŠŃü¤Ńü»õĖŖķÖÉ5,000õĖćŃā¼ŃéóŃā½Ńü©ŃĆüLGPDŃü©ÕÉīµ¦śŃü½ķ½śķĪŹŃü¬ÕłČĶŻüķćæŃüīĶ©ŁŃüæŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Õ║āÕæŖĶ”ÅÕłČŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüCONAR’╝łÕøĮµ░æÕ║āÕæŖĶć¬õĖ╗Ķ”ÅÕłČĶ®ĢĶŁ░õ╝Ü’╝ēŃü©ŃüäŃüåĶć¬õĖ╗Ķ”ÅÕłČµ®¤ķ¢óŃüīõĖ╗Õ░ÄŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüńē╣Ńü½Ķ│ŁÕŹÜķ¢óķĆŻŃü«Õ║āÕæŖŃü¬Ńü®ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«ÕłåķćÄŃü½Ķ®│ń┤░Ńü¬Ķ”ÅÕēćŃéÆĶ©ŁŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü
Ńā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«µ│ĢÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüķĆŻķé”ÕłČŃü«ÕżÜÕ▒żµĆ¦ŃĆüÕŖ┤ÕāŹĶĆģõ┐ØĶŁĘŃéÆÕ╝ĘŃüÅÕ┐ŚÕÉæŃüÖŃéŗµ│ĢõĮōń│╗ŃĆüŃüØŃüŚŃü”ńĄČŃüłŃüÜÕżēÕī¢ŃüÖŃéŗń©ÄÕłČŃéäµ¢░µŖĆĶĪōŃüĖŃü«Ķ”ÅÕłČŃü¬Ńü®ŃĆüµŚźµ£¼Ńü«ŃüØŃéīŃü©Ńü»ÕżÜŃüÅŃü«ńé╣Ńü¦ńĢ░Ńü¬ŃéŖŃĆüńē╣Ńü½µ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéõ╝ÜńżŠĶ©Łń½ŗŃüŗŃéēŃĆüÕŖ┤ÕāŹĶĆģŃü«ķøćńö©ŃĆüń©ÄÕŗÖŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣ŃĆüŃüØŃüŚŃü”ń┤øõ║ēÕ»ŠÕ┐£Ńü½Ķć│ŃéŗŃüŠŃü¦ŃĆüõ║łµ£¤ŃüøŃü¼Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéäĶ¬▓ķĪīŃü½ńø┤ķØóŃüÖŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«µ│ĢńÜäńē╣µĆ¦ŃéÆõ║ŗÕēŹŃü½µĘ▒ŃüÅńÉåĶ¦ŻŃüŚŃĆüķü®ÕłćŃü¬Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü«ÕŖ®Ķ©ĆŃéÆÕŠŚŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéƵ£ĆÕ░ÅķÖÉŃü½µŖæŃüłŃĆüŃā¢Ńā®ŃéĖŃā½Ńü«ÕĘ©Õż¦Ńü¬ÕĖéÕĀ┤Ńü¦µłÉÕŖ¤ŃéÆÕÅÄŃéüŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕÅ»ĶāĮŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ