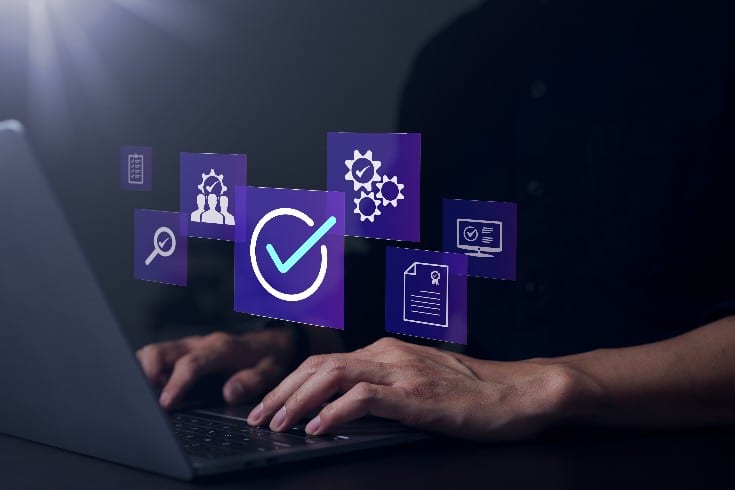セルビア共和国の法律の全体像とその概要を弁護士が解説

セルビア(正式名称、セルビア共和国)は、バルカン半島の中央に位置する内陸国であり、近年、欧州における重要なビジネス拠点としての地位を確立しつつあります。外務省のデータによると、同国は2014年に欧州連合(EU)加盟交渉を開始し、現在も加盟に向けて法制度の整備を精力的に進めています。この取り組みは、EUの厳格な基準に合わせた法改正を促しており、投資家にとって予測可能性の高い法的環境を形成しています。また、近年では経済成長が顕著であり、特に情報通信技術(IT)分野においては、優秀な人材と競争力のある賃金水準を背景に、活発な投資が続いています。
セルビアの法制度は、日本と同様に大陸法系(Civil Law System)を基本とし、成文化された制定法を中心に法体系が構築されています。このため、日本企業にとって、民法や会社法の基本的な概念は理解しやすいものです。しかし、その歴史的背景、特に旧ユーゴスラビア連邦の解体という独自の過程を経て発展した点や、EU加盟に向けた大規模な法改正が進行中である点は、日本の法体系と異なる重要な特徴です。
本記事では、これらの点を踏まえ、セルビアへのビジネス展開を検討する上で不可欠な法律知識を、日本法との比較を交えながら体系的に解説します。
この記事の目次
セルビアの法体系と司法制度の全体像
日本との比較から見る法体系の特質
セルビアの法体系は、日本と同じく大陸法系に属し、憲法、法律、国際条約、その他の規則が主要な法源となります。2006年に国民投票を経て制定された現行憲法が最高法規であり、法体系の基礎を形成しています。
日本の法体系と比較する上で特に注目すべきは、その歴史的背景と、EU法との調和という二つの動向です。セルビアの民法典は1844年に制定され、当時のオーストリア民法典をモデルとしていました。これは、ナポレオン法典やオーストリア法典に次ぐ、ヨーロッパで3番目の民法典であり、その起源が日本と同じ大陸法系の源流に属することを示唆します。この共通の歴史的ルーツから、財産権、契約、不法行為といった基本概念は日本法と類似しているため、日本の法務実務家にとって、セルビアの契約法や債務法を理解する上でのハードルは低いと考えられます。
しかし、その後の歴史は異なります。セルビアは旧ユーゴスラビア連邦社会主義共和国という歴史を経ており、法体系には社会主義的な要素が影響を与えた時期も存在しました。この影響は、1990年代の連邦解体後に刷新され、現代的な市場経済の原則に基づく法制度へと移行しています。また、セルビアはEU加盟交渉の正式候補国であり、法制度をEU法に完全に調和させることを目指しています。このため、企業法務においては、EUの一般データ保護規則(GDPR)やEU AI法といったEUの主要法規を理解することが、セルビア法を理解する上で不可欠となります。
法源の階層構造と国際条約の優越
セルビアの法源は、最上位に「憲法(Ustav)」が位置し、次いで国会が制定する「法律(Zakon)」、政府や各省庁が制定する「政令・規則(Uredba/Pravilnik)」と続きます。日本企業にとって特筆すべき点は、セルビアが批准し公布された国際条約が、国内法の一部となり、かつ国内法(法律)に優越する効力を持つと憲法で規定されていることです。
したがって、例えば日本とセルビアとの間で締結されている「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税・租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約」(日・セルビア租税条約)などの規定は、セルビアの国内税法と矛盾する場合において、条約の規定が優先して適用されることとなります。
司法制度と裁判所の構造
セルビアの司法制度は、憲法第4条に規定される三権分立の原則に基づき、独立した地位を保障されています。日本の司法制度が裁判官の独立を基盤とするのと同様に、セルビアの裁判官も憲法と法律にのみ責任を負い、その職務執行への影響は禁止されています。
セルビアの裁判所は、一般管轄裁判所と特別管轄裁判所の2種類に大別され、それぞれが多層的な構造を形成しています。
- 一般管轄裁判所:軽微な事件を扱う基礎裁判所(Basic Courts)が第一審となり、その上級審として高等裁判所(High Courts)が位置付けられます。さらにその上には控訴裁判所(Appellate Courts)があり、最上位に位置する最高破毀裁判所(Supreme Court)が最終審を管轄します。
- 特別管轄裁判所:商事裁判所(Commercial Courts)、行政裁判所(Administrative Court)、軽犯罪裁判所(Misdemeanour Courts)など、特定の種類の紛争を専門的に扱う裁判所が存在します。
日本の裁判所制度では、商事事件は原則として地方裁判所の民事部が管轄しますが、セルビアでは商取引に関する紛争を専門的に扱う商事裁判所が独立して存在します。この専門裁判所は、会社設立に関する紛争や破産手続きなど、企業活動に特化した紛争を専門的に扱うため、商事紛争の迅速かつ専門的な解決に資すると考えられます。日本の事業者にとって、現地で取引上の紛争が生じた場合、専門的な知識を持つ裁判官によって裁かれる可能性が高いことは、複雑な国際商取引において、より予測可能で信頼性の高い紛争解決の道筋が提供されることを示唆しています。
セルビアの会社法とコーポレートガバナンス

セルビアでビジネスを展開する際の法的基盤となるのが、2011年に制定され、その後数度の改正を経てEU法との整合性を高めてきた「会社法(Law on Companies)」です。日本の会社法と比較すると、機関設計の柔軟性や設立手続きの簡素化において共通する部分が多い一方で、役員の責任範囲やマイノリティ株主の保護規定などにおいて独自の特徴が見られます。
有限会社(DOO – Društvo sa ograničenom odgovornošću)
日本企業がセルビアに進出する際、主に検討される会社形態は「有限会社(DOO)」と「株式会社(AD)」の2つです。
日本の合同会社に近い性質を持ちますが、セルビアでは最も一般的かつ支配的な会社形態であり、日本の株式会社の実質的な機能を果たしています。
- 最低資本金:100セルビア・ディナール(約1ユーロ未満)という象徴的な金額で設立が可能です。
- 特徴:出資者(社員)の持分は証券化されず、定款(設立行為書)による自治が広く認められています。閉鎖的な所有構造を維持しやすく、手続きも簡便であるため、外資系企業の子会社の大部分はこの形態を選択します。
- ガバナンス:株主総会(Assembly)と取締役(Director)が必置機関です。監査役会は任意設置となります。
株式会社(AD – Akcionarsko društvo)
多数の投資家からの資金調達や、将来的な株式上場を想定する場合に選択される形態です。
- 最低資本金:300万セルビア・ディナール(約25,000ユーロ相当)が必要です。
- 特徴:株式の発行が可能であり、より厳格な情報開示義務やコーポレートガバナンス規制が適用されます。
- ガバナンス:機関設計において、一元制または二元制の選択が可能です。公開会社(上場会社)となる場合は、より厳格な監督体制が求められます。
これらと別に、パートナーシップ(OD)や合資会社(KD)も存在しますが、出資者が無限責任を負うリスクがあるため、外国企業がこれらの形態を利用することは稀であると言えます。
会社設立手続きのデジタル化とワンストップショップ
セルビアの会社設立手続きは、「セルビア事業登録庁(SBRA:Serbian Business Registers Agency)」による一元管理(ワンストップショップ)システムが導入されており、日本と比較しても非常に迅速かつ効率的です。
- 商号の確認と予約:SBRAのオンラインシステムで希望する商号の利用可能性を確認し、予約することができます。
- 定款(設立行為書)の作成と認証:設立時における最も重要なステップです。定款には、商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、株主の構成などを記載します。この定款は、公証人(Notary Public)による認証を受ける必要があります。近年では、電子署名を用いたオンライン認証も可能となりつつあります。
- 資本金の払込み:銀行に一時的な口座を開設し、資本金を払い込みます。ただし、DOOの場合、設立登記後の払込みも認められるなど、柔軟な運用がなされています。
- SBRAへの登記申請:必要書類を添えてSBRAに登記申請を行います。この際、税務署への税籍登録(PIB取得)、健康保険基金への登録、年金・障害保険基金への登録などが同時に処理されます。
手続きが順調に進めば、申請から3〜5営業日程度で設立が完了します。これは、定款認証から法務局での登記完了まで通常1〜2週間を要する日本の実務と比較して、特筆すべきスピード感と言えるでしょう。
事業登録に関する詳細な手続きや必要書類、手数料については、セルビア事業登録庁の公式ウェブサイトで確認できます。
コーポレートガバナンス
セルビアの会社法は、企業の規模やニーズに合わせてガバナンス構造を選択できる柔軟な設計となっています。
機関設計の選択肢としては、一元制と二元制があります。
- 一元制(One-tier system):株主総会の下に、業務執行と監督の双方を担う取締役会(または単独の取締役)を設置する形態です。DOOや多くの中小規模ADで採用されており、迅速な意思決定が可能です。
- 二元制(Two-tier system):業務執行を行う取締役会(Management Board)と、その選任・解任および監督を行う監査役会(Supervisory Board)を明確に分離する形態です。ドイツ法の制度に類似しており、大規模な公開会社や、親会社による厳格なモニタリングを希望する外資系企業に適しています。
日本の会社法と同様に、取締役などの役員は会社に対して「善管注意義務(Duty of Care)」と「忠実義務(Duty of Loyalty)」を負います。特にセルビアの会社法は、「個人的利益の追求の禁止(利益相反)」に関して、日本法よりも具体的かつ厳格な規定を置いています。
役員が会社と取引を行う場合や、会社の事業機会を利用しようとする場合には、事前に取締役会や株主総会への開示と承認を得ることが義務付けられています。これに違反した場合、取引の無効や損害賠償責任に加え、当該役員に対する刑事罰が科される可能性もあります。また、「会社機会の奪取(Corporate Opportunity Doctrine)」の法理も明文化されており、役員がその地位を利用して得た情報を元に個人的な利益を得ることは厳しく制限されています。
外国投資法とM&A(企業の合併・買収)

日本企業がセルビアへ進出する際、新規設立(グリーンフィールド投資)だけでなく、既存の現地企業を買収するM&A(ブラウンフィールド投資)の手法も有力な選択肢となります。セルビアでは、外国投資を積極的に誘致するための法整備が進められています。
投資法による内国民待遇の保障
「投資法(Law on Investments)」は、外国投資家に対して「内国民待遇(National Treatment)」を保障しています。これは、外国投資家がセルビアの国内投資家と全く同等の権利を持ち、同等の義務を負うことを意味します。法的な差別的扱いは原則として禁止されています。
また、同法は以下の権利を明確に保障しています。
- 送金の自由:納税義務を果たした後であれば、利益、配当、残余財産などを自由に海外へ送金することができます。
- 収用に対する保護:公共の利益のために必要かつ法に基づいた手続きによる場合を除き、外国投資家の資産が国有化や収用されることはありません。万が一収用される場合でも、市場価格に基づく迅速かつ適切な補償が保障されています。
- 安定化条項(Stabilization Clause):投資契約において、将来の法改正によって投資環境が悪化した場合でも、投資時点の法制度を適用することを合意できる場合があります。
公開買付け(TOB)規制
日本企業がセルビアの上場会社(AD)を買収する場合、「株式引受法(Law on Takeovers of Joint Stock Companies)」に基づく公開買付け規制に注意する必要があります。
セルビアの公開買付け規制は、少数株主保護を重視しており、以下のトリガー基準が設けられています。
- マンダトリー・オファー(義務的公開買付け):議決権の25%を超える株式を取得しようとする者は、原則として他のすべての株主に対して、保有株式の買い取りを申し出る公開買付け(TOB)を行う義務が生じます。
- 日本の金融商品取引法における「3分の1(33.3%)ルール」と比較すると、セルビアの基準はより厳格です。マイノリティ出資からスタートする戦略的提携であっても、25%という低い閾値を超える場合には、全株主へのオファー義務が発生し、予期せぬ資金負担や買収プロセスの複雑化を招くリスクがあります。
- さらに、25%を超えて株式を取得した後、追加で株式を取得し特定の閾値(例えば75%)を超えた場合にも、再度オファー義務が発生する詳細な規定があります。
公開買付けの閾値や手続きに関する詳細は、証券委員会の規制および関連する法律事務所の解説等で確認することが重要です。
競争法(独占禁止法)と企業結合審査
M&Aを行う際、もう一つの重要なハードルとなるのが「競争法(Law on Protection of Competition)」に基づく企業結合審査(Merger Control)です。
セルビアの競争法は、EU競争法をモデルとしており、「競争保護委員会(Commission for Protection of Competition)」が執行を担っています。注意すべきは、届出基準の閾値が比較的低く設定されている点です。
- 全世界での売上高合計が1億ユーロを超え、かつ、セルビア内での売上高が少なくとも1社の当事者について1,000万ユーロを超える場合
- または、セルビア内での売上高合計が2,000万ユーロを超え、かつ、少なくとも2社の当事者についてそれぞれのセルビア内売上高が100万ユーロを超える場合
この基準により、グローバル規模の大企業同士のM&Aであっても、セルビア内に一定の売上(例えば販売子会社がある等)があれば、セルビアの競争保護委員会への届出義務が発生するケース(域外適用)が頻繁に生じます。クリアランス取得前にクロージング(取引実行)を行うことは禁止されており(ガン・ジャンピング規制)、違反には巨額の制裁金が科される可能性があります。
労働法
セルビアでビジネスを行う上で、最も留意すべき分野の一つが労働法です。「労働法(Labor Law)」は、社会主義時代の労働者保護の理念を色濃く残しつつ、EU基準への適合を図った結果、非常に形式的で厳格な手続きを要求する法律となっています。
解雇規制の厳格さと形式主義
セルビアの労働法は、解雇の理由(能力不足、規律違反、整理解雇など)が法律で限定列挙されており、かつ、解雇に至るまでの「手続き」が極めて厳格に定められています。
例えば、従業員の能力不足や規律違反を理由に解雇する場合、以下のプロセスを文書で証明できなければなりません。
- 警告書(Warning Notice)の送付:具体的な違反事実や能力不足の点を指摘し、解雇の可能性があることを警告する文書を従業員に手交します。
- 弁明の機会の付与:従業員に対して、警告に対する回答や弁明を行うための期間(通常8日以上)を与えなければなりません。
- 解雇通知書の交付:弁明を考慮した上でもなお解雇が相当と判断される場合に初めて、理由を付した解雇通知書を交付できます。
この形式的な手続きに一つでも不備があれば、実質的な解雇理由がどれほど正当であっても(例:横領などの明白な非行)、裁判所で解雇無効と判断される可能性が極めて高くなります。
不当解雇に対する救済
解雇が無効と判断された場合、従業員は職場復帰(Reinstatement)を請求する権利を持ちます。さらに、解雇期間中の未払い賃金(バックペイ)と社会保険料の支払いが命じられます。
特筆すべきは、従業員が職場復帰を望まない場合、あるいは裁判所が職場復帰を現実的でないと判断した場合の金銭補償です。裁判所は、従業員の勤続年数や年齢、扶養家族数などを考慮し、最大で給与の36ヶ月分に相当する損害賠償を命じることができます。これは日本の労働審判や裁判における解決金相場と比較しても、企業にとって極めて重い経済的リスクとなります。
有期雇用契約の制限
有期雇用契約(Fixed-term contract)に関しては、その期間の上限が24ヶ月と定められています。この期間を超える場合、または契約更新の間に十分な空白期間がない場合、契約は自動的に無期雇用契約(Indefinite-term contract)とみなされます。
日本では、有期契約が通算5年を超えた場合に無期転換申込権が発生しますが、セルビアでは2年という短い期間で無期化の効果が生じるため、人員計画においてはより慎重な管理が求められます。ただし、特定のプロジェクト業務や、新規事業の立ち上げ時など、例外的に24ヶ月を超える有期契約が認められるケースもあります。
外国人の就労とシングル・パーミット制度
外国人がセルビアで働くための手続きは、2024年の法改正により大幅に簡素化されました。従来は、内務省が管轄する「滞在許可(Residence Permit)」と、国立雇用局(NES)が管轄する「労働許可(Work Permit)」という2つの異なる行政手続きを経る必要がありました。
新制度では、これらが統合された「シングル・パーミット(Single Permit)」が導入されました。
- 申請方法:すべての手続きがオンラインポータルを通じて一元的に行われます。
- 有効期間:最大で3年間の許可が取得可能となりました。
- 労働市場テスト:依然として、同様のスキルを持つセルビア人求職者がいないことを確認する「労働市場テスト」が原則として必要ですが、一定の専門職や欠員補充の場合には免除される規定もあります。
日本企業が駐在員を派遣する場合、このシングル・パーミット制度を利用することになりますが、申請には雇用契約書に加え、詳細な職務記述書や資格証明書が必要となるため、事前の周到な準備が不可欠です。
外国人雇用およびシングル・パーミットの詳細な手続きについては、ナショナル・エンプロイメント・サービスの公式情報が重要です。
不動産法と建設・開発

セルビアにおける不動産取引、特に土地の所有に関しては、外国人に対する制限と、それを緩和する「相互主義」の原則を正しく理解する必要があります。
相互主義(Reciprocity)による土地所有
セルビアの「財産関係の基礎に関する法律」は、外国人が不動産を所有する要件として「相互主義」を定めています。これは、相手国(この場合は日本)においてセルビアの国民が不動産を所有できる場合に限り、その国の国民もセルビアで不動産を所有できるという原則です。
実務上、日本とセルビアの間には事実上の相互主義が存在すると認められています。したがって、日本の個人および法人は、事業活動に必要な事務所、工場、倉庫などの建物、およびその敷地となる建設用地(Construction Land)を、所有権として取得することが可能です。
農業用地の取得制限と実務的対応
一方で、農業用地(Agricultural Land)については、外国人による所有が原則として禁止されています。これは食料安全保障や国土保全の観点からの強い規制です。
しかし、実務上は合法的な「回避策」が存在します。日本企業がセルビア内に現地法人(DOOなど)を設立した場合、その法人はセルビアの国内法人として扱われます。したがって、外国資本100%の現地法人名義であれば、農業用地を取得することが可能です。工場建設のために農地を転用して取得する場合などには、このスキームが一般的に利用されています。
建設許可プロセス(CEOP)の電子化
工場建設やオフィス開発を行う際に必須となる「建設許可(Construction Permit)」の手続きは、かつては不透明で時間がかかるとされていましたが、現在はCEOP(Central Unified Procedure)と呼ばれる電子システムにより完全にデジタル化されています。
手続きは以下のステップで進行します:
- 立地条件(Location Conditions)の取得:計画地においてどのような建物が建築可能か(用途、高さ、建ぺい率など)を行政から取得します。
- 建設許可の申請:建築設計図書や所有権証明書などをアップロードし、許可を申請します。行政は法定の期限内(通常5〜8日)に審査を行い、許可を発行します。
- 工事開始届:許可取得後、工事の開始を届け出ます。
- 使用許可(Usage Permit):建物完成後、技術検査委員会による検査を受け、適合していると認められれば使用許可が発行されます。これにより、建物の登記と本格的な利用が可能となります。
このプロセスは透明性が高く、進捗状況をリアルタイムで追跡できるため、外国投資家にとっても予見可能性の高いシステムとなっています。
建設許可手続きに関する詳細や電子申請ポータルについては、セルビア事業登録庁の関連ページを参照してください。
デジタル資産とテクノロジー法制
セルビアは、ブロックチェーン技術や暗号資産(仮想通貨)の分野において、欧州内でも先進的な法整備を行っている国の一つです。
デジタル資産法による包括的規制
2021年に施行された「デジタル資産法(Law on Digital Assets)」は、暗号資産を法的に定義し、発行、取引、保管(カストディ)に至るまでのライフサイクル全体を規制しています。日本の資金決済法や金融商品取引法に相当しますが、イノベーション促進を強く意識した内容となっています。
同法は、デジタル資産を大きく2つに分類しています。
- 仮想通貨(Virtual Currency):価値の保存や交換手段として機能するもの(例:ビットコイン)。
- デジタルトークン(Digital Token):発行者に対する債権や、特定のサービスを利用する権利、利益の配当を受ける権利などを表章するもの。証券(Security)に近い性質を持つ場合、資本市場法の規制も併せて適用される可能性があります。
仮想通貨交換業やカストディサービスを提供する事業者は、国立銀行(NBS)または証券委員会の監督下に置かれ、ライセンス取得が義務付けられています。最低資本金要件などは定められていますが、主要な欧州諸国と比較すると参入障壁は低めに設定されており、フィンテック企業の誘致を意図しています。
また、ICO(Initial Coin Offering)などを通じてデジタル資産を発行する場合、事業計画やリスク要因を詳細に記載したホワイトペーパーを作成し、規制当局の承認を得る必要があります。これにより、投資家保護と市場の透明性が図られています。
デジタル資産法の詳細やライセンス要件については、国立銀行の関連規定を確認してください。
セルビアにおけるその他の特徴的な法分野

契約法と民法
セルビアの債務関係法(Law on Obligations)は、日本民法と同様に契約自由の原則を中核としています。しかし、国際取引におけるリスク管理の観点から、不可抗力と事情変更の原則に関する規定には特に注目すべき点があります。
- 契約の履行不能と不可抗力:債務関係法第354条第1項は、債務者の責めに帰すべからざる事由によって履行が不可能になった場合、その債務は消滅すると定めています。これは、日本法における危険負担の考え方と類似しています。
- 事情変更の原則:債務関係法第133条は、契約締結後に予見不可能な事情の変更が生じ、契約が当事者の期待に合致しなくなった場合、裁判所は、当事者の一方の請求により、契約を解除するか、または公正にその内容を変更することができると定めています。
日本の民法には同様の明文規定はありませんが、判例法理として事情変更の原則が認められています。しかし、日本の判例ではその要件が厳格に解釈される傾向があります。一方、セルビアの債務関係法は、この原則を明文で規定し、裁判所による契約の変更も認めている点が異なります。セルビアとの国際取引契約を締結する際は、不可抗力条項やハードシップ条項(事情変更条項)を契約書に詳細に盛り込むことで、予見不能なリスクに対する法的安定性を高めることができます。
個人情報保護法
セルビアの「個人データ保護法」(Personal Data Protection Act, PDPA)は、2018年11月に制定され、2019年8月に施行されました。この法律は、EUの一般データ保護規則(GDPR)にほぼ完全に調和しており、日本の「個人情報保護法」との間で重要な相違点があります。
- 域外適用:セルビアの個人データ保護法は、セルビア国内のデータ主体に商品やサービスを提供する場合、またはその行動を監視する場合、コントローラーやプロセッサーがセルビアに事業所を持たなくても適用されると明記しています。したがって、日本のeコマース事業者がセルビア市場にオンラインで参入する場合にも適用されます。
- 7つの基本原則と8つの権利:セルビア法は、GDPRと同様に、適法性、公正性、透明性、目的制限、データ最小化、正確性、保存期間の制限、完全性と機密性、アカウンタビリティという7つの基本原則を定めています。また、データ主体に知らされる権利、訂正の権利、消去の権利(忘れられる権利)、データポータビリティの権利など、8つの重要な権利を認めています。
- データ漏洩時の通知義務:データ漏洩が発生した場合、コントローラーは、72時間以内に監督機関(Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection)へ通知する義務があります。日本の法制度では「遅滞なく」とされているため、具体的な時間制限が課されている点が大きな違いです。
- 現地代理人の選任義務:セルビアに事業所を持たない事業者であっても、大規模な個人データ処理を行う場合など、特定の要件を満たす場合には、セルビア国内にデータ保護代表者(Data Protection Representative)を選任する必要があります。
広告規制法
セルビアの広告法(Law on Advertising)は、虚偽・誤認惹起広告の禁止や、広告が広告として認識可能であることなど、日本の景表法と共通する一般原則を定めています。一方で、特定の分野においては、日本法と比較してより厳格な制限が存在します。
- アルコール飲料:ビールとワインは特定のメディア(テレビ、ラジオ)で広告が禁止され、スピリッツ(蒸留酒)はさらに多くのメディア(新聞、雑誌、映画館、看板など)で広告が禁止されています。
- 医療・医薬品:医薬品や医療サービスに関する広告は厳しく制限されています。処方薬(処方箋が必要な医薬品)の一般向け広告は厳格に禁止されています。
- 医療サービスの広告も、医療機関名や所在地、事業内容の記載に限定されます。
これらの規制は、広告内容、掲載メディア、対象者など、多岐にわたるため、現地でのプロモーション活動には入念な法的確認が不可欠です。
AI(人工知能)関連法
セルビアは、AI分野において「地域リーダー」としての地位を確立しようとしており、EUのAI法に倣った包括的な法整備を進めています。
現在、AIを包括的に規制する法律は存在しませんが、2024年6月に法案起草ワーキンググループが発足しています。新法は、EU AI法と同様に、AIシステムをリスクベースで分類し、高リスクなAIシステムにはより厳格なコンプライアンス義務を課すことが見込まれます。
セルビア法がEU法に準拠する場合、日本のAI関連企業は、セルビア市場を通じて欧州市場への参入を試みる際に、二重のコンプライアンス義務を負うことになります。しかし、逆に言えば、セルビア法を遵守することは、同時にEU市場への参入要件を事前に満たすことに繋がるため、セルビアが欧州市場へのテストベッドとなり得ることを示唆します。
まとめ
セルビアの法制度は、日本の法体系と多くの共通点を持ち、特に民法や会社法の基礎概念は日本の法務実務家にとって理解しやすいものです。しかし、旧ユーゴスラビアという歴史的背景と、EU加盟に向けた法整備という現代的な動向が、この国の法制度を独自の、そして非常にダイナミックなものにしています。
具体的には、極めて低いハードルで会社設立ができる一方、データ保護や広告規制ではEU水準の厳格なコンプライアンスが求められます。また、税制面では法人税率の低さやIPボックス制度といった強力なインセンティブが提供されているなど、日本とは異なる魅力とリスクが混在しています。これらの複雑な要素を正確に理解し、ビジネスチャンスを最大限に活かすためには、現地の法的知識が不可欠です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務