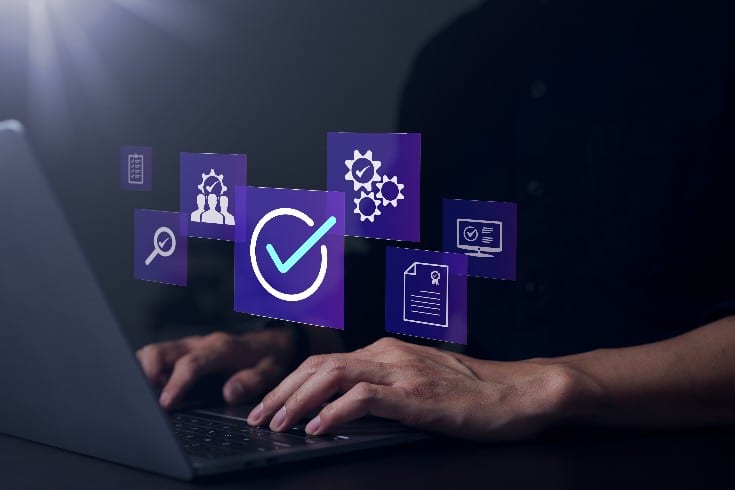ハンガリーの会社法が定めるコーポレートガバナンス

ハンガリーは、欧州連合(EU)加盟国として、企業活動に安定した法的枠組みを提供しています。そのコーポレートガバナンスの根幹は、2014年3月15日に施行されたハンガリー民法典(Act V of 2013)やその他の関連法令によって形成されています。日本の経営者や法務担当者がハンガリーでの事業展開を検討する際、特に注目すべきは、日本の法制度とは異なる機関設計の柔軟性、取締役の責任範囲、M&Aにおける株主の権利保護、そして近年の外国投資に対する政府の介入強化です。
本記事では、これらのテーマについて、日本の法制度との重要な異同に焦点を当て、ハンガリーの法務・実務に関する実践的な洞察を提供します。
なお、ハンガリーの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
ハンガリーにおける主要な事業体
日本の会社形態との比較
ハンガリーの会社法は、日本の会社法と共通する点が多い一方で、独特の概念や構造も有しています。最も一般的な会社形態は、日本の合同会社(G.K.)に類似した有限責任会社(Korlátolt felelősségű társaság、以下「Kft.」)と、日本の株式会社(K.K.)に類似した株式会社(Zártkörűen működő részvénytársaságまたはNyilvánosan működő részvénytársaság、以下それぞれ「Zrt.」「Nyrt.」)です。これらの会社形態は、原則として株主の有限責任を特徴としていますが、詳細な機関設計や持分の性質には重要な違いが存在します。
Kft.は、中小企業を中心にハンガリーで最も一般的な会社形態で、日本の合同会社と同様に、株主は出資額を限度として責任を負い、その個人資産は会社の債務から保護されます。日本の合同会社との最も重要な違いの一つは、所有権の性質が「持分(business quota)」によって表され、これは日本の株式のような流通性の高い有価証券ではない点です。この持分は、他のメンバーや会社が法律上当然に有する先買権(pre-emption right)が法定されており、譲渡手続きに複雑さを伴います。また、ハンガリー最高裁判所(Kúria)の判例によると、Kft.の持分譲渡は当事者間の契約締結をもって有効となりますが、会社に対しては、新株主が持分取得に関する書面を提出し、会社登記簿への登録が完了した時点で初めて効力を生じます。
一方、Zrt.(非公開株式会社)およびNyrt.(公開株式会社)は、Kft.よりも大規模なビジネスに適した会社形態であり、所有権は「株式(shares)」によって表されます。日本の株式会社と同様に株式は有価証券として扱われ、流通性が高いという特徴があります。
ハンガリー機関設計の基本原則
柔軟な機関設計とワン・ティア制
ハンガリーのコーポレートガバナンスは、日本の典型的な監査役会設置会社や監査等委員会設置会社といった厳格なモデルとは異なり、柔軟な選択肢が提供されています。特に公開会社(Nyrt.)では、取締役会と監査役会の構造に類似したツー・ティア制に加えて、取締役会が経営と監督の両方を担うワン・ティア制を採用することができます。また、非公開会社(Zrt.)やKft.では、複数の取締役を置くことも、単独の執行役員を選任することも可能とされています。
取締役会と監査役会(Supervisory Board)の役割
ハンガリー法では、取締役会(Board of Directors)の権限は「残余権限(residual powers)」と規定されています。これは、株主総会に明示的に留保されていないすべての決定権が取締役会に帰属することを意味し、この原則は、日本の会社法における取締役会の権限と概念的にほぼ同様です。一方、監査役会(Supervisory Board)は、経営陣を監督し、株主の利益を保護する役割を担います。
日本の会社法にはないユニークな特徴として、ハンガリーでは年間平均従業員数が200人を超える企業において、監査役会を設置することが法律で義務付けられています。この義務は、従業員代表が設置の権利を放棄しない限り適用されるため、日本企業が現地法人を設立する際には、労働法との関係で慎重な検討が求められます。
ハンガリー取締役の権限と義務

忠実義務と善管注意義務
ハンガリー法において、取締役は会社に対して、その最善の利益のために行動し、利益相反を回避する「忠実義務(Fiduciary Duties)」を負います。また、会社が税法や労働法を含むハンガリーの法令を遵守するよう努める「善管注意義務」も負っています。これらの義務は、日本の会社法における取締役の義務と概念的に非常に類似しています。
会社及び第三者に対する責任
ハンガリーにおける取締役の民事責任は、取締役が会社とどのような法的関係にあるかによってルールが異なります。
まず前提として、ハンガリーでは、取締役が会社と雇用契約または委任契約のいずれかを締結することが可能です。そして、この法的関係の違いは、取締役の責任範囲に大きな影響を与えます。
- 雇用契約に基づいている場合:取締役は「執行社員(executive employee)」とみなされ、労働法が適用されます。取締役が故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合、全損害を賠償する責任を負いますが、会社が損害を軽減するための措置を怠った場合や、予見不可能であった損害については、その責任を免除される可能性があります。
- 委任契約に基づいている場合:民法典が適用されます。取締役は、自らの職務行為によって会社に生じた損害を賠償する責任を負いますが、損害が不可抗力や予見不可能な状況によるものであり、かつそれを回避できなかったことを証明できれば、責任を免除される可能性があります。
また、2014年の新民法典(Act V of 2013)は、取締役の責任範囲を大きく広げました。新法は、取締役が職務に関連して第三者に与えた損害について、会社と共同で、連帯して責任を負うという重要な変更を加えています。これは、会社が損害賠償を行った後、取締役に対して求償できるという従来の原則を補強するものであり、日本の会社法と比べ、より厳格な責任を課すものと言えるでしょう。
罰金に対する個人的責任
日本の法務担当者にとって特に注意すべきは、会社に課された罰金に対する取締役の個人的な責任に関するハンガリーの解釈です。
ハンガリーの裁判所は、取締役の業務上の行為によって会社に罰金が発生した場合、例えば競合他社との価格談合による競争法違反などが行われた場合、会社に課された罰金相当額の損害賠償を取締役個人に命じる判決を出すことがあります。つまり、取締役が法令違反により会社に損害(罰金)を与えた場合、その原因となった行為が職務の範囲内であっても、個人的に責任を負うべきという理論です。これは、罰金の抑止効果が会社に帰属すべきという他のEU加盟国(例:ドイツ)における議論とは一線を画すものであり、ハンガリーの法務実務における非常に重要なリスク要因として認識すべきです。
ハンガリー株主の権利とその行使
株主総会の権限
株主は、合併や買収、配当の決定、資本構成の変更など、会社の重要な意思決定に対し、株主総会を通じて議決権を行使する権利を有します。登録住所や事業目的の変更といった事項であっても、定款の変更を伴う場合には株主総会の承認が必要です。
少数株主の保護
ハンガリー民法典は、一定の持株比率を持つ少数株主に対し、会社経営に対する監督権や是正権を付与することで保護を図っています。具体的には、Zrt.やKft.では議決権の5%以上、Nyrt.では議決権の1%以上を保有する株主は、株主総会の招集を要求したり、過去2年間の財務諸表や経営陣の行為に関する特別監査を請求したりすることができます。また、ハンガリーの判例では、多数株主による「濫用的な議決権行使(shareholder oppression)」が会社利益に反して行われ、増資に追随できなかったことによる議決権の希薄化などの損害を被った場合、裁判所に損害賠償や決議の無効化を請求できる可能性があります。裁判所は、少数株主間の平等を害し、会社の利益に反し、多数株主にのみ利益をもたらすような行為があったかどうかを審査します。
有限責任会社(Kft.)における持分譲渡と先買権
Kft.の持分を第三者に譲渡する場合、他のメンバーおよび会社は法律で定められた先買権を有します。これは日本の会社法にはない法定の権利であり、譲渡を完了させるためには、先買権を放棄してもらうための「先買権放棄書(preemption right waiver letters)」を取得する必要があります。この手続きは、スムーズなM&A取引の実現において、特に注意すべき実務上の課題となります。
ハンガリーにおけるM&A(合併・買収)の法規制
公開買付(Takeover Bid)の要件と日本法との差異
公開会社(Nyrt.)の買収は、ハンガリー資本市場法(Act CXX of 2001)および民法典(Act V of 2013)によって規制されています。日本の公開買付制度と類似したルールとして、買収者が議決権の33%(他に10%以上を所有する者がいない場合は25%)を超える場合、強制公開買付が義務付けられます。買収の結果、90%以上の議決権を保有することになった株主には、残りの株主を強制的に買い取る「スクイーズアウト権」が発生します。同時に、少数株主は自己の株式を売却する「セルアウト権」を行使できます。
外国投資に対する国家の先買権
M&Aにおいて、近年注目すべき法改正として、外国投資に対する国家の介入権限の拡大があります。2025年6月24日に施行された政府令改正により、ハンガリー政府は、特定の「戦略的」分野における外国投資を禁止するだけでなく、国家が外国投資家と同じ条件で会社を取得する「先買権」を普遍的に行使する権限を拡大しました。この改正は、進行中の取引にも遡及的に適用されるため、外国人投資家は予期せぬリスクに直面する可能性があります。ただし、この国家による介入はEU法上の制約を受けることにも留意が必要です。欧州司法裁判所(CJEU)は、Xella Hungary事件(Case C-106/22)において、特定の目的だけでは、外国からの投資を制限する正当な根拠にはならないと判示しました。
まとめ
ハンガリーのコーポレートガバナンスは、EU法との調和を図りつつも、独自の法制度と解釈が共存する複雑なものです。特に、有限責任会社(Kft.)における持分の性質と譲渡の複雑性、取締役の個人責任を広範に認める厳格な判例、そして外国投資に対する国家の介入強化は、日本企業が事業展開を検討する上で見過ごせないリスクです。これらの法的・実務的課題は、現地の専門的な知識がなければ正確なリスク評価が困難と言えるでしょう。モノリス法律事務所は、貴社のハンガリー進出、日々の事業運営、そしてM&A取引を成功に導くための包括的なリーガルサービスを提供いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務