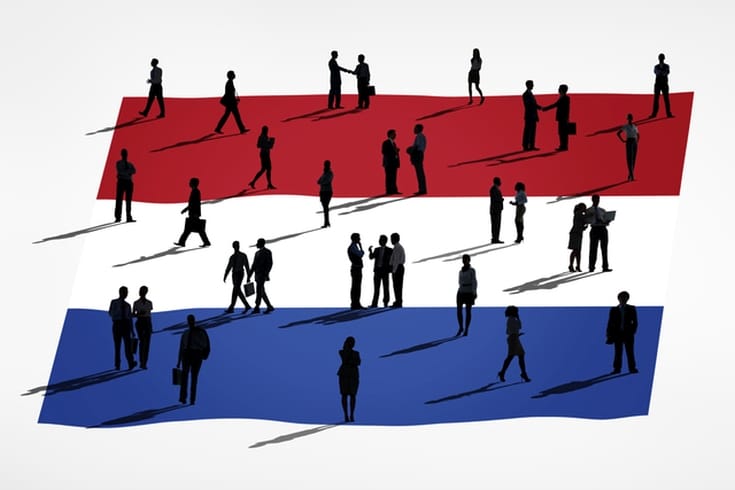ハンガリーの広告・インフルエンサーマーケティング規制
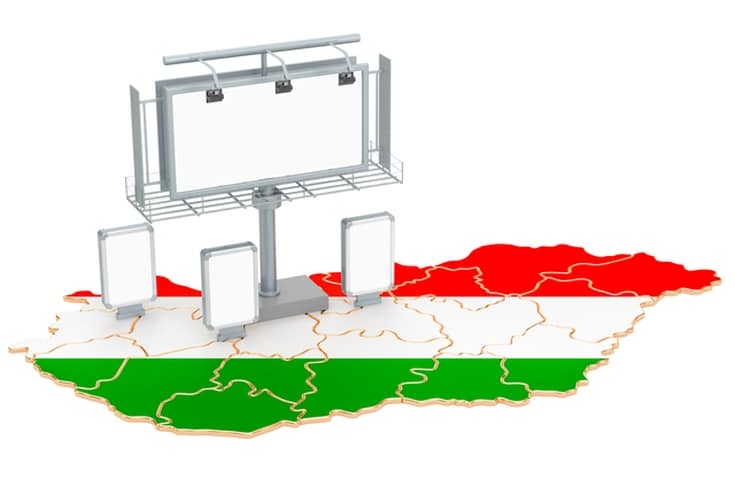
ハンガリーは、EU(欧州連合)の加盟国として、その消費者保護指令に準拠した強固な広告規制を敷いています。特に、EUが推進する「New Deal for Consumers」の流れを受け、2022年以降、電子商取引やデジタルサービス、価格表示に関する法改正が相次いで行われました。そして、2023年6月30日には、インフルエンサーマーケティングに関する具体的な規定を含む新しい広告倫理規定が施行され、デジタル広告の透明性確保に向けた姿勢がより一層明確になりました。これは、2023年10月1日からステルスマーケティングを景品表示法違反と定めた日本の法改正と軌を一にする動きです。しかし、両国の規制には、その法的根拠、規制対象、そして実務上の表示方法において、重要な差異が存在します。
本記事では、ハンガリーの広告規制の全体像を概観しつつ、特にインフルエンサーマーケティングに関する新規則を詳細に解説し、日本の規制と比較することで、ハンガリー市場への進出を検討する企業が直面しうる法的リスクと、その対策について考察します。
なお、ハンガリーの包括的な法制度の概要は下記記事にてまとめています。
この記事の目次
ハンガリーの広告規制の全体像
EUの「不公正な取引方法指令」に基づく基本原則
ハンガリーの広告規制の根幹は、EUの消費者保護指令を国内法に転換したものであり、消費者を欺く行為を厳格に禁止することにあります。具体的には、広告は「合法的で、品位があり、主張が正直で真実であること」が基本原則として求められます。虚偽または誤解を招く広告は厳しく禁止されており、製品の主要な特性、価格、環境への影響などに関して消費者を欺く行為は、不公正な取引行為と見なされます。この規制は、社会の一般的な道徳・倫理基準に反する広告、暴力、身体の完全性を脅かす行為、人種・性別・性的指向などに基づく差別的な広告、動物虐待を誘発または正当化するような広告も禁止しています。さらに、消費者の経験不足や知識不足、信用につけ込むような行為も禁じられています。
ハンガリーでは、法的な強制力を持つ公的機関として、ハンガリー競争庁(GVH)が不公正な商慣行を監督する主要な役割を担っています。GVHは、独占禁止法や消費者保護に関連する法律に基づき、虚偽または誤解を招く広告に対して罰金を科す権限を有します。同時に、業界の自主規制団体である広告自主規制委員会(ÖRT)も重要な役割を担っています。ÖRTは、広告業界の専門家や関連団体の代表者で構成されており、独自の倫理規定(Hungarian Code of Advertising Ethics)を策定しています。この倫理規定は、法律の規定を補完する形で、より詳細で厳格な基準を定めていることが特徴です。
ÖRTの存在は、ハンガリーの広告規制が単なる法的な強制だけでなく、業界全体の倫理基準を向上させようとする、より自律的かつ協調的なアプローチを持っていることを示しています。これは、日本の消費者庁が景品表示法のような行政主導の規制を主に運用しているのとは異なり、法的強制力と業界の自主規制という二重の監督体制が存在することを意味します。企業は、法的義務だけでなく、ÖRTが定める倫理規範にも準拠する必要があり、この二重のレイヤーを理解することが、円滑な事業運営には不可欠となります。ÖRTが提供する「コピーアドバイス」(広告原稿の事前審査)サービスは、企業が法規制と倫理規範の両方を満たすための有効な手段となり得ます。
虚偽・不当表示に関する法的責任と判例
ハンガリーでは、虚偽・不当表示に対する法的判断は非常に厳格であり、その責任は広範に及びます。
その代表的な例が、欧州司法裁判所(ECJ)の判例、C-388/13 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság v UPC Magyarország Kft です。この事件では、ハンガリーの消費者が、ケーブルテレビ会社を変更しようとしており、旧契約の最後の支払いがいつ期限切れになるか、その日にサービスを停止するよう求めていました。ところが、この会社から誤った情報が提供されたため、消費者は旧サプライヤーと新サプライヤーの両方から短期間、料金を請求されることになりました。この一度限りの誤った情報提供について、ECJはこれを「誤解を招く取引方法」と認定しました。この判例は、行為が反復的であるか、複数の消費者に影響を及ぼしているかに関わらず、責任を問われる可能性があるという、極めて厳しい判断基準を示しています。この判決は、事業者の行為が意図的でなかったことや、消費者が被った損害がわずかであったことも、法的評価には影響しないことを明確にしました。
また、ハンガリー競争庁(GVH)が下した処分事例も、この厳格な判断基準を裏付けています。2021年1月、GVHは、医療機器を扱う卸売・サービス会社に対し、製品が医療機器であることの明確な表示を怠ったとして、600万フォリント(約260万円)の罰金を科しました。この事例では、企業がテレビ広告、新聞、店頭広告で製品を宣伝する際、法律で定められた警告文(使用説明書を読むよう促す文言)を記載せず、製品が医療機器であることも明確に示していませんでした。GVHは、特に軽失禁に悩む女性といった、その状態に苦慮している消費者層をターゲットにしていたことを考慮し、この行為を消費者を欺く行為と判断しました。
これらの判例は、ハンガリーの消費者保護が「平均的な消費者の行動を歪める可能性」という抽象的な基準に留まらず、「単一の事実の不開示」や「単一の行為」といった具体的なレベルまで厳格に適用されることを明確に示しています。特に製品の表示や広告文言には極めて細心の注意を払う必要があると言えるでしょう。
ハンガリーのインフルエンサーマーケティングに関する新規則
2023年6月30日施行の新しい広告倫理規定
新しいハンガリー広告倫理規定は、デジタルマーケティングにおける透明性向上の要請に応える形で施行されました。この規定の核心は、インフルエンサーと広告主の間の商業的関係を消費者に「極めて明白に」表示することを義務付けた点にあります。
この規定に基づき、インフルエンサーは、そのコンテンツが広告であることを明確に宣言しなければなりません。特に、ハッシュタグを使用する場合、「#advertisement」などの広告であることを示すタグを冒頭に記載することが求められています。また、その表示は、消費者が「次のボタン」などをクリックすることなく、即座に認識できる形でなければならないと定められています。これは、SNSのプラットフォームやデバイス(スマートフォン、PC、スマートウォッチなど)の特性を考慮に入れた、非常に実務的な要件です。
さらに、ハンガリー競争庁(GVH)は、インフルエンサーマーケティングに関する指針を公表しています。その中でGVHは「インフルエンサー」を「特定の分野で支配的な影響力を行使する能力のある人物、または仮想の存在」と定義し、コミットしたフォロワーベースを持つ人物がこれに該当すると説明しています。また、インフルエンサーが受ける「対価」は金銭的な支払いに限らず、無料の商品、割引、バウチャー、イベントチケットなど、通常であれば費用を要するあらゆる有形無形の利益を含むと広範に定義されています。
法律にインフルエンサーの明確な定義がない中で、GVHが指針を公表している事実は、法規制の空白を実務的な指針で埋め、市場参加者に予測可能性を提供しようとする政府の意図によるものでしょう。また、「対価」の広範な定義は、日本でいうところの「金銭授受がない場合でも、関係性があれば規制対象となり得る」という考え方と似ていますが、ハンガリーではより具体的に利益が列挙されています。
日本のステルスマーケティング規制とハンガリー規制の比較

日本の景品表示法とハンガリーの広告規制は、どちらも広告の透明性向上を目的としていますが、その法的根拠、規制対象、そして実務上の表示方法には大きな違いがあります。
日本の景品表示法では、2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(ステルスマーケティング)が不当表示として明確に規制されました。この規制の対象は、商品やサービスを供給する事業者(広告主)のみであり、企業から依頼を受けたインフルエンサー等の第三者自身は直接の規制対象とはなりません。これは、インフルエンサーの行為を「事業者の表示」として捉え、その表示の主体である事業者に責任を負わせるという構造をとっているためです。
一方、ハンガリーでは、自主規制機関であるÖRTがインフルエンサーを直接の対象としており、さらにGVHの指針では、販売に直接的な利害関係を持つインフルエンサーは、広告主と連帯責任を負う可能性があるとされています。
表示方法の具体性も両国で異なります。ハンガリーの新しい広告倫理規定は、「#advertisement」などの広告であることを示すタグを冒頭に記載することを義務付けており、これは非常に具体的で厳格な要件です。これに対し、日本の規制は、特定の表示方法を義務付けてはいません。しかし、消費者庁のガイドブックでは、ハッシュタグを使用する場合でも、他のハッシュタグの中に紛れ込ませる行為は不適切とされています。ハンガリーの冒頭に記載するという要件は、日本の「判別困難性」をより厳格に解釈した実務指針といえるでしょう。
以下の表は、両国の規制の主要な相違点を比較したものです。
| ハンガリー | 日本 | |
|---|---|---|
| 法的根拠 | EU指令に基づく国内法(消費者保護法など)および厳格な業界の自主規制(ÖRTの倫理規定) | 景品表示法 |
| 規制対象者 | 広告主および場合によってはインフルエンサー双方 | 事業者(広告主)のみ |
| 広告表示義務 | インフルエンサーと広告主の商業的関係を「極めて明白に」表示 | 「事業者の表示であると一般消費者が判別することが困難な表示」を禁止 |
| 表示方法の具体性 | ハッシュタグを使用する場合、「#advertisement」などを冒頭に記載することが義務付けられている | 特定の表示方法を義務付けてはいないが、判別困難な表示(ハッシュタグを埋もれさせるなど)は不適切とされる |
| インフルエンサーの責任 | 販売に直接的な利害関係を持つ場合、広告主と連帯責任を負う可能性がある | 直接の規制対象にはならない |
この比較から、ハンガリーの規制の具体性・厳格性は、日本企業が国内で慣れ親しんだ広告表示の慣行がそのまま通用しないリスクがあることを示しています。日本のガイドラインでは、ハッシュタグの前に「PR」と書くことが推奨されていますが、ハンガリーではハッシュタグの先頭に特定の単語を置くことが義務付けられています。また、ハッシュタグ以外にも、動画内のテロップやナレーションなど、多様な方法での開示が求められる可能性があります。
まとめ
ハンガリーの広告規制は、EUの消費者保護指令を基盤とし、インフルエンサーマーケティングをはじめとする新しいデジタル広告手法に対して、日本よりも具体的かつ厳格なルールを設けています。特に、インフルエンサーと広告主双方に法的責任が及びうる点や、広告表示方法に関する詳細な義務は、日本の事業者が国内での慣行に倣って行動した場合、予期せぬ法的リスクを招く可能性があります。
ハンガリーでの事業展開を成功させるためには、これらの規制を深く理解し、現地の法務専門家と連携して、広告戦略と実務上のコンプライアンスを徹底することが不可欠です。単一の広告違反であっても、厳しい法的判断が下される可能性を考慮すると、事前の法的リスク評価と予防措置が極めて重要となります。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務