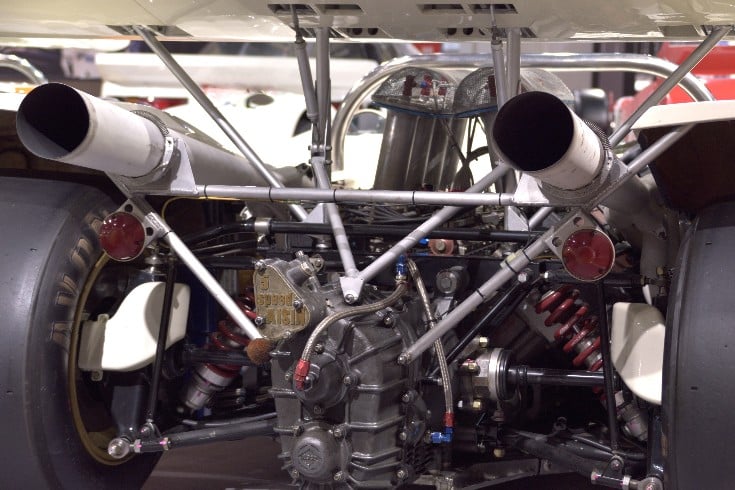ŃüčŃüúŃüčńŞÇš×ČŃü«ŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃüîňłćŃüĹŃü芜Ċ܌Ńâ╝Ńâ╝ŃâľŃâČŃâ╝ŃéşňżîŃü«ÚÇ▓ŔĚ»ňĄëŠŤ┤Ńé嚎üŃüśŃéőF1Ńü«ŃÇîŃâáŃâ╝ŃâôŃâ│Ńé░Ńâ╗ŃéóŃâ│ŃâÇŃâ╝Ńâ╗ŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâ│Ńé░ŃÇŹŔŽĆňłÂŃéĺŔ¬şŃü┐ŔžúŃüĆ

ÚźśÚÇčÚüôŔĚ»ŃéĺŔÁ░ŃüúŃüŽŃüäŃéőŃüĘŃüŹŃÇüňëŹŃü«Ŕ╗ŐŃüîŠÇąŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃüŚŃü¬ŃüîŃé뚬üšäÂŔ╗ŐšĚÜŃéĺňĄëŃüłŃüčŃéëÔöÇÔöÇň┐âŔçôŃüóŃüżŃéŐŃüŁŃüćŃüźŃü¬ŃéŐŃüżŃüÖŃéłŃüşŃÇé
ŠÖéÚÇč300kmŃü«F1ŃüžŃééń║őŠâůŃü»ňÉîŃüśŃÇé
ŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃéĺŔŞĆŃéôŃüáš×ČÚľôŃüôŃüŁŃÇüŃâ×ŃéĚŃâ│ŃüÇŃééńŞŹň«ëň«ÜŃüźŃü¬ŃéŐŃÇüňŹ▒ÚÖ║ŃüáŃüĘŔĘÇŃéĆŃéîŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüŁŃü«šŐŠůőŃüžňëŹŃü«Ŕ╗ŐŃüîŠÇąŃüźŠĘ¬ŃüŞňőĽŃüäŃüčŃéëÔÇŽÔÇťŃé│ŃâäŃâ│ÔÇŁŃü«Ŕ┐Żš¬üŃüžŃü»ŠŞłŃü┐ŃüżŃüŤŃéôŃÇé
ÔÇťŃé»ŃâęŃââŃéĚŃâąÔÇŁŃü»ńŞÇš×ČŃüžŃüÖŃÇé
ŃüŁŃüôŃüžF1ŃüźŃü»ŃÇüŃÇîŃâľŃâČŃâ╝ŃéşńŞşŃü»ÚÇ▓ŔĚ»ŃéĺňĄëŃüłŃüŽŃü»Ńü¬ŃéëŃü¬ŃüäŃÇŹŃüĘŃüäŃüćšë╣ňłąŃü¬ŃâźŃâ╝ŃâźŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇéŃüŁŃü«ÔÇťšĚÜň╝ĽŃüŹÔÇŁŃüîŠ│ĘšŤ«ŃüĽŃéîŃüčŃâČŃâ╝Ńé╣ŃüîŃüéŃéŐŃüżŃüŚŃüčŃÇéň«ëňůĘŃéĺň«łŃéőŃüčŃéüŃü«ŃâźŃâ╝ŃâźŃü»ŃÇüŃüęŃüôŃüżŃüžÚüŞŠëőŃé嚪ŤŃéőŃü«ŃüőŃÇéŃüŁŃü«ňó⚼îšĚÜŃüîňĽĆŃéĆŃéîŃüčŃéĚŃâ╝Ńâ│ŃéĺŃü▓ŃééŔžúŃüŹŃüżŃüÖŃÇé
ŃüôŃü«ŔĘśń║őŃü«šŤ«ŠČí
2025ň╣┤Ńü«Ŕžĺšö░Ńü«ŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâ│Ńé░Ńüîň╝ĽŃüŹÚçĹŃüź
ŃüôŃüĘŃü«šÖ║šź»Ńü»Š▒║ňőŁŃüž10Šťł19ŠŚąŃüźŔíîŃéĆŃéîŃüčF1Ńü«ń╗ŐňşúšČČ19ŠłŽŃüĘŃü¬Ńéőš▒│ňŤŻGPŃü«Š▒║ňőŁŃüžŃüŚŃüčŃÇé7ńŻŹŃüĘŃü¬ŃüúŃüčŔžĺšö░ŔúĽŠ»ůÚüŞŠëőŃüîŃüîŃâŁŃéŞŃéĚŃâžŃâ│šó║ń┐ŁŃéĺňŤ│ŃüúŃüŽŃüäŃüč34ňĹĘšŤ«Ńü«ŃüôŃüĘŃüžŃüŚŃüčŃÇéňżîŃéŹŃüőŃéëŃü»Š×ťŠĽóŃüźŃéĄŃâ│Ńé嚬üŃüôŃüćŃüĘŃé¬Ńâ¬ŃâÉŃâ╝Ńâ╗ŃâÖŃéóŃâ×Ńâ│ÚüŞŠëőŃüîŠö╗ŃéüňůąŃüúŃüŽŃüŹŃüżŃüÖŃÇéŃüŁŃéîŃüźň»żŃüŚŃüŽŃÇü25Šş│Ńü«ŠŚąŠťČń║║ŃâëŃâęŃéĄŃâÉŃâ╝Ńü»ŃâľŃâşŃââŃé»ŃâęŃéĄŃâ│ŃéĺňĆľŃéŐŃü¬ŃüîŃéëŃé¬Ńâ╝ŃâÉŃâ╝ŃâćŃéĄŃé»ŃéĺÚś▓ŃüÄŃüżŃüŚŃüčŃÇé
ňĺäňŚčŃüźŃé│Ńâ╝Ńé╣Ńéĺňí×ŃüîŃéîŃÇüŔíîŃüŹňá┤ŃéĺňĄ▒ŃüúŃüčŃâÖŃéóŃâ×Ńâ│Ńü«Ńâ×ŃéĚŃâ│Ńü»ŃüŁŃü«ŃüżŃüżŃé│Ńâ╝Ńé╣Ńé¬ŃâĽŃüŚŃüŽŃüŚŃüżŃüäŃüżŃüŚŃüčŃÇéšÁÉň▒ÇŃÇüŃâ×ŃéĚŃâ│Ńü»ňłÂňżíńŞŹŔâŻŃüźŃü¬ŃéŐŃÇüŃé╣ŃâöŃâ│ŃüŚŃüŽŃüŚŃüżŃüäŃüżŃüŚŃüčŃÇéň╣ŞŃüäňĄžŃüŹŃü¬Ńé»ŃâęŃââŃéĚŃâąŃüźŃü»Ŕç│ŃéëŃü¬ŃüőŃüúŃüčŃééŃü«Ńü«ŃÇüš┤ŹňżŚŃüäŃüőŃü¬ŃüäŃâÖŃéóŃâ×Ńâ│Ńü»Ŕžĺšö░ÚüŞŠëőŃéĺŃÇîňŻ╝Ńü«Ŕíîšé║Ńü»ŃâźŃâ╝ŃâźŃüźÚüĽňĆŹŃüŚŃÇüš▓żšą×ŃüźŃééňĆŹŃüŚŃüŽŃüäŃéőŃÇŹŃÇîňůłŃü«ŃüôŃüĘŃéĺŔÇâŃüłŃü¬ŃüäŠäÜŃüőŃü¬ÚüőŔ╗óŃüáŃÇŹŃüĘšŚŤšâłŃüźŠë╣ňłĄŃüŚŃüżŃüŚŃüčŃÇé
ńŞÇńŻôŃâÖŃéóŃâ×Ńâ│ÚüŞŠëőŃü»Ńü¬ŃüťŔžĺšö░ÚüŞŠëőŃéĺŠë╣ňłĄŃüŚŃüčŃü«ŃüžŃüŚŃéçŃüćŃüőŃÇéňŤŻÚÜŤŃé╣ŃâŁŃâ╝ŃâćŃéúŃâ│Ńé░Ńé│Ńâ╝Ńâë´╝łISC´╝ëÚÖäňëçL šČČIVšźá šČČ2ŠŁíŃÇüF1Ńé╣ŃâŁŃâ╝ŃâćŃéúŃâ│Ńé░Ńâ╗ŃâČŃé«ŃâąŃâČŃâ╝ŃéĚŃâžŃâ│ŃÇüŃüŁŃüŚŃüŽF1ŃâëŃâęŃéĄŃâôŃâ│Ńé░Ńâ╗Ńé╣Ńé┐Ńâ│ŃâÇŃâ╝ŃâëŃâ╗ŃéČŃéĄŃâëŃâęŃéĄŃâ│ŃéĺŃééŃüĘŃüźŃÇüŔÂúŠŚĘŃâ╗Šá╣ŠőáŃâ╗ň«čňőÖÚüőšöĘŃé劼┤šÉćŃüŚŃüżŃüÖŃÇé
ŃâźŃâ╝ŃâźŃü«ŠáŞ´╝ÜŠŞŤÚÇčÚľőňžőňżîŃü»ŃÇîňőĽŃüőŃü¬ŃüäŃÇŹ
ISCÚÖäňëçL šČČIVšźá šČČ2ŠŁíŃü»ŃÇüŃé¬Ńâ╝ŃâÉŃâ╝ŃâćŃéĄŃé»ŃüĘÚś▓ňżíŃü«ńŞÇŔłČňÄčňëçŃüĘŃüŚŃüŽŃÇîÚś▓ňżíŃü«ŃüčŃéüŃü«Šľ╣ňÉĹŔ╗óŠĆŤŃü»1ňŤ×ŃüżŃüžŃÇŹŃÇüŃÇ░ňŞŞŃü¬Šľ╣ňÉĹŔ╗óŠĆŤŃü»šŽüŠşóŃÇŹŃéĺň«ÜŃéüŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüĽŃéëŃüźF1Ńü«ŃâëŃâęŃéĄŃâôŃâ│Ńé░Ńâ╗Ńé╣Ńé┐Ńâ│ŃâÇŃâ╝ŃâëŃâ╗ŃéČŃéĄŃâëŃâęŃéĄŃâ│Ńü»ŃÇüŠŞŤÚÇ芫ÁÚÜÄ´╝łŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâ│Ńé░´╝ëŃüźňůąŃüúŃüŽŃüőŃéëŃü»ŃÇüŃâČŃâ╝ŃéĚŃâ│Ńé░ŃâęŃéĄŃâ│ŃüźňżôŃüćňá┤ňÉłŃéĺÚÖĄŃüŹŃÇüÚÇ▓ŔĚ»ňĄëŠŤ┤ŃéĺŔíîŃéĆŃü¬ŃüäŃüôŃüĘŃé劜Ěó║ŃüźŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüÖŃü¬ŃéĆŃüíŃÇüŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâ│Ńé░ňżîŃü«ÔÇťňĆŹň┐ťšÜäŃü¬ŃâľŃâşŃââŃé»ÔÇŁŃü»ńŞŹňĆ»ŃüĘŃüäŃüćŃéĆŃüĹŃüžŃüÖ´╝łmoving under braking´╝ëŃÇé
Ńü¬ŃüťŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâ│Ńé░ńŞşŃüźŃÇîŃâľŃâşŃââŃé»ŃÇŹŃüüŃüśŃéëŃéîŃüŽŃüäŃéőŃü«ŃüžŃüŚŃéçŃüćŃüőŃÇéŃüŁŃü«ŔÂúŠŚĘŃü»ŃÇîň«ëňůĘŃüĘňůČŠşúŃÇŹŃüźŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇé
ŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâ│Ńé░ńŞşŃü»ŔŹĚÚçŹŃüîňëŹŔ╝¬ňü┤Ńüźšž╗ŃéŐŃÇüŔ╗ŐńŞíŃü»ńŞŹň«ëň«ÜŃüźŃü¬ŃéŐŃéäŃüÖŃüĆŃÇüňżîšÂÜŔ╗ŐŔ╝îŃééŃé«Ńâ¬Ńé«Ńâ¬Ńü«Ńé╣ŃâöŃâ╝ŃâëŃéĺšÂşŠîüŃüŚŃüŽŃÇüŃâęŃéĄŃâ│ňĆľŃéŐŃéĺŃüŚŃü¬ŃüîŃé늪ŤÚÇčŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇéŃüôŃü«ň▒ÇÚŁóŃüžňëŹŔ╗ŐŃüîňżîšÂÜŃü«ňőĽŃüŹŃüźňĆŹň┐ťŃüŚŃüŽÚÇ▓ŔĚ»ŃéĺňĄëŃüłŃéőŃüĘŃÇüňżîšÂÜŃüźŠÇąňłÂňőĽŃéäňŤ×Úü┐ŠôŹńŻťŃéĺň╝ĚŃüäŃüŽń║őŠĽůŃâ¬Ńé╣Ńé»ŃüîńŞÇŠ░ŚŃüźÚźśŃüżŃéŐŃüżŃüÖŃÇéŃüéŃéĆŃüŤŃüŽŃÇüŔĄçŠĽ░ňŤ×Ńü«ŃâęŃéĄŃâ│ňĄëŠŤ┤ŃüźŃéłŃéőÔÇťŔŤçŔíîÔÇŁŃéĺŠŐĹŠşóŃüÖŃéőŃüôŃüĘŃüžŃÇüÚś▓ňżíŃü»1ňŤ×ŃüĘŃüäŃüćŃâĽŃéžŃéóŃâŚŃâČŃâ╝Ńü«ňč║Š║ľŃééŠőůń┐ŁŃüĽŃéîŃüżŃüÖŃÇé
ň«čňőÖŃü«šëęňĚ«ŃüŚ´╝ÜŠŁíŠľçÔćĺŃéČŃéĄŃâëŃâęŃéĄŃâ│Ôćĺń║őň«čŔ¬Źň«Ü

2016ň╣┤ŃÇüňŻôŠÖéŃü«ŃâČŃâ╝Ńé╣ŃâçŃéúŃâČŃé»Ńé┐Ńâ╝ŃüžŃüéŃüúŃüčŃâüŃâúŃâ╝Ńâ¬Ńâ╝Ńâ╗ŃâŤŃâ»ŃéĄŃâćŃéúŃâ│Ńé░Š░ĆŃüîŃÇîŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâ│Ńé░ńŞşŃü«Šľ╣ňÉĹŔ╗óŠĆŤŃü»ÔÇťšĽ░ňŞŞÔÇŁŃüĘŃüŚŃüŽňá▒ňĹŐŃüÖŃéőŃÇŹŠŚĘŃéĺňÉäŃâüŃâ╝ŃâáŃüŞÚÇÜÚüöŃüŚŃüŽń╗ąÚÖŹŃÇüF1ŃüžŃü»ŃüôŃü«Ŕźľšé╣ŃüîňÄ│Šá╝ŃüźÚüőšöĘŃüĽŃéîŃüŽŃüŹŃüżŃüŚŃüčŃÇé2025ň╣┤ŠÖéšé╣ŃüžÚüőšöĘŃüĽŃéîŃüŽŃüäŃéőŠťÇŠľ░šëłŃü«ŃâëŃâęŃéĄŃâôŃâ│Ńé░Ńâ╗Ńé╣Ńé┐Ńâ│ŃâÇŃâ╝ŃâëŃâ╗ŃéČŃéĄŃâëŃâęŃéĄŃâ│Ńü»ŃÇüŃüŁŃü«ŔÇâŃüłŠľ╣ŃéĺŠö╣ŃéüŃüŽŔĘÇŔ¬×ňîľŃüŚŃÇüŃÇŤÚÇčŃüîňžőŃüżŃüúŃüčňżîŃü»´╝łŃâČŃâ╝ŃéĚŃâ│Ńé░ŃâęŃéĄŃâ│Ŕ┐ŻňżôŃéĺÚÖĄŃüŹ´╝늾╣ňÉĹŔ╗óŠĆŤŃéĺŃüŚŃü¬ŃüäŃÇŹŠŚĘŃé劜ÄŔĘśŃüŚŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
ň«čňőÖńŞŐŃÇüŃé╣ŃâüŃâąŃâ»Ńâ╝ŃâëŃü»ŠČíŃü«ŔŽ│šé╣Ńüžń║őň«čŔ¬Źň«ÜŃéĺŔíîŃüúŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃÇé
- ŠŞŤÚÇčŃâĽŃéžŃâ╝Ńé║Ńü«Úľőňžőšé╣´╝łŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâŁŃéĄŃâ│Ńâł´╝ëŃü»ŃüęŃüôŃüő´╝ĆŃüŁŃüôŃüőŃéëňőĽŃüäŃüŽŃüäŃü¬ŃüäŃüő
- šŤŞň»żńŻŹšŻ«Ńâ╗šŤŞň»żÚÇčň║ŽňĚ«´╝łŃüęŃéîŃüáŃüĹńŞŽŃéôŃüžŃüäŃüčŃüőŃÇüňŹ▒ÚÖ║ŃéĺšöčŃüśŃüĽŃüŤŃüčŃüő´╝ë
- ňŤ×Úü┐ŔíîňőĽŃü«Šťëšäí´╝łŠÇąŠŞŤÚÇčŃÇüŃé│Ńâ╝Ńé╣ňĄľňŤ×Úü┐Ńü¬Ńüę´╝ë
- ńŞÇÚÇúŃü«ňőĽŃüŹŃüîń║łŔŽőňĆ»ŔâŻŃüáŃüúŃüčŃüő´╝łÔÇťňĆŹň┐ťÔÇŁŃüžŃü»Ńü¬ŃüĆń║őňëŹŃü«ÔÇťÚüŞŠŐ×ÔÇŁŃüő´╝ë
- ÚüĽňĆŹŠÖéŃü«ŠĘÖŠ║ľŃâÜŃâŐŃâźŃâćŃéúš»äňŤ▓´╝łŔşŽňĹŐ´Ż×5šžĺňŐáš«Ś´Ż×ŃâöŃââŃâłŃé╣ŃâźŃâ╝šşë´╝ëŃü«ňŽąňŻôŠÇž
COTA 2025Ńü«ń║őńżő´╝ÜŃü¬ŃüťŔ¬┐Šč╗Ńâ╗ňçŽňłćŃüźŔç│ŃéëŃü¬ŃüőŃüúŃüčŃü«Ńüő
Ŕžĺšö░ÚüŞŠëőŃü«ŃâçŃéúŃâĽŃéžŃâ│Ńé╣Ńüźň»żŃüŚŃüŽŃâÖŃéóŃâ×Ńâ│ÚüŞŠëőŃüîŃÇîŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâ│Ńé░ńŞşŃü«ŃâęŃéĄŃâ│ňĄëŠŤ┤ŃüáŃÇŹŃüĘńŞŹŠ║ÇŃéĺŔ┐░Ńü╣ŃüżŃüŚŃüčŃÇéńŞÇŠľ╣ŃüžŃé╣ŃâüŃâąŃâ»Ńâ╝ŃâëŃü»Ŕ¬┐Šč╗ŃüźšŁÇŠëőŃüŤŃüÜŃÇüŃâČŃâ╝ŃéĚŃâ│Ńé░ŃéĄŃâ│ŃéĚŃâçŃâ│ŃⳊë▒Ńüä´╝łŠśÄšó║Ńü¬ÚüĽňĆŹŃüžŃü»Ńü¬ŃüĆŃÇüŃâČŃâ╝Ńé╣ńŞşŃü«Ŕ笚äÂŃü¬ňç║ŠŁąń║ő´╝ëŃüĘŃüŚŃÇüŃâÜŃâŐŃâźŃâćŃéúŃü»Ńü¬ŃüŚŃüĘŃüŚŃüżŃüŚŃüčŃÇé
ŃüŁŃü«šÉćšö▒ŃüĘŃüŚŃüŽŃü»
- Ŕžĺšö░ÚüŞŠëőŃü«ňőĽŃüŹŃüŤÚÇčÚľőňžőňżîŃü«ÔÇťňĆŹň┐ťšÜäŃü¬ŃâľŃâşŃââŃé»ÔÇŁŃüžŃü»Ńü¬ŃüĆŃÇüŠâ│ň«ÜňĆ»ŔâŻŃü¬Úś▓ňżíŃâęŃéĄŃâ│ŃüŞŃü«ÚüŞŠŐ×ŃüźšĽÖŃüżŃéőŃüĘŔęĽńżíŃüĽŃéîŃüč
- ŃâÖŃéóŃâ×Ńâ│ÚüŞŠëőŃü«ňëŹňżîńŻŹšŻ«Ńâ╗ńŞŽŃü│ŃüőŃüĹň║ŽňÉłŃüäŃüîňŤ×Úü┐Ńéĺň╝ĚŔŽüŃüĽŃéîŃüčŃüĘŠľşň«ÜŃüÖŃéőŃüźŔÂ│ŃéőŃâČŃâÖŃâźŃüźÚüöŃüŚŃüŽŃüäŃü¬ŃüőŃüúŃüč
ÔÇĽÔÇĽŃü¬ŃüęŃü«ňĆ»Ŕ⯊ǞŃüîŔÇâŃüłŃéëŃéîŃüżŃüÖŃÇé
šÁÉň▒ÇŃü«ŃüĘŃüôŃéŹŃÇüŠŁíŠľçŃü»ňÉîŃüśŃüžŃééÔÇťń║őň«čŔ¬Źň«ÜÔÇŁŃüžšÁÉŔźľŃüîňłćŃüőŃéîňżŚŃéőŃüôŃüĘŃé嚥║ŃüŚŃüčŃé▒Ńâ╝Ńé╣ŃüáŃüĘŃüäŃüłŃüżŃüÖŃÇé
ň«čňőÖŃü«ŃâüŃéžŃââŃé»ŃâŁŃéĄŃâ│Ńâł
ň«čÚÜŤŃüźŃüęŃéôŃü¬ňőĽŃüŹŃüîŃéóŃéŽŃâłŃüžŃÇüŃüęŃéôŃü¬ňőĽŃüŹŃü¬ŃéëŃé╗Ńâ╝ŃâĽŃü¬Ńü«ŃüőŃÇéňłŁň┐âŔÇůŃüźŃééňłĄŠľşŃüŚŃéäŃüÖŃüäŃéłŃüćŃÇüňůŞň×őšÜäŃü¬ŃâĹŃé┐Ńâ╝Ńâ│Ńé劼┤šÉćŃüÖŃéőŃüĘŠČíŃü«ŃüĘŃüŐŃéŐŃüžŃüÖŃÇé
Ôľá NGŃü«ňůŞň×ő
- ňżîšÂÜŃü«š¬üŃüúŔż╝Ńü┐ŃéĺŔŽőŃüŽŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâ│Ńé░ňżîŃüźňĆŹň┐ťŃüŚŃüŽňí×ŃüÉ´╝ł=ňŤ×Úü┐ň╝ĚŔŽü´╝ë
- ŔĄçŠĽ░ňŤ×Ńü«ŃâęŃéĄŃâ│ňĄëŠŤ┤´╝łŃé╣Ńâ¬ŃââŃâŚňłçŃéŐŃü«ŔŤçŔíîŃéĺňÉźŃéÇ´╝ë
- ňĄľňü┤Ńüžň«łŃüúŃüčňżîŃüźŃâČŃâ╝ŃéĚŃâ│Ńé░ŃâęŃéĄŃâ│ŃüŞŠł╗ŃéőÚÜŤŃÇü1ňĆ░ňłćŃü«Ńé╣ŃâÜŃâ╝Ńé╣Ńé劫őŃüĽŃü¬Ńü䊳╗ŃéŐŠľ╣´╝łISCÚÖäňëçL šČČIVšźá šČČ2ŠŁí´╝ĆF1ŃéČŃéĄŃâëŃâęŃéĄŃâ│Ńü«ŔÂúŠŚĘŃüźňĆŹŃüŚŃüżŃüÖ´╝ë
Ôľá ŔĘ▒ň«╣ŃüĽŃéîňżŚŃéőńżő´╝łšŐŠ│üŠČíšČČ´╝ë
- ŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃâ│Ńé░ňëŹŃü«ňŹśšÖ║ŃâçŃéúŃâĽŃéžŃâ│Ńé╣
- ŃâČŃâ╝ŃéĚŃâ│Ńé░ŃâęŃéĄŃâ│Ŕ┐ŻňżôŃü«ŃüčŃéüŃü«Š╗ĹŃéëŃüőŃü¬Ŕ╗îŔĚí´╝łÔÇťňĆŹň┐ťÔÇŁŃüžŃü»Ńü¬Ńüä´╝ë
- ň«ëňůĘŃü¬ŔĚŁÚŤóŃüîŃüéŃéŐŃÇüňżîšÂÜŃüîňŹüňłćŃüźńŞŽŃéôŃüžŃüäŃü¬Ńü䊫ÁÚÜÄŃüžŃü«Ńé╣Ńâ¬ŃââŃâŚňłçŃéŐ´╝łńŞÇŠČíŃü«ňőĽŃüŹŃüźÚÖÉŃéő´╝ë
ŃüżŃüĘŃéü´╝ÜŃÇŤÚÇčÚľőňžőňżîŃüźňőĽŃüőŃü¬ŃüäŃÇŹ
šÁÉŔźľŃüĘŃüŚŃüŽŃÇüšĚÜň╝ĽŃüŹŃü»ŃéĚŃâ│ŃâŚŃâźŃüžŃüÖŃÇ銪ŤÚÇčŃüîňžőŃüżŃüúŃüčŃéëňőĽŃüőŃü¬Ńüä´╝łŃâČŃâ╝ŃéĚŃâ│Ńé░ŃâęŃéĄŃâ│Ŕ┐ŻňżôŃü«Ńü┐ňĆ»´╝ëŃÇéŃüôŃéîŃüîň«ëňůĘŃéĺň«łŃéőŠťÇńŻÄŠŁíń╗ÂŃüžŃüéŃéŐŃÇüŃâĽŃéžŃéóŃü¬ňőŁŔ▓áŃü«ňč║šĄÄŃüžŃééŃüéŃéŐŃüżŃüÖŃÇéŔ┐Ĺň╣┤Ńü»ŃéČŃéĄŃâëŃâęŃéĄŃâ│Ńü«ŠśÄŠľçňîľŃüĘŃâÜŃâŐŃâźŃâćŃéúŃâČŃâ│ŃéŞŃü«ňůČÚľőŃüžÚÇĆŠśÄŠÇžŃüîÚźśŃüżŃüúŃüŽŃüäŃüżŃüÖŃüîŃÇüŠťÇšÁéňłĄŠľşŃü»Ńé¬Ńâ│ŃâťŃâ╝Ńâë´╝łŃâëŃâęŃéĄŃâÉŃâ╝ŔŽľšé╣Ńü«Ŕ╗ŐŔ╝늜áňâĆ´╝ëŃéäŃâćŃâČŃâíŃâłŃ⬴╝łŃâľŃâČŃâ╝ŃéşŃéäŠôŹŔłÁŃü«ŃâçŃâ╝Ńé┐´╝ëŃéĺňÉźŃéÇń║őň«čŔ¬Źň«ÜŃüźńżŁňşśŃüŚŃüżŃüÖŃÇé
COTAŃü«ńŞÇń╗ÂŃü»ŃÇüňÉîŃüśŠŁíŠľçŃüžŃééÚüęšöĘŃü»ÔÇťšŐŠ│üŠČíšČČÔÇŁŃüžŃüéŃéőŃüôŃüĘŃÇüŃüŁŃüŚŃüŽŃâëŃâęŃéĄŃâÉŃâ╝ŃüźŃÇîŃüäŃüĄŃâ╗ŃüęŃüôŃüžŃâ╗ŃüęŃéîŃüáŃüĹňőĽŃüĹŃéőŃüőŃÇŹŃü«Ŕç¬ŔŽÜŃüîńŞÇŠ«ÁŃüĘŠ▒éŃéüŃéëŃéîŃüŽŃüäŃéőŃüôŃüĘŃéĺŠö╣ŃéüŃüŽšĄ║ŃüŚŃüżŃüŚŃüčŃÇé
ňŻôń║őňőÖŠëÇŃüźŃéłŃéőň»żšşľŃü«ŃüöŠíłňćů
ŃâóŃâÄŃâ¬Ńé╣Š│Ľňżőń║őňőÖŠëÇŃü»ŃÇüITŃÇüšë╣ŃüźŃéĄŃâ│Ńé┐Ńâ╝ŃâŹŃââŃâłŃüĘŠ│ĽňżőŃü«ńŞíÚŁóŃüźÚźśŃüäň░éھNJǞŃé劝ëŃüÖŃéőŠ│Ľňżőń║őňőÖŠëÇŃüžŃüÖŃÇéňŻôń║őňőÖŠëÇŃüžŃü»ŃÇüŠŁ▒ŔĘ╝ŃâŚŃâęŃéĄŃâáńŞŐňá┤ń╝üŠąşŃüőŃéëŃâÖŃâ│ŃâüŃâúŃâ╝ń╝üŠąşŃüżŃüžŃÇüń║║ń║őŃâ╗ňŐ┤ňőÖš«íšÉćŃüźŃüŐŃüĹŃéőŃéÁŃâŁŃâ╝ŃâłŃéäŃÇüŃüĽŃüżŃüľŃüżŃü¬Šíłń╗ÂŃüźň»żŃüÖŃéőňąĹš┤䊍ŞŃü«ńŻťŠłÉŃâ╗ŃâČŃâôŃâąŃâ╝šşëŃéĺŔíîŃüúŃüŽŃüŐŃéŐŃüżŃüÖŃÇéŔę│ŃüŚŃüĆŃü»ŃÇüńŞőŔĘśŔĘśń║őŃéĺŃüöňĆéšůžŃüĆŃüáŃüĽŃüäŃÇé
ŃéźŃâćŃé┤Ńâ¬Ńâ╝: ITŃâ╗ŃâÖŃâ│ŃâüŃâúŃâ╝Ńü«ń╝üŠąşŠ│ĽňőÖ
Ńé┐Ńé░: Formula1