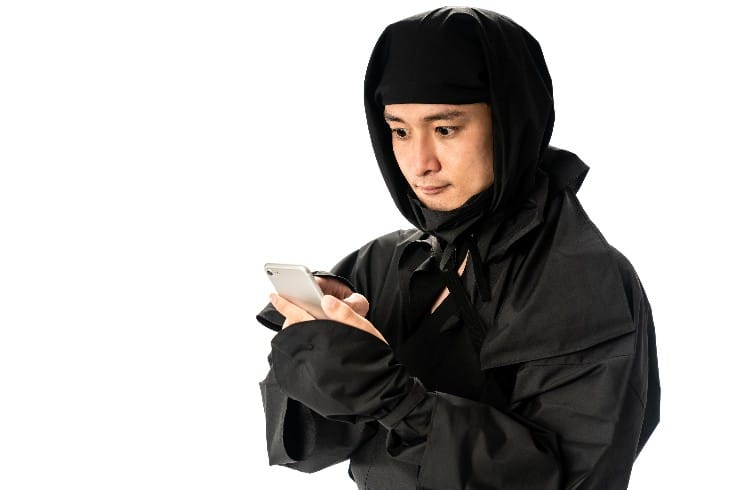景品表示法における課徴金制度とは?実際の事例を交えて対処法を解説

景品表示法(景表法)に違反すると、罰則として課徴金が課せられるケースがあります。課徴金などの行政措置が課せられると、その旨が消費者庁のサイトなどで公表されてしまうため、金銭の問題だけではなく企業のイメージ低下にもつながってしまいます。
景表法における不当表示についての正しい知識がないと、広告の作成段階でうっかり不備を見落としていたり、思いもよらない部分で景表法に抵触していたりするリスクがあります。
不当表示について理解し適切に対策しておくことで、課徴金などの措置を回避できます。この記事では、実際の事例をもとに課徴金制度について詳しく解説します。
この記事の目次
景表法における課徴金とは
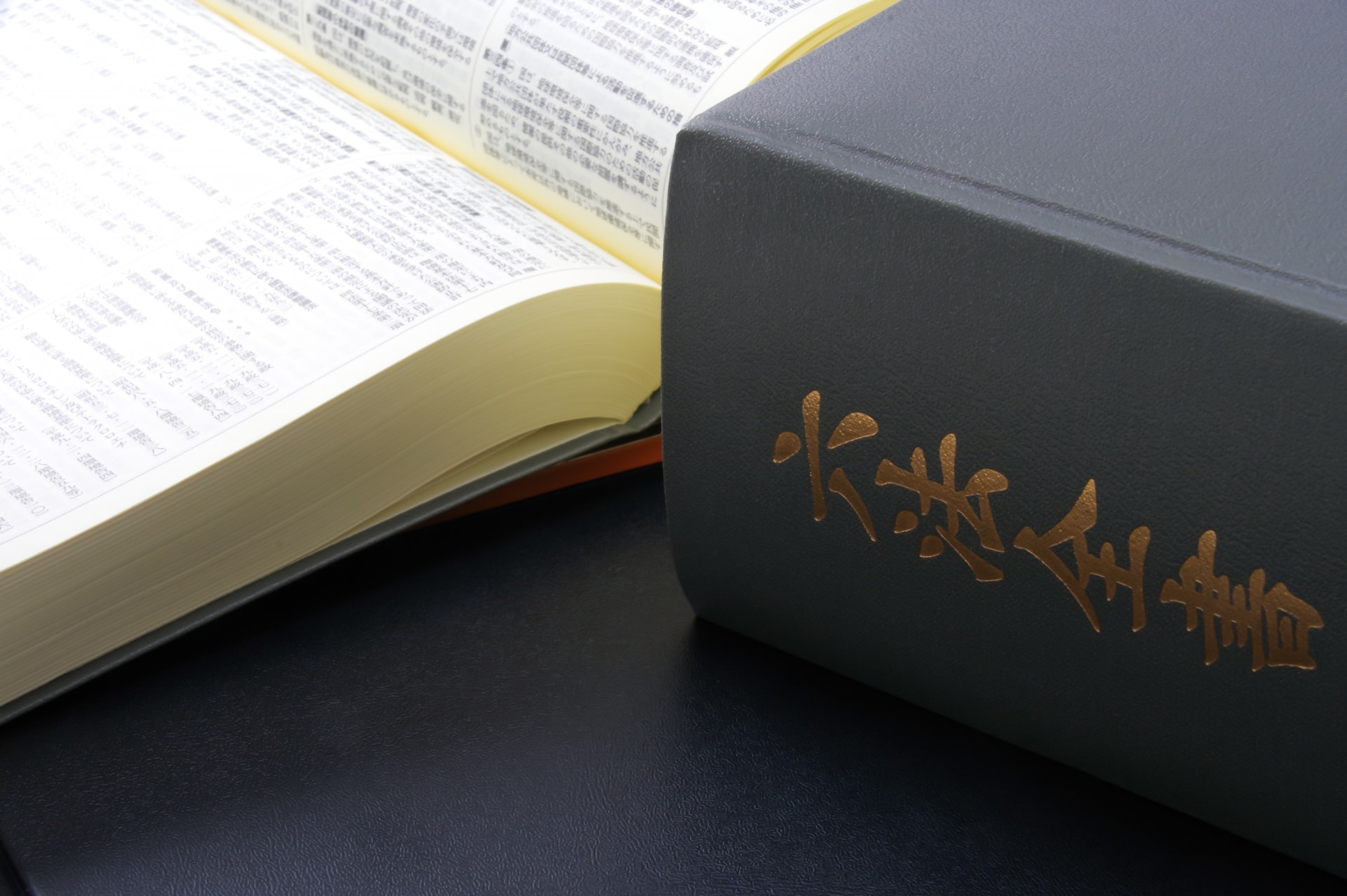
平成26年(2014年)に「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」が国会で可決され、平成28年(2016年)4月1日から施行され課徴金制度が導入されました。課徴金については下記のように記されています。
不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入するとともに、被害回復を促進する観点から返金による課徴金額の減額等の措置を講ずる
出典:消費者庁|景品表示法への課徴金制度導入について
不当な広告表示による消費者の誘導や誘引を防止するために、違反した事業者には消費者庁が制裁金として課徴金の納付を命じることができます。さらに、事業者が消費者への自主的な返金措置などを実施した場合には、課徴金の金額が減額されることも定められています。
関連記事:景品表示法(景表法)に違反するとどうなる?課徴金制度についても解説
景表法の改正に伴い課徴金制度が導入された背景
景品表示法が改正されて課徴金の納付制度が導入された背景には、2013年に日本全国で多発した食品偽装事件や食品表示等問題があります。これらの問題は、消費者の食に対する信用や安心を根底から揺るがした大きな社会問題になり、食品に関する表示などを適正化して不当表示などを抑止することを目的として、2016年に課徴金制度が導入されました。
また、刑事罰での罰金の上限が300万円であることから、金銭的な制裁が不十分との指摘があったことも課徴金制度の導入のきっかけとなっています。さらに、消費者の被害回復の促進を目的として、違反をした事業者が自主的に返金などの措置をした場合には課徴金を減額することも同時に定められました。
その後、2023年5月10日に再び景品表示法の改正案が可決され、「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」(令和5年法律第29号)によって課徴金制度の見直しや罰則規定の拡充などが新たに盛り込まれました。
景表法における課徴金納付対象となる不当表示

景品表示法における課徴金は2016年から施行された制度で、2023年に見直しの改正案が可決されるなど比較的新しい制度です。施行されてから年数があまり経っていないこともあり、どのようなケースが課徴金納付命令の対象となってしまうのか把握しておく必要があるでしょう。
課徴金の納付対象となる不当表示は、大きく分類すると優良誤認表示と有利誤認表示(景表法5条)です。この2つの違反の場合は、直罰として100万円以下の罰金を科せられることが2023年の景品表示法改正によって新設されました(景表法48条)。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、商品やサービスを実際の品質や内容よりも良く見せようとする行為です。
景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。
出典:消費者庁|事例でわかる景品表示法
商品の原材料を偽って表示したり、品質や規格を実際より良く思わせる表示をしたりする行為が優良誤認表示です。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、取引において価格・料金が他の事業者のものより消費者にとって著しく有利に思われるように不当に表示することです。値段や料金を不当に安く思わせたり、内容量を不当に多く見せたりなどが有利誤認表示にあたります。
優良誤認表示が商品の品質を良く見せる表示なのに対して、有利誤認表示は取引の条件を良く見せる表示です。
その他の不当表示
このほか、優良誤認表示や有利誤認表示だけでは表示に十分に対応することができないとされる下記の6つの告示が個別に定められています。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
これら6つにおいても、不当表示をした事業者には課徴金が科せられる場合があります。
景表法における課徴金の算定方法と納付期限

景品表示法に違反した際に科される課徴金は一律ではなく、不当表示をしていた期間や不当表示によって得た金額などによって異なります。課徴金の金額の算定方法と納付期限について解説します。
課徴金の算定方法
景品表示法違反の課徴金の金額は、不当表示の期間と売上金額から算定します。期間の算定方法は、以下の2つの期間の合計です。
- 課徴金の対象となる不当表示をしていた期間
- 不当表示をやめた日から商品・サービスの販売を停止した日までの期間
不当表示をしていた期間だけでなく、不当表示をやめたとしても、対象商品を販売し続けているとその期間も算定されてしまうのです。商品の販売を継続していても、不当表示に該当することを一般消費者に周知するなど誤認解消の措置を取れば、その日までが該当期間となります。
また、2の商品サービスの販売継続期間については最長6ヶ月まで、1と2の合計期間は最長3年までと定められています。課徴金の支払い額は、上記の「課徴金対象期間」にした不正表示による取引で得られた売上高の3%に相当する金額です(景品表示法第8条)。
課徴金の納付期限
課徴金の納付期限は、対象の事業者に「課徴金納付命令書」の謄本が発送された日から7ヶ月が経過した日です。謄本を受け取った日ではなく、発送された日から7ヶ月となるため、注意しましょう。
納付期限を過ぎても納付しなかった場合は新たな納付期限を定めた督促が来る、かつ延滞金も請求される恐れがあります。
景表法で課徴金の納付が命じられた事例3選

景品表示法で課徴金納付の対象になるケースや課徴金の算定方法について解説してきました。ここで、実際に課徴金納付の対象となった事例を3つご紹介します。具体的な事例を知ることで、対策を施す際の参考にしてみてください。
オゾン除菌消臭器に対して課徴金が課せられた事例
1つ目の事例は、マクセル株式会社のオゾン除菌消臭器の事例です。ウェブサイト上にて、「20畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」などと表記し、20畳までならどんな空間でも新型コロナウイルスを除去できるかのような表示をしていました。
消費者庁がウイルスを除去できる表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めましたが、提出された資料内容は合理的な根拠を示すものとは言えず、課徴金納付の対象となりました。
飲料の広告表示に対して課徴金が課せられた事例
2つ目の事例は、キリンビバレッジ株式会社の飲料表示の事例です。果実ミックスジュースの表示に、「厳選マスクメロン」「100%MELON TASTE」などと記載し、使われている果汁の大部分がメロン果汁であるかのように示していました。
しかし、実際にはぶどう・りんご・バナナなどメロン以外の果汁がほとんどで、メロン果汁は2%程度しか使われていないことで課徴金納付の対象となりました。
テレビショッピングに対して課徴金が課せられた事例
3つ目の事例は、株式会社TBSグロウディアのテレビ通販番組の事例です。テレビ番組のダイエット器具の紹介にて、モニターの人が使用した様子の映像とナレーションによって、1日わずか10分の使用を4週間続けるだけで、ダイエット効果があるかのように示していました。
消費者庁が裏付けとなる根拠を示す資料の提出を求めましたが、提出された資料内容は合理的な根拠を示すものとは言えず、課徴金納付の対象となりました。テレビ番組内では、使用環境や使用条件を示したほか「※効果には個人差があります」「※食事摂取に気を配り軽微な運動を併せて行った結果です」などのテロップが入っていました。
しかし、これらのテロップは前述した表示から受ける効果の印象を打ち消すほどのものではないとされ、課徴金納付の対象となったのです。
景表法違反により課徴金の納付が命ぜられそうな場合の対策

景品表示法に違反してしまって課徴金の納付対象になる不安がある場合は、早めにできる対策をとることが重要です。もし、課徴金の納付対象になってしまいそうな場合は、以下の対策をとることを検討してください。課徴金納付命令の回避や支払額の減額の可能性があります。
不実証広告規制による根拠書類の提出をする
客観的な根拠がないのに商品を良く見えるように消費者に誤認させる不当な広告表示を規制することを「不実証広告規制」と言います。優良誤認の疑いがあるときは、不実証広告規制によって消費者庁が事業者に対して表示の根拠となる裏付け資料の提出を求めることがあります(景品表示法第7条第2項)。
資料を提出して根拠があると認められれば不当表示とならず、景品表示法違反には問われません。提出する書類の内容は、実験や調査のデータ、さらに学術文献や専門家の見解など、客観的・合理的な根拠でなければなりません。
消費者庁へ不当表示に関する自主申告をする
不当表示をしていることが消費者庁から指摘される前に判明した場合は、消費者庁長官に自主的に申告・報告すると課徴金の額が2分の1に減額されます(景品表示法第9条)。
すぐに自主申告を行うことで、不当表示の対象期間が短くなって課徴金の金額をさらに減額することにつながります。高額な課徴金の支払いの命令を受けるリスクや企業イメージの損失を考慮すると、消費者庁に発覚する前に自ら申告することはメリットが大きいです。
事業者自ら返金対応を行う
不当表示で得た金額を消費者に返金する措置を取ることもできます。消費者に返金対応をする場合、「実施予定返金措置計画」を作成して消費者庁の認定を受ければ、返金する額が課徴金の額から控除されます(景品表示法第10条、第11条)。自主申告と同様に、課徴金の支払いを減額できることにつながる可能性があります。
景表法違反により課徴金納付を命じられた場合の対応方法
優良誤認や有利誤認の不当表示を認めざるを得ないのであれば、課徴金を納付したり返金対応をしたりなどの対応は仕方のないことでしょう。しかし、景品表示法違反で課徴金納付の対象になることを不服とするケースもあります。ここでは、景品表示法違反とされて課徴金を納付するよう命じられた際に、不服がある場合の対応について解説します。
審査請求による不服申し立てを行う
課徴金の納付命令が出された場合、納付命令をした消費者庁を相手に不服を申し立てることができます(行政不服審査法第4条第1号)。不服申し立てと審査請求を行うには、課徴金の納付命令が出されたことを知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求書を提出します。
取り消しを求めて訴訟を起こす
課徴金の納付命令に対して、処分を取り消すように訴訟を起こすことも可能です(行政事件訴訟法第3条第2項)。課徴金納付命令の取消訴訟は、納付命令が出されたことを知った日から6ヶ月以内に国を被告として提起します。
景表法違反でも課徴金の納付が免除されるケース

不当表示をすると景品表示法違反となりますが、全てのケースで課徴金の納付をしなければならないわけではありません。以下の3つのケースの場合は、課徴金の納付が免除されます。
- 算定された課徴金の額が150万円未満の場合(景品表示法第8条)
- 故意や重過失がない場合(景品表示法第8条)
- 不当表示をやめてから5年以上が経過していた場合(景品表示法第12条第7項)
課徴金を算定した金額が150万円未満だった場合は、課徴金を納付する義務は負いません。ただし、この金額は対象期間の売上金額から算定した金額であり、自主申告などでの減額は考えないので注意です。
課徴金の金額は対象期間の売上の3%なので、課徴金が150万円未満ということは売上が5000万円未満になります。故意や重過失がないというのは、不当表示になることを全く知らない場合や、相当の注意を怠っていないと認められる場合です。
そして、不当表示をやめる対応をとってから5年以上が経過してから過去にしていたことが発覚しても課徴金は請求されません。
これらのケースは課徴金の納付は免除されますが、不当表示については停止するなり是正するなりの対応をとらなければなりません。
事業者が課徴金納付命令を受けないために気を付けるべき3点
景品表示法に違反して課徴金の納付命令を受けてしまうと、金銭的な制裁に加えて企業イメージも大きく損なってしまうリスクがあります。課徴金の納付命令を回避するために気をつけるべきポイントを解説します。
広告内容を確認する体制を整える
広告の不当表示を避けるために、広告担当者だけで対応するのは限界があります。表示内容の確認をするセクションを設置し、社内でのダブルチェック体制を整えることが大切です。
社内研修により不当表示の理解度を高める
社内でダブルチェック体制を整えても、社員の知識が不足していてはうまく機能しません。定期的に社内研修を実施し、従業員1人1人の知識や理解、そして不当表示をしない遵法意識を作り上げていくことが重要です。
また、知識をアップデートをしていくことは、法律の変化に対応するためにも必要不可欠です。
弁護士によるリーガルチェックを行う
社内研修で、従業員1人1人の知識を深めたりアップデートしたりすることは必要ですが、関連する法律やガイドラインを正しく理解するのは難しくもあります。社内だけで広告などの表示全てに対応することは難しい側面もあるため、事前に法律の専門家である弁護士にリーガルチェックしてもらうことも有用です。
まとめ:景表法違反による課徴金制度の正しい理解を

課徴金の納付命令は、企業イメージを下げるリスクもあり、避けなければいけないことです。普段から、社内での景品表示法に対する知識を深めておき、不当表示をしない意識を高めておきましょう。
一方で社内だけで対応することが難しい場合も多く、知識不足からペナルティを受けるケースも多くあります。広告・表示に関する不安がある場合は、まずは法律の専門家である弁護士に相談してみてください。
当事務所による対策のご案内
モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。近年、ネット広告をめぐる優良誤認などの景品表示法違反は大きな問題となっており、リーガルチェックの必要性はますます増加しています。当事務所はさまざまな法律の規制を踏まえた上で、広告やLPのリーガルチェック、ガイドライン作成などのサービスを提供しています。下記記事にて詳細を記載しております。
モノリス法律事務所の取扱分野:記事・LPの薬機法等チェック
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務