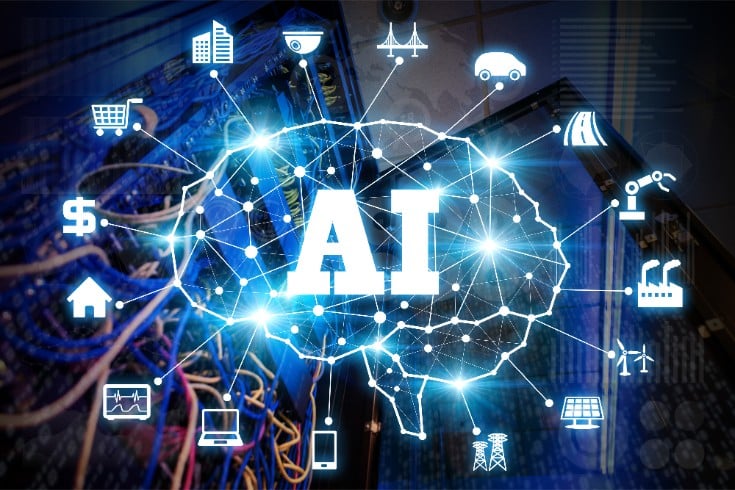ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«Õ«ÜńŠ®Ńü©µæśńÖ║õ║ŗõŠŗŃĆüµ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼

ÕøĮŃéäÕ£░µ¢╣Ķ欵▓╗õĮōŃüīµÅÉõŠøŃüÖŃéŗĶŻ£ÕŖ®ķćæŃéäÕŖ®µłÉķćæŃü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«µö┐ńŁ¢ńø«ńÜäŃéÆķüöµłÉŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ŃĆüĶ┐öµĖłõĖŹĶ”üŃü«Ķ│ćķćæŃéƵ░æķ¢ōõ╝üµźŁŃéäÕĆŗõ║║õ║ŗµźŁõĖ╗ńŁēŃü½õ║żõ╗śŃüÖŃéŗÕłČÕ║”Ńü¦ŃüÖŃĆéõ╝üµźŁŃü½Ńü©ŃüŻŃü”Ńü»ŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«Ķ│ćķćæŃü»ÕŻ▓õĖŖŃü©Ńü»ńĢ░Ńü¬ŃéŗŃĆīķøæÕÅÄÕģźŃĆŹŃü©ŃüŚŃü”Ķ©łõĖŖŃüĢŃéīŃĆüĶ┐öµĖłŃü«ńŠ®ÕŗÖŃüīŃü¬ŃüäŃü¤ŃéüŃĆüńĄīÕ¢ČŃü«Õ«ēÕ«ÜÕī¢Ńéäµ¢░Ńü¤Ńü¬µŖĢĶ│ćŃĆüµłÉķĢʵł”ńĢźŃü«Õ«¤ńÅŠŃü½ÕÉæŃüæŃü¤Õ╝ĘÕŖøŃü¬ÕŠīµŖ╝ŃüŚŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚĶ┐æÕ╣┤ŃĆüńē╣Ńü½µ¢░Õ×ŗŃé│ŃāŁŃāŖŃé”ŃéżŃā½Ńé╣µä¤µ¤ōńŚćŃü«ŃāæŃā│ŃāćŃā¤ŃāāŃé»õĖŗŃü¦Õ░ÄÕģźŃüĢŃéīŃü¤ńĘŖµĆźµĆ¦Ńü«ķ½śŃüäńĄ”õ╗śķćæ’╝łµīüńČÜÕī¢ńĄ”õ╗śķćæŃĆüÕ«ČĶ│āµö»µÅ┤ńĄ”õ╗śķćæŃĆüķøćńö©Ķ¬┐µĢ┤ÕŖ®µłÉķćæŃü¬Ńü®’╝ēŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüīµĘ▒Õł╗Ńü¬ńżŠõ╝ÜÕĢÅķĪīŃü©ŃüŚŃü”µĄ«õĖŖŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«ÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüńĄīµĖłńÜäŃü¬µēōµÆāŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤õ║ŗµźŁĶĆģŃüĖŃü«Ķ┐ģķƤŃü¬Ķ│ćķćæõŠøńĄ”ŃéƵ£ĆÕä¬ÕģłŃüŚŃü¤Ńü¤ŃéüŃĆüÕ»®µ¤╗µØĪõ╗ČŃüīµ»öĶ╝āńÜäńĘ®ÕÆīŃüĢŃéīŃĆüŃüØŃü«ķÜÖŃéÆń¬üŃüäŃü¤õĖŹµŁŻĶĪīńé║ŃüīÕżÜńÖ║ŃüÖŃéŗńĄÉµ×£Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéĶ┐ģķƤŃü¬Ķ│ćķćæõŠøńĄ”Ńüīµ▒éŃéüŃéēŃéīŃéŗńĘŖµĆźµÖéŃü½Ńü»ŃĆüÕ»®µ¤╗Ńü«ń░Īń┤ĀÕī¢ŃüīõĖŹÕÅ»ķü┐Ńü¦ŃüéŃéŗõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüŃüōŃéīŃüīõĖŹµŁŻŃü«µĖ®Õ║ŖŃü©Ńü¬ŃéŗŃü©ŃüäŃü嵦ŗķĆĀńÜäŃü¬Ķ¬▓ķĪīŃüīµĄ«ŃüŹÕĮ½ŃéŖŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«õ║ŗµģŗŃü»ŃĆüµö┐ńŁ¢ń½ŗµĪłĶĆģŃüīµö»µÅ┤Ńü«Ķ┐ģķƤµĆ¦Ńü©õĖŹµŁŻķś▓µŁóŃü«ÕĀģńēóµĆ¦Ńü©ŃüäŃüåõ║īÕŠŗĶāīÕÅŹŃü«ŃāÉŃā®Ńā│Ńé╣ŃéÆŃüäŃüŗŃü½ÕÅ¢ŃéŗŃüŗŃü©ŃüäŃüåŃĆüµĀ╣µ£¼ńÜäŃü¬ÕĢÅķĪīµÅÉĶĄĘŃéÆÕɽŃéōŃü¦ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü¦Ńü»ŃĆüĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«Õ«ÜńŠ®Ńéäõ╝üµźŁŃüīõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«µ│ĢńÜäŃü¬Ńā¬Ńé╣Ńé»Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ķ®│ŃüŚŃüÅĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü©Ńü»’╝¤Õ«ÜńŠ®Ńü©õĖ╗Ķ”üŃü¬µēŗÕÅŻ
ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃéÆÕÅŚŃüæÕÅ¢ŃüŻŃü¤ķÜøŃü½Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬ĶĪīńé║ŃéÆŃüÖŃéŗŃü©ŃĆīõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃĆŹŃü©ŃüĢŃéīŃéŗŃü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆéŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüŃüØŃü«µ│ĢńÜäŃü¬Õ«ÜńŠ®Ńü©ŃĆüÕ«¤ķÜøŃü½ĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃéŗõĖ╗Ńü¬µēŗÕÅŻŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¬¼µśÄŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«µ│ĢńÜäÕ«ÜńŠ®Ńü©ŃĆīõĖŹµŁŻŃü«ĶĪīńé║ŃĆŹŃü«ń»äÕø▓
ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü»ŃĆüŃĆīÕüĮŃéŖŃüØŃü«õ╗¢õĖŹµŁŻŃü«ĶĪīńé║Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüµ£¼µØźÕÅŚŃüæŃéŗŃüōŃü©Ńü«Ńü¦ŃüŹŃü¬ŃüäĶŻ£ÕŖ®ķćæńŁēŃü«õ║żõ╗śŃéÆÕÅŚŃüæŃĆüÕÅłŃü»ÕÅŚŃüæŃéłŃüåŃü©ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃĆŹŃü©Õ«ÜńŠ®ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«Õ«ÜńŠ®Ńü½ŃüŖŃüäŃü”ķćŹĶ”üŃü¬Ńü«Ńü»ŃĆüÕ«¤ķÜøŃü½ÕŖ®µłÉķćæŃéÆÕÅŚńĄ”ŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüÅŃü”ŃééŃĆüõĖŹµŁŻŃéÆńø«ńÜäŃü½ńö│Ķ½ŗŃüŚŃü¤µ«ĄķÜÄŃü¦õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü½Ķ®▓ÕĮōŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüåńé╣Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüżŃüŠŃéŖŃĆüńö│Ķ½ŗµøĖķĪ×Ńü«ÕüĮķĆĀŃéäĶÖÜÕüĮŃü«ńö│ÕæŖŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤µÖéńé╣Ńü¦ŃĆüõĖŹµŁŻĶĪīńé║Ńü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õĖŹµŁŻĶĪīńé║Ńü«Ķ▓¼õ╗╗Ńü»ŃĆüńö│Ķ½ŗŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤õ║ŗµźŁõĖ╗Ńü«õ╗ŻĶĪ©ĶĆģŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüõ║ŗµźŁõĖ╗Ńü«ÕĮ╣ÕōĪŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃĆüõ╗ŻńÉåõ║║ŃĆüńö│Ķ½ŗµøĖķĪ×Ńü«õĮ£µłÉŃü½ķ¢óŃéÅŃüŻŃü¤ĶĆģŃĆüŃüĢŃéēŃü½Ńü»Ķ©ōńĘ┤Õ«¤µ¢Įµ®¤ķ¢óŃü¬Ńü®ŃüīõĖŹµŁŻĶĪīńé║Ńü½ķ¢óõĖÄŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃééŃĆüÕĮōĶ®▓õ║ŗµźŁõĖ╗ŃüīõĖŹµŁŻĶĪīńé║ŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤Ńü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃĆüķĆŻÕĖ»ŃüŚŃü”Ķ▓¼õ╗╗ŃéÆÕĢÅŃéÅŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæÕłČÕ║”ŃüīÕģ¼ńÜäĶ│ćķćæŃéƵē▒ŃüåµĆ¦Ķ│¬õĖŖŃĆüŃüØŃü«ķü®µŁŻŃü¬ķüŗńö©Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗńżŠõ╝ÜńÜäŃü¬Ķ”üĶ½ŗŃüīµźĄŃéüŃü”ķ½śŃüäŃü¤ŃéüŃü¦ŃüÖŃĆé
ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü½Ńü»ŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬µēŗÕÅŻŃüīÕŁśÕ£©ŃüŚŃĆüŃüØŃü«ÕĘ¦Õ”ÖÕī¢ŃüīķĆ▓ŃéōŃü¦ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõ╗źõĖŗŃü½õĖ╗Ńü¬ķĪ×Õ×ŗŃü©ÕģĘõĮōńÜäŃü¬õ║ŗõŠŗŃéƵīÖŃüÆŃüŠŃüÖŃĆé
ĶÖÜÕüĮńö│Ķ½ŗŃā╗ĶÖÜÕüĮÕĀ▒ÕæŖ
ĶÖÜÕüĮńö│Ķ½ŗŃā╗ĶÖÜÕüĮÕĀ▒ÕæŖŃü©Ńü»ŃĆüńö│Ķ½ŗµøĖķĪ×Ńü½õ║ŗÕ«¤Ńü©ńĢ░Ńü¬ŃéŗµāģÕĀ▒ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüÖŃéŗĶĪīńé║Õģ©Ķł¼ŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½Ńü»ŃĆüÕ«¤ķÜøŃü½Ńü»ÕŁśÕ£©ŃüŚŃü¬Ńüäõ║ŗµźŁÕåģÕ«╣ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüÖŃéŗŃĆüÕŠōµźŁÕōĪµĢ░ŃéäÕŻ▓õĖŖķ½śŃéÆÕüĮŃüŻŃü”ÕĀ▒ÕæŖŃüÖŃéŗ’╝łõŠŗ’╝ÜÕŻ▓õĖŖŃéÆķüÄÕ░æńö│ÕæŖŃüŚŃĆüÕÅŚńĄ”Ķ”üõ╗ČŃéƵ║ĆŃü¤ŃüÖŃéłŃüåŃü½Ķ”ŗŃüøŃüŗŃüæŃéŗŃĆüÕŠōµźŁÕōĪµĢ░ŃéƵ░┤ÕóŚŃüŚŃüÖŃéŗ’╝ēŃü©ŃüäŃüŻŃü¤µēŗÕÅŻŃüīÕɽŃüŠŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüõ║ŗµźŁŃü«ÕŁśńČÜńŖȵ│üŃéÆÕüĮŃéŗĶĪīńé║ŃééĶ®▓ÕĮōŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ķøćńö©ķ¢óõ┐éÕŖ®µłÉķćæŃü¦Ńü»ŃĆüõ╝æµźŁŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜõ╝æµźŁŃüŚŃü¤Ńü©ÕüĮŃüŻŃü”ńö│Ķ½ŗŃüÖŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕżÜńÖ║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ¢░Õ×ŗŃé│ŃāŁŃāŖŃé”ŃéżŃā½Ńé╣ķ¢óķĆŻŃü«ńĄ”õ╗śķćæŃü¦Ńü»ŃĆüõ║ŗµźŁÕ«¤µģŗŃüīŃü¬ŃüäÕŁ”ńö¤ŃéäŃāĢŃā¬Ńā╝Ńé┐Ńā╝ŃüīÕĆŗõ║║õ║ŗµźŁõĖ╗Ńü©ÕüĮŃüŻŃü”ńö│Ķ½ŗŃüÖŃéŗõ║ŗõŠŗŃééÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«ĶĪīńé║Ńü»ŃĆüńö│Ķ½ŗµ«ĄķÜÄŃü¦ĶÖÜÕüĮŃü«õ║ŗÕ«¤ŃéÆńö│ÕæŖŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüµ£¼µØźÕÅŚńĄ”Ķ│ćµĀ╝Ńü«Ńü¬ŃüäĶ│ćķćæŃéÆÕŠŚŃéłŃüåŃü©ŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
ńĄīĶ▓╗Ńü«µ░┤ÕóŚŃüŚŃā╗µ×Čń®║Ķ©łõĖŖ
ńĄīĶ▓╗Ńü«µ░┤ÕóŚŃüŚŃā╗µ×Čń®║Ķ©łõĖŖŃü©Ńü»ŃĆüÕ«¤ķÜøŃü½Ńü»µö»Õć║ŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäńĄīĶ▓╗ŃéÆĶ©łõĖŖŃüŚŃü¤ŃéŖŃĆüńĄīĶ▓╗Ńü«ķćæķĪŹŃéÆķüÄÕż¦Ńü½ÕĀ▒ÕæŖŃüÖŃéŗĶĪīńé║Ńü¦ŃüÖŃĆéÕģĘõĮōńÜäŃü½Ńü»ŃĆüµ×Čń®║Ńü«ÕÅ¢Õ╝ĢÕģłŃü©Ńü«Ķ½ŗµ▒éµøĖŃéÆõĮ£µłÉŃüÖŃéŗŃĆüÕ«¤ķÜøŃéłŃéŖŃééķ½śķĪŹŃü¬Ķ½ŗµ▒éµøĖŃéÆÕł®ńö©ŃüÖŃéŗŃĆüµ×Čń®║Ńü«µźŁÕŗÖÕ¦öĶ©ŚŃéäń┤ŹÕōüŃéÆĶŻģŃüåŃü©ŃüäŃüŻŃü¤µēŗÕÅŻŃüīĶ”ŗŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéITÕ░ÄÕģźĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü¦Ńü»ŃĆüķĆÜÕĖĖ150õĖćÕååń©ŗÕ║”Ńü«ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃéÆ400õĖćÕååŃü©µ░┤ÕóŚŃüŚńö│Ķ½ŗŃüŚŃĆüŃüØŃü«ÕĘ«ķĪŹŃéÆŃéŁŃāāŃé»ŃāÉŃāāŃé»Ńü©ŃüŚŃü”ÕÅŚŃüæÕÅ¢ŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃééÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃéŁŃāāŃé»ŃāÉŃāāŃé»Ńā╗Õ«¤Ķ│¬ńäĪµ¢ÖŃé╣ŃéŁŃā╝ŃāĀ
ŃéŁŃāāŃé»ŃāÉŃāāŃé»Ńü©Ńü»ŃĆīÕ«¤Ķ│¬ńäĪµ¢ÖŃé╣ŃéŁŃā╝ŃāĀŃĆŹŃü©ŃééĶ©ĆŃéÅŃéīŃĆüĶ©ōńĘ┤Õ«¤µ¢Įµ®¤ķ¢óŃéäITÕ░ÄÕģźµö»µÅ┤õ║ŗµźŁĶĆģŃü¬Ńü®ŃüīŃĆüõ║ŗµźŁõĖ╗Ńü«Ķć¬ÕĘ▒Ķ▓ĀµŗģķĪŹŃéƵĖøķĪŹŃüŠŃü¤Ńü»ńäĪÕä¤Ńü½ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ŃĆüµö»µēĢŃéÅŃéīŃü¤Ķ▓╗ńö©Ńü«õĖĆķā©ŃéÆķćæķŖŁńÜä’╝łńÅŠķćæŃĆüŃé»Ńā╝ŃāØŃā│ŃĆüŃāØŃéżŃā│ŃāłŃü¬Ńü®’╝ēŃü½ķé䵥üŃüĢŃüøŃéŗĶĪīńé║Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«ķé䵥üŃü»ŃĆüŃĆīŃé│Ńā│ŃéĄŃā½ŃāåŃéŻŃā│Ńé░µ¢ÖŃĆŹŃĆīŃéŁŃāŻŃāāŃéĘŃāźŃāÉŃāāŃé»ŃĆŹŃĆīÕ║āÕæŖÕ«Żõ╝ØŃā¼ŃāōŃāźŃā╝õ╗ŻŃĆŹŃĆīÕÅŚĶ¼øĶĆģŃü«µä¤µā│µÅÉÕć║ŃüĖŃü«Ķ¼Øńż╝ŃĆŹŃü¬Ńü®ŃĆüÕżÜµ¦śŃü¬ÕÉŹńø«Ńü¦ĶĪīŃéÅŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńüīńē╣ÕŠ┤Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüõ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃü»ŃĆüŃüōŃü«Ńé╣ŃéŁŃā╝ŃāĀŃüīŃĆīõ║ŗµźŁõĖ╗ŃüīĶ©ōńĘ┤ńĄīĶ▓╗ŃéÆÕģ©ķĪŹĶ▓ĀµŗģŃüÖŃéŗŃĆŹŃü©ŃüäŃüåÕŖ®µłÉķćæŃā╗ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü«Õ¤║µ£¼Ķ”üõ╗ČŃü½ķüĢÕÅŹŃüÖŃéŗŃü©µśÄńó║Ńü½µīćµæśŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖŹµŁŻŃüŗŃü®ŃüåŃüŗŃü«Õłżµ¢ŁŃü»ŃĆüÕŹśŃü¬ŃéŗÕĮóÕ╝ÅńÜäŃü¬ŃāüŃé¦ŃāāŃé»Ńü½ńĢÖŃüŠŃéēŃüÜŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢŃü«Õ«¤µģŗŃéäĶ│ćķćæŃü«µĄüŃéīÕģ©õĮōŃéÆń▓Šµ¤╗ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
µ×Čń®║Ńü«ÕŠōµźŁÕōĪÕÉŹńŠ®Ńü¦Ńü«ńö│Ķ½ŗŃā╗ÕÉŹńŠ®Ķ▓ĖŃüŚ
Õ«¤ķÜøŃü½ķøćńö©ŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäÕŠōµźŁÕōĪŃü«ÕÉŹÕēŹŃéÆńö│Ķ½ŗµøĖŃü½Ķ©śĶ╝ēŃüŚŃü¤ŃéŖŃĆüÕ£©ń▒ŹŃüŚŃü”ŃüäŃü¬Ńüäµ£¤ķ¢ōŃü½ńĄ”õĖÄŃéƵö»µēĢŃüŻŃü¤ŃéłŃüåŃü½ĶŻģŃüåĶĪīńé║ŃééõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüÕŖ®µłÉķćæŃü«Õ»ŠĶ▒Īõ║║µĢ░ŃéƵ░┤ÕóŚŃüŚŃüÖŃéŗńø«ńÜäŃü¦ĶĪīŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
õ║īķćŹńö│Ķ½ŗŃā╗õ║īķćŹÕÅŚńĄ”
õ║īķćŹńö│Ķ½ŗŃā╗õ║īķćŹÕÅŚńĄ”Ńü©Ńü»ŃĆüÕÉīõĖĆŃü«ńĄīĶ▓╗Ńéäõ║ŗµźŁÕåģÕ«╣Ńü¦ĶżćµĢ░Ńü«ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃéÆķćŹĶżćŃüŚŃü”ńö│Ķ½ŗŃā╗ÕÅŚńĄ”ŃüÖŃéŗĶĪīńé║ŃéƵīćŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüÕŖ®µłÉķćæŃü»ÕÉīõĖĆŃü«ńĄīĶ▓╗Ńéäõ║ŗµźŁŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”õĖĆÕ║”ŃüŚŃüŗÕł®ńö©Ńü¦ŃüŹŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ńø«ńÜäÕż¢Õł®ńö©
ńø«ńÜäÕż¢Õł®ńö©Ńü©Ńü»ŃĆüĶŻ£ÕŖ®ķćæŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤Ķ│ćķćæŃéÆŃĆüńö│Ķ½ŗŃüŚŃü¤ÕåģÕ«╣Ńü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗńø«ńÜäŃéäÕĆŗõ║║ńÜäŃü¬ńö©ķĆöŃü½Ķ╗óńö©ŃüÖŃéŗĶĪīńé║Ńü¦ŃüÖŃĆé
õŠŗŃüłŃü░ŃĆüITÕ░ÄÕģźĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü¦Õ░ÄÕģźŃüŚŃü¤µĖģµÄāŃāŁŃā£ŃāāŃāłŃéÆĶć¬Õ«ģŃü«µÄāķÖżŃü½Õł®ńö©ŃüÖŃéŗŃĆüĶ©ŁÕéÖµŖĢĶ│ćŃü«ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃéÆÕŠōµźŁÕōĪŃü«ńĄ”õĖĵö»µēĢŃüäŃü½ÕģģŃü”ŃéŗŃü©ŃüäŃüŻŃü¤õ║ŗõŠŗŃüīÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
µøĖķĪ×µö╣Ńü¢ŃéōŃā╗µ£¤ķÖɵ£¬ķüĄÕ«ł
Ķ½ŗµ▒éµøĖŃü«µŚźõ╗śŃéƵøĖŃüŹµÅøŃüłŃéŗŃĆüõ║ŗµźŁÕ«īõ║åÕĀ▒ÕæŖŃü«ķüģÕ╗ČŃĆüµłÉµ×£ńē®Ńü«µÅÉÕć║µ£¤ķÖÉŃéÆÕ«łŃéēŃü¬ŃüäŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ĶĪīńé║ŃééõĖŹµŁŻŃü©Ńü┐Ńü¬ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõ║ŗµźŁŃü«ķ¢ŗÕ¦ŗµŚźŃéäńĄéõ║åµŚźŃéÆÕüĮŃüŻŃü”ńö│ÕæŖŃüÖŃéŗĶĪīńé║ŃééĶ®▓ÕĮōŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
Ńü¬ŃéŖŃüÖŃüŠŃüŚŃā╗ń¼¼õĖēĶĆģŃü½ŃéłŃéŗõĖŹķü®ÕłćŃü¬ńö│Ķ½ŗõ╗ŻĶĪī
ĶŻ£ÕŖ®õ║ŗµźŁĶĆģĶć¬Ķ║½ŃüīĶĪīŃüåŃü╣ŃüŹńö│Ķ½ŗŃā×ŃéżŃāÜŃā╝ŃéĖŃü«ķ¢ŗĶ©ŁŃéäõ║żõ╗śńö│Ķ½ŗµēŗńČÜŃüŹńŁēŃéÆŃĆüĶŻ£ÕŖ®õ║ŗµźŁĶĆģõ╗źÕż¢ŃüīĶĪīŃüåĶĪīńé║Ńü»õĖŹķü®ÕłćŃü©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüńżŠõ╝Üõ┐ØķÖ║ÕŖ┤ÕŗÖÕŻ½Ńü«Ķ│ćµĀ╝ŃéƵīüŃü¤Ńü¬ŃüäĶĆģŃüīķøćńö©ķ¢óõ┐éÕŖ®µłÉķćæŃü«ńö│Ķ½ŗõ╗ŻĶĪīŃéÆĶĪīŃüåŃüōŃü©Ńü»ŃĆüńżŠõ╝Üõ┐ØķÖ║ÕŖ┤ÕŗÖÕŻ½µ│ĢŃü½ķüĢÕÅŹŃüÖŃéŗńŗ¼ÕŹĀµźŁÕŗÖõŠĄÕ«│Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«ńÖ║Ķ”ÜńĄīĶĘ»’╝ÜŃü¬Ńü£ŃĆīŃāÉŃā¼ŃéŗŃĆŹŃü«Ńüŗ

ĶĪīµö┐µ®¤ķ¢óŃü»ŃĆüõĖŹµŁŻĶĪīńé║ŃéÆń£ŗķüÄŃüŚŃü¬ŃüäõĮōÕłČŃéƵ¦ŗń»ēŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüØŃü«ńøŻĶ”¢Ńü«ńø«Ńü»Õ╣┤ŃĆģÕÄ│ŃüŚŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ĶĪīµö┐µ®¤ķ¢ó’╝łÕŖ┤ÕāŹÕ▒ĆŃĆüõĖŁÕ░Åõ╝üµźŁÕ║üŃü¬Ńü®’╝ēŃü½ŃéłŃéŗÕÄ│Õ»åŃü¬Õ»®µ¤╗Ńü©Õ«¤Õ£░Ķ¬┐µ¤╗
ńö│Ķ½ŗµøĖķĪ×Ńü»ŃĆüµŗģÕĮōĶüĘÕōĪŃü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüńö│Ķ½ŗÕåģÕ«╣Ńü©Õ«¤ķÜøŃü«ńŖȵ│üŃü½ń¤øńøŠńé╣ŃéäÕ«¤µģŗŃü©ńĢ░Ńü¬ŃéŗĶ©śĶ╝ēŃüīŃü¬ŃüäŃüŗŃĆüĶ®│ń┤░Ńü½ńó║Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüĶ©ōńĘ┤µŚźĶ¬īŃü½Ķ©ōńĘ┤ÕåģÕ«╣ŃüīĶ©śĶ╝ēŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¤µŚźŃüīŃĆüÕć║Õŗżń░┐Ńü¦Ńü»µ£ēńĄ”õ╝æµÜćŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃüŗŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ń¤øńøŠńé╣ŃüīĶ¬┐µ¤╗ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüĢŃéēŃü½ŃĆüķāĮķüōÕ║£ń£īŃü«ÕŖ┤ÕāŹÕ▒ĆŃéäĶŻ£ÕŖ®ķćæõ║ŗÕŗÖÕ▒ĆŃü«Õ»®µ¤╗Õ«śŃā╗ńøŻµ¤╗Õ«śŃü½ŃéłŃéŗµŖ£ŃüŹµēōŃüĪŃü«Õ«¤Õ£░Ķ¬┐µ¤╗ŃééķĀ╗ń╣üŃü½ĶĪīŃéÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ķ¬┐µ¤╗Ńü¦Ńü»ŃĆüÕć║Õŗżń░┐ŃĆüĶ│āķćæÕÅ░ÕĖ│ŃĆüÕŖ┤ÕāŹĶĆģÕÉŹń░┐ŃĆüõ╝ÜĶ©łÕĖ│ń░┐Ńü¬Ńü®Ńü«µøĖķĪ×ŃüīĶ®│ń┤░Ńü½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»ŃüĢŃéīŃĆüńö│Ķ½ŗÕåģÕ«╣Ńü©Ńü«µĢ┤ÕÉłµĆ¦Ńüīµż£Ķ©╝ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüõ╝æµźŁŃüŚŃü¤ÕŠōµźŁÕōĪŃü©ŃüŚŃü”Õ«¤ķÜøŃü½Ńü»ÕŁśÕ£©ŃüŚŃü¬Ńüäõ║║ńē®Ńü«ÕÉŹÕēŹŃüīĶ©śÕģźŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«õ║║ńē®Ńü«Õ«¤µģŗŃéÆńż║ŃüÖĶ│ćµ¢ÖŃüīĶ”ŗŃüżŃüŗŃéēŃü¬ŃüæŃéīŃü░õĖŹµŁŻŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüõ╝æµźŁõĖŁŃü«ÕŠōµźŁÕōĪŃü«µ┤╗ÕŗĢĶ©śķī▓ŃéäŃāŚŃāŁŃéĖŃé¦Ńé»Ńāłń«ĪńÉåĶĪ©Ńü¬Ńü®Ńééń┤░ŃüŗŃüÅńó║Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃĆüµźŁÕŗÖÕ«¤µģŗŃüīŃü¬ŃüäŃü»ŃüÜŃü«õ╝æµźŁõĖŁŃü½µźŁÕŗÖŃü½ķ¢óõĖÄŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ÕĮóĶĘĪŃüīĶ”ŗŃüżŃüŗŃéīŃü░ŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü©Ķ¬ŹÕ«ÜŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃééŃĆüĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü«ķü®µŁŻŃü¬Õ¤ĘĶĪīŃéƵż£µ¤╗ŃüÖŃéŗÕĮ╣Õē▓ŃéƵŗģŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüØŃü«Ķ¬┐µ¤╗Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ÕżÜŃüÅŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃü»ŃĆüńē╣Ńü½ŃéŁŃāāŃé»ŃāÉŃāāŃé»ŃéäĶÖÜÕüĮńö│Ķ½ŗŃĆüńø«ńÜäÕż¢Õł®ńö©Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤µé¬Ķ│¬Ńü¬µēŗÕÅŻŃü½ńä”ńé╣ŃéÆÕĮōŃü”Ńü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüØŃü«µīćµæśŃéÆÕÅŚŃüæŃü”ÕÉäń£üÕ║üŃéäõ║ŗÕŗÖÕ▒ĆŃüīõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«Ķ┐öķéäĶ½ŗµ▒éŃéäÕåŹńÖ║ķś▓µŁóńŁ¢ŃéÆĶ¼øŃüśŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Õåģķā©ÕæŖńÖ║Ńā╗ķĆÜÕĀ▒ÕłČÕ║”Ńü«µ┤╗ńö©
ÕŠōµźŁÕōĪŃéäÕģāÕŠōµźŁÕōĪŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢÕģłŃü¬Ńü®ŃüŗŃéēŃü«Õåģķā©ÕæŖńÖ║ŃéäµāģÕĀ▒µÅÉõŠøŃééŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüÖŃéŗõĖ╗Ķ”üŃü¬ńĄīĶĘ»Ńü«õĖĆŃüżŃü¦ŃüÖŃĆéÕŖ┤ÕāŹÕ▒ĆŃü«ŃāøŃā╝ŃāĀŃāÜŃā╝ŃéĖŃü½Ńü»ŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃéÆÕæŖńÖ║ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«Õ░éńö©µŖĢń©┐ŃāĢŃé®Ńā╝ŃāĀŃüīńö©µäÅŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕī┐ÕÉŹŃü¦Ńü«ķĆÜÕĀ▒ŃééÕÅ»ĶāĮŃü¦ŃüÖŃĆéÕżÜŃüÅŃü«ÕæŖńÖ║ŃüīÕ»äŃüøŃéēŃéīŃéŗÕŖ┤ÕāŹÕ▒ĆŃééÕŁśÕ£©ŃüŚŃĆüŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖõĖŹµŁŻŃüīµśÄŃéŗŃü┐Ńü½Õć║ŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕóŚÕŖĀŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńē╣Ńü½ŃĆüõ╝üµźŁÕåģŃü¦Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣µäÅĶŁśŃüīõĮÄŃüäÕĀ┤ÕÉłŃéäŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃüīõĖŹµ║ĆŃéƵŖ▒ŃüłŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüÕåģķā©ÕæŖńÖ║Ńü«Ńā¬Ńé╣Ńé»Ńüīķ½śŃüŠŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõĖŹµŁŻĶĪīńé║Ńü½ķ¢óõĖÄŃüŚŃü¤õ╗ŻńÉåõ║║ŃéäĶ©ōńĘ┤µ®¤ķ¢óŃü«õĖŹµŁŻŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃüōŃüŗŃéēĶŖŗŃüźŃéŗÕ╝ÅŃü½ŃĆüŃüØŃü«µźŁĶĆģŃü©ÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ŃüéŃüŻŃü¤õ╗¢Ńü«õ║ŗµźŁĶĆģŃü«õĖŹµŁŻŃé鵜ÄŃéēŃüŗŃü½Ńü¬ŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃüäŃéÅŃéåŃéŗŃéŁŃāāŃé»ŃāÉŃāāŃé»Õ×ŗŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü¬Ńü®Ńü»ŃĆüÕÉīõĖĆŃü«Ķ©ōńĘ┤Õ«¤µ¢Įµ®¤ķ¢óŃéäITÕ░ÄÕģźµö»µÅ┤õ║ŗµźŁĶĆģŃü¬Ńü®Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ĶĪīŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕżÜŃüäŃü¤ŃéüŃĆüŃĆīĶŖŗŃüźŃéŗÕ╝ÅŃĆŹŃü½õĖŹµŁŻŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüÖŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕżÜŃüäŃü©Ķ©ĆŃüłŃüŠŃüÖŃĆé
õ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃü½ŃéłŃéŗńøŻµ¤╗Ńü©µīćµæś
õ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃü»ŃĆüÕøĮŃü«õ╝ÜĶ©łńĄīńÉåŃü«ÕÉłĶ”ÅµĆ¦Ńéäµ£ēÕŖ╣µĆ¦ŃéƵż£µ¤╗ŃüÖŃéŗńŗ¼ń½ŗŃüŚŃü¤µ®¤ķ¢óŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü«µö»ńĄ”Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃééÕÄ│ŃüŚŃüÅŃāüŃé¦ŃāāŃé»ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃü«µż£µ¤╗Ńü»ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«ĶŻ£ÕŖ®ķćæÕłČÕ║”Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻŃü«Õ«¤µģŗŃéƵśÄŃéēŃüŗŃü½ŃüŚŃĆüÕÄÜńö¤ÕŖ┤ÕāŹń£üŃéäńĄīµĖłńöŻµźŁń£üŃü¬Ńü®Ńü«µēĆń«Īń£üÕ║üŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüµś»µŁŻµÄ¬ńĮ«Ńéäµö╣Õ¢äµÄ¬ńĮ«ŃéÆĶ”üµ▒éŃüÖŃéŗµ©®ķÖÉŃéƵīüŃüĪŃüŠŃüÖŃĆé
õŠŗŃüłŃü░ŃĆüITÕ░ÄÕģźĶŻ£ÕŖ®ķćæŃéäõ║║µØÉķ¢ŗńÖ║µö»µÅ┤ÕŖ®µłÉķćæŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃéŁŃāāŃé»ŃāÉŃāāŃé»ÕĢÅķĪīŃü»ŃĆüõ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃü«Ķ¬┐µ¤╗Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Õż¦Ķ”ŵ©ĪŃü¬õĖŹµŁŻŃüīµīćµæśŃüĢŃéīŃĆüÕłČÕ║”Ńü«Ķ”ŗńø┤ŃüŚŃéäÕÄ│µĀ╝Õī¢Ńü½ŃüżŃü¬ŃüīŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃü«µīćµæśŃü»ŃĆüÕŹśŃü¬ŃéŗÕĆŗÕłźŃü«õĖŹµŁŻĶĪīńé║Ńü«µæśńÖ║Ńü½ńĢÖŃüŠŃéēŃüÜŃĆüÕłČÕ║”Ķ©ŁĶ©łŃéäķüŗńö©õĖŖŃü«õĖŹÕéÖŃéƵĄ«ŃüŹÕĮ½ŃéŖŃü½ŃüŚŃĆüŃéłŃéŖÕ║āń»äŃü¬õĖŹµŁŻķś▓µŁóńŁ¢Ńü«Õ░ÄÕģźŃéÆõ┐āŃüÖÕĮ╣Õē▓ŃéƵףŃü¤ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õ╗¢Ńü«ÕŖ®µłÉķćæŃā╗ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü©Ńü«ŃāćŃā╝Ńé┐ńģ¦ÕÉł
ĶĪīµö┐µ®¤ķ¢óŃü»ŃĆüńö│Ķ½ŗŃüĢŃéīŃü¤µøĖķĪ×Ńü«ÕåģÕ«╣ŃéÆŃĆüķüÄÕÄ╗Ńü½ńö│Ķ½ŗŃüĢŃéīŃü¤õ╗¢Ńü«ÕŖ®µłÉķćæŃā╗ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü«ŃāćŃā╝Ńé┐Ńü©ńģ¦ÕÉłŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüÕÉīõĖĆŃü«ńĄīĶ▓╗Ńéäõ║ŗµźŁÕåģÕ«╣Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗõ║īķćŹńö│Ķ½ŗŃā╗õ║īķćŹÕÅŚńĄ”ŃüīŃü¬ŃüäŃüŗŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»ńö│Ķ½ŗÕåģÕ«╣Ńü½ń¤øńøŠŃüīŃü¬ŃüäŃüŗŃéÆńó║Ķ¬ŹŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéńĢ░Ńü¬ŃéŗÕłČÕ║”ķ¢ōŃü¦Ńü«ŃāćŃā╝Ńé┐Ńü«ķĆŻµÉ║ŃüīķĆ▓ŃéĆŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüõĖŹµŁŻĶĪīńé║Ńü«ńÖ║Ķ”ŗń▓ŠÕ║”Ńüīķ½śŃüŠŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«ńÖ║Ķ”ÜńĄīĶĘ»ŃüīÕżÜµ¦śÕī¢Ńā╗ÕÄ│µĀ╝Õī¢ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüÕģ¼ńÜäĶ│ćķćæŃü«ķü®µŁŻŃü¬Õł®ńö©Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗńżŠõ╝ÜÕģ©õĮōŃü«ńøŻĶ”¢ŃüīÕ╝ĘÕī¢ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃéłŃéŗŃééŃü«Ńü©Ķ©ĆŃüłŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«ÕÄ│µĀ╝Ńü¬ŃāÜŃāŖŃā½ŃāåŃéŻ

ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«ŃāÜŃāŖŃā½ŃāåŃéŻŃü»ķØ×ÕĖĖŃü½ÕÄ│ŃüŚŃüÅŃĆüķćæķŖŁńÜäĶ▓ĀµŗģŃü½ÕŖĀŃüłŃü”ŃĆüõ╝üµźŁŃü«ÕŁśńČÜŃéäÕĆŗõ║║Ńü«õ║║ńö¤Ńü½ŃüŠŃü¦µĘ▒Õł╗Ńü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüÖÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µ│ĢńÜäŃā╗ĶĪīµö┐ńÜäµÄ¬ńĮ«
- ÕŖ®µłÉķćæŃā╗ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü«Õģ©ķĪŹĶ┐öķéäŃü©ÕŖĀń«ŚķćæŃā╗Õ╗ȵ╗×ķćæ’╝ÜõĖŹµŁŻŃü½ÕÅŚńĄ”ŃüŚŃü¤ÕŖ®µłÉķćæŃā╗ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü»ŃĆüÕģ©ķĪŹĶ┐öķéäŃüīÕæĮŃüśŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ÕŖĀŃüłŃü”ŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ķĪŹŃü«2Õē▓Ńü½ńøĖÕĮōŃüÖŃéŗÕŖĀń«Śķćæ’╝łķüĢń┤äķćæ’╝ēŃü©ŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”µŚźŃü«ń┐īµŚźŃüŗŃéēĶ┐öķéäÕ«īõ║åµŚźŃüŠŃü¦Ńü«Õ╣┤3%’╝łŃüŠŃü¤Ńü»Õ╣┤10.95%Ńü¬Ńü®ŃĆüÕłČÕ║”Ńü½ŃéłŃéŖńĢ░Ńü¬Ńéŗ’╝ēŃü«Õ╗ȵ╗×ķćæŃüīĶ¬▓ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüµ£ĆńĄéńÜäŃü¬Ķ┐öķéäķĪŹŃü»ÕÅŚńĄ”ķĪŹŃü«1.3ÕĆŹõ╗źõĖŖŃü½Ńü¬ŃéŗŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- Ķ®Éµ¼║ńĮ¬’╝łÕłæµ│Ģ’╝ēŃüŖŃéłŃü│ĶŻ£ÕŖ®ķćæńŁēķü®µŁŻÕī¢µ│ĢķüĢÕÅŹŃü½ŃéłŃéŗÕłæõ║ŗńĮ░’╝ܵé¬Ķ│¬Ńü¬õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü»ŃĆüÕłæµ│Ģń¼¼246µØĪŃü«Ķ®Éµ¼║ńĮ¬Ńü½ÕĢÅŃéÅŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéĶ®Éµ¼║ńĮ¬Ńüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüµ£ĆÕż¦Ńü¦10Õ╣┤õ╗źõĖŗŃü«µŗśń”üÕłæ’╝łµć▓ÕĮ╣’╝ēŃüīń¦æŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüĶŻ£ÕŖ®ķćæńŁēŃü½õ┐éŃéŗõ║łń«ŚŃü«Õ¤ĘĶĪīŃü«ķü®µŁŻÕī¢Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗ’╝łĶŻ£ÕŖ®ķćæńŁēķü®µŁŻÕī¢µ│Ģ’╝ēŃü½ŃééķüĢÕÅŹŃüŚŃĆüÕÉīµ│Ģń¼¼29µØĪŃü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆü5Õ╣┤õ╗źõĖŗŃü«µŗśń”üÕłæŃüŠŃü¤Ńü»100õĖćÕååõ╗źõĖŗŃü«ńĮ░ķćæŃĆüŃüéŃéŗŃüäŃü»ŃüØŃü«õĖĪµ¢╣Ńüīń¦æŃüĢŃéīŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéĶÖÜÕüĮŃü«ÕĀ▒ÕæŖŃé䵿£µ¤╗µŗÆÕÉ”Ńü¬Ńü®ŃüīŃüéŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆü3õĖćÕååõ╗źõĖŗŃü«ńĮ░ķćæŃü½Õć”ŃüøŃéēŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- ķøćńö©ķ¢óõ┐éÕŖ®µłÉķćæŃü«ÕÅŚńĄ”Õü£µŁó’╝ł5Õ╣┤ķ¢ō’╝ē’╝ÜõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńüīµ▒║Õ«ÜŃüŚŃü¤µŚźŃüŗŃéē5Õ╣┤ķ¢ōŃü»ŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤ÕŖ®µłÉķćæŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅŃĆüõ╗¢Ńü«ķøćńö©ķ¢óõ┐éÕŖ®µłÉķćæŃéÆÕɽŃéĆŃüÖŃü╣Ńü”Ńü«ÕŖ®µłÉķćæŃü«ÕÅŚńĄ”Ķ│ćµĀ╝ŃüīÕü£µŁóŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕģ©ķĪŹŃüīĶ┐öń┤ŹŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüōŃü«µ£¤ķ¢ōŃü»Õ╗ČķĢĘŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- õ╝üµźŁÕÉŹŃā╗õ╗ŻĶĪ©ĶĆģÕÉŹŃā╗ķ¢óõĖÄĶĆģŃü«Õģ¼ĶĪ©’╝ÜõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüõ║ŗµźŁõĖ╗ÕÉŹŃĆüõ╗ŻĶĪ©ĶĆģÕÉŹŃĆüõ║ŗµźŁµēĆŃü«µēĆÕ£©Õ£░ŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«ÕåģÕ«╣ŃéäķćæķĪŹŃüīŃĆüµēĆń«ĪŃü«ÕŖ┤ÕāŹÕ▒ĆŃéäńĄīµĖłńöŻµźŁń£üŃü«Ńé”Ńé¦Ńā¢ŃéĄŃéżŃāłŃü¬Ńü®Ńü¦Õģ¼ĶĪ©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüĶć¬õĖ╗ńö│ÕæŖŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”õ║ŗµĪłŃü¦µö»ńĄ”ÕÅ¢µČłķĪŹŃüī100õĖćÕååõ╗źõĖŖŃü«ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”Õģ¼ĶĪ©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõ╝üµźŁÕÉŹŃü«Õģ¼ĶĪ©Ńü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃü½Ńü©ŃüŻŃü”Ķ©łŃéŖń¤źŃéīŃü¬ŃüäŃāĆŃāĪŃā╝ŃéĖŃü©Ńü¬ŃéŖŃĆüķĢʵ£¤ķ¢ōŃü½ŃéÅŃü¤ŃüŻŃü”õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«õ║ŗÕ«¤Ńüīń¤źŃéīµĖĪŃéŗŃüōŃü©Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- õ╗ŻńÉåõ║║Ńā╗ńżŠõ╝Üõ┐ØķÖ║ÕŖ┤ÕŗÖÕŻ½Ńā╗Ķ©ōńĘ┤Õ«¤µ¢Įµ®¤ķ¢óŃüĖŃü«ķĆŻÕĖ»Ķ▓¼õ╗╗Ńü©ńĮ░Õēć’╝ÜõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü½ńżŠõ╝Üõ┐ØķÖ║ÕŖ┤ÕŗÖÕŻ½Ńéäõ╗ŻńÉåõ║║ŃĆüĶ©ōńĘ┤Õ«¤µ¢Įµ®¤ķ¢óŃüīķ¢óõĖÄŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüōŃéīŃéēŃü«ķ¢óõĖÄĶĆģŃééõ║ŗµźŁõĖ╗Ńü©ķĆŻÕĖ»ŃüŚŃü”Ķ┐öķéäÕéĄÕŗÖŃéÆĶ▓ĀŃüåŃüōŃü©Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüõ║ŗµźŁµēĆŃü«ÕÉŹń¦░Ńéäµ░ÅÕÉŹŃĆüõĖŹµŁŻÕåģÕ«╣ŃüīÕģ¼ĶĪ©ŃüĢŃéīŃéŗŃü╗ŃüŗŃĆü5Õ╣┤ķ¢ōŃü»ķøćńö©ķ¢óõ┐éÕŖ®µłÉķćæŃü«ńö│Ķ½ŗŃüīÕÅŚńÉåŃüĢŃéīŃü¬ŃüÅŃü¬ŃéŗŃü¬Ńü®Ńü«ŃāÜŃāŖŃā½ŃāåŃéŻŃüīń¦æŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüÕ░éķ¢ĆÕ«ČŃüīŃüØŃü«ń¤źĶŁśŃéäń½ŗÕĀ┤ŃéƵé¬ńö©ŃüŚŃü”õĖŹµŁŻĶĪīńé║ŃéÆÕŖ®ķĢĘŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«Ķ▓¼õ╗╗Ńü»µźĄŃéüŃü”ķćŹŃüäŃü©ŃüäŃüåĶĪīµö┐Ńü«Õ¦┐ÕŗóŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńżŠõ╝ÜńÜäŃā╗ńĄīµĖłńÜäÕĮ▒ķ¤┐
- õ╝üµźŁõ┐Īńö©ÕŖøŃü«Õż▒Õó£Ńü©õ║ŗµźŁńČÖńČÜŃüĖŃü«µēōµÆā’╝Üõ╝üµźŁÕÉŹŃéäõ╗ŻĶĪ©ĶĆģÕÉŹŃüīÕģ¼ĶĪ©ŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢÕģłŃéäķĪ¦Õ«óŃüŗŃéēŃü«õ┐ĪķĀ╝ŃéÆÕż▒ŃüäŃĆüõ║ŗµźŁńČÖńČÜŃü½µĘ▒Õł╗Ńü¬ÕĢÅķĪīŃüīńö¤ŃüśŃéŗÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéķĪ¦Õ«óŃüŗŃéēŃü«Ķ▓ĘŃüäµÄ¦ŃüłŃüīńÖ║ńö¤ŃüŚŃĆüµźŁńĖŠŃüīµé¬Õī¢ŃüÖŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»Ńééķ½śŃüŠŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõĖĆÕ║”Õż▒ŃéÅŃéīŃü¤õ┐Īńö©ŃéÆÕø×ÕŠ®ŃüÖŃéŗŃü½Ńü»ŃĆüÕżÜÕż¦Ńü¬µÖéķ¢ōŃü©ÕŖ┤ÕŖøŃéÆĶ”üŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
- ķćæĶ׏µ®¤ķ¢óŃüŗŃéēŃü«Ķ®ĢõŠĪõĮÄõĖŗŃü©Ķ│ćķćæĶ¬┐ķüöŃüĖŃü«µé¬ÕĮ▒ķ¤┐’╝ܵ│Ģõ╗żŃü½ķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤õ╝üµźŁŃü©ŃüŚŃü”ķćæĶ׏µ®¤ķ¢óŃüŗŃéēŃü«Ķ®ĢõŠĪŃüīõĖŗŃüīŃéŖŃĆüµ¢░Ķ”ÅĶ׏Ķ│ćŃü«Õø░ķøŻÕī¢Ńé䵌óÕŁśĶ׏Ķ│ćµØĪõ╗ČŃü«µé¬Õī¢Ńü¬Ńü®ŃĆüĶ│ćķćæĶ¬┐ķüöŃü½µé¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüÖÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
- ĶŻ£ÕŖ®ķćæµīćիܵźŁĶĆģŃüŗŃéēŃü«ķÖżÕż¢’╝ÜITÕ░ÄÕģźĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕ░ÄÕģźµö»µÅ┤õ║ŗµźŁĶĆģŃü¬Ńü®ŃĆüńē╣Õ«ÜŃü«ĶŻ£ÕŖ®ķćæÕłČÕ║”Ńü¦µīćիܵźŁĶĆģŃü©ŃüŚŃü”ńÖ╗ķī▓ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃĆüõĖŹµŁŻĶĪīńé║ŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüÖŃéīŃü░ŃüØŃü«ńÖ╗ķī▓ŃüīÕÅ¢ŃéŖµČłŃüĢŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½ŃéłŃéŖŃĆüŃüØŃü«ÕŠīŃü«õ║ŗµźŁÕ▒Ģķ¢ŗŃü½Õż¦ŃüŹŃü¬ÕłČń┤äŃüīńö¤ŃüśŃüŠŃüÖŃĆé
õĖ╗Ķ”üŃü¬ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«ÕģĘõĮōõŠŗŃü©ńē╣ÕŠ┤
ŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüõĖ╗Ķ”üŃü¬ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕ«¤ķÜøŃü½ŃüéŃüŻŃü¤õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«ÕģĘõĮōõŠŗŃéÆŃü©ŃéŖŃüéŃüÆŃü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
ķøćńö©Ķ¬┐µĢ┤ÕŖ®µłÉķćæŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”
ķøćńö©Ķ¬┐µĢ┤ÕŖ®µłÉķćæŃü»ŃĆüµ¢░Õ×ŗŃé│ŃāŁŃāŖŃé”ŃéżŃā½Ńé╣µä¤µ¤ōńŚćŃü«ÕĮ▒ķ¤┐Ńü¦õ║ŗµźŁµ┤╗ÕŗĢŃü«ńĖ«Õ░ÅŃéÆõĮÖÕäĆŃü¬ŃüÅŃüĢŃéīŃü¤õ║ŗµźŁõĖ╗ŃüīŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃéÆõĖƵÖéńÜäŃü½õ╝æµźŁŃüĢŃüøŃĆüõ╝æµźŁµēŗÕĮōŃéƵö»µēĢŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃĆüŃüØŃü«Ķ▓╗ńö©Ńü«õĖĆķā©ŃéÆÕøĮŃüīÕŖ®µłÉŃüÖŃéŗÕłČÕ║”Ńü¦ŃüÖŃĆéŃé│ŃāŁŃāŖń”ŹŃü½ŃüŖŃüäŃü”Ńü»ŃĆüĶ┐ģķƤŃü¬µö»ńĄ”ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”µēŗńČÜŃüŹŃüīÕż¦Õ╣ģŃü½ń░Īń┤ĀÕī¢ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ń░Īń┤ĀÕī¢Ńü»ŃĆüńĘŖµĆźµÖéŃü«Õ»ŠÕ┐£Ńü©ŃüŚŃü”Ńü»õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕÉīµÖéŃü½õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«µĖ®Õ║ŖŃü©Ńü¬Ńéŗµ¦ŗķĆĀńÜäŃü¬ĶäåÕ╝▒µĆ¦ŃéÆńö¤Ńü┐Õć║ŃüŚŃü¤Õü┤ķØóŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õĖ╗Ķ”üŃü¬µēŗÕÅŻŃü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüõ╝æµźŁŃü«µ░┤ÕóŚŃüŚŃéäµ×Čń®║õ╝æµźŁŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕ«¤ķÜøŃü½Ńü»ÕŗżÕŗÖŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕŠōµźŁÕōĪŃéÆõ╝æµźŁõĖŁŃü©ÕüĮŃüŻŃü”ńö│Ķ½ŗŃüÖŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕżÜŃüÅĶ”ŗŃéēŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüõ╝æµźŁõĖŁŃü½Ķć¬Õ«ģŃüŗŃéēķĪ¦Õ«óŃü½ŃāĪŃā╝Ńā½ŃéÆķĆüõ┐ĪŃüÖŃéŗŃü¬Ńü®Ńü«µźŁÕŗÖŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Ńü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüõ╝æµźŁŃü©ŃüŚŃü”ńö│Ķ½ŗŃüÖŃéŗĶĪīńé║ŃééõĖŹµŁŻŃü¦ŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüµ×Čń®║Ńü«ÕŠōµźŁÕōĪÕÉŹńŠ®Ńü¦ńö│Ķ½ŗŃüŚŃü¤ŃéŖŃĆüõ╝æµźŁµēŗÕĮōŃéƵö»µēĢŃüŻŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüܵö»µēĢŃüŻŃü¤ŃüŗŃü«ŃéłŃüåŃü½µøĖķĪ×ŃéÆÕüĮķĆĀŃüŚŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗµēŗÕÅŻŃééńó║Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüõ╝ÜńżŠŃéÆńĄīÕ¢ČŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃéłŃüåŃü½Ķ”ŗŃüøŃüŗŃüæŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃéÆõ╝æµźŁŃüĢŃüøŃü¤ŃüōŃü©Ńü½ŃüŚŃü”ÕŖ®µłÉķćæŃéÆńö│Ķ½ŗŃüÖŃéŗŃü¬Ńü®ŃĆüŃüÖŃü╣Ńü”Ńüīµ×Čń®║Ńü«Ńé▒Ńā╝Ńé╣ŃééÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕģĘõĮōńÜäŃü¬õ║ŗõŠŗŃü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüµäøń¤źń£īŃü«ńŠÄÕ«╣ŃéĄŃāŁŃā│ķüŗÕ¢Čõ╝ÜńżŠŃüīń┤ä2Õää2,900õĖćÕååŃéÆõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüŚŃü¤Ńé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕĀ▒ŃüśŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃü«õ╝ÜńżŠŃü»ŃĆüõ╝ÜńżŠŃéÆõ╝æµźŁŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜõ╝æµźŁŃüŚŃü¤Ńü©ŃüÖŃéŗÕüĮŃü«ńö│Ķ½ŗµøĖķĪ×ŃéÆõĮ£µłÉŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
Ńé│ŃāŁŃāŖķ¢óķĆŻńĄ”õ╗śķćæ’╝łµīüńČÜÕī¢ńĄ”õ╗śķćæŃĆüÕ«ČĶ│āµö»µÅ┤ńĄ”õ╗śķćæŃü¬Ńü®’╝ēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”
µīüńČÜÕī¢ńĄ”õ╗śķćæŃéäÕ«ČĶ│āµö»µÅ┤ńĄ”õ╗śķćæŃü¬Ńü®Ńü«Ńé│ŃāŁŃāŖķ¢óķĆŻńĄ”õ╗śķćæŃü»ŃĆüµ¢░Õ×ŗŃé│ŃāŁŃāŖŃé”ŃéżŃā½Ńé╣µä¤µ¤ōńŚćŃü«ÕĮ▒ķ¤┐Ńü¦ÕŻ▓õĖŖŃüīµĖøÕ░æŃüŚŃü¤õ║ŗµźŁĶĆģŃéäŃĆüÕ«ČĶ│āĶ▓ĀµŗģŃü½Ķŗ”ŃüŚŃéĆõ║ŗµźŁĶĆģŃéƵö»µÅ┤ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ÕēĄĶ©ŁŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«ńĄ”õ╗śķćæŃééŃĆüńĘŖµĆźµĆ¦ŃéÆĶ”üŃüÖŃéŗµĆ¦Ķ│¬õĖŖŃĆüµ»öĶ╝āńÜäń░Īń┤ĀŃü¬ńö│Ķ½ŗŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣ŃüīµÄĪńö©ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«ńĘŖµĆźµĆ¦Ńü©Õ»®µ¤╗Ńü«ÕÄ│µĀ╝µĆ¦Ńü«ŃāłŃā¼Ńā╝ŃāēŃé¬ŃāĢŃüīŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«µĖ®Õ║ŖŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤Ńü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
õĖ╗Ķ”üŃü¬µēŗÕÅŻŃü»ŃĆüĶÖÜÕüĮńö│Ķ½ŗŃéäĶÖÜÕüĮÕĀ▒ÕæŖŃü¦ŃüÖŃĆéÕ«¤ķÜøŃü½Ńü»õ║ŗµźŁŃéÆÕ¢ČŃéōŃü¦ŃüäŃü¬ŃüäŃéĄŃā®Ńā¬Ńā╝Ńā×Ńā│ŃĆüÕŁ”ńö¤ŃĆüńäĪĶüĘŃü«õ║║ŃüīŃĆüĶć¬Ķ║½ŃéÆõ║ŗµźŁĶĆģŃü©ÕüĮŃüŻŃü”ńö│Ķ½ŗŃüÖŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕżÜńÖ║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõĖŁŃü½Ńü»ŃĆüŃĆīĶ╗óÕŻ▓ŃéĄŃéżŃāłŃü¦1Õø×Ńü¦Ńééńē®ŃéÆÕŻ▓ŃéīŃü░ŃāĢŃā¬Ńā╝Ńā®Ńā│Ńé╣Ńü½Ńü¬ŃéŗŃĆŹŃü©ŃüäŃüŻŃü¤Ķ¬żŃüŻŃü¤Ķ¬ŹĶŁśŃéÆĶ¬śńÖ║ŃüÖŃéŗµēŗÕÅŻŃééÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüńö│Ķ½ŗĶ”üõ╗ČŃü¦ŃüéŃéŗÕŻ▓õĖŖµĖøÕ░æńÄćŃéƵ║ĆŃü¤ŃüÖŃü¤ŃéüŃĆüÕŻ▓õĖŖŃéÆķüÄÕ░æŃü½Ķ©śĶ╝ēŃüŚŃü¤ŃéŖŃĆüµ×Čń®║Ńü«ÕŻ▓õĖŖŃéÆĶ©łõĖŖŃüŚŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗµēŗÕÅŻŃüīńö©ŃüäŃéēŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕ«ČĶ│āµö»µÅ┤ńĄ”õ╗śķćæŃü¦Ńü»ŃĆüĶ│āĶ▓ĖÕĆ¤Õźæń┤äŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅĶ│āµ¢ÖŃéÆÕ«¤ķÜøŃéłŃéŖŃééķ½śŃüÅÕüĮŃüŻŃü”ńö│Ķ½ŗŃüÖŃéŗµēŗÕÅŻŃééÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüŃā»Ńā│Ńā½Ńā╝ŃāĀŃā×Ńā│ŃéĘŃā¦Ńā│Ńü¦µ£łŃĆģ200õĖćÕååŃü«Õ«ČĶ│āŃéÆńö│Ķ½ŗŃüŚŃĆü6Ńāȵ£łŃü¦ń┤ä550õĖćÕååŃéÆõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüŚŃü¤õ║ŗõŠŗŃüīÕĀ▒ŃüśŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃéēŃü«ńĄ”õ╗śķćæÕłČÕ║”Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻŃüīÕż¦Ķ”ŵ©ĪÕī¢ŃüŚŃü¤ĶāīµÖ»Ńü½Ńü»ŃĆüńó║Õ«Üńö│ÕæŖŃü«µ¢╣µ│ĢŃü¬Ńü®ŃéƵīćńż║ŃüŚŃĆüńö│Ķ½ŗµøĖķĪ×Ńü«õĮ£µłÉŃéäńö│Ķ½ŗµēŗńČÜŃüŹŃéÆõ╗ŻĶĪīŃüÖŃéŗŃĆīµīćÕŹŚÕĮ╣ŃĆŹŃüīõ╗ŗÕ£©ŃüŚŃĆüńö│Ķ½ŗĶĆģŃü«Õż¦ÕŹŖŃüīÕż¦ÕŁ”ńö¤ŃéäõĖ╗Õ®”Ńü¬Ńü®Ńü¦ŃüéŃüŻŃü¤Ńé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕżÜµĢ░ÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéµīćÕŹŚÕĮ╣Ńü»ķ½śķĪŹŃü¬µīćÕŹŚµ¢ÖŃéÆÕŠ┤ÕÅÄŃüŚŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüīÕÅŗõ║║Ńā╗ń¤źõ║║ŃéäSNSŃéÆķĆÜŃüśŃü”ķĆŻķÄ¢ńÜäŃü½Õ║āŃüīŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüµīćÕŹŚÕĮ╣Ńüīń¼¼õĖēĶĆģŃéÆńĄ”õ╗śķćæńö│Ķ½ŗŃü½Ķ¬śŃüäŃĆüõ╗▓õ╗ŗµ¢ÖŃéÆÕÅŚŃüæÕÅ¢ŃüŻŃü”ŃĆüŃüØŃü«õĖĆķā©ŃéÆõĖ╗ńŖ»Ńü½µĖĪŃüÖŃü©ŃüäŃüåÕżÜÕ▒żńÜäŃü¬µ¦ŗķĆĀŃüīÕĮóµłÉŃüĢŃéīŃĆüńö│Ķ½ŗĶĆģŃüīŃüŁŃüÜŃü┐ń«ŚÕ╝ÅŃü½ÕóŚÕŖĀŃüŚŃĆüÕĘ©ķĪŹĶ®Éµ¼║õ║ŗõ╗ČŃü½ńÖ║Õ▒ĢŃüŚŃü¤ŃĆīŃüŁŃüÜŃü┐Ķ¼øÕ╝ÅĶ®Éµ¼║ŃĆŹŃééńó║Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāćŃéĖŃé┐Ńā½Õī¢Õ┐£µÅ┤ķÜŖõ║ŗµźŁŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”
ŃāćŃéĖŃé┐Ńā½Õī¢Õ┐£µÅ┤ķÜŖõ║ŗµźŁŃü»ŃĆüõĖŁÕ░Åõ╝üµźŁŃüīŃāåŃā¼Ńā»Ńā╝Ńé»Ńü¬Ńü®Ńü«ŃāćŃéĖŃé┐Ńā½Õī¢Ńü½ÕÅ¢ŃéŖńĄäŃéĆķÜøŃĆüITÕ░éķ¢ĆÕ«ČŃüŗŃéēŃü«ÕŖ®Ķ©ĆŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗĶ▓╗ńö©ŃéÆĶŻ£ÕŖ®ŃüÖŃéŗõ║ŗµźŁŃü¦ŃüŚŃü¤’╝ł2020Õ╣┤9µ£łŃüŗŃéē2022Õ╣┤1µ£łŃü½Õ«¤µ¢ĮŃüĢŃéīŃĆü17,245õ╗ČŃüīĶŻ£ÕŖ®ŃüĢŃéīŃü”ńĄéõ║å’╝ēŃĆé
õĖŁÕ░Åõ╝üµźŁÕ║üŃü«Ķ¬┐µ¤╗Ńü½ŃéłŃéŖŃĆü455õ╗ČŃü«õĖŹµŁŻŃüīÕłżµśÄŃüŚŃĆüń┤ä1ÕääÕååńøĖÕĮōŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńüīńó║Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«õ║ŗµźŁŃü«õĖŹµŁŻµēŗÕÅŻŃü»ŃĆüITŃé│Ńā│ŃéĄŃā½ŃāåŃéŻŃā│Ńé░Ńü©ŃüäŃüåŃĆīŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃĆŹŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü¦ŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüńē®ńÉåńÜäŃü¬Ķ©ŁÕéÖÕ░ÄÕģźŃü¬Ńü®Ńü½µ»öŃü╣Ńü”Õ«¤µģŗŃü«µŖŖµÅĪŃüīķøŻŃüŚŃüÅŃĆüµ×Čń®║Ķ½ŗµ▒éŃéäµ░┤ÕóŚŃüŚŃüīÕ«╣µśōŃü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüäŃüåńē╣µĆ¦ŃéłŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
õĖ╗Ķ”üŃü¬µēŗÕÅŻŃü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüÕ«¤ķÜøŃü½Ńü»µö»µÅ┤ŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüµö»µÅ┤ŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤Ńü©ĶÖÜÕüĮŃü«ÕĀ▒ÕæŖŃéÆŃüŚŃü”Ķ½ŗµ▒éŃüÖŃéŗŃĆīµ×Čń®║Ķ½ŗµ▒éŃĆŹŃéäŃĆüµö»µÅ┤ŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤ŃüīŃĆüŃüØŃü«µÖéķ¢ōŃéƵ░┤ÕóŚŃüŚŃüŚŃü”Ķ½ŗµ▒éŃüÖŃéŗŃĆīµö»µÅ┤µÖéķ¢ōŃü«µ░┤ÕóŚŃüŚŃĆŹŃüīµīÖŃüÆŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéń¤ŁµÖéķ¢ōŃü½õĮĢÕ║”ŃééńØƵø┐ŃüłŃü”ķĢʵÖéķ¢ōŃü«Ńé│Ńā│ŃéĄŃā½ŃéÆÕÅŚŃüæŃü¤Ńü©ÕüĮĶŻģŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ÕåÖń£¤ŃéƵƫŃéŖŃĆüĶŻ£ÕŖ®ķćæŃéÆŃüĀŃüŠŃüŚÕÅ¢ŃéŗŃé░Ńā½Ńā╝ŃāŚŃü«ÕŁśÕ£©ŃééÕĀ▒ķüōŃü¦µśÄŃéēŃüŗŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õ║ŗµźŁÕåŹµ¦ŗń»ēĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”
õ║ŗµźŁÕåŹµ¦ŗń»ēĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü»ŃĆüµ¢░ÕłåķćÄÕ▒Ģķ¢ŗŃĆüµźŁµģŗĶ╗óµÅøŃĆüõ║ŗµźŁŃā╗µźŁń©«Ķ╗óµÅøŃĆüõ║ŗµźŁÕåŹńĘ©Ńü¬Ńü®ŃĆüŃāØŃé╣ŃāłŃé│ŃāŁŃāŖŃā╗Ńé”ŃéŻŃé║Ńé│ŃāŁŃāŖµÖéõ╗ŻŃü«ńĄīµĖłńżŠõ╝ÜŃü«ÕżēÕī¢Ńü½Õ»ŠÕ┐£ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«õ╝üµźŁŃü«µĆØŃüäÕłćŃüŻŃü¤õ║ŗµźŁÕåŹµ¦ŗń»ēŃéƵö»µÅ┤ŃüÖŃéŗĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü¦ŃüÖŃĆéÕżÜķĪŹŃü«ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃüīÕŗĢŃüÅÕéŠÕÉæŃü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õĖ╗Ķ”üŃü¬µēŗÕÅŻŃü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüĶÖÜÕüĮŃü«ńö│Ķ½ŗŃüīÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü½Ńü»ŃĆüÕŻ▓õĖŖŃéäÕŠōµźŁÕōĪµĢ░Ńü«ĶÖÜÕüĮÕĀ▒ÕæŖŃĆüõĖŹµŁŻŃü¬ńĄīĶ▓╗Ńü«ńö│ÕæŖŃĆüõ║ŗµźŁŃü«ÕŁśńČÜńŖȵ│üŃü«ÕüĮĶŻģŃü¬Ńü®ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü«ńø«ńÜäÕż¢Õł®ńö©ŃééÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüńö│Ķ½ŗŃüŚŃü¤ÕåģÕ«╣Ńü©Ńü»ńĢ░Ńü¬Ńéŗńø«ńÜäŃü¦ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃéÆÕł®ńö©ŃüÖŃéŗĶĪīńé║Ńü¦ŃüÖŃĆéõŠŗŃüłŃü░ŃĆüµĖģµÄāŃāŁŃā£ŃāāŃāłŃéÆÕ░ÄÕģźŃüŚŃü¤ķŻ▓ķŻ¤Õ║ŚŃüīŃĆüŃüØŃü«ŃāŁŃā£ŃāāŃāłŃéÆÕ║ŚŃü«µÄāķÖżŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅĶć¬Õ«ģŃü«µÄāķÖżŃü½Õł®ńö©ŃüŚŃü¤õ║ŗõŠŗŃüīÕģĖÕ×ŗõŠŗŃü©ŃüŚŃü”µīÖŃüÆŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüĢŃéēŃü½ŃĆüõĖŹÕĮōŃü½ķćŻŃéŖõĖŖŃüÆŃü¤ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃéÆŃĆüµ×Čń®║Ńü«Ķ½ŗµ▒éµøĖŃü¬Ńü®ŃéÆńö©ŃüäŃü”ķ¢óõ┐éĶĆģ’╝łÕÅŗõ║║ŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢÕģłŃü¬Ńü®’╝ēŃü½ÕłåķģŹŃüÖŃéŗµēŗÕÅŻŃééńó║Ķ¬ŹŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃééŃü«ŃüźŃüÅŃéŖĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”
ŃééŃü«ŃüźŃüÅŃéŖĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü»ŃĆüõĖŁÕ░Åõ╝üµźŁŃā╗Õ░ÅĶ”ŵ©Īõ║ŗµźŁĶĆģŃüīŃĆüķØ®µ¢░ńÜäŃü¬ĶŻĮÕōüķ¢ŗńÖ║Ńéäńö¤ńöŻŃāŚŃāŁŃé╗Ńé╣µö╣Õ¢äŃü«Ńü¤ŃéüŃü«Ķ©ŁÕéÖµŖĢĶ│ćŃü¬Ńü®ŃéÆĶĪīŃüåķÜøŃü½µö»µÅ┤ŃüÖŃéŗĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü¦ŃüÖŃĆéŃééŃü«ŃüźŃüÅŃéŖĶŻ£ÕŖ®ķćæÕŹśõĮōŃü¦Ńü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”õ╗ȵĢ░Ńü«ÕģĘõĮōńÜäŃü¬µĢ░ÕĆżŃü»ńż║ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüITÕ░ÄÕģźĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü©Ńü«ķ¢óķĆŻŃü¦ŃĆüÕÉīõĖĆŃü«ķĪ¦Õ«óń«ĪńÉåŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃééŃü«ŃüźŃüÅŃéŖĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü©ITÕ░ÄÕģźĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü«õĖĪµ¢╣ŃéÆķćŹĶżćŃüŚŃü”ńö│Ķ½ŗŃüŚŃĆüÕÅŚńĄ”ŃüÖŃéŗŃĆīõ║īķćŹńö│Ķ½ŗŃĆŹŃü«õ║ŗõŠŗŃüīÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃü»ŃĆüńĢ░Ńü¬Ńéŗń£üÕ║üŃéäÕłČÕ║”ķ¢ōŃü¦Ńü«µāģÕĀ▒ķĆŻµÉ║Ńü«ķÜÖŃéÆń¬üŃüŵēŗÕÅŻŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃéŁŃāŻŃā¬ŃéóŃéóŃāāŃāŚÕŖ®µłÉķćæŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”
ŃéŁŃāŻŃā¬ŃéóŃéóŃāāŃāŚÕŖ®µłÉķćæŃü»ŃĆüķØ×µŁŻĶ”Åķøćńö©ÕŖ┤ÕāŹĶĆģŃü«ŃéŁŃāŻŃā¬ŃéóŃéóŃāāŃāŚŃéÆõ┐āķĆ▓ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµŁŻńżŠÕōĪÕī¢ŃéäĶ│āķćæĶ”ÅÕ«ÜńŁēŃü«µö╣Õ«ÜŃĆüõ║║µØÉĶé▓µłÉŃü¬Ńü®Ńü½ÕÅ¢ŃéŖńĄäŃéōŃüĀõ║ŗµźŁõĖ╗Ńü½Õ»ŠŃüŚŃü”µö»ńĄ”ŃüĢŃéīŃéŗÕŖ®µłÉķćæŃü¦ŃüÖŃĆéõ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃü«ÕĀ▒ÕæŖŃü½ŃéłŃéŗŃü©ŃĆüõ╗żÕÆī3Õ╣┤Õ║”Ńü»22õ╗ČŃü¦4,300õĖćÕååŃĆüõ╗żÕÆī4Õ╣┤Õ║”Ńü»5õ╗ČŃü¦399õĖćÕååŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õĖ╗Ķ”üŃü¬µēŗÕÅŻŃü©ŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüÕŖ®µłÉķćæŃü«Ķ”üõ╗ČŃéƵ║ĆŃü¤ŃüŚŃü”ŃüäŃü¬ŃüäŃü½ŃééŃüŗŃüŗŃéÅŃéēŃüÜŃĆüńö│Ķ½ŗÕåģÕ«╣ŃéÆÕüĮŃüŻŃü”µö»ńĄ”ŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüõ║ŗµźŁõĖ╗Ńü½õ╗ŻŃéÅŃüŻŃü”õ╗ŻńÉåõ║║Ńüīµö»ńĄ”ńö│Ķ½ŗµēŗńČÜŃüŹŃéÆĶĪīŃüŻŃü¤ķÜøŃü½ŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü½ŃüżŃü¬ŃüīŃüŻŃü¤õ║ŗõŠŗŃééÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüÕż¢ķā©Ńü«Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃéäõ╗ŻĶĪīµźŁĶĆģŃéÆõ╗ŗŃüŚŃü¤ńö│Ķ½ŗŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕģ▒ķĆÜŃü«õĖŹµŁŻŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆńż║ÕöåŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ITÕ░ÄÕģźĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”
ITÕ░ÄÕģźĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü¦Ńü»ŃĆüITÕ░ÄÕģźµö»µÅ┤õ║ŗµźŁĶĆģŃüŗŃéēõ╝üµźŁŃüĖŃü«ŃéŁŃāāŃé»ŃāÉŃāāŃé»ŃüīõĖ╗Ńü¬õĖŹµŁŻµēŗÕÅŻŃü©ŃüŚŃü”µīćµæśŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüITŃāäŃā╝Ńā½Ńü«Ķ▓╗ńö©ŃüīŃĆīÕ«¤Ķ│¬Ńé╝ŃāŁÕååŃĆŹŃü½Ńü¬ŃéŗŃéłŃüåŃü¬Ńé╣ŃéŁŃā╝ŃāĀŃüīÕĢÅķĪīĶ”¢ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ITÕ░ÄÕģźĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«Ķ©śõ║ŗŃü¦Ķ®│ŃüŚŃüÅĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ÜITÕ░ÄÕģźĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü«ŃéŁŃāāŃé»ŃāÉŃāāŃé»Ńü½ŃéłŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü©µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»
Ńā¬Ńé╣ŃéŁŃā¬Ńā│Ńé░ÕŖ®µłÉķćæŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”
Ńā¬Ńé╣ŃéŁŃā¬Ńā│Ńé░ÕŖ®µłÉķćæ’╝łõ║║µØÉķ¢ŗńÖ║µö»µÅ┤ÕŖ®µłÉķćæ’╝ēŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃééŃĆüĶ©ōńĘ┤Õ«¤µ¢Įµ®¤ķ¢óŃüŗŃéēõ╝üµźŁŃüĖŃü«ŃéŁŃāāŃé»ŃāÉŃāāŃé»Ńüīµ©¬ĶĪīŃüŚŃĆüńĀöõ┐«Ķ▓╗ńö©ŃüīŃĆīÕ«¤Ķ│¬ńäĪµ¢ÖŃĆŹŃü©Ńü¬ŃéŗµēŗÕÅŻŃüīõ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃü½ŃéłŃüŻŃü”µīćµæśŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃéīŃéēŃü«ÕłČÕ║”Ńü¦ŃééŃĆüĶÖÜÕüĮńö│Ķ½ŗŃéäńø«ńÜäÕż¢Õł®ńö©Ńü¬Ńü®Ńü«õĖŹµŁŻŃüīÕĀ▒ÕæŖŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Ńā¬Ńé╣ŃéŁŃā¬Ńā│Ńé░ÕŖ®µłÉķćæŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗŃü«Ķ©śõ║ŗŃü¦Ķ®│ŃüŚŃüÅĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ÜŃā¬Ńé╣ŃéŁŃā¬Ńā│Ńé░ÕŖ®µłÉķćæŃü«ŃéŁŃāāŃé»ŃāÉŃāāŃé»Ńü½ŃéłŃéŗõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü©µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»
õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃéƵ£¬ńäČŃü½ķś▓ŃüÉŃü¤ŃéüŃü«Õ»ŠńŁ¢Ńü©ķü®ÕłćŃü¬Õ»ŠÕ┐£

ńö│Ķ½ŗµ«ĄķÜÄŃü¦Ńü«ÕŠ╣Õ║ĢŃüŚŃü¤µ│Ģõ╗żķüĄÕ«łŃü©µŁŻńó║Ńü¬µāģÕĀ▒µÅÉõŠø
µ£ĆŃééÕ¤║µ£¼ńÜäŃü¬Õ»ŠńŁ¢Ńü»ŃĆüńö│Ķ½ŗµøĖķĪ×Ńü½ĶÖÜÕüĮŃü«ÕåģÕ«╣ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü¬ŃüäŃüōŃü©Ńü¦ŃüÖŃĆéõ║ŗµźŁÕåģÕ«╣ŃéäÕ«¤ńĖŠŃĆüńĄīĶ▓╗Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗµāģÕĀ▒Ńü»ŃĆüÕĖĖŃü½õ║ŗÕ«¤Ńü½Õ¤║ŃüźŃüŹŃĆüµŁŻńó║Ńü½ÕĀ▒ÕæŖŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéŃü¤Ńü©Ńüłµé¬µäÅŃüīŃü¬ŃüÅŃü”ŃééŃĆüĶ©śĶ╝ēŃā¤Ńé╣Ńéäńó║Ķ¬ŹõĖŹĶČ│ŃüīÕĤÕøĀŃü¦õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü©Õłżµ¢ŁŃüĢŃéīŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü½Ńü»ŃüØŃéīŃü×ŃéīÕø║µ£ēŃü«Ķ”üõ╗ČŃéäńø«ńÜäŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńö│Ķ½ŗŃüÖŃéŗÕēŹŃü½ŃĆüÕ┐ģŃüܵ£Ćµ¢░Ńü«Õģ¼Õŗ¤Ķ”üķĀśŃéäÕłČÕ║”ĶČŻµŚ©ŃéÆĶć¬ńżŠŃü¦ńó║Ķ¬ŹŃüŚŃĆüÕłČÕ║”Ńü«ńø«ńÜäŃü©Ķć¬ńżŠŃü«õ║ŗµźŁĶ©łńö╗ŃüīÕÉłĶć┤ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüŗŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéõ║ŗµźŁĶ©łńö╗Ńü«ķĆöõĖŁŃü¦ÕåģÕ«╣ŃéäńĄīĶ▓╗Ńü«õĮ┐ŃüäķüōŃü½Õżēµø┤Ńüīńö¤ŃüśŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüĶć¬ÕĘ▒Õłżµ¢ŁŃüøŃüÜŃĆüÕ┐ģŃüÜĶŻ£ÕŖ®ķćæõ║ŗÕŗÖÕ▒ĆŃü½ńøĖĶ½ćŃüŚŃĆüõ║ŗÕēŹŃü½µē┐Ķ¬ŹŃéÆÕŠŚŃéŗµēŗńČÜŃüŹŃéÆĶĪīŃüåŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆé
Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü©Ńü«ķĆŻµÉ║Ńü©õ┐ĪķĀ╝Ńü¦ŃüŹŃéŗŃāæŃā╝ŃāłŃāŖŃā╝ķüĖŃü│
ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü«ńö│Ķ½ŗµēŗńČÜŃüŹŃü»Õ░éķ¢ĆńÜäŃü¬ń¤źĶŁśŃéÆĶ”üŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüńżŠõ╝Üõ┐ØķÖ║ÕŖ┤ÕŗÖÕŻ½ŃéäĶ¬ŹÕ«Üµö»µÅ┤µ®¤ķ¢óŃü¬Ńü®Ńü«Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü©Ńü«ķĆŻµÉ║Ńüīµ£ēÕŖ╣Ńü¦ŃüÖŃĆéÕĮ╝ŃéēŃü»µøĖķĪ×õĮ£µłÉŃü«µŁŻńó║µĆ¦Ńéäńö│Ķ½ŗµ£¤ķÖÉŃü«ń«ĪńÉåŃü¬Ńü®ŃĆüń¼¼õĖēĶĆģŃü«Ķ”¢ńé╣ŃüŗŃéēķü®ÕłćŃü¬ŃéĄŃāØŃā╝ŃāłŃéƵÅÉõŠøŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
ÕēŹĶ┐░Ńü«ķĆÜŃéŖŃĆüµé¬Ķ│¬Ńü¬Ńé│Ńā│ŃéĄŃā½Ńé┐Ńā│ŃāłŃéäĶ®Éµ¼║µźŁĶĆģŃééÕŁśÕ£©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃĆīÕ«¤Ķ│¬ńäĪµ¢ÖŃĆŹŃĆī100%ÕÅŚńĄ”õ┐ØĶ©╝ŃĆŹŃü©ŃüäŃüŻŃü¤Ķ¬śŃüäŃü½Ńü»µ▒║ŃüŚŃü”õ╣ŚŃéēŃüÜŃĆüõ┐ĪķĀ╝Ńü¦ŃüŹŃéŗŃāæŃā╝ŃāłŃāŖŃā╝ŃéÆķüĖŃü│ŃüŠŃüŚŃéćŃüåŃĆé
Õåģķā©ń«ĪńÉåõĮōÕłČŃü«Õ╝ĘÕī¢Ńü©ÕŠōµźŁÕōĪŃüĖŃü«Õæ©ń¤ź
õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü»ŃĆüµé¬Ķ│¬Ńü¬Ńé│Ńā│ŃéĄŃā½Ńé┐Ńā│ŃāłŃéäĶ®Éµ¼║µźŁĶĆģŃü½ŃĆīÕĘ╗ŃüŹĶŠ╝ŃüŠŃéīŃéŗŃĆŹÕĮóŃü¦õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃééÕżÜŃüÅŃĆüńĄäń╣öÕåģķā©Ńü«ŃüÜŃüĢŃéōŃü¬ń«ĪńÉåŃéäÕŠōµźŁÕōĪŃü«Ķ¬ŹĶŁśõĖŹĶČ│ŃüŗŃéēńÖ║ńö¤ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõ╝üµźŁŃü»ŃĆüķü®ÕłćŃü¬ÕŗżµĆĀń«ĪńÉåŃĆüńĄīĶ▓╗ń▓Šń«ŚŃĆüµøĖķĪ×õ┐Øń«ĪŃü«õĮōÕłČŃéƵĢ┤ÕéÖŃüŚŃĆüõĖŹµŁŻŃü«õĮÖÕ£░ŃéÆŃü¬ŃüÅŃüÖÕ┐ģĶ”üŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ŃĆüńö│Ķ½ŗŃü½Õ┐ģĶ”üŃü¬µøĖķĪ×ŃéäĶ©╝µåæŃü»ŃĆüµö»ńĄ”µ▒║իܵŚźŃüŗŃéēĶĄĘń«ŚŃüŚŃü”5Õ╣┤ķ¢ōõ┐ØÕŁśŃüÖŃéŗńŠ®ÕŗÖŃüīŃüéŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµŁŻńó║Ńü½õ┐Øń«ĪŃüŚŃĆüµ▒éŃéüŃü½Õ┐£ŃüśŃü”ķƤŃéäŃüŗŃü½µÅÉńż║Ńü¦ŃüŹŃéŗŃéłŃüåŃü½ŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü¤ŃĆüÕŠōµźŁÕōĪŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæÕłČÕ║”Ńü«ńø«ńÜäŃéäĶ”üõ╗ČŃĆüõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«Õ«ÜńŠ®ŃĆüŃüØŃüŚŃü”õĖŹµŁŻĶĪīńé║ŃüīńÖ║Ķ”ÜŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«µĘ▒Õł╗Ńü¬ŃāÜŃāŖŃā½ŃāåŃéŻŃü½ŃüżŃüäŃü”Õæ©ń¤źÕŠ╣Õ║ĢŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéŃé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣µäÅĶŁśŃü«ÕÉæõĖŖŃü»ŃĆüÕåģķā©ÕæŖńÖ║Ńü«Ńā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆõĮĵĖøŃüŚŃĆüńĄäń╣öÕģ©õĮōŃü¦õĖŹµŁŻŃéÆĶ©▒ŃüĢŃü¬Ńüäµ¢ćÕī¢ŃéÆķåĖµłÉŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õĖŹµŁŻŃā╗õĖŹķü®µŁŻŃüīń¢æŃéÅŃéīŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü«Ķć¬õĖ╗ńö│ÕæŖŃü«ķćŹĶ”üµĆ¦
õĖćŃüīõĖĆŃĆüĶć¬ńżŠŃü¦õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü«Õ┐āÕĮōŃü¤ŃéŖŃüīŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃéäŃĆüõĖŹķü®µŁŻŃü¬ÕÅŚńĄ”Ńü¦ŃüéŃüŻŃü¤ŃüōŃü©Ńü½µ░ŚŃüźŃüäŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüķƤŃéäŃüŗŃü½Ķć¬õĖ╗ńö│ÕæŖŃéÆĶĪīŃüåŃüōŃü©ŃüīµźĄŃéüŃü”ķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
ÕŖ┤ÕāŹÕ▒ĆŃéäõ║ŗÕŗÖÕ▒ĆŃü½ŃéłŃéŗĶ¬┐µ¤╗ŃüīÕģźŃéŗÕēŹŃü½Ķć¬õĖ╗ńö│ÕæŖŃéÆĶĪīŃüäŃĆüĶ┐ģķƤŃü½Õģ©ķĪŹŃéÆĶ┐öķéäŃüÖŃéīŃü░ŃĆüÕĤÕēćŃü©ŃüŚŃü”õ╝üµźŁÕÉŹŃü«Õģ¼ĶĪ©ŃéÆÕģŹŃéīŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüÕŖĀń«ŚķćæŃéäÕ╗ȵ╗×ķćæŃüīĶ¬▓ŃüĢŃéīŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńē╣Ńü½ķćŹÕż¦ŃüŠŃü¤Ńü»µé¬Ķ│¬Ńü¬Ńé▒Ńā╝Ńé╣ŃéÆķÖżŃüŹŃĆüĶć¬õĖ╗ńö│ÕæŖŃü»µ£ĆŃééŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéÆĶ╗ĮµĖøŃü¦ŃüŹŃéŗÕ»ŠÕ┐£ńŁ¢Ńü¦ŃüÖŃĆéĶć¬õĖ╗ńö│ÕæŖŃü«µēŗķĀåŃü»õ╗źõĖŗŃü«ķĆÜŃéŖŃü¦ŃüÖŃĆé
- ķƤŃéäŃüŗŃü¬ķĆŻńĄĪ’╝Üńö│Ķ½ŗŃüŚŃü¤ķāĮķüōÕ║£ń£īÕŖ┤ÕāŹÕ▒ĆŃéäĶŻ£ÕŖ®ķćæŃü«õ║ŗÕŗÖÕ▒ĆŃü½ŃĆüŃüØŃü«µŚ©ŃéÆķƤŃéäŃüŗŃü½ķĆŻńĄĪŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
- õ║ŗÕ«¤Ńü«Ķ¬┐µ¤╗Ńü©µøĖķĪ×µÅÉÕć║’╝ÜĶć¬ŃéēÕ«¤µģŗĶ¬┐µ¤╗ŃéÆĶĪīŃüäŃĆüĶ”üõ╗ČŃü½ÕÉłĶć┤ŃüŚŃü¬ŃüäŃüōŃü©ŃüīŃéÅŃüŗŃéŗµøĖķĪ×ŃéÆÕŖ┤ÕāŹÕ▒ĆŃü½µÅÉÕć║ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
- Õ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüĖŃü«ńøĖĶ½ć’╝ÜĶŁ”Õ»¤ŃüĖŃü«Ķć¬ķ”¢ŃéäĶĪīµö┐µ®¤ķ¢óŃüĖŃü«Ķć¬õĖ╗ńö│ÕæŖŃü½õĖŹÕ«ēŃüīŃüéŃéŗÕĀ┤ÕÉłŃü»ŃĆüÕ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½µŚ®µ£¤Ńü½ńøĖĶ½ćŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīµÄ©Õź©ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü»ŃĆüĶć¬õĖ╗Ķ┐öķéäµēŗńČÜŃüŹŃü«õ╗ŻĶĪīŃéäŃĆüĶ®Éµ¼║ńĮ¬Ńü½ŃéłŃéŗķĆ«µŹĢÕø×ķü┐Ńü½ÕÉæŃüæŃü¤Õ╝üĶŁĘµ┤╗ÕŗĢŃĆüŃé▒Ńā╝Ńé╣Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Ńü»µźŁĶĆģŃüĖŃü«Ķ┐öķćæĶ½ŗµ▒éŃü¬Ńü®ŃĆüÕżÜÕ▓ÉŃü½ŃéÅŃü¤ŃéŗŃéĄŃāØŃā╝ŃāłŃéƵÅÉõŠøŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü’╝ÜĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæŃü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»Õ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½ńøĖĶ½ćŃéÆ
ĶŻ£ÕŖ®ķćæŃā╗ÕŖ®µłÉķćæÕłČÕ║”Ńü»ŃĆüõ╝üµźŁŃü«µłÉķĢĘŃü©ńĄīµĖłŃü«ńÖ║Õ▒ĢŃü½õĖŹÕÅ»µ¼ĀŃü¬Õģ¼ńÜäµö»µÅ┤ńŁ¢Ńü¦ŃüÖŃĆéŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüŃüØŃü«µü®µüĄŃéÆõ║½ÕÅŚŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½Ńü»ŃĆüÕłČÕ║”Ńü«ĶČŻµŚ©ŃéÆńÉåĶ¦ŻŃüŚŃĆüµ│Ģõ╗żķüĄÕ«łŃéÆÕŠ╣Õ║ĢŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīÕēŹµÅÉŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü»ÕŹśŃü¬ŃéŗĶ│ćķćæŃü«Ķ┐öķéäŃü½ńĢÖŃüŠŃéēŃüÜŃĆüÕĘ©ķĪŹŃü«ÕŖĀń«ŚķćæŃéäÕ╗ȵ╗×ķćæŃü«µö»µēĢŃüäŃĆüõ╝üµźŁÕÉŹŃā╗õ╗ŻĶĪ©ĶĆģÕÉŹŃü«Õģ¼ĶĪ©Ńü½ŃéłŃéŗõ┐Īńö©Õż▒Õó£ŃĆüķøćńö©ķ¢óõ┐éÕŖ®µłÉķćæŃü«ÕÅŚńĄ”Õü£µŁóŃĆüŃüĢŃéēŃü½Ńü»Ķ®Éµ¼║ńĮ¬Ńü½ŃéłŃéŗÕłæõ║ŗńĮ░ŃéäķĆ«µŹĢŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ŃĆüõ╝üµźŁŃü©ÕĆŗõ║║Ńü½Ńü©ŃüŻŃü”Õż¦ŃüŹŃü¬ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆÕÅŖŃü╝ŃüÖÕÅ»ĶāĮµĆ¦Ńü«ŃüéŃéŗĶĪīńé║Ńü¦ŃüÖŃĆé
õĖŹµŁŻĶĪīńé║Ńü»ÕĘ¦Õ”ÖÕī¢ŃüŚŃĆüÕ░éķ¢ĆÕ«ČŃéäõ╗▓õ╗ŗµźŁĶĆģŃüīķ¢óõĖÄŃüÖŃéŗŃĆīÕ«¤Ķ│¬ńäĪµ¢ÖŃĆŹŃé╣ŃéŁŃā╝ŃāĀŃéäĶÖÜÕüĮńö│Ķ½ŗŃüīµ©¬ĶĪīŃüÖŃéŗõĖƵ¢╣Ńü¦ŃĆüĶĪīµö┐µ®¤ķ¢óŃü½ŃéłŃéŗÕ»®µ¤╗õĮōÕłČŃéäõ╝ÜĶ©łµż£µ¤╗ķÖóŃü½ŃéłŃéŗńøŻµ¤╗Ńü»Õ╝ĘÕī¢ŃüĢŃéīŃĆüÕåģķā©ÕæŖńÖ║ÕłČÕ║”Ńééµ®¤ĶāĮŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖŹµŁŻĶĪīńé║Ńü»ķ½śŃüäńó║ńÄćŃü¦ńÖ║Ķ”ÜŃüŚŃĆüŃüØŃü«õ╗ŻÕä¤Ńü»µźĄŃéüŃü”Õż¦ŃüŹŃüäŃüōŃü©ŃéÆŃĆüÕģ©Ńü”Ńü«õ║ŗµźŁĶĆģŃü»ĶéØŃü½ķŖśŃüśŃéŗŃü╣ŃüŹŃü¦ŃüÖŃĆéŃüŠŃü¤ŃĆüŃééŃüŚõĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”ŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤Ńā╗ÕĘ╗ŃüŹĶŠ╝ŃüŠŃéīŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüĶć¬õĖ╗ńö│ÕæŖŃü»ŃĆüõ╝üµźŁŃü«Ńé│Ńā│ŃāŚŃā®ŃéżŃéóŃā│Ńé╣µäÅĶŁśŃéÆńż║ŃüÖĶĪīńé║Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüõ┐ĪķĀ╝Õø×ÕŠ®ŃüĖŃü«ń¼¼õĖƵŁ®Ńü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü½ŃéłŃéŗÕ»ŠńŁ¢Ńü«ŃüöµĪłÕåģ
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüITŃā╗ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Ńü©µ│ĢÕŠŗŃü«õĖĪķØóŃü½ķ½śŃüäÕ░éķ¢ĆµĆ¦ŃéƵ£ēŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦ŃüÖŃĆéÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦Ńü»ŃĆüµØ▒Ķ©╝ŃāŚŃā®ŃéżŃāĀõĖŖÕĀ┤õ╝üµźŁŃüŗŃéēŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝õ╝üµźŁŃüŠŃü¦ŃĆüŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ŃāóŃāćŃā½Ńéäõ║ŗµźŁÕåģÕ«╣ŃéƵĘ▒ŃüÅńÉåĶ¦ŻŃüŚŃü¤õĖŖŃü¦µĮ£Õ£©ńÜäŃü¬µ│ĢńÜäŃā¬Ńé╣Ńé»ŃéƵ┤ŚŃüäÕć║ŃüŚŃĆüŃā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃéĄŃāØŃā╝ŃāłŃéÆĶĪīŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéĶŻ£ÕŖ®ķćæŃéäÕŖ®µłÉķćæŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Ńü½ķ¢óķĆŻŃüÖŃéŗµźŁÕŗÖŃü½ķ¢óŃüŚŃü”Ńü»ŃĆüõĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”Ķ®│ń┤░ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü«ÕÅ¢µē▒ÕłåķćÄ’╝ÜĶŻ£ÕŖ®ķćæńŁēŃü«õĖŹµŁŻÕÅŚńĄ”Õ»ŠÕ┐£
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ