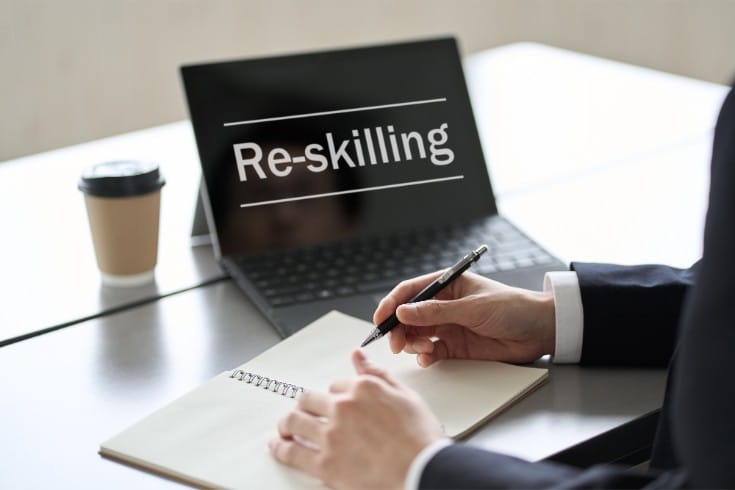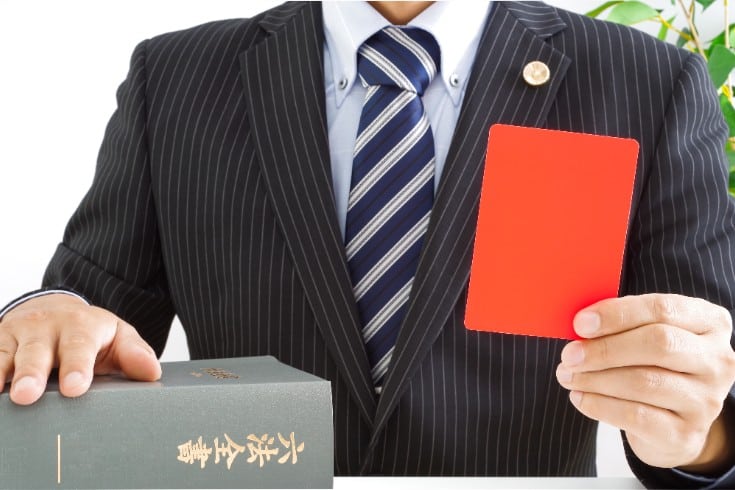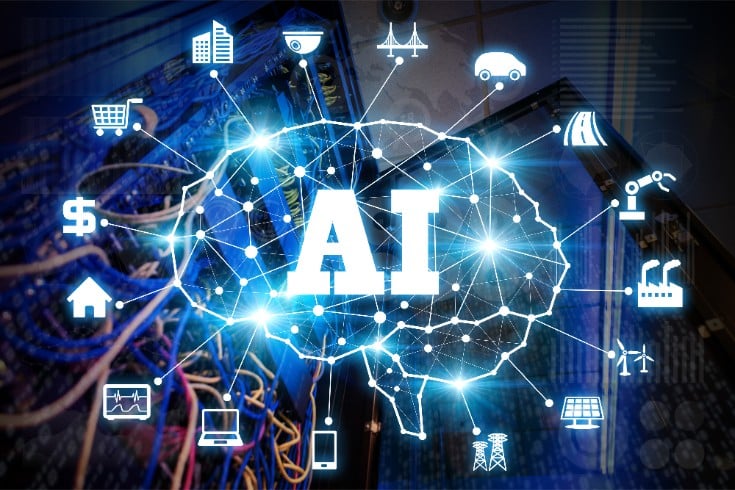сђљТюђТѓфТІўудЂтѕЉ5т╣┤сђЉтіЕТѕљжЄЉсЃ╗УБютіЕжЄЉсЂ«СИЇТГБтЈЌухдсЂДуДЉсЂЋсѓїсѓІсђїуй░тЅЄсђЇсѓњтЙ╣т║ЋУДБУфгРђЋУЕљТг║уйфсђЂтіау«ЌжЄЉсђЂт«ЪтљЇтЁгУАесЂ«сЃфсѓ╣сѓ»сЂеС╝ЂТЦГсЂ«тЈќсѓІсЂ╣сЂЇт»ЙуГќ

тЏйсѓётю░Тќ╣УЄфТ▓╗СйЊсЂїТЈљСЙЏсЂЎсѓІУБютіЕжЄЉсЃ╗тіЕТѕљжЄЉсЂ»сђЂС╝ЂТЦГухїтќХсЂФсЂесЂБсЂдУ┐ћТИѕСИЇУдЂсЂ«У▓┤жЄЇсЂфУ│ЄжЄЉТ║љсЂДсЂѓсѓісђЂС╝ЂТЦГсЂ«ТѕљжЋиТѕдуЋЦсѓёухїтќХсЂ«т«Ѕт«џтїќсѓњТћ»сЂѕсѓІжЄЇУдЂсЂфтѕХт║дсЂДсЂЎсђѓсЂЌсЂІсЂЌсђЂсЂЮсЂ«сђїУ┐ћТИѕСИЇУдЂсђЇсЂесЂёсЂєТђДУ│фсѓєсЂѕсЂФсђЂСИЇТГБтЈЌухдсЂїтЙїсѓњухХсЂЪсЂџсђЂТи▒тѕ╗сЂфуцЙС╝џтЋЈжАїсЂесЂфсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓуЅ╣сЂФсђЂТќ░тъІсѓ│сЃГсЃісѓдсѓцсЃФсѓ╣ТёЪТЪЊуЌЄсЃЉсЃ│сЃЄсЃЪсЃЃсѓ»СИІсЂДт░јтЁЦсЂЋсѓїсЂЪТїЂуХџтїќухдС╗ўжЄЉсѓёжЏЄућеУф┐ТЋ┤тіЕТѕљжЄЉсЂфсЂЕсЂ«уиіТђЦухдС╗ўжЄЉсЂ»сђЂУ┐ЁжђЪсЂфТћ»ухдсѓњтёфтЁѕсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂФт»ЕТЪ╗сЂїу░Ау┤атїќсЂЋсѓїсЂЪухљТъюсђЂСИЇТГБсЂ«ТИЕт║ісЂесЂфсѓісђЂтцџсЂЈсЂ«С║ІСЙІсЂїТЉўуЎ║сЂЋсѓїсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
ухїтќХУђЁсѓёсѓ│сЃ│сЃЌсЃЕсѓцсѓбсЃ│сѓ╣ТІЁтйЊУђЁсЂ»сђЂуй░тЅЄсѓњУ┐ћжѓёсЂЎсѓїсЂ░ухѓсѓЈсѓісЂеУ╗йУдќсЂЏсЂџсђЂС╝ЂТЦГсЂ«тГўуХџсѓњтидтЈ│сЂЌсЂІсЂГсЂфсЂёжЄЇтцДсЂфсЃфсѓ╣сѓ»сЂесЂЌсЂдУфЇУГўсЂЎсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓСИЇТГБтЈЌухдсЂїуЎ║УдџсЂЌсЂЪта┤тљѕсђЂС╝ЂТЦГсЂФсЂ»УАїТћ┐уй░сђЂухїТИѕуџёсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсђЂтѕЉС║Іуй░сђЂсЂЮсЂЌсЂдуцЙС╝џуџётѕХУБЂсЂесЂёсЂєсђЂтцџт▓љсЂФсѓЈсЂЪсѓІтј│Та╝сЂфуй░тЅЄсЂїуДЉсЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
ТюгУеўС║ІсЂДсЂ»сђЂсЂЊсѓїсѓЅсЂ«уй░тЅЄсЂ«тЁет«╣сѓњТ│ЋС╗цсЂФтЪ║сЂЦсЂЇуХ▓уЙЁуџёсЂФУДБУфгсЂЌсђЂС╝ЂТЦГсЂїсЂЊсЂ«сЃфсѓ╣сѓ»сЂФт»ЙсЂЌсЂдтЈќсѓІсЂ╣сЂЇтЁиСйЊуџёсЂІсЂцТ│ЋуџёсЂфт»ЙуГќсѓњТЈљуц║сЂёсЂЪсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
У┐Љт╣┤сђЂУБютіЕжЄЉсЃ╗тіЕТѕљжЄЉсЂ«СИЇТГБтЈЌухдсЂ»сђЂС╝ЂТЦГсЂїСИ╗СйЊуџёсЂФУЎџтЂйућ│УФІсѓњУАїсЂєсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЂФтіасЂѕсђЂТѓфУ│фсЂфТћ»ТЈ┤С║ІТЦГУђЁсЂФсѓѕсѓІухёу╣ћуџёсЂфтІДУфўсѓ╣сѓГсЃ╝сЃасЂФсѓѕсЂБсЂдсђЂТёЈтЏ│сЂЏсЂџти╗сЂЇУЙ╝сЂЙсѓїсѓІсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЂїтбЌтіасЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓITт░јтЁЦУБютіЕжЄЉсѓёсЃфсѓ╣сѓГсЃфсЃ│сѓ░тіЕТѕљжЄЉ№╝ѕС║║ТЮљжќІуЎ║Тћ»ТЈ┤тіЕТѕљжЄЉ№╝ЅсЂ«тѕєжЄјсЂДсѓѓсђЂсђїт«ЪУ│фуёАТќЎсђЇсђїсѓГсЃЃсѓ»сЃљсЃЃсѓ»сђЇсЂесЂёсЂБсЂЪСИЇТГБсѓњУфўуЎ║сЂЎсѓІтІДУфўсЂїТефУАїсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
С╝ЂТЦГсЂїсЂЊсѓїсѓЅсЂ«ТѓфУ│фсЂфсѓ╣сѓГсЃ╝сЃасЂФС╣ЌсЂБсЂдсЂЌсЂЙсЂБсЂЪта┤тљѕсђЂсђїУЄфтѕєсЂЪсЂАсЂ»жеЎсЂЋсѓїсЂЪсђЇсЂеСИ╗т╝хсЂЌсЂЪсЂесЂЌсЂдсѓѓсђЂУЎџтЂйсЂ«ућ│УФІсЂФжќбСИјсЂЌсЂЪС║Іт«ЪсЂїсЂѓсѓїсЂ░сђЂСИЇТГБтЈЌухдсЂїТѕљуФІсЂЌсђЂтј│сЂЌсЂёуй░тЅЄсЂ«т»ЙУ▒АсЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂфТДІжђауџёУф▓жАїсѓњТі▒сЂѕсѓІуЈЙС╗БсЂФсЂісЂёсЂдсђЂС╝ЂТЦГсЂ»ућ│УФІсЃЌсЃГсѓ╗сѓ╣тЁеСйЊсѓњтј│сЂЌсЂЈу«АуљєсЂЌсђЂСИЇТГБсЂ«уќЉт┐хсЂїућЪсЂўсЂЪжџЏсЂФсЂ»сђЂсЂЎсЂљсЂФт╝ЂУГитБФсЂ«т░ѓжќђуџёсЂфсѓхсЃЮсЃ╝сЃѕсѓњтЈЌсЂЉсђЂсЃфсѓ╣сѓ»сѓњТюђт░ЈжЎљсЂФТіЉсЂѕсѓІУАїтІЋсѓњтЈќсѓІсЂЊсЂесЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЊсЂ«УеўС║ІсЂ«уЏ«ТгА
сђїСИЇТГБтЈЌухдсђЇсЂ«Т│Ћуџёт«џуЙЕсЂеТЉўуЎ║сЂЋсѓїсѓІтЁиСйЊуџёсЂфТЅІтЈБ

СИЇТГБтЈЌухдсЂ«Т│Ћуџёт«џуЙЕсђЂТѕљуФІТЎѓТюЪсЂеУ▓гС╗╗сЂ«у»ётЏ▓
тіЕТѕљжЄЉсѓёУБютіЕжЄЉсЂ«СИЇТГБтЈЌухдсЂ»сђЂтЇўсЂфсѓІУАїТћ┐ТЅІуХџсЂЇСИісЂ«сЃЪсѓ╣сЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂТ│ЋуџёсЂФТўјуб║сЂФт«џуЙЕсЂЋсѓїсЂЪСИЇТГБУАїуѓ║сЂДсЂЎсђѓ
т«џуЙЕ№╝џсђїтЂйсѓісЂЮсЂ«С╗ќСИЇТГБсЂ«УАїуѓ║сђЇсЂФсѓѕсѓІС║цС╗ў
СИЇТГБтЈЌухдсЂ»сђЂсђїтЂйсѓісЂЮсЂ«С╗ќСИЇТГБсЂ«УАїуѓ║сЂФсѓѕсѓісђЂТюгТЮЦтЈЌсЂЉсѓІсЂЊсЂесЂ«сЂДсЂЇсЂфсЂёУБютіЕжЄЉуГЅсЂ«С║цС╗ўсѓњтЈЌсЂЉсђЂтЈѕсЂ»тЈЌсЂЉсѓѕсЂєсЂесЂЎсѓІсЂЊсЂесђЇсЂет«џуЙЕсЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓуЅ╣сЂФжЄЇУдЂсЂфсЂ«сЂ»сђЂт«ЪжџЏсЂФтіЕТѕљжЄЉсѓёУБютіЕжЄЉсѓњтЈЌсЂЉтЈќсЂБсЂдсЂёсЂфсЂЈсЂдсѓѓсђЂСИЇТГБсЂфуЏ«уџёсЂДућ│УФІТЏИжАъсѓњСйюТѕљсЃ╗ТЈљтЄ║сЂЌсЂЪТЎѓуѓ╣сЂДсђїСИЇТГБтЈЌухдсђЇсЂїТѕљуФІсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂДсЂЎсђѓ
У▓гС╗╗сЂ«у»ётЏ▓№╝џухїтќХУђЁсЂІсѓЅтЙЊТЦГтЊАсЂЙсЂД
СИЇТГБтЈЌухдсЂФжќбсѓЈсѓІУ▓гС╗╗сЂ»сђЂућ│УФІСИ╗СйЊсЂДсЂѓсѓІС║ІТЦГСИ╗сЂ«С╗БУАеУђЁсЂасЂЉсЂФуЋЎсЂЙсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓтй╣тЊАсђЂтЙЊТЦГтЊАсђЂС╗БуљєС║║сђЂсЂЮсЂЌсЂдућ│УФІТЏИжАъсЂ«СйюТѕљсЂФжќбСИјсЂЌсЂЪуггСИЅУђЁсЂфсЂЕсђЂСИЇТГБУАїуѓ║сЂФжќбсѓЈсЂБсЂЪУђЁсЂ»жђБтИ»сЂЌсЂдУ▓гС╗╗сѓњтЋЈсѓЈсѓїсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓуЅ╣сЂФсђЂтЙЊТЦГтЊАсЂїС╝џуцЙсЂ«тѕЕуЏісЂ«сЂЪсѓЂсЂФУАїсЂБсЂЪСИЇТГБУАїуѓ║сЂДсЂѓсЂБсЂдсѓѓсђЂтйЊУЕ▓С║ІТЦГСИ╗сЂїСИЇТГБУАїуѓ║сѓњУАїсЂБсЂЪсЂесЂ┐сЂфсЂЋсѓїсђЂС╝џуцЙтЁеСйЊсЂїсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсѓњУ▓асЂєсЂЊсЂесЂФсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓУБютіЕжЄЉжЂЕТГБтїќТ│ЋсЂФт«џсѓЂсѓЅсѓїсЂЪСИАуй░УдЈт«џсЂФсѓѕсѓісђЂС╝ЂТЦГсЂетђІС║║сЂ«тЈїТќ╣сЂФт»ЙсЂЌсЂдуй░тЅЄсЂїжЂЕућесЂЋсѓїсѓІсЃфсѓ╣сѓ»сЂїтГўтюесЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
С╗БУАеуџёсЂфСИЇТГБтЈЌухдсЂ«ТЅІтЈБ
СИЇТГБтЈЌухдсЂ«ТЅІтЈБсЂ»тцџт▓љсЂФсѓЈсЂЪсѓісЂЙсЂЎсЂїсђЂСИ╗сЂФС╗ЦСИІсЂ«жАътъІсЂФтѕєжАъсЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
- УЎџтЂйућ│УФІсЃ╗УЎџтЂйта▒тЉі№╝џтБ▓СИісѓёС╝ЉТЦГсЂ«т«ЪТЁІсђЂтЙЊТЦГтЊАТЋ░сЂфсЂЕсЂ«С║Іт«ЪжќбС┐ѓсѓњтЂйсЂБсЂдућ│УФІсЂЎсѓІУАїуѓ║сђѓжЏЄућеУф┐ТЋ┤тіЕТѕљжЄЉсЂФсЂісЂёсЂдсЂ»сђЂт«ЪжџЏсЂФсЂ»тІцтІЎсЂЌсЂдсЂёсѓІсЂФсѓѓсЂІсЂІсѓЈсѓЅсЂџС╝ЉТЦГсЂЌсЂдсЂёсѓІсЂетЂйсѓІсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЂфсЂЕсЂїУЕ▓тйЊсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
- ухїУ▓╗сЂ«Т░┤тбЌсЂЌсЃ╗ТъХуЕ║УеѕСИі№╝џт«ЪжџЏсЂФТћ»тЄ║сЂЌсЂдсЂёсЂфсЂёухїУ▓╗сѓњтЂйсѓісЂ«УФІТ▒ѓТЏИсѓёжаўтЈјТЏИсѓњућесЂёсЂдУеѕСИісЂЎсѓІУАїуѓ║сђѓсЂѓсѓІсЂёсЂ»сђЂт«ЪжџЏсЂ«ухїУ▓╗сѓњСИЇтйЊсЂФжФўжАЇсЂФТ░┤тбЌсЂЌсЂЌсЂдућ│УФІсЂЎсѓІУАїуѓ║сЂДсЂЎсђѓ
- уЏ«уџётцќСй┐уће№╝џС║цС╗ўсЂЋсѓїсЂЪУБютіЕжЄЉсѓњсђЂтйЊтѕЮТїЄт«џсЂЋсѓїсЂЪС║цС╗ўуЏ«уџёС╗ЦтцќсЂФСй┐ућесЂЎсѓІУАїуѓ║сђѓСЙІсЂѕсЂ░сђЂУеГтѓЎТіЋУ│ЄсЂ«сЂЪсѓЂсЂФтЈЌсЂЉсЂЪУБютіЕжЄЉсѓњжЂІУ╗бУ│ЄжЄЉсЂФТхЂућесЂЎсѓІсЂфсЂЕсЂїУЕ▓тйЊсЂЌсђЂсЂЊсѓїсЂ»тЙїУ┐░сЂ«жђџсѓітѕЉС║Іуй░сЂ«т»ЙУ▒АсЂесѓѓсЂфсѓітЙЌсЂЙсЂЎсђѓ
- сѓГсЃЃсѓ»сЃљсЃЃсѓ»сЃ╗т«ЪУ│фуёАТќЎсѓ╣сѓГсЃ╝сЃа№╝џУБютіЕжЄЉТћ»ТЈ┤С║ІТЦГУђЁсЂїсђЂУБютіЕжЄЉсѓњСй┐сЂБсЂдт░јтЁЦсЂЌсЂЪУБйтЊЂсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂ«т«ЪУ│фуџёсЂфУ▓╗ућесѓњсђЂтЙїсЂІсѓЅућ│УФІС╝ЂТЦГсЂФсђїсѓГсЃБсЃЃсѓисЃЦсЃљсЃЃсѓ»сђЇсѓёсђїсѓГсЃЃсѓ»сЃљсЃЃсѓ»сђЇсЂесЂЌсЂджѓёТхЂсЂЋсЂЏсѓІсѓ╣сѓГсЃ╝сЃасЂДсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂ»С╝џУеѕТцюТЪ╗жЎбсЂІсѓЅсѓѓтѕХт║дсЂ«тЪ║ТюгУдЂС╗ХжЂЋтЈЇсЂесЂЌсЂдТўјуб║сЂФТїЄТЉўсЂЋсѓїсЂдсЂісѓісђЂухёу╣ћуџёсЂІсЂцУеѕућ╗уџёсЂфСИЇТГБУАїуѓ║сЂ«тЁИтъІСЙІсЂесЂ┐сЂфсЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
тцќжЃесЂ«Тћ»ТЈ┤ТЦГУђЁсЂФСЙЮтГўсЂЌсђЂсЂЮсЂ«ТЦГУђЁсЂїТёЈтЏ│уџёсЂФСИЇТГБсЂфсѓ╣сѓГсЃ╝сЃасѓњТїЄтЇЌсЂЌсЂЪта┤тљѕсЂДсЂѓсЂБсЂдсѓѓсђЂС╝ЂТЦГтЂ┤сЂ»УЎџтЂйућ│УФІсЂФжќбСИјсЂЌсЂЪсЂесЂёсЂєС║Іт«ЪсЂІсѓЅСИЇТГБтЈЌухдсЂїТѕљуФІсЂЌсЂЙсЂЎсђѓуЅ╣сЂФУцЄжЏЉсЂфсѓГсЃЃсѓ»сЃљсЃЃсѓ»ТАѕС╗ХсЂДсЂ»сђЂС╝ЂТЦГсЂ»СИЇТГБсЂ«ТёЈтЏ│сЂїтИїУќёсЂДсЂѓсЂБсЂЪсЂеСИ╗т╝хсЂЌсЂЪсЂёсЂесЂЊсѓЇсЂДсЂЎсЂїсђЂТ│ЋуџёсЂФсЂ»СИЇТГБтЈЌухдсЂ«У▓гС╗╗сЂІсѓЅжђЃсѓїсѓІсЂЊсЂесЂ»тЏ░жЏБсЂДсЂѓсѓісђЂт╝ЂУГитБФсЂФсѓѕсѓІтѕЮТюЪсЂ«С║Іт«ЪУф┐ТЪ╗сЂежў▓тЙАТѕдуЋЦсЂїСИЇтЈ»ТгасЂДсЂЎсђѓ
сђљТюђжЄЇУдЂсђЉСИЇТГБтЈЌухдсЂїуЎ║УдџсЂЌсЂЪта┤тљѕсЂФуДЉсЂЋсѓїсѓІсђїуй░тЅЄсђЇ

сђїуй░тЅЄсђЇсЂ»сђЂСИЇТГБтЈЌухдтЋЈжАїсЂ«ТаИт┐ЃсЂДсЂѓсѓісђЂсЂЮсЂ«жЂЕућеу»ётЏ▓сЂ»ухїТИѕуџёсЂфТљЇтц▒сђЂС║ІТЦГТ┤╗тІЋсЂ«тѕХжЎљсђЂсЂЮсЂЌсЂдтђІС║║сЂ«УЄфућ▒сѓњУёЁсЂІсЂЎТІўудЂтѕЉсЂФсЂЙсЂДтЈісЂ│сЂЙсЂЎсђѓСИЇТГБтЈЌухдсЂїуЎ║УдџсЂЌсЂЪта┤тљѕсђЂС╝ЂТЦГсЂ»сЂЊсѓїсѓЅсЂЎсЂ╣сЂдсЂ«уй░тЅЄсѓњтЈЌсЂЉсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
тѕЉС║Іуй░сЂ«сЃфсѓ╣сѓ»сѓёТІўудЂтѕЉсЂ«жЂЕућетЈ»УЃйТђД
СИЇТГБтЈЌухдсЂ»сђЂУАїТћ┐тЄдтѕєсѓњтЈЌсЂЉсѓІсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈсђЂтЏйт«ХсЂФт»ЙсЂЎсѓІТг║уйћУАїуѓ║сЂесЂЌсЂдуі»уйфУАїуѓ║сЂФУЕ▓тйЊсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
тѕЉТ│ЋСИісЂ«УЕљТг║уйф
СИЇТГБтЈЌухдсЂ«ТѓфУ│фТђДсЂїжФўсЂёта┤тљѕсђЂтѕЉТ│Ћугг246ТЮАсЂ«УЕљТг║уйфсЂФтЋЈсѓЈсѓїсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓУЕљТг║уйфсЂ»сђЂтЏйсѓёУЄфТ▓╗СйЊсѓњжеЎсЂЌсЂдУ▓АућБуџётѕЕуЏісѓњтЙЌсЂЪУАїуѓ║сЂФжЂЕућесЂЋсѓїсђЂсЂЮсЂ«Т│Ћт«џтѕЉсЂ»10т╣┤С╗ЦСИІсЂ«ТІўудЂтѕЉсЂесЂёсЂєжЄЇсЂёсѓѓсЂ«сЂДсЂЎсђѓуЅ╣сЂФсђЂСИЇТГБтЈЌухджАЇсЂїтцџжАЇсЂФСИісѓІта┤тљѕсѓёсђЂухёу╣ћуџёсЃ╗Уеѕућ╗уџёсЂфСИЇТГБсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсѓІта┤тљѕсђЂтѕЉС║ІтЉіуЎ║сЂЋсѓїсѓІсЃфсѓ╣сѓ»сЂїТЦхсѓЂсЂджФўсЂЈсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
УБютіЕжЄЉжЂЕТГБтїќТ│ЋжЂЋтЈЇсЂФсѓѕсѓІуй░тЅЄ№╝ѕуЅ╣тѕЦТ│Ћ№╝Ѕ
УБютіЕжЄЉсЃ╗тіЕТѕљжЄЉсЂ«СИЇТГБтЈЌухдсЂФт»Йт┐юсЂЎсѓІуЅ╣тѕЦТ│ЋсЂесЂЌсЂдсђЂсђїУБютіЕжЄЉуГЅсЂФС┐ѓсѓІС║ѕу«ЌсЂ«тЪиУАїсЂ«жЂЕТГБтїќсЂФжќбсЂЎсѓІТ│ЋтЙІсђЇ№╝ѕУБютіЕжЄЉжЂЕТГБтїќТ│Ћ№╝ЅсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЊсЂ«Т│ЋтЙІсЂ»сђЂСИЇТГБтЈЌухдсЂФт»ЙсЂЎсѓІУЕ│у┤░сЂфуй░тЅЄсѓњт«џсѓЂсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
СИЇТГБтЈЌухдсЂФжќбжђБсЂЎсѓІСИ╗сЂфтѕЉС║Іуй░сЂеТ│Ћт«џтѕЉ
| Т│ЋС╗ц/уйфтљЇ | жЂЕућесЂЋсѓїсѓІУАїуѓ║ | Т│Ћт«џтѕЉ№╝ѕуй░тЅЄ№╝Ѕ | жЄЇУдЂТђД |
| тѕЉТ│Ћ / УЕљТг║уйф№╝ѕугг246ТЮА№╝Ѕ | тЂйУеѕсѓњућесЂёсЂдухдС╗ўжЄЉсѓњУЕљтЈќсЂЎсѓІУАїуѓ║ | 10т╣┤С╗ЦСИІсЂ«ТІўудЂтѕЉ | СИЇТГБтЈЌухдсЂ«СИђУѕгуџёсЂфжЂЕућеуйфтљЇсЂДсЂѓсѓісђЂТюђсѓѓжЄЇсЂёТІўудЂтѕЉсЃфсѓ╣сѓ»сѓњуц║сЂЎсђѓ |
| УБютіЕжЄЉжЂЕТГБтїќТ│Ћ / СИЇТГБтЈЌухд№╝ѕугг29ТЮА№╝Ѕ | тЂйсѓісЂЮсЂ«С╗ќСИЇТГБсЂ«ТЅІТ«хсЂДУБютіЕжЄЉсѓњтЈЌухдсЂЌсЂЪУАїуѓ║ | 5т╣┤С╗ЦСИІсЂ«ТІўудЂтѕЉсЂЙсЂЪсЂ»100СИЄтєєС╗ЦСИІсЂ«уй░жЄЉ | уЅ╣тѕЦТ│ЋсЂФсѓѕсѓІуЏ┤ТјЦуџёсЂфуй░тЅЄсђѓУЕљТг║уйфсЂеуФХтљѕсЂЌсЂджЂЕућесЂЋсѓїсѓІсђѓ |
| УБютіЕжЄЉжЂЕТГБтїќТ│Ћ / уЏ«уџётцќСй┐уће№╝ѕугг30ТЮА№╝Ѕ | УБютіЕжЄЉуГЅсѓњТюгТЮЦсЂ«С║цС╗ўуЏ«уџёС╗ЦтцќсЂФСй┐ућесЂЌсЂЪУАїуѓ║ | 3т╣┤С╗ЦСИІсЂ«ТІўудЂтѕЉсЂЙсЂЪсЂ»50СИЄтєєС╗ЦСИІсЂ«уй░жЄЉ | ТёЈтЏ│уџёсЂфТхЂућесѓѓтѕЉС║Іуй░сЂ«т»ЙУ▒АсЂесЂфсѓІуѓ╣сѓњУГджљўсђѓ |
СИАуй░УдЈт«џсЂ«жЂЕућесЂФсѓѕсѓІС╗БУАеУђЁсЃ╗Т│ЋС║║сЂ«У▓гС╗╗
УБютіЕжЄЉжЂЕТГБтїќТ│ЋсЂФсЂ»сђЂСИАуй░УдЈт«џ№╝ѕугг32ТЮА№╝ЅсЂїУеГсЂЉсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂ»сђЂТ│ЋС║║сЂ«С╗БУАеУђЁсђЂС╗БуљєС║║сђЂСй┐ућеС║║сЂЮсЂ«С╗ќсЂ«тЙЊТЦГУђЁсЂїсђЂсЂЮсЂ«Т│ЋС║║сЂ«ТЦГтІЎсЂФжќбсЂЌСИЇТГБУАїуѓ║сѓњУАїсЂБсЂЪта┤тљѕсђЂт«ЪУАїУђЁтђІС║║№╝ѕтй╣тЊАсѓётЙЊТЦГтЊА№╝ЅсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈсђЂТ│ЋС║║сЂФт»ЙсЂЌсЂдсѓѓуй░жЄЉтѕЉсѓњуДЉсЂЎсЂесЂёсЂєУдЈт«џсЂДсЂЎсђѓ
сЂЊсЂ«УдЈт«џсЂФсѓѕсѓісђЂухїтќХт▒цсЂ»уЏ┤ТјЦТЅІсѓњСИІсЂЌсЂдсЂёсЂфсЂЈсЂдсѓѓсђЂжЃеСИІсЂ«СИЇТГБсѓњТїЄуц║сЃ╗ж╗ЎУфЇсЂЌсЂЪта┤тљѕсЂФсЂ»сђЂС╝џуцЙсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈУЄфУ║ФсѓѓтѕЉС║ІУ▓гС╗╗№╝ѕТІўудЂтѕЉсѓёуй░жЄЉтѕЉ№╝ЅсѓњтЋЈсѓЈсѓїсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓС╝ЂТЦГсЂ«сѓ│сЃ│сЃЌсЃЕсѓцсѓбсЃ│сѓ╣СйЊтѕХсЂ«СИЇтѓЎсЂїсђЂС╗БУАеУђЁтђІС║║сЂ«С║║ућЪсѓњтидтЈ│сЂЎсѓІухљТъюсЂФсЂцсЂфсЂїсѓітЙЌсѓІсЂЪсѓЂсђЂТЦхсѓЂсЂджЄЇтцДсЂфсЃфсѓ╣сѓ»сЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
ухїТИѕуџёсЃџсЃісЃФсЃєсѓБ№╝ѕтЈЌухджАЇсЂ«120%УХЁсѓњУФІТ▒ѓсЂЋсѓїсѓІТДІжђа№╝Ѕ
СИЇТГБтЈЌухдсЂїуЎ║УдџсЂЌсЂЪта┤тљѕсђЂС╝ЂТЦГсЂїУАїТћ┐т║ЂсЂІсѓЅУФІТ▒ѓсЂЋсѓїсѓІжЄЉжАЇсЂ»сђЂтЇўсЂФтЈЌухдсЂЌсЂЪжЄЉжАЇсЂ«У┐ћТИѕсЂФуЋЎсЂЙсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓтЈЌухджАЇсЂФтіасЂѕсЂдсђЂжЂЋу┤ёжЄЉсЂесЂЌсЂдсЂ«тіау«ЌжЄЉсЂет╗ХТ╗ъжЄЉсЂїУф▓сЂЋсѓїсѓІсЂЪсѓЂсђЂт«ЪУ│фуџёсЂФтЈЌухджАЇсЂ«120%сѓњУХЁсЂѕсѓІжЄЉжАЇсЂ«У┐ћжѓёсЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсѓІсЂЊсЂесЂФсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂ»сђЂС╝ЂТЦГсЂ«У▓АтІЎуіХТ│ЂсѓњСИђуъгсЂФсЂЌсЂдТѓфтїќсЂЋсЂЏсѓІуй░тЅЄсЂДсЂЎсђѓ
СИЇТГБтЈЌухдуЎ║УдџТЎѓсЂ«У┐ћжѓёУФІТ▒ѓсЂісѓѕсЂ│тіау«ЌжЄЉсЂ«тєЁУе│
| сЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂ«уе«жАъ | УФІТ▒ѓсЂЋсѓїсѓІжЄЉжАЇ/Тјфуй« | Т│Ћуџётй▒жЪ┐сЃ╗тѓЎУђЃ |
| СИЇТГБтЈЌухджАЇсЂ«У┐ћжѓё | СИЇТГБуЎ║ућЪТЌЦсѓњтљФсѓђТюЪжќЊС╗ЦжЎЇсЂ«тЈЌухджАЇтЁежАЇ | СИЇТГБсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂЪТюЪжќЊС╗ЦжЎЇсђЂтЈЌухдсЂЌсЂЪсЂЎсЂ╣сЂдсЂ«жЄЉжАЇсЂїУ┐ћжѓёуЙЕтІЎсЂ«т»ЙУ▒АсЂесЂфсѓІсђѓ |
| тіау«ЌжЄЉ№╝ѕжЂЋу┤ёжЄЉ№╝Ѕ | СИЇТГБтЈЌухджАЇсЂ«20%уЏИтйЊжАЇ | УАїТћ┐т║ЂсЂїУф▓сЂЎсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсђѓУЄфСИ╗ућ│тЉісѓњУАїсЂБсЂЪта┤тљѕсЂ»сђЂсЂЊсЂ«тіау«ЌжЄЉсЂ«тЁЇжЎцсЃ╗У╗йТИЏсЂїТюЪтЙЁсЂДсЂЇсѓІсђѓ |
| т╗ХТ╗ъжЄЉ | т╣┤ујЄ3%сЂфсЂЕУдЈт«џсЂФтЪ║сЂЦсЂЈжЂЁт╗ХТљЇт«│жЄЉ | У┐ћжѓёТюЪжЎљсЂІсѓЅсЂ«ухїжЂјТЌЦТЋ░сЂФт┐юсЂўсЂдсђЂтѕЕТЂ»уЏИтйЊжАЇсЂїтіау«ЌсЂЋсѓїсѓІсђѓ |
сЂЊсЂЊсЂДжЄЇУдЂсЂфсЂ«сЂ»сђЂУ┐ћжѓёУФІТ▒ѓсЂ«т»ЙУ▒АсЂїсђїСИЇТГБуЎ║ућЪТЌЦсѓњтљФсѓђТюЪжќЊС╗ЦжЎЇсЂ«тЁежАЇсђЇсЂДсЂѓсѓІсЂесЂёсЂєуѓ╣сЂДсЂЎсђѓсЂцсЂЙсѓісђЂС╗«сЂФСИЇТГБсЂїтЈЌухдТюЪжќЊсЂ«жђћСИГсЂДСИђт║дсЂДсѓѓуЎ║ућЪсЂЌсЂдсЂёсЂЪта┤тљѕсђЂсЂЮсЂ«тЙїсЂ«тЁесЂдсЂ«тЈЌухджАЇсЂїжЂАтЈіуџёсЂФУ┐ћжѓёсЂ«т»ЙУ▒АсЂесЂфсЂБсЂдсЂЌсЂЙсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂФ20%сЂ«тіау«ЌжЄЉсЂет╗ХТ╗ъжЄЉсЂїСИіС╣ЌсЂЏсЂЋсѓїсѓІсЂЪсѓЂсђЂС╝ЂТЦГсЂ»СИЇТГБсЂФсѓѕсЂБсЂдтЙЌсЂЪтѕЕуЏісЂЕсЂЊсѓЇсЂІсђЂтцџтцДсЂфуй░жЄЉсѓњТћ»ТЅЋсЂєС║ІТЁІсЂФжЎЦсѓісЂЙсЂЎсђѓ
ТїЂуХџтїќухдС╗ўжЄЉсЂ«СИЇТГБтЈЌухдС║ІСЙІсЂДсѓѓсђЂтЁгУАесЂЋсѓїсЂЪ2,458УђЁсЂ«сЂєсЂАсђЂ1,824УђЁсЂ»СИЇТГБтЈЌухджЄЉжАЇсЂФтіасЂѕсђЂ20%сЂ«тіау«ЌжЄЉтЈісЂ│т╣┤ујЄ3%сЂ«т╗ХТ╗ъжЄЉсѓњтљФсѓђтЁежАЇсѓњтЏйт║ФсЂФу┤ЇС╗ўТИѕсЂ┐сЂДсЂѓсѓІсЂЊсЂесЂїуц║сЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсЂ«С║Іт«ЪсЂІсѓЅсѓѓсђЂУАїТћ┐сЂїтј│Та╝сЂФсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсѓњжЂЕућесЂЌсЂдсЂёсѓІт«ЪТЃЁсЂїТўјсѓЅсЂІсЂДсЂЎсђѓ
УАїТћ┐тЄдтѕєсЂеуцЙС╝џуџётѕХУБЂсђЂС║ІТЦГуХЎуХџсЂИсЂ«УЄ┤тЉйтѓи
ухїТИѕуџёсЂфсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсѓётѕЉС║Іуй░сЂ«сЃфсѓ╣сѓ»сЂФтіасЂѕсђЂС╝ЂТЦГсЂФт»ЙсЂЎсѓІУАїТћ┐тЄдтѕєсЂеуцЙС╝џуџётѕХУБЂсЂ»сђЂС║ІТЦГуХЎуХџсЂЮсЂ«сѓѓсЂ«сЂФУЄ┤тЉйуџёсЂфтй▒жЪ┐сѓњтЈісЂ╝сЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
СИЇТћ»ухдТјфуй«№╝ѕУ│ЄТа╝тѕХжЎљ№╝Ѕ
СИЇТГБтЈЌухдсЂїуЎ║УдџсЂЌсЂЪта┤тљѕсђЂУАїТћ┐т║ЂсЂ»сђЂтйЊУЕ▓С║ІТЦГСИ╗сЂФт»ЙсЂЌсЂдС╗ітЙїсЂ«тіЕТѕљжЄЉсЃ╗УБютіЕжЄЉсЂ«ућ│УФІУ│ЄТа╝сѓњтѕХжЎљсЂЎсѓІТјфуй«сѓњУгЏсЂўсЂЙсЂЎсђѓуЅ╣сЂФжЏЄућежќбС┐ѓтіЕТѕљжЄЉсЂФсЂісЂёсЂдсЂ»сђЂСИЇТГБтЈЌухдТЌЦсЂІсѓЅ5т╣┤жќЊсЂФсѓЈсЂЪсѓісђЂСИЇТГБтЈЌухдсѓњУАїсЂБсЂЪсѓѓсЂ«С╗ЦтцќсЂ«С╗ќсЂ«жЏЄућежќбС┐ѓтіЕТѕљжЄЉсѓњтљФсѓђсђЂсЂЎсЂ╣сЂдсЂ«жЏЄућежќбС┐ѓтіЕТѕљжЄЉсЂїтЈЌухдсЂДсЂЇсЂфсЂЈсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
тЁгуџёУ│ЄжЄЉсЂ«тЈЌухдУ│ЄТа╝сѓњ5т╣┤жќЊтц▒сЂєсЂЊсЂесЂ»сђЂуХЎуХџуџёсЂфухїтќХтіфтіЏсѓёсђЂті┤тЃЇуњ░тбЃТћ╣тќёсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«У│ЄжЄЉУф┐жЂћТЅІТ«хсѓњт«їтЁесЂФТќГсЂЪсѓїсѓІсЂЊсЂесѓњТёЈтЉ│сЂЌсђЂС╝ЂТЦГухїтќХсЂ«УЄфућ▒т║дсѓњУЉЌсЂЌсЂЈтѕХжЎљсЂЎсѓІжЄЇтцДсЂфУАїТћ┐тЄдтѕєсЂДсЂЎсђѓ
С║ІТЦГСИ╗тљЇуГЅсЂ«тЁгУАе№╝ѕт«ЪтљЇтЁгУАе№╝Ѕ
УЄфСИ╗ућ│тЉісЂДсЂ»сЂфсЂёСИЇТГБтЈЌухдсЂїуЎ║УдџсЂЌсђЂтЈќсѓіТХѕсЂЌсЂЪТћ»ухджАЇсЂї100СИЄтєєС╗ЦСИісЂесЂфсЂБсЂЪта┤тљѕсђЂУАїТћ┐т║ЂсЂ»тјЪтЅЄсЂесЂЌсЂдсђЂС║ІТЦГСИ╗сЂ«тљЇуД░сђЂС╗БУАеУђЁтљЇсђЂСИЇТГБсЂ«тєЁт«╣сѓњтЁгУАесЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
т«ЪтљЇтЁгУАесЂ»сђЂС╝ЂТЦГсЂФсЂесЂБсЂдТюђсѓѓжЂ┐сЂЉсЂЪсЂёуцЙС╝џуџётѕХУБЂсЂ«СИђсЂцсЂДсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂФсѓѕсѓісђЂС╝ЂТЦГсЂ»тЈќт╝ЋсѓёТјАућесЂфсЂЕсЂѓсѓЅсѓєсѓІжЮбсЂДС┐Аућесѓњтц▒сЂєсЂісЂЮсѓїсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
- тЈќт╝ЋтЁѕсЂІсѓЅсЂ«С┐Ажа╝тќфтц▒№╝џтЁгУАесЂЋсѓїсЂЪС║Іт«ЪсЂ»сђЂтЈќт╝ЋтЁѕсЂесЂ«тЦЉу┤ёУДБжЎцсѓётЈќт╝ЋтЂюТГбсЂ«уљєућ▒сЂесЂфсѓітЙЌсЂЙсЂЎсђѓ
- жЄЉУъЇТЕЪжќбсЂІсѓЅсЂ«УъЇУ│ЄтЂюТГб№╝џУ│ЄжЄЉУф┐жЂћсЂїтЏ░жЏБсЂФсЂфсѓісђЂжЂІУ╗бУ│ЄжЄЉсЂ«уб║С┐ЮсЂФТћ»жџюсѓњсЂЇсЂЪсЂЎта┤тљѕсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
- С║║ТЮљТјАућесЂ«тЏ░жЏБ№╝џуцЙС╝џуџёУЕЋСЙАсЂ«СйјСИІсЂ»сђЂтёфуДђсЂфС║║ТЮљсЂ«уЇ▓тЙЌсѓњСИЇтЈ»УЃйсЂФсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
т«ЪжџЏсЂФсђЂухїТИѕућБТЦГуюЂсЂ»ТїЂуХџтїќухдС╗ўжЄЉсЂД2,458УђЁсѓњСИЇТГБтЈЌухдУђЁсЂесЂЌсЂдУфЇт«џсЂЌсђЂтЁгУАесЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎ№╝ѕСИЇТГБтЈЌухдуиЈжАЇу┤ё25тёётєє№╝ЅсђѓсЂЙсЂЪсђЂжЏЄућеУф┐ТЋ┤тіЕТѕљжЄЉсЂ«СИЇТГБтЈЌухдтЁгУАесѓѓу┤»Уеѕ1,446С╗ХсЂФСИісѓІсЂфсЂЕсђЂтЁгУАеС║ІСЙІсЂ»Т▒║сЂЌсЂдСЙІтцќуџёсЂфС║ІУ▒АсЂДсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓт«ЪтљЇтЁгУАесЂ»сђЂС╝ЂТЦГсЂїтЈЌсЂЉсѓІуцЙС╝џуџёсЃђсЃАсЃ╝сѓИсЂ«СИГсЂДсђЂтѕЉС║Іуй░сЂФУЄ│сѓЅсЂфсЂЈсЂесѓѓсђЂС║ІТЦГуХЎуХџсѓњТа╣ТюгсЂІсѓЅУёЁсЂІсЂЎТюђтцДсЂ«уй░тЅЄсЂесЂфсѓітЙЌсЂЙсЂЎсђѓ
СИЇТГБтЈЌухдсЂ«уЎ║УдџухїУи»сЂеУАїТћ┐сЃ╗ТЇюТЪ╗ТЕЪжќбсЂ«жђБТљ║

СИЇТГБтЈЌухдсЂ»сђЂУАїТћ┐ТЕЪжќбсЂФсѓѕсѓІтј│Та╝сЂфУф┐ТЪ╗СйЊтѕХсЂесђЂуЈЙС╗БуџёсЂфсЃфсѓ╣сѓ»у«АуљєТЅІТ«хсЂФсѓѕсЂБсЂдсђЂжЮътИИсЂФжФўсЂёуб║ујЄсЂДсђїсЃљсЃгсѓІсђЇТДІжђасЂесЂфсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
уЎ║УдџухїУи»сЂ«тцџТДўтїќсЂФсѓѕсѓІсђЂсЂЕсЂєсЂЌсЂдсђїсЃљсЃгсѓІсђЇсЂ«сЂІ№╝Ъ
СИЇТГБсЂїуЎ║УдџсЂЎсѓІсЂЇсЂБсЂІсЂЉсЂ»сђЂС╝ЂТЦГсЂїТЃ│тЃЈсЂЎсѓІС╗ЦСИісЂФтцџт▓љсЂФсѓЈсЂЪсѓісЂЙсЂЎсђѓ
- УАїТћ┐ТЕЪжќбсЂФсѓѕсѓІтј│т»єсЂфт»ЕТЪ╗сЂет«Ътю░Уф┐ТЪ╗№╝џућ│УФІтєЁт«╣сЂеТЈљтЄ║сЂЋсѓїсЂЪУе╝ТІаТЏИжАъ№╝ѕтБ▓СИітЈ░тИ│сђЂтЄ║тІцу░┐сђЂУ│ЃжЄЉтЈ░тИ│сЂфсЂЕ№╝ЅсЂ«ТЋ┤тљѕТђДсЂїУЕ│у┤░сЂФуб║УфЇсЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓті┤тЃЇт▒ђсѓёУБютіЕжЄЉС║ІтІЎт▒ђсЂ«т»ЕТЪ╗т«ўсЃ╗уЏБТЪ╗т«ўсЂ»сђЂТіюсЂЇТЅЊсЂАсЂДС╝ЂТЦГсЂИсЂ«т«Ътю░Уф┐ТЪ╗сѓњт«ЪТќйсЂЌсђЂућ│УФІтєЁт«╣сЂїт«ЪТЁІсЂетљѕсЂБсЂдсЂёсѓІсЂІсѓњтј│сЂЌсЂЈсЃЂсѓДсЃЃсѓ»сЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
- С╝џУеѕТцюТЪ╗жЎбсЂФсѓѕсѓІтЪиУАїТцюТЪ╗№╝џС╝џУеѕТцюТЪ╗жЎбсЂ»сђЂтЏйсЂ«УБютіЕжЄЉтѕХт║дтЁеСйЊсЂ«тЪиУАїсЂїжЂЕТГБсЂФУАїсѓЈсѓїсЂдсЂёсѓІсЂІсѓњТцюТЪ╗сЂЎсѓІТЕЪжќбсЂДсЂѓсѓісђЂсЂЮсЂ«ТїЄТЉўсЂ»ТЦхсѓЂсЂджЄЇтцДсЂфТёЈтЉ│сѓњТїЂсЂАсЂЙсЂЎсђѓ
- тєЁжЃетЉіуЎ║сЃ╗жђџта▒тѕХт║дсЂ«Т┤╗уће№╝џтЙЊТЦГтЊАсђЂтЁЃтЙЊТЦГтЊАсђЂтЈќт╝ЋтЁѕсЂфсЂЕсЂІсѓЅсЂ«ТЃЁта▒ТЈљСЙЏ№╝ѕтєЁжЃетЉіуЎ║№╝ЅсЂ»сђЂСИЇТГБтЈЌухдсЂїуЎ║УдџсЂЎсѓІСИ╗УдЂсЂфухїУи»сЂ«СИђсЂцсЂДсЂЎсђѓуЅ╣сЂФті┤тЃЇжќбС┐ѓсЂ«тіЕТѕљжЄЉсЂФсЂісЂёсЂдсЂ»сђЂУДБжЏЄсѓёті┤тЃЇТЮАС╗ХсѓњтиАсѓІсЃѕсЃЕсЃќсЃФсЂІсѓЅсђЂтЁЃтЙЊТЦГтЊАсЂїті┤тЃЇт▒ђсЂФжђџта▒сЂЎсѓІсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЂїтцџуЎ║сЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
ТЇюТЪ╗ТЕЪжќбсЂесЂ«жђБТљ║т╝итїќ
УАїТћ┐ТЕЪжќбсЂ»сђЂСИЇТГБтЈЌухдсЂИсЂ«т»Йт┐юсѓњт╝итїќсЂЌсЂдсЂісѓісђЂТѓфУ│фсЂфС║ІТАѕсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»уЕЇТЦхуџёсЂФтѕЉС║ІтЉіуЎ║сѓњжђ▓сѓЂсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
жЃйжЂЊт║юуюїті┤тЃЇт▒ђсЂ»сђЂСИЇТГБтЈЌухдт»Йт┐юсЂФсЂцсЂёсЂджЃйжЂЊт║юуюїУГдт»ЪТюгжЃесЂежђБТљ║сѓњтЏ│сѓісђЂТЃЁта▒тЁ▒ТюЅуГЅсѓњУАїсЂёсЂфсЂїсѓЅуЕЇТЦхуџёсЂФУф┐ТЪ╗сѓњсЂЎсЂЎсѓЂсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂ»сђЂУАїТћ┐уџёсЂфсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂ«жЂЕућесЂесђЂтѕЉС║ІуџёсЂфУ▓гС╗╗У┐йтЈісЂїт»єТјЦсЂФжђБТљ║сЂЌсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесѓњТёЈтЉ│сЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
УАїТћ┐Уф┐ТЪ╗сЂ«жЂјуеІсЂДсђЂСИЇТГБсЂ«ТёЈтЏ│сѓёУеѕућ╗ТђДсђЂтЈЇтЙЕТђДсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсђЂТѓфУ│фсЂДсЂѓсѓІсЂетѕцТќГсЂЋсѓїсЂЪта┤тљѕсђЂУАїТћ┐тЂ┤сЂ»У║іУ║ЄсЂфсЂЈТЇюТЪ╗ТЕЪжќбсЂФт»ЙсЂЌтѕЉС║ІтЉіуЎ║сѓњУАїсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсЂ«Т«хжџјсЂФУЄ│сѓІсЂесђЂС╝ЂТЦГтЂ┤сЂ»УбФуќЉУђЁсЂесЂЌсЂдУГдт»ЪсЃ╗Тцют»ЪсЂФсѓѕсѓІТЇюТЪ╗сЂ«т»ЙУ▒АсЂесЂфсѓісђЂУАїТћ┐т»Йт┐юсЂІсѓЅтѕЉС║Іт╝ЂУГисЂИсЂежў▓тЙАТѕдуЋЦсѓњтѕЄсѓіТЏ┐сЂѕсЂфсЂЉсѓїсЂ░сЂфсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓС╝ЂТЦГсЂФсЂесЂБсЂдсђЂУАїТћ┐Уф┐ТЪ╗сЂїтДІсЂЙсѓІтѕЮТюЪсЂ«Т«хжџјсЂДсђЂсЂёсЂІсЂФтѕЉС║ІтЉіуЎ║сЂ«сЃфсѓ╣сѓ»сѓњу«АуљєсЂЎсѓІсЂІсЂїсђЂтГўС║АсЂФжќбсѓЈсѓІТюђжЄЇУдЂУф▓жАїсЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
уй░тЅЄсЃфсѓ╣сѓ»сѓњТюђт░ЈтїќсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«т╝ЂУГитБФсЂФсѓѕсѓІтЁиСйЊуџёт»ЙуГќ
СИЇТГБтЈЌухдсЂ«уќЉсЂёсЂїућЪсЂўсЂЪта┤тљѕсђЂС╝ЂТЦГсЂїтЈќсѓІсЂ╣сЂЇУАїтІЋсЂ»сђЂтЋЈжАїсѓњжџаУћйсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂТЌЕТюЪсЂФС║Іт«ЪсѓњУфЇсѓЂсђЂУЄфСИ╗уџёсЂФт»Йт┐юсѓњжђ▓сѓЂсѓІсЂЊсЂесЂДсЂЎсђѓуй░тЅЄсЃфсѓ╣сѓ»сЂ«у«АуљєсЂФсЂісЂёсЂдсђЂт╝ЂУГитБФсЂ«т░ѓжќђуџёсЂфсѓхсЃЮсЃ╝сЃѕсЂ»СИЇтЈ»ТгасЂДсЂЎсђѓ
тЇ▒ТЕЪу«АуљєсЂ«УдЂсЂДсЂѓсѓІТЌЕТюЪсЂ«УЄфСИ╗У┐ћжѓёсЃ╗УЄфти▒ућ│тЉісЂ«тюДтђњуџёсЃАсЃфсЃЃсЃѕ
СИЇТГБтЈЌухдсЂФсЂ»сђЂТЌЕТюЪсЂ«УЄфСИ╗У┐ћжѓёсЃ╗УЄфти▒ућ│тЉісѓњУАїсЂєсЂЊсЂесЂїсђЂуй░тЅЄсЃфсѓ╣сѓ»сѓњТюђт░ЈтїќсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«ТюђсѓѓуЈЙт«ЪуџёсЂІсЂцТюЅті╣сЂфжў▓тЙАуГќсЂДсЂЎсђѓ
сЂЊсѓїсЂ«ТюђтцДсЂ«сЃАсЃфсЃЃсЃѕсЂ»сђЂУАїТћ┐т║ЂсЂФсѓѕсѓІтіау«ЌжЄЉ№╝ѕ20%№╝ЅсЂфсЂЕсЂ«сЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂїтЁЇжЎцсЂЙсЂЪсЂ»У╗йТИЏсЂЋсѓїсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїжФўсЂЙсѓІсЂЊсЂесЂДсЂЎсђѓсЂЋсѓЅсЂФжЄЇУдЂсЂфсЂ«сЂ»сђЂУАїТћ┐тЂ┤сЂФт»ЙсЂЌсђїуюЪТЉ»сЂФтЈЇуюЂсЂЌсђЂтЋЈжАїУДБТ▒║сЂФуЕЇТЦхуџёсЂФтЇћтіЏсЂЎсѓІтД┐тІбсђЇсѓњуц║сЂЎсЂЊсЂесЂДсђЂтѕЉС║ІтЉіуЎ║сЂ«тЏъжЂ┐сѓњуЏ«ТїЄсЂЎсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсѓІуѓ╣сЂДсЂЎсђѓ
т«ЪжџЏсЂФсђЂухїТИѕућБТЦГуюЂсЂїу«АУйёсЂЎсѓІСИђТЎѓТћ»ТЈ┤жЄЉсѓёТюѕТгАТћ»ТЈ┤жЄЉсЂФсЂісЂёсЂдсЂ»сђЂТЌбсЂФТЋ░тЇЃС╗ХсѓѓсЂ«УЄфСИ╗У┐ћжѓёсЂ«ућ│тЄ║сЂїсЂѓсѓісђЂСЙІсЂѕсЂ░ТюѕТгАТћ»ТЈ┤жЄЉсЂДсЂ»10,818С╗ХсЂ«ућ│тЄ║сђЂу┤ё12тёё4,300СИЄтєєсЂїУ┐ћжѓёТИѕсЂ┐сЂесЂфсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсЂ«С║Іт«ЪсЂ»сђЂУАїТћ┐тЂ┤сЂїУЄфСИ╗ућ│тЉісЂФсѓѕсѓІУДБТ▒║сЂ«жЂЊсѓњуЕЇТЦхуџёсЂФТЈљСЙЏсЂЌсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесѓњуц║сЂЌсЂдсЂісѓісђЂС╝ЂТЦГсЂ»сЂЊсЂ«ТЕЪС╝џсѓњТюђтцДжЎљсЂФТ┤╗ућесЂЎсЂ╣сЂЇсЂДсЂЎсђѓ
т╝ЂУГитБФсЂ«тй╣тЅ▓сЂ»С║Іт«ЪжќбС┐ѓсЂ«Уф┐ТЪ╗сЂеУАїТћ┐ТЕЪжќбсЂесЂ«ТіўУАЮС╗БУАї
УЄфСИ╗ућ│тЉісЂФсЂ»сђЂтЇўсЂФУ│ЄжЄЉсѓњУ┐ћжѓёсЂЎсѓІС╗ЦСИісЂ«УцЄжЏЉсЂфТЅІуХџсЂЇсЂїС╝┤сЂёсЂЙсЂЎсђѓСИЇТГБсЂ«ТГБуб║сЂфС║Іт«ЪжќбС┐ѓсЂ«Уф┐ТЪ╗сђЂУ┐ћжѓёт»ЙУ▒АТюЪжќЊсЂ«уЅ╣т«џсђЂУАїТћ┐ТЕЪжќбсЂесЂ«т░ѓжќђуџёсЂфТіўУАЮсЂїт┐ЁУдЂсЂесЂфсѓІсЂЪсѓЂсђЂС╝ЂТЦГтЇўуІгсЂДсЂЊсѓїсѓњУАїсЂєсЂ«сЂ»сЃфсѓ╣сѓ»сЂїжФўсЂЎсЂјсЂЙсЂЎсђѓт╝ЂУГитБФсЂ»сђЂС╗ЦСИІсЂ«тй╣тЅ▓сѓњТІЁсЂёС╝ЂТЦГсЂ«жў▓тЙАсѓњсѓхсЃЮсЃ╝сЃѕсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
С║Іт«ЪжќбС┐ѓсЂ«ТГБуб║сЂфУф┐ТЪ╗сЃ╗тѕЄсѓітѕєсЂЉ
т╝ЂУГитБФсЂ»сђЂС╝ЂТЦГтєЁжЃесЂ«С╝џУеѕУ│ЄТќЎсђЂті┤тЃЇУеўжї▓сђЂжђџС┐АУеўжї▓сЂфсЂЕсѓњу▓ЙТЪ╗сЂЌсђЂСИЇТГБсЂ«уеІт║дсђЂжќбСИјсЂЌсЂЪС║║уЅЕсђЂТЋЁТёЈТђДсЂ«ТюЅуёАсѓњт«бУд│уџёсЂФтѕцТќГсЂЌсЂЙсЂЎсђѓуЅ╣сЂФсђЂТѓфУ│фсЂфТћ»ТЈ┤С║ІТЦГУђЁсЂФсѓѕсѓІсђїсѓГсЃЃсѓ»сЃљсЃЃсѓ»сђЇсѓ╣сѓГсЃ╝сЃасЂФти╗сЂЇУЙ╝сЂЙсѓїсЂЪта┤тљѕсђЂС╝ЂТЦГтЂ┤сЂ«сђїУбФт«│УђЁТђДсђЇсѓњТ│ЋуџёсЂФСИ╗т╝хсЂЌсђЂТёЈтЏ│уџёсЂфСИЇТГБсЂДсЂ»сЂфсЂІсЂБсЂЪсЂесЂёсЂєС║Іт«ЪжќбС┐ѓсЂ«тѕЄсѓітѕєсЂЉсѓњУАїсЂєсЂЊсЂесЂїтЈ»УЃйсЂДсЂЎсђѓ
УАїТћ┐ТіўУАЮсЂ«С╗БУАїсЂесЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂ«Тюђт░Јтїќ
УАїТћ┐ТЕЪжќб№╝ѕті┤тЃЇт▒ђсђЂС║ІтІЎт▒ђсЂфсЂЕ№╝ЅсЂесЂ«С║цТИЅсѓњтЁесЂдт╝ЂУГитБФсЂїС╗БУАїсЂЌсЂЙсЂЎсђѓУ┐ћжѓёжАЇсЂ«у«Ќт«џсђЂтіау«ЌжЄЉсѓёт╗ХТ╗ъжЄЉсЂ«тЈќсѓіТЅ▒сЂёсЂФсЂцсЂёсЂдсђЂТюђсѓѓС╝ЂТЦГсЂФТюЅтѕЕсЂфУДБТ▒║сѓњуЏ«ТїЄсЂЌсЂдТіўУАЮсѓњУАїсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂФсѓѕсѓісђЂС╝ЂТЦГсЂ«ТІЁтйЊУђЁсЂїУАїТћ┐тЂ┤сЂ«тј│сЂЌсЂёУ┐йТ▒ѓсЂФуЏ┤ТјЦсЂЋсѓЅсЂЋсѓїсѓІсЂЊсЂесѓњжў▓сЂјсђЂтєижЮЎсЂІсЂцуџёуб║сЂфт»Йт┐юсѓњуХЎуХџсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
тѕЉС║ІтЉіуЎ║сЃфсѓ╣сѓ»сЂ«у«Ауљє
УАїТћ┐ТЕЪжќбсЂїУГдт»ЪсЂесЂ«жђБТљ║сѓњт╝итїќсЂЌсЂдсЂёсѓІуЈЙС╗БсЂФсЂісЂёсЂдсђЂУАїТћ┐т»Йт┐юсЂ»тљїТЎѓсЂФтѕЉС║Іжў▓тЙАсЂ«тЂ┤жЮбсѓњТїЂсЂАсЂЙсЂЎсђѓт╝ЂУГитБФсЂ»сђЂУЄфСИ╗ућ│тЉісѓёУАїТћ┐сЂИсЂ«тЇћтіЏтД┐тІбсЂїсђЂт░єТЮЦуџёсЂФУГдт»ЪсѓёТцют»ЪсЂФсѓѕсѓІТЇюТЪ╗сЂїУАїсѓЈсѓїсЂЪта┤тљѕсЂФсђЂсђїТЃЁуіХжЁїжЄЈсЂ«СйЎтю░сЂїсЂѓсѓІсђЇсЂЙсЂЪсЂ»сђїУхиУе┤сѓњуїХС║ѕсЂЎсЂ╣сЂЇсђЇсЂетѕцТќГсЂЋсѓїсѓІсЂЪсѓЂсЂ«жЄЇУдЂсЂфТЮљТќЎсЂесЂфсѓІсѓѕсЂєсђЂТѕдуЋЦуџёсЂФт»Йт┐юсѓњжђ▓сѓЂсЂЙсЂЎсђѓТйютюеуџёсЂфтѕЉС║ІсЃфсѓ╣сѓ»сѓњу«АуљєсЂЌсЂфсЂїсѓЅсђЂУАїТћ┐тЄдтѕєсѓњТюђт░ЈжЎљсЂФТіЉсЂѕсѓІтїЁТІгуџёсЂфсЃфсѓ╣сѓ»сЃъсЃЇсѓИсЃАсЃ│сЃѕсЂЊсЂЮсЂїсђЂт╝ЂУГитБФсЂФСЙЮжа╝сЂЎсѓІТюђтцДсЂ«СЙАтђцсЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЂЙсЂесѓЂ№╝џсЃбсЃјсЃфсѓ╣Т│ЋтЙІС║ІтІЎТЅђсЂФсѓѕсѓІСИЇТГБтЈЌухдт»Йт┐юсѓхсЃЮсЃ╝сЃѕ
тйЊС║ІтІЎТЅђсЂ«т░ѓжќђТђДсЂет╝исЂ┐
сЃбсЃјсЃфсѓ╣Т│ЋтЙІС║ІтІЎТЅђсЂ»сђЂУБютіЕжЄЉсЃ╗тіЕТѕљжЄЉсЂ«СИЇТГБтЈЌухдтЋЈжАїсђЂуЅ╣сЂФITт░јтЁЦУБютіЕжЄЉсѓёсЃфсѓ╣сѓГсЃфсЃ│сѓ░тіЕТѕљжЄЉ№╝ѕС║║ТЮљжќІуЎ║Тћ»ТЈ┤тіЕТѕљжЄЉ№╝ЅсЂесЂёсЂБсЂЪУцЄжЏЉсЂфсѓ╣сѓГсЃ╝сЃасЂФти╗сЂЇУЙ╝сЂЙсѓїсЂЪС╝ЂТЦГсЂ«т»Йт┐юсЂФуЅ╣тїќсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
СИЇТГБтЈЌухдсЂ»сђЂтЇўсЂфсѓІС╝џУеѕСИісЂ«тЋЈжАїсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂжФўт║дсЂфITТіђУАЊсѓётЦЉу┤ёТДІжђасЂїухАсѓђсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЂїтцџуЎ║сЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓтйЊС║ІтІЎТЅђсЂ»сђЂITсЃ╗сЃєсЃЃсѓ»тѕєжЄјсЂФт╝исЂёсЂесЂёсЂєт░ѓжќђуџёсЂфуЪЦУдІсѓњТ┤╗ућесЂЌсђЂУцЄжЏЉсЂфућ│УФІТЏИжАъсѓёсђЂтцќжЃеТћ»ТЈ┤ТЦГУђЁсЂїС╗ЋТјЏсЂЉсЂЪухёу╣ћуџёсЂфсђїт«ЪУ│фуёАТќЎсђЇсђїсѓГсЃЃсѓ»сЃљсЃЃсѓ»сђЇсѓ╣сѓГсЃ╝сЃасЂ«ТДІжђасѓњТ│ЋуџёсЂФУДБТўјсЂЌсђЂС╝ЂТЦГсЂ«жў▓тЙАТѕдуЋЦсѓњТДІу»ЅсЂЌсЂЙсЂЎсђѓС╝џУеѕТцюТЪ╗жЎбсЂ«Уф┐ТЪ╗сЂФсѓѕсЂБсЂдсѓѓсђЂсЃфсѓ╣сѓГсЃфсЃ│сѓ░тіЕТѕљжЄЉсѓёITт░јтЁЦУБютіЕжЄЉсЂФсЂісЂЉсѓІСИЇТГБсЂїт║Ѓу»ёсЂФсѓЈсЂЪсѓІТДІжђауџёсЂфУф▓жАїсЂДсЂѓсѓІсЂЊсЂесЂїТїЄТЉўсЂЋсѓїсЂдсЂісѓісђЂтйЊС║ІтІЎТЅђсЂ»сЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂфУцЄжЏЉсЂфТАѕС╗ХсЂФсЂісЂЉсѓІт░ѓжќђт«ХсЂесЂЌсЂдсђЂтЇ▒ТЕЪуџёсЂфуіХТ│ЂсЂФжЎЦсЂБсЂЪС╝ЂТЦГсѓњсѓхсЃЮсЃ╝сЃѕсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
уй░тЅЄсЂїуб║т«џсЂЎсѓІтЅЇсЂФсђЂт░ѓжќђт«ХсЂИуЏИУФЄсѓњ
тіЕТѕљжЄЉсЃ╗УБютіЕжЄЉсЂ«СИЇТГБтЈЌухдсЂїсѓѓсЂЪсѓЅсЂЎсђїуй░тЅЄсђЇсЂ»сђЂТюђжФў10т╣┤С╗ЦСИІсЂ«ТІўудЂтѕЉсЂесЂёсЂєтѕЉС║Іуй░сђЂтЈЌухджАЇсЂ«120%сѓњУХЁсЂѕсѓІухїТИѕуџёсЃџсЃісЃФсЃєсѓБсђЂсЂЮсЂЌсЂдт«ЪтљЇтЁгУАесЂФсѓѕсѓІС║ІТЦГсЂ«С┐АућесЂ«тц▒тбюсѓњтљФсЂ┐сЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсѓЅсЂ«уй░тЅЄсЂ»сђЂС╝ЂТЦГсЂ«тГўуХџсѓњтидтЈ│сЂЎсѓІжЄЇтцДсЂфсЃфсѓ╣сѓ»сЂДсЂѓсѓісђЂТ▒║сЂЌсЂдуюІжЂјсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂ»сЂДсЂЇсЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
СИЇТГБтЈЌухдсЂ«уќЉсЂёсЂїућЪсЂўсЂЪТ«хжџјсѓёсђЂУАїТћ┐сЂІсѓЅУф┐ТЪ╗сЂїтЁЦсЂБсЂЪтѕЮТюЪсЂ«Т«хжџјсЂЊсЂЮсЂїсђЂС╗ітЙїсЂ«т»Йт┐юсѓњтидтЈ│сЂЎсѓІТюђсѓѓжЄЇУдЂсЂфсѓ┐сѓцсЃЪсЃ│сѓ░сЂДсЂЎсђѓтіау«ЌжЄЉсЂ«тЁЇжЎцсђЂтѕЉС║ІтЉіуЎ║сЂ«тЏъжЂ┐сђЂсЂЮсЂЌсЂдуцЙС╝џуџётѕХУБЂсЂ«Тюђт░ЈтїќсѓњуЏ«ТїЄсЂЎсЂЪсѓЂсЂФсѓѓсђЂтєижЮЎсЂІсЂцУ┐ЁжђЪсЂфт»Йт┐юсЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
СИЇТГБтЈЌухдтЋЈжАїсЂДсЂіТѓЕсЂ┐сЂ«та┤тљѕсђЂуй░тЅЄсЂїуб║т«џсЂЌсђЂтЈќсѓіУ┐ћсЂЌсЂ«сЂцсЂІсЂфсЂёС║ІТЁІсЂФжЎЦсѓІтЅЇсЂФсђЂт«ЪуИЙсЂет░ѓжќђТђДсѓњТїЂсЂцт╝ЂУГитБФсЂФсЂћуЏИУФЄсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓсЃбсЃјсЃфсѓ╣Т│ЋтЙІС║ІтІЎТЅђсЂ»сђЂтЙАуцЙсЂ«уіХТ│ЂсѓњУЕ│у┤░сЂФсЃњсѓбсЃфсЃ│сѓ░сЂЌсђЂТюђсѓѓТюЅтѕЕсЂфУДБТ▒║уГќсЂИсЂет░јсЂЈсЂЪсѓЂсЂ«сѓхсЃЮсЃ╝сЃѕсѓњТЈљСЙЏсЂёсЂЪсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
тіЕТѕљжЄЉсЃ╗УБютіЕжЄЉсЂ«СИЇТГБтЈЌухдт»Йт┐юсЂФжќбсЂЎсѓІтйЊС║ІтІЎТЅђсЂ«тЁиСйЊуџёсЂфсѓхсЃЮсЃ╝сЃѕтєЁт«╣сђЂсЃЋсЃГсЃ╝сђЂТќЎжЄЉСйЊу│╗сЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»сђЂС╗ЦСИІсЂ«т░ѓжќђсЃџсЃ╝сѓИсЂФсЂдУЕ│у┤░сѓњсЂћуб║УфЇсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓ
сѓФсЃєсѓ┤сЃфсЃ╝: ITсЃ╗сЃЎсЃ│сЃЂсЃБсЃ╝сЂ«С╝ЂТЦГТ│ЋтІЎ