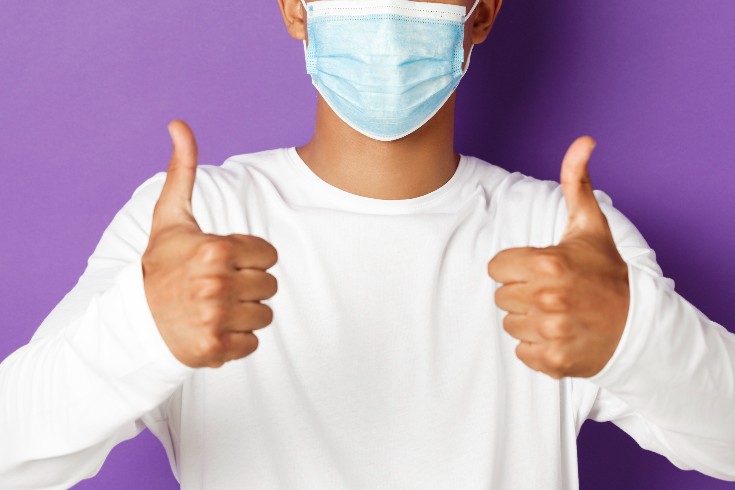еәғе‘ҠеҸ–еј•еҹәжң¬еҘ‘зҙ„жӣёгҒ§гғҲгғ©гғ–гғ«гӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иҰҒгғҒгӮ§гғғгӮҜгғқгӮӨгғігғҲ

гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒ®зҷ»е ҙгҒ§еәғе‘ҠгҒ®жүӢжі•гҒҢеӨҡж§ҳеҢ–гҒ—гҖҒеәғе‘ҠеҸ–еј•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҘ‘зҙ„гҒ®еҶ…е®№гӮӮгҖҢйӣ‘иӘҢеәғе‘ҠгҖҚгҖҢгғҚгғғгғҲеәғе‘ҠгҖҚгҖҢTVеәғе‘ҠгҖҚгҒЁгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®гғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ®зү№жҖ§гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰдҪңжҲҗгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжҘӯеӢҷгӮ’дҫқй јгҒ•гӮҢгҒҹиҖ…гҒҢеәғе‘ҠжҘӯеӢҷгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒдҫқй јдё»гҒҢгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—е ұй…¬гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒЁгҒ„гҒҶи«ӢиІ еҘ‘зҙ„гҒ®1гҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒҜеӨүгӮҸгӮҠгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«жҘӯеӢҷгҒ®дҫқй јгӮ’иЎҢгҒҶе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒеҹәжң¬зҡ„гҒӘеҸ–еј•жқЎд»¶гӮ’е®ҡгӮҒгҒҹеҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒЁеҖӢеҲҘгҒ®еҸ–еј•гҒ®еҶ…е®№гӮ’е®ҡгӮҒгҒҹеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ®2ж®өйҡҺгҒ®еҘ‘зҙ„гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒ«жјҸгӮҢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҠдёҚе®Ңе…ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§д»ҠеӣһгҒҜгҖҒз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘеәғе‘ҠеҸ–еј•гҒ®йҡӣгҒ«жңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҖҢеәғе‘ҠеҸ–еј•еҹәжң¬еҘ‘зҙ„жӣёгҖҚгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҒз„Ўз”ЁгҒӘгғҲгғ©гғ–гғ«гӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҮҚиҰҒгғқгӮӨгғігғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ігҒ—гҒҸиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҖҖгҖҖ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
еәғе‘ҠеҸ–еј•еҹәжң¬еҘ‘зҙ„жӣёгҒЁгҒҜпјҹ

еәғе‘ҠеҸ–еј•еҹәжң¬еҘ‘зҙ„жӣёгҒЁгҒҜгҖҒеәғе‘Ҡдё»гҒЁгӮўгғүгғҶгӮҜгғҷгғігғҖгӮ„еәғе‘Ҡд»ЈзҗҶеә—гҒ®й–“гҒ§гҖҒз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶеәғе‘ҠеҮәзЁҝгҒ«е…ұйҖҡгҒҷгӮӢжқЎд»¶гӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰеҗҲж„ҸгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҘ‘зҙ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲеәғе‘ҠгҒҜеӘ’дҪ“гӮ„иӘІйҮ‘жҢҮжЁҷгҒҢеӨҡж§ҳгҒӘгҒҹгӮҒгҖҒжқЎд»¶гӮ’жӣ–жҳ§гҒӘгҒҫгҒҫе§ӢгӮҒгӮӢгҒЁи§ЈйҮҲгҒ®йҒ•гҒ„гӮ„гғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢиө·гҒҚгӮ„гҒҷгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒ§гҒҜд»ҘдёӢгӮ’еҢ…жӢ¬зҡ„гҒ«е®ҡгӮҒгҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
- йҒ©з”ЁзҜ„еӣІгӮ„з”ЁиӘһгҒ®е®ҡзҫ©
- зҙ жқҗгҒ®еҜ©жҹ»гӮ„жҺІијүеҒңжӯўгҒ®еҹәжә–
- жҲҗжһңиЁҲжё¬гҒ®ж–№жі•
- гӮўгғүгғ•гғ©гӮҰгғүеҜҫзӯ–
- гғ–гғ©гғігғүгӮ»гғјгғ•гғҶгӮЈ
- з§ҳеҜҶдҝқжҢҒгӮ„зҹҘиІЎгҒ®жүұгҒ„
- еҶҚ委託гҒ®еҸҜеҗҰ
- жҗҚе®іиі е„ҹ
- еҘ‘зҙ„жңҹй–“гҒЁжӣҙж–°
е®ҹеӢҷгҒ§гҒҜгҖҒеҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒҢе…ЁгӮӯгғЈгғігғҡгғјгғігҒ®е…ұйҖҡгғ«гғјгғ«гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгӮӯгғЈгғігғҡгғјгғіеҚҳдҪҚгҒ§з· зөҗгҒҷгӮӢжіЁж–Үгғ»и«ӢжӣёпјҲеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„пјүгҒҢе…·дҪ“зҡ„гҒӘжқЎд»¶гӮ’зўәе®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзҙ жқҗгҒҜеәғе‘Ҡдё»гҒҢз”Ёж„ҸгҒ—гҖҒгғҷгғігғҖгҒҜеҜ©жҹ»еҹәжә–гҒ«еҹәгҒҘгҒҚжҺІијүеҸҜеҗҰгӮ’еҲӨж–ӯгҒ—гҖҒе•ҸйЎҢгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°жҺІијүеҒңжӯўгӮӮгҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒ®гҒҢеҺҹеүҮгҒ§гҒҷгҖӮ
жҲҗжһңиЁҲжё¬гҒҜгғҷгғігғҖеҒҙгҒ®иЁҲжё¬еҖӨгӮ’еҹәжә–гҒ«гҒ—гҒӨгҒӨгҖҒд№–йӣўгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„е ҙеҗҲгҒҜеҚ”иӯ°гҒ§иӘҝж•ҙгҒҷгӮӢжһ зө„гҒҝгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮгӮўгғүгғ•гғ©гӮҰгғүгҒёгҒ®еҜҫеҝңжүӢй ҶгӮ„иҝ”йҮ‘еҲӨж–ӯгҖҒжҺІијүе…ҲгҒ®е“ҒиіӘзўәдҝқгӮ„еҸ–гӮҠдёӢгҒ’и«ӢжұӮгҒ®гғ«гғјгғ«гҖҒйӣ»еӯҗеҘ‘зҙ„гӮ„еҚ°зҙҷзЁҺгҒ®иІ жӢ…гӮӮжҳҺзўәгҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁе®ҹеӢҷгҒ§иҝ·гҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
еҚҳзҷәгҒ®еЈІиІ·еҘ‘зҙ„гӮ„дёҖиҲ¬зҡ„гҒӘжҘӯеӢҷ委託еҘ‘зҙ„гҒҜгҖҒзӣ®зҡ„зү©гӮ„жҲҗжһңзү©гҒ®еҸ—гҒ‘жёЎгҒ—гӮ’дёӯеҝғгҒ«зө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒеәғе‘ҠеҸ–еј•еҹәжң¬еҘ‘зҙ„жӣёгҒҜгҖҒеәғе‘Ҡзү№жңүгҒ®еҜ©жҹ»гғ»иЁҲжё¬гғ»гғ•гғ©гӮҰгғүеҜҫзӯ–гғ»гғ–гғ©гғігғүе®үе…ЁгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйҒӢз”ЁеүҚжҸҗгҒ®иҰҒзҙ гӮ’зө„гҒҝиҫјгӮҖзӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгӮ’дёҒеҜ§гҒ«ж•ҙеӮҷгҒҷгӮӢгҒ»гҒ©гҖҒгӮӯгғЈгғігғҡгғјгғігҒ®ж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒҢйҖҹгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒжі•д»ӨгӮ„жЁ©еҲ©гҖҒе“ҒиіӘгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгӮ’жҠ‘гҒҲгҒҹйҒӢз”ЁгӮ’е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒ®еҪ№еүІ

еҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®зӣёжүӢгҒЁгҒ®й–“гҒ§е°ҶжқҘгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠеҗҢж§ҳгҒ®еҸ–еј•гҒҢз№°гӮҠиҝ”гҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҖҒе…ЁгҒҰгҒ®еҸ–еј•гҒ«е…ұйҖҡгҒҷгӮӢгҖҢеҘ‘зҙ„гҒ®зҜ„еӣІгҖҚгҖҢж”Ҝжү•жқЎд»¶гҖҚгҖҢжҗҚе®іиі е„ҹгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®еҹәжң¬дәӢй …гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒеҚ”иӯ°гҒ—з· зөҗгҒҷгӮӢеҘ‘зҙ„гҒ§гҒҷгҖӮ
еҖӢгҖ…гҒ®еҸ–еј•гҒ®йҡӣгҒ«гҒҜеҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒ§е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®еҸ–еј•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҖҢжҘӯеӢҷгҒ®еҶ…е®№гҖҚгҖҢе ұй…¬гҖҚгҖҢзҙҚжңҹгҖҚгҒӘгҒ©гӮ’е®ҡгӮҒгҒҹз°Ўжҳ“гҒӘеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒ§е®ҡгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҖӢеҲҘгҒ®еҸ–еј•гӮ’иЎҢгҒҶйҡӣгҒ«гҒҜжҘӯеӢҷгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒ гҒ‘гҒ§жёҲгӮҖгҒҹгӮҒгҖҒеҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁеҖӢгҖ…гҒ®еҸ–еј•гӮ’гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«йҖІгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ§гҒҜгҖҒж¬Ўй …гҒӢгӮүеәғе‘ҠеҸ–еј•еҹәжң¬еҘ‘зҙ„жӣёгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘгғҒгӮ§гғғгӮҜгғқгӮӨгғігғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘжқЎж–ҮгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еәғе‘ҠеҸ–еј•еҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒ®дҫқй јжҘӯеӢҷгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎй …

第в—ҜжқЎ (е®ҡзҫ©)гҖҖ
жң¬еҘ‘зҙ„гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеәғе‘Ҡе®ЈдјқеҸ–еј•гҒЁгҒҜгҖҒз”ІгҒҢд№ҷгҒ«еҜҫгҒ—з”ІгҒ®е•Ҷе“ҒгҒҠгӮҲгҒігӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®е®Јдјқеәғе‘ҠгҒ«й–ўгҒ—гҖҒж¬ЎгҒ®еҗ„еҸ·гҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ«е®ҡгӮҒгӮӢжҘӯеӢҷ(д»ҘдёӢгҖҒгҖҢжң¬д»¶жҘӯеӢҷгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶ)гӮ’дҫқй јгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҜҫдҫЎгӮ’д№ҷгҒ«ж”Ҝжү•гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒҶгҖӮ
1. еәғе‘Ҡе®Јдјқж–№жі•гҒ®дјҒз”»гғ»з«ӢжЎҲ
2. еәғе‘ҠеӘ’дҪ“гҒ®йҒёе®ҡ(гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲеәғе‘ҠгҖҒеҸҠгҒігҒқгҒ®д»–гҒ®йӣ»еӯҗгғЎгғҮгӮЈгӮўзӯү)
3. еәғе‘ҠгҒ®еҮәзЁҝз®ЎзҗҶ
4. еүҚеҗ„еҸ·гҒ«д»ҳеёҜй–ўйҖЈгҒ—гҒҰз”ІгҒҢд№ҷгҒ«зҷәжіЁгҒҷгӮӢдёҖеҲҮгҒ®жҘӯеӢҷ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒеҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒ®еүҚжҸҗгҒЁгҒӘгӮӢгҖҢеәғе‘Ҡе®ЈдјқеҸ–еј•гҖҚгҒ®еҶ…е®№гӮ’е®ҡзҫ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒ4гҒ«е®ҡгӮҒгӮӢд»ҳеёҜжҘӯеӢҷгҒ®дёӯгҒ«гҖҢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгӮ„гҖҢеҲ¶дҪңгҖҚгҒӘгҒ©гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒжң¬д»¶жҘӯеӢҷгҒ«гҖҢеәғе‘ҠгҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғіеҸҠгҒіеҲ¶дҪңгҖҚгҒЁеҲҶгҒ‘гҒҰиЁҳијүгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҖҒеҲ¶дҪңзү©гҒ«гҒҜгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘжЁ©еҲ©гҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҖ…гҒӮгӮҠгҖҒеҲ¶дҪңгҒ®йҒҺзЁӢгҒ§з”ҹгҒҝеҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢжҲҗжһңзү©гҖҚгҒ®жүұгҒ„гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒзү№иЁұжЁ©гғ»ж„ҸеҢ жЁ©гғ»и‘—дҪңжЁ©гҒӘгҒ©гҒ®гҖҢзҹҘзҡ„иІЎз”ЈжЁ©гҖҚгҒ®её°еұһгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎй …гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
еҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒЁеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ®й–ўдҝӮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎй …

第в—ҜжқЎ (жң¬еҘ‘зҙ„гҒЁеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„)
в’Ҳ жң¬еҘ‘зҙ„гҒ®е®ҡгӮҒгҒҜгҖҒеәғе‘Ҡе®ЈдјқеҸ–еј•гҒ«й–ўгҒ—зҷәжіЁгҒ”гҒЁгҒ«з”Ід№ҷй–“гҒ§з· зөҗгҒҷгӮӢе…ЁгҒҰгҒ®еҖӢеҲҘгҒ®еҘ‘зҙ„(д»ҘдёӢгҖҢеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶ)гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҖӮ
2. еүҚй …гҒ®иҰҸе®ҡгҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒз”Ід№ҷй–“гҒ§жң¬еҘ‘зҙ„гҒЁз•°гҒӘгӮӢе®ҡгӮҒгӮ’гҒ—гҒҹеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜеҪ“и©ІеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒҢе„Әе…ҲгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®жқЎй …гҒҜгҖҢеҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҖҚгҒЁгҖҢеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҖҚгҒ®й–ўдҝӮгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒ2гҒӨгҒ®еҘ‘зҙ„гҒ®й–“гҒ§зҹӣзӣҫгӮ„жҠөи§ҰгҒҷгӮӢе®ҡгӮҒгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ®е„Әе…Ҳй ҶдҪҚгӮ’иҰҸе®ҡгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гӮ’е„Әе…ҲгҒҷгӮӢгҒЁиҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжӢ…еҪ“иҖ…гғ¬гғҷгғ«гҒ§дәӨгӮҸгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„еҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ§еҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒ®е®ҡгӮҒгӮ’еӨүжӣҙгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒејҒиӯ·еЈ«гҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰеҚҒеҲҶжӨңиЁҺгҒ—дҪңжҲҗгҒ—гҒҹеҹәжң¬еҘ‘зҙ„гӮ’е„Әе…ҲгҒҷгӮӢж–№гҒҢе®үеҝғгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е„Әе…ҲжқЎй …гҒҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒеҫҢгҒ«з· зөҗгҒ—гҒҹеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒҢе„Әе…ҲгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҰӢж–№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҳҺзўәгҒ«иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„д»ҘдёҠгҒҜгҒ©гҒЎгӮүгҒҢе„Әе…ҲгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®жқЎй …гӮ’е…ҘгӮҢеҝҳгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁеҪ“дәӢиҖ…й–“гҒ§гғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«зҷәеұ•гҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
еҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎй …

第в—ҜжқЎ (еҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ®жҲҗз«Ӣ)
в’Ҳ еҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒҜгҖҒзҷәжіЁж—ҘгҖҒжҘӯеӢҷгҒ®еҗҚз§°гҖҒжҘӯеӢҷгҒ®еҶ…е®№гҖҒж•°йҮҸгҖҒеҜҫдҫЎгҖҒеұҘиЎҢжҷӮжңҹгҒӘгҒ©гҒ®еҝ…иҰҒдәӢй …гӮ’иЁҳијүгҒ—гҒҹжіЁж–ҮжӣёгӮ’з”ІгҒҢд№ҷгҒ«йҖҒд»ҳгҒ—гҖҒеҪ“и©ІжіЁж–ҮжӣёгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжіЁж–Үи«ӢжӣёгӮ’д№ҷгҒҢз”ІгҒ«йҖҒд»ҳгҒ—з”ІгҒҢеҸ—й ҳгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«жҲҗз«ӢгҒҷгӮӢгҖӮ
в’ү еүҚй …гҒ®жіЁж–ҮжӣёеҸҠгҒіжіЁж–Үи«ӢжӣёгҒҜгҖҒйӣ»еӯҗгғЎгғјгғ«гҒҫгҒҹгҒҜгғ•гӮЎгӮҜгӮ·гғҹгғӘйҖҒдҝЎгӮҲгҒЈгҒҰд»ЈжӣҝгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
еҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ§гҒҜгҖҒжҘӯеӢҷдҫқй јгҒ®еҶ…е®№гӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгҒ„гҒӨеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒҢжҲҗз«ӢгҒҷгӮӢгҒӢгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒжҘӯеӢҷ委託гӮ„еҸ—иЁ—гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘй …зӣ®гҒ«жјҸгӮҢгҒҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒз”Ід№ҷй–“гҒ§гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒжіЁж–ҮжӣёгӮ„жіЁж–Үи«ӢжӣёгҒӘгҒ©гҒ®жӣёејҸгӮ’жұәгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
дёҠиЁҳгҒ®иҰӢжң¬гҒ«гҒҜ1гҒӨе•ҸйЎҢзӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒжіЁж–ҮжӣёгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиҝ”зӯ”жңҹйҷҗгҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒҠгҒӢгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒзҷәжіЁиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢз”ІгҒҢжұӮгӮҒгӮӢеұҘиЎҢжҷӮжңҹгҒ«й–“гҒ«еҗҲгӮҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ®иІ¬д»»гҒ®жүҖеңЁгҒҢгҒӮгҒ„гҒҫгҒ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжқЎж–ҮгӮ’第1й …гҒ®жң«е°ҫгҒ«иҝҪиЁҳгҒ—гҖҒеӣһзӯ”жңҹйҷҗгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгҒҹгҒ гҒ—гҖҒжіЁж–ҮжӣёгҒ®йҖҒд»ҳеҫҢв—Ӣв—Ӣе–¶жҘӯж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ«д№ҷгҒӢгӮүз”ІгҒ«еҜҫгҒ—еӣһзӯ”гҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒеҪ“и©ІжіЁж–ҮжӣёгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒҜжҲҗз«ӢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒҝгҒӘгҒҷгҖӮгҖҚ
жҘӯеӢҷгҒ®еҶҚ委託гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎй …
第в—ҜжқЎ (еҶҚ委託)
в’Ҳ д№ҷгҒҜгҖҒжң¬еҘ‘зҙ„еҸҲгҒҜеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ«еҹәгҒҘгҒҸжҘӯеӢҷгҒ®е…ЁйғЁеҸҲгҒҜдёҖйғЁгӮ’з”ІгҒ®дәӢеүҚеҗҢж„ҸгҒӘгҒ—гҒ«з¬¬дёүиҖ…гҒ«еҶҚ委託гҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
в’ү д№ҷгҒҢеүҚй …гҒ®еҶҚ委託гӮ’иЎҢгҒҶе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒд№ҷгҒҜеҪ“и©ІеҶҚ委託е…ҲгҒ«жң¬еҘ‘зҙ„еҸҠгҒіеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒЁеҗҢзӯүгҒ®зҫ©еӢҷгӮ’йҒөе®ҲгҒ•гҒӣгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒд№ҷгҒҢеҶҚ委託гӮ’иЎҢгҒӘгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒжң¬еҘ‘зҙ„еҸҠгҒіеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ§иІ гҒҶд№ҷгҒ®иІ¬д»»гӮ’е…ҚгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ
еҶҚ委託гҒ®е ҙеҗҲгҒ«гғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒз”ІгҒ®дәӢеүҚеҗҢж„ҸгӮ’жқЎд»¶гҒЁгҒҷгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ§гҒҷгҖӮдёҠиЁҳгҒ®дҫӢгҒ§гҒҜгҖҒдәӢеүҚеҗҢж„ҸгҒҜдёҚиҰҒгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжҘӯеӢҷеҶ…е®№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜдәӢеүҚеҗҢж„ҸгӮ’жқЎд»¶гҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒҶ1гҒӨгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒҜгҖҒ第дёүиҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжң¬еҘ‘зҙ„еҸҠгҒіеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ§е®ҡгӮҒгӮӢд№ҷгҒЁеҗҢзӯүгҒ®зҫ©еӢҷгӮ’йҒөе®ҲгҒ•гҒӣгӮӢгҒЁиҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гӮӮз”Ід№ҷй–“гҒ®еҘ‘зҙ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰжң¬еҘ‘зҙ„гҒ®еҪ“дәӢиҖ…гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„第дёүиҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒз”ІгҒҢеҘ‘зҙ„йҒ•еҸҚгӮ’зҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰжҗҚе®іиі е„ҹгӮ’и«ӢжұӮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгғӘгӮ№гӮҜгӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒ
гҖҢеҶҚ委託е…ҲгҒ®иЎҢзӮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®дёҖеҲҮгҒ®иІ¬д»»гҒҜд№ҷгҒҢиІ гҒҶгӮӮгҒ®гҒЁгҒҷгӮӢгҖҚ
гҒЁгҒ„гҒҶжқЎж–ҮгӮ’第1й …жң«е°ҫгҒ«иҝҪиЁҳгҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
з§ҳеҜҶдҝқжҢҒгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎй …

第в—ҜжқЎ (з§ҳеҜҶдҝқжҢҒ)
в’Ҳ з”ІеҸҠгҒід№ҷгҒҜгҖҒжң¬еҘ‘зҙ„еҸҠгҒіеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ«еҹәгҒҘгҒҚзӣёжүӢж–№гҒӢгӮүз§ҳеҜҶгҒ§гҒӮгӮӢж—ЁгӮ’жҳҺзӨәгҒ•гӮҢгҒҹдёҠгҒ§й–ӢзӨәгҒ•гӮҢгҒҹжғ…е ұ(д»ҘдёӢгҖҢз§ҳеҜҶжғ…е ұгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶ)гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒжң¬еҘ‘зҙ„еҸҠгҒіеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ®зӣ®зҡ„д»ҘеӨ–гҒ«дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒҡгҖҒзӣёжүӢж–№гҒ®дәӢеүҚгҒ®жӣёйқўгҒ«гӮҲгӮӢжүҝи«ҫгӮ’еҫ—гҒҡгҒ«з¬¬дёүиҖ…гҒ«й–ӢзӨәгҖҒжјҸжҙ©гҒ—гҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
з§ҳеҜҶдҝқжҢҒжқЎй …гҒ§жңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜвҖңдҪ•гҒҢз§ҳеҜҶгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢгҒӢвҖқгӮ’зү№е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҠиЁҳгҒ§гҒҜгҖҢз§ҳеҜҶгҒ§гҒӮгӮӢж—ЁгӮ’жҳҺзӨәгҒ•гӮҢгҒҹжғ…е ұгҖҚгҒЁиҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҸЈй ӯгӮ„гғўгғӢгӮҝгғјгҒ®з”»йқўдёҠгҒ§й–ӢзӨәгҒ•гӮҢгҒҹжғ…е ұгҒҜиЁјжӢ гҒ«ж®ӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒеҪ“и©Із§ҳеҜҶжғ…е ұгҒ®жјҸжҙ©гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«е®Ҳз§ҳзҫ©еӢҷйҒ•еҸҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒҷгӮӢдё»ејөгҒҢеӣ°йӣЈгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒеҸЈй ӯгҒӘгҒ©гҒ®иЁҳйҢІгҒ«ж®ӢгӮүгҒӘгҒ„з§ҳеҜҶжғ…е ұгӮ’зү№е®ҡгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒз§ҳеҜҶжғ…е ұгҒ®иЈңи¶ігҒЁгҒ—гҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж–ҮиЁҖгӮ’иҝҪиЁҳгҒҷгӮӢгҒЁиүҜгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҢеҸЈй ӯгӮ„гғўгғӢгӮҝгғјгҒ®з”»йқўдёҠгҒ§й–ӢзӨәгҒ•гӮҢгҒҹжғ…е ұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒй–ӢзӨәгҒ®йҡӣгҒ«з§ҳеҜҶгҒ§гҒӮгӮӢж—ЁгӮ’е‘ҠзҹҘгҒ—гҖҒгҒӢгҒӨв—Ӣж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ«з§ҳеҜҶжғ…е ұгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁеҸҠгҒігҒқгҒ®еҶ…е®№гӮ’жӣёйқўгҒ§зӣёжүӢж–№гҒ«йҖҡзҹҘгҒ—гҒҹжғ…е ұгҖҚ
гҒӘгҒҠгҖҒз§ҳеҜҶдҝқжҢҒжқЎй …гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰи©іиҝ°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жңүеҠ№жңҹй–“еҸҠгҒіжӣҙж–°гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎй …
第в—ҜжқЎ (жңүеҠ№жңҹй–“)
в’Ҳ жң¬еҘ‘зҙ„гҒ®жңүеҠ№жңҹй–“гҒҜгҖҒв—Ӣв—Ӣе№ҙв—Ӣв—ӢжңҲв—Ӣв—Ӣж—ҘгӮҲгӮҠв—Ӣв—Ӣе№ҙв—Ӣв—ӢжңҲв—Ӣв—Ӣж—ҘгҒҫгҒ§гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮдҪҶгҒ—гҖҒжңҹй–“жәҖдәҶгҒ®3гғөжңҲеүҚгҒҫгҒ§гҒ«з”Ід№ҷгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгӮүгӮӮжң¬еҘ‘зҙ„гӮ’жӣҙж–°гҒ—гҒӘгҒ„ж—ЁгҒ®з”ігҒ—еҮәгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҒ•гӮүгҒ«1е№ҙ間延長гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҖҒд»ҘеҫҢгӮӮеҗҢж§ҳгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
в’ү жң¬еҘ‘зҙ„гҒҢзөӮдәҶгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒЁгҒ„гҒҲгҒ©гӮӮгҖҒжң¬еҘ‘зҙ„гҒ®жңүеҠ№жңҹй–“дёӯгҒ«з· зөҗгҒ•гӮҢгҒҹеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒҢеӯҳз¶ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒеҪ“и©ІеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ«еҜҫгҒ—еј•гҒҚз¶ҡгҒҚжң¬еҘ‘зҙ„гҒ®еҗ„иҰҸе®ҡгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
жңүеҠ№жңҹй–“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎй …гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒҜеҘ‘зҙ„гҒҢиҮӘеӢ•жӣҙж–°гҒӢеҗҰгҒӢгҖҒиҮӘеӢ•жӣҙж–°гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°зөӮдәҶгҒҷгӮӢж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжҳҺзўәгҒ«иҰҸе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ§гҒҷгҖӮ
дёҠиЁҳгҒ®е ҙеҗҲгҖҒе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒҜгҖҢжӣҙж–°гҒ—гҒӘгҒ„ж—ЁгҒ®з”ігҒ—еҮәгҖҚгӮ’гҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢжҳҺиЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
еҸЈй ӯгҒ§з”ігҒ—еҮәгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁиЁјжӢ гҒҢж®ӢгӮүгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒжңҹй–“жәҖдәҶгҒ®3гғөжңҲеүҚгҒҫгҒ§гҒ«з”ігҒ—еҮәгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ§гғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гҒӘгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒжӣҙж–°гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎй …гҒ«гҒҜгҖҢжӣёйқўеҸҲгҒҜгғЎгғјгғ«гҒ§з”ігҒ—еҮәгӮӢгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁгҖҒз”ігҒ—еҮәгҒ®ж–№жі•гӮӮжҢҮе®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁиүҜгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒз§ҳеҜҶдҝқжҢҒзҫ©еӢҷгӮ„жҗҚе®іиі е„ҹгҒӘгҒ©гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҰҸе®ҡгҒҜеҘ‘зҙ„жңҹй–“зөӮдәҶеҫҢгӮӮеӯҳз¶ҡгҒ•гҒӣгҒҹж–№гҒҢиүҜгҒ„е ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒиҰӢжң¬гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҖӢеҲҘгҒ®жқЎй …гҒ®дёӯгҒ§иҰҸе®ҡгҒҷгӮӢж–№жі•гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжңүеҠ№жңҹй–“гҒЁгҒҜеҲҘгҒ«гҖҢеӯҳз¶ҡжқЎй …гҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҰҸе®ҡгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҖҒеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢжқЎй …гӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰиЁҳијүгҒҷгӮӢж–№жі•гӮӮиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
жҗҚе®іиі е„ҹгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжқЎй …
第в—ҜжқЎ (жҗҚе®іиі е„ҹ)
д№ҷгҒҜгҖҒжң¬еҘ‘зҙ„еҸҠгҒіеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ§е®ҡгӮҒгҒҹжң¬д»¶жҘӯеӢҷгҒ®дёҚеұҘиЎҢгҖҒеҸҲгҒҜеұҘиЎҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒз”ІгҒҢжҗҚе®ігӮ’иў«гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«з”ҹгҒҳгҒҹйҖҡеёёгҒӢгҒӨзӣҙжҺҘгҒ®жҗҚе®ігӮ’иі е„ҹгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮдҪҶгҒ—гҖҒиі е„ҹйЎҚгҒҜеҪ“и©Іжң¬д»¶жҘӯеӢҷгҒ«еҜҫгҒ—з”ІгҒҢд№ҷгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰж”Ҝжү•гҒЈгҒҹйҮ‘йЎҚгӮ’дёҠйҷҗгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
жҗҚе®іиі е„ҹгҒ®жқЎй …гҒҜеҝ…гҒҡе…ҘгӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®еҶ…е®№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҸҢж–№гҒ«жҗҚе®ігҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜеҸҢж–№гҒ®жҗҚе®іиі е„ҹзҫ©еӢҷгӮ’е®ҡгӮҒгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҠиЁҳгҒ®иҰӢжң¬гҒ§гҒҜд№ҷгҒ®з”ІгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҗҚе®іиі е„ҹзҫ©еӢҷгҒ®гҒҝгӮ’иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеүҚиҝ°гҒ®гҖҢз§ҳеҜҶдҝқжҢҒзҫ©еӢҷгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҸҢж–№гҒҢзҫ©еӢҷгӮ’иІ гҒҶжқЎй …гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒжң¬еҘ‘зҙ„гҒ®йҒ•еҸҚгҒ«гӮҲгӮӢжҗҚе®ігҒҢд№ҷгҒ«з”ҹгҒҳгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҜҫеҮҰж–№жі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒ第1й …гҒ§з”ІеҸҲгҒҜд№ҷгҒҢжң¬еҘ‘зҙ„еҸҠгҒіеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ«йҒ•еҸҚгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒ®жҗҚе®іиі е„ҹзҫ©еӢҷгӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒҠгҒҚгҖҒ2й …гҒ§иҰӢжң¬гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«д№ҷгҒ®з”ІгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҗҚе®іиі е„ҹзҫ©еӢҷгӮ’е®ҡгӮҒгӮӢгҒ®гҒҢиүҜгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒдёҠиЁҳгҒ®жқЎй …гҒ®гҒҫгҒҫгҒ гҒЁд№ҷгҒҢиІ гҒҶиі е„ҹиІ¬д»»гҒ®зҜ„еӣІгҒҢеәғгҒҷгҒҺгӮӢгҒ®гҒ§ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҒ©з”ЁйҷӨеӨ–гҒ®иЈңи¶іжқЎж–ҮгӮ’иҝҪиЁҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢдҪҶгҒ—гҖҒд№ҷгҒ®ж•…ж„ҸгҒҫгҒҹгҒҜгҖҒйҮҚйҒҺеӨұгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜйҒ©з”ЁгҒ—гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒЁгҒҷгӮӢгҖҚ
еҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒЁеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒ®зЁҺжі•дёҠгҒ®жүұгҒ„
еҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒЁеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒЁгҒ§гҒҜеҚ°зҙҷзЁҺжі•дёҠгҒ®жүұгҒ„гҒҢз•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§жіЁж„ҸгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
зү№е®ҡгҒ®зӣёжүӢгҒЁ3гғ¶жңҲд»ҘдёҠгҒ®жңҹй–“гҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«еҸ–еј•гӮ’иЎҢгҒҶйҡӣгҒ®еҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҚ°зҙҷзЁҺжі•гҒ®з¬¬7еҸ·ж–ҮжӣёгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§1йҖҡгҒ«гҒӨгҒҚ4,000еҶҶгҒ®еҸҺе…ҘеҚ°зҙҷгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒҜи«ӢиІ гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҘ‘зҙ„жӣёгҒӘгҒ®гҒ§з¬¬2еҸ·ж–ҮжӣёгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒи«ӢиІ йҮ‘йЎҚгҒ«еҝңгҒҳгҒҰе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹеҚ°зҙҷзЁҺгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӮгҒ—гҖҒеҘ‘зҙ„жӣёгҒ«еҸҺе…ҘеҚ°зҙҷгӮ’иІјгӮүгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҒҜ2еҖҚгҒ®йҒҺжҖ зЁҺгҒҢиӘІгҒ•гӮҢгҖҒж¶ҲеҚ°гӮ’гҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гӮӮеҗҢйЎҚгҒ®йҒҺжҖ зЁҺгҒ®ж”Ҝжү•гҒҢиӘІгҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҚ°зҙҷзЁҺгҒ®иІ жӢ…гҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮеҹәжң¬еҘ‘зҙ„гҒ§иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮӮиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒпјҡеәғе‘ҠеҸ–еј•еҹәжң¬еҘ‘зҙ„жӣёгҒ§гғҲгғ©гғ–гғ«гӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«
еәғе‘ҠеҸ–еј•еҹәжң¬еҘ‘зҙ„жӣёгҒ®еҪ№еүІгӮ„еҖӢеҲҘеҘ‘зҙ„гҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒӘгҒ©гҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘзҹҘиӯҳгӮ„гҖҒзӣёжүӢж–№гҒЁгҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘгғҒгӮ§гғғгӮҜгғқгӮӨгғігғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгҒӘгҒ©гҒ®ж–°гҒ—гҒ„гғЎгғҮгӮЈгӮўгӮ’еәғе‘ҠеӘ’дҪ“гҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®еҶ…е®№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘгғӘгӮ№гӮҜгӮ’жҠұгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘеҪўж…ӢгҒҢгҒӮгӮӢеәғе‘ҠеҸ–еј•гӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘжі•еҫӢзҹҘиӯҳгҒЁзөҢйЁ“иұҠеҜҢгҒӘжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒ«зӣёи«ҮгҒ—гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲеәғе‘Ҡд»ЈзҗҶеә—гҒ®еҘ‘зҙ„жӣёгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰи©іиҝ°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҪ“дәӢеӢҷжүҖгҒ«гӮҲгӮӢеҘ‘зҙ„жӣёдҪңжҲҗгғ»гғ¬гғ“гғҘгғјзӯүгҒ®гҒ”жЎҲеҶ…
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒITгғ»гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгғ»гғ“гӮёгғҚгӮ№гҒ«еј·гҒҝгӮ’жҢҒгҒӨжі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеәғе‘ҠеҸ–еј•еҹәжң¬еҘ‘зҙ„жӣёгҒ«йҷҗгӮүгҒҡгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘеҘ‘зҙ„жӣёгҒ®дҪңжҲҗгғ»гғ¬гғ“гғҘгғјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҘӯеӢҷгӮ’гҖҒйЎ§е•Ҹе…ҲдјҒжҘӯж§ҳгӮ„гӮҜгғ©гӮӨгӮўгғігғҲдјҒжҘӯж§ҳгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёӢиЁҳгғҡгғјгӮёгҒ«гҒҰи©ізҙ°гӮ’иЁҳијүгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ