µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│Ģ’╝łµÖ»ĶĪ©µ│Ģ’╝ēŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü»’╝¤µ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü«ķüĢŃüäŃéäõ║ŗõŠŗŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¦ŻĶ¬¼

µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│Ģ’╝łµÖ»ĶĪ©µ│Ģ’╝ēŃü©Ńü»ŃĆüµÖ»ÕōüŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶ”ÅÕłČŃéäÕ║āÕæŖĶĪ©ńż║Ńü½ŃüżŃüäŃü”Õ«ÜŃéüŃü¤µ│ĢÕŠŗŃü¦ŃüÖŃĆéµÖ»ÕōüŃéäÕ║āÕæŖĶĪ©ńż║Ńü½ŃéłŃéŗõĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃüĖŃü«õĖŹÕĮōŃü¬Ķ¬żĶ¬ŹŃéäĶ¬śÕ░ÄŃéÆń”üŃüśŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüķüĢÕÅŹŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü»Õ║āÕæŖÕü£µŁóŃü«µÄ¬ńĮ«ŃüīÕÅ¢ŃéēŃéīŃü¤ŃéŖĶ¬▓ÕŠ┤ķćæŃü«ń┤Źõ╗śÕæĮõ╗żŃüīÕć║ŃüĢŃéīŃü¤ŃéŖŃüÖŃéŗŃü«Ńü¦µ│©µäÅŃüīÕ┐ģĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹÕĮōĶĪ©ńż║Ńü»ŃĆüŃĆīÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃĆŹŃü©ŃĆīµ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃĆŹŃü«’╝ÆŃüżŃü½Õż¦ŃüŹŃüÅÕłåŃüæŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©µ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ®│ŃüŚŃüÅĶ¦ŻĶ¬¼ŃüÖŃéŗŃü©Ńü©ŃééŃü½ŃĆüÕ«¤ķÜøŃü«õ║ŗõŠŗŃééń┤╣õ╗ŗŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕ║āÕæŖŃü¦Ńü«µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢķüĢÕÅŹŃéÆÕø×ķü┐ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü«ÕÅéĶĆāŃü½ŃüŚŃü”ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
ŃüōŃü«Ķ©śõ║ŗŃü«ńø«µ¼Ī
µÖ»ĶĪ©µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü»
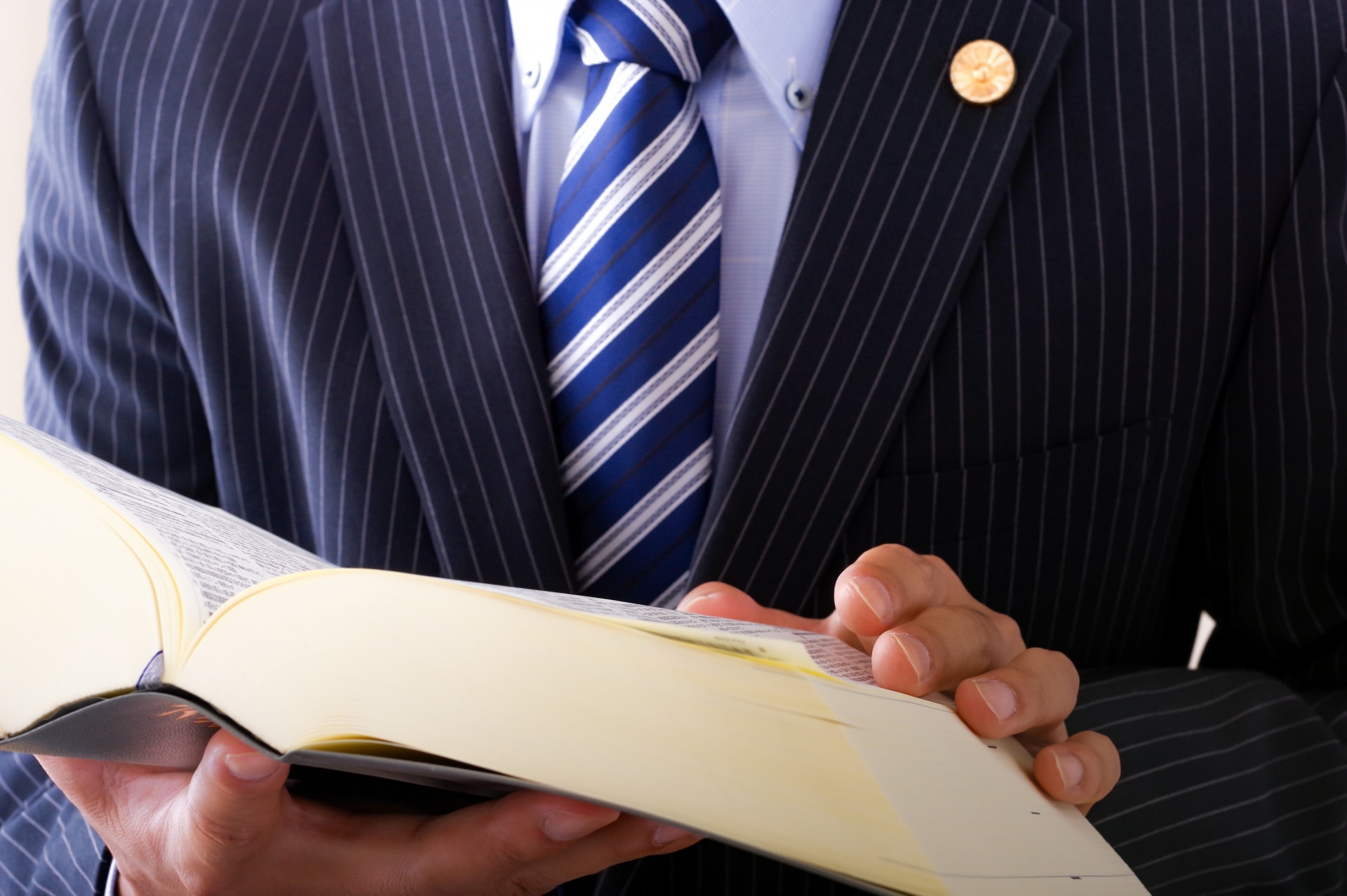
Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü»ŃĆüµÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”õĖŗĶ©śŃü«ŃéłŃüåŃü½Õ«ÜńŠ®ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝łµÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│Ģń¼¼5µØĪń¼¼1ÕÅĘ’╝ēŃĆé
ÕĢåÕōüÕÅłŃü»ÕĮ╣ÕŗÖŃü«ÕōüĶ│¬ŃĆüĶ”ŵĀ╝ŃüØŃü«õ╗¢Ńü«ÕåģÕ«╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüõĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆüÕ«¤ķÜøŃü«ŃééŃü«ŃéłŃéŖŃééĶæŚŃüŚŃüÅÕä¬Ķē»Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©ńż║ŃüŚŃĆüÕÅłŃü»õ║ŗÕ«¤Ńü½ńøĖķüĢŃüŚŃü”ÕĮōĶ®▓õ║ŗµźŁĶĆģŃü©ÕÉīń©«ŃĆüĶŗźŃüŚŃüÅŃü»ķĪ×õ╝╝Ńü«ÕĢåÕōüĶŗźŃüŚŃüÅŃü»ÕĮ╣ÕŗÖŃéÆõŠøńĄ”ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗõ╗¢Ńü«õ║ŗµźŁĶĆģŃü½õ┐éŃéŗŃééŃü«ŃéłŃéŖŃééŃĆüĶæŚŃüŚŃüÅÕä¬Ķē»Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©ńż║ŃüÖĶĪ©ńż║Ńü¦ŃüéŃüŻŃü”ŃĆüõĖŹÕĮōŃü½ķĪ¦Õ«óŃéÆĶ¬śÕ╝ĢŃüŚŃĆüõĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½ŃéłŃéŗĶć¬õĖ╗ńÜäŃüŗŃüżÕÉłńÉåńÜäŃü¬ķüĖµŖ×ŃéÆķś╗Õ«│ŃüÖŃéŗµüÉŃéīŃüīŃüéŃéŗŃü©Ķ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃéŗŃééŃü«
Õ╝Ģńö©’╝Üe-GOV’Į£õĖŹÕĮōµÖ»ÕōüķĪ×ÕÅŖŃü│õĖŹÕĮōĶĪ©ńż║ķś▓µŁó
ÕÅ¢ŃéŖµē▒ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗÕĢåÕōüŃā╗ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«ÕōüĶ│¬ŃéäÕåģÕ«╣ŃüīŃĆüÕ«¤ķÜøŃü«ŃééŃü«ŃéłŃéŖŃééĶæŚŃüŚŃüÅÕä¬ŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü©õĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½Ķ¬żĶ¬ŹŃüĢŃüøŃéŗÕ║āÕæŖĶĪ©ńż║Ńü»ŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü½ŃüéŃü¤ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
õĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃüīÕĢåÕōüŃā╗ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃéÆķüĖµŖ×ŃüÖŃéŗŃü©ŃüŹŃü½Ńü»ŃĆüŃüØŃü«ÕĢåÕōüŃā╗ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«ÕōüĶ│¬ŃéäµĆ¦ĶāĮŃü¬Ńü®ŃéÆÕłżµ¢ŁµØɵ¢ÖŃü©ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüÕ«¤ķÜøŃéłŃéŖŃééÕōüĶ│¬ŃéäµĆ¦ĶāĮŃüīķ½śŃüäÕĢåÕōüŃü¦ŃüéŃéŗŃü©µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½Ķ¬żĶ¬ŹŃüĢŃüøŃü”ŃĆüõĖŹµŁŻŃü½ÕżÜŃüÅÕŻ▓ŃéŹŃüåŃü©ŃüÖŃéŗŃü«ŃéÆķś▓µŁóŃüÉŃü«Ńüīńø«ńÜäŃü¦ŃüÖŃĆé
ķ¢óķĆŻĶ©śõ║ŗ’╝ֻܵÕōüĶĪ©ńż║µ│Ģ’╝łµÖ»ĶĪ©µ│Ģ’╝ēŃü©Ńü»’╝¤ŃéÅŃüŗŃéŖŃéäŃüÖŃüäĶ¦ŻĶ¬¼Ńü©ķüĢÕÅŹõ║ŗõŠŗŃā╗ńĮ░ÕēćŃéÆń┤╣õ╗ŗ
µÖ»ĶĪ©µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗµ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü«ķüĢŃüä
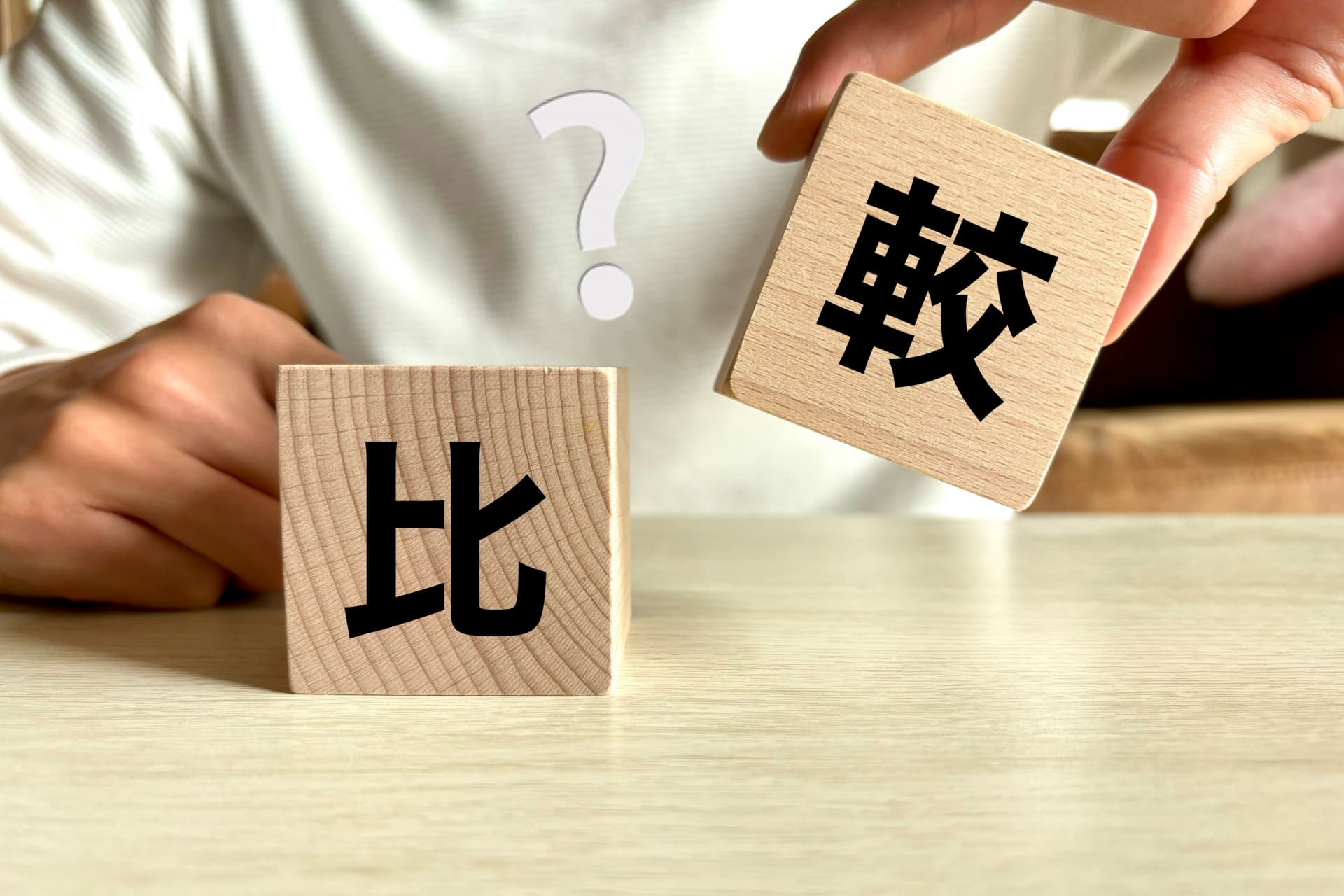
µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗõĖŹÕĮōĶĪ©ńż║Ńü½Ńü»ŃĆüÕż¦ŃüŹŃüÅÕłåŃüæŃü”ŃĆīÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃĆŹŃü©ŃĆīµ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃĆŹŃü«’╝ÆŃüżŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃĆīµ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃĆŹŃü©Ńü»Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü¬Ķ”ÅÕłČŃü¬Ńü«ŃüŗŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©µĘĘÕÉīŃüŚŃü¬ŃüäŃéłŃüåŃü½ŃĆüńÉåĶ¦ŻŃéƵĘ▒ŃéüŃü”ŃüŖŃüŹŃüŠŃüŚŃéćŃüåŃĆé
µ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü»
µ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü»ŃĆüµČłĶ▓╗ĶĆģÕ║üŃü«Õģ¼Õ╝ÅŃéĄŃéżŃāłŃü½ŃéłŃéŗŃü©õĖŗĶ©śŃü«ŃéłŃüåŃü½Ķ©śĶ╝ēŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝łµÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│Ģń¼¼5µØĪń¼¼2ÕÅĘ’╝ēŃĆé
õ║ŗµźŁĶĆģŃüīŃĆüĶć¬ÕĘ▒Ńü«õŠøńĄ”ŃüÖŃéŗÕĢåÕōüŃā╗ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«ÕÅ¢Õ╝ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃĆüõŠĪµĀ╝ŃüØŃü«õ╗¢Ńü«ÕÅ¢Õ╝ĢµØĪõ╗ČŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüõĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃĆü
Õć║ÕģĖ’╝ܵȳĶ▓╗ĶĆģÕ║ü’Į£µ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü»
(1)Õ«¤ķÜøŃü«ŃééŃü«ŃéłŃéŖŃééÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ńøĖµēŗµ¢╣Ńü½ĶæŚŃüŚŃüŵ£ēÕł®Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©õĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½Ķ¬żĶ¬ŹŃüĢŃéīŃéŗŃééŃü«(2)ń½Čõ║ēõ║ŗµźŁĶĆģŃü½õ┐éŃéŗŃééŃü«ŃéłŃéŖŃééÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ńøĖµēŗµ¢╣Ńü½ĶæŚŃüŚŃüŵ£ēÕł®Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©õĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½Ķ¬żĶ¬ŹŃüĢŃéīŃéŗŃééŃü«
ÕÅ¢Õ╝ĢŃü«ÕåģÕ«╣Ńü¦õ╗¢õ║ŗµźŁĶĆģŃü©µ»öĶ╝āŃüŚŃü”µ£ēÕł®Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©Ķ¬żĶ¬ŹŃüĢŃüøŃéŗŃüōŃü©ŃüīŃĆīµ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃĆŹŃü¦ŃüÖŃĆéÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃüīÕĢåÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«ÕōüĶ│¬Ńā╗Ķ”ŵĀ╝Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Õ«ÜńŠ®ŃüĢŃéīŃéŗŃü«Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüµ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü»ÕÅ¢Õ╝ĢÕåģÕ«╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü«Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Õ«ÜńŠ®ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©ÕÉīµ¦śŃü½ŃĆüÕĢåÕōüŃā╗ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«ÕÅ¢Õ╝ĢµØĪõ╗ČŃéÆÕ«¤ķÜøŃéłŃéŖŃééŃéłŃüŵĆØŃéÅŃüøŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ÕŻ▓õĖŖŃéÆõĖŹµŁŻŃü½ŃéóŃāāŃāŚŃüĢŃüøŃéŗŃüōŃü©ŃéÆķś▓µŁóŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńø«ńÜäŃü©ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü«ÕģĘõĮōõŠŗ
µČłĶ▓╗ĶĆģÕ║üŃü«ŃéĄŃéżŃāłŃü¦Ńü»Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü«ÕģĘõĮōõŠŗŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüõĖŗĶ©śŃü«ŃééŃü«ŃüīµÄ▓Ķ╝ēŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õĖŁÕÅżĶć¬ÕŗĢĶ╗ŖŃü«ÕĀ┤ÕÉłĶ▓®ÕŻ▓ŃüÖŃéŗõĖŁÕÅżĶć¬ÕŗĢĶ╗ŖŃü«ĶĄ░ĶĪīĶĘØķøóŃéÆ3õĖćkmŃü©ĶĪ©ńż║ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕ«¤Ńü»10õĖćkmõ╗źõĖŖĶĄ░ĶĪīŃüŚŃü¤õĖŁÕÅżĶć¬ÕŗĢĶ╗ŖŃü«ŃāĪŃā╝Ńé┐Ńā╝ŃéÆÕĘ╗ŃüŹµł╗ŃüŚŃü¤ŃééŃü«ŃüĀŃüŻŃü¤ŃĆé
ķŻ¤ĶéēŃü«ÕĀ┤ÕÉłÕøĮńöŻµ£ēÕÉŹŃā¢Ńā®Ńā│ŃāēńēøŃü«ĶéēŃü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃü«ŃéłŃüåŃü½ĶĪ©ńż║ŃüŚŃü”Ķ▓®ÕŻ▓ŃüŚŃü”ŃüäŃü¤ŃüīŃĆüÕ«¤Ńü»Ńā¢Ńā®Ńā│ŃāēńēøŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüäÕøĮńöŻńēøĶéēŃüĀŃüŻŃü¤ŃĆé
Õī╗ńÖéõ┐ØķÖ║Ńü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆīÕģźķÖó1µŚźńø«ŃüŗŃéēÕģźķÖóńĄ”õ╗śķćæŃéÆŃüŖµö»µēĢŃüäŃĆŹŃü©ĶĪ©ńż║ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕģźķÖóÕŠīŃü½Ķ©║µ¢ŁŃüīńó║Õ«ÜŃüŚŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃü«µŚźŃüŗŃéēŃü«ńĄ”õ╗śķćæŃüŚŃüŗµö»µēĢŃéÅŃéīŃü¬ŃüäŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃüĀŃüŻŃü¤ŃĆéŃéóŃé»Ńé╗ŃéĄŃā¬Ńā╝Ńü«ÕĀ┤ÕÉłÕż®ńäČŃāĆŃéżŃāżŃéÆõĮ┐ńö©ŃüŚŃü¤ŃāŹŃāāŃé»Ńā¼Ńé╣Ńü«ŃéłŃüåŃü½ĶĪ©ńż║ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüõĮ┐ŃéÅŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü»ŃüÖŃü╣Ńü”õ║║ķĆĀŃāĆŃéżŃāżŃüĀŃüŻŃü¤ŃĆé
Õć║ÕģĖ’╝ܵȳĶ▓╗ĶĆģÕ║ü’Į£Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü»
ŃüōŃéīŃéēŃü»ŃĆüÕĢåÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«ÕōüĶ│¬ŃéƵĀ╣µŗĀŃü¬ŃüÅÕä¬ŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüŚŃü”Õ«Żõ╝ØŃüŚŃü”ŃüäŃéŗõ║ŗõŠŗŃü¦ŃüÖŃĆéĶ¬ćÕż¦Õ║āÕæŖŃĆüķŻ¤ÕōüŃü«ńöŻÕ£░ÕüĮķĆĀŃĆüĶ┤ŗõĮ£ŃéƵ£¼ńē®Ńü©ÕüĮŃüŻŃü”Ķ▓®ÕŻ▓ŃüÖŃéŗŃü¬Ńü®ŃĆüŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬ŃāæŃé┐Ńā╝Ńā│ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéµĢģµäÅŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅĶ¬żŃüŻŃü”ĶÖÜÕüĮŃü«µāģÕĀ▒ŃéÆĶĪ©ńż║ŃüŚŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü¦ŃééŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü«ÕģĘõĮōõŠŗ
µČłĶ▓╗ĶĆģÕ║üŃü«Õģ¼Õ╝ÅŃéĄŃéżŃāłŃü¦Ńü»µ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü«õ║ŗõŠŗŃü©ŃüŚŃü”ŃĆüõĖŗĶ©śŃü«ŃééŃü«ŃüīµÄ▓Ķ╝ēŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Õż¢Ķ▓©Õ«Üµ£¤Ńü«ÕĀ┤ÕÉłÕż¢Ķ▓©ķĀÉķćæŃü«ÕÅŚÕÅ¢Õł®µü»ŃéƵēŗµĢ░µ¢ÖµŖ£ŃüŹŃü¦ĶĪ©ńż║ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕ«¤Ķ│¬ńÜäŃü¬ÕÅŚÕÅ¢ķĪŹŃü»ĶĪ©ńż║Ńü«1/3õ╗źõĖŗŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃĆé
Õć║ÕģĖ’╝ܵȳĶ▓╗ĶĆģÕ║ü’Į£µ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü»
ķüŗķĆüµźŁĶĆģŃü«ÕĀ┤ÕÉłÕ¤║µ£¼õŠĪµĀ╝ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüøŃüÜŃü½ŃĆüŃĆīõ╗ŖŃü¬ŃéēÕŹŖķĪŹ’╝üŃĆŹŃü©ĶĪ©ńż║ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕ«¤Ńü»50%Õē▓Õ╝ĢŃü©Ńü»Ķ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü¬Ńüäµ¢ÖķćæŃü¦õ╗Ģõ║ŗŃéÆĶ½ŗŃüæĶ▓ĀŃüŻŃü”ŃüäŃü¤ŃĆé
ÕÅ¢Õ╝ĢÕåģÕ«╣Ńü½ŃüŖŃüæŃéŗķćæķĪŹŃü«ĶĪ©ńż║Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüÕÅ¢Õ╝ĢŃü½ŃüŗŃüŗŃéŗķćæķĪŹŃéÆõĮÄŃüÅŃüŖŃüĢŃüłŃéēŃéīŃü”µ£ēÕł®Ńü½ÕÅ¢Õ╝ĢŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃü©Ķ¬żĶ¬ŹŃüĢŃüøŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕÅ¢Õ╝ĢŃü¦µö»µēĢŃüåķćæķĪŹŃéÆÕ«¤ķÜøŃéłŃéŖÕ░æŃü¬ŃüÅĶ¬żĶ¬ŹŃüĢŃüøŃéŗŃü╗ŃüŗŃĆüÕÅŚŃüæÕÅ¢ŃéŗÕł®µü»Ńü«ķćæķĪŹŃü¬Ńü®ŃéÆÕ«¤ķÜøŃéłŃéŖÕżÜŃüÅĶ¬żĶ¬ŹŃüĢŃüøŃéŗŃüōŃü©Ńééµ£ēÕł®Ķ¬żĶ¬ŹŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µÖ»ĶĪ©µ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüåµØĪõ╗Č

µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃéŗÕ»ŠĶ▒ĪõŠŗŃéÆń░ĪÕŹśŃü½ń┤╣õ╗ŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃéŗµØĪõ╗ČŃü»õĖŗĶ©śŃü«4ŃüżŃü¦ŃüÖŃĆé
- õ╝üµźŁŃéäµ│Ģõ║║Ńü¬Ńü®ńĄīµĖłµ┤╗ÕŗĢŃéÆĶĪīŃüåõ║ŗµźŁĶĆģŃü½ŃéłŃéŗĶĪ©ńż║
- Ķć¬ńżŠŃüīÕ▒Ģķ¢ŗŃüÖŃéŗĶŻĮÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶĪ©ńż║
- µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ķ¬żĶ¬ŹŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü¬ĶĪ©ńż║
- Ķć¬ńżŠŃü«ĶŻĮÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü½ķ¢óŃüŚŃü”ĶÖÜÕüĮŃü«ÕåģÕ«╣Ńü«ĶĪ©ńż║
õ╝üµźŁŃéäµ│Ģõ║║Ńü¬Ńü®ńĄīµĖłµ┤╗ÕŗĢŃéÆĶĪīŃüåõ║ŗµźŁĶĆģŃü½ŃéłŃéŗĶĪ©ńż║
µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü¦Ńü«Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü«Ķ”ÅÕłČÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŗŃü«Ńü»ŃĆüõ║ŗµźŁĶĆģŃü½ŃéłŃéŗĶĪ©ńż║Ńü¦ŃüÖŃĆéõĖĆĶł¼õ╝üµźŁŃüĀŃüæŃü½ķÖÉŃéēŃüÜŃĆüÕŁ”µĀĪµ│Ģõ║║ŃéäÕī╗ńÖéµ│Ģõ║║ŃéäńżŠÕøŻµ│Ģõ║║Ńü¬Ńü®ŃĆüńĄīµĖłµ┤╗ÕŗĢŃéÆŃüÖŃéŗõ║ŗµźŁĶĆģŃü½ŃéłŃéŗĶĪ©ńż║Ńü»Õģ©Ńü”ŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü«Ķ”ÅÕłČÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ķć¬ńżŠŃüīÕ▒Ģķ¢ŗŃüÖŃéŗĶŻĮÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗĶĪ©ńż║
µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü¦Ńü»ŃĆüõ╗¢ńżŠŃü«Ńü¤ŃéüŃü½Õ║āÕæŖÕ¬ÆõĮōŃéƵÅÉõŠøŃüÖŃéŗõ║ŗµźŁĶĆģŃü«ĶĪ©ńż║Ńü»Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü«Ķ”ÅÕłČŃü«Õ»ŠĶ▒ĪÕż¢Ńü©Õ«ÜŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖ’╝łµÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│Ģń¼¼2µØĪń¼¼4ķĀģ’╝ēŃĆéŃüżŃüŠŃéŖŃĆüĶć¬ńżŠŃüīÕ▒Ģķ¢ŗŃüÖŃéŗĶŻĮÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü½õ┐éŃéŗĶĪ©ńż║Ńü«Ńü┐ŃüīĶ”ÅÕłČÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”Ķ¬żĶ¬ŹŃüĢŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü¬ĶĪ©ńż║
Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü«Ķ”ÅÕłČÕ»ŠĶ▒ĪŃü»õĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗĶĪ©ńż║Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüõ║ŗµźŁĶĆģķ¢ōŃü¦Ńü«ÕÅ¢Õ╝ĢŃü½õĮ┐ŃéÅŃéīŃéŗõ║ŗµźŁĶĆģÕÉæŃüæŃü«ĶĪ©ńż║Ńü»Õ»ŠĶ▒ĪÕż¢Ńü¦ŃüÖŃĆéõĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃü«ń¤źĶŁśŃéäÕłżµ¢ŁŃüīÕ¤║µ║¢Ńü©Ńü¬ŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüµźŁńĢīķ¢óõ┐éĶĆģŃüīŃüéŃüŹŃéēŃüŗŃü½Ķ¬żĶ¬ŹŃüŚŃü¬ŃüäĶĪ©ńż║Ńü¦ŃééõĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃüīĶ¬żĶ¬ŹŃüÖŃéŗÕåģÕ«╣Ńü¦ŃüéŃéīŃü░Ķ”ÅÕłČÕ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüØŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃéÆÕø×ķü┐ŃüÖŃéŗŃü½Ńü»õĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃü«ńø«ńĘÜŃü¦ĶĆāŃüłŃéŗŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆé
Ķć¬ńżŠŃü«ĶŻĮÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü½ķ¢óŃüŚŃü”ĶÖÜÕüĮŃü«ÕåģÕ«╣Ńü«ĶĪ©ńż║
ÕĢåÕōüŃéäŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«ÕōüĶ│¬ŃéäÕåģÕ«╣Ńü½ŃüżŃüäŃü”ĶÖÜÕüĮŃü«ĶĪ©ńż║ŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü»ÕĮōńäČŃü¬ŃüīŃéēĶ”ÅÕłČŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃü¤ŃüĀŃüŚŃĆüÕ║āÕæŖĶĪ©ńż║Ńü½ŃüżŃüäŃü”Ńü»ŃĆīõĖŹÕ«¤Ķ©╝Õ║āÕæŖĶ”ÅÕłČŃĆŹŃüīķü®ńö©ŃüĢŃéīŃéŗŃü«Ńü¦ŃĆüĶĪ©ńż║ŃüīĶÖÜÕüĮŃü¦Ńü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü½ŃüŖŃüäŃü”ŃééŃĆüÕ«óĶ”│ńÜäŃü¬µĀ╣µŗĀĶ│ćµ¢ÖŃéƵÅÉÕć║Ńü¦ŃüŹŃü¬ŃüäÕĀ┤ÕÉłŃü»Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéĶÖÜÕüĮŃü¦Ńü¬Ńüäõ║ŗÕ«¤Ńü«ĶĪ©ńż║ŃéÆŃüÖŃéŗŃü«Ńü»ÕĮōńäČŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüõ║ŗÕ«¤Ńü¦ŃüéŃéŗÕ«óĶ”│ńÜäŃü¬µĀ╣µŗĀŃéÆńż║ŃüÖŃüōŃü©ŃééÕ┐ģĶ”üŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüÖŃĆé
µÖ»ĶĪ©µ│ĢŃü½ŃüŖŃüäŃü”Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹĶĪ©ńż║Ńü©Ńü¬ŃüŻŃü¤3ŃüżŃü«õ║ŗõŠŗ

Õ«¤ķÜøŃü½Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤õ║ŗõŠŗŃéÆ3Ńüżń┤╣õ╗ŗŃüŚŃüŠŃüÖŃĆéÕ«¤õŠŗŃéƵŖŖµÅĪŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü«Õ»ŠĶ▒ĪŃü©Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäÕ║āÕæŖĶĪ©ńż║Ńü«õĮ£µłÉŃü«ÕÅéĶĆāŃü½ŃüŚŃü”ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
Ńé┤Ńā¤ĶóŗŃüŖŃéłŃü│Ńā¼ŃéĖĶóŗŃü«Õ║āÕæŖÕåģÕ«╣ŃüīÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤õ║ŗõŠŗ
Ńé┤Ńā¤ĶóŗŃéäŃā¼ŃéĖĶóŗŃü«Õ║āÕæŖÕåģÕ«╣ŃüīÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤õ║ŗõŠŗŃü¦ŃüÖŃĆéĶć¬ńżŠŃü«Õģ¼Õ╝ÅŃéĄŃéżŃāłŃü½Ńü”ŃĆüĶć¬ńżŠĶŻĮÕōüŃü«Ńé┤Ńā¤ĶóŗŃéäŃā¼ŃéĖĶóŗŃü½ŃĆīń┤ä2Õ╣┤Ńü¦ńö¤ÕłåĶ¦ŻŃüĢŃéīńä╝ÕŹ┤ŃüŚŃü”Ńééµ£ēÕ«│Ńé¼Ńé╣ŃéÆńÖ║ńö¤ŃüŚŃü¬ŃüäŃĆŹŃü¬Ńü®Ńü©ĶĪ©ńż║ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µČłĶ▓╗ĶĆģÕ║üŃü»ŃĆüŃüōŃü«ĶĪ©ńż║Ńü«ĶŻÅõ╗śŃüæŃü©Ńü¬ŃéŗÕÉłńÉåńÜäŃü¬µĀ╣µŗĀŃéÆńż║ŃüÖĶ│ćµ¢ÖŃü«µÅÉÕć║ŃéƵ▒éŃéüŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüµÅÉÕć║ŃüĢŃéīŃü¤Ķ│ćµ¢ÖŃü»ÕÉłńÉåńÜäŃü¬ĶŻÅõ╗śŃüæŃü©Ńü¬ŃéŗÕåģÕ«╣Ńü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüń┤ä2Õ╣┤Ńü¦ńö¤ÕłåĶ¦ŻŃüĢŃéīŃü”Õ£░ńÉāńÆ░ÕóāŃü½Õä¬ŃüŚŃüäĶŻĮÕōüŃü¦ŃüéŃéŗŃüōŃü©ŃéÆĶæŚŃüŚŃüÅĶ¬żĶ¬ŹŃüĢŃüøŃéŗĶĪ©ńż║Ńü¦ŃüéŃéŗŃü©ŃüĢŃéīŃü”Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ńŠÄÕ«╣µĢ┤ÕĮóŃü½ķ¢óŃüŚŃü”Õ║āÕæŖŃü«ÕåģÕ«╣ŃüīĶÖÜÕüĮŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤Ńü¤ŃéüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤õ║ŗõŠŗ
ńŠÄÕ«╣µĢ┤ÕĮóŃü¦Ńü«Õ║āÕæŖÕåģÕ«╣Ńü¦Ńü«Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü«õ║ŗõŠŗŃü¦ŃüÖŃĆéĶć¬ńżŠŃü«ŃéĄŃéżŃāłŃü½Ńü”ŃĆīŃüéŃü«µźĮÕż®Ńā¬ŃéĄŃā╝ŃāüŃü¦2ÕåĀķüöµłÉŌśģŃāÉŃé╣ŃāłĶ▒ŖĶāĖ’╝åńŚ®Ķ║½ķā©ķ¢ĆŃü¦ń¼¼1õĮŹ’╝üŃĆŹŃü¬Ńü®ŃĆüµ¢ĮĶĪōŃü«ķĪ¦Õ«óµ║ĆĶČ│Õ║”ŃüīµźŁńĢīŃü¦1õĮŹŃü¦ŃüéŃéŗŃéłŃüåŃü¬ĶĪ©ńż║ŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüÕ«¤ķÜøŃü«Ķ¬┐µ¤╗Ńü¦Ńü»ķĪ¦Õ«óµ║ĆĶČ│Õ║”Ńü«ķĀåõĮŹŃü»1õĮŹŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüõĖĆĶł¼µČłĶ▓╗ĶĆģŃü½µ¢ĮĶĪōÕåģÕ«╣ŃéÆĶē»ŃüÅĶ”ŗŃüøŃéŗÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü«ÕåģÕ«╣Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
µ®¤ĶāĮµĆ¦ķŻ¤ÕōüŃü«µæéÕÅ¢Ńü¦ńŚģµ░ŚŃüīÕ«īµ▓╗ŃüÖŃéŗŃü©ŃüäŃüŻŃü¤ĶĪ©ńż║ŃüīÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤õ║ŗõŠŗ
µ®¤ĶāĮµĆ¦ķŻ¤ÕōüŃü«õ║ŗõŠŗŃü¦Ńü»ŃĆüŃāüŃā®ŃéĘŃü½Ńü”õ╗źõĖŗŃü«µ¢ćķØóŃü¬Ńü®ŃéƵÄ▓Ķ╝ēŃüŚŃü¤ŃüōŃü©ŃüīÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
- ķøŻńŚģµö╣Õ¢äŃü½’╝ü’╝ü ń│¢ķÄ¢Ńü«ķćŹĶ”üµĆ¦
- ŃüōŃéōŃü¬µ¢╣ŃüĖŃüŖŃé╣Ńé╣ŃāĪ ŌŚåńÅŠÕ£©Ńé¼Ńā│ŃéƵéŻŃüŻŃü”ŃüŖŃéēŃéīŃéŗµ¢╣ ŌŚåķøŻńŚģ Ńü©Ķ©║µ¢ŁŃüĢŃéīµ▓╗ńÖéõĖŁŃüĀŃüīŃĆüÕŠÉŃĆģŃü½µé¬Õī¢ŃüŚŃü”ŃüŖŃéēŃéīŃéŗµ¢╣
µæéÕÅ¢ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüŃüīŃéōŃéäķøŻµ▓╗µĆ¦ń¢ŠµéŻŃéÆÕ«īµ▓╗Ńā╗µö╣Õ¢äŃüÖŃéŗÕŖ╣µ×£ŃüīÕŠŚŃéēŃéīŃéŗŃüŗŃü«ŃéłŃüåŃü¬ĶĪ©ńż║Ńü©ŃüĢŃéīŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©ŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
µÖ»ĶĪ©µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃüīĶ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«ńĮ░Õēć
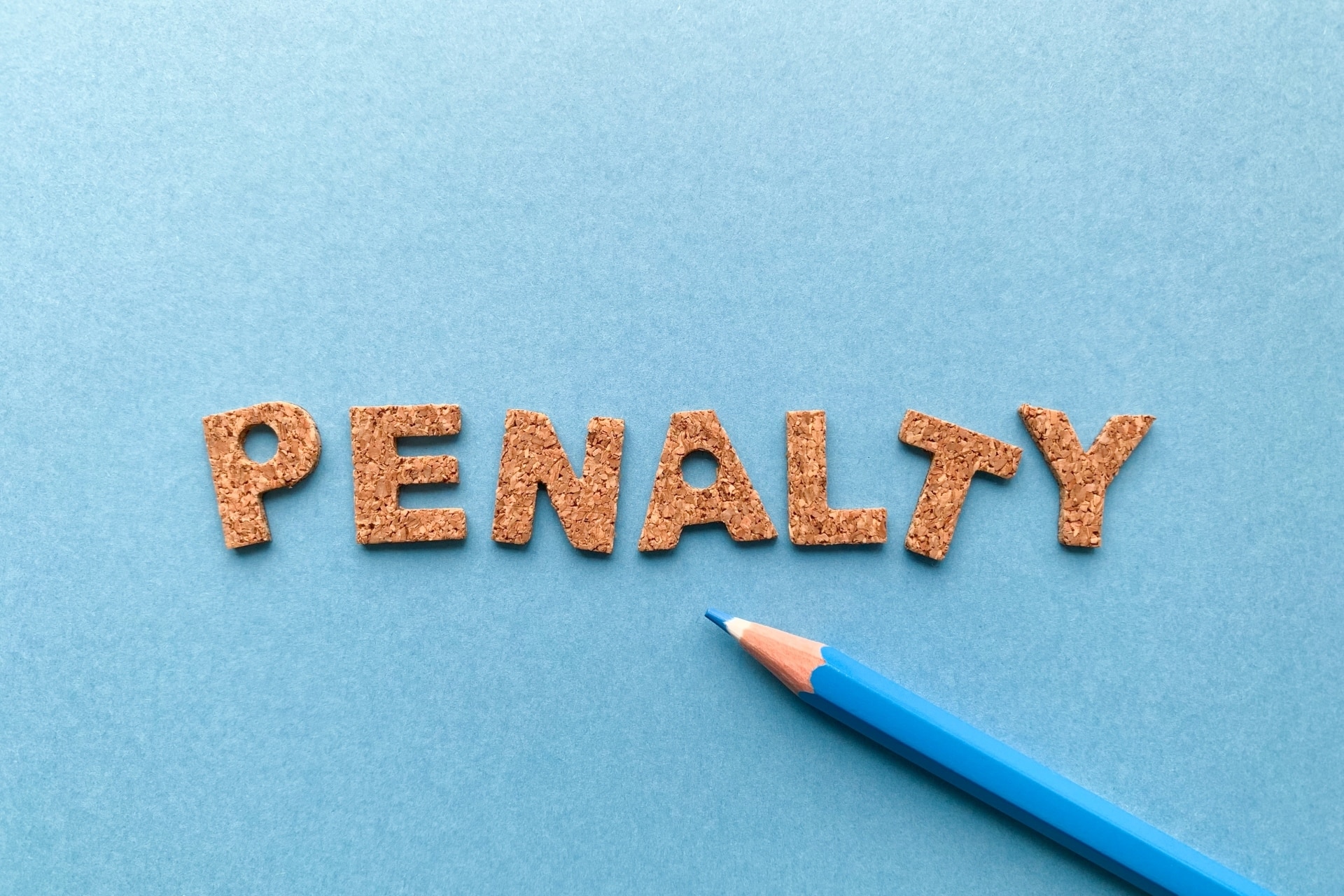
µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü¦Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣Ńü»ŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü»ńĮ░ÕēćŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüōŃüōŃü¦Ńü»ŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü«ńĮ░ÕēćŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
µÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗ż
Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃĆüõĖŹÕĮōŃü¬Õ║āÕæŖĶĪ©ńż║Ńü«Õü£µŁóŃéÆÕæĮŃüśŃéēŃéīŃéŗŃĆīµÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃĆŹŃüīÕć║ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
µÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃüīÕć║ŃüĢŃéīŃü¤µÖéńé╣Ńü¦ŃĆüÕ║āÕæŖŃéÆÕü£µŁóŃüŚŃü¤ŃéŖĶĪ©ńż║ÕåģÕ«╣ŃéƵś»µŁŻŃüŚŃü¤ŃéŖŃüÖŃéīŃü░ŃĆüķćæķŖŁńÜäŃü¬ŃāÜŃāŖŃā½ŃāåŃéŻŃüīŃü¬ŃüÅńĄéõ║åŃü©Ńü¬ŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Ńü¤ŃüĀŃüŚŃĆüµÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃüīÕć║ŃüĢŃéīŃéŗŃü©µČłĶ▓╗ĶĆģÕ║üŃéäĶ欵▓╗õĮōŃü«ŃéĄŃéżŃāłŃü½ŃüØŃü«µŚ©ŃüīµÄ▓Ķ╝ēŃüĢŃéīŃéŗŃü¤ŃéüŃĆüõ╝üµźŁŃéżŃāĪŃā╝ŃéĖŃüīõĮÄõĖŗŃüŚŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃā¬Ńé╣Ńé»ŃüīŃüéŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
Ķ¬▓ÕŠ┤ķćæń┤Źõ╗śÕæĮõ╗ż
Õ║āÕæŖĶĪ©ńż║Ńü«Õü£µŁóŃéÆÕæĮŃüśŃéŗµÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃü«Ńü╗ŃüŗŃĆüķćæķŖŁńÜäŃü¬ŃāÜŃāŖŃā½ŃāåŃéŻŃü©ŃüŚŃü”Ķ¬▓ÕŠ┤ķćæŃü«ń┤Źõ╗śÕæĮõ╗żŃüīń¦æŃüĢŃéīŃéŗŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéĶ¬▓ÕŠ┤ķćæŃü«µö»µēĢķĪŹŃü»ŃĆüõĖŹÕĮōŃü¬Õ║āÕæŖĶĪ©ńż║ŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃü¤µ£¤ķ¢ōŃü©Õ»ŠĶ▒ĪŃü«ÕĢåÕōüŃā╗ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«Ķ▓®ÕŻ▓µ£¤ķ¢ōŃü½ÕŠŚŃü¤ÕŻ▓õĖŖŃü«3’╝ģŃü½ńøĖÕĮōŃüÖŃéŗķćæķĪŹŃü¦ŃüÖ’╝łµÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│Ģń¼¼8µØĪ’╝ēŃĆé
µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü«Ķ¬▓ÕŠ┤ķćæŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüķćæķĪŹŃü«Ńü╗ŃüŗŃü½ń┤Źõ╗śµ£¤ķÖÉŃü¬Ńü®Ńü«Ķ®│ŃüŚŃüäÕåģÕ«╣Ńü»ŃĆüõ╗źõĖŗĶ©śõ║ŗŃéÆÕÅéĶĆāŃü½ŃüŚŃü”Ńü┐Ńü”ŃüÅŃüĀŃüĢŃüäŃĆé
ÕÅéĶĆāĶ©śõ║ŗ’╝ֻܵÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗĶ¬▓ÕŠ┤ķćæÕłČÕ║”Ńü©Ńü»’╝¤Õ«¤ķÜøŃü«õ║ŗõŠŗŃéÆõ║żŃüłŃü”Õ»ŠÕ攵│ĢŃéÆĶ¦ŻĶ¬¼
µÖ»ĶĪ©µ│ĢŃü«Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃéÆķś▓ŃüÉŃü¤ŃéüŃü«4ŃüżŃü«Õ»ŠńŁ¢

µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½ķüĢÕÅŹŃüÖŃéŗŃü©ŃĆüµÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃéäĶ¬▓ÕŠ┤ķćæŃü«ń┤Źõ╗śÕæĮõ╗żŃüīÕć║ŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆéõ╝üµźŁŃéżŃāĪŃā╝ŃéĖŃü«õĮÄõĖŗŃéäķćæķŖŁńÜäŃü¬ŃāÜŃāŖŃā½ŃāåŃéŻŃéÆÕø×ķü┐ŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃéŗÕ║āÕæŖĶĪ©ńż║ŃéÆŃüŚŃü¬ŃüäŃéłŃüåŃü½ŃüŚŃü¬ŃüæŃéīŃü░Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆéÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃéÆķś▓ŃüÉŃü¤ŃéüŃü«Õ»ŠńŁ¢µ¢╣µ│ĢŃéÆ4Ńüżń┤╣õ╗ŗŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õ╝üµźŁÕåģŃü½Õ░éķ¢ĆŃü«ńó║Ķ¬Źķā©ńĮ▓ŃéÆĶ©ŁńĮ«ŃüÖŃéŗ
Õ║āÕæŖŃü«õĖŹÕĮōĶĪ©ńż║Ńü½ŃéłŃéŗÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃéÆķś▓µŁóŃüÖŃéŗŃü¤ŃéüŃü½ŃĆüÕ║āÕæŖŃü«µŗģÕĮōĶĆģŃüĀŃüæŃü¦ŃāüŃé¦ŃāāŃé»ŃüÖŃéŗŃü½Ńü»Ńü®ŃüåŃüŚŃü”ŃééķÖÉńĢīŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéõ╝üµźŁÕåģŃü½Õ║āÕæŖÕåģÕ«╣Ńü«ńó║Ķ¬ŹŃéÆŃüÖŃéŗÕ░éķ¢Ćķā©ńĮ▓ŃéÆĶ©ŁńĮ«ŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüńżŠÕåģŃü¦Ńü«ŃāĆŃā¢Ńā½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»õĮōÕłČŃéäµīćÕ░ÄõĮōÕłČŃéƵĢ┤ŃüłŃéēŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
ĶĪ©ńż║Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗµśÄńó║Ńü¬µĀ╣µŗĀĶ│ćµ¢ÖŃéÆńö©µäÅŃüÖŃéŗ
Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃéÆń¢æŃéÅŃéīŃü”µÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃüīÕć║ŃüĢŃéīŃü”ŃüŚŃüŠŃüŻŃü¤ÕĀ┤ÕÉłŃü¦ŃééŃĆüµśÄńó║Ńü¦ÕÉłńÉåńÜäŃü¬µĀ╣µŗĀŃü©Ńü¬ŃéŗĶ│ćµ¢ÖŃéÆńö©µäÅŃüŚŃü”ŃüŖŃüÅŃüōŃü©Ńü¦Õ╝üµśÄŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéÕÉłńÉåńÜäŃü¬µĀ╣µŗĀŃü¦ŃüéŃéŗŃü©Ķ¬ŹŃéüŃéēŃéīŃéīŃü░ŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü»Ńü¬ŃéēŃüÜŃü½ŃāÜŃāŖŃā½ŃāåŃéŻŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗńżŠÕåģńĀöõ┐«ŃéÆÕ«¤µ¢ĮŃüÖŃéŗ
µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕŠōµźŁÕōĪŃü«ń¤źĶŁśŃüīõĖŹĶČ│ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃĆüķā©ńĮ▓Ńü©ŃüŚŃü”µ®¤ĶāĮŃüøŃüÜŃĆüµĀ╣µŗĀĶ│ćµ¢ÖŃü«ńö©µäÅŃéäń«ĪńÉåŃü½ŃééõĖŹÕéÖŃüīÕć║ŃéäŃüÖŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéńżŠÕåģńĀöõ┐«ŃéäµĢÖĶé▓Ńü½µ│©ÕŖøŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü¦ŃĆüÕŠōµźŁÕōĪ1õ║║1õ║║Ńü«ń¤źĶŁśŃĆüŃüØŃüŚŃü”õĖŹÕĮōĶĪ©ńż║ŃéÆķś▓ŃüÉŃü¤ŃéüŃü«µäÅĶŁśŃéÆõĮ£ŃéŖõĖŖŃüÆŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃüżŃü¬ŃüīŃéŗŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃĆé
õ║ŗÕēŹŃü½Õ╝üĶŁĘÕŻ½ŃüĖŃü«ńøĖĶ½ćŃéÆŃüÖŃéŗ
ńżŠÕåģńĀöõ┐«Ńü½Ńü”ÕŠōµźŁÕōĪŃü«ń¤źĶŁśŃéƵĘ▒ŃéüŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ńü©Ńü”ŃééķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüµÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü¬Ńü®Ńü«Õ░éķ¢Ćń¤źĶŁśŃü½ńżŠÕåģŃüĀŃüæŃü¦Õ»ŠÕ┐£ŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃüÅŃü½Ńü»ķøŻŃüŚŃüäńé╣ŃüīŃüäŃüÅŃüżŃééÕć║Ńü”ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆéµ│ĢÕŠŗŃü«Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü¦ŃüéŃéŗÕ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½ńøĖĶ½ćŃüŚŃĆüÕ»ŠÕ┐£ŃéäÕ»ŠńŁ¢Ńü½ÕŹöÕŖøŃéÆõ╗░ŃüÄŃüŠŃüŚŃéćŃüåŃĆé
Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü«Ķ”¢ńé╣ŃüŗŃéēŃü«µäÅĶ”ŗŃéäõĖŹÕéÖŃü«µīćµæśŃü¬Ńü®Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü¬Ńü®Ńü«µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢķüĢÕÅŹŃéÆÕø×ķü┐Ńü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüŠŃü©Ńéü’╝ֻܵĶĪ©µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹĶĪ©ńż║Ńü½ķ¢óŃüÖŃéŗµŁŻŃüŚŃüäńÉåĶ¦ŻŃéÆ

µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢŃü½ŃüŖŃüæŃéŗÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü½ŃüżŃüäŃü”Ķ¦ŻĶ¬¼ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕ║āÕæŖĶĪ©ńż║ŃüīÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃü©ŃĆüµÄ¬ńĮ«ÕæĮõ╗żŃü«Ńü┐Ńü¬ŃéēŃüÜĶ¬▓ÕŠ┤ķćæŃü«ń┤Źõ╗śÕæĮõ╗żŃü¦ķćæķŖŁŃü«ŃāÜŃāŖŃā½ŃāåŃéŻŃéÆń¦æŃüøŃéēŃéīŃéŗŃā¬Ńé╣Ńé»ŃüŠŃü¦ŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
Õä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü¬Ńü®Ńü«õĖŹÕĮōĶĪ©ńż║ŃéÆÕø×ķü┐ŃüŚŃü”ŃĆüµÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢķüĢÕÅŹŃü½Ńü¬ŃéēŃü¬ŃüäŃéłŃüåŃü½ŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃüīķćŹĶ”üŃü¦ŃüÖŃĆéÕ║āÕæŖŃü½ŃüŖŃüäŃü”õĖŹÕ«ēŃüīŃüéŃéīŃü░ŃĆüµ│ĢÕŠŗŃü«Õ░éķ¢ĆÕ«ČŃü¦ŃüéŃéŗÕ╝üĶŁĘÕŻ½Ńü½ŃüéŃéēŃüŗŃüśŃéüńøĖĶ½ćŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃéÆŃüŖÕŗ¦ŃéüŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
õĖŹÕ«ēĶ”üń┤ĀŃü«Ķ¦ŻµČłŃéäŃā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»Ńü¦Ńü«µīćµæśŃü¬Ńü®Ńü¦ŃĆüÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü¬Ńü®Ńü«õĖŹÕĮōĶĪ©ńż║ŃéÆķś▓ŃüĵĬńĮ«ÕæĮõ╗żŃéäĶ¬▓ÕŠ┤ķćæń┤Źõ╗śŃü«Õø×ķü┐Ńü½ŃüżŃü¬ŃüīŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüITŃĆüńē╣Ńü½ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃü©µ│ĢÕŠŗŃü«õĖĪķØóŃü½Ķ▒ŖÕ»īŃü¬ńĄīķ©ōŃéƵ£ēŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦ŃüÖŃĆéĶ┐æÕ╣┤ŃĆüŃāŹŃāāŃāłÕ║āÕæŖŃéÆŃéüŃüÉŃéŗÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü¬Ńü®Ńü«µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢķüĢÕÅŹŃü»Õż¦ŃüŹŃü¬ÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»Ńü«Õ┐ģĶ”üµĆ¦Ńü»ŃüŠŃüÖŃüŠŃüÖÕóŚÕŖĀŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬µ│ĢÕŠŗŃü«Ķ”ÅÕłČŃéÆĶĖÅŃüŠŃüłŃü¤õĖŖŃü¦ŃĆüÕ║āÕæŖŃéäLPŃü«Ńā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»ŃĆüŃé¼ŃéżŃāēŃā®ŃéżŃā│õĮ£µłÉŃü¬Ńü®Ńü«ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”Ķ®│ń┤░ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü½ŃéłŃéŗÕ»ŠńŁ¢Ńü«ŃüöµĪłÕåģ
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃĆüITŃĆüńē╣Ńü½ŃéżŃā│Ńé┐Ńā╝ŃāŹŃāāŃāłŃü©µ│ĢÕŠŗŃü«õĖĪķØóŃü½Ķ▒ŖÕ»īŃü¬ńĄīķ©ōŃéƵ£ēŃüÖŃéŗµ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü¦ŃüÖŃĆéĶ┐æÕ╣┤ŃĆüŃāŹŃāāŃāłÕ║āÕæŖŃéÆŃéüŃüÉŃéŗÕä¬Ķē»Ķ¬żĶ¬ŹŃü¬Ńü®Ńü«µÖ»ÕōüĶĪ©ńż║µ│ĢķüĢÕÅŹŃü»Õż¦ŃüŹŃü¬ÕĢÅķĪīŃü©Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»Ńü«Õ┐ģĶ”üµĆ¦Ńü»ŃüŠŃüÖŃüŠŃüÖÕóŚÕŖĀŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéÕĮōõ║ŗÕŗÖµēĆŃü»ŃüĢŃüŠŃü¢ŃüŠŃü¬µ│ĢÕŠŗŃü«Ķ”ÅÕłČŃéÆĶĖÅŃüŠŃüłŃü¤õĖŖŃü¦ŃĆüÕ║āÕæŖŃéäLPŃü«Ńā¬Ńā╝Ńé¼Ńā½ŃāüŃé¦ŃāāŃé»ŃĆüŃé¼ŃéżŃāēŃā®ŃéżŃā│õĮ£µłÉŃü¬Ńü®Ńü«ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣ŃéƵÅÉõŠøŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĖŗĶ©śĶ©śõ║ŗŃü½Ńü”Ķ®│ń┤░ŃéÆĶ©śĶ╝ēŃüŚŃü”ŃüŖŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāóŃāÄŃā¬Ńé╣µ│ĢÕŠŗõ║ŗÕŗÖµēĆŃü«ÕÅ¢µē▒ÕłåķćÄ’╝ÜĶ©śõ║ŗŃā╗LPŃü«Ķ¢¼µ®¤µ│ĢńŁēŃāüŃé¦ŃāāŃé»
Ńé½ŃāåŃé┤Ńā¬Ńā╝: ITŃā╗ŃāÖŃā│ŃāüŃāŻŃā╝Ńü«õ╝üµźŁµ│ĢÕŗÖ


































