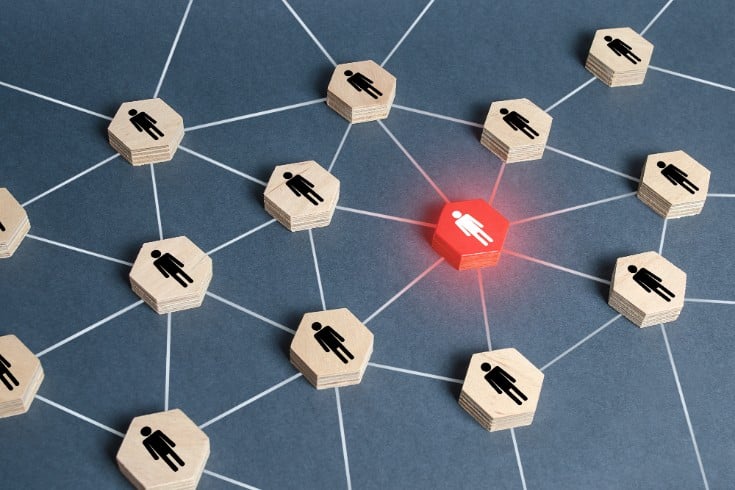ТЎ»тЊЂсЂФсЂ»СИіжЎљжЄЉжАЇсЂїсЂѓсѓІ№╝ЪТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ№╝ѕТЎ»УАеТ│Ћ№╝ЅсЂДт«џсѓЂсѓЅсѓїсЂЪ3сЂцсЂ«ТЎ»тЊЂсЃ╗ТЄИУ│ъсѓњУДБУфг

сђїт░ЉсЂЌсЂДсѓѓтцџсЂЈсЂ«С║║сЂФУ│╝тЁЦсЂЌсЂдсЂ╗сЂЌсЂёсђЇсђїт░ЉсЂЌсЂДсѓѓтцџсЂЈсЂ«сЂіт«бсЂЋсѓЊсѓњжЏєсѓЂсЂЪсЂёсђЇсЂфсЂЕсЂ«ТђЮсЂёсЂІсѓЅсђЂтЋєтЊЂсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂФт»ЙсЂЌсЂдТЎ»тЊЂжАъсѓњсЂцсЂЉсѓІсЂЊсЂеУЄфСйЊсЂ»ТѓфсЂёсЂЊсЂесЂДсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсЂїсђЂТЎ»тЊЂсЂ«жЄЉжАЇсѓёСЙАтђцсЂїсЂѓсЂЙсѓісЂФтцДсЂЇсЂЈсЂфсѓіжЂјсЂјсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂетЋЈжАїсЂїућЪсЂўсЂЙсЂЎсђѓсЂѓсЂЙсѓісЂФжФўСЙАсЂфТЎ»тЊЂсЂДТХѕУ▓╗УђЁсЂФУ│╝тЁЦсЂ«тѕцТќГсѓњТЃЉсѓЈсЂЏсЂфсЂёсѓѕсЂєсЂФсђЂТЎ»тЊЂуГЅсЂФСИіжЎљжЄЉжАЇсѓњт«џсѓЂсЂдсЂёсѓІТ│ЋтЙІсЂїсђїТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ№╝ѕТЎ»УАеТ│Ћ№╝ЅсђЇсЂДсЂЎсђѓ
сЂЊсЂЊсЂДсЂ»сђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂДт«џсѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІТЄИУ│ъсѓёТЎ»тЊЂсЂФжќбсЂЎсѓІУдЈтѕХсЂФсЂцсЂёсЂдУЕ│сЂЌсЂЈУДБУфгсЂЌсЂЙсЂЎсђѓТЎ»УАеТ│ЋсЂДт«џсѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІТЎ»тЊЂсЂ«жЄЉжАЇсЂ«СИіжЎљсѓњТЄИУ│ъсѓёТЎ»тЊЂсЂћсЂесЂ«уе«жАътѕЦсЂФТііТЈАсЂЌсђЂтЄдуй░т»ЙУ▒АсЂФсЂфсѓЅсЂфсЂёсѓѕсЂєсЂФТ│еТёЈсЂЌсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
сЂЊсЂ«УеўС║ІсЂ«уЏ«ТгА
ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ№╝ѕТЎ»УАеТ│Ћ№╝ЅсЂе2уе«жАъсЂ«ТЄИУ│ъ

ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ№╝ѕТЎ»УАеТ│Ћ№╝ЅсЂ»сђЂТГБт╝ЈсЂФсЂ»сђјСИЇтйЊТЎ»тЊЂжАътЈісЂ│СИЇтйЊУАеуц║жў▓ТГбТ│ЋсђЈсЂесЂёсЂёсђЂТХѕУ▓╗УђЁсЂїтЋєтЊЂсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сѓњУЄфСИ╗уџёсЂІсЂцтљѕуљєуџёсЂФжЂИсЂ╣сѓІсѓѕсЂєсЂФсђЂСИЇтйЊсЂфУАеуц║сѓёжЂјтцДсЂфТЎ»тЊЂсѓњУдЈтѕХсЂЎсѓІТ│ЋтЙІсЂДсЂЎсђѓТЎ»тЊЂжАъсЂФжќбсЂЌсЂдсЂ»сђЂСИ╗сЂФсѓ»сЃГсЃ╝сѓ║сЃЅтъІТЄИУ│ъсѓњУдЈтѕХт»ЙУ▒АсЂесЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
ТХѕУ▓╗УђЁт║ЂсЂДсЂ»сђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФсЂцсЂёсЂдС╗ЦСИІсЂ«сѓѕсЂєсЂФУфгТўјсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂ»сђЂтЋєтЊЂсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂ«тЊЂУ│фсђЂтєЁт«╣сђЂСЙАТа╝уГЅсѓњтЂйсЂБсЂдУАеуц║сѓњУАїсЂєсЂЊсЂесѓњтј│сЂЌсЂЈУдЈтѕХсЂЎсѓІсЂесЂесѓѓсЂФсђЂжЂјтцДсЂфТЎ»тЊЂжАъсЂ«ТЈљСЙЏсѓњжў▓сЂљсЂЪсѓЂсЂФТЎ»тЊЂжАъсЂ«ТюђжФўжАЇсѓњтѕХжЎљсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂфсЂЕсЂФсѓѕсѓісђЂТХѕУ▓╗УђЁсЂ«сЂ┐сЂфсЂЋсѓЊсЂїсѓѕсѓіУЅ»сЂётЋєтЊЂсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сѓњУЄфСИ╗уџёсЂІсЂцтљѕуљєуџёсЂФжЂИсЂ╣сѓІуњ░тбЃсѓњт«ѕсѓісЂЙсЂЎсђѓ
т╝Ћуће№╝џТХѕУ▓╗УђЁт║Ђ№йюТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ
сЂцсЂЙсѓісђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂДсЂ»сђЂтЋєтЊЂсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂФсЂцсЂёсЂдсЂЈсѓІсЂісЂЙсЂЉсѓёу▓ЌтЊЂсЂфсЂЕсЂ«ТЎ»тЊЂсђЂт║ЃтЉісЂФУАеуц║сЂЎсѓІУфўсЂёТќЄтЈЦуГЅсѓњУдЈтѕХсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓТЎ»тЊЂсѓёУАеуц║сЂФсѓѕсЂБсЂдТХѕУ▓╗УђЁсЂїтЋєтЊЂсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂ«тЊЂУ│фсЃ╗тєЁт«╣сѓњУдІУфцсѓЅсЂфсЂёсѓѕсЂєсЂФсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«УдЈтѕХсЂДсЂЎсђѓ
ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФсЂісЂЉсѓІсђїТЄИУ│ъсђЇсЂесЂ»сђЂсЂЈсЂўт╝ЋсЂЇсЂфсЂЕсЂ«тЂХуёХТђДсѓёсѓ»сѓцсѓ║сЃ╗сѓ▓сЃ╝сЃасЂфсЂЕсЂ«ТГБУфцсЃ╗тёфтіБсѓњтѕЕућесЂЌсЂдсђЂТЎ»тЊЂжАъсѓњТЈљСЙЏсЂЎсѓІуЏИТЅІсЂЙсЂЪсЂ»ТЎ»тЊЂжАъсѓњТ▒║сѓЂсѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂЎсђѓ
ТЄИУ│ъсЂФсЂ»сђЂсЂЈсЂўт╝ЋсЂЇсѓњсЂ»сЂўсѓЂсЂЋсЂЙсЂќсЂЙсЂфуе«жАъсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓТЄИУ│ъсЂ«уе«жАъсЂФсѓѕсЂБсЂдсЂ»сђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФсЂісЂЉсѓІУдЈтѕХсЂ«т»ЙУ▒АсЂФсЂфсѓІсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЂесЂфсѓЅсЂфсЂёсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
ТЄИУ│ъсЂ»сђЂСИІУеўсЂ«2сЂцсЂФтцДсЂЇсЂЈтѕєсЂЉсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
- сѓфсЃ╝сЃЌсЃ│тъІТЄИУ│ъ
- сѓ»сЃГсЃ╝сѓ║сЃЅтъІТЄИУ│ъ
сЂЊсЂ«2сЂцсЂ«ТЄИУ│ъсЂФсЂцсЂёсЂдсђЂтєЁт«╣сѓёТЮАС╗ХсЂФсЂцсЂёсЂдУЕ│сЂЌсЂЈУДБУфгсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сѓфсЃ╝сЃЌсЃ│тъІТЄИУ│ъ
сѓфсЃ╝сЃЌсЃ│тъІТЄИУ│ъсЂесЂ»сђЂТЄИУ│ъсЂФтЈѓтіасЃ╗т┐ютІЪсЂДсЂЇсѓІт»ЙУ▒АУђЁсЂ«ТЮАС╗ХсЂїсЂфсЂёТЄИУ│ъсЂДсЂЎсђѓт┐ютІЪУђЁсЂесЂ«жќЊсЂДтЋєтЊЂсЂ«У│╝тЁЦсЂфсЂЕсЂ«жЄЉжіГуџёсЂфтЈќт╝ЋсЂїуЎ║ућЪсЂЌсЂфсЂёТЄИУ│ъсЂДсђЂтЈѓтіасЂЌсЂЪсЂёС║║сЂ»т┐ютІЪсЂЎсѓїсЂ░Уф░сЂДсѓѓу░АтЇўсЂФтЈѓтіасЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓсЂЙсЂЪсђЂт║ЌУѕЌсЂИсЂ«ТЮЦт║ЌсЂ»т┐ЁУдЂсЂфсЂЈсђЂсѓцсЃ│сѓ┐сЃ╝сЃЇсЃЃсЃѕсЃ╗SNSсЂДсЂ«т┐ютІЪсѓёжЃхСЙ┐сЂ»сЂїсЂЇсЂ«жЃхжђЂсЂфсЂЕсЂДућ│сЂЌУЙ╝сЂ┐сЂїсЂДсЂЇсѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂЎсђѓ
сѓфсЃ╝сЃЌсЃ│тъІТЄИУ│ъсЂ«СЙІсЂесЂЌсЂдсђЂуёАТќЎС╝џтЊАуЎ╗жї▓сѓёсЃАсЃФсЃъсѓгуЎ╗жї▓сђЂсЂЙсЂЪсѓбсЃ│сѓ▒сЃ╝сЃѕсѓёсѓ»сѓцсѓ║сЂИсЂ«тЏъуГћ№╝ѕТГБУфцсЂ»тЋЈсѓЈсЂфсЂё№╝ЅсЂДтЈѓтіаУђЁсѓњжЏєсѓЂсЂЙсЂЎсђѓсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│тъІТЄИУ│ъсЂ»сђЂжЄЉжіГуџёсЂфтЈќт╝ЋсЂїуЎ║ућЪсЂЏсЂџУф░сЂДсѓѓуёАТЮАС╗ХсЂДу░АтЇўсЂФтЈѓтіасЂДсЂЇсѓІсЂЪсѓЂсђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФсЂісЂЉсѓІсђїТЄИУ│ъсђЇсЂесЂ»сЂфсѓЅсЂџУдЈтѕХсЂ«т»ЙУ▒АсЂФсЂ»сЂфсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
СИђУѕгуџёсЂФсђЂсѓфсЃ╝сЃЌсЃ│тъІТЄИУ│ъсЂ»тЋєтЊЂУ│╝тЁЦсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣тѕЕућесЂ«С┐Ѓжђ▓сЂ«сЂЪсѓЂсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂтЋєтЊЂсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂ«уЪЦтљЇт║дсЂ«тљЉСИісѓњуЏ«уџёсЂесЂЌсЂдУАїсѓЈсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
сѓ»сЃГсЃ╝сѓ║сЃЅтъІТЄИУ│ъ
сѓ»сЃГсЃ╝сѓ║сЃЅтъІТЄИУ│ъсЂесЂ»сђЂтЈѓтіаТЮАС╗ХсЂїУеГсЂЉсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІТЄИУ│ъсЂДсЂЎсђѓТЄИУ│ъсЂФтЈѓтіасЂЎсѓІсЂФсЂѓсЂЪсѓісђЂТЎ»тЊЂсѓњТЈљСЙЏсЂЎсѓІтЂ┤сЂет┐ютІЪсЂЎсѓІтЂ┤сЂесЂ«жќЊсЂФтЈќт╝ЋсЂїуЎ║ућЪсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
СЙІсЂесЂЌсЂдсђЂтЋєтЊЂУ│╝тЁЦсЂЌсЂЪжџЏсЂФТЅІсЂФтЁЦсѓІсЃгсѓисЃ╝сЃѕсѓёсђЂсѓисЃ╝сЃФсЂфсЂЕсЂДТійжЂИсЂФт┐ютІЪсЂДсЂЇсѓІсЂЈсЂўсѓёТЄИУ│ъсЂїсѓЈсЂІсѓісѓёсЂЎсЂёсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
тЋєтЊЂУ│╝тЁЦсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣тѕЕућесЂфсЂЕсЂ«уЏ┤ТјЦуџёсЂфтЈќт╝ЋсЂїсЂфсЂЈсЂдсѓѓсђЂт║ЌУѕЌсЂИсЂ«ТЮЦт║ЌсЂїТійжЂИсЂИсЂ«т┐ютІЪсЂФт┐ЁУдЂсЂфТЮАС╗ХсЂДсЂѓсѓїсЂ░сѓ»сЃГсЃ╝сѓ║тъІТЄИУ│ъсЂФтѕєжАъсЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓТЮЦт║ЌсЂЌсЂЪтЁѕуЮђжаєсЂДсЂ«ТійжЂИт┐ютІЪсѓёт║ЌжаГсЂДжќІтѓгсЂЎсѓІсЂЈсЂўт╝ЋсЂЇсЂфсЂЕсѓѓсђЂсѓ»сЃГсЃ╝сѓ║сЃЅтъІТЄИУ│ъсЂФтљФсЂЙсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ№╝ѕТЎ»УАеТ│Ћ№╝ЅсЂФсЂісЂЉсѓІТЎ»тЊЂсЂ«т«џуЙЕ
ТЄИУ│ъсЂДсЂ»сѓ»сЃГсЃ╝сѓ║сЃЅТЄИУ│ъсЂїТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФсЂісЂёсЂдУдЈтѕХсЂ«т»ЙУ▒АсЂесЂфсѓісђЂТЈљСЙЏсЂДсЂЇсѓІТЎ»тЊЂсЂ«жЄЉжАЇсЂФСИіжЎљсЂїТ▒║сѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂДсЂ»сђЂсЂЮсѓѓсЂЮсѓѓТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФсЂісЂЉсѓІТЎ»тЊЂсЂ«т«џуЙЕсЂесЂ»СйЋсЂДсЂЌсѓЄсЂєсЂІ№╝Ъ
ТХѕУ▓╗УђЁт║ЂсЂДсЂ»сђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФсЂісЂЉсѓІТЎ»тЊЂсѓњСИІУеўсЂ«3сЂцсЂ«УдЂу┤асЂДт«џуЙЕсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
- жАДт«бсѓњУфўт╝ЋсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«ТЅІТ«х
- С║ІТЦГУђЁсЂїУЄфти▒сЂ«СЙЏухдсЂЎсѓІтЋєтЊЂсЃ╗сѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂ«тЈќт╝ЋсЂФС╗ўжџЈсЂЌсЂдТЈљСЙЏсЂЎсѓІ
- уЅЕтЊЂсђЂжЄЉжіГсЂЮсЂ«С╗ќсЂ«ухїТИѕСИісЂ«тѕЕуЏі
сЂЊсЂ«т«џуЙЕсЂФтйЊсЂдсЂ»сЂЙсѓІта┤тљѕсЂ»сђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФсЂісЂёсЂдСИіжЎљжЄЉжАЇсЂ«УдЈтѕХсЂїжЂЕућесЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ№╝ѕТЎ»УАеТ│Ћ№╝ЅсЂїжЂЕућесЂЋсѓїсѓІТЄИУ│ъсЂеТЎ»тЊЂсЂ«жЄЉжАЇ

ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂДсЂ»сђЂсђїсѓ»сЃГсЃ╝сѓ║сЃЅтъІТЄИУ│ъсђЇсЂїУдЈтѕХсЂЋсѓїсѓІсЂеУДБУфгсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓсѓ»сЃГсЃ╝сѓ║сЃЅтъІТЄИУ│ъсѓѓсЂЋсѓЅсЂФу┤░сЂІсЂЈсђЂСИІУеўсЂ«3сЂцсЂФтѕєжАъсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
- сЂЈсЂўсѓёТійжЂИсЂфсЂЕсЂФсѓѕсѓІсђїСИђУѕгТЄИУ│ъсђЇ
- УцЄТЋ░сЂ«С║ІТЦГУђЁсЂФсѓѕсѓІсђїтЁ▒тљїТЄИУ│ъсђЇ
- т┐ютІЪУђЁсЂФтЁетЊАжЁЇтИЃсЂЎсѓІсђїуиЈС╗ўТЎ»тЊЂсђЇ
сЂЊсѓїсѓЅ3сЂцсЂ«уе«жАъсЂ«ТЄИУ│ъсЂДсЂ»сђЂТЎ»тЊЂсЂ«жЄЉжАЇсЂ«СИіжЎљсЂїсЂЮсѓїсЂъсѓїТ▒║сѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЈсЂўсѓёТійжЂИсЂфсЂЕсЂФсѓѕсѓІсђїСИђУѕгТЄИУ│ъсђЇ
сЂЙсЂџсђЂТюђсѓѓУ║ФУ┐ЉсЂеУеђсЂѕсѓІТЄИУ│ъсЂ«уе«жАъсЂДсЂѓсѓІсђїСИђУѕгТЄИУ│ъсђЇсЂФсЂцсЂёсЂдУДБУфгсЂЌсЂЙсЂЎсђѓСИђУѕгТЄИУ│ъсЂесЂ»сђЂСИђУѕгуџёсЂФТюђсѓѓтцџсЂёсѓ┐сѓцсЃЌсЂїсЂЈсЂўсѓёТійжЂИсЂфсЂЕсЂФсѓѕсЂБсЂдтйЊжЂИУђЁсѓњТ▒║т«џсЂЎсѓІТЄИУ│ъсЂДсЂЎсђѓ
тЋєтЊЂсЂ«У│╝тЁЦсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂ«тѕЕућесЂфсЂЕсѓњсЂЌсЂЪС║║сЂїтЈѓтіасЂДсЂЇсђЂтЂХуёХТђДсѓёуЅ╣т«џУАїуѓ║сЂ«тёфтіБсЂДТЎ»тЊЂсѓњсѓѓсѓЅсЂѕсѓІсЂІсЂїТ▒║сЂЙсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЪсЂесЂѕсЂ░сђЂсЂЈсЂўсѓёсѓИсЃБсЃ│сѓ▒сЃ│сЂфсЂЕсЂ«тЂХуёХТђДсЂДсЂ«тйЊжЂИсђЂсѓ»сѓцсѓ║сЃ╗сЃЉсѓ║сЃФсЂ«ТГБУДБсђЂуФХТіђсЃ╗жЂіТѕ»сЂ«ТѕљтіЪсЂфсЂЕсЂФсѓѕсЂБсЂдТЎ»тЊЂжАъсѓњУф░сЂФТЈљСЙЏсЂЎсѓІсЂІсѓњТ▒║сѓЂсЂЙсЂЎсђѓ
СИђУѕгТЄИУ│ъсЂДсЂ»сђЂТЎ»тЊЂсЂ«жЄЉжАЇсЂ«СИіжЎљсЂ»СИІУеўсЂ«УАесЂ«сЂесЂісѓісЂДсЂЎсђѓ
| ТЄИУ│ъсЂФсѓѕсѓІтЈќт╝ЋжЄЉжАЇ | ТЎ»тЊЂжАъсЂ«жЄЉжАЇсЂ«СИіжЎљ | |
| ТюђжФўжЄЉжАЇ | уиЈжАЇ | |
| 5,000тєєТюфТ║ђсЂ«та┤тљѕ | тЈќт╝ЋжЄЉжАЇсЂ«20тђЇ | ТЄИУ│ъсЂФС┐ѓсѓІтБ▓СИіС║ѕт«џуиЈжАЇсЂ«2% |
| 5,000тєєС╗ЦСИісЂ«та┤тљѕ | 10СИЄтєє | |
тЋєтЊЂУ│╝тЁЦсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣тѕЕућесЂ«жџЏсЂФсЂІсЂІсѓІжЄЉжАЇсЂїсђЂ5,000тєєС╗ЦСИісЂФсЂфсѓІсЂІсЂЕсЂєсЂІсЂїтцДсЂЇсЂфсЃЮсѓцсЃ│сЃѕсЂДсЂЎсђѓ5,000тєєС╗ЦСИісЂДсЂѓсЂБсЂдсѓѓсђЂТЎ»тЊЂсЂ«ТюђжФўжЄЉжАЇсЂ»1сЂцсЂѓсЂЪсѓі10СИЄтєєсЂЙсЂДсЂесЂфсЂБсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесЂФТ│еТёЈсЂЌсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
УцЄТЋ░сЂ«С║ІТЦГУђЁсЂФсѓѕсѓІсђїтЁ▒тљїТЄИУ│ъсђЇ
тЁ▒тљїТЄИУ│ъсЂесЂ»сђЂСИђУѕгТЄИУ│ъсЂ«СИГсЂДсѓѓСИ╗тѓгсЂЎсѓІС║ІТЦГУђЁсЂфсЂЕсЂїУцЄТЋ░сЂ«та┤тљѕсЂ«ТЄИУ│ъсЂДсЂЎсђѓТЎ»тЊЂсЂ«ТЈљСЙЏтйбт╝ЈсЂ»СИђУѕгТЄИУ│ъсЂетљїсЂўсЂДсЂЎсЂїсђЂТЎ»тЊЂсѓњТЈљСЙЏсЂЎсѓІтЂ┤сЂїУцЄТЋ░сЂДсЂѓсѓІсЂІсЂїтцДсЂЇсЂфжЂЋсЂёсЂФсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЂЪсЂесЂѕсЂ░сђЂтЋєт║ЌУАЌсѓёсѓисЃДсЃЃсЃћсЃ│сѓ░сЃбсЃ╝сЃФсЂДсЂ«сЂЈсЂўт╝ЋсЂЇсЂфсЂЕсђЂУцЄТЋ░сЂ«т║ЌУѕЌсЂ«тЇћтіЏсЂФсѓѕсЂБсЂджќІтѓгсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсЂЈсЂўсѓёТійжЂИС╝џсЂфсЂЕсЂїСЙІсЂесЂЌсЂдсѓЈсЂІсѓісѓёсЂЎсЂёсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
тЁ▒тљїТЄИУ│ъсЂДсЂ«ТЎ»тЊЂжЄЉжАЇсЂ«СИіжЎљсЂ»сђЂСИІУеўсЂ«сѓѕсЂєсЂФсЂфсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
| ТЎ»тЊЂжАъсЂ«жЄЉжАЇсЂ«СИіжЎљ | |
| ТюђжФўжЄЉжАЇ | уиЈжАЇ |
| СИђтЙІ30СИЄтєє | ТЄИУ│ъсЂФС┐ѓсѓІтБ▓СИіС║ѕт«џуиЈжАЇсЂ«3% |
тЁ▒тљїТЄИУ│ъсЂ«та┤тљѕсЂ»сђЂтЈќт╝ЋсЂ«жЄЉжАЇсЂФжќбС┐ѓсЂфсЂЈТЎ»тЊЂжАъсЂ«жЄЉжАЇсЂ«СИіжЎљсЂ»30СИЄтєєсЂДсЂЎсђѓСИђУѕгТЄИУ│ъсЂ«сѓѕсЂєсЂФсђЂтЈќт╝ЋжЄЉжАЇсЂ«жЂЋсЂёсЂФсѓѕсѓІта┤тљѕтѕєсЂЉсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
тЪ║ТюгсЂ»т┐ютІЪУђЁсЂФтЁетЊАжЁЇтИЃсЂЎсѓІуиЈС╗ўТЎ»тЊЂ
уиЈС╗ўТЎ»тЊЂсЂесЂ»сђЂтЈѓтіаУђЁсѓёт┐ютІЪУђЁсЂ«СИГсЂІсѓЅТійжЂИсЂДтйЊжЂИУђЁсѓњТ▒║сѓЂсѓІсЂЊсЂесЂ»сЂЏсЂџсђЂтЈѓтіасЂЌсЂЪС║║тЁетЊАсЂФТЎ»тЊЂсѓњТЈљСЙЏсЂЎсѓІтйбт╝ЈсЂДсЂЎсђѓтЂХуёХТђДсѓётёфтіБсЂФсѓѕсЂБсЂдтйЊжЂИУђЁсѓњТ▒║сѓЂсѓІсѓёсѓіТќ╣сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂЪсѓЂсђЂсђїТЄИУ│ъсђЇсЂФсЂ»сЂѓсЂЪсѓЅсЂџсђїуиЈС╗ўТЎ»тЊЂсђЇсЂФтѕєжАъсЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЪсЂесЂѕсЂ░сђЂсђїт┐ютІЪУђЁтЁетЊАсЃЌсЃгсѓ╝сЃ│сЃѕсђЇсѓёсђїТЮЦт║ЌсЂЌсЂЪсѓЅсѓѓсѓїсЂфсЂЈу▓ЌтЊЂсѓњсѓѓсѓЅсЂѕсЂЙсЂЎсђЇсЂфсЂЕсЂ«тйбт╝ЈсЂїуиЈС╗ўТЎ»тЊЂсЂФсЂѓсЂЪсѓісЂЙсЂЎсђѓТЮЦт║ЌУђЁтЁетЊАсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂТЮЦт║ЌУђЁсЂ«сЂєсЂАтЁѕуЮђсЂЌсЂЪСйЋС║║сЂІсЂасЂЉсЂїт»ЙУ▒АсЂесЂфсѓІуѓ╣сЂДсЂ»сђЂСИђУдІсѓ»сЃГсЃ╝сѓ║тъІТЄИУ│ъсЂетљїсЂўсЂФТђЮсЂѕсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂІсѓѓсЂЌсѓїсЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
сЂЌсЂІсЂЌсђЂТЮЦт║ЌсЂ«тЁѕуЮђжаєсЂ«ТЮАС╗ХсѓњТ║ђсЂЪсЂЌсЂЋсЂѕсЂЎсѓїсЂ░сђЂТійжЂИсѓњсЂЏсЂџсЂФтЁетЊАсЂїТЎ»тЊЂсѓњсѓѓсѓЅсЂѕсѓІта┤тљѕсЂФсЂ»сђїуиЈС╗ўТЎ»тЊЂсђЇсЂФсЂѓсЂЪсѓісЂЙсЂЎсђѓ
уиЈС╗ўТЎ»тЊЂсЂ«ТЎ»тЊЂжЄЉжАЇсЂ«СИіжЎљсЂ»сђЂСИІУеўсЂ«сЂесЂісѓісЂФТ▒║сѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
| тЈќт╝ЋжЄЉжАЇ | ТЎ»тЊЂжАъсЂ«жЄЉжАЇсЂ«СИіжЎљ |
| 1,000тєєТюфТ║ђ | 200тєє |
| 1,000тєєС╗ЦСИі | тЈќт╝ЋжЄЉжАЇсЂ«20№╝Ё |
СИђУѕгТЄИУ│ъсЂетљїсЂўсѓѕсЂєсЂФсђЂтЈќт╝ЋжЄЉжАЇсЂФсѓѕсЂБсЂдТЎ»тЊЂжЄЉжАЇсЂ«ТЮАС╗ХсЂїуЋ░сЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
тЈѓтіаУђЁсѓёт┐ютІЪУђЁсЂ«тЁетЊАсЂФТЎ»тЊЂсѓњТЈљСЙЏсЂЎсѓІсЂ«сЂДсђЂСИђУѕгТЄИУ│ъсЂеТ»ћУ╝ЃсЂЌсЂджЄЉжАЇсЂїт░ЉсЂфсЂЈсЂфсЂБсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесЂФТ│еТёЈсЂЌсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
сЂЙсЂЪсђЂтЈѓтіаУђЁсЂ«тЁетЊАсЂФТЎ»тЊЂсЂїТЈљСЙЏсЂЋсѓїсѓІсЂЊсЂесЂІсѓЅсђЂСИђУѕгТЄИУ│ъсѓётЁ▒тљїТЄИУ│ъсЂеуЋ░сЂфсѓіуиЈжАЇсЂФсЂцсЂёсЂдСИіжЎљсЂ»т«џсѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
УЕ│сЂЌсЂЈсЂ»С╗ЦСИІсЂ«сѓхсѓцсЃѕсѓѓтЈѓУђЃсЂФсЂЌсЂдсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓ
тЈѓУђЃ№╝џТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ№йюТХѕУ▓╗УђЁт║Ђ
ТЎ»тЊЂсЃ╗ТЄИУ│ъсЂїТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФжЂЋтЈЇсЂЎсѓІС║ІСЙІ

ТЎ»тЊЂсЃ╗ТЄИУ│ъсЂїжЂЋтЈЇсЂЎсѓІтЁиСйЊуџёсЂфС║ІСЙІсѓњС╗ЦСИІсЂФу┤╣С╗ІсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
- ТЎ»тЊЂсЂ«С║цТЈЏсЃ╗тЈЌсЂЉтЈќсѓісЂ«СИЇТГБсЃ╝тйЊжЂИжђџуЪЦтЙїсЂФТЎ»тЊЂсЂїТЈљСЙЏсЂЋсѓїсЂфсЂёсђЂсЂЙсЂЪсЂ»тЈЌсЂЉтЈќсѓітЏ░жЏБсЂфсѓ▒сЃ╝сѓ╣
- ТійжЂИухљТъюсЂ«СИЇТГБТЊЇСйюсЃ╝уЅ╣т«џсЂ«С║║сЂФтйЊжЂИсЂЋсЂЏсѓІсЂфсЂЕсђЂтЁгт╣│ТђДсѓњТгасЂЈжЂІтќХсѓњУАїсЂєсѓ▒сЃ╝сѓ╣
сЂЊсѓїсѓЅсЂ«жЂЋтЈЇсЂ»сђЂТХѕУ▓╗УђЁсЂФт»ЙсЂЌсЂдСИЇтйЊсЂфТюЪтЙЁсѓњТі▒сЂІсЂЏсЂЪсѓісђЂУфцУДБсѓњТІЏсЂёсЂЪсѓісЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂЎсђѓуЅ╣сЂФтЋЈжАїсЂесЂфсѓІсЂ«сЂ»сђЂт«ЪжџЏсЂ«тЈќт╝ЋТЮАС╗ХсѓёТЎ»тЊЂсЂ«тєЁт«╣сЂїт║ЃтЉісѓёУАеуц║сЂетцДсЂЇсЂЈуЋ░сЂфсѓІсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЂДсЂЎсђѓ
СЙІсЂѕсЂ░сђЂсђїУф░сЂДсѓѓтЈѓтіасЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђЇсЂеУАеуц║сЂЌсЂфсЂїсѓЅт«ЪжџЏсЂФсЂ»тЋєтЊЂУ│╝тЁЦсЂїт┐ЁУдЂсЂасЂБсЂЪсѓісђЂсђї1/1,000сЂ«уб║ујЄсЂДтйЊжЂИсђЇсЂеУг│сЂёсЂфсЂїсѓЅт«ЪжџЏсЂ«тйЊжЂИуб║ујЄсЂїУЉЌсЂЌсЂЈСйјсЂІсЂБсЂЪсѓісЂЎсѓІсѓѕсЂєсЂфС║ІСЙІсЂїТїЎсЂњсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЙсЂЪсђЂТЎ»тЊЂсЂ«ТЈљСЙЏТќ╣Т│ЋсЂФжќбсЂЎсѓІСИЇТГБсѓѓжЄЇтцДсЂфжЂЋтЈЇсЂДсЂЎсђѓтйЊжЂИУђЁсЂФт»ЙсЂЌсЂдсђЂТГБтйЊсЂфуљєућ▒сЂфсЂЈТЎ»тЊЂсЂ«ТЈљСЙЏсѓњжЂЁт╗ХсЂЌсЂЪсѓісђЂжЂјт║дсЂФУцЄжЏЉсЂфтЈЌсЂЉтЈќсѓіТЮАС╗ХсѓњУеГт«џсЂЌсЂЪсѓісЂЎсѓІсЂ«сЂ»сђЂТХѕУ▓╗УђЁсЂ«тѕЕуЏісѓњУЉЌсЂЌсЂЈТљЇсЂфсЂєУАїуѓ║сЂесЂЌсЂдУдЈтѕХсЂ«т»ЙУ▒АсЂДсЂЎсђѓ
ТЎ»тЊЂТЈљСЙЏсѓњУАїсЂєС║ІТЦГУђЁсЂ»сђЂсЂЊсѓїсѓЅсЂ«жЂЋтЈЇС║ІСЙІсѓњтЇЂтѕєсЂФуљєУДБсЂЌсђЂжЂЕтѕЄсЂфжЂІтќХсѓњт┐ЃсЂїсЂЉсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ№╝ѕТЎ»УАеТ│Ћ№╝ЅсЂДт«џсѓЂсѓЅсѓїсЂЪжЄЉжАЇсѓњУХЁжЂјсЂЌсЂдсЂЌсЂЙсЂБсЂЪта┤тљѕ
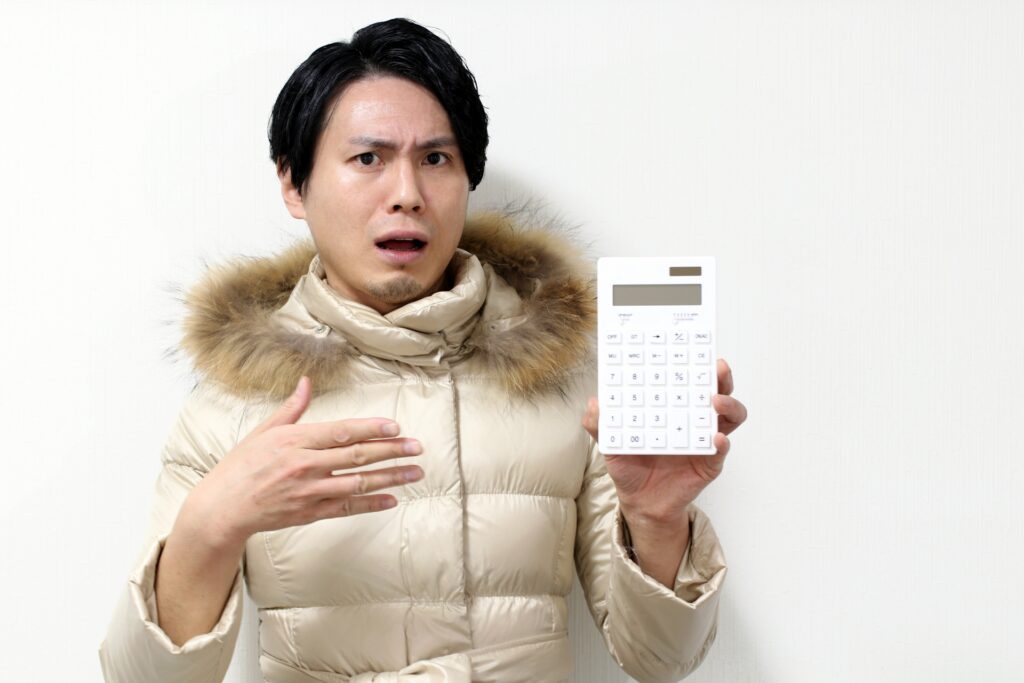
ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂДсЂ»сђЂТЄИУ│ъсЂ«тєЁт«╣сѓётйбт╝ЈсЂФсѓѕсЂБсЂдТЈљСЙЏсЂДсЂЇсѓІТЎ»тЊЂсЂ«жЄЉжАЇсЂ«СИіжЎљсЂїТ▒║сѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓт«џсѓЂсѓЅсѓїсЂЪСИіжЎљжЄЉжАЇсѓњУХЁсЂѕсѓІТЎ»тЊЂсѓњТЈљСЙЏсЂЌсЂдсЂЌсЂЙсЂБсЂЪта┤тљѕсЂ»сђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋжЂЋтЈЇсЂФтЋЈсѓЈсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФжЂЋтЈЇсЂЌсЂЪТЎ»тЊЂТЈљСЙЏсѓњсЂЌсЂЪта┤тљѕсЂФсЂ»сђЂС╗ЦСИІсЂ«3сЂцсЂ«сЃџсЃісЃФсЃєсѓБсЂїУф▓сЂЋсѓїсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎ
- ТХѕУ▓╗УђЁт║ЂсѓёжЃйжЂЊт║юуюїсЂФсѓѕсѓІТјфуй«тЉйС╗ц
- ТХѕУ▓╗УђЁт║ЂсЂФсѓѕсѓІУф▓тЙ┤жЄЉу┤ЇС╗ўтЉйС╗ц
- жЂЕТа╝ТХѕУ▓╗УђЁтЏБСйЊсЂІсѓЅсЂ«ти«ТГбУФІТ▒ѓ
сЂЙсЂџсђЂТХѕУ▓╗УђЁт║ЂсѓёжЃйжЂЊт║юуюїсЂФсѓѕсѓІТјфуй«тЉйС╗цсЂФсЂцсЂёсЂдсЂДсЂЎсђѓ
Тјфуй«тЉйС╗цсЂесЂ»ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћугг7ТЮАсЂФт«џсѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІсѓѓсЂ«сЂДсђЂу░АтЇўсЂФУеђсЂѕсЂ░сђїжЂјтцДсЂфжЄЉжАЇсЂ«ТЎ»тЊЂсѓњТЈљСЙЏсЂЎсѓІсЂ«сѓњсѓёсѓЂсЂфсЂЋсЂёсђЇсЂесѓёсѓЂсѓІсѓѕсЂєТ│еТёЈсЃ╗ТїЄт░јсЂЋсѓїсѓІсЂЊсЂесЂДсЂЎсђѓ
ТХѕУ▓╗УђЁт║ЂсѓѓсЂЌсЂЈсЂ»УЄфТ▓╗СйЊсЂІсѓЅТјфуй«тЉйС╗цсѓњтЈЌсЂЉсЂЪта┤тљѕсЂ»сђЂТЎ»тЊЂсЂ«ТЈљСЙЏсѓњтЂюТГбсЃ╗тѕХжЎљсЂЋсѓїсѓІсЂЊсЂесѓѓсЂѓсѓісђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋжЂЋтЈЇсЂФсЂфсѓЅсЂфсЂёсѓѕсЂєсЂФТћ╣тќёсѓњсЂЎсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
Тјфуй«тЉйС╗цсЂасЂЉсЂДсђЂТћ╣тќёсЂЋсѓїсѓїсЂ░уй░жЄЉсЂфсЂЕсЂ«жЄЉжіГуџёсЂфуй░тЅЄсѓњтЈЌсЂЉсѓІсЂЊсЂесЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
ТгАсЂФсђЂТХѕУ▓╗УђЁт║ЂсЂФсѓѕсѓІУф▓тЙ┤жЄЉу┤ЇС╗ўтЉйС╗цсЂФсЂцсЂёсЂдсЂДсЂЎсђѓ
Уф▓тЙ┤жЄЉсЂесЂ»сђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋжЂЋтЈЇсЂДСИЇТГБсЂФтЙЌсЂЪтѕЕуЏісѓњС║ІТЦГУђЁсЂ«ТЅІтЁЃсЂФТ«ІсЂЋсЂЏсЂфсЂёсЂЪсѓЂсЂФсђЂУф▓тЙ┤жЄЉсЂесЂёсЂєтйбсЂДу┤ЇС╗ўсЂЋсЂЏсЂЙсЂЎсђѓ
Уф▓тЙ┤жЄЉсЂ«жЄЉжАЇУеѕу«ЌсЂ»сђЂУф▓тЙ┤жЄЉсЂ«т»ЙУ▒АУАїуѓ║сЂФС┐ѓсѓІтЋєтЊЂсѓёсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂ«тБ▓СИіжАЇсЂФ3%сѓњС╣ЌсЂўсЂЪжЄЉжАЇсЂДсЂЎсђѓ
сЂцсЂЙсѓісђЂтБ▓СИісѓњсЂЎсЂ╣сЂдТ▓АтЈјсЂЋсѓїсЂЪСИісЂФсђЂтБ▓СИіжЄЉжАЇсЂ«3№╝Ёсѓњуй░жЄЉсЂесЂЌсЂдсЂЋсѓЅсЂФТћ»ТЅЋсѓЈсЂфсЂёсЂесЂёсЂЉсЂфсЂёсЂеУђЃсЂѕсѓїсЂ░сѓѕсЂёсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
сЂЊсѓїсѓЅсЂ«Тјфуй«тЉйС╗цсѓёУф▓тЙ┤жЄЉу┤ЇС╗ўтЉйС╗цсЂФтЙЊсѓЈсЂфсЂёта┤тљѕсЂ»сђЂТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋжЂЋтЈЇсЂ«уй░тЅЄсЂїуДЉсЂЋсѓїсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋжЂЋтЈЇсЂ«уй░тЅЄсЂ»сђЂтђІС║║сЂ«та┤тљѕсЂ»2т╣┤С╗ЦСИІсЂ«ТЄ▓тй╣сЂЙсЂЪсЂ»300СИЄтєєС╗ЦСИІсЂ«уй░жЄЉсђЂТ│ЋС║║сЂ«та┤тљѕсЂ»3тёётєєС╗ЦСИІсЂ«уй░жЄЉсЂДсЂЎсђѓ
ТЎ»тЊЂсЃ╗ТЄИУ│ъсЂФжќбсЂЎсѓІСИЇтйЊУАеуц║сѓѓNG

ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂДсЂ»сђЂТЎ»тЊЂжАъсЂ«ТЈљСЙЏсЂФжќбсЂЎсѓІУдЈтѕХсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈсђЂУАеуц║Тќ╣Т│ЋсЂФсЂцсЂёсЂдсѓѓтј│сЂЌсЂЈУдЈтѕХсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓСИЇтйЊУАеуц║сЂесЂ»сђЂСИђУѕгТХѕУ▓╗УђЁсЂФт«ЪжџЏсЂ«сѓѓсЂ«сѓѕсѓісѓѓтёфсѓїсЂдсЂёсѓІсЃ╗ТюЅтѕЕсЂасЂфсЂЕсЂетІўжЂЋсЂёсЂЋсЂЏсЂдсЂЌсЂЙсЂєТЂљсѓїсЂ«сЂѓсѓІУАеуц║сЂ«сЂЊсЂесЂДсЂЎсђѓТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂДсЂ»сђїтёфУЅ»УфцУфЇУАеуц║сђЇсђїТюЅтѕЕУфцУфЇУАеуц║сђЇсЂфсЂЕсЂетѕєжАъсЂЌсђЂУдЈтѕХсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
уЅ╣сЂФТЎ»тЊЂсЃ╗ТЄИУ│ъсЂФжќбсЂЎсѓІСИЇтйЊУАеуц║сЂДТ│еТёЈсЂЎсЂ╣сЂЇуѓ╣сЂесЂЌсЂдсђЂТЎ»тЊЂсЂ«СЙАтђцсѓётЈќт╝ЋТЮАС╗ХсЂФжќбсЂЎсѓІУфцУДБсѓњТІЏсЂЈУАеуц║сЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓСЙІсЂѕсЂ░сђїжФўу┤џУ▓ЮсЃЉсЃ╝сЃФсЂ«сѓцсЃцсЃфсЃ│сѓ░сЂїтйЊсЂЪсѓІсЃЂсЃБсЃ│сѓ╣№╝ЂсђЇсЂеУАеуц║сЂЌсЂфсЂїсѓЅсђЂт«ЪжџЏсЂФсЂ»т«ЅСЙАсЂфС║║тиЦсЃЉсЃ╝сЃФсѓњТЈљСЙЏсЂЎсѓІсѓѕсЂєсЂфта┤тљѕсЂ»ТюЅтѕЕУфцУфЇУАеуц║сЂДсЂЎсђѓ
сѓ»сЃ╝сЃЮсЃ│сѓёуЅ╣тЁИсЂ«тѕЕућеТЮАС╗ХсЂФжќбсЂЎсѓІУАеуц║сѓѓжЄЇУдЂсЂДсЂЎсђѓсђїтЁетЏйсЂЕсЂ«т║ЌУѕЌсЂДсѓѓСй┐ућесЂДсЂЇсѓІтЅ▓т╝ЋтѕИсЃЌсЃгсѓ╝сЃ│сЃѕсђЇсЂесЂєсЂЪсЂёсЂфсЂїсѓЅсђЂт«ЪжџЏсЂФсЂ»тцџсЂЈсЂ«т»ЙУ▒Атцќт║ЌУѕЌсЂїтГўтюесЂЎсѓІсѓѕсЂєсЂфта┤тљѕсѓѓСИЇтйЊУАеуц║сЂесЂЌсЂдТЅ▒сѓЈсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
сђїС╗ітЏъуЅ╣тѕЦсЂФжђЂТќЎуёАТќЎсђЇсЂеУАеуц║сЂЌсЂфсЂїсѓЅсђЂт«ЪжџЏсЂФсЂ»сђЂсЂѓсѓЅсЂІсЂўсѓЂтЋєтЊЂСЙАТа╝сѓњжђЂТќЎуЏИтйЊжАЇтѕєт╝ЋсЂЇСИісЂњсЂдсЂёсѓІсѓѕсЂєсЂфта┤тљѕсѓѓсђЂТХѕУ▓╗УђЁсЂФт»ЙсЂЌсЂдтЈќт╝ЋТЮАС╗ХсѓњУфцУфЇсЂЋсЂЏсѓІСИЇтйЊУАеуц║сЂДсЂЎсђѓ
сЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂфСИЇтйЊУАеуц║сЂ»сђЂС╗цтњї6т╣┤№╝ѕ2024т╣┤№╝Ѕ10ТюѕсЂІсѓЅсЂ»уЏ┤уй░УдЈт«џсЂ«т»ЙУ▒АсЂесЂфсѓісђЂТјфуй«тЉйС╗цуГЅсѓњухїсЂџсЂФ100СИЄтєєС╗ЦСИІсЂ«уй░жЄЉсЂїуДЉсЂЋсѓїсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЙсЂЪсђЂтБ▓СИіжАЇсЂ«3%№╝ѕжЂјтј╗10т╣┤С╗ЦтєЁсЂФжЂЋтЈЇТГ┤сЂїсЂѓсѓІта┤тљѕсЂ»4.5%№╝ЅсЂ«Уф▓тЙ┤жЄЉсЂїУф▓сЂЋсѓїсѓІта┤тљѕсѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
жќбжђБУеўС║І№╝џсђљС╗цтњї6т╣┤10ТюѕТќйУАїсђЉуб║у┤ёТЅІуХџсЃ╗уЏ┤уй░УдЈт«џсЂесЂ»№╝ЪТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋТћ╣ТГБсЂ«сЃЮсѓцсЃ│сЃѕсѓњУДБУфг
ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋжЂЋтЈЇсЂ«СИЇтйЊУАеуц║сЂФт»ЙсЂЌсЂдсЂ»сђЂжЂЋтЈЇУАїуѓ║сЂИсЂ«тѕХУБЂсЂесЂЌсЂдуДЉсЂЋсѓїсѓІсЂ«сЂїсђїуй░жЄЉсђЇсЂДсЂЎсђѓжЂЋтЈЇУАїуѓ║сѓњТіЉТГбсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«УАїТћ┐Тјфуй«сЂесЂЌсЂдтЙ┤тЈјсЂЋсѓїсѓІсЂ«сЂїсђїУф▓тЙ┤жЄЉсђЇ№╝ѕтБ▓СИіжАЇсЂ«3%сђЂжЂЋтЈЇТГ┤сЂїсЂѓсѓІта┤тљѕсЂ»4.5%№╝ЅсЂДсђЂтѕХУБЂсЂФсЂ»сЂЊсЂ«2уе«жАъсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓуй░жЄЉсЂ»тѕЉС║Іуй░сЂесЂЌсЂджЂЋтЈЇУђЁтђІС║║сЂФуДЉсЂЋсѓїсѓІСИђТќ╣сђЂУф▓тЙ┤жЄЉсЂ»УАїТћ┐СИісЂ«тѕХУБЂжЄЉсЂесЂЌсЂдС║ІТЦГУђЁсЂІсѓЅтЙ┤тЈјсЂЋсѓїсђЂСИАТќ╣сЂїУф▓сЂЋсѓїсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓІсЂЪсѓЂТ│еТёЈсЂїт┐ЁУдЂсЂДсЂЎсђѓ
ТЎ»тЊЂсЃ╗ТЄИУ│ъсЂ«С╝Ђућ╗сѓњт«ЪТќйсЂЎсѓІжџЏсЂ»сђЂТЎ»тЊЂжАъсЂ«СЙАжАЇсѓёТЈљСЙЏТќ╣Т│ЋсЂФжќбсЂЎсѓІУдЈтѕХсѓњжЂхт«ѕсЂЎсѓІсЂасЂЉсЂДсЂ»СИЇтЇЂтѕєсЂДсЂЎсђѓУАеуц║Тќ╣Т│ЋсЂФсЂцсЂёсЂдсѓѓтЇЂтѕєсЂфТ│еТёЈсѓњТЅЋсЂёсђЂТХѕУ▓╗УђЁсЂФУфцУфЇсѓњСИјсЂѕсѓІсЂЊсЂесЂ«сЂфсЂёсѓѕсЂєсђЂТГБуб║сЂфТЃЁта▒ТЈљСЙЏсѓњт┐ЃсЂїсЂЉсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
УЕ│сЂЌсЂЈсЂ»С╗ЦСИІсЂ«сѓхсѓцсЃѕсѓѓтЈѓУђЃсЂФсЂЌсЂдсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓ
жќбжђБУеўС║І№╝џТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ№╝ѕТЎ»УАеТ│Ћ№╝ЅсЂесЂ»№╝ЪсѓЈсЂІсѓісѓёсЂЎсЂёУДБУфгсЂежЂЋтЈЇС║ІСЙІсЃ╗уй░тЅЄсѓњу┤╣С╗І
уЅ╣т«џсЂ«ТЦГуе«сЂФт»ЙсЂЎсѓІуЅ╣тѕЦсЂфУдЈтѕХ№╝ѕТЦГуе«тѕЦТЎ»тЊЂтЉіуц║№╝Ѕ

ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂДсЂ»сђЂСИђУѕгуџёсЂфТЎ»тЊЂУдЈтѕХсЂФтіасЂѕсЂдсђЂуЅ╣т«џсЂ«ТЦГуе«сЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»ТЦГуЋїсЂ«т«ЪТЃЁсѓњУђЃТЁ«сЂЌсЂЪуЅ╣тѕЦсЂфУдЈтѕХсЂїУеГсЂЉсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсѓЅсЂ«УдЈтѕХсЂ»ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћугг4ТЮАсЂ«УдЈт«џсЂФтЪ║сЂЦсЂЇсђЂтЉіуц║сЂФсѓѕсЂБсЂдТїЄт«џсЂЋсѓїсЂдсЂісѓісђЂуЈЙтюе4сЂцсЂ«ТЦГуе«сЂФт»ЙсЂЌсЂдуЅ╣тѕЦсЂфУдЈтѕХсЂїжЂЕућесЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂ»СИђУѕгуџёсЂфУдЈтѕХсЂеТЦГуе«тѕЦсЂ«уЅ╣тѕЦУдЈтѕХсѓњухёсЂ┐тљѕсѓЈсЂЏсЂдсђЂтљёТЦГуЋїсЂ«уЅ╣ТђДсЂФт┐юсЂўсЂЪтЁгТГБсЂфуФХС║Ѕуњ░тбЃсЂ«уХГТїЂсѓњтЏ│сЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
Тќ░УЂъТЦГ
Тќ░УЂъТЦГуЋїсЂДсЂ»сђЂУ│╝УфГтЦЉу┤ёсЂ«уЇ▓тЙЌсѓёуХГТїЂсѓњуЏ«уџёсЂесЂЌсЂЪТЎ»тЊЂТЈљСЙЏсЂїСИђУѕгуџёсЂФУАїсѓЈсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсЂїсђЂжЂјт║дсЂфТЎ»тЊЂуФХС║ЅсЂ»У│╝УфГУђЁсЂ«жЂЕтѕЄсЂфжЂИТіъсѓњтдесЂњсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЮсЂ«сЂЪсѓЂсђЂсђїТќ░УЂъТЦГсЂФсЂісЂЉсѓІТЎ»тЊЂжАъсЂ«ТЈљСЙЏсЂФжќбсЂЎсѓІС║ІжаЁсЂ«тѕХжЎљсђЇ№╝ѕтЁгТГБтЈќт╝ЋтДћтЊАС╝џтЉіуц║№╝ЅсЂФсѓѕсѓісђЂТќ░УЂъсЂ«т«џТюЪУ│╝УфГтЦЉу┤ёсЂФжќбжђБсЂЌсЂдТЈљСЙЏсЂЋсѓїсѓІТЎ»тЊЂжАъсЂФсЂцсЂёсЂдсђЂжђџуД░сђї6сЃ╗8сЃФсЃ╝сЃФсђЇсЂетЉ╝сЂ░сѓїсѓІуЅ╣тѕЦсЂфтѕХжЎљсЂїУеГсЂЉсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂ»сђЂТќ░УдЈтЦЉу┤ёТЎѓсЂ«ТЎ»тЊЂТЈљСЙЏжАЇсѓњ6сЂІТюѕтѕєсЂ«У│╝УфГТќЎжЄЉсЂ«8%сѓњСИіжЎљсЂесЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂЎсђѓ
СЙІсЂѕсЂ░сђЂТюѕжАЇУ│╝УфГТќЎсЂї4,000тєєсЂ«Тќ░УЂъсЂ«та┤тљѕсђЂ6сЂІТюѕтѕєсЂ«У│╝УфГТќЎсЂ»24,000тєєсЂесЂфсѓісђЂТЈљСЙЏсЂДсЂЇсѓІТЎ»тЊЂсЂ«СИіжЎљжАЇсЂ»1,920тєє№╝ѕ24,000тєєсЂ«8%№╝ЅсЂДсЂЎсђѓсЂЊсЂ«сЃФсЃ╝сЃФсЂФсѓѕсѓісђЂжЂјт║дсЂфТЎ»тЊЂуФХС║ЅсѓњТіЉтѕХсЂЌсђЂУ│╝УфГУђЁсЂїТќ░УЂъсЂ«тєЁт«╣сѓётЊЂУ│фсЂДжЂИТіъсЂДсЂЇсѓІуњ░тбЃсѓњТЋ┤сЂѕсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЊсѓїсЂФсѓѕсѓІті╣ТъюсЂ»сђЂУ│╝УфГУђЁсЂїТќ░УЂъсЂ«тєЁт«╣сѓётЊЂУ│фсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂТЎ»тЊЂсЂ«жГЁтіЏсЂФсѓѕсЂБсЂдУ│╝УфГсѓњТ▒║т«џсЂЎсѓІсЂЊсЂесѓњжў▓сЂњсѓІуѓ╣сЂДсЂЎсђѓ
жЏЉУфїТЦГ
жЏЉУфїТЦГуЋїсЂДсѓѓсђЂУфГУђЁуЇ▓тЙЌсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«ТЎ»тЊЂТЈљСЙЏсЂїУАїсѓЈсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсЂїсђЂсЂЊсѓїсЂФсЂцсЂёсЂдсѓѓсђїжЏЉУфїТЦГсЂФсЂісЂЉсѓІТЎ»тЊЂжАъсЂ«ТЈљСЙЏсЂФжќбсЂЎсѓІС║ІжаЁсЂ«тѕХжЎљсђЇ№╝ѕтЁгТГБтЈќт╝ЋтДћтЊАС╝џтЉіуц║№╝ЅсЂФсѓѕсѓісђЂуЅ╣тѕЦсЂфУдЈтѕХсЂїжЂЕућесЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓжЏЉУфїсЂ«У│╝тЁЦсѓёт«џТюЪУ│╝УфГсЂФС╗ўжџЈсЂЌсЂдТЈљСЙЏсЂЋсѓїсѓІТЎ»тЊЂжАъсЂ«СЙАжАЇсѓёТЈљСЙЏТќ╣Т│ЋсЂФсЂцсЂёсЂдтѕХжЎљсѓњУеГсЂЉсЂдсђЂУфГУђЁсЂїжЏЉУфїсЂ«тєЁт«╣сЂЮсЂ«сѓѓсЂ«сЂФсѓѕсЂБсЂджЂИТіъсЂДсЂЇсѓІуњ░тбЃсѓњТЋ┤сЂѕсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
СИЇтІЋућБТЦГ
СИЇтІЋућБТЦГуЋїсЂДсЂ»сђїСИЇтІЋућБТЦГсЂФсЂісЂЉсѓІТЎ»тЊЂжАъсЂ«ТЈљСЙЏсЂ«тѕХжЎљсЂФжќбсЂЎсѓІтЁгТГБуФХС║ЅУдЈу┤ёсђЇсЂФсѓѕсѓісђЂСИЇтІЋућБтЈќт╝ЋсЂ«ТЎ»тЊЂТЈљСЙЏсЂФУЄфСИ╗УдЈтѕХсЂїУеГсЂЉсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂ»сђЂСИЇтІЋућБтЈќт╝ЋсЂїСИђУѕгуџёсЂФжФўжАЇсЂДсЂѓсѓісђЂТХѕУ▓╗УђЁсЂФсЂесЂБсЂджЄЇУдЂсЂфТёЈТђЮТ▒║т«џсѓњС╝┤сЂєсЂЊсЂесѓњУђЃТЁ«сЂЌсђЂТЦГуЋїтЏБСйЊсЂїт«џсѓЂсЂЪсЃФсЃ╝сЃФсЂДсЂЎсђѓ
тЈќт╝ЋСЙАжАЇсЂФжќбсѓЈсѓЅсЂџсђЂТЎ»тЊЂжАъсЂ«ТюђжФўжАЇсЂ»10СИЄтєєсЂЙсЂДсЂесЂЋсѓїсђЂТЄИУ│ъТЎ»тЊЂсЂ«уиЈжАЇсЂ»тЈќт╝ЋС║ѕт«џуиЈжАЇсЂ«2%С╗ЦтєЁсЂесЂёсЂєтѕХжЎљсЂїжЂЕућесЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
СЙІсЂѕсЂ░сђЂ5,000СИЄтєєсЂ«сЃъсЃ│сѓисЃДсЃ│У▓ЕтБ▓сЂДТЄИУ│ъС╗ўсЂЇсѓГсЃБсЃ│сЃџсЃ╝сЃ│сѓњт«ЪТќйсЂЎсѓІта┤тљѕсђЂТЈљСЙЏсЂДсЂЇсѓІТЎ»тЊЂсЂ«уиЈжАЇсЂ»100СИЄтєє№╝ѕ5,000СИЄтєєсЂ«2%№╝ЅсЂїСИіжЎљсЂДсЂЎсђѓсЂЙсЂЪсђЂ1С╗ХсЂѓсЂЪсѓісЂ«ТЎ»тЊЂжАЇсЂ»10СИЄтєєсѓњУХЁсЂѕсѓІсЂЊсЂесЂ»сЂДсЂЇсЂЙсЂЏсѓЊсђѓсЂЊсѓїсЂФсѓѕсѓісђЂжЂјтцДсЂфТЎ»тЊЂсЂФсѓѕсЂБсЂдТХѕУ▓╗УђЁсЂ«уЅЕС╗ХжЂИТіъсЂ«тѕцТќГсЂїТГфсѓЂсѓЅсѓїсѓІсЂ«сѓњжў▓ТГбсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
тЈѓУђЃ№╝џтЁгТГБуФХС║ЅУдЈу┤ёсЂ«у┤╣С╗І№йюСИЇтІЋућБтЁгТГБтЈќт╝ЋтЇћУГ░С╝џжђБтљѕС╝џ
тї╗уЎѓућетї╗УќгтЊЂТЦГсђЂтї╗уЎѓТЕЪтЎеТЦГтЈісЂ│УАЏућЪТцюТЪ╗ТЅђТЦГ
тї╗уЎѓућетї╗УќгтЊЂТЦГсђЂтї╗уЎѓТЕЪтЎеТЦГтЈісЂ│УАЏућЪТцюТЪ╗ТЅђТЦГсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»сђЂТЦГуЋїтЏБСйЊсЂФсѓѕсѓІУЄфСИ╗УдЈтѕХсђїтї╗уЎѓућетї╗УќгтЊЂУБйжђаУ▓ЕтБ▓ТЦГсЂФсЂісЂЉсѓІТЎ»тЊЂжАъсЂ«ТЈљСЙЏсЂ«тѕХжЎљсЂФжќбсЂЎсѓІтЁгТГБуФХС║ЅУдЈу┤ёсђЇсЂїУеГсЂЉсѓЅсѓїсЂдсЂісѓісђЂТюђсѓѓтј│Та╝сЂфУдЈтѕХсЂїжЂЕућесЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓтї╗уЎѓТЕЪжќбуГЅсЂФт»ЙсЂЌсЂдтЈќт╝ЋсѓњСИЇтйЊсЂФУфўт╝ЋсЂЎсѓІТЅІТ«хсЂесЂЌсЂдТЎ»тЊЂжАъсѓњТЈљСЙЏсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїтЁежЮбуџёсЂФудЂТГбсЂЋсѓїсЂдсЂісѓісђЂтї╗уЎѓТЕЪтЎесЂ«уёАтёЪУ▓ИСИјсѓётй╣тІЎсЂ«ТЈљСЙЏсѓѓтљФсЂЙсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЊсЂ«УдЈтѕХсЂ»сђЂтї╗уЎѓућетї╗УќгтЊЂсѓётї╗уЎѓТЕЪтЎесЂ«жЂИт«џсЂїу┤ћу▓ІсЂФтї╗тГдуџёсЃ╗уДЉтГдуџёсЂфтѕцТќГсЂФтЪ║сЂЦсЂёсЂдУАїсѓЈсѓїсѓІсЂ╣сЂЇсЂесЂёсЂєУђЃсЂѕсЂФтЪ║сЂЦсЂёсЂдсЂісѓісђЂТЎ»тЊЂсЂФсѓѕсѓІтй▒жЪ┐сѓњт«їтЁесЂФТјњжЎцсЂЌсЂдсђЂТѓБУђЁсЂ«тЂЦт║исЂет«ЅтЁесѓњт«ѕсѓІсЂ«сЂїуЏ«уџёсЂДсЂЎсђѓСЙІсЂѕсЂ░сђЂТќ░УќгсЂ«ТјАућесѓњТЮАС╗ХсЂесЂЌсЂЪтї╗уЎѓТЕЪтЎесЂ«уёАтёЪТЈљСЙЏсѓёсђЂтЄдТќ╣ТЋ░сЂФт┐юсЂўсЂЪухїТИѕуџётѕЕуЏісЂ«СЙЏСИјсЂфсЂЕсЂ»сђЂТўјуб║сЂфжЂЋтЈЇУАїуѓ║сЂДсЂЎсђѓ
сЂЙсЂесѓЂ№╝џсЃјсЃЎсЃФсЃєсѓБсЂфсЂЕсЂ«СйюТѕљтЅЇсЂФТЎ»УАеТ│ЋсЂ«жЄЉжАЇсЂФсЂцсЂёсЂдт╝ЂУГитБФсЂФуЏИУФЄсЂЌсЂдсЂЈсЂасЂЋсЂё

ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФсЂцсЂёсЂдУДБУфгсЂЌсђЂТЄИУ│ъсѓёТЎ»тЊЂсЂ«уе«жАъсЂћсЂесЂФт«џсѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІТЎ»тЊЂсЂ«СИіжЎљжЄЉжАЇсЂфсЂЕсЂФсЂцсЂёсЂдсѓѓУДБУфгсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓТЎ»тЊЂсЂ«СИіжЎљжЄЉжАЇсЂ»сђЂТЄИУ│ъсЂ«тєЁт«╣сЂћсЂесЂФу┤░сЂІсЂЈт«џсѓЂсѓЅсѓїсЂдсЂісѓісђЂжЂЋтЈЇсЂЌсЂЪта┤тљѕсЂ»Тјфуй«тЉйС╗цсѓёУф▓тЙ┤жЄЉу┤ЇС╗ўтЉйС╗цсѓњтЈЌсЂЉсѓІсЂЊсЂесѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
Т│ЋтЙІсѓњжЂхт«ѕсЂЌсЂдТЄИУ│ъсѓњжќІтѓгсЂЌсЂЪсЂёсЂеТђЮсЂБсЂдсѓѓсђЂУЄфтѕєсЂїжќІтѓгсЂЎсѓІТЄИУ│ъсЂїсЂЕсЂ«сѓ┐сѓцсЃЌсЂ«ТЄИУ│ъсЂФтѕєжАъсЂЋсѓїсѓІсЂ«сЂІТѓЕсѓђсѓ▒сЃ╝сѓ╣сѓѓсЂѓсѓІсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
ТЄИУ│ъсЂ«уе«жАъсѓњжќЊжЂЋсЂѕсЂЪсЂЪсѓЂТЎ»тЊЂсЂ«жЄЉжАЇсЂїСИіжЎљсѓњУХЁсЂѕсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂесЂёсЂєсЃфсѓ╣сѓ»сѓњТИЏсѓЅсЂЎсЂЪсѓЂсЂФсѓѓсђЂсЃјсЃЎсЃФсЃєсѓБсЂфсЂЕсЂ«ТЎ»тЊЂсѓњСйюТѕљсЂЎсѓІтЅЇсЂФт╝ЂУГитБФсЂФуЏИУФЄсЂЎсѓІсЂЊсЂесѓњсЂітІДсѓЂсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
т╝ЂУГитБФсЂїт░ѓжќђсЂ«уЪЦУГўсЂеухїжеЊсЂФсѓѕсЂБсЂдсђЂТЄИУ│ъсЂ«тєЁт«╣сѓёуіХТ│ЂсЂ«тѕцТќГсѓёсђЂТЎ»тЊЂжЄЉжАЇсЂ«Уеѕу«ЌсЂ«ТЅІтіЕсЂЉсѓњсЂёсЂЪсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
СйЎУеѕсЂфсЃфсѓ╣сѓ»сѓёт┐ЃжЁЇсѓњућЪсЂўсЂЋсЂЏсЂфсЂёсЂЪсѓЂсЂФсѓѓсђЂСИЇт«ЅсЂїсЂѓсѓІсЂ«сЂфсѓЅТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋсЂФУЕ│сЂЌсЂёт╝ЂУГитБФсѓёТ│ЋтЙІС║ІтІЎТЅђсЂФсЂЙсЂџсЂ»уЏИУФЄсЂЌсЂдсЂ┐сЂдсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓ
тйЊС║ІтІЎТЅђсЂФсѓѕсѓІт»ЙуГќсЂ«сЂћТАѕтєЁ
сЃбсЃјсЃфсѓ╣Т│ЋтЙІС║ІтІЎТЅђсЂ»сђЂITсђЂуЅ╣сЂФсѓцсЃ│сѓ┐сЃ╝сЃЇсЃЃсЃѕсЂеТ│ЋтЙІсЂ«СИАжЮбсЂФУ▒іт»їсЂфухїжеЊсѓњТюЅсЂЎсѓІТ│ЋтЙІС║ІтІЎТЅђсЂДсЂЎсђѓУ┐Љт╣┤сђЂсЃЇсЃЃсЃѕт║ЃтЉісѓњсѓЂсЂљсѓІтёфУЅ»УфцУфЇсЂфсЂЕсЂ«ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│ЋжЂЋтЈЇсЂ»тцДсЂЇсЂфтЋЈжАїсЂесЂфсЂБсЂдсЂісѓісђЂсЃфсЃ╝сѓгсЃФсЃЂсѓДсЃЃсѓ»сЂ«т┐ЁУдЂТђДсЂ»сЂЙсЂЎсЂЙсЂЎтбЌтіасЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓтйЊС║ІтІЎТЅђсЂ»сЂЋсЂЙсЂќсЂЙсЂфТ│ЋтЙІсЂ«УдЈтѕХсѓњУИЈсЂЙсЂѕсЂЪСИісЂДсђЂуЈЙсЂФжќІтДІсЂЌсЂЪсЃЊсѓИсЃЇсѓ╣сђЂжќІтДІсЂЌсѓѕсЂєсЂесЂЌсЂЪсЃЊсѓИсЃЇсѓ╣сЂФжќбсЂЎсѓІТ│ЋуџёсЃфсѓ╣сѓ»сѓњтѕєТъљсЂЌсђЂтЈ»УЃйсЂфжЎљсѓісЃЊсѓИсЃЇсѓ╣сѓњТГбсѓЂсѓІсЂЊсЂесЂфсЂЈжЂЕТ│ЋтїќсѓњтЏ│сѓісЂЙсЂЎсђѓСИІУеўУеўС║ІсЂФсЂдУЕ│у┤░сѓњУеўУ╝ЅсЂЌсЂдсЂісѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЃбсЃјсЃфсѓ╣Т│ЋтЙІС║ІтІЎТЅђсЂ«тЈќТЅ▒тѕєжЄј№╝џITсЃ╗сЃЎсЃ│сЃЂсЃБсЃ╝сЂ«С╝ЂТЦГТ│ЋтІЎ
сѓФсЃєсѓ┤сЃфсЃ╝: ITсЃ╗сЃЎсЃ│сЃЂсЃБсЃ╝сЂ«С╝ЂТЦГТ│ЋтІЎ
сѓ┐сѓ░: ТЎ»тЊЂУАеуц║Т│Ћ