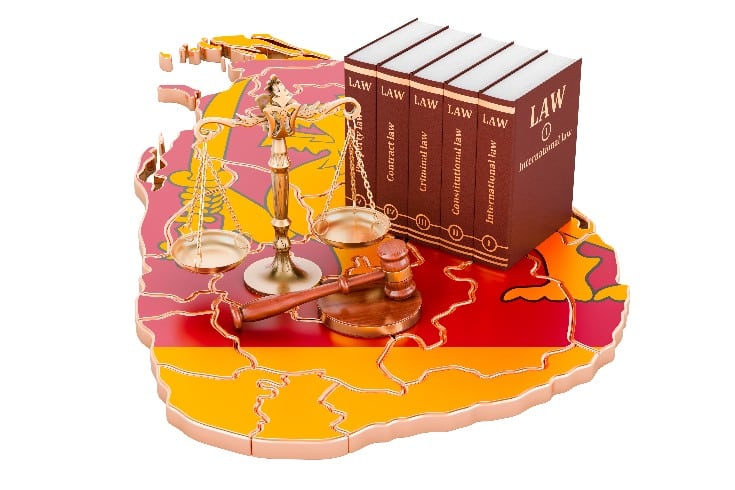гғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгӮ’ејҒиӯ·еЈ«гҒҢи§ЈиӘ¬

гғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«еӨ§йҷёжі•зі»гҒ®дјқзөұгӮ’жҢҒгҒӨжі•жІ»еӣҪ家гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжҲҗж–Үжі•е…ёгҒҢзӨҫдјҡгҒ®жі•зҡ„й–ўдҝӮгҒ®еҹәзӨҺгӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еӣҪгҒ®жі•еҲ¶еәҰгӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„зӢ¬иҮӘгҒ®еҺіж јгҒӘжі•еҫӢгҖҢжһўиҰҒжі•пјҲsarkalatos tГ¶rvГ©nyпјүгҖҚгӮ„гҖҒиҝ‘е№ҙгҒ®ж”ҝжІ»зҡ„еӢ•еҗ‘гҒҢеҸёжі•гҒ«дёҺгҒҲгӮӢеҪұйҹҝгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒ«гӮӮзӣ®гӮ’еҗ‘гҒ‘гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®жі•дҪ“зі»гҒЁеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®йӘЁж јгӮ’и©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҖҒзү№гҒ«ж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢзӣҙйқўгҒ—гҒҶгӮӢжі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжі•еҲ¶еәҰгҒ®жҰӮиҰҒгҒҜдёӢиЁҳиЁҳдәӢгҒ«гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®жі•дҪ“зі»гҒ®еҹәзӨҺ
еӨ§йҷёжі•зі»гҒ®жі•дҪ“зі»
гғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„жі•гӮ’гғ«гғјгғ„гҒЁгҒҷгӮӢеӨ§йҷёжі•зі»гҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒЁе…ұйҖҡгҒҷгӮӢеҹәзӣӨгҒ§гҒҷгҖӮгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒ2012е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгҒ«ж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢеҹәжң¬жі•пјҲFundamental LawпјүгҖҚгӮ’жңҖй«ҳиҰҸзҜ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӢгҒ«гҖҒж°‘жі•е…ёпјҲ2013е№ҙжі•еҫӢ第5еҸ·пјүгҖҒеҲ‘жі•е…ёгҖҒдјҡзӨҫжі•е…ёгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘжҲҗж–Үжі•гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҖҒе•ҶеҸ–еј•гӮ„еёӮж°‘з”ҹжҙ»гҒ®жі•зҡ„й–ўдҝӮгӮ’иҰҸеҫӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•гӮ„е•Ҷжі•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжі•е…ёдёӯеҝғгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒЁе…ұйҖҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғҸгғігӮ¬гғӘгғјзӢ¬иҮӘгҒ®гҖҢжһўиҰҒжі•гҖҚгҒЁгҒқгҒ®ж„Ҹзҫ©
гғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҢж—Ҙжң¬гҒЁжұәе®ҡзҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮӢзӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҹәжң¬жі•пјҲжҶІжі•пјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹзү№е®ҡгҒ®йҮҚиҰҒдәӢй …гӮ’иҰҸеҫӢгҒҷгӮӢгҖҢжһўиҰҒжі•пјҲsarkalatos tГ¶rvГ©nyпјүгҖҚгҒ®еӯҳеңЁгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жһўиҰҒжі•гӮ’еҲ¶е®ҡгғ»ж”№жӯЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеӣҪдјҡгҒ«еҮәеёӯгҒҷгӮӢиӯ°е“ЎгҒ®3еҲҶгҒ®2д»ҘдёҠгҒ®иіӣжҲҗгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒйҖҡеёёгҒ®жі•еҫӢгҒ®жҲҗз«ӢиҰҒ件пјҲеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҮәеёӯиӯ°е“ЎгҒ®йҒҺеҚҠж•°пјүгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒйқһеёёгҒ«й«ҳгҒ„гғҸгғјгғүгғ«гҒҢиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жһўиҰҒжі•гҒҢиҰҸеҫӢгҒҷгӮӢдәӢй …гҒҜгҖҒеҸёжі•еҲ¶еәҰгҖҒжӨңеҜҹе®ҳгҒ®ең°дҪҚгҖҒдёӯеӨ®йҠҖиЎҢгҒ®зӢ¬з«ӢжҖ§гҖҒеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·ж©ҹй–ўгҖҒгғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ®иҮӘз”ұгҖҒеӣҪзұҚгҖҒе®—ж•ҷе…ұеҗҢдҪ“гҒӘгҒ©гҖҒеӣҪгҒ®ж №е№№гҒ«й–ўгӮҸгӮӢеәғзҜ„гҒӘеҲҶйҮҺгҒ«еҸҠгҒігҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҺіж јгҒӘжҲҗз«ӢиҰҒ件гҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®еҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжі•зҡ„е®үе®ҡжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒ—гҖҒж”ҝжЁ©дәӨд»ЈеҫҢгӮӮе®№жҳ“гҒ«жі•еҫӢгҒҢеӨүжӣҙгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®жҜ”ијғ
гҒ“гҒ®жһўиҰҒжі•гҒ®еӯҳеңЁгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еӢҷе®ҹеӢҷ家гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®жі•зҡ„жҖ§иіӘгҒЁе®ҹеӢҷдёҠгҒ®ж„Ҹе‘іеҗҲгҒ„гӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒжһўиҰҒжі•гҒ®еҲ¶е®ҡиҰҒ件гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жҶІжі•ж”№жӯЈжүӢз¶ҡгҒҚгҒЁеҜҫжҜ”гҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®зЎ¬жҖ§гҒ®еәҰеҗҲгҒ„гҒҢгӮҲгӮҠжҳҺзўәгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жҶІжі•ж”№жӯЈгҒҜгҖҒдёЎиӯ°йҷўгҒ®з·Ҹиӯ°е“ЎгҒ®3еҲҶгҒ®2д»ҘдёҠгҒ®иіӣжҲҗгҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒеӣҪж°‘жҠ•зҘЁгҒ§гҒ®йҒҺеҚҠж•°гҒ®жүҝиӘҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жҘөгӮҒгҒҰеҺіж јгҒӘиҰҒ件гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®зҸҫиЎҢжҶІжі•гҒҜеҲ¶е®ҡд»ҘжқҘгҖҒдёҖеәҰгӮӮж”№жӯЈгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®жһўиҰҒжі•гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жҶІжі•ж”№жӯЈгҒ«еҢ№ж•өгҒҷгӮӢгҖҢеҮәеёӯиӯ°е“ЎгҒ®3еҲҶгҒ®2д»ҘдёҠгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҺіж јгҒӘиӯ°дјҡиҰҒ件гӮ’жҢҒгҒЎгҒӘгҒҢгӮүгҖҒеӣҪж°‘жҠ•зҘЁгҒҢдёҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒ2010е№ҙд»ҘйҷҚгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®дёҺе…ҡгҒҜеӣҪж”ҝйҒёжҢҷгҒ§з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«иӯ°дјҡе…ЁдҪ“гҒ®3еҲҶгҒ®2д»ҘдёҠгҒ®иӯ°еёӯгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢгӮ№гғјгғ‘гғјгғһгӮёгғ§гғӘгғҶгӮЈгҖҚгӮ’зҚІеҫ—гҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж”ҝжІ»зҡ„зҸҫе®ҹгҒ®гӮӮгҒЁгҒ§гҒҜгҖҒжһўиҰҒжі•гҒҜгҖҢж”ҝжЁ©дәӨд»ЈеҫҢгӮӮе®№жҳ“гҒ«еӨүжӣҙгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҖ§иіӘгӮ’жҢҒгҒЎгҒӨгҒӨгӮӮгҖҒзҸҫж”ҝжЁ©гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеӣҪж°‘гҒ®зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘж„ҸжҖқзўәиӘҚгӮ’зөҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒиҮӘгӮүгҒ®ж”ҝзӯ–гӮ„гӮӨгғҮгӮӘгғӯгӮ®гғјгӮ’жҒ’д№…зҡ„гҒ«жі•дҪ“зі»гҒ«зө„гҒҝиҫјгӮҖгҒҹгӮҒгҒ®еј·еҠӣгҒӘгғ„гғјгғ«гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжһўиҰҒжі•гҒ®еҲ¶е®ҡгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒе…¬иЎҶгҒ®й–ўдёҺгҒЁгҒ„гҒҶиҰізӮ№гҒӢгӮүгӮӮжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®йҖҡеёёгҒ®жі•еҫӢеҲ¶е®ҡгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҶ…й–ЈжҸҗеҮәжі•жЎҲгҒ®е ҙеҗҲгҖҒй–Јиӯ°жұәе®ҡгҒ«иҮігӮӢеүҚгҒ«гҖҒй–ўдҝӮзңҒеәҒй–“гҒ®еҚ”иӯ°гҖҒе ҙеҗҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜи«®е•Ҹж©ҹй–ўгӮ„е…¬иҒҙдјҡгҒ§гҒ®ж„ҸиҰӢиҒҙеҸ–гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ§гҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®жһўиҰҒжі•гӮ„жҶІжі•ж”№жӯЈгҒҢгҖҒж”ҝеәңжҸҗеҮәжі•жЎҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе…¬зҡ„еҚ”иӯ°гҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҢиӯ°е“ЎжҸҗеҮәжі•жЎҲгҖҚгҒ®еҪўејҸгҒ§жҸҗеҮәгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиӯ°дјҡгҒ§гҒ®еҜ©иӯ°жҷӮй–“гҒҢж„Ҹеӣізҡ„гҒ«зҹӯзё®гҒ•гӮҢгҖҒеҚҒеҲҶгҒӘиӯ°и«–гӮ„е…¬иЎҶгҒ®ж„ҸиҰӢгҒҢеҸҚжҳ гҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫжҲҗз«ӢгҒҷгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жһўиҰҒжі•гҒ®е…·дҪ“дҫӢпјҡгғЎгғҮгӮЈгӮўжі•
жһўиҰҒжі•гҒ®е…·дҪ“дҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгғЎгғҮгӮЈгӮўжі•гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гғЎгғҮгӮЈгӮўжі•гҒҜгҖҒе ұйҒ“гҒ®иҮӘз”ұгҒЁеӨҡж§ҳжҖ§гӮ’иҰҸеҫӢгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жһўиҰҒжі•гҒЁгҒ—гҒҰеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒгғЎгғҮгӮЈгӮўгӮ’зӣЈзқЈгҒҷгӮӢеҚҳдёҖгҒ®зӢ¬з«Ӣж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеӣҪз«ӢгғЎгғҮгӮЈгӮўгғ»гӮӨгғігғ•гӮ©гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғіеұҖпјҲNMHHпјүгҖҚгӮ’иЁӯз«ӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮNMHHгҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒҜгҖҒиӯ°дјҡгҒ®еҮәеёӯиӯ°е“ЎгҒ®3еҲҶгҒ®2д»ҘдёҠгҒ®иіӣжҲҗгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒёеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒе ұйҒ“еҶ…е®№гҒҢгҖҢе…¬е№ігҒӢгҒӨеқҮиЎЎгҒ®еҸ–гӮҢгҒҹгҖҚгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣЈиҰ–гҒҷгӮӢеәғзҜ„гҒӘжЁ©йҷҗгӮ’NMHHгҒ«дёҺгҒҲгҖҒйҒ•еҸҚгҒ—гҒҹгғЎгғҮгӮЈгӮўгҒ«гҒҜй«ҳйЎҚгҒӘзҪ°йҮ‘гӮ’科гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒдәӢжҘӯгӮ’еҒңжӯўгҒ•гҒӣгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒ欧е·һгҒ®еҗ„ж©ҹй–ўгҒӢгӮүжү№еҲӨгҒҢиЎЁжҳҺгҒ•гӮҢгҖҒе ұйҒ“гҒ®иҮӘз”ұгӮ’еҲ¶йҷҗгҒ—гҖҒж”ҝеәңгҒ«жү№еҲӨзҡ„гҒӘгғЎгғҮгӮЈгӮўгӮ’жҠ‘еҲ¶гҒҷгӮӢж„ҸеӣігҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶжҮёеҝөгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒеҮәзүҲзү©гӮ„гӮӘгғігғ©гӮӨгғігғЎгғҮгӮЈгӮўгӮ’NMHHгҒ®еҲ¶иЈҒжЁ©йҷҗгҒ®еҜҫиұЎеӨ–гҒЁгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒжі•еҫӢгҒ®дёҖйғЁгҒ®жқЎй …гӮ’з„ЎеҠ№гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жһўиҰҒжі•гҒ®е…·дҪ“дҫӢпјҡеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·жі•
дёҖж–№гҒ§гҖҒжһўиҰҒжі•гҒҜеҖӢдәәгҒ®еҹәжң¬зҡ„жЁ©еҲ©гӮ’дҝқйҡңгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгӮҲгӮҠдёӯз«Ӣзҡ„гҒӘзӣ®зҡ„гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮӮеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®д»ЈиЎЁдҫӢгҒҢгҖҒеҖӢдәәгҒ®гҖҢжғ…е ұиҮӘе·ұжұәе®ҡжЁ©гҒЁжғ…е ұе…¬й–ӢгҒ®иҮӘз”ұгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•гҖҚпјҲAct CXII of 2011пјүгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒеҹәжң¬жі•пјҲжҶІжі•пјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹеҖӢдәәгҒ®гҖҢеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҒ®дҝқиӯ·гӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢжЁ©еҲ©гҖҚгӮ’дҝқйҡңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝгҒ®еҮҰзҗҶгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҹәжң¬зҡ„гҒӘгғ«гғјгғ«гӮ’е®ҡгӮҒгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгҒқгҒ®зӣЈзқЈгӮ’иЎҢгҒҶзӢ¬з«Ӣж©ҹй–ўгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢеӣҪ家гғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·гғ»жғ…е ұе…¬й–ӢеәҒпјҲNAIHпјүгҖҚгӮ’иЁӯз«ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҰҸе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒҢ欧е·һйҖЈеҗҲпјҲEUпјүеҠ зӣҹеӣҪгҒЁгҒ—гҒҰиІ гҒҶеҖӢдәәгғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘзҫ©еӢҷгӮ’еӣҪеҶ…жі•гҒ«еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгӮӢеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҖҒеҫҢгҒ®EUгҒ®дёҖиҲ¬гғҮгғјгӮҝдҝқиӯ·иҰҸеүҮпјҲGDPRпјүгҒ®е°Һе…ҘгҒ«йҡӣгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒқгҒ®еҹәзӣӨгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гғҸгғігӮ¬гғӘгғјеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®ж§ӢйҖ гҒЁеӢ•еҗ‘
еҸёжі•зө„з№”гҒ®йҡҺеұӨ
гғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«йҡҺеұӨзҡ„гҒӘж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йҡҺеұӨгҒҜгҖҒ第дёҖеҜ©гҒ®ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖпјҲDistrict CourtsпјүгҖҒ第дәҢеҜ©гҒ®ең°еҹҹиЈҒеҲӨжүҖпјҲRegional CourtsпјүгҖҒгҒқгҒ—гҒҰең°еҹҹжҺ§иЁҙиЈҒеҲӨжүҖпјҲRegional Courts of AppealпјүгҒЁгҒ„гҒҶдёүгҒӨгҒ®дёӢзҙҡеҜ©гҒЁгҖҒжңҖдёҠдҪҚгҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒӮгӮӢгӮҜгғјгғӘгӮўпјҲCuriaпјүгҒӢгӮүж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
| иЈҒеҲӨжүҖеҗҚпјҲгғҸгғігӮ¬гғӘгғјпјү | еҪ№еүІгҒЁз®ЎиҪ„жЁ© | зӣёеҪ“гҒҷгӮӢж—Ҙжң¬гҒ®иЈҒеҲӨжүҖ |
|---|---|---|
| ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖпјҲDistrict Courtsпјү | гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®дәӢ件гҒ®з¬¬дёҖеҜ© | ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгғ»з°Ўжҳ“иЈҒеҲӨжүҖ |
| ең°еҹҹиЈҒеҲӨжүҖпјҲRegional Courtsпјү | жі•еҫӢгҒ§е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹзү№е®ҡгҒ®дәӢ件гҒ®з¬¬дёҖеҜ©гҖҒең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҒ®жҺ§иЁҙеҜ© | ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгғ»й«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖпјҲдёҖйғЁпјү |
| ең°еҹҹжҺ§иЁҙиЈҒеҲӨжүҖпјҲRegional Courts of Appealпјү | ең°еҹҹиЈҒеҲӨжүҖгҒ®жҺ§иЁҙеҜ© | й«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖ |
| гӮҜгғјгғӘгӮўпјҲCuriaпјү | жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҖӮдёӢзҙҡеҜ©гҒӢгӮүгҒ®жҺ§иЁҙгҖҒең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒ®иЎҢзӮәгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиЁҙгҒҲзӯү | жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖ |
гӮҜгғјгғӘгӮўпјҲжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖпјүгҒ®еҪ№еүІгҒЁеҲӨдҫӢгҒ®жӢҳжқҹеҠӣ
гӮҜгғјгғӘгӮўгҒҜгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®й ӮзӮ№гҒ«з«ӢгҒӨжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®дё»иҰҒгҒӘеҪ№еүІгҒ®дёҖгҒӨгҒҜгҖҒжі•еҫӢгҒ®зөұдёҖзҡ„гҒӘйҒ©з”ЁгӮ’дҝқиЁјгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгӮҜгғјгғӘгӮўгҒҢдёӢгҒҷгҖҢжі•зөұдёҖжұәе®ҡпјҲuniformity decisionsпјүгҖҚгҒҜгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгӮ’жӢҳжқҹгҒҷгӮӢжі•зҡ„еҠ№еҠӣгӮ’жңүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж©ҹиғҪгҒҜгҖҒеӨ§йҷёжі•зі»гҒ«еұһгҒҷгӮӢеӣҪгҖ…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒз•°гҒӘгӮӢиЈҒеҲӨжүҖй–“гҒ§гҒ®еҲӨжұәгҒ®зҹӣзӣҫгӮ’йҳІгҒҺгҖҒжі•зҡ„е®үе®ҡжҖ§гӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒ2020е№ҙ4жңҲд»ҘйҷҚгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ§гҒҜгҖҢйҷҗе®ҡзҡ„еҲӨдҫӢгҖҚгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж–°еҲ¶еәҰгҒ®дёӢгҒ§гҒҜгҖҒгӮҜгғјгғӘгӮўгҒҢе…¬иЎЁгҒ—гҒҹгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жұәе®ҡгҒҢдёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгӮ’жӢҳжқҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгӮҜгғјгғӘгӮўгҒ®жі•зҡ„и§ЈйҮҲгҒӢгӮүж„Ҹеӣізҡ„гҒ«йҖёи„ұгҒҷгӮӢеҲӨжұәгӮ’дёӢгҒҷе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒ®зҗҶз”ұгҒЁж №жӢ гӮ’жҳҺзўәгҒ«иӘ¬жҳҺгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„зҫ©еӢҷгҒҢиӘІгҒӣгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒеҲӨдҫӢгӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮӢиӢұзұіжі•пјҲгӮігғўгғігғ»гғӯгғјпјүгҒ®иҰҒзҙ гӮ’дёҖйғЁеҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁжҚүгҒҲгӮүгӮҢгҖҒе®ҹеӢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮҜгғјгғӘгӮўгҒ®еҲӨдҫӢгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гҒҢгҒ•гӮүгҒ«й«ҳгҒҫгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иҝ‘е№ҙгҒ®еҸёжі•ж”№йқ©гҒЁзӢ¬з«ӢжҖ§гҒёгҒ®еҪұйҹҝ
гғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®еҸёжі•гҒҜгҖҒиҝ‘е№ҙгҒ®ж”ҝжІ»зҡ„гғ»еҲ¶еәҰзҡ„ж”№йқ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒқгҒ®зӢ¬з«ӢжҖ§гҒ«й–ўгҒ—гҒҰеӣҪеҶ…еӨ–гҒӢгӮүеӨҡгҒҸгҒ®иӯ°и«–гӮ’е‘јгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еӢ•еҗ‘гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҢгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ§гҒ®дәӢжҘӯгғӘгӮ№гӮҜгӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҒжіЁж„Ҹж·ұгҒҸзӣЈиҰ–гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒеҸёжі•иЎҢж”ҝгҒ®з®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶гҒ®еӨүжӣҙгҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ2012е№ҙгҒ®ж”№йқ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®дәәдәӢгӮ„дәҲз®—гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеәғзҜ„гҒӘзӣЈзқЈжЁ©йҷҗгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§иЈҒеҲӨе®ҳгҒ®иҮӘжІ»зө„з№”гҒ§гҒӮгӮӢеӣҪж°‘еҸёжі•и©•иӯ°дјҡпјҲNational Judicial CouncilпјүгҒҢжӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒӢгӮүгҖҒиӯ°дјҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒёеҮәгҒ•гӮҢгӮӢеӨ§зөұй ҳгҒҢзҺҮгҒ„гӮӢеӣҪз«ӢеҸёжі•еәҒпјҲNational Office for the Judiciary, NOJпјүгҒ«з§»з®ЎгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж”№йқ©гҒҜгҖҒеҸёжі•иЎҢж”ҝгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒеҸёжі•гҒ®зӢ¬з«ӢжҖ§гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҮёеҝөгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЈҒеҲӨе®ҳгҒ®дәәдәӢгӮ„дәҲз®—й…ҚеҲҶгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжЁ©йҷҗгҒҢж”ҝжІ»зҡ„еҪұйҹҝдёӢгҒ«гҒӮгӮӢж©ҹй–ўгҒ«йӣҶдёӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҸёжі•гҒ®ж„ҸжҖқжұәе®ҡгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢеӨ–йғЁгҒӢгӮүгҒ®ең§еҠӣгҒ«жҷ’гҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®жЁ©йҷҗгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдёҖйҖЈгҒ®еӨүжӣҙгҒҜгҖҒеҸёжі•гҒ®зӢ¬з«ӢжҖ§гӮ’е·ЎгӮӢгӮҲгӮҠж·ұеҲ»гҒӘеӢ•еҗ‘гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ2013е№ҙгҒ®з¬¬еӣӣж¬ЎжҶІжі•ж”№жӯЈгҒҜгҖҒйҒҺеҺ»20е№ҙд»ҘдёҠгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®еҲӨдҫӢгӮ’з„ЎеҠ№еҢ–гҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҒжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒҢж–°гҒҹгҒӘжҶІжі•ж”№жӯЈгҒ®еҶ…е®№гӮ’е®ҹиіӘзҡ„гҒ«еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢжЁ©йҷҗгӮ’еүҘеҘӘгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒз«Ӣжі•еәңгҒҢжҶІжі•иЈҒеҲӨжүҖгҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ’еӣһйҒҝгҒ—гҖҒиҮӘгӮүгҒ®ж”ҝзӯ–гӮ’жҶІжі•гҒ®жқЎж–ҮгҒ«зӣҙжҺҘзӣӣгӮҠиҫјгӮҖйҒ“гӮ’й–ӢгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹеӢ•гҒҚгҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®ж”ҝжІ»еӢўеҠӣгҒҢеҸёжі•гҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜж©ҹиғҪгӮ’дҪ“зі»зҡ„гҒ«ејұгӮҒгҖҒеҸёжі•жЁ©гӮ’иҮӘгӮүгҒ®ж”Ҝй…ҚдёӢгҒ«зҪ®гҒ“гҒҶгҒЁгҒҷгӮӢй•·жңҹзҡ„гҒӘжҲҰз•ҘгҒ®дёҖз’°гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж”№йқ©гҒҜгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒҢеҠ зӣҹгҒҷгӮӢ欧е·һйҖЈеҗҲпјҲEUпјүгҒЁгҒ®ж‘©ж“ҰгӮ’з”ҹгҒҳгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮEUгҒҜгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®еӣҪеҶ…жі•гҒҢEUжі•гӮ„еӣҪйҡӣзҡ„гҒӘдәәжЁ©еҹәжә–гҒ«жә–жӢ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒеҺігҒ—гҒ„зӣЈиҰ–гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒEUгҒҜгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®гҖҢе…җз«Ҙдҝқиӯ·жі•гҖҚгҒҢLGBTIQ+гҒ®дәәгҖ…гҒ®еҹәжң¬зҡ„дәәжЁ©гӮ’дҫөе®ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ欧е·һеҸёжі•иЈҒеҲӨжүҖпјҲCJEUпјүгҒ«жҸҗиЁҙгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиІЎз”ЈжЁ©гҒ®дҫөе®ігӮ’зҗҶз”ұгҒ«гҖҒ欧е·һдәәжЁ©иЈҒеҲӨжүҖпјҲECtHRпјүгҒҢгғҸгғігӮ¬гғӘгғјж”ҝеәңгҒ«жҗҚе®іиі е„ҹгӮ’е‘ҪгҒҳгҒҹеҲӨдҫӢгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮиЁҖгҒ„ж–№гӮ’еӨүгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®еӣҪеҶ…жі•гҒҜгҖҒеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮжңҖзөӮзҡ„гҒӘиҰҸзҜ„гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒEUгҒЁгҒ„гҒҶи¶…еӣҪ家зҡ„ж©ҹй–ўгҒ«гӮҲгӮӢгғҒгӮ§гғғгӮҜгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁеҗҢгҒҳеӨ§йҷёжі•зі»гҒ®еҹәзӣӨгҒ«з«ӢгҒЎгҒӘгҒҢгӮүгӮӮгҖҒгҒқгҒ®йҒӢз”ЁгҒ«гҒҜзӢ¬зү№гҒ®иӨҮйӣ‘жҖ§гҒҢдјҙгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒиӯ°дјҡгҒҢж”ҝжІ»зҡ„гҒӘж„Ҹеҝ—гӮ’жі•зҡ„гҒ«еӣәе®ҡеҢ–гҒҷгӮӢжүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҖҢжһўиҰҒжі•гҖҚгҒ®еӯҳеңЁгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜгҒӘгҒ„жҰӮеҝөгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еҲ¶е®ҡгғ»ж”№жӯЈгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®жЁ©йҷҗгӮ„иЈҒеҲӨе®ҳгҒ®д»»е‘Ҫгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҸёжі•гҒ®ж №е№№гҒ«гҒҫгҒ§еҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—еҗҢжҷӮгҒ«гҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ§гҒӮгӮӢгӮҜгғјгғӘгӮўгҒҜгҖҒжі•зөұдёҖжұәе®ҡгӮ„ж–°гҒ—гҒ„еҲӨдҫӢгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒжі•еҫӢгҒ®и§ЈйҮҲгҒЁйҒ©з”ЁгҒ«еӢ•зҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬зЁҝгҒ§и©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ®жі•еӢҷз’°еўғгҒҜеӨҡеұӨзҡ„гҒ§гғҖгӮӨгғҠгғҹгғғгӮҜгҒӘжҖ§иіӘгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘиҰҒзҙ гӮ’жӯЈзўәгҒ«зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘжі•еӢҷжҲҰз•ҘгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгғҸгғігӮ¬гғӘгғјгҒ§гҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№гӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒӘиҰҒзҙ гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ«гғҶгӮҙгғӘгғј: ITгғ»гғҷгғігғҒгғЈгғјгҒ®дјҒжҘӯжі•еӢҷ
гӮҝгӮ°: гғҸгғігӮ¬гғӘгғјжө·еӨ–дәӢжҘӯ