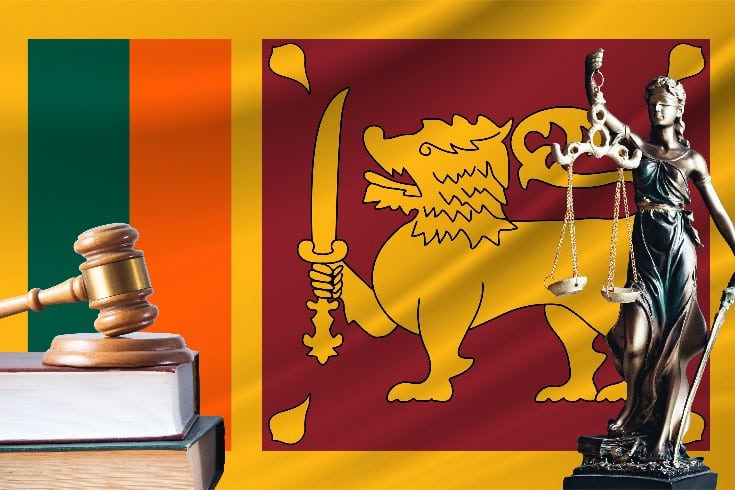キプロスの労働法を弁護士が解説

地中海東部に位置し、欧州連合(EU)の一員であるキプロスは、その地理的条件と有利な税制から、国際的なビジネス拠点として注目を集めています。しかし、その労働法は、英国統治時代に由来するコモン・ロー(判例法)の伝統と、EU指令に基づく労働者保護の枠組みが融合した、独特の構造を持っています。この二重の法的背景は、日本の法制度とは大きく異なる雇用慣行と思考様式を形成しており、特に従業員の解雇に関する規制は極めて厳格です。安易な解雇は法的に認められず、不当解雇と判断された場合には高額な金銭賠償を命じられるリスクを伴います。
本稿では、キプロスでの事業運営において特に重要となる労働法の主要分野について、具体的な法令や判例を基に、日本法との違いを明確にしながら専門的に解説します。まず、キプロス労働法の根幹をなすEU法とコモン・ローの関係性を概観し、次に、日本企業が最も注意を払うべき雇用契約の終了、すなわち解雇の正当事由、整理解雇の要件、そして不当解雇に関する司法判断の動向を深掘りします。さらに、EU労働時間指令に基づく労働時間、休憩、休暇の規制、2023年に導入された全国最低賃金制度、そして性別、年齢、人種などに基づく差別を広く禁じる平等雇用法制についても詳述します。これらの規制を遵守することは、法的なリスクを回避するだけでなく、現地での円滑な人材確保と定着、ひいては企業の持続的な成長に不可欠です。
この記事の目次
キプロス労働法の全体像
キプロスの労働法を理解する上で、その二つの主要な源流、すなわちEU法とコモン・ローを把握することが不可欠です。キプロスは2004年にEUに加盟して以来、労働者の権利を保護するためのEU指令を国内法として積極的に導入してきました。これにより、労働時間、健康と安全、均等待遇といった分野では、EU全体で標準化された高いレベルの規制が適用されています。例えば、「労働時間の組織化に関する法律(Organisation of Working Time Laws)」や「雇用及び職業における均等待遇法(Equal Treatment in Employment and Occupation Law)」などは、関連するEU指令を国内法化した典型例です。
一方で、キプロスは英国の旧植民地であった歴史的経緯から、法体系の根幹にコモン・ロー、すなわち判例法主義を採用しています。これは、成文法典を法解釈の第一義的な拠り所とする日本の大陸法(シビル・ロー)体系とは根本的に異なります。コモン・ローの国では、過去の裁判所の判決(判例)が、将来の同様の事件を拘束する法源としての効力を持ちます。したがって、キプロスの労働法を実務的に運用する上では、成文化された法律の条文を読むだけでは不十分であり、労働紛争裁判所(Industrial Disputes Tribunal)や最高裁判所(Supreme Court)がそれらの法律をどのように解釈し、適用してきたかを判例を通じて理解することが極めて重要となります。
このEU法とコモン・ローの二重構造は、キプロス労働法に独特の力学を生み出しています。EU指令が定める労働者保護という大きな原則が、コモン・ローの伝統に則った裁判所の解釈を通じて具体化されるのです。その結果、他のEU加盟国と共通の法規制を持ちながらも、その具体的な適用や救済措置のあり方においては、キプロス独自の司法判断が色濃く反映されることになります。日本企業が現地で労務管理を行う際には、EUレベルでの法改正動向を注視すると同時に、キプロス国内の裁判所の判例動向を継続的に把握するという、二元的なリーガルモニタリングが不可欠となるでしょう。
キプロスにおける雇用契約の成立と労働条件の明示
キプロスでは、雇用契約は口頭または書面のいずれでも有効に成立します。しかし、契約の形式に関わらず、雇用主には従業員に対して主要な労働条件を書面で明示する厳格な法的義務が課せられています。特に、EU指令を国内法化した「透明かつ予測可能な労働条件に関する法律(Law on Transparent and Predictable Working Conditions, Law 25(I)/2023)」に基づき、雇用主は雇用開始から7日以内に、当事者の情報、勤務地、職務内容、契約開始日、有期契約の場合はその期間、賃金、労働時間、年次有給休暇、解雇予告期間など、法律で定められた必須事項を記載した書面を従業員に提供しなければなりません。この義務を怠った場合、法的な紛争において雇用主に不利に働く可能性があるため、書面による労働条件の明示は必須の実務対応と言えます。
キプロス労働法において、日本企業が特に注目すべき制度の一つが試用期間(Probationary Period)です。標準的な試用期間は最長6ヶ月ですが、雇用契約締結時に書面で合意することにより、最大で104週間(2年)まで延長することが可能です。この試用期間中の解雇は、理由の提示や法律で定められた解雇予告期間の遵守が不要とされており、雇用主にとって比較的自由な裁量が認められています。
この非常に長い試用期間の設定可能性は、試用期間終了後の解雇が極めて困難であるというキプロス労働法の厳格さに対する、一種の均衡装置として機能しています。日本では試用期間が比較的短く、その期間中の解雇にも合理的な理由が求められることが多いのに対し、キプロスでは最長2年という期間が、雇用主にとって従業員の能力や適性を慎重に見極めるための戦略的なリスク管理期間として位置づけられています。
したがって、キプロスで従業員を雇用する際には、この試用期間を最大限に活用し、入社初日から体系的かつ客観的な記録に基づいたパフォーマンス管理を行うことが、将来の労務リスクを回避する上で極めて重要となります。この期間を過ぎると、後述する厳格な解雇法制の対象となるため、試用期間は単なる「お試し期間」ではなく、雇用関係を継続するか否かを判断するための決定的に重要な機会と捉えるべきです。
キプロスにおける従業員の解雇

キプロスにおける従業員の解雇は、日本の労働契約法が定める「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という解雇権濫用法理と比較して、さらに厳格な要件が課せられています。特に、解雇が法的に有効と認められるための理由が法律で限定的に列挙されており、そのいずれにも該当しない解雇は原則として不当解雇とみなされます。
解雇の正当事由
従業員の解雇を規律する基本法である「雇用終了法(Termination of Employment Law, Law 24 of 1967)」の第5条は、解雇が正当と認められる理由を以下の通り、網羅的かつ限定的に定めています。
- 従業員の満足のいく水準にない業務遂行(Unsatisfactory Performance):ただし、単にパフォーマンスが低いというだけでは不十分で、後述する適正な手続きを踏むことが裁判で要求されます。
- 整理解雇(Redundancy):事業の近代化、事業量の減少など、法律で定められた特定の経済的理由に基づく人員削減。
- 不可抗力(Force Majeure):戦争、天災など。
- 有期雇用契約の期間満了。
- 即時解雇を正当化する従業員の行為:職務中の重大な非行、雇用主の同意なき職務中の犯罪行為、雇用関係の継続を合理的に期待できなくさせるような行為などが含まれます。
これらのいずれかの理由に該当しない解雇は、すべて不当解雇(Unlawful Dismissal)となります。日本の解雇権濫用法理が「合理的理由」や「社会的相当性」といった比較的抽象的な要件を掲げ、裁判所が個別事案ごとに幅広い裁量で判断するのとは対照的に、キプロスではまずこの限定列挙された事由に該当するかどうかが厳密に問われます。
特に「満足のいく水準にない業務遂行」を理由とする解雇は、実務上、そのハードルが非常に高い点に注意が必要です。キプロスの裁判所は、判例を通じて、この理由で解雇する前に、雇用主が公正な手続きを踏むことを要求しています。具体的には、雇用主は、①従業員に対して業務遂行能力が低いことを具体的な事例を挙げて通知し、②期待される業務水準を明確に設定し、③改善のために合理的かつ十分な期間を与え、④必要に応じて追加のトレーニングやサポートを提供する、といった一連のプロセスを経なければなりません。これらの手続きを怠った場合、たとえ従業員のパフォーマンスが実際に低かったとしても、解雇は手続きの不備を理由に不当と判断されるリスクがあります。
不当解雇と救済措置
従業員が不当に解雇されたと主張する場合、その紛争は原則として労働紛争裁判所(IDT)で審理されます。不当解雇が認定された場合の主要な救済措置は、原職復帰(Reinstatement)ではなく、金銭による賠償です。これは、解雇紛争において原職復帰が比較的多く命じられる日本の司法判断とは大きく異なる点です。キプロスで原職復帰が命じられるのは、雇用主が20人以上の従業員を雇用しており、かつ解雇が悪意(in bad faith)に基づくものであると裁判所が判断した場合など、極めて例外的な状況に限られます。
賠償額には法律上の上限と下限が定められており、最大で従業員の2年分の給与、最小でもしその従業員が整理解雇されていた場合に受け取れたであろう補償額となります。裁判所は、従業員の勤続年数、給与、年齢、キャリア喪失の度合い、解雇の状況などを総合的に考慮して、この範囲内で具体的な賠償額を決定します。
近年の判例は、この賠償額算定における裁判所の裁量のあり方について重要な示唆を与えています。2025年1月30日に上訴裁判所が下した判決(Civil Appeals 311/2022 and 333/2022)は、その象徴的な事例です。この事件では、金融危機後の銀行の破綻処理過程で解雇された勤続25年のシニア幹部に対する解雇が不当と認定されました。しかし、裁判所は、銀行が破綻処理下にあったという特殊な状況や広範な経済的背景を「軽減要因」として考慮し、法定上限(2年分の給与)を大幅に下回る、上限額の約12.5%に相当する保守的な賠償額を命じました。この判決からは、解雇の違法性そのものは法律の要件に基づき厳格に判断される一方で、その結果として命じられる賠償額については、企業の置かれた経済的状況や公共の利益といった、より広い文脈が裁判所の裁量判断に影響を与えうるという、実務上極めて重要な傾向が読み取れます。
整理解雇(Redundancy)の要件と判例
事業の再編や経営状況の悪化に伴う人員削減、すなわち整理解雇は、雇用終了法で認められた正当な解雇理由の一つです。しかし、その認定には厳格な要件が課せられています。法律は、整理解雇が認められる具体的な状況として、事業所の閉鎖、事業の近代化・自動化による必要人員の削減、事業量の減少などを挙げています。
判例は、整理解雇の正当性を判断する上で、その理由が客観的かつ真実であることを雇用主が証明する必要がある、という立場を一貫してとっています。例えば、Dionas Georgios v. Cyprus Airways Ltd (2016) 1 A.A.D. 1235 事件において、最高裁判所は、整理解雇は雇用主の主観的な判断ではなく、企業の真のビジネス上の必要性から生じるものでなければならないと強調しました。また、Galatariotis Bros Ltd v. Grigora (2001) 1 A.A.D. 1985 事件では、解雇された従業員の職務を別の従業員が引き継いでいたことから、解雇は真の整理解雇ではなく、単なる従業員の入れ替えを目的とした偽装であるとして、その正当性が否定されました。一方で、Phileleftheros Public Co Ltd v. Giannoulas Christou (2017) 事件では、たとえ一人しかいない部署であっても、その廃止が真の組織再編の一環であれば、有効な整理解雇理由となりうることが認められています。
手続き面では、雇用主は整理解雇を意図する場合、解雇予定日の少なくとも1ヶ月前までに、影響を受ける従業員の数や氏名、解雇理由などを記載した書面を労働省に届け出る義務があります。さらに、一定規模以上の人員削減(例えば、従業員21人から99人の事業所で10人以上を30日以内に解雇する場合)は「集団的解雇(Collective Redundancies)」と見なされ、解雇回避の可能性などを協議するため、従業員代表との事前協議が義務付けられます。
キプロスの特徴的な制度として、整理解雇された従業員への補償金が、原則として雇用主ではなく「整理解雇基金(Redundancy Fund)」という政府管轄の基金から支払われる点が挙げられます。この基金は、全雇用主からの拠出金によって賄われており、企業の倒産等により雇用主が支払い不能な状況であっても、従業員の権利が保護される仕組みとなっています。勤続104週(2年)以上の従業員がこの基金からの支払い対象となります。
キプロスの労働時間、休憩、休暇制度
キプロスの労働時間、休憩、休暇に関する規制は、主にEUの労働時間指令を国内法化した「労働時間の組織化に関する法律(Organisation of Working Time Laws of 2002 and 2007)」によって定められています。これらの規制は、労働者の健康と安全を保護することを目的としており、日本企業にとっては、日本の労働基準法や「36協定」の運用とは異なる厳格なルールとして理解する必要があります。
主要な規定は以下の通りです。
- 最大労働時間:1週間の労働時間は、時間外労働を含めて平均48時間を超えてはなりません。この「平均」は、通常4ヶ月の参照期間にわたって計算されます。これは、特定の週に48時間を超えて働くことがあっても、4ヶ月間の平均が48時間以内に収まっていればよいという考え方ですが、無制限の時間外労働を許容するものではありません。
- 休息期間:従業員は、24時間ごとに最低連続11時間の「日次休息(daily rest)」と、1週間ごとに最低連続24時間の「週次休息(weekly rest)」を取得する権利を有します。
- 休憩:1日の労働時間が6時間を超える場合、従業員は少なくとも15分から30分の休憩を取得する権利があります。
- 年次有給休暇:5日勤務制の従業員は最低20日、6日勤務制の従業員は最低24日の年次有給休暇を取得する権利があります。
日本の経営者にとって極めて重要なのは、これらの労働時間規制の適用除外に関する規定です。法律は、自身の労働時間を計算・決定できない、または従業員自身が決定できるカテゴリーの労働者を適用除外としています。具体的には、「管理職(managing executives)」や特定の専門職などがこれに該当するとされています。日本の労働基準法における「管理監督者」の概念と類似していますが、その判断基準は現地の法律と判例に基づいて慎重に行われなければなりません。単に役職名が「マネージャー」であるというだけでは適用除外とは認められず、職務内容、権限、待遇の実態から、真に経営と一体的な立場にあるかどうかが問われます。従業員を安易に適用除外の管理職として扱い、時間外労働手当の支払いを怠った場合、後に労働紛争に発展し、多額の未払い賃金の支払いを命じられるリスクがあるため、専門家のアドバイスを基に慎重な判断が求められます。
キプロスの賃金制度と全国最低賃金
キプロスの賃金制度において、最も重要な近年の動向は、2023年1月1日に全国的な法定最低賃金制度が導入されたことです。これは、閣僚評議会令(Decree KDP 350/2022)によって定められ、それまで特定の職種にのみ適用されていた最低賃金制度から、ほぼすべての労働者を対象とする制度へと大きく転換したものです。
2024年1月1日時点での全国最低賃金は、月額で以下のように設定されています。
- 同一の雇用主の下での雇用開始から最初の6ヶ月間:月額900ユーロ
- 6ヶ月の継続雇用後:月額1,000ユーロ
この制度は、パートタイム労働者にも比例して適用されます。この最低賃金額は、キプロスの生活水準や経済状況を考慮して、原則として2年ごとに見直されることになっています。
ただし、この全国最低賃金制度にはいくつかの適用除外があります。家事労働者、農業・畜産労働者、そして海運業に従事する労働者は対象外とされており、これらの職種の賃金は、個別の雇用契約や別途の法令、労働協約によって定められます。
この制度の根拠法は「最低賃金法(Minimum Wages Act, Chapter 183)」です。最低賃金を下回る賃金を支払った雇用主には罰金が科される可能性があり、従業員は差額の支払いを請求する権利を有します。
また、キプロスの雇用慣行として特筆すべき点に、13ヶ月目の給与(13th salary)の支払いがあります。これは法律で義務付けられているものではありませんが、多くの企業で慣行として定着しており、通常は12月に支払われます。労働協約や個別の雇用契約で支払いが定められている場合、または長年の慣行となっている場合には、法的に支払い義務が生じるため注意が必要です。キプロスで事業を行う際には、この全国最低賃金制度の遵守はもちろんのこと、こうした現地の慣行も踏まえた上で、競争力のある報酬体系を設計することが重要となります。
キプロスにおける差別の禁止
キプロスは、EU指令の国内法化を通じて、雇用におけるあらゆる段階での差別を禁止する強固な法的枠組みを構築しています。その中核をなすのが、「雇用及び職業における均等待遇法(Equal Treatment in Employment and Occupation Law)」や「雇用及び職業訓練における男女の均等待遇に関する法律(Equal Treatment of Men and Women in Employment and Vocational Training Law)」といった一連の法律です。
これらの法律は、非常に広範な属性を理由とする差別を禁止しています。保護される特性(Protected Characteristics)には、性別(妊娠・出産を含む)、人種または民族的出身、宗教または信条、年齢、障がい、性的指向、さらにはパートタイム労働者や有期契約労働者であることといった雇用形態も含まれます。この保護は、募集・採用から昇進、賃金、研修、そして解雇に至るまで、雇用関係の全側面に及びます。日本法と比較しても、保護対象となる属性がより広く、明確に規定されている点が特徴です。
特に、雇用主の責任範囲を理解する上で、近年の最高裁判所の判例は重要な指針となります。2022年3月、最高裁判所は、職場におけるセクシャルハラスメントに関する判断を下しました。この事件で裁判所は、ハラスメント行為が従業員間で行われたものであっても、雇用主がその行為を停止させ、再発を防止するための「合理的かつ効果的な措置」を講じることを怠った場合、雇用主も共同で法的責任を負うとの判断を示しました。
この判決が持つ意味は重大です。これは、雇用主の責任が、自らの直接的な差別行為だけでなく、職場環境全体を安全かつハラスメントのない状態に維持するという、より積極的な義務にまで及ぶことを明確にしたものです。単に問題が発生した後に対応するだけでは不十分であり、雇用主には、差別やハラスメントを未然に防ぐための体制を構築する責任がある、ということです。したがって、キプロスに進出する日本企業は、コンプライアンス体制の一環として、
- 明確なアンチハラスメント方針の策定と全従業員への周知
- 定期的な研修の実施
- 従業員が安心して相談・申告できる実効性のある窓口の設置
- 申告があった場合に公正かつ迅速な調査を行うためのプロセスの確立
といった予防的措置を積極的に講じることが、法的なリスクを管理する上で不可欠となります。
まとめ
本稿では、キプロス共和国の労働法について、日本企業が現地で事業を展開する上で特に留意すべき点を中心に解説しました。キプロスの労働法制は、EU指令に基づく高い労働者保護基準と、判例が重要な法源となるコモン・ローの伝統が融合した複雑な体系を有しています。
まず、従業員の解雇は法律で限定列挙された正当事由のいずれかに該当しなければならず、能力不足を理由とする場合でも、警告や改善機会の付与といった厳格な手続きが判例上要求されます。安易な解雇は不当と判断され、救済措置は原職復帰ではなく金銭賠償が原則ですが、その額は最大で2年分の給与に達する可能性があります。
次に、労働時間や差別禁止といった分野では、EU基準が直接適用される点です。週平均48時間という労働時間の上限や、性別、年齢、人種など広範な理由に基づく差別禁止規定は、日本の制度よりも厳格に運用される場面が多く、特にハラスメント防止に関しては、雇用主に積極的な職場環境配慮義務が課せられていることを近年の判例が示しています。
そして、法解釈における判例の重要性です。成文法だけでなく、労働紛争裁判所や最高裁判所が下した判決が、法律の具体的な適用基準を形成しています。したがって、法改正の動向を追うだけでなく、最新の判例を常に把握しておくことが、実務上のリスク管理において不可欠です。
キプロスでの労務管理においては、日本での常識や慣行をそのまま持ち込むのではなく、現地の法制度と司法判断の動向を正確に理解し、それに基づいた就業規則の整備、雇用契約書の作成、そして日々の労務対応を行うことが重要です。
カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務