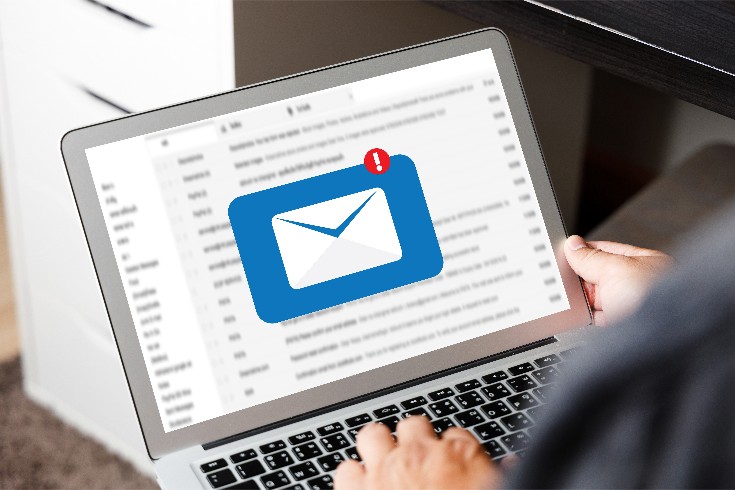тљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ«ТюЅті╣ТђДсЂФжќбсЂЎсѓІУБЂтѕцСЙІсЃ╗С║ІСЙІсЂесЂ»

ті┤тЃЇтЦЉу┤ёсЂФсЂісЂёсЂдсЂ»сђЂті┤тЃЇУђЁсЂ«ті┤тЃЇуЙЕтІЎсЂеСй┐ућеУђЁсЂ«У│ЃжЄЉТћ»ТЅЋуЙЕтІЎсЂесЂёсЂєтЪ║ТюгуџёсЂфуЙЕтІЎсЂ«сЂ╗сЂІсЂФсђЂС╗ўжџЈуџёсЂфуЙЕтІЎсѓѓуЎ║ућЪсЂЌсЂЙсЂЎсЂїсђЂсЂЊсЂ«С╗ўжџЈуЙЕтІЎсЂ«СИђсЂцсЂесЂЌсЂдсђЂСИАУђЁсЂ»С║њсЂёсЂФсђЂсђїуЏИТЅІТќ╣сЂ«ТГБтйЊсЂфтѕЕуЏісѓњСИЇтйЊсЂФСЙхт«│сЂЌсЂфсЂёсѓѕсЂєжЁЇТЁ«сЂЎсѓІуЙЕтІЎсђЇ№╝ѕті┤тЃЇУђЁсЂФсЂесЂБсЂдсЂ»Уфат«ЪуЙЕтІЎсђЂСй┐ућеУђЁсЂФсЂесЂБсЂдсЂ»жЁЇТЁ«уЙЕтІЎ№╝ЅсѓњС┐АуЙЕтЅЄСИіУ▓асЂєсѓѓсЂ«сЂеУДБсЂЋсѓїсЂЙсЂЎ№╝ѕті┤тЃЇтЦЉу┤ёТ│Ћугг№╝ЊТЮАугг№╝ћжаЁ№╝Ѕсђѓ Сй┐ућеУђЁсЂїУ▓асЂєсЂ╣сЂЇУфат«ЪуЙЕтІЎсЂФсЂ»т«ЅтЁежЁЇТЁ«уЙЕтІЎсђЂтЂЦт║ижЁЇТЁ«уЙЕтІЎсЂїсЂѓсѓісђЂті┤тЃЇУђЁсЂїУ▓асЂєсЂ╣сЂЇУфат«ЪуЙЕтІЎсЂФсЂ»сђЂСй┐ућеУђЁсЂ«С┐АућесЃ╗тљЇУфЅсѓњТ»ђТљЇсЂЌсЂфсЂёуЙЕтІЎсђЂС║їжЄЇт░▒ТЦГудЂТГбуЙЕтІЎсђЂуДўт»єС┐ЮТїЂуЙЕтІЎсђЂтљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбуЙЕтІЎ№╝ѕуФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎ№╝ЅсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЂфсЂісђЂуДўт»єС┐ЮТїЂуЙЕтІЎсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»тйЊсѓхсѓцсЃѕсЂ«тѕЦУеўС║ІсЂДУЕ│сЂЌсЂЈУДБУфгсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЊсЂ«УеўС║ІсЂ«уЏ«ТгА
тљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ«ТюЅті╣ТђДсЂ«тѕцТќГ
тЙЊТЦГтЊАсЂ«уФХТЦГУАїуѓ║сЂФсѓѕсѓіС╝џуцЙсЂ«жЄЇУдЂсЂфсЃјсѓдсЃЈсѓдуГЅсЂїтцќжЃесЂФТхЂтЄ║сЂЌсЂдсЂЌсЂЙсЂєтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓІсЂ«сЂДсђЂжЏЄућетЦЉу┤ёТЏИуГЅсЂФсЂісЂёсЂдтљїТЦГС╗ќуцЙсЂИсЂ«У╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсѓњТўјуб║сЂФУдЈт«џсЂЌсЂдсЂісЂЈсЂЊсЂесЂїт┐ЁУдЂсЂДсЂЎсЂїсђЂсЂЮсЂєсЂЌсЂдсЂісЂёсЂЪсЂесЂЌсЂдсѓѓсђЂті┤тЃЇУђЁсЂ«УЂиТЦГжЂИТіъсЂ«УЄфућ▒№╝ѕТє▓Т│Ћ22ТЮА1жаЁ№╝ЅсЂесЂ«жќбС┐ѓсЂІсѓЅсђЂтИИсЂФсЂЮсЂ«ТюЅті╣ТђДсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓтљїТЦГС╗ќуцЙсЂИсЂ«У╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ»сђЂсЂЮсЂ«тѕХжЎљсЂїсЂѓсЂЙсѓісЂФт╝ит║дсЂДсЂѓсѓІсЂесђЂтЁгт║ЈУЅ»С┐ЌсЂФтЈЇсЂЎсѓІ№╝ѕТ░ЉТ│Ћугг90ТЮА№╝ЅсЂесЂЌсЂдсђЂуёАті╣сЂетѕцТќГсЂЋсѓїсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЂЮсЂЊсЂДсђЂсЂЕсЂ«сѓѕсЂєсЂфтєЁт«╣сЂДсЂѓсѓїсЂ░сђЂТюЅті╣сЂетѕцТќГсЂЋсѓїсѓІсЂІсѓњТёЈУГўсЂЌсЂдсђЂжЏЄућетЦЉу┤ёсЂФсЂісЂёсЂдтљїТЦГС╗ќуцЙсЂИсЂ«У╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсѓњУдЈт«џсЂЎсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
ухїТИѕућБТЦГуюЂсЂ»сђЂсђїуФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎтЦЉу┤ёсЂ«ТюЅті╣ТђДсЂФсЂцсЂёсЂдсђЇ№╝ѕухїТИѕућБТЦГуюЂтЈѓУђЃУ│ЄТќЎ№╝Ћ№╝ЅсЂФсЂісЂёсЂдсђЂтѕцСЙІСИісђЂтљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ«ТюЅті╣ТђДсѓњтѕцТќГсЂЎсѓІжџЏсЂ«сЃЮсѓцсЃ│сЃѕсѓњсђЂ
- т«ѕсѓІсЂ╣сЂЇС╝ЂТЦГсЂ«тѕЕуЏісЂїсЂѓсѓІсЂІсЂЕсЂєсЂІРєњ1.сѓњУИЈсЂЙсЂѕсЂцсЂцсђЂуФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎтЦЉу┤ёсЂ«тєЁт«╣сЂїуЏ«уџёсЂФуЁДсѓЅсЂЌсЂдтљѕуљєуџёсЂфу»ётЏ▓сЂФуЋЎсЂЙсЂБсЂдсЂёсѓІсЂІсЂесЂёсЂєУд│уѓ╣сЂІсѓЅсђЂ
- тЙЊТЦГтЊАсЂ«тю░СйЇ
- тю░тЪЪуџёсЂфжЎљт«џсЂїсЂѓсѓІсЂІ
- уФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎсЂ«тГўуХџТюЪжќЊсЂФсЂцсЂёсЂдт┐ЁУдЂсЂфтѕХжЎљсЂїТјЏсЂЉсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІсЂІ
- удЂТГбсЂЋсѓїсѓІуФХТЦГУАїуѓ║сЂ«у»ётЏ▓сЂФсЂцсЂёсЂдт┐ЁУдЂсЂфтѕХжЎљсЂїТјЏсЂЉсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІсЂІ
- С╗БтёЪТјфуй«сЂїУгЏсЂўсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІсЂІ
сЂесђЂТЋ┤уљєсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсЂ«уѓ╣сЂФжќбсЂЌсЂдсЂ»сђЂСИІУеўУеўС║ІсЂФсЂдУЕ│у┤░сЂФУДБУфгсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
уФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎтЦЉу┤ёсЂ«ТюЅті╣ТђДсЂїС║ЅсѓЈсѓїсЂЪУБЂтѕцСЙІсЂФсЂісЂёсЂдсЂ»сђЂсЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂфтцџжЮбуџёсЂфУд│уѓ╣сЂІсѓЅтЦЉу┤ёуиаухљсЂ«тљѕуљєТђДсѓётЦЉу┤ётєЁт«╣сЂ«тдЦтйЊТђДуГЅсЂїтѕцТќГсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсЂїсђЂтѕцСЙІсЂФсЂісЂЉсѓІтѕцТќГсЂ«сЃЮсѓцсЃ│сЃѕсЂФсЂцсЂёсЂдуљєУДБсЂЌсЂдсЂісЂЈсЂЊсЂесЂ»сђЂтљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ«т░јтЁЦсЃ╗УдІуЏ┤сЂЌсѓњТцюУејсЂЎсѓІСИісЂДжЄЇУдЂсЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
тљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ«ТюЅті╣ТђДсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂІсЂБсЂЪта┤тљѕ

сЂДсЂ»сђЂт«ЪжџЏсЂФсЂ»сЂЕсЂ«сѓѕсЂєсЂфта┤тљѕсЂФтљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ«ТюЅті╣ТђДсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂІсЂБсЂЪсЂ«сЂІсѓњсђЂсЂЊсЂ«6сЂцсЂ«сЃЮсѓцсЃ│сЃѕсЂФсЂцсЂЇсђЂУдІсЂдсЂ┐сѓІсЂЊсЂесЂесЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сђїт«ѕсѓІсЂ╣сЂЇС╝ЂТЦГсЂ«тѕЕуЏісЂїсЂѓсѓІсЂІсЂЕсЂєсЂІсђЇсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂІсЂБсЂЪС║ІСЙІ
С╗ЋтЁЦтЁѕсЂІсѓЅт╗ЃсЃЌсЃЕсѓ╣сЃЂсЃЃсѓ»уГЅсѓњС╗ЋтЁЦсѓїсђЂсЂЊсѓїсѓњтиЦта┤сЂДу▓ЅуаЋсЂЎсѓІсЂфсЂЕсЂЌсЂдТхитцќсЂФУ╝ИтЄ║сЂЎсѓІсЂ«сѓњТЦГсЂесЂЎсѓІС╝џуцЙсЂїсђЂтјЪтЉітЙЊТЦГтЊАсЂДсЂѓсЂБсЂЪ№╝╣1сђЂ№╝╣2сђЂ№╝╣3сЂетй╝сѓЅсѓњТќ░УдЈсЂФжЏЄућесЂЌсЂЪС╝џуцЙсѓњуДўт»єС┐ЮТїЂуЙЕтІЎжЂЋтЈЇсђЂуФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎжЂЋтЈЇуГЅсЂФтйЊсЂЪсѓІсЂесЂЌсЂдсђЂСИЇТ│ЋУАїуѓ║сЂфсЂёсЂЌжЏЄућетЦЉу┤ёСИісЂ«тѓхтІЎСИЇт▒ЦУАїсЂФтЪ║сЂЦсЂЈТљЇт«│У│атёЪсѓњУФІТ▒ѓсЂЌсЂЪС║ІСЙІсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
тјЪтЉіС╝џуцЙсЂ«т░▒ТЦГУдЈтЅЄсЂФсЂ»сђЂсђїуцЙтЊАсЂ»сђЂжђђУЂитЙїсѓѓС╝џуцЙсђЂжАДт«бтЈісЂ│тЈќт╝ЋтЁѕуГЅсЂ«ТЕЪт»єС║ІжаЁтЈісЂ│ТЦГтІЎСИіуЪЦсѓітЙЌсЂЪТЃЁта▒сђЂсЃјсѓдсЃЈсѓдуГЅсѓњС╗ќсЂФТ┤ЕсѓЅсЂЌсЂдсЂ»сЂфсѓЅсЂфсЂёсђЇсЂесЂѓсѓісђЂсЂЙсЂЪсђЂсђїС╝џуцЙсЂ«ТЕЪт»є№╝ѕтќХТЦГсЃјсѓдсЃЈсѓдсђЂжАДт«бТЃЁта▒уГЅсѓњтљФсѓђсђѓ№╝ЅсЂФжќбсѓЈсЂБсЂЪуцЙтЊАсЂ»сђЂжђђУЂитЙї№╝Њт╣┤жќЊсЂ»сЂЮсЂ«ТЕЪт»єсѓњтѕЕућесЂЌсЂдсђЂтљїТЦГС╗ќуцЙсЂФУ╗бУЂисЂЌсђЂтЈѕсЂ»тљїТЦГуе«сЂ«С║ІТЦГсѓњтќХсѓЊсЂДсЂ»сЂфсѓЅсЂфсЂёсђЇсЂесЂёсЂєУдЈт«џсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
тјЪтЉіС╝џуцЙсЂ»3тљЇсЂїт«бтЁѕсЂћсЂесЂ«тЈќт╝ЋсЂ«уе«жАъсђЂС╗ЋтЁЦжЄЈсђЂСЙАТа╝сЂесЂёсЂБсЂЪтќХТЦГСИісЂ«жЄЇУдЂсЂфТЃЁта▒сѓњУ╗бУЂитЁѕсЂДућесЂёсЂЪсЂеСИ╗т╝хсЂЌсЂЪсЂ«сЂДсЂЎсЂїсђЂУБЂтѕцТЅђсЂ»сђЂсЂЊсѓїсѓЅсЂ»тќХТЦГуДўт»єсЂесЂЌсЂдС┐ЮУГисЂЋсѓїсЂдсЂёсЂфсЂІсЂБсЂЪсЂесЂЌсЂдС╝ЂТЦГуДўт»єсЂ«СИЇТГБтѕЕућесѓњтљдт«џсЂЌсЂЪСИісЂДсђЂ
т░▒ТЦГУдЈтЅЄсЂ«уФХТЦГжЂ┐ТГбТЮАжаЁсѓётљѕТёЈсЂФсѓѕсѓІуФХТЦГжЂ┐ТГбуЅ╣у┤ёсЂїТюЅті╣сЂеУфЇсѓЂсѓЅсѓїсѓІсЂЪсѓЂсЂФсЂ»сђЂСй┐ућеУђЁсЂїуб║С┐ЮсЂЌсѓѕсЂєсЂесЂЎсѓІтѕЕуЏісЂФуЁДсѓЅсЂЌсЂдсђЂуФХТЦГудЂТГбсЂ«тєЁт«╣сЂїт┐ЁУдЂТюђт░ЈжЎљт║дсЂФТГбсЂЙсЂБсЂдсЂісѓісђЂсЂІсЂцсђЂтЇЂтѕєсЂфС╗БтёЪТјфуй«сЂїТќйсЂЋсѓїсѓІсЂЊсЂесЂїт┐ЁУдЂсЂДсЂѓсѓІсЂеУДБсЂЋсѓїсѓІсђѓсЂЮсЂЌсЂдсђЂсЂЮсЂ«сѓѕсЂєсЂфТЮАС╗ХсѓњТ║ђсЂЪсЂЋсЂфсЂёта┤тљѕсЂФсЂ»сђЂСИіУеўТЮАжаЁсЂфсЂёсЂЌуЅ╣у┤ёсЂ»сђЂті┤тЃЇУђЁсЂ«ТеЕтѕЕсѓњСИђТќ╣уџёсЂІсЂцСИЇтйЊсЂФтѕХу┤ёсЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂДтЁгт║ЈУЅ»С┐ЌсЂФтЈЇсЂЎсѓІсЂесЂЌсЂдсђЂТ░ЉТ│Ћ90ТЮАсЂФсѓѕсѓіуёАті╣сЂесЂфсѓІсЂеУДБсЂЋсѓїсѓІсђѓ
ТЮ▒С║гтю░Тќ╣УБЂтѕцТЅђ2012т╣┤3Тюѕ13ТЌЦтѕцТ▒║
сЂЌсЂІсѓІсЂФсђЂТюгС╗ХсЂФсЂісЂёсЂдсЂ»сђЂУбФтЉі№╝╣2сѓЅсЂ»сђЂтЅЇУеў(1)сЂДУфЇт«џсЂЌсЂЪсЂесЂісѓісђЂтјЪтЉісЂДсЂ«ТЦГтІЎжЂѓУАїжЂјуеІсЂФсЂісЂёсЂдсђЂТЦГтІЎСИісЂ«уДўт»єсѓњСй┐ућесЂЎсѓІуФІта┤сЂФсЂѓсЂБсЂЪсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂфсЂёсЂІсѓЅсђЂсЂЮсѓѓсЂЮсѓѓуФХТЦГсѓњудЂсЂџсЂ╣сЂЇтЅЇТЈљТЮАС╗ХсѓњТгасЂЈсѓѓсЂ«сЂДсЂѓсѓІсЂЌсђЂтјЪтЉісЂ»сђЂУбФтЉі№╝╣2сѓЅсЂФт»ЙсЂЌсђЂСйЋсѓЅсЂ«С╗БтёЪТјфуй«сѓѓУгЏсЂўсЂдсЂёсЂфсЂёсЂ«сЂДсЂѓсѓІсЂІсѓЅсђЂСИіУеўуФХТЦГжЂ┐ТГбТЮАжаЁсЂфсЂёсЂЌуЅ╣у┤ёсЂ»сђЂТ░ЉТ│Ћ90ТЮАсЂФсѓѕсѓіуёАті╣сЂеУфЇсѓЂсЂќсѓІсѓњтЙЌсЂфсЂёсђѓ
сЂесђЂсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
сЂѓсѓЅсѓєсѓІуцЙтЊАсЂФтљїТЦГС╗ќуцЙсЂИсЂ«У╗бУЂиудЂТГбсѓњТ▒ѓсѓЂсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсѓІсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсЂЌсђЂТЦГтІЎСИісЂ«уДўт»єсѓёсђЂсЂЮсѓїсЂФУЄ│сѓЅсЂфсЂёта┤тљѕсЂДсѓѓуЅ╣Т«ісЂфсЃјсѓдсЃЈсѓдсѓёТЃЁта▒сЂфсЂЕсђЂсђїт«ѕсѓІсЂ╣сЂЇС╝ЂТЦГсЂ«тѕЕуЏісЂїсЂѓсѓІсЂІсЂЕсЂєсЂІсђЇсЂїтљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ«ТюЅті╣ТђДсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсѓІсЂІтљдсЂІсЂ«сђЂТюђтцДсЂ«сЃЮсѓцсЃ│сЃѕсЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сђїтЙЊТЦГтЊАсЂ«тю░СйЇсђЇсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂІсЂБсЂЪС║ІСЙІ
УЂиТЦГт«Ѕт«џТ│ЋсЂФтЪ║сЂЦсЂЈТюЅТќЎУЂиТЦГу┤╣С╗ІТЦГуГЅсѓњтќХсЂ┐сђЂтї╗уЎѓтЙЊС║ІУђЁсѓњт»ЙУ▒АсЂесЂЌсЂдуЌЁжЎбуГЅсЂ«УЂиТЦГТќАТЌІсѓњсЂЌсЂдсЂёсѓІтјЪтЉіС╝џуцЙсЂїсђЂт░▒ті┤сЂЌсЂдсЂёсЂЪтЁЃтЙЊТЦГтЊАсЂїтљїТЦГ№╝АуцЙсЂФУ╗бУЂисЂЌсђЂтјЪтЉісЂФуЎ╗жї▓сЂЌсЂдсЂёсѓІтї╗уЎѓтЙЊС║ІУђЁсЂ«ТЃЁта▒сѓњТїЂсЂАтЄ║сЂЌсЂдтѕЕућесЂЌсђЂсЂЊсѓїсЂФсѓѕсѓітјЪтЉісЂФуЎ╗жї▓сЂЌсЂдсЂёсЂЪтї╗тИФсѓњтѕЦсЂ«тї╗уЎѓТ│ЋС║║сЂФт░▒УЂиТќАТЌІсЂЌсЂЪсЂесЂЌсЂдсђЂуФХТЦГудЂТГбуГЅсЂФжЂЋтЈЇсЂЌсЂЪсЂЊсЂесЂФсѓѕсѓІТљЇт«│У│атёЪсѓњтЁЃтЙЊТЦГтЊАсЂФУФІТ▒ѓсЂЌсЂЪС║ІСЙІсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
УБЂтѕцТЅђсЂ»сђЂтї╗уЎѓтЙЊС║ІУђЁсѓњт»ЙУ▒АсЂФуЌЁжЎбуГЅсЂ«т░▒УЂиТќАТЌІсѓњсЂЎсѓІС║ІТЦГУђЁсЂ»тјЪтЉісѓё№╝АуцЙС╗ЦтцќсЂФсѓѓУцЄТЋ░сЂѓсѓісђЂсЂЊсѓїсѓЅсЂ«С║ІТЦГУђЁсЂ»сђЂсѓцсЃ│сѓ┐сЃ╝сЃЇсЃЃсЃѕСИісЂФтї╗уЎѓтЙЊС║ІУђЁтљЉсЂЉсЂ«уЎ╗жї▓сЃЋсѓЕсЃ╝сЃъсЃЃсЃѕсѓњУеГуй«сЂЎсѓІсЂфсЂЕсЂЌсЂдУ╗бУЂитИїТюЏУђЁуГЅсѓњтІЪсЂБсЂдсЂісѓісђЂУцЄТЋ░сЂ«С║ІТЦГУђЁсЂФжЄЇУцЄсЂЌсЂдуЎ╗жї▓сЂЎсѓІтї╗уЎѓтЙЊС║ІУђЁсѓѓтцџТЋ░сЂёсѓІсЂЊсЂесЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсѓІсЂесЂЌсЂдсђЂУбФтЉісЂ«ТќАТЌІУАїуѓ║сѓњУфЇсѓЂсЂџсђЂ
ТюгС╗ХсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ┐сѓІсЂесђЂУбФтЉісЂ»сЂёсѓЈсѓєсѓІт╣│уцЙтЊАсЂФсЂЎсЂјсЂфсЂёсЂєсЂѕсђЂтјЪтЉісЂИсЂ«тюеу▒ЇТюЪжќЊсѓѓу┤ё1т╣┤сЂФсЂЎсЂјсЂфсЂёсђѓС╗ќТќ╣сђЂуФХТЦГудЂТГбуЙЕтІЎсѓњУ▓асЂєу»ётЏ▓сЂ»сђЂжђђУЂисЂ«ТЌЦсЂІсѓЅ3т╣┤сЂФсѓЈсЂЪсЂБсЂдуФХТЦГжќбС┐ѓсЂФуФІсЂцС║ІТЦГУђЁсЂИсЂ«т░▒УЂиуГЅсѓњудЂТГбсЂЎсѓІсЂесЂёсЂєсѓѓсЂ«сЂДсЂѓсѓісђЂСйЋсѓЅсЂ«тю░тЪЪтѕХжЎљсѓѓС╗ўсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂфсЂёсЂІсѓЅсђЂуЏИтйЊуеІт║дсЂФт║Ѓу»ёсЂесЂёсѓЈсЂќсѓІсѓњтЙЌсЂфсЂёсђѓ
тцДжўфтю░Тќ╣УБЂтѕцТЅђ2016т╣┤7Тюѕ14ТЌЦтѕцТ▒║
сЂесЂЌсЂдсђЂсђїТюгС╗ХУфЊу┤ёТЏИсЂФсѓѕсѓІуФХТЦГудЂТГбсЂ«у»ётЏ▓сЂ»тљѕуљєуџёсЂфу»ётЏ▓сЂФсЂесЂЕсЂЙсѓІсѓѓсЂ«сЂесЂ»сЂёсЂѕсЂфсЂёсЂІсѓЅсђЂтЁгт║ЈУЅ»С┐ЌсЂФтЈЇсЂЌуёАті╣сЂДсЂѓсѓісђЂуФХТЦГудЂТГбсЂ«тљѕТёЈсЂФтЪ║сЂЦсЂЈУФІТ▒ѓсЂ»уљєућ▒сЂїсЂфсЂёсђЇсЂесЂЌсЂдсђЂУФІТ▒ѓсѓњТБётЇ┤сЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
С╝ЂТЦГуДўт»єсѓёуЅ╣Т«ісЂфсЃјсѓдсЃЈсѓдсЂфсЂЕсЂФТјЦсЂЎсѓІТЕЪС╝џсЂ«сЂфсЂёт╣│уцЙтЊАсЂФсЂЙсЂДтљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбсѓњТ▒ѓсѓЂсѓІсЂ«сЂ»сђЂуёАуљєсЂфта┤тљѕсЂїтцџсЂёсЂесЂёсЂѕсѓІсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓтюеУЂиСИГсЂ«тю░СйЇсЂФуЁДсѓЅсЂЌсђЂУ╗бУЂисѓњудЂТГбсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂФтљѕуљєТђДсЂїсЂѓсѓІсЂеУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂёсЂесЂЇсЂ»сђЂтЁгт║ЈУЅ»С┐ЌсЂФтЈЇсЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂесЂЌсЂдТюЅті╣ТђДсЂїтљдт«џсЂЋсѓїсѓІсЂЊсЂесЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сђїтю░тЪЪуџёсЂфжЎљт«џсЂїсЂѓсѓІсЂІсђЇсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂІсЂБсЂЪС║ІСЙІ
тЁЃтЙЊТЦГтЊАсЂДсЂѓсѓІУбФтЉісЂїжђђУЂиуЏ┤тЙїсЂФуФХТЦГС╗ќуцЙсЂФт░▒УЂисЂЌсЂЪсЂЊсЂесЂ»жђђУЂижЄЉСИЇТћ»ухдС║Іућ▒сЂФУЕ▓тйЊсЂЎсѓІсЂеСИ╗т╝хсЂЎсѓІтјЪтЉісЂїсђЂТћ»ТЅЋТИѕсЂ┐сЂ«жђђУЂижЄЉсЂФсЂцсЂЇСИЇтйЊтѕЕтЙЌсЂФтЪ║сЂЦсЂЈУ┐ћжѓёУФІТ▒ѓсѓњсЂЌсЂЪС║ІСЙІсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
тјЪтЉіС╝џуцЙсЂ»уЕ║Т░ЌУф┐тњїтѕХтЙАТЕЪтЎесЃ╗уЄЃуё╝т«ЅтЁеУЄфтІЋтѕХтЙАТЕЪтЎесЂ«УеѕУБЁтиЦС║ІсђЂС┐Ют«ѕтЈісЂ│сЃЊсЃФу«АуљєТЦГуГЅсѓњТЦГсЂесЂЎсѓІТафт╝ЈС╝џуцЙсЂДсЂѓсѓісђЂУбФтЉісЂ»тјЪтЉіС╝џуцЙсѓњжђђУЂитЙїсђЂтјЪтЉіС╝џуцЙсЂ«тЁЃтЈќуиатй╣сЂїжАДтЋЈсЂесЂЌсЂдтЁЦуцЙсЂЌсђЂтЙїсЂФС╗БУАетЈќуиатй╣сЂФт░▒С╗╗сЂЌсЂЪС╝џуцЙсЂФУ╗бУЂисЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
тјЪтЉіС╝џуцЙсЂеУбФтЉісЂ»сђЂУбФтЉісЂ«жђђУЂиТЎѓсЂФсђїТЕЪт»єС┐ЮТїЂсЃ╗уФХТЦГжЂ┐ТГбсЂФжќбсЂЎсѓІУфЊу┤ёТЏИсђЇсЂежАїсЂЎсѓІТќЄТЏИсѓњС║цсѓЈсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсЂїсђЂсЂЮсЂ«СИГсЂФсЂ»сђЂ
- жђђУЂитЙї№╝Љт╣┤жќЊсЂ»сђЂУ▓┤уцЙсЂ«тќХТЦГТЕЪт»єсѓњуггСИЅУђЁсЂФжќІуц║сђЂТ╝ЈТ┤ЕсЂЌсЂфсЂёсЂЊсЂе
- жђђУЂитЙї№╝Љт╣┤жќЊсЂ»сђЂУ▓┤уцЙсЂ«тќХТЦГТЕЪт»єсѓњУЄфти▒сЂ«сЂЪсѓЂсђЂсЂЙсЂЪсЂ»У▓┤уцЙсЂеуФХтљѕсЂЎсѓІС║ІТЦГУђЁсЂЮсЂ«С╗ќуггСИЅУђЁсЂ«сЂЪсѓЂсЂФСй┐ућесЂЌсЂфсЂёсЂЊсЂесђѓ
- У▓┤уцЙсЂ«тќХТЦГТЕЪт»єсЂФжќбсЂЎсѓІсЃЄсЃ╝сѓ┐сђЂТЏИжАъсЂфсЂЕсЂ»жђђУЂиТЎѓсЂФсЂЎсЂ╣сЂдУ┐ћжѓёсЂЌсђЂтцќжЃесЂФТїЂсЂАтЄ║сЂЋсЂфсЂёсЂЊсЂесђѓ
- сЂЊсЂ«УфЊу┤ёТЏИтЈісЂ│тќХТЦГТЕЪт»єсЂФжќбсЂЎсѓІУФИУдЈт«џсЂФжЂЋтЈЇсЂЌсЂдУ▓┤уцЙсЂФТљЇт«│сѓњСИјсЂѕсЂЪта┤тљѕсЂФсЂ»сђЂУ▓гС╗╗сѓњсѓѓсЂБсЂдУ│атёЪсЂФсЂѓсЂЪсѓІсЂЊсЂесђѓ
сЂесђЂУеўУ╝ЅсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
сЂЊсѓїсЂФт»ЙсЂЌсђЂУБЂтѕцТЅђсЂ»сђЂ
уФХТЦГудЂТГбуГЅТЮАжаЁсЂФсѓѕсЂБсЂдтјЪтЉіС╝џуцЙсЂїС┐ЮУГисЂЌсѓѕсЂєсЂесЂЌсЂдсЂёсѓІсђїтќХТЦГТЕЪт»єсђЇсЂїтЅЇУеўсЂ«сЃјсѓдсЃЈсѓдсЂДсЂѓсЂБсЂЪсЂесЂЌсЂдсѓѓсђЂсЂЮсЂ«жЄЇУдЂТђДсЂ»тјЪтЉіС╝џуцЙсЂФсЂесЂБсЂдсѓѓсЂЮсѓїсЂ╗сЂЕУдЂС┐ЮУГиТђДсЂ«жФўсЂёсѓѓсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂесЂёсѓЈсЂќсѓІсѓњтЙЌсЂфсЂёсђѓсЂЙсЂЪсђЂуФХТЦГудЂТГбуГЅТЮАжаЁсЂДсЂ»сђЂТюЪжќЊсЂЊсЂЮТ»ћУ╝ЃуџёуЪГсЂёсѓѓсЂ«сЂ«сђЂт»ЙУ▒АУАїуѓ║сѓѓуФХТЦГС╗ќуцЙсЂИсЂ«т░▒УЂисѓњт║Ѓу»ёсЂФудЂсЂўсЂдсЂісѓіжАДт«бтЦфтЈќУАїуѓ║уГЅсЂФжЎљт«џсЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂЌсђЂтї║тЪЪсЂ»тЁесЂЈжЎљт«џсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂфсЂёсђѓсЂЮсЂєсЂДсЂѓсѓІсЂФсѓѓсЂІсЂІсѓЈсѓЅсЂџсђЂтЙЊТЦГтЊАсЂФт»ЙсЂЎсѓІС╗БтёЪТјфуй«сЂ»сЂфсѓЊсѓЅУгЏсЂўсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂфсЂёсЂ«сЂДсЂѓсѓІсђѓ
ТЮ▒С║гтю░Тќ╣УБЂтѕцТЅђ2009т╣┤11Тюѕ9ТЌЦтѕцТ▒║
сЂесЂЌсђЂтјЪтЉіС╝џуцЙсЂ«тљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ»сђЂтљѕуљєТђДсѓњТюЅсЂЎсѓІсЂесЂ»сЂёсЂѕсЂџсђЂУЂиТЦГжЂИТіъсЂ«УЄфућ▒сЂФт»ЙсЂЎсѓІжЂјт║дсЂ«тѕХу┤ёсѓњУф▓сЂЎсѓѓсЂ«сЂДтЁгт║ЈУЅ»С┐ЌсЂФтЈЇсЂЌуёАті╣сЂДсЂѓсѓІсЂесЂЌсЂдсђЂтјЪтЉісЂФсѓѕсѓІжђђУЂижЄЉсЂ«У┐ћжѓёУФІТ▒ѓсѓњТБётЇ┤сЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
удЂТГбсЂ«у»ётЏ▓сЂїТўјуб║сЂФжЎљт«џсЂЋсѓїсЂџсђЂсЂѓсЂЙсѓісЂФсѓѓт║ЃТ▒јсЂФтЈісЂ│сђЂсЂЮсЂ«ухљТъюС╗ќсЂ«ТЦГуе«сЂ«С╝џуцЙсЂФсЂЌсЂІт░▒УЂисЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂфсЂЈсЂфсѓІсЂесђЂУ║ФсЂФС╗ўсЂЉсЂЪухїжеЊсѓњтЇЂтѕєсЂФТ┤╗сЂІсЂЎсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂфсЂёсЂесЂёсЂєСИЇтѕЕуЏісѓњУбФсѓІсЂЊсЂесЂФсЂфсѓІсЂЊсЂесЂїУђЃТЁ«сЂЋсѓїсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
сђїуФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎсЂ«тГўуХџТюЪжќЊсђЇсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂІсЂБсЂЪС║ІСЙІ
ті┤тЃЇУђЁТ┤ЙжЂБС║ІТЦГуГЅсѓњУАїсЂєтјЪтЉіС╝џуцЙ№╝ѕсѓ┐сЃісѓФсѓ░сЃФсЃ╝сЃЌ№╝ЅсЂїсђЂ№╝АуцЙсЂФТ┤ЙжЂБсЂЌсЂдсЂёсЂЪуцЙтЊАсЂїжђђУЂисЂЌсђЂУ╗бУЂисЂЌсЂЪ№╝буцЙсѓѕсѓітєЇсЂ│№╝АуцЙсЂФТ┤ЙжЂБсЂЋсѓїсЂЪсЂЊсЂесЂФт»ЙсЂЌсђЂжЏЄућетЦЉу┤ёСИісЂ«уФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎжЂЋтЈЇтЈѕсЂ»СИЇТ│ЋУАїуѓ║сЂФтЪ║сЂЦсЂЇТљЇт«│У│атёЪсѓњТ▒ѓсѓЂсЂЪС║ІСЙІсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
тјЪтЉіС╝џуцЙсЂФсЂ»сђїжђђУЂисЂЌсЂЪта┤тљѕсѓѓуФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎсЂесЂЌсЂджђђУЂиТЌЦсЂІсѓЅУхиу«ЌсЂЌсЂд№╝Њт╣┤С╗ЦтєЁсЂ»тйЊуцЙсЂеуФХТЦГжќбС┐ѓсЂФуФІсЂцТЦГуе«сЂФжќбСИјсЂЎсѓІсЂЊсЂесѓњудЂТГбсЂЎсѓІсђЇсЂесЂЎсѓІт░▒ТЦГУдЈтЅЄсЂїсЂѓсѓісђЂжђђУЂиТЎѓсЂФсЂ»сђїтюеУЂиСИГсЂФТЦГтІЎСИіуЪЦсѓітЙЌсЂЪт«бтЁѕтЈісЂ│уггСИЅУђЁсЂФт»ЙсЂЌсЂдсђЂУЄфсѓЅсЂ«тќХТЦГТ┤╗тІЋсѓњсЂЌсЂфсЂёсЂЊсЂесђЂтЈѕсђЂуЏ┤ТјЦС╗ЋС║ІсЂ«ТЅЊУе║сЂїсЂѓсЂБсЂЪта┤тљѕсЂФсЂ»сѓ┐сЃісѓФсѓ░сЃФсЃ╝сЃЌсЂФт»ЙсЂЌсЂдта▒тЉісЂЌсђЂТЏИжЮбсЂФсѓѕсѓІТЅ┐УФЙсѓњтЙЌсЂдС╗ЋС║ІсѓњтЈЌТ│есЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂесЂЎсѓІсђЇсЂесЂѓсѓісђЂсЂЙсЂЪжђђУЂиТЎѓсЂФТ▒ѓсѓЂсЂЪУфЊу┤ёТЏИсЂФсЂ»сђЂсђїтЅЇжаЁсЂ«УдЈт«џсЂ»№╝їУЄфсѓЅсЂїуФХТЦГТЦГУђЁсѓњтљФсѓђсЂЮсЂ«С╗ќсЂ«С╝џуцЙсЂФжЏЄућесЂЋсѓїсЂЪта┤тљѕсЂФсЂ»№╝їсЂЮсЂ«С╝џуцЙтєЁсЂДсЂ«Т┤╗тІЋсЂФТ║ќућесЂЎсѓІсђЇсЂесЂѓсЂБсЂЪсЂ«сЂДсЂЎсЂїсђЂУБЂтѕцТЅђсЂ»сђЂУбФтЉісЂїтјЪтЉіС╝џуцЙсЂФсЂ»1т╣┤уеІт║дсЂЌсЂІтІцтІЎсЂЌсЂдсЂёсЂфсЂІсЂБсЂЪсЂЊсЂесѓњУИЈсЂЙсЂѕсђЂ
ТюгС╗ХуФХТЦГжЂ┐ТГбУдЈт«џсЂїсЂЮсѓїсЂъсѓїт«џсѓЂсѓІУдЂС╗ХсЂ»ТійУ▒АуџёсЂфтєЁт«╣сЂДсЂѓсЂБсЂд№╝ѕт░▒ТЦГУдЈтЅЄугг13ТЮАсђїуФХТЦГжќбС┐ѓсЂФуФІсЂцТЦГуе«сђЇсђЂТюгС╗ХУдџТЏИсђїтЄ║тљЉСИГуЪЦсѓітЙЌсЂЪС║ІТЦГУђЁсђЇсђЂТюгС╗ХУфЊу┤ёТЏИсђїтюеУЂиСИГуЪЦсѓітЙЌсЂЪт«бтЁѕтЈісЂ│уггСИЅУђЁсђЇсђЂсђїуФХТЦГТЦГУђЁсѓњтљФсѓђсЂЮсЂ«С╗ќсЂ«С╝џуцЙсђЇ№╝ЅсђЂт╣Ёт║ЃсЂёС╝ЂТЦГсЂИсЂ«У╗бУЂисЂїудЂТГбсЂЋсѓїсѓІсЂЊсЂесЂФсЂфсѓІсђѓсЂЙсЂЪсђЂудЂТГбсЂЋсѓїсѓІТюЪжќЊсѓѓсђЂ№╝Њт╣┤жќЊсЂ«уФХТЦГжЂ┐ТГбТюЪжќЊ№╝ѕт░▒ТЦГУдЈтЅЄугг13ТЮА№╝ЅсЂ»УбФтЉісЂ«тІцуХџТюЪжќЊ№╝Љт╣┤сЂеТ»ћУ╝ЃсЂЌсЂджЮътИИсЂФжЋисЂёсЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсѓІсЂЌсђЂТюгС╗ХУфЊу┤ёТЏИтЈісЂ│ТюгС╗ХУдџТЏИсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»ТюЪжќЊсЂ«жЎљт«џсЂїтЁесЂЈсЂфсЂёсЂЊсЂесЂІсѓЅсђЂсЂёсЂџсѓїсѓѓжЂјт║дсЂ«тѕХу┤ёсѓњУбФтЉісЂФт╝исЂёсЂдсЂёсѓІсѓѓсЂ«сЂеУЕЋСЙАсЂЏсЂќсѓІсѓњтЙЌсЂфсЂёсђѓ
ТЮ▒С║гтю░Тќ╣УБЂтѕцТЅђ2015т╣┤10Тюѕ30ТЌЦтѕцТ▒║
сЂесЂЌсЂдсђЂТюгС╗ХуФХТЦГжЂ┐ТГбУдЈт«џсЂФсѓѕсЂБсЂдУбФтЉісЂ«У╗бУЂисѓњудЂТГбсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂФтљѕуљєТђДсЂїсЂѓсѓІсЂесЂ»тѕ░т║ЋУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂџсђЂтЁгт║ЈУЅ»С┐ЌсЂФтЈЇсЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂесЂЌсЂдТюЅті╣ТђДсѓњтљдт«џсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
СИісЂ«сђїсђјтЙЊТЦГтЊАсЂ«тю░СйЇсђЈсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂІсЂБсЂЪС║ІСЙІсђЇсЂетљїсЂўсЂЈсђЂтІцтІЎТюЪжќЊ1т╣┤сЂФТ»ћсЂЌсЂд№╝Њт╣┤жќЊсЂ«уФХТЦГжЂ┐ТГбТюЪжќЊсЂ»жЋисЂЎсЂјсѓІсЂЌсђЂТюЪжќЊсЂ«жЎљт«џсЂїсЂфсЂёУфЊу┤ёТЏИсѓёУдџТЏИсЂ»тЁгт║ЈУЅ»С┐ЌсЂФтЈЇсЂЎсѓІсЂесЂёсЂєтѕцТќГсЂДсЂЎсђѓ
сЂфсЂісђЂсђїуФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎсЂ«тГўуХџТюЪжќЊсђЇсЂ»сђЂухїТИѕућБТЦГуюЂсђїуФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎтЦЉу┤ёсЂ«ТюЅті╣ТђДсЂФсЂцсЂёсЂдсђЇсЂФсѓѕсѓїсЂ░сђЂтЇіт╣┤№йъ2т╣┤сЂїжђџтИИсЂДсЂѓсѓісђЂ5т╣┤сЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂЪСЙІсѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсЂїсђЂ3т╣┤сЂ»уЅ╣Т«ісЂфта┤тљѕсЂФжЎљсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сђїудЂТГбсЂЋсѓїсѓІуФХТЦГУАїуѓ║сЂ«у»ётЏ▓сђЇсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂІсЂБсЂЪта┤тљѕ
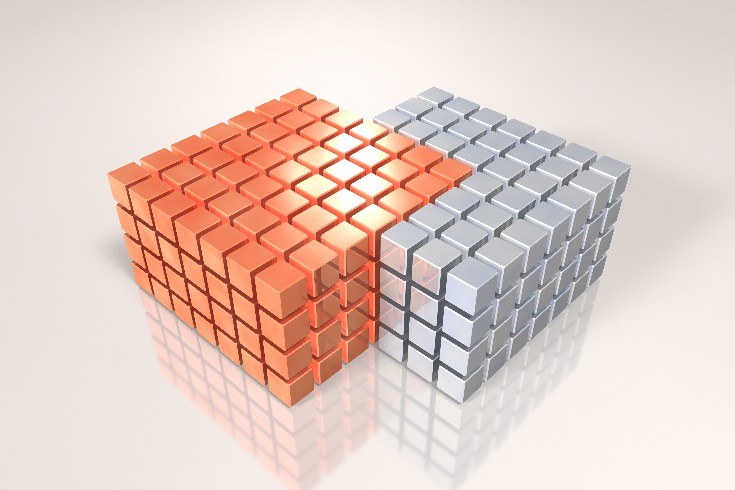
УбФтЉіС╝џуцЙсѓњжђђУЂисЂЌсЂдуФХтљѕС╗ќуцЙсЂФУ╗бУЂисЂЌсЂЪсЃљсЃ│сѓ»сѓбсѓисЃЦсѓбсЃЕсЃ│сѓ╣ТЦГтІЎТІЁтйЊсЂ«тјЪтЉісЂїсђЂУбФтЉіС╝џуцЙсЂІсѓЅсђЂуФХТЦГжЂ┐ТГбТЮАжаЁсЂФжЂЋтЈЇсЂЌсЂЪсЂесЂЌсЂдСИЇТћ»ухдТЮАжаЁсЂФтЪ║сЂЦсЂёсЂджђђУЂижЄЉсЂ«Тћ»ТЅЋсѓњТІњтљдсЂЋсѓїсЂЪсЂЪсѓЂсђЂТюгС╗ХСИЇТћ»ухдТЮАжаЁсЂ»тЁгт║ЈУЅ»С┐ЌсЂФтЈЇсЂЎсѓІсЂесЂЌсЂдсђЂжђђУЂижЄЉТћ»ТЅЋтљѕТёЈсЂФтЪ║сЂЦсЂЈжђђУЂижЄЉуГЅсЂ«Тћ»ТЅЋсѓњТ▒ѓсѓЂсЂЪС║ІСЙІсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
УБЂтѕцТЅђсЂ»сђЂуФХТЦГжЂ┐ТГбТЮАжаЁсЂФсѓѕсѓІУ╗бУЂиудЂТГбсЂ«т»ЙУ▒Ау»ётЏ▓сЂїсђЂтјЪтЉісЂеУбФтЉітЂ┤ТІЁтйЊУђЁсЂ«УфЇУГўсЂФсЂісЂёсЂдсѓѓСИЇТўјуб║сЂДсЂѓсѓісђЂтјЪУбФтЉіжќЊсЂ«УфЇУГўсЂФти«сЂїсЂѓсѓІсЂесЂЌсЂЪСИісЂДсђЂ
уФХТЦГсЂїудЂТГбсЂЋсѓїсѓІТЦГтІЎсЂ«у»ётЏ▓сЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»сђЂСИЇТўјуб║сЂфжЃетѕєсѓѓсЂѓсѓІсѓѓсЂ«сЂ«сђЂсЃљсЃ│сѓ»сѓбсѓисЃЦсѓбсЃЕсЃ│сѓ╣ТЦГтІЎсѓњУАїсЂєућЪтЉйС┐ЮжЎ║С╝џуцЙсЂИсЂ«У╗бУЂисЂїудЂТГбсЂЋсѓїсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесЂ»Тўјуб║сЂДсЂѓсЂБсЂЪсђѓ
ТЮ▒С║гтю░Тќ╣УБЂтѕцТЅђ2012т╣┤1Тюѕ13ТЌЦтѕцТ▒║
сЂЌсЂІсЂЌсђЂтјЪтЉісЂ«УбФтЉісЂФсЂісЂёсЂдтЙЌсЂЪсЃјсѓдсЃЈсѓдсЂ»сђЂсЃљсЃ│сѓ»сѓбсѓисЃЦсѓбсЃЕсЃ│сѓ╣ТЦГтІЎсЂ«тќХТЦГсЂФжќбсЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂїСИ╗сЂДсЂѓсѓі№╝ѕтјЪтЉіТюгС║║№╝ЅсђЂТюгС╗ХуФХТЦГжЂ┐ТГбТЮАжаЁсЂїсЃљсЃ│сѓ»сѓбсѓисЃЦсѓбсЃЕсЃ│сѓ╣ТЦГтІЎсЂ«тќХТЦГсЂФсЂесЂЕсЂЙсѓЅсЂџсђЂтљїТЦГтІЎсѓњУАїсЂєућЪтЉйС┐ЮжЎ║С╝џуцЙсЂИсЂ«У╗бУЂиУЄфСйЊсѓњудЂТГбсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂ»сђЂсЂЮсѓїсЂЙсЂДућЪтЉйС┐ЮжЎ║С╝џуцЙсЂФсЂісЂёсЂдтІцтІЎсЂЌсЂдсЂЇсЂЪтјЪтЉісЂИсЂ«У╗бУЂитѕХжЎљсЂесЂЌсЂдсђЂт║Ѓу»ёсЂФсЂЎсЂјсѓІсѓѓсЂ«сЂесЂёсЂєсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсѓІсђѓ
сЂесЂЌсђЂудЂТГбсЂЋсѓїсѓІТЦГтІЎсЂ«у»ётЏ▓сЂїт║ЃсЂЎсЂјсђЂсЂЮсЂ«С╗ќсЂ«С║ІТЃЁсѓњУђЃТЁ«сЂЌсЂдсѓѓТюгС╗ХуФХТЦГжЂ┐ТГбТЮАжаЁсЂ»тљѕуљєТђДсѓњТгасЂЇсђЂті┤тЃЇУђЁсЂ«УЂиТЦГжЂИТіъсЂ«УЄфућ▒сѓњСИЇтйЊсЂФт«│сЂЎсѓІсѓѓсЂ«сЂДтЁгт║ЈУЅ»С┐ЌсЂФтЈЇсЂЌуёАті╣сЂДсЂѓсѓІсЂІсѓЅсђЂсЂЊсѓїсѓњтЅЇТЈљсЂесЂЎсѓІСИЇТћ»ухдТЮАжаЁсѓѓуёАті╣сЂДсЂѓсѓІсЂесЂЌсЂдсђЂжђђУЂижЄЉсЂ«Тћ»ТЅЋсЂёсѓњтјЪтЉісЂФтЉйсЂўсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
жЋисЂёжќЊућЪтЉйС┐ЮжЎ║С╝џуцЙсЂФтІцтІЎсЂЌсђЂсЂЮсЂ«ТЦГуЋїсЂФсЂісЂЉсѓІсЃјсѓдсЃЈсѓдсЂЌсЂІуЪЦсѓЅсЂфсЂёуцЙтЊАсЂФсђЂућЪтЉйС┐ЮжЎ║С╝џуцЙсЂИсЂ«У╗бУЂисЂЮсЂ«сѓѓсЂ«сѓњудЂТГбсЂЎсѓІсЂ«сЂ»сђЂуёАуљєсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓуЙјт«╣тИФсЂїжђђУЂисЂЎсѓІжџЏсЂФсђЂуЙјт«╣жЎбсЂИсЂ«У╗бУЂиУЄфСйЊсѓњудЂТГбсЂЎсѓІсЂ«сЂФуёАуљєсЂїсЂѓсѓІсЂ«сЂетљїТДўсЂесЂёсЂѕсѓІсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
сђїС╗БтёЪТјфуй«сЂїУгЏсЂўсѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІсЂІсђЇсЂїУфЇсѓЂсѓЅсѓїсЂфсЂІсЂБсЂЪта┤тљѕ
СИісЂ«С║ІСЙІсЂїсЂЮсЂ«сЂЙсЂЙУЕ▓тйЊсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
ућЪтЉйС┐ЮжЎ║С╝џуцЙсЂДсЃљсЃ│сѓ»сѓбсѓисЃЦсѓбсЃЕсЃ│сѓ╣ТЦГтІЎсѓњТІЁтйЊсЂЌсЂдсЂёсЂЪтјЪтЉісЂ»ТюгжЃежЋитЈісЂ│тЪиУАїтй╣тЊАсЂ«уФІта┤сЂФсЂѓсѓісђЂуЏИтйЊжФўт║дсЂфтю░СйЇсЂДсЂѓсЂБсЂЪсЂ«сЂДсђЂУ│ЃжЄЉсЂ»уЏИтйЊжФўжАЇсЂДсЂѓсЂБсЂЪсЂ«сЂДсЂЎсЂїсђЂУБЂтѕцТЅђ№╝ѕтљїСИі№╝ЅсЂ»сђЂ
- ТюгС╗ХуФХТЦГжЂ┐ТГбТЮАжаЁсѓњт«џсѓЂсЂЪтЅЇтЙїсЂФсЂісЂёсЂдсђЂУ│ЃжЄЉжАЇсЂ«ти«сЂ»сЂЋсЂ╗сЂЕсЂфсЂёсЂ«сЂДсђЂтјЪтЉісЂ«У│ЃжЄЉжАЇсѓњсѓѓсЂБсЂдсђЂТюгС╗ХуФХТЦГжЂ┐ТГбТЮАжаЁсЂ«С╗БтёЪТјфуй«сЂесЂЌсЂдтЇЂтѕєсЂфсѓѓсЂ«сЂїСИјсЂѕсѓЅсѓїсЂдсЂёсЂЪсЂесЂёсЂєсЂЊсЂесЂ»тЏ░жЏБсЂДсЂѓсѓІсђѓ
- тјЪтЉісЂ«жЃеСИІсЂ«СИГсЂФсђЂтјЪтЉісѓѕсѓіжФўжАЇсЂфухдСИјсЂ«УђЁсЂїуЏИтйЊТЋ░сЂёсѓІсЂїсђЂсЂЮсѓїсѓЅсЂ«тјЪтЉісЂ«жЃеСИІсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»сђЂуЅ╣Т«хуФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎсЂ«т«џсѓЂсЂ»сЂфсЂёсЂ«сЂДсЂѓсѓІсЂІсѓЅсђЂсѓёсЂ»сѓісђЂтјЪтЉісЂФт»ЙсЂЎсѓІС╗БтёЪТјфуй«сЂїтЇЂтѕєсЂДсЂѓсЂБсЂЪсЂесЂёсЂєсЂЊсЂесЂ»тЏ░жЏБсЂДсЂѓсѓІсђѓ
сЂесЂЌсЂдсђЂсѓёсЂ»сѓісђЂуФХТЦГжЂ┐ТГбуЙЕтІЎсѓњт«џсѓЂсѓІтљѕТёЈсЂїуёАті╣сЂДсЂѓсѓІТа╣ТІасЂесЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
сЂЙсЂесѓЂ
тЙЊТЦГтЊАсЂ«жђђУЂитЙїсЂ«тљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ»сђЂт░▒ТЦГУдЈтЅЄсЂ«УдЈт«џсѓёУфЊу┤ёТЏИсЂїсЂѓсѓїсЂ░у░АтЇўсЂФУфЇсѓЂсѓЅсѓїсѓІсђЂсЂесЂёсЂєсѓѓсЂ«сЂДсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓтљїТЦГС╗ќуцЙУ╗бУЂиудЂТГбТЮАжаЁсЂ»жђђУЂиті┤тЃЇУђЁсЂ«УЂиТЦГжЂИТіъсЂ«УЄфућ▒сѓётќХТЦГсЂ«УЄфућ▒сѓњтѕХу┤ёсЂЎсѓІт║дтљѕсЂёсЂїт╝исЂёсЂЪсѓЂсђЂСй┐ућеУђЁсЂ«тќХТЦГТеЕсЂесЂ«Уф┐ТЋ┤сЂїт┐ЁУдЂсЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓС╝џуцЙсЂесЂЌсЂдТюгтйЊсЂФт«ѕсѓІсЂ╣сЂЇтѕЕуЏісЂїсЂѓсѓісђЂУ╗бУЂиудЂТГбуЙЕтІЎсЂ«у»ётЏ▓сѓѓт┐ЁУдЂТюђт░ЈжЎљсЂФсЂесЂЕсѓЂсѓІсЂЊсЂесЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
жЂЕтѕЄсЂфсЃФсЃ╝сЃФсЂежЂЕтѕЄсЂфжЂІућесЂїт┐ЁУдЂсЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсЂїсђЂтЁиСйЊуџёС║ІТЃЁсЂесЂ«жќбС┐ѓсЂДтђІтѕЦтЁиСйЊуџёсЂФТцюУејсЂЎсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓт╝ЂУГитБФсЂФсѓѕсѓІсѓбсЃЅсЃљсѓцсѓ╣сЂїт┐ЁУдЂсЂесЂёсЂѕсЂЙсЂЎсђѓ