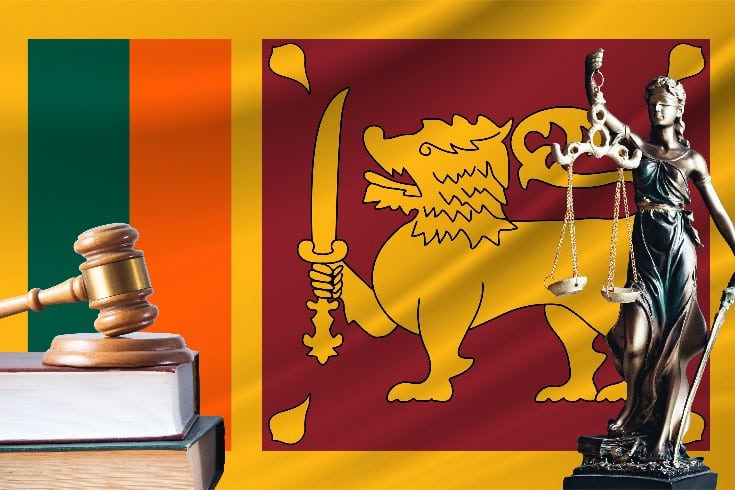гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«ж°‘дё»зӨҫдјҡдё»зҫ©е…ұе’ҢеӣҪгҒ®жі•дҪ“зі»гғ»жі•еҲ¶еәҰгғ»еҸёжі•еҲ¶еәҰ

гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«ж°‘дё»зӨҫдјҡдё»зҫ©е…ұе’ҢеӣҪпјҲд»ҘдёӢгҖҢгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҖҚпјүгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒгҒқгҒ®иӨҮйӣ‘гҒ•гҒЁеӨҡж§ҳжҖ§гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдё–з•ҢгҒ§гӮӮзҸҚгҒ—гҒ„зү№ж®ҠгҒӘж··еҗҲжі•дҪ“зі»гӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҠгӮҲгҒқ400е№ҙгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«гҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ«гӮҲгӮӢжӨҚж°‘ең°ж”Ҝй…ҚгҒЁгҒ„гҒҶжіўд№ұгҒ«жәҖгҒЎгҒҹжӯҙеҸІгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®зөұжІ»жҷӮд»ЈгҒ«жҢҒгҒЎиҫјгҒҫгӮҢгҒҹжі•жәҗгӮ’йҮҚеұӨзҡ„гҒ«з©ҚгҒҝйҮҚгҒӯгҒҰгҒҚгҒҹзөҗжһңгҖҒд»Ҡж—ҘгҒ®гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«жі•гӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒеҚҳдёҖгҒ®жҲҗж–Үжі•гӮ’еҹәзӣӨгҒЁгҒҷгӮӢеӨ§йҷёжі•зі»гҒЁгҒҜдёҖз·ҡгӮ’з”»гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®ж №жәҗзҡ„гҒӘжҖқжғігӮ„ж§ӢйҖ гҒ®йҒ•гҒ„гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжі•еӢҷгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§дёҚеҸҜж¬ гҒӘ第дёҖжӯ©гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘж··еҗҲжі•дҪ“зі»гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжӯҙеҸІзҡ„еӨүйҒ·гӮ’зөҢгҒҰзўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒқгҒ®дёӯеҝғгҒ«гҒӮгӮӢеҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгӮ’гҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒ®жҜ”ијғгӮ’дәӨгҒҲгҒӘгҒҢгӮүи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ®зү№иіӘгҒЁжӯҙеҸІзҡ„иғҢжҷҜ

дё»иҰҒгҒӘдёүеҖӢгҒ®жі•жәҗ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒеӨ§гҒҚгҒҸеҲҶгҒ‘гҒҰдёүгҒӨгҒ®дё»иҰҒгҒӘжі•жәҗгҒӢгӮүжҲҗгӮҠз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
第дёҖгҒҜгҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®жӨҚж°‘ең°ж”Ҝй…ҚдёӢгҒ§е°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹиӢұзұіжі•пјҲCommon LawпјүгҒ§гҒҷгҖӮдё»гҒ«еҲ‘дәӢжі•гӮ„е…¬жі•гҖҒзү№гҒ«жҶІжі•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж”Ҝй…Қзҡ„гҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҲӨдҫӢгӮ’йҮҚиҰҒгҒӘжі•жәҗгҒЁгҒҷгӮӢгҖҢеҲӨдҫӢжӢҳжқҹжҖ§гҒ®еҺҹеүҮгҖҚпјҲjudicial precedentпјүгӮ„гҖҒеҲӨжұәзҗҶз”ұгӮ’жі•зҡ„ж №жӢ гҒЁгҒҷгӮӢratio decidendiгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиӢұзұіжі•гҒ®ж №жң¬зҡ„гҒӘжҰӮеҝөгҒҢгҖҒд»Ҡж—ҘгҒ®гӮұгғјгӮ№гғ»гғӯгғјгҒ®и§ЈйҮҲгӮ’дё»е°ҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
第дәҢгҒҜгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ«гӮҲгӮӢж”Ҝй…ҚжҷӮд»ЈгҒ«жҢҒгҒЎиҫјгҒҫгӮҢгҒҹгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•пјҲRoman-Dutch lawпјүгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•жәҗгҒҜгҖҒж°‘жі•гӮ„дҝЎиЁ—жі•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҲҶйҮҺгҒ§гҖҒзү№е®ҡгҒ®жі•еҫӢгӮ„ж…Јзҝ’жі•гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҖҒгҒқгҒ®йҡҷй–“гӮ’еҹӢгӮҒгӮӢгҖҢж®ӢдҪҷжі•гҖҚпјҲresiduary lawпјүгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘзү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•еҫӢгҒ®дё»иҰҒгҒӘж №жӢ гҒҜеҲ¶е®ҡжі•гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҲ¶е®ҡжі•гҒҢжІҲй»ҷгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢе…ұйҖҡгҒ®иҰҸзҜ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҢж®ӢдҪҷжі•гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ«гҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«зӢ¬иҮӘгҒ®зү№иіӘгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ«гҒҜгӮ·гғігғҸгғ©дәәгҖҒгӮҝгғҹгғ«дәәгҖҒгғ гӮ№гғӘгғ гҒӘгҒ©иӨҮж•°гҒ®ж°‘ж—ҸйӣҶеӣЈгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«еӣәжңүгҒ®ж…Јзҝ’жі•гӮ„еҖӢдәәжі•пјҲKandyan lawгҖҒThesavalamai lawгҖҒMuslim lawгҒӘгҒ©пјүгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒеҖӢдәәжі•гҒЁгҒҜгҖҒзү№е®ҡгҒ®ж°‘ж—ҸгӮ„е…ұеҗҢдҪ“гҒ®ж…Јзҝ’гҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒдё»гҒ«зөҗе©ҡгҖҒйӣўе©ҡгҖҒзӣёз¶ҡгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹ家ж—Ҹжі•зҡ„гҒӘдәӢй …гӮ’иҰҸе®ҡгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгғ гӮ№гғӘгғ жі•гҒҜгғ гӮ№гғӘгғ гҒ«гҖҒгӮ«гғҮгӮЈгӮўгғіжі•гҒҜж—§гӮӯгғЈгғігғҮгӮЈзҺӢеӣҪеҮәиә«гҒ®д»Ҹж•ҷеҫ’гӮ·гғігғҸгғ©дәәгҒ«гҖҒгғҶгӮөгғҜгғ©гғһгӮӨжі•гҒҜеҢ—йғЁе·һгҒ«дҪҸгӮҖгӮҝгғҹгғ«дәәгҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…·еҗҲгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ«еұһгҒҷгӮӢдәәгҖ…гҒҢдҪ•гӮүгҒӢгҒ®жі•еҫӢе•ҸйЎҢгҒ«зӣҙйқўгҒ—гҖҒгҒқгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰеҪјгӮүгҒ®еҖӢдәәжі•гҒ«жҳҺзўәгҒӘиҰҸе®ҡгҒҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒгҒқгҒ®йҡҷй–“гӮ’еҹӢгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гҒҢгҖҢж®ӢдҪҷжі•гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰ第дёүгҒ«гҖҒеүҚиҝ°гҒ®йҖҡгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®ж°‘ж—ҸйӣҶеӣЈгҒ«еӣәжңүгҒ®ж…Јзҝ’жі•гӮ„еҖӢдәәжі•пјҲKandyan lawгҖҒThesavalamai lawгҖҒMuslim lawгҒӘгҒ©пјүгҒҢгҖҒзү№е®ҡгҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
жӯҙеҸІзҡ„еӨүйҒ·
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®зҸҫеңЁгҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒзҙ„400е№ҙгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢеӨ–еӣҪж”Ҝй…ҚгҒ®жӯҙеҸІзҡ„её°зөҗгҒ§гҒҷгҖӮ16дё–зҙҖгҒ«еҲ°жқҘгҒ—гҒҹгғқгғ«гғҲгӮ¬гғ«гҖҒз¶ҡгҒ„гҒҰ17дё–зҙҖгҒӢгӮү18дё–зҙҖгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰжІҝеІёйғЁгӮ’ж”Ҝй…ҚгҒ—гҒҹгӮӘгғ©гғігғҖгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢиҮӘеӣҪгҒ®жі•жәҗгӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҖҒзү№гҒ«гӮӘгғ©гғігғҖгҒҜиЈҒеҲӨеҲ¶еәҰгӮ’ж•ҙеӮҷгҒ—гҒҰгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гӮ’йҒ©з”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ®иӨҮйӣ‘гҒ•гӮ’жұәе®ҡгҒҘгҒ‘гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ1796е№ҙгҒ«гӮӘгғ©гғігғҖгӮ’ж”ҫйҖҗгҒ—гҒҰж”Ҝй…ҚжЁ©гӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҹгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®зөұжІ»ж”ҝзӯ–гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮйҖҡеёёгҖҒеҫҒжңҚең°гҒ§гҒҜж—§е®—дё»еӣҪгҒ®жі•еҫӢгҒҢе»ғжӯўгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒҜж—ўеӯҳгҒ®жі•еҫӢгӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҺҹеүҮгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж–°гҒҹгҒӘзөұжІ»иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®гҖҒж—§е®—дё»еӣҪгҒ®жі•дҪ“зі»гӮ’е®Ңе…ЁгҒ«жҠ№ж¶ҲгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиӢұзұіжі•гӮ’дёҰиЎҢгҒ—гҒҰе°Һе…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж”Ҝй…ҚгҒ®жӯЈеҪ“жҖ§гӮ’зўәдҝқгҒ—гҖҒзӨҫдјҡгҒ®еҶҶж»‘гҒӘ移иЎҢгӮ’еӣігӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж”Ҝй…Қж”ҝзӯ–гҒ®её°зөҗгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж”ҝзӯ–гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гҒҜе»ғжӯўгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгҖҒиӢұзұіжі•гҒЁе…ұеӯҳгҒҷгӮӢеҪўгҒ§гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ«зө„гҒҝиҫјгҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®иЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒжӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҒ«е°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹжі•жәҗгӮ’йқҷзҡ„гҒ«йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒжҷӮд»ЈгҒ®еӨүеҢ–гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰжі•гӮ’зҷәеұ•гҒ•гҒӣгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЁҖгҒ„ж–№гӮ’еӨүгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒеҚҳгҒӘгӮӢеӨ–еӣҪжі•гҒ®з¶ҷеҸ—гҒ«з•ҷгҒҫгӮүгҒҡгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«зӢ¬иҮӘгҒ®жі•дҪ“зі»гӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиЈҒеҲӨе®ҳгҒҜгҖҒгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гӮ„иӢұзұіжі•гҒ®еҹәжң¬еҺҹеүҮгӮ’гҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«зӨҫдјҡгҒ®зҸҫе®ҹгҒЁзөҗгҒігҒӨгҒ‘гҒҰи§ЈйҮҲгҒ—гҖҒж–°гҒҹгҒӘеҲӨдҫӢгӮ’еҪўжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжі•еҫӢгӮ’еӢ•зҡ„гҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒ®ж§ӢйҖ гҒЁжЁ©йҷҗ

жҶІжі•дёҠгҒ®еҸёжі•жЁ©гҒ®дҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гҒЁзӢ¬з«ӢжҖ§
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«жҶІжі•гҒҜгҖҒдё»жЁ©гҒҢеӣҪж°‘гҒ«гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®дё»жЁ©гҒҢз«Ӣжі•гҖҒиЎҢж”ҝгҖҒеҸёжі•гҒ®дёүжЁ©гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиЎҢдҪҝгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§зү№зӯҶгҒҷгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒжҶІжі•з¬¬4жқЎ(c)гҒҢгҖҒеҸёжі•жЁ©гӮ’гҖҢиӯ°дјҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒиЈҒеҲӨжүҖгҖҒжі•е»·гҒҠгӮҲгҒіеүөиЁӯгҒ•гӮҢгҒҹж©ҹй–ўгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиЎҢдҪҝгҒ•гӮҢгӮӢгҖҚгҒЁиҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒӘгҒ©гҒ®жҶІжі•гҒҢеҸёжі•жЁ©гӮ’зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹжЁ©еҠӣгҒЁгҒ—гҒҰдҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ§гҒҜгҖҒеҸёжі•жЁ©гҒҢиӯ°дјҡгҒ«жәҗгӮ’зҷәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒзӢ¬зү№гҒӘж§ӢйҖ гӮ’еҸ–гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®иҰҸе®ҡгҒҢеҸёжі•гҒ®зӢ¬з«ӢгӮ’жҗҚгҒӘгҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ§гҒҜгҖҒжҶІжі•и©•иӯ°дјҡпјҲConstitutional CouncilпјүгҒҢгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгӮ„жҺ§иЁҙйҷўгҒ®иЈҒеҲӨе®ҳгҒ®еӨ§зөұй ҳгҒ«гӮҲгӮӢд»»е‘ҪгӮ’жүҝиӘҚгҒҷгӮӢд»•зө„гҒҝгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®и©•иӯ°дјҡгҒҜгҖҒйҰ–зӣёгӮ„йҮҺе…ҡе…ҡйҰ–гҖҒеӣҪдјҡиӯ°е“ЎгҖҒеёӮж°‘зӨҫдјҡгҒ®д»ЈиЎЁгҒӘгҒ©гҖҒеӨҡж§ҳгҒӘгғЎгғігғҗгғјгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиЎҢж”ҝжЁ©гҒ®зӢ¬ж–ӯгӮ’жҺ’йҷӨгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘгғҒгӮ§гғғгӮҜгғ»гӮўгғігғүгғ»гғҗгғ©гғігӮ№ж©ҹиғҪгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иЈҒеҲӨжүҖгҒ®йҡҺеұӨж§ӢйҖ гҒЁеҪ№еүІ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®еҸёжі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒҷгӮӢжҳҺзўәгҒӘйҡҺеұӨж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
| гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®иЈҒеҲӨжүҖеҗҚ | дё»иҰҒгҒӘз®ЎиҪ„жЁ© | ж—Ҙжң¬гҒ®иЈҒеҲӨжүҖпјҲйЎһдјјж©ҹиғҪпјү |
|---|---|---|
| Supreme Court | жңҖзөӮдёҠиЁҙгҖҒжҶІжі•дәӢй …гҖҒеҹәжң¬зҡ„дәәжЁ©гҒ®дҝқиӯ·гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҺҹеҜ©гҖҒйҒёжҢҷиЁҙиЁҹгҒӘгҒ© | жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖ |
| Court of Appeal | й«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖгҒҠгӮҲгҒідёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүгҒ®жҺ§иЁҙеҜ© | й«ҳзӯүиЈҒеҲӨжүҖ |
| High Court | еҲ‘дәӢдәӢ件гҒ®з¬¬дёҖеҜ©гҖҒдёӢзҙҡиЈҒеҲӨжүҖгҒӢгӮүгҒ®жҺ§иЁҙеҜ© | ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖпјҲдёҖйғЁгҒ®ж©ҹиғҪпјү |
| District Court | ж°‘дәӢдәӢ件гҒ®з¬¬дёҖеҜ© | ең°ж–№иЈҒеҲӨжүҖгҖҒ家еәӯиЈҒеҲӨжүҖпјҲдёҖйғЁгҒ®ж©ҹиғҪпјү |
| Magistrates’ Court | и»Ҫеҫ®гҒӘеҲ‘дәӢдәӢ件гҒ®з¬¬дёҖеҜ© | з°Ўжҳ“иЈҒеҲӨжүҖпјҲдёҖйғЁгҒ®ж©ҹиғҪпјү |
ж—Ҙжң¬гҒЁеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒ®жЁ©йҷҗгҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҢгҖҒзү№е®ҡгҒ®дәӢ件гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰжі•д»ӨгҒ®еҗҲжҶІжҖ§гӮ’еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҖҢе…·дҪ“зҡ„иҰҸзҜ„зөұеҲ¶гҖҚгӮ’еҺҹеүҮгҒЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒжі•жЎҲгҒҢжҲҗз«ӢгҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҒқгҒ®еҗҲжҶІжҖ§гӮ’еҜ©жҹ»гҒҷгӮӢгҖҢжҠҪиұЎзҡ„иҰҸзҜ„зөұеҲ¶гҖҚгҒ«иҝ‘гҒ„е”ҜдёҖгҒӢгҒӨжҺ’д»–зҡ„гҒӘз®ЎиҪ„жЁ©гӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖгҒҜгҖҒз«Ӣжі•гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ«зӣҙжҺҘзҡ„гҒ«й–ўдёҺгҒҷгӮӢеј·еҠӣгҒӘжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
жң¬зЁҝгҒ§иҰӢгҒҰгҒҚгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•дҪ“зі»гҒҜгҖҒиӨҮйӣ‘гҒӘжӯҙеҸІзҡ„иғҢжҷҜгҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹж··еҗҲжі•дҪ“зі»гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢзӢ¬иҮӘгҒ®жҖқжғігӮ„ж§ӢйҖ гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜиӨҮж•°гҒ®жі•жәҗгҒҢйҮҚгҒӘгӮҠеҗҲгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзү№е®ҡгҒ®жі•зҡ„е•ҸйЎҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ©гҒ®жі•жәҗгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгӮ’еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйқһеёёгҒ«йӣЈгҒ—гҒҸгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒжі•еҫӢгҒ®жңҖж–°зүҲгӮ’йӣ»еӯҗзҡ„гҒ«е…ҘжүӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе®ҹеӢҷзҡ„гҒӘиӘІйЎҢгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеӨ–еӣҪгҒ®жі•еҫӢ家гӮ„гғ“гӮёгғҚгӮ№гғ‘гғјгӮҪгғігҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒзҸҫең°гҒ®жі•еҫӢе®ҹеӢҷгҒ«зІҫйҖҡгҒ—гҒҹе°Ӯй–Җ家гҒ®зҹҘиҰӢгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
й–ўйҖЈеҸ–жүұеҲҶйҮҺпјҡеӣҪйҡӣжі•еӢҷгғ»жө·еӨ–дәӢжҘӯ