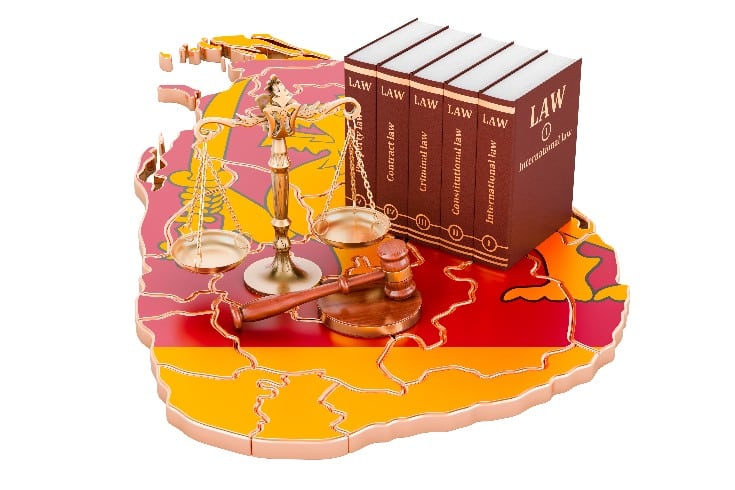гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«ж°‘дё»зӨҫдјҡдё»зҫ©е…ұе’ҢеӣҪгҒ®еҘ‘зҙ„жі•гҒҠгӮҲгҒідёҚеӢ•з”Јжі•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢи§ЈиӘ¬

гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒҜгҖҒгӮӨгғігғүжҙӢгҒ®жҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘиҰҒиЎқгҒ«дҪҚзҪ®гҒ—гҖҒеӨҡж§ҳгҒӘж–ҮеҢ–гҒЁзөҢжёҲзҡ„еҸҜиғҪжҖ§гӮ’з§ҳгӮҒгҒҹеӣҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҖҒгҒқгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®еӨ§йҷёжі•пјҲCivil LawпјүдҪ“зі»гҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢжӯҙеҸІзҡ„иғҢжҷҜгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®ж°‘жі•гҒҜгҖҒиӢұеӣҪгӮігғўгғігғӯгғјгҒЁгҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ®жӨҚж°‘ең°жҷӮд»ЈгҒ«е°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гҒ®ж··еҗҲдҪ“зі»гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүгҒӘжҖ§иіӘгҒҢгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒ«гҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„зӢ¬иҮӘгҒ®жі•жҰӮеҝөгӮ„иҰҒ件гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жң¬зЁҝгҒ§гҒҜгҖҒзү№гҒ«ж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҫӢе®ҹеӢҷиҖ…гҒҢзӣҙйқўгҒ—гҒҢгҒЎгҒӘгҖҢеҘ‘зҙ„жі•гҖҚгҒЁгҖҢдёҚеӢ•з”Јй–ўйҖЈжі•гҖҚгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҮҚиҰҒгҒӘйҒ•гҒ„гҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘжі•д»ӨгӮ’ж №жӢ гҒЁгҒ—гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮз„Ўе„ҹгҒ®зҙ„жқҹгҒҢжі•зҡ„гҒ«з„ЎеҠ№гҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒйӣ»еӯҗеҘ‘зҙ„гҒ®жі•зҡ„жңүеҠ№жҖ§гҒ®зҜ„еӣІгҖҒгҒқгҒ—гҒҰеӨ–еӣҪдәәгҒҢеңҹең°гӮ’жүҖжңүгҒҷгӮӢйҡӣгҒ®еҺігҒ—гҒ„иҰҸеҲ¶гҒЁгҖҒгҒқгӮҢгӮ’еӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҗҲжі•зҡ„гҒӘжүӢж®өгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒи©ізҙ°гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжң¬зЁҝгҒҢгҖҒиІҙзӨҫгҒ®гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ§гҒ®жі•зҡ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ’дҪҺжёӣгҒ—гҖҒеҶҶж»‘гҒӘдәӢжҘӯеұ•й–ӢгӮ’йҖІгӮҒгӮӢдёҖеҠ©гҒЁгҒӘгӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ®зӣ®ж¬Ў
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®еҘ‘зҙ„жі•гҒ®еҹәжң¬еҺҹеүҮ
гҖҢзҙ„еӣ пјҲConsiderationпјүгҖҚгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢеҺҹеӣ пјҲCausaпјүгҖҚгҒ®иҰҒ件
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®еҘ‘зҙ„жі•гӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§гҖҒгҒқгҒ®жі•зҡ„ж №жӢ гҒҢгӮігғўгғігғӯгғјгҒЁгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гҒ®ж··еҗҲдҪ“зі»гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«з•ҷж„ҸгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҘ‘зҙ„гҒ®жҲҗз«ӢиҰҒ件гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒЁгҒҜж №жң¬зҡ„гҒ«з•°гҒӘгӮӢжҰӮеҝөгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«жі•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжңүеҠ№гҒӘеҘ‘зҙ„гӮ’жҲҗз«ӢгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеҪ“дәӢиҖ…й–“гҒ®з”іиҫјгҒҝпјҲOfferпјүгҒЁжүҝи«ҫпјҲAcceptanceпјүгҒҢеҗҲиҮҙгҒ—гҖҒжі•зҡ„й–ўдҝӮгӮ’зҜүгҒҸж„ҸжҖқпјҲIntention to create legal relationsпјүгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иҰҒ件гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬жі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢж„ҸжҖқгҒ®еҗҲиҮҙгҖҚгҒЁйЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«жі•гҒ§гҒҜгҒ•гӮүгҒ«гҖҒеҘ‘зҙ„еҪ“дәӢиҖ…гҒ®иғҪеҠӣгҖҒеҘ‘зҙ„зӣ®зҡ„гҒ®йҒ©жі•жҖ§гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҢзҙ„еӣ пјҲConsiderationпјүгҖҚгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢеҺҹеӣ пјҲCausaпјүгҖҚгҒ®иҰҒ件гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®жі•еҫӢе®ҹеӢҷиҖ…гҒҢз•ҷж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гҖҢзҙ„еӣ гҖҚгҒЁгҖҢеҺҹеӣ гҖҚгҒ®жҰӮеҝөгҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®ж°‘жі•гҒ§гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒҜеҪ“дәӢиҖ…й–“гҒ®ж„ҸжҖқгҒҢеҗҲиҮҙгҒҷгӮҢгҒ°жҲҗз«ӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҘ‘зҙ„гҒҢжңүе„ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢз„Ўе„ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҘ‘зҙ„гҒ®жңүеҠ№жҖ§гҒ«гҒҜеҪұйҹҝгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®зӮ№гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҡеүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮігғўгғігғӯгғјгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢзҙ„еӣ гҖҚгҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„гҒҢжі•зҡ„гҒ«еј·еҲ¶еҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҗ„еҪ“дәӢиҖ…гҒҢзӣёжүӢж–№гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҖҢеҜҫдҫЎгҖҚгӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒйҮ‘йҠӯгӮ„зү©е“ҒгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҒзҙ„жқҹгҒӘгҒ©гҖҒдҪ•гӮүгҒӢгҒ®дәӨжҸӣгӮ’дјҙгҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒзҙ”зІӢгҒӘгӮігғўгғігғӯгғјзі»гҒ®еӣҪгҖ…гҒ§гҒҜгҖҒгҖҢеҜҫдҫЎгҖҚгҒ®гҒӘгҒ„еҘ‘зҙ„гҒҜгҖҒжі•зҡ„гҒ«жңүеҠ№гҒӘеҘ‘зҙ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дёҖж–№гҖҒгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гҒ®гҖҢеҺҹеӣ пјҲCausaпјүгҖҚгҒҜгҖҒзҙ„жқҹгҒҢжі•зҡ„гҒ«жӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢж №жӢ гҖҒзҗҶз”ұгҖҒзӣ®зҡ„гҖҚгӮ’жҢҮгҒҷгҖҒгӮҲгӮҠеәғзҜ„гҒӘжҰӮеҝөгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жҰӮеҝөгҒ«гҒҜгҖҒйҒ“еҫізҡ„зҫ©еӢҷгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖҒгӮігғўгғігғӯгғјгҒ®зҙ„еӣ гҒ«гҒҜеҗ«гҒҫгӮҢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгӮӢгҒЁи§ЈйҮҲгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еүҚжҸҗгҒ®дёҠгҒ§гҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®еҘ‘зҙ„жі•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгӮігғўгғігғӯгғјгҒ®гҖҢзҙ„еӣ пјҲConsiderationпјүгҖҚгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гҒ®гҖҢеҺҹеӣ пјҲCausaпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөгҒҢж”Ҝй…Қзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ§гҒҜеҚҳзҙ”гҒӘгҖҢеҜҫдҫЎгҖҚгҒҢгҒӘгҒ„з„Ўе„ҹгҒ®зҙ„жқҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгӮ’е®ҹиЎҢгҒҷгӮӢгҒ«и¶ігӮӢжӯЈеҪ“гҒӘгҖҢзҗҶз”ұгҖҚгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжі•зҡ„гҒ«жңүеҠ№гҒӘеҘ‘зҙ„гҒЁиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
еҘ‘зҙ„жі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢд»ЈиЎЁзҡ„гҒӘеҲӨдҫӢ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®еҘ‘зҙ„жі•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘжҰӮеҝөгҒҜгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®еҲӨдҫӢгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гҖҒзҙ„еӣ пјҲConsiderationпјүгҒЁеҺҹеӣ пјҲCausaпјүгҒ®жҰӮеҝөгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢдёҠгҒ§йҮҚиҰҒгҒӘеҲӨдҫӢгӮ’гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
Lipton v. Buchanan (1904) 8 NLR 49гҒ§гҒҜгҖҒеӮөжЁ©иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢLгҒҢгҖҒеӮөеӢҷиҖ…гҒ®1дәәгҒ§гҒӮгӮӢFгҒҢиІ еӮөгҒ®дёҖйғЁгӮ’ж”Ҝжү•гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгӮӮгҒҶ1дәәгҒ®еӮөеӢҷиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢBгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеӣһеҸҺжүӢж®өгӮ’е°ҪгҒҸгҒҷгҒҫгҒ§гҒҜFгӮ’иЁҙгҒҲгҒӘгҒ„гҒЁзҙ„жқҹгҒ—гҒҹдәӢжЎҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®зҙ„жқҹгҒ«гҖҢжӯЈеҪ“гҒӘеҺҹеӣ пјҲjusta causaпјүгҖҚгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҗҲж„ҸгҒҢжі•зҡ„гҒ«жңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиӘҚгӮҒгҒҹиЈҒеҲӨдҫӢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЈҒеҲӨдҫӢгҒҢгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгӮігғўгғігғӯгғјгҒ®зҙ„еӣ гҒ®еҺҹеүҮгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«е„Әе…ҲгҒ•гӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖҒд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҖҒгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гҒ®еҺҹеӣ пјҲcausaпјүгҒ®жҰӮеҝөгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜзҙ„жқҹгҒҢжі•зҡ„гҒ«жӢҳжқҹеҠӣгӮ’жҢҒгҒӨгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢж №жӢ гҖҒзҗҶз”ұгҖҒзӣ®зҡ„гҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒJayawickrema v. Amarasuriya (1918) 20 NLR 293гҒҜгҖҒзҙ„еӣ гҒ®жҰӮеҝөгҒҢйҒ“еҫізҡ„зҫ©еӢҷгӮ’еҗ«гӮҖеҸҜиғҪжҖ§гӮ’гҒ•гӮүгҒ«жҳҺзўәгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дәӢжЎҲгҒ§гҒҜгҖҒиў«зӣёз¶ҡдәәгҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹеҫҢгҖҒгҒқгҒ®иІЎз”ЈгҒҢйҒәиЁҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзү№е®ҡгҒ®зӣёз¶ҡдәәгҒ«еј•гҒҚз¶ҷгҒҢгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йҒәиЁҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгӮӮгҒҶдёҖдәәгҒ®зӣёз¶ҡдәәпјҲеҰ№пјүгҒҜе®ҹиіӘзҡ„гҒӘиІЎз”ЈгҒ®жҸҗдҫӣгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒйҒәз”ЈгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰзӣёз¶ҡгҒ—гҒҹзӣёз¶ҡдәәпјҲе…„пјүгҒҜгҖҒеҰ№гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиІЎз”ЈгӮ’еҲҶгҒ‘дёҺгҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶйҒ“еҫізҡ„зҫ©еӢҷгӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҖҒеҰ№гҒ«йҮ‘йҠӯгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’зҙ„жқҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҙ„жқҹгҒҜгҖҒеҰ№гҒҢиЁҙиЁҹгӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒЁгҒ„гҒҶи„…еЁҒгӮ’жҺ’йҷӨгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е’Ңи§ЈгҒ®дёҖйғЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮеҲӨжұәгҒ§гҒҜгҖҒгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гҒ®еҺҹеӣ пјҲcausaпјүгҒ®жҰӮеҝөгҒҜгҖҒйҒ“еҫізҡ„зҫ©еӢҷгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгӮігғўгғігғӯгғјгҒ®зҙ„еӣ гҒ«гҒҜйҖҡеёёеҗ«гҒҫгӮҢгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’еҢ…еҗ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ§гҒҜгҖҒеҚҳзҙ”гҒӘеҜҫдҫЎгҒ®дәӨжҸӣгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒйҒ“еҫізҡ„зҫ©еӢҷгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжӯЈеҪ“гҒӘзҗҶз”ұгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеҘ‘зҙ„гҒҜжңүеҠ№гҒ«жҲҗз«ӢгҒ—гҒҶгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҺҹеүҮгҒҢзўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҲӨдҫӢгҒҜгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®еҘ‘зҙ„жі•гҒҢеҚҳгҒӘгӮӢжңүе„ҹгғ»з„Ўе„ҹгҒ®дәӨжҸӣгҒЁгҒ„гҒҶиҰ–зӮ№гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒзҙ„жқҹгҒ®иғҢеҫҢгҒ«гҒӮгӮӢгҖҢзҗҶз”ұгҖҚгӮ„гҖҢзӣ®зҡ„гҖҚгӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжі•зҗҶгӮ’жҢҒгҒӨгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’еҗ«гӮҖеҺҹеӣ пјҲcausaпјүгҒ®жҰӮеҝөгҒҜеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’ж¬ гҒҸеҘ‘зҙ„гҒҜжі•зҡ„гҒ«жңүеҠ№гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гҒ®зӮ№гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒЁгҒ®еҘ‘зҙ„гӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҖҒзү№гҒ«жіЁж„ҸгӮ’жү•гҒҶгҒ№гҒҚйҮҚиҰҒгҒӘйҒ•гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®йӣ»еӯҗеҘ‘зҙ„гҒЁйӣ»еӯҗзҪІеҗҚгҒ®жңүеҠ№жҖ§
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®йӣ»еӯҗеҸ–еј•жі•пјҲElectronic Transactions Act No. 19 of 2006пјүгҒҜгҖҒйӣ»еӯҗе•ҶеҸ–еј•гӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйӣ»еӯҗзҪІеҗҚгӮ„йӣ»еӯҗж–ҮжӣёгҒ«жі•зҡ„жңүеҠ№жҖ§гӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®йӣ»еӯҗзҪІеҗҚжі•гҒӘгҒ©гҒЁе…ұйҖҡгҒҷгӮӢзҸҫд»Јзҡ„гҒӘжі•еҫӢе®ҹеӢҷгҒ®йҖІеұ•гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
йӣ»еӯҗеҸ–еј•жі•пјҲд»ҘдёӢгҖҢETAгҖҚпјүгҒҜгҖҒйӣ»еӯҗзҡ„гҒӘгғҮгғјгӮҝгғЎгғғгӮ»гғјгӮёгҖҒйӣ»еӯҗж–ҮжӣёгҖҒйӣ»еӯҗиЁҳйҢІгҒҢгҖҒжі•зҡ„еҠ№еҠӣгҖҒжңүеҠ№жҖ§гҖҒеј·еҲ¶еҠӣгӮ’еҗҰе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁе®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзү©зҗҶзҡ„гҒӘжӣёйқўгӮ„зҪІеҗҚгҒҢжі•еҫӢгҒ§иҰҒжұӮгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷйӣ»еӯҗж–ҮжӣёгҒҢгҒқгҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮETAгҒҜгҖҒйӣ»еӯҗиЁҳйҢІгҒҢиЈҒеҲӨгҒ§гҒ®иЁјжӢ гҒЁгҒ—гҒҰиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘе•ҶжҘӯеҘ‘зҙ„гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒйӣ»еӯҗзҪІеҗҚгҒҢзү©зҗҶзҡ„гҒӘзҪІеҗҚгҒЁеҗҢзӯүгҒ«жүұгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒETAгҒҜйӣ»еӯҗзҪІеҗҚгҒ®жі•зҡ„жңүеҠ№жҖ§гӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒзү№е®ҡгҒ®зЁ®йЎһгҒ®ж–ҮжӣёгӮ„еҸ–еј•гҒ«гҒҜдҫӢеӨ–гӮ’иЁӯгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдёҚеӢ•з”ЈгҒ®иӯІжёЎгӮ„дҝЎиЁ—гҖҒйҒәиЁҖгҖҒе…¬жӯЈиЁјжӣёгҒ«гӮҲгӮӢд»ЈзҗҶ権委任зҠ¶гҒӘгҒ©гҖҒдјқзөұзҡ„гҒӘжі•еҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҺіж јгҒӘеҪўејҸиҰҒ件гҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҸ–еј•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒдҫқ然гҒЁгҒ—гҒҰжүӢжӣёгҒҚзҪІеҗҚгӮ„е…¬иЁјдәәгҒ«гӮҲгӮӢиӘҚиЁјгҒҢеҝ…й ҲгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•дҪ“зі»гҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖҒгғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гҒ®гҖҢйқһйҖЈз¶ҡжҖ§гҖҚгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘе•ҶеҸ–еј•гҒҜгғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гҒ®жҒ©жҒөгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒдёҚеӢ•з”ЈеҸ–еј•гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҮҚеӨ§гҒӘжЎҲ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒи©җж¬әйҳІжӯўжқЎдҫӢпјҲPrevention of Frauds OrdinanceпјүгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдјқзөұзҡ„гҒӘжі•д»ӨгҒҢе®ҡгӮҒгӮӢжӣёйқўгҒЁе…¬иЁјгҒЁгҒ„гҒҶеҺіж јгҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢз¶ӯжҢҒгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®дәӢжҘӯиҖ…гҒҢгҒ“гҒ®йҒ•гҒ„гӮ’иӘҚиӯҳгҒӣгҒҡгҒ«йҖІгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒеҘ‘зҙ„гҒ®жңүеҠ№жҖ§гҒ«й–ўгҒҷгӮӢйҮҚеӨ§гҒӘгғӘгӮ№гӮҜгӮ’иІ гҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒзү№гҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёҚеӢ•з”Јй–ўйҖЈгҒ®жі•еҲ¶еәҰ

еӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢдёҚеӢ•з”ЈеҸ–еҫ—
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒёгҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёҚеӢ•з”ЈгҒ®еҸ–еҫ—гҒҜйҮҚиҰҒгҒӘиӘІйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒҜгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢеңҹең°жүҖжңүгӮ’еҺігҒ—гҒҸиҰҸеҲ¶гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜж—Ҙжң¬гҒ®гҒқгӮҢгҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ§гҒҜгҖҒеңҹең°пјҲиӯІжёЎеҲ¶йҷҗпјүжі•пјҲLand (Restrictions on Alienation) Act No. 38 of 2014пјүгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҖҒеӨ–еӣҪдјҒжҘӯгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜеӨ–еӣҪиіҮжң¬гҒҢ50%д»ҘдёҠгӮ’дҝқжңүгҒҷгӮӢгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«жі•дәәгҒ«гӮҲгӮӢгғ•гғӘгғјгғӣгғјгғ«гғүпјҲFreeholdпјүеңҹең°гҒ®зӣҙжҺҘжүҖжңүгҒҢеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰзҰҒжӯўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒҜ2013е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгҒ«йҒЎгҒЈгҒҰзҷәеҠ№гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жі•еҫӢгҒ®еүҚж–ҮгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢгҖҢгӮ°гғӯгғјгғҗгғ«зөұеҗҲз’°еўғгҒ®иғҢжҷҜгҒ®дёӯгҒ§ж”ҝеәңгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдҝғйҖІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢй–Ӣзҷәж”ҝзӯ–гҒ®жҺЁйҖІгҒ®дёҖз’°гҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҖҢеңҹең°гҒ®дҪҝз”ЁгӮ’жҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒӘж–№жі•гҒ§иҰҸеҲ¶гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҳҺиЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«еӨ–еӣҪдәәгҒ®еңҹең°жүҖжңүгӮ’еҲ¶йҷҗгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеӣҪ家гҒ®иіҮжәҗгҒ§гҒӮгӮӢеңҹең°гӮ’гҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢ無秩еәҸгҒӘжҠ•ж©ҹгҒӢгӮүе®ҲгӮҠгҖҒжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒӘзҷәеұ•гҒЁгҒ„гҒҶеӣҪ家ж”ҝзӯ–гҒ«жІҝгҒЈгҒҰз®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжҳҺзўәгҒӘж„ҸеӣігҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҺігҒ—гҒ„иҰҸеҲ¶гҒҢгҒӮгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒеӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮ家гҒҢеҗҲжі•зҡ„гҒ«дёҚеӢ•з”ЈгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иӨҮж•°гҒ®д»ЈжӣҝжүӢж®өгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- гӮігғігғүгғҹгғӢгӮўгғ гҒ®жүҖжңүпјҡзү№е®ҡгҒ®гӮігғігғүгғҹгғӢгӮўгғ пјҲйҖҡеёёгҒҜең°дёҠ4йҡҺд»ҘдёҠпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒҢгғ•гғӘгғјгғӣгғјгғ«гғүгҒ§зӣҙжҺҘжүҖжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒжө·еӨ–гҒӢгӮүгҒ®жҠ•иіҮгӮ’еҘЁеҠұгҒҷгӮӢж”ҝзӯ–гҒ®дёҖз’°гҒЁиЁҖгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
- й•·жңҹгғӘгғјгӮ№пјҡгғ•гғӘгғјгғӣгғјгғ«гғүеңҹең°гҒ®д»ЈжӣҝгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжңҖеӨ§99е№ҙй–“гҒ®й•·жңҹгғӘгғјгӮ№еҘ‘зҙ„гӮ’з· зөҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгғӘгғјгӮ№гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеңҹең°гҒ®еёӮе ҙдҫЎеҖӨгҒ«еҝңгҒҳгҒҰеҚ°зҙҷзЁҺпјҲStamp DutyпјүгҒҢиӘІзЁҺгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
- зҸҫең°жі•дәәгҒ«гӮҲгӮӢжүҖжңүпјҡеӨ–еӣҪиіҮжң¬гҒҢ50%жңӘжәҖгҒ®гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«жі•дәәгӮ’иЁӯз«ӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жі•дәәгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгғ•гғӘгғјгғӣгғјгғ«гғүеңҹең°гӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеӨ–еӣҪиіҮжң¬жҜ”зҺҮгҒҢ50%жңӘжәҖгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҚеӢ•з”ЈеЈІиІ·еҘ‘зҙ„гҒ®еҪўејҸиҰҒ件
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ§гҒ®дёҚеӢ•з”ЈеҸ–еј•гҒҜгҖҒйқһеёёгҒ«еҺіж јгҒӘеҪўејҸиҰҒ件гҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮи©җж¬әйҳІжӯўжқЎдҫӢпјҲPrevention of Frauds Ordinanceпјү第2жқЎгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒдёҚеӢ•з”ЈгҒ®еЈІиІ·гҖҒиӯІжёЎгҖҒжҠөеҪ“жЁ©иЁӯе®ҡгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁјжӣёгҒҜгҖҒеҝ…гҒҡжӣёйқўгҒ§дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒе…¬иЁјдәәпјҲnotary publicпјүгҒ®йқўеүҚгҒ§2еҗҚгҒ®иЁјдәәгҒҢеҗҢжҷӮгҒ«з«ӢгҒЎдјҡгҒЈгҒҰгҖҒй–ўдҝӮиҖ…е…Ёе“ЎгҒҢзҪІеҗҚгҒЁжҚәеҚ°пјҲжӢҮеҚ°пјүгӮ’иЎҢгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒиіҮйҮ‘移еӢ•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеӨ–еӣҪгҒӢгӮүйҖҒйҮ‘гҒ•гӮҢгӮӢиіҮйҮ‘гҒҜгҖҒгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«еӣҪеҶ…гҒ®йҠҖиЎҢгҒ«й–ӢиЁӯгҒ•гӮҢгҒҹгӮӨгғігғҜгғјгғүгғ»гӮӨгғігғҷгӮ№гғҲгғЎгғігғҲгғ»гӮўгӮ«гӮҰгғігғҲпјҲInward Investment Account, IIAпјүгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰйҖҒйҮ‘гҒ•гӮҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒиҰҸеҲ¶йҒөе®ҲгӮ’зўәдҝқгҒ—гҖҒе°ҶжқҘгҒ®иіҮйҮ‘гҒ®жң¬еӣҪйҖҒйӮ„гӮ’еҶҶж»‘гҒ«иЎҢгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒдёҚеӢ•з”ЈеҸ–еј•гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢзЁҺеҲ¶гҒҜеӨүеӢ•гҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеӨ–еӣҪдәәгҒҢиІ жӢ…гҒҷгӮӢеҚ°зҙҷзЁҺгҒҜгҖҒдёҚеӢ•з”Јиіје…ҘжҷӮгҒ«гҒҜжңҖеҲқгҒ®10дёҮгғ«гғ”гғјгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰ3%гҖҒж®ӢйЎҚгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰ4%гҒ§гҒҷгҖӮдёҖж–№гҖҒVATгҒҜгҖҒVATзҷ»йҢІдәӢжҘӯиҖ…гҒҢиІ©еЈІгҒҷгӮӢгӮігғігғүгғҹгғӢгӮўгғ гҒ®иіје…ҘжҷӮгҒ«18%гҒҢиӘІзЁҺгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиіҮжң¬еҲ©еҫ—зЁҺпјҲCapital Gains TaxпјүгҒҜгҖҒиіҮз”ЈеЈІеҚҙзӣҠгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰ10%гҒҢиӘІгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮйҒҺеҺ»гҒ«гҒҜеӨ–еӣҪдәәеҗ‘гҒ‘гҒ®еңҹең°гғӘгғјгӮ№зЁҺгҒҢ2017е№ҙгҒ«е»ғжӯўгҒ•гӮҢгҖҒVATгҒ®зЁҺзҺҮгҒҜ2024е№ҙ1жңҲгҒ«15%гҒӢгӮү18%гҒ«еј•гҒҚдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®зЁҺеҲ¶еӨүжӣҙгҒҜгҖҒеӨ–еӣҪдәәжҠ•иіҮ家гҒ®гғӘгӮҝгғјгғігҒ«зӣҙжҺҘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжҠ•иіҮ家гҒҜжңҖж–°гҒ®жғ…е ұгӮ’еёёгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҖҒй•·жңҹзҡ„гҒӘжҠ•иіҮиЁҲз”»гҒ«гҒқгҒ®еӨүеӢ•гғӘгӮ№гӮҜгӮ’з№”гӮҠиҫјгӮҖеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒиӢұеӣҪгӮігғўгғігғӯгғјгҒЁгғӯгғјгғһгғ»гӮӘгғ©гғігғҖжі•гҒ®ж··еҗҲдҪ“зі»гҒЁгҒ„гҒҶзӢ¬иҮӘгҒ®иғҢжҷҜгҒӢгӮүгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®е®ҹеӢҷгҒЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢеҒҙйқўгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒеҘ‘зҙ„жі•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢеҺҹеӣ пјҲCausaпјүгҖҚгҒ®жҰӮеҝөгҒҜгҖҒз„Ўе„ҹгҒ®зҙ„жқҹгҒ®жңүеҠ№жҖ§гӮ’е·ҰеҸігҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘиҰҒзҙ гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®гҖҢж„ҸжҖқгҒ®еҗҲиҮҙгҖҚгҒ®гҒҝгҒ§еҘ‘зҙ„гҒҢжҲҗз«ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒЁгҒҜдёҖз·ҡгӮ’з”»гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдёҚеӢ•з”ЈеҸ–еј•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеӨ–еӣҪдәәгҒ«гӮҲгӮӢеңҹең°гҒ®зӣҙжҺҘжүҖжңүгҒҢеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒгӮігғігғүгғҹгғӢгӮўгғ жүҖжңүгӮ„й•·жңҹгғӘгғјгӮ№гҖҒзҸҫең°жі•дәәгӮ’йҖҡгҒҳгҒҹеҸ–еҫ—гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹд»ЈжӣҝжүӢж®өгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒҜеҺіж јгҒӘе…¬иЁјжүӢз¶ҡгҒҚгҒЁиіҮйҮ‘移еӢ•гҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘжі•иҰҸеҲ¶гҒҜгҖҒзҸҫең°гҒ®жі•зҡ„е°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгҒӘгҒҸгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒж„ҸеӣігҒ—гҒӘгҒ„гғӘгӮ№гӮҜгӮ„гӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№йҒ•еҸҚгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе®үжҳ“гҒӘиҮӘе·ұеҲӨж–ӯгҒҜгҖҒжҖқгӮҸгҒ¬жі•зҡ„гғҲгғ©гғ–гғ«гӮ’жӢӣгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒӢгҒӯгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гғўгғҺгғӘгӮ№жі•еҫӢдәӢеӢҷжүҖгҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ®жі•еӢҷгҒ«й–ўгҒҷгӮӢе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘзҹҘиҰӢгӮ’жңүгҒ—гҖҒгҒҠе®ўж§ҳгҒ®дәӢжҘӯеұ•й–ӢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҘ‘зҙ„з· зөҗгҒӢгӮүдёҚеӢ•з”ЈеҸ–еј•гҖҒдјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҖҒеҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘгӮөгғқгғјгғҲгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гҒ§гҒ®гғ“гӮёгғҚгӮ№еұ•й–ӢгӮ’гҒ”жӨңиЁҺгҒ®йҡӣгҒҜгҖҒгҒңгҒІејҠжүҖгҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
й–ўйҖЈеҸ–жүұеҲҶйҮҺпјҡеӣҪйҡӣжі•еӢҷгғ»жө·еӨ–дәӢжҘӯ